「ヴィクトリア (イギリス女王)」の版間の差分
編集の要約なし |
Omaemona1982 (会話 | 投稿記録) 編集の要約なし タグ: サイズの大幅な増減 |
||
| 6行目: | 6行目: | ||
| 画像サイズ = |
| 画像サイズ = |
||
| 画像説明 = 1887年 |
| 画像説明 = 1887年 |
||
| 在位 = [[1837年]][[6月20日]] - [[1901年]][[1月22日]] |
| 在位 = [[1837年]][[6月20日]]<ref name="秦(2001)507">[[#秦(2001)|秦(2001)]] p.507</ref> - [[1901年]][[1月22日]]<ref name="秦(2001)507"/> |
||
| 戴冠日 = [[1838年]][[6月28日]]、於[[ウェストミンスター寺院]] |
| 戴冠日 = [[1838年]][[6月28日]]<ref name="秦(2001)507"/>、於[[ウェストミンスター寺院]]<ref name="君塚(2007)25">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.25</ref> |
||
| 別号 = [[インド皇帝|インド女帝 |
| 別号 = [[インド皇帝|インド女帝]] |
||
| 全名 = アレクサンドリナ・ヴィクトリア<br />{{Lang-en|Alexandrina Victoria}} |
| 全名 = アレクサンドリナ・ヴィクトリア<br />{{Lang-en|Alexandrina Victoria}} |
||
| 出生日 = {{生年月日と年齢|1819|5|24|no}} |
| 出生日 = {{生年月日と年齢|1819|5|24|no}} |
||
| 生地 = {{ENG}} [[ロンドン]] [[ケンジントン宮殿]] |
| 生地 = {{UK}} {{ENG}}<br>[[File:Coat of Arms of The City of London.svg|25px]] [[ロンドン]] [[ケンジントン宮殿]] |
||
| 死亡日 = {{死亡年月日と没年齢|1819|5|24|1901|1|22}} |
| 死亡日 = {{死亡年月日と没年齢|1819|5|24|1901|1|22}} |
||
| 没地 = {{ENG}} [[ワイト島]] [[オズボーン・ハウス]] |
| 没地 = {{UK}} {{ENG}}<br>[[File:Isle of Wight Council Flag.svg|25px]] [[ワイト島]] [[オズボーン・ハウス]] |
||
| 埋葬日 = [[1901年]][[2月2日]] |
| 埋葬日 = [[1901年]][[2月2日]] |
||
| 埋葬地 = {{ |
| 埋葬地 = {{UK}} {{ENG}}<br>[[ウィンザー (イングランド)|ウィンザー]] [[:en:Frogmore|フロッグモア]] |
||
| 配偶者1 = [[アルバート (ザクセン=コーブルク=ゴータ公子)|アルバート・オブ・サクス=コバーグ・アンド・ゴータ]] |
| 配偶者1 = [[アルバート (ザクセン=コーブルク=ゴータ公子)|アルバート・オブ・サクス=コバーグ・アンド・ゴータ]] |
||
| 子女 = [[#子女|一覧参照]] |
| 子女 = [[#子女|一覧参照]] |
||
| 26行目: | 26行目: | ||
| サイン = Queen Victoria Signature.svg |
| サイン = Queen Victoria Signature.svg |
||
}} |
}} |
||
'''ヴィクトリア'''({{Lang-en|Victoria}}、[[1819年]][[5月24日]] - [[1901年]][[1月22日]])は、[[グレートブリテンおよびアイルランド連合王国 |
'''ヴィクトリア'''({{Lang-en|Victoria}}、[[1819年]][[5月24日]] - [[1901年]][[1月22日]])は、[[グレートブリテンおよびアイルランド連合王国|イギリス]]・[[ハノーヴァー朝]]の第6代[[イギリスの君主|女王]](在位:[[1837年]][[6月20日]] - [[1901年]][[1月22日]])、初代[[イギリス領インド帝国|インド]][[インド皇帝|女帝]](在位:[[1877年]][[1月1日]] - [[1901年]][[1月22日]])。世界各地を[[植民地化]]・半植民地化して繁栄を極めた[[イギリス帝国|大英帝国]]を象徴する女王として知られ、その治世は[[ヴィクトリア朝]]と呼ばれる。在位は63年7か月にも及び、歴代イギリス国王の中でも最長である{{#tag:ref|二番目に在位が長いのは現英国女王[[エリザベス2世]]であり、彼女は[[2012年]][[2月6日]]に在位60周年を迎えた<ref>[[朝日新聞]]{{Jdate|2012}}[[2月6日]]夕刊2面。[http://www.asahi.com/international/update/0206/TKY201202060068.html 朝日新聞デジタル]</ref>。外国の君主で在位年数が、ヴィクトリアに匹敵するのは(近代以降では)オーストリアの[[フランツ・ヨーゼフ1世 (オーストリア皇帝)|フランツ・ヨーゼフ1世]]帝(在位68年)、日本の[[昭和天皇]](在位62年+[[摂政宮]]5年)、タイの[[ラーマ9世]](※1946年より在位中)がいる。|group=#}}。 |
||
== |
== 概要 == |
||
イギリス・ハノーヴァー朝第3代国王[[ジョージ3世 (イギリス王)|ジョージ3世]]の第四王子である[[ケント公]][[エドワード・オーガスタス (ケント公)|エドワード]]の一人娘。3人の伯父たちが[[嫡出子]]を残さなかったため、1837年に18歳でハノーヴァー朝第6代女王に即位する。 |
|||
近代以降、英国の最も輝かしい時代である[[イギリス帝国]]の最盛期の象徴として君臨した女王。「君臨すれども統治せず」の立憲君主制の理念によって[[間接民主制|議会制民主主義]]を貫き、[[ベンジャミン・ディズレーリ]]、そして、王配:[[アルバート (ザクセン=コーブルク=ゴータ公子)|アルバート]]の助言によって[[イギリス帝国]]を繁栄させた。その治世は'''[[ヴィクトリア朝]]'''と呼ばれ、政治・経済のみならず、文化・技術面でも優れた成果を上げた。アルバートとの円満な家庭生活はこれを象徴した。また子女が欧州各国と婚姻を結び、'''[[ヨーロッパの祖母]]'''と呼ばれるに至った。 |
|||
ハノーヴァー朝の国王は代々[[ドイツ連邦|ドイツ]]の[[ハノーファー王国]](選帝侯国)の君主を兼ねていたが、ハノーファーでは[[サリカ法典]]による継承法を取っており、女性の統治が認められていない。そのためヴィクトリアはハノーファー王位を継承せず、叔父[[エルンスト・アウグスト (ハノーファー王)|エルンスト・アウグスト]]がその地位を継ぎ、イギリスとハノーファーの[[同君連合]]は解消された<ref name="世界大百科事典ハノーバー朝">[[#世界大百科事典|世界大百科事典]]「ハノーバー朝」の項目</ref>。 |
|||
この時代、イギリスは世界各地を植民地化して一大[[植民地帝国]]を築き上げ、ヴィクトリアは「[[インド皇帝|インド女帝]]」の称号を得ている。 [[ヴィクトリア湖]]、[[ヴィクトリア滝]]など、女王の名に因んだ命名も少なくない。 |
|||
はじめ[[ホイッグ党 (イギリス)|ホイッグ党]]の首相[[メルボルン子爵ウィリアム・ラム|メルバーン子爵]]を偏愛したが、1840年に母方の[[従姉弟]]にあたる[[ザクセン=コーブルク=ゴータ公国]]公子[[アルバート (ザクセン=コーブルク=ゴータ公子)|アルバート]]と結婚すると彼の忠告に従って王権の中立化に努めるようになった。その後もしばしば政治に影響力を行使しながらも基本的に議会の状況に基づいて首相を選ぶようになった。国王の政治的影響力の面ではアルバートがヴィクトリアに代わって重きをなすようになっていったが、彼はその権威が絶対的になる前の1861年に薨去した。これによりイギリスに[[立憲君主制]]の道が開かれることとなった。 |
|||
[[ハノーヴァー朝]]の国王は代々[[ドイツ連邦|ドイツ]]の[[ハノーファー王国]](選帝侯国)の君主を兼ねていたが、ハノーファーでは[[サリカ法典]]による継承法を取っており、女性の統治が認められていない。そのためヴィクトリアはハノーファー王位を継承せず、叔父[[エルンスト・アウグスト (ハノーファー王)|エルンスト・アウグスト]]がその地位を継いだ。 |
|||
一方悲しみにくれるヴィクトリアはその後10年以上にわたって喪服し、公務に姿を見せなくなったが、1870年代に[[保守党 (イギリス)|保守党]]の首相[[ベンジャミン・ディズレーリ]]に励まされて公務に復帰し、彼の帝国主義政策を全面的に支援し、大英帝国の最盛期を築き上げた。1876年には「[[インド皇帝|インド女帝]]」に即位した。ディズレーリを偏愛する一方、ディズレーリと並んでヴィクトリア朝を代表する[[自由党 (イギリス)|自由党]]首相[[ウィリアム・グラッドストン]]のことは一貫して嫌っていた。彼のアイルランド自治法案の阻止に全力を挙げた。晩年には老衰で政治的な活動は少なくなり、立憲君主化が一層進展した。 |
|||
== 家系 == |
|||
[[ジョージ3世 (イギリス王)|ジョージ3世]]の四男:[[ケント公|ケント公爵]][[エドワード・オーガスタス (ケント公)|エドワード]]の一人娘。 |
|||
1901年に崩御し、王位は長男である[[エドワード7世 (イギリス王)|エドワード7世]]に受け継がれた。 |
|||
母:[[ヴィクトリア・オブ・サクス=コバーグ=ザールフィールド|ヴィクトリア・フォン・ザクセン=コーブルク=ザールフェルト]]は後の[[ベルギー]][[ベルギー国王の一覧|国王]][[レオポルド1世 (ベルギー王)|レオポルド1世]]の姉であった。 |
|||
彼女の63年7か月の治世は'''[[ヴィクトリア朝]]'''と呼ばれ、政治・経済のみならず、文化・技術面でも優れた成果を上げた。この時代の物は政治であれ、外交であれ、軍事であれ、文学であれ、科学であれ、家具であれ「ヴィクトリア朝の~」という形容をされることが多い<ref name="ベイカー(1997)182">[[#ベイカー(1997)|ベイカー(1997)]] p.182</ref>。 |
|||
レオポルドの妻は[[摂政王太子]](のちの[[ジョージ4世 (イギリス王)|ジョージ4世]])の一人娘で、イギリスの王位継承者である[[シャーロット・オーガスタ・オブ・ウェールズ|シャーロット王女]](=ヴィクトリアの従姉)であったが、シャーロットは[[1817年]]に死去し、ジョージ4世の直系の後継者はいなくなった。 |
|||
この時代、イギリスは世界各地を植民地化して一大[[植民地帝国]]を築き上げた。その名残で [[ヴィクトリア湖]]([[ケニア]]、[[ウガンダ]]、[[タンザニア]])、[[ヴィクトリア滝]]([[ジンバブエ]]・[[ザンビア]])、[[ヴィクトリア・ハーバー]]([[香港]])、[[ヴィクトリア・パーク]](世界各地)など、女王の名に因んだ命名も少なくない。 |
|||
ジョージ4世は、[[キャロライン・オブ・ブランズウィック|キャロライン王妃]]の死後も再婚せず、愛人と隠遁生活に入った。このため独身生活を謳歌していたジョージ4世の弟たちは、王位継承者となるべき子をもうけようとにわかに結婚を始め、ヴィクトリアの父:ケント公も50歳で結婚した。 |
|||
子女が欧州各国の王室・皇室と婚姻を結んだ結果、'''[[ヨーロッパの祖母]]'''と呼ばれるに至った<ref name="朝倉(1996)122">[[#朝倉(1996)|朝倉・三浦(1996)]] p.122</ref>。[[ヴィルヘルム2世 (ドイツ皇帝)|ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世]]と[[アレクサンドラ・フョードロヴナ (ニコライ2世皇后)|ロシア皇后アレクサンドラ]]([[ロシア皇帝]][[ニコライ2世]]妃)は孫にあたる<ref name="ワイントラウブ(1993)下524-525">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.524-525</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
== 生涯 == |
== 生涯 == |
||
=== |
=== 生誕 === |
||
ヴィクトリアは[[1819年]][[5月24日]]午後4時15分頃に[[ロンドン]]の[[ケンジントン宮殿]]で生まれた<ref name="ワイントラウブ(1993)上67">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.67</ref> |
|||
ヴィクトリアの洗礼式に[[代父母|代父]]となったのは、[[ケント公]]の兄・摂政王太子ジョージ、[[ロシア帝国|ロシア]][[ロシア君主一覧|皇帝]][[アレクサンドル1世]](イギリス訪問中で、ジョージとも仲が良かった)。代母は、ケント公爵夫人ヴィクトリアの実母アウグスタ、[[ヴュルテンベルク王国|ヴュルテンベルク]]公妃[[シャーロット (ヴュルテンベルク王妃)|シャルロット]](ケント公爵の姉)だった。洗礼を司った[[カンタベリー大主教]]マナーズサットンが、赤子の名は何と呼ぶか尋ねたとき、皇帝アレクサンドルが「アレクサンドリナ」と答えた。兄に、聞き慣れない異国風の名前を付けられたケント公爵は、摂政王太子の兄の機嫌を損ねないように、「せめて母親の名前を一つつけたい」と控えめに願い出て、「アレクサンドリナ・ヴィクトリア」という名前となった。このいきさつもあり、公的に名乗るときは「ヴィクトリア・オブ・ケント」としていた。[[1820年]][[1月23日]]、ヴィクトリアが生後8ヶ月のとき、父ケント公爵は亡くなった。 |
|||
父は[[ケント公|ケント公爵]][[エドワード・オーガスタス (ケント公)|エドワード]]([[ハノーヴァー朝]]第3代英国王[[ジョージ3世 (イギリス王)|ジョージ3世]]の四男)。母はその妃[[ヴィクトリア・オブ・サクス=コバーグ=ザールフィールド|ヴィクトリア]]({{仮リンク|ザクセン=コーブルク=ザールフェルト公国|de|Sachsen-Coburg-Saalfeld}}の公[[フランツ (ザクセン=コーブルク=ザールフェルト公)|フランツ]]の娘){{#tag:ref|母のザクセン=コーブルク=ザールフェルト公家は11世紀以来[[エルベ川]]畔地域を支配した[[マイセン辺境伯]][[ヴェッティン家]]の分家[[エルネスティン家]]の一流であり、人口6万ほどの小公国の君主であった<ref name="ストレイチイ(1953)19">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.19</ref>。|group=#}}。 |
|||
母ケント公爵夫人ヴィクトリアは[[ドイツ語]]を母語とし、ヴィクトリアは3歳までドイツ語のみを話す生活を送った。幼児期に[[英語]]の学習を始め、のちに古典[[ギリシア語]]や[[ラテン語]]、[[フランス語]]も学んだ。また[[オペラ]]を好んだため[[イタリア語]]の学習も行った。 |
|||
父ケント公は借金まみれであり、物価の高いイギリスでは暮らしていけないと言って、[[ベルギー]]やドイツ内を転々として暮らしていたが、妃の出産が近くなると、生まれてくる子を「ロンドン出生」にするため流産の危険を冒してでも一時帰国し<ref name="川本(2006)244">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.244</ref><ref>[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.21-22</ref><ref name="森(1986)552">[[#森(1986)|森(1986)]] p.552</ref>{{#tag:ref|[[マーガレット・サッチャー]]首相による1981年の国籍法改正(父か母がイギリス国籍でなければイギリス国籍は認められない)以前のイギリスでは基本的にイギリス国王の領土内に生まれた者にイギリス国籍が認められていた<ref>[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.227-229</ref>。|group=#}}、ケンジントン宮殿を兄の[[ジョージ4世 (イギリス王)|摂政皇太子ジョージ(後の英国王ジョージ4世)]]から借り受けていた<ref>[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.63-64</ref>。 |
|||
ヴィクトリアが10歳のとき、伯父ジョージ4世は子供を残さずに死去し、王弟[[ウィリアム4世 (イギリス王)|ウィリアム4世]]が王位を継承した。ウィリアム4世には子がなく、ヴィクトリアは[[法定推定相続人|推定王位継承者]]となった。母:ケント公夫人は、ヴィクトリアを厳しい監視下に置いた。 |
|||
{{Gallery |
|||
|File:Edward, Duke of Kent and Strathearn by Sir William Beechey.jpg|父の[[ケント公|ケント公爵]][[エドワード・オーガスタス (ケント公)|エドワード]] |
|||
|File:Vicky of Kent.jpg|母の[[ヴィクトリア・オブ・サクス=コバーグ=ザールフィールド|ヴィクトリア]]妃 |
|||
|File:Victoria and Kensington Palace.jpg|ケンジントン宮殿とヴィクトリア像(2005年撮影) |
|||
}} |
|||
=== 生誕時の王位継承における立場 === |
|||
ハノーヴァー王家はドイツの邦国[[ハノーファー王国]]の君主の家柄であるが、旧イギリス王家[[ステュアート朝|ステュアート家]]と縁戚関係があり、その関係でステュアート家が絶えた後、ハノーファー王が同君連合でイギリス王位も継承した。ハノーファー王室は[[サリカ法]]の適用を受けるため、女子の王位継承が認められていないが、イギリス王室にはサリカ法の適用がないため、女子にも継承権があった<ref name="川本(2006)3">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.3</ref>。イギリス王位継承は[[コモン・ロー]]に基づいて定められており、王の最年長の男子が継承するのが基本だが、男子がなく女子のみある場合には最年長の女子が王位を継承する<ref name="川本(2006)3"/><ref>[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.6-7</ref>。 |
|||
生誕時のヴィクトリアのイギリス王位継承順位は3人の伯父、[[摂政皇太子]][[ジョージ4世 (イギリス王)|ジョージ]]、[[ヨーク公]][[フレデリック (ヨーク・オールバニ公)|フレデリック]]、[[クラレンス公]][[ウィリアム4世 (イギリス王)|ウィリアム(後の英国王ウィリアム4世)]]と父ケント公に次ぐ第5位であった<ref name="ワイントラウブ(1993)上71">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.71</ref>。 |
|||
=== 女王時代 === |
|||
[[File:Queen victoria.jpg|thumb|180px|若き女王]] |
|||
[[File:Victoria Marriage01.jpg|left|thumb|180px|アルバートとの婚礼]] |
|||
[[1837年]][[6月20日]]、ウィリアム4世の崩御により、ヴィクトリアは18歳で即位した。即位当初の[[イギリスの首相|首相]]:[[メルボルン子爵ウィリアム・ラム|メルバーン子爵]]の助言により政治を行った。メルバーン子爵を信頼するあまり、1839年に彼が首相を辞した際、後任となるべき[[ロバート・ピール]]と女官人事をめぐって対立し、組閣を承認せず、メルバーン子爵を続投させ政権交代を阻止してしまった。 |
|||
かつて摂政皇太子ジョージには[[シャーロット・オーガスタ・オブ・ウェールズ|シャーロット]]という[[嫡出子]]がおり、いずれ彼女が王位を継ぐものと目されていたが、1817年11月6日に身ごもった子供を死産させた際に[[薨去]]したため次々世代の王位継承者が消滅した<ref>[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.5-6</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)上47">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.47</ref>。というのもこの1817年の時点ではジョージ3世の王子らは摂政皇太子を除いて誰も[[嫡出子]]を持っていなかったからである<ref name="ワイントラウブ(1993)上47">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.47</ref>。 |
|||
[[1840年]][[2月10日]]、母方の従弟に当たる[[ザクセン=コーブルク=ゴータ家|ザクセン=コーブルク=ゴータ公子]] [[アルバート (ザクセン=コーブルク=ゴータ公子)|アルバート]]と挙式。1841年、メルバーン子爵が首相を再び辞した際には、本来何らの権限のないアルバートが妥協案をもたらして、女王と新首相ピールを仲裁した。この一件で軋轢が生じたものの、間もなく妥協が成立し、以後20年余りに渡り、アルバートは「良き夫」として女王を公私ともに支えた。[[1857年]]になって、アルバートに対し正式に「王配殿下」(HRH the Prince consort)の称号を与えた。 |
|||
これに焦った摂政皇太子と議会は結婚していない王子たちに資金援助をちらつかせて、しかるべき君主家の娘を正妃に迎えて嫡出子作りを促した。借金まみれのケント公もそれが目当てでドイツの小邦国の君主の娘と結婚してヴィクトリアを儲けたのであった。ヴィクトリアが生まれる二か月ほど前に伯父クラレンス公にも嫡出子シャルロッテが生まれていたが、その子は出生後すぐに薨去したため、ヴィクトリア誕生の時点ではヴィクトリアが次々世代の王位継承最有力候補者であった<ref name="君塚(2007)10">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.10</ref>。とはいえクラレンス公妃はまだ十分に子を産めそうであり、またヴィクトリアの母ケント公妃もまだ子が産めそうであったため、これから弟が生まれる可能性もあり、そうした場合には第四王子の女子に過ぎないヴィクトリアの王位継承は一気に遠のくという不安定な立場であった<ref name="ストレイチイ(1953)23">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.23</ref>。 |
|||
結婚21年目の[[1861年]][[12月14日]]、42歳で夫アルバートが死去する。女王は悲嘆し、常に喪服を着用するようになり、数年に渡り公の場に姿を現さなくなった。 |
|||
<center>'''ヴィクトリア生誕時のイギリス王位継承順位'''(灰色は故人、かっこの中はハノーファー王位の継承順位)</center> |
|||
<br> |
|||
{{familytree/start}} |
|||
{{familytree | | | | | | | | | | GRP |~|y|~| GRM | |GRP=イギリス王<br>ハノーファー王<br>[[ジョージ3世 (イギリス王)|ジョージ3世]]|GRM=王妃<br>[[シャーロット・オブ・メクレンバーグ=ストレリッツ|シャーロット]]}} |
|||
{{familytree | |,|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| }} |
|||
{{familytree | uncle1 | | uncle2 | | uncle3 | | DAD | | uncle4 | | uncle5 | | uncle6 | uncle1=[[摂政皇太子]]<br>[[ジョージ4世 (イギリス王)|ジョージ]]<br>1位(1位)|uncle2=[[ヨーク公]]<br>[[フレデリック (ヨーク・オールバニ公)|フレデリック]]<br>2位(2位)|uncle3=[[クラレンス公]]<br>[[ウィリアム4世 (イギリス王)|ウィリアム]]<br>3位(3位)|DAD= [[ケント公]]<br>[[エドワード・オーガスタス (ケント公)|エドワード]]<br>4位(4位)|uncle4=[[カンバーランド公]]<br>[[エルンスト・アウグスト (ハノーファー王)|アーネスト]]<br>6位(5位)|uncle5=[[:en:Duke of Sussex|サセックス公]]<br>[[オーガスタス・フレデリック (サセックス公)|オーガスタス]]<br>7位(6位)|uncle6=[[ケンブリッジ公]]<br>[[アドルファス (ケンブリッジ公)|アドルファス]]<br>8位(7位)}} |
|||
{{familytree | |!| | | | | | | |!| | | |!| | | | | | | | | | | |!| }} |
|||
{{familytree |cousin1 | | | | | |cousin2 | | ME | | | | | | | | | | cousin3 | cousin1=[[シャーロット・オーガスタ・オブ・ウェールズ|シャーロット]]|cousin2=シャルロッテ|ME='''ヴィクトリア'''<br>5位(-)|cousin3=[[ジョージ (ケンブリッジ公)|ジョージ]]<br>9位(8位) |
|||
|boxstyle_cousin1=background-color: #808080; |
|||
|boxstyle_cousin2=background-color: #808080; |
|||
}} |
|||
{{familytree | |!| }} |
|||
{{familytree |child of cousin1 | | child of cousin1=男子 |
|||
|boxstyle_child of cousin1=background-color: #808080; |
|||
}} |
|||
{{familytree/end}} |
|||
=== 洗礼式の命名をめぐる騒動 === |
|||
後半生においては、[[ベンジャミン・ディズレーリ]]に絶大な信頼を寄せ、[[ウィリアム・グラッドストン]]とは対立した。 |
|||
6月24日に行われたヴィクトリアの洗礼式において[[代父母|代父]]となったのは、摂政皇太子ジョージ、[[ロシア帝国|ロシア]][[ツァーリ|皇帝]][[アレクサンドル1世]](イギリス訪問中で、ジョージとも仲が良かった)。代母は、ケント公爵夫人ヴィクトリアの実母アウグスタ、[[ヴュルテンベルク王国|ヴュルテンベルク]]公妃[[シャーロット (ヴュルテンベルク王妃)|シャルロット]](伯母)だった。 |
|||
ケント公は娘に「ジョージアナ(ジョージの女性名)」や「エリザベス」といった将来の英国女王としてふさわしい名前を付けたがっていたが<ref name="君塚(2007)10">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.10</ref><ref name="ストレイチイ(1953)23">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.23</ref>、ケント公と仲の悪い摂政皇太子ジョージは命名権は自分にあると主張して譲らなかった<ref name="ワイントラウブ(1993)上69">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.69</ref>。摂政皇太子はできればクラレンス公夫妻に再び嫡出子を作らせて、その子に王位を継がせたかった<ref name="ワイントラウブ(1993)上73">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.73</ref>。 |
|||
晩年は、アルバートを記念した事業に精力を注いだ。その代表例が、[[ヴィクトリア&アルバート博物館]]や[[ロイヤル・アルバート・ホール]]である。「ゴールデン・ジュビリー」と名付けられた即位50周年、「ダイヤモンド・ジュビリー」と名付けられた60周年の記念式典は、それぞれ盛大に行われた。同名の長女:[[ヴィクトリア (ドイツ皇后)|ヴィクトリア王女]]とは最晩年まで親密で、数千通に及ぶ書簡が現存している。 |
|||
洗礼式当日に[[カンタベリー大主教]]が「何という名で祝福するか」王族たちに尋ねると摂政皇太子は「アレクサンドリナ」(ロシア皇帝の名前アレクサンドルの女性名)と答えた<ref name="君塚(2007)10">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.10</ref><ref name="ストレイチイ(1953)23">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.23</ref><ref name="森(1986)552">[[#森(1986)|森(1986)]] p.552</ref>。それに対してケント公はミドルネームに「エリザベス」を加えるよう訴えたが、摂政皇太子は拒否し、母と同じ「ヴィクトリア」をミドルネームとさせた<ref name="ワイントラウブ(1993)上71">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.71</ref>。 |
|||
[[1901年]][[1月22日]]死去。{{没年齢|1819|5|24|1901|1|22}}。在位64年におよんだ<ref>在位年数が、女王に匹敵するのは(近代以降では)オーストリアの[[フランツ・ヨーゼフ1世 (オーストリア皇帝)|フランツ・ヨーゼフ1世]]帝(在位68年)、日本の[[昭和天皇]](在位62年+[[摂政宮]]5年)、タイの[[ラーマ9世]](※1946年より在位中)がいる。</ref>。 |
|||
こうして彼女の名前は「アレクサンドリナ・ヴィクトリア」というイギリス人になじみが薄いロシア名とドイツ名になった(ヴィクトリアの名がイギリスの一般的な名前になるのは彼女が女王に即位した後のことである)<ref name="君塚(2007)10">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.10</ref>。王女時代にはアレクサンドリナという名から「ドリナ」と愛称された<ref name="君塚(2007)10">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.10</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)上71">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.71</ref>。 |
|||
== 子女 == |
|||
[[File:Queen Victoria Prince Albert and their nine children.JPG|thumb|right|280px|女王夫妻と9人の子供たち]] |
|||
=== ジョージ4世治世下の幼女時代 === |
|||
子供達をドイツを中心とした各国に嫁がせ、晩年には「[[ヨーロッパの祖母]]」と呼ばれるに至る。しかし女王自身が[[血友病]]の因子を持っており、ロシア皇太子[[アレクセイ・ニコラエヴィチ (ロシア皇太子)|アレクセイ]]を始めとする男子が次々と発病した。ヴィクトリア女王の傍系の親族には血友病保因者はいないため、ヴィクトリア女王が血友病の突然変異を持って生まれたと見られる。 |
|||
[[File:Princess Victoria aged Four.jpeg|thumb|200px|4歳の頃のヴィクトリア([[ステファン・ポインツ・デニング]]([[:en:Stephen Poyntz Denning|en]])画)]] |
|||
[[1820年]][[1月23日]]、ヴィクトリアが生後8ヶ月のとき、父ケント公が薨去した<ref name="君塚(2007)11">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.11</ref><ref name="森(1986)553">[[#森(1986)|森(1986)]] p.553</ref><ref>[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.79-80</ref>。時期同じくして1月29日には国王ジョージ3世が崩御し、摂政皇太子ジョージがジョージ4世としてハノーヴァー朝第4代国王に即位した<ref name="君塚(2007)11"/><ref name="ワイントラウブ(1993)上81">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.81</ref>。 |
|||
夫が残した莫大な借金を背負わされた母ケント公妃はヴィクトリアを連れて英国を離れることも考えたが、兄[[レオポルド1世 (ベルギー王)|レオポルド]](亡きシャーロットの夫で1831年にベルギー王に即位するまで英国に滞在し続けていた)から資金援助を受け、ジョージ4世からそのまま住むことを認められていたケンジントン宮殿に留まることにした<ref name="君塚(2007)12">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.12</ref><ref name="ストレイチイ(1953)26">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.26</ref>。 |
|||
1820年12月にはクラレンス公が娘エリザベスを儲けたため、ヴィクトリアの王位継承は一時遠のいた<ref name="君塚(2007)10">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.10</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)上86">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.86</ref>。しかしこのエリザベスは1821年春に生後4カ月で薨去したため、再びヴィクトリアの王位継承の可能性が高まった<ref name="ストレイチイ(1953)27">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.27</ref><ref name="森(1986)553">[[#森(1986)|森(1986)]] p.553</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)上87">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.87</ref>。 |
|||
ヴィクトリアはケンジントン宮殿で母ケント公妃に大事に育てられた。ヴィクトリアは何歳になっても個室を与えられず、母と同じ寝室で寝起きして母の監視を受けた<ref name="ストレイチイ(1953)36">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.36</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)上92">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.92</ref>。母はケント公爵家家令{{仮リンク|ジョン・コンロイ|label=サー・ジョン・コンロイ|en|John Conroy}}の影響を強く受けており<ref name="ストレイチイ(1981)44">[[#ストレイチイ(1981)|ストレイチイ(1981)]] p.44</ref>、ヴィクトリアもコンロイの娘ヴィクトワールとよく一緒に遊んだ<ref name="ストレイチイ(1953)30">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.30</ref>。 |
|||
母は[[ドイツ語]]を母語としていたので、ヴィクトリアも3歳までドイツ語のみを話す生活を送った。幼児期に[[英語]]と[[フランス語]]の学習を始め、やがて三ヶ国語を自由に話せるようになった。後にはイタリア語とラテン語も少し使えるようになった<ref name="ストレイチイ(1953)36"/>。ヴィクトリアは5歳まで反抗して[[アルファベット]]の勉強をしようとしなかったというが、5歳の頃イギリスと同君連合の[[ハノーファー王国]]出身の{{仮リンク|ルイーゼ・レーツェン|de|Louise Lehzen}}が[[ガヴァネス]]に付くと反抗も落ち着いてきて勉強をするようになったという<ref name="ストレイチイ(1953)29">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.29</ref>。このレーツェンはヴィクトリアに非常に大きな影響を与えた<ref name="ストレイチイ(1953)38">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.38</ref>。 |
|||
6歳の頃には自らの高貴な身分を自覚していたといい、臣民の友人が身分をわきまえずに自分のおもちゃに触ろうとしたり、自分の名前を呼び捨てにするとたしなめるようになったという<ref name="ストレイチイ(1953)30">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.30</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)上100">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.100</ref>。 |
|||
* [[ヴィクトリア (ドイツ皇后)|ヴィクトリア]]([[1840年]]-[[1901年]]) - [[ドイツ帝国|ドイツ]][[ドイツ皇帝|皇帝]][[フリードリヒ3世 (ドイツ皇帝)|フリードリヒ3世]]皇后 |
|||
* [[エドワード7世 (イギリス王)|アルバート・エドワード]]([[1841年]]-[[1910年]]) - [[エドワード7世 (イギリス王)|エドワード7世]] |
|||
* [[アリス (ヘッセン大公妃)|アリス]]([[1843年]]-[[1878年]]) - [[ヘッセン大公国|ヘッセン大公]][[ルートヴィヒ4世 (ヘッセン大公)|ルートヴィヒ4世]]大公妃 |
|||
* [[アルフレート (ザクセン=コーブルク=ゴータ公)|アルフレッド]]([[1844年]]-[[1900年]]) - [[ザクセン=コーブルク=ゴータ公国|ザクセン=コーブルク=ゴータ公]]・[[エディンバラ公|エディンバラ公爵]] |
|||
* [[ヘレナ (イギリス王女)|ヘレナ]]([[1846年]]-[[1922年]]) - シュレースヴィヒ=ホルシュタイン公子[[クリスティアン・フォン・シュレースヴィヒ=ホルシュタイン=ゾンダーブルク=アウグステンブルク|クリスティアン]]夫人 |
|||
* [[ルイーズ (アーガイル公爵夫人)|ルイーズ]]([[1848年]]-[[1939年]]) - [[ジョン・キャンベル (第9代アーガイル公爵)|アーガイル公爵ジョン・ダグラス・サザーランド・キャンベル]]夫人 |
|||
* [[アーサー (コノート公)|アーサー]]([[1850年]]-[[1942年]]) - [[コノート|コノート公爵]] |
|||
* [[レオポルド (オールバニ公)|レオポルド]]([[1853年]]-[[1884年]]) - [[オールバニ|オールバニ公爵]] |
|||
* [[ベアトリス (イギリス王女)|ベアトリス]]([[1857年]]-[[1944年]]) - [[バッテンベルク家|バッテンベルク公]][[ヘンリー・オブ・バッテンバーグ|ハインリヒ・モーリッツ]]公妃 |
|||
国王ジョージ4世は相変わらずケント公妃を嫌っていたが、同時にこの頃にはヴィクトリアの王位継承は避けられないと考えるようにもなっていた。1825年にケント公爵家の年金が6000ポンド増額され、1826年にヴィクトリアは7歳にして[[ガーター勲章]]を与えられ、以降国王は頻繁に彼女を引見するようになった<ref name="君塚(2007)14">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.14</ref>。国王の釣り船に乗せてもらった際に国王が軍楽隊に何を弾かせるかヴィクトリアに尋ねると彼女は『[[女王陛下万歳|神よ、国王陛下を守りたまえ]]』をリクエストしたという<ref name="ストレイチイ(1953)32">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.32</ref>。 |
|||
== 系譜 == |
|||
{{Gallery |
|||
{{競走馬血統表 |
|||
| |
|File:George IV of the United Kingdom.jpg|伯父である国王[[ジョージ4世 (イギリス王)|ジョージ4世]] |
||
|File:Arts-graphics-2008 1131738a.jpg|母ケント公妃と5歳の頃のヴィクトリア。 |
|||
|inf = ([[ウィンザー家]]) |
|||
|File:Baroness Lehzen, 1842 by Koepke.jpg|ヴィクトリアの[[ガヴァネス]]だったルイーゼ・レーツェン。 |
|||
|f= 2. [[ケント公|ケント公爵]][[エドワード・オーガスタス (ケント公)|エドワード]] |
|||
|File:Sir John Conroy.jpg|母ケント公妃に強い影響力を持っていた家令サー・ジョン・コンロイ。 |
|||
|m= 3. [[ヴィクトリア・オブ・サクス=コバーグ=ザールフィールド|ヴィクトリア]] |
|||
|ff= 4. 英国王[[ジョージ3世 (イギリス王)|ジョージ3世]] |
|||
|fm= 5. [[シャーロット・オブ・メクレンバーグ=ストレリッツ|シャーロット]] |
|||
|mf= 6. [[フランツ (ザクセン=コーブルク=ザールフェルト公)|フランツ]] |
|||
|mm= 7. [[アウグステ・ロイス・ツー・エーベルスドルフ|アウグステ]] |
|||
|fff= 8. [[プリンス・オブ・ウェールズ|英国王太子]][[フレデリック・ルイス (プリンス・オブ・ウェールズ)|フレデリック]] |
|||
|ffm= 9. [[オーガスタ・オブ・サクス=ゴータ|オーガスタ]] |
|||
|fmf= 10. カール |
|||
|fmm= 11. エリーザベト |
|||
|mff= 12. [[エルンスト・フリードリヒ (ザクセン=コーブルク=ザールフェルト公)|エルンスト]] |
|||
|mfm= 13. ゾフィー |
|||
|mmf= 14. [[ハインリヒ24世 (ロイス=エーベルスドルフ伯)|ハインリヒ]] |
|||
|mmm= 15. カロリーネ |
|||
|ffff= 16. 英国王[[ジョージ2世 (イギリス王)|ジョージ2世]] |
|||
|fffm= 17. [[キャロライン・オブ・アーンズバック|キャロライン]] |
|||
|ffmf= 18. [[フリードリヒ2世 (ザクセン=ゴータ=アルテンブルク公)|フリードリヒ2世]] |
|||
|ffmm= 19. [[マグダレーナ・アウグスタ・フォン・アンハルト=ツェルプスト|マグダレーナ]] |
|||
|fmff= 20. [[:en:Adolphus Frederick II, Duke of Mecklenburg|Adolphus Frederick II]] |
|||
|fmfm= 21. [[:en:Princess Christiane Emilie of Schwarzburg-Sondershausen|Princess Christiane Emilie]] |
|||
|fmmf= 22. [[:en:Ernest Frederick I, Duke of Saxe-Hildburghausen|Ernest Frederick I]] |
|||
|fmmm= 23. [[:en:Countess Sophia Albertine of Erbach-Erbach|Countess Sophia Albertine]] |
|||
|mfff= 24. [[:en:Francis Josias, Duke of Saxe-Coburg-Saalfeld|Francis Josias]] |
|||
|mffm= 25. [[:en:Princess Anna Sophie of Schwarzburg-Rudolstadt|Princess Anna Sophie]] |
|||
|mfmf= 26. [[フェルディナント・アルブレヒト2世 (ブラウンシュヴァイク=ヴォルフェンビュッテル公)|フェルディナント・アルブレヒト2世]] |
|||
|mfmm= 27. [[アントイネッテ・アマーリエ・フォン・ブラウンシュヴァイク=ヴォルフェンビュッテル|アントイネッテ・アマーリエ]] |
|||
|mmff= 28. [[:en:Heinrich XIX, Count of Reuss-Ebersdorf|Heinrich XIX]] |
|||
|mmfm= 29. [[:en:Countess Sophia Dorothea of Castell-Castell|Countess Sophia Dorothea ]] |
|||
|mmmf= 30. [[:en:George Augustus, Count of Erbach-Schönberg|George Augustus]] |
|||
|mmmm= 31. [[:en:Countess Ferdinande Henriette of Stolberg-Gedern|Countess Ferdinande Henriette]] |
|||
}} |
}} |
||
=== ウィリアム4世治世下の少女時代 === |
|||
[[File:Victoria sketch 1835.jpg|thumb|200px|1835年のヴィクトリアの[[自画像]]のスケッチ]] |
|||
1830年6月26日、国王ジョージ4世が子のないまま崩御した。国王の次弟ヨーク公はすでになく、三弟クラレンス公ウィリアムがウィリアム4世としてハノーヴァー朝第5代国王に即位した<ref name="君塚(2007)15">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.15</ref>。ウィリアム4世は即位時すでに65歳であり、新しい嫡出子を儲けることはほとんど諦めており、ヴィクトリアに王位継承の期待を寄せるようになっていた<ref name="森(1986)553"/>。ただ彼はヴィクトリアの母であるケント公妃のことを非常に嫌っていた<ref name="君塚(2007)17">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.17</ref>。 |
|||
ウィリアム4世即位にあたってヴィクトリアは議会から「暫定王位継承者」に認定され<ref name="森(1986)553"/><ref name="ストレイチイ(1953)32">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.32</ref>、彼女の帝王教育も強化された<ref name="君塚(2007)15">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.15</ref>。乗馬や舞踏、絵画、音楽など上流階級のたしなみを身に付けていった。とりわけスケッチが好きであり、彼女は生涯にわたって絵を描き続けた。歴代英国首相や[[フランス皇帝]][[ナポレオン3世]]を描いたヴィクトリアの絵が現代の[[ロイヤル・コレクション]]の中にも残っている<ref name="君塚(2007)15">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.15</ref>。 |
|||
「暫定王位継承者」になったとはいえヴィクトリアはいまだ自らが王位継承者であることを教えられていなかった。この年ヴィクトリアは11歳であったが、母ケント公妃は[[カンタベリー大主教]]ら聖職者たちの助言に従ってヴィクトリアに女王となる定めであることを告げることを決心した。歴史の授業の際に保母が英国王室系譜表を本の中に隠しておき、それをヴィクトリアに発見させ、いかなる立場にあるのか説明させたという。それを聞いたヴィクトリアはしばらく口をつぐんでいたが、やがて「良い人になるようにしますわ」と述べたという。そしてその後一人で大泣きしたという<ref name="ストレイチイ(1953)35">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.35</ref>。 |
|||
この頃、[[トーリー党 (イギリス)|トーリー党]]([[保守党 (イギリス)|保守党]])の政権が崩壊し、[[ホイッグ党 (イギリス)|ホイッグ党]]([[自由党 (イギリス)|自由党]])が政権を掌握して政府が自由主義的な色彩を持つようになった<ref name="ストレイチイ(1953)32">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.32</ref>。亡き父ケント公は兄との対立からホイッグ党に肩入れしており、ケント公妃も夫に従って同じ党派に属していた<ref>[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.27-28</ref>。そのためヴィクトリアは保守的な叔父[[カンバーランド公]][[エルンスト・アウグスト (ハノーファー王)|アーネスト]]と対比される形で自由主義者の期待を一身に受けていた<ref>[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.27-28</ref>。一方国王ウィリアム4世はホイッグ党の大臣たちと対立を深めていき、その黒幕と看做したケント公妃をより憎むようになった<ref name="ストレイチイ(1953)45">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.45</ref>。 |
|||
ヴィクトリアが暫定王位継承者になると母ケント公妃はしばしば摂政同然にふるまうようになった。帝王教育の一環でヴィクトリアはケント公妃に連れられてイギリス各地を旅行するようになったが、ヴィクトリアを差し置いてケント公妃の摂政然とした態度が目立ったという<ref name="森(1986)554">[[#森(1986)|森(1986)]] p.554</ref>。[[ソレント海峡]]の旅行ではケント公妃は海峡沿岸の砲台や軍艦に[[礼砲|王礼砲]]を行う事を要求したが、これに国王は激怒し、王と王妃以外への礼砲を禁じる緊急勅令を下している<ref>[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.44-45</ref><ref name="森(1986)554">[[#森(1986)|森(1986)]] p.554</ref>。 |
|||
また国王はケント公妃が実家ザクセン=コーブルク家の公子たちをやたらとヴィクトリアに引き会わせようとすることに苛立ち、その阻止に全力を尽くした<ref name="君塚(2007)17">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.17</ref><ref name="ストレイチイ(1953)45">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.45</ref>。またケント公妃の兄であるベルギー王レオポルドが頻繁にヴィクトリアに手紙を送ってくることも気にくわなかった。国王にはザクセン=コーブルク家をあげてイギリス王室を乗っ取ろうとしているように思えた<ref name="君塚(2007)18">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.18</ref>。 |
|||
1837年5月24日にヴィクトリアは18歳になり、成人した。国王はお祝いとして彼女の年金を1万ポンド増額させるとともに新宮殿を与えるので母親から独立してはどうかと勧めたが、ケント公妃の反対によりヴィクトリアは辞退した<ref name="君塚(2007)19">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.19</ref>。 |
|||
{{Gallery |
|||
|File:William IV of Great Britain c. 1850.jpg|伯父である国王[[ウィリアム4世 (イギリス王)|ウィリアム4世]]。ヴィクトリアをケント公妃から引き離したがっていた。 |
|||
|File:Queen Victoria as a girl - Westall 1830.jpg|1830年のスケッチをするヴィクトリアを描いた絵画({{仮リンク|リチャード・ウェスタール|en|Richard Westall}}画) |
|||
|File:Queen Victoria when a girl 1832.jpg|1832年のヴィクトリアを描いた絵画([[ロイヤル・コレクション]]の絵画) |
|||
|File:Princess Victoria and Dash by George Hayter.jpg|1833年のヴィクトリアを描いた絵画({{仮リンク|ジョージ・ハイター|en|George Hayter}}画) |
|||
}} |
|||
{{-}} |
|||
=== 英国女王に即位 === |
|||
[[File:Dronning victoria.jpg|thumb|250px|戴冠式の際のヴィクトリア女王を描いた[[ジョージ・ハイター]]([[:en:George Hayter|en]])の肖像画。]] |
|||
1837年6月20日午前2時20分にウィリアム4世は[[ウィンザー城]]で崩御した。これによりヴィクトリアが18歳にしてハノーヴァー朝第6代女王に即位した{{#tag:ref|これまでハノーヴァー朝はイギリス王位とハノーファー王位を兼ねてきたが、ハノーファー王位はサリカ法により男性しか継げないため、ヴィクトリアはイギリス王位しか継げず、ハノーファー王位は叔父カンバーランド公アーネストが[[エルンスト・アウグスト (ハノーファー王)|エルンスト・アウグスト]]として受け継いだ。|group=#}}。 |
|||
{{仮リンク|宮内長官 (イギリス)|label=宮内長官|en|Lord Chamberlain}}{{仮リンク|フランシス・カニンガム|label=カニンガム卿|en|Francis Conyngham, 2nd Marquess Conyngham}}と[[カンタベリー大主教]]{{仮リンク|ウィリアム・ハウリ|en|William Howley}}は新女王に即位の報告をするためロンドン・ケンジントン宮殿へと向かった。ヴィクトリアは午前6時に母ケント公妃に起こされ、カニンガム卿とカンタベリー大主教を引見した。カニンガム卿は彼女に国王崩御を報告し、その場に跪いて新女王の手に口づけした<ref name="君塚(2007)20">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.20</ref>。 |
|||
ついで午前9時と午前11時に首相である[[メルボルン子爵ウィリアム・ラム|メルバーン子爵]]がケンジントン宮殿を訪問してヴィクトリアの引見を受け、彼女の手に口づけした<ref>[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.52-53</ref>。ヴィクトリアは彼に引き続き国政を任せると述べた<ref name="ストレイチイ(1953)53">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.53</ref>。 |
|||
午前11時半よりケンジントン宮殿内の赤の大広間において最初の[[枢密院 (イギリス)|枢密院会議]]を開いた。出席した[[枢密顧問官]]たちは新女王の優雅な物腰、毅然とした態度、堂々たる勅語に感服したという<ref>[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.21-22</ref><ref>[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.53-55</ref><ref>[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.156-158</ref>。[[アーサー・ウェルズリー (初代ウェリントン公爵)|ウェリントン公爵]]はその光景を「彼女はその肉体で自らの椅子を満たし、その精神で部屋全体を満たしていた」と表した<ref name="ワイントラウブ(1993)上158">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.158</ref>。また[[ジョン・ラッセル (初代ラッセル伯)|ジョン・ラッセル卿]]は「ヴィクトリア女王の治世は後代まで、また世界万国に対して不滅の光を放つであろう」と予言した<ref name="ストレイチイ(1953)55">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.55</ref>。 |
|||
イギリスでは[[ピューリタン革命]]や[[名誉革命]]、またハノーヴァー朝初代国王[[ジョージ1世 (イギリス王)|ジョージ1世]](ハノーファー選帝侯ゲオルク1世)がハノーファーばかりに関心を持ち、イギリスにほとんど関心を示さなかったことなどにより、他国の君主に比べると君主権がやや弱く、内閣や議会の力が強い傾向があった。とはいえ19世紀半ばのイギリス王はいまだ巨大な{{仮リンク|国王大権|en|Royal Prerogative}}を有しており、いざという時には強権発動が可能であった。大臣の任免、議会の招集・解散、国教会の聖職者と判事の任免、宣戦布告などは国王の大権であった。前王ウィリアム4世も自分と対立した首相をクビにしている。彼女が受け継いだ王位とはそうした巨大な権力であった<ref>[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.23-24</ref>。 |
|||
ヴィクトリアは即位の日の日記に「私が王位につくのが神の思し召しなら私は全力を挙げて国に対する義務を果たすだろう。私は若いし、多くの点で未経験者である。だが正しいことをしようという善意・欲望においては誰にも負けないと信じている。」と抱負を書いている<ref name="ストレイチイ(1953)53">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.53</ref>。 |
|||
即位の日に行った引見はいずれも母の同席なしで行った。この日以来彼女は家族絡みの会見以外はすべて一人で行うようになった<ref name="君塚(2007)20">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.20</ref>。母もヴィクトリアとともにケンジントン宮殿から[[バッキンガム宮殿]]へ移っているが、ヴィクトリアは母が自分に干渉してこないよう、母の部屋を自分の部屋から遠ざけた<ref name="ストレイチイ(1953)57">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.57</ref><ref>[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.159-160</ref>。家令サー・ジョン・コンロイに至っては今後の目通りは一切叶わない旨を通達している<ref name="ストレイチイ(1953)57"/>。一方レーツェンは自分の部屋の隣に留め置いて相談役として重用した<ref name="ストレイチイ(1953)58">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.58</ref>。また伯父ベルギー王レオポルドの側近であるコーブルク家臣{{仮リンク|クリスティアン・フリードリヒ・フォン・シュトックマー|de|Christian Friedrich von Stockmar}}男爵がレオポルドとの連絡役としてバッキンガム宮殿に勤務するようになり、ヴィクトリアの新たな助言役となっていった<ref>[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.59-61</ref>。しかしベルギーに肩入れするよう求めるレオポルドの要請に対してはヴィクトリアは慎重に回避し続けた<ref>[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.78-81</ref>。 |
|||
女王として年金38万5000ポンド、[[ランカスター公]]として{{仮リンク|ランカスター公領|en|Duchy of Lancaster}}からの収入2万7000ポンドを受けるようになり、そのお金で父親が残した巨額の借金を返済し、何不自由ない生活を送るようになった<ref name="ストレイチイ(1953)70">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.70</ref>。 |
|||
翌6月21日に[[セント・ジェームズ宮殿]]で君主宣言の儀を行い、勅命によって王名を「ヴィクトリア」と定め、以降「アレクサンドリナ」は使用されなくなった<ref name="君塚(2007)20">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.20</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)上161">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.161</ref>。 |
|||
[[戴冠式]]は即位後1年後の1938年6月28日にロンドン・[[ウェストミンスター寺院]]において挙行した。ウェストミンスター寺院までの道すがら、「女王陛下万歳」を叫ぶ群衆たちの中を{{仮リンク|黄金馬車|en|Gold State Coach}}で通過した。ヴィクトリアはその日の日記に「このような国民たちの女王となることをいかに誇りに思うことか」と書いている<ref name="君塚(2007)25">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.25</ref>。 |
|||
{{Gallery |
|||
|File:Victoriatothrone.jpg|新女王の御前に跪いてその手に口づけする宮内長官カニンガム卿とカンタベリー大主教ウィリアム・ハウリ。 |
|||
|File:Victoria Privy Council (Wilke).jpg|即位当日、最初の枢密院会議を開くヴィクトリア女王を描いた{{仮リンク|デヴィッド・ヴィルキー|en|David Wilkie (artist)}}の絵画。ヴィクトリアが純白の服を着ているが、これは彼女を目立たせるためであり、実際には黒い喪服を着ていた<ref>[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.156-157</ref>。 |
|||
|File:Coronation of Queen Victoria - John Martin.jpg|ウェストミンスター寺院でのヴィクトリア女王の戴冠式を描いた{{仮リンク|ジョン・マーティン|en|John Martin}}の絵画 |
|||
|File:Victoria coronation 1.jpg|戴冠式。カンタベリー大主教から[[聖油]]を注がれるヴィクトリアを描いた絵画。 |
|||
}} |
|||
{{-}} |
|||
=== 内政 === |
|||
==== メルバーン子爵を寵愛 ==== |
|||
[[File:2nd V Melbourne.jpg|thumb|150px|首相[[メルボルン子爵ウィリアム・ラム|メルバーン子爵]]]] |
|||
首相メルバーン子爵は保守主義者であったが、機会主義者でもあったのでホイッグ党に所属し、本心では反対だったにもかかわらず選挙法改正などの改革を押し進めた<ref name="ストレイチイ(1953)65">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.65</ref>。彼は前王ウィリアム4世との関係は悪かったが、シュトックマー男爵がメルバーン子爵の良い評判をヴィクトリアに聞かせていたため、ヴィクトリアからは早々に気に入られることとなった<ref name="君塚(2007)31">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.31</ref><ref name="ストレイチイ(1953)68">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.68</ref><ref name="森(1986)558">[[#森(1986)|森(1986)]] p.558</ref>。 |
|||
国王秘書官の職が廃され、メルバーン子爵がこれを兼務し、彼は首相であると同時に女王の第一の側近となった<ref name="伊藤(2004)247">[[#伊藤(2004)|伊藤・川田(2004)]] p.247</ref>。メルバーン子爵は洗練されたマナーと話術の持ち主でヴィクトリアを魅了して止まなかった<ref name="森(1986)559">[[#森(1986)|森(1986)]] p.559</ref>。二人は君臣の関係を越えて、まるで父娘のような関係になっていった<ref name="君塚(2007)31"/>。女王の日記には毎日のように「メルバーン卿」「M卿」の名前が登場するようになる<ref name="君塚(2007)31"/><ref>[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.71-74</ref>。 |
|||
しかし1839年にホイッグ党の右派が離党してトーリー党に合流し、また左派もメルバーン批判を強めた結果、メルバーンは議会において苦しい立場に立たされた<ref name="君塚(2007)32">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.32</ref>。1839年5月初めに[[英領西インド諸島|英領ジャマイカ]]の奴隷制度廃止法案をめぐってトーリー党と現地の農場主から攻撃を受けたメルバーンは5月7日にヴィクトリアに辞表を提出した<ref name="ワイントラウブ(1993)上192">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.192</ref>。ヴィクトリアの衝撃は大きく、泣き崩れたという<ref name="ストレイチイ(1953)87">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.87</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)上193">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.193</ref>。 |
|||
トーリー党の指導者である{{仮リンク|貴族院議長 (イギリス)|label=貴族院議長|en|Leader of the House of Lords}}[[アーサー・ウェルズリー (初代ウェリントン公爵)|ウェリントン公爵]]を召し、ウェリントン公爵の勧めに従って[[ロバート・ピール]]に首相の[[大命降下]]を下した<ref name="君塚(2007)33">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.33</ref><ref name="ストレイチイ(1953)87">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.87</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)上194">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.194</ref>。この際にヴィクトリアはウェリントン公爵やピールに対して今後もメルバーン卿に諮問して良いかと下問した<ref name="君塚(2007)33"/>。ウェリントン公爵はこれを承諾しているが、ピールは拒絶した。枢密院や議会においてではなく、宮中で野党党首が個人的に女王の側近になるなど前代未聞のことであった<ref name="伊藤(2004)248">[[#伊藤(2004)|伊藤・川田編(2004)]] p.248</ref>。 |
|||
これがきっかけでヴィクトリアはピールに嫌悪感を持つようになり、ピールが宮中の女官(ほとんどがホイッグ党の政治家の家族)をトーリー党の者に刷新する案をヴィクトリアに献策した際にヴィクトリアは「一人たりとも辞めさせない」と言って頑強に退けた<ref name="朝倉(1996)122"/><ref name="君塚(2007)34">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.34</ref><ref name="ストレイチイ(1953)89">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.89</ref>。結局ピールはこのために首相職を辞退し、メルバーンが首相に戻ることとなった({{仮リンク|寝室女官事件|en|Bedchamber crisis}}<ref name="君塚(2007)34">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.34</ref>。 |
|||
ヴィクトリアは女官の人事は女王の私的人事であることを強調したが、政権交代のたびに宮廷内の役人も入れ替わるのが慣例であった<ref name="伊藤(2004)248"/><ref name="ストレイチイ(1953)89">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.89</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)上196">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.196</ref>。マスコミはヴィクトリアのきまぐれが立憲政治の確立を妨げていると批判し、彼女を諌める夫が必要だという議論を加速させた<ref name="ワイントラウブ(1993)上197">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.197</ref>。ヴィクトリア本人は後年に寝室女官事件について「あの頃の私は非常に若かった。あの一件を今やり直せるとしたら、私は違った行動を取るだろう。」と語っている<ref name="ワイントラウブ(1993)上197"/><ref name="朝倉(1996)122"/>。 |
|||
{{-}} |
|||
==== アルバート公子との結婚と「共同統治」 ==== |
|||
[[File:Prince Albert - Partridge 1840.jpg|thumb|200px|1840年時の[[アルバート (ザクセン=コーブルク=ゴータ公子)|アルバート公子]]を描いた[[ジョン・パートリッジ]]([[:en:John Partridge (artist)|en]])の肖像画(ロイヤル・コレクション)。]] |
|||
[[ザクセン=コーブルク=ゴータ公]][[エルンスト1世 (ザクセン=コーブルク=ゴータ公)|エルンスト1世]](母ケント公妃の兄)の次男である[[アルバート (ザクセン=コーブルク=ゴータ公子)|アルベルト]](英語名アルバート)がヴィクトリアの婿の最有力候補だった。この二人の結婚はエルンスト1世、母ケント公妃、ベルギー王レオポルドとザクセン=コーブルク家をあげて推進していた<ref name="朝倉(1996)122"/><ref name="ストレイチイ(1953)99">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.99</ref>。 |
|||
ヴィクトリアは1836年にアルバートと会ったことがあり、その時の日記の中でアルバートを「目は綺麗な[[碧眼]]、美しい鼻と口。顔の魅力はその表情によってうっとりする。同時に善良さと甘美さと知的さを持っている」と絶賛していた<ref name="君塚(2007)38">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.38</ref><ref name="ストレイチイ(1953)41">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.41</ref>。 |
|||
もっとも1839年4月にヴィクトリアはメルバーン子爵に対して「私は当面いかなる結婚もしたくない」と語っている<ref name="ストレイチイ(1953)96">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.96</ref>。アルバートのことは嫌いではなかったが、周囲が勝手にアルバートとのお見合いを進めているのが気に入らなかったという<ref name="ストレイチイ(1953)97">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.97</ref>。だが結局周囲に流される形で1839年10月10日にウィンザーを訪れたアルバートを引見することになった。この頃アルバートは一層美男になっており、ヴィクトリアはすっかり彼に一目ぼれした。引見の翌日に彼女はメルバーン子爵に対して「結婚に対する意見を変えた」と述べ、さらに翌々日には「アルバートと結婚する意志を固めた」と述べた<ref name="ストレイチイ(1953)98">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.98</ref>。 |
|||
後日再びアルバートを召し、君主である彼女の方からプロポーズを行った。「貴方が私の(結婚の)望みを叶えてくれたらどんなに幸せでしょう」と言ってプロポーズしたという<ref name="川本(2006)7">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.7</ref><ref name="ストレイチイ(1953)98">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.98</ref>。 |
|||
ヴィクトリアとアルバートは1840年2月10日にロンドンのセント・ジェームズ宮殿で結婚式を挙行した<ref name="君塚(2007)39">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.39</ref>。その翌日のベルギー王レオポルドへの手紙でヴィクトリアは「世界で私ほど幸せな人間はいないと思います。彼は天使のようです。昨日の披露宴は楽しくて熱気にあふれていました。ロンドン市内では群衆が果てしなく沿道に続いていました」と書いている<ref name="朝倉(1996)122"/>。 |
|||
ヴィクトリアのハードスケジュールのため、新婚旅行はウィンザーまでのわずか42キロで済まされた。アルバートがそれについて不満を述べるとヴィクトリアは「貴方は私が君主であることをお忘れなのね。今は議会の会期中であり、私が行わねばならない執務も山のようにあります。ほんの2、3日であっても私がロンドンを離れることは許されないのです」と反論したという<ref name="川本(2006)62">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.62</ref><ref name="君塚(2007)42">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.42</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)上219">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.219</ref>。{{-}} |
|||
[[File:Edward Oxford shoots at H. M. the Queen, 1840.jpg|thumb|200px|1840年のヴィクトリアとアルバートの乗った馬車への狙撃事件。]] |
|||
1840年6月、ヴィクトリアとアルバートが馬車で{{仮リンク|コンスティテューション・ヒル (ロンドン)|label=コンスティテューション・ヒル|en|Constitution Hill, London}}を通過中、見物人の一人が女王に向けて発砲する事件が発生した。一発目は外れ、続けて二発目が撃たれる直前にアルバートはヴィクトリアを馬車のなかに引き倒して彼女を守った<ref name="ワイントラウブ(1993)上231">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.231</ref>。アルバートの行動は新聞に称賛され、ヴィクトリアとアルバートが行くところ国民の万歳の声があがるようになった<ref name="ワイントラウブ(1993)上231">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.231</ref>。 |
|||
しかし貴族社会や[[社交界]]からはアルバートは「外国人」として疎まれていた<ref name="森(1986)561">[[#森(1986)|森(1986)]] p.561</ref>。ヴィクトリアも結婚初期にはアルバートが公文書を見ることを許可しなかったが<ref name="川本(2006)23">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.23</ref>、1840年11月に生まれた[[ヴィクトリア (ドイツ皇后)|長女ヴィクトリア(愛称ヴィッキー)]]、1841年11月に生まれた[[エドワード7世 (イギリス王)|長男アルバート・エドワード(愛称バーティ)]]を筆頭に1840年代にヴィクトリアが出産を繰り返したため、アルバートが補佐役を務める必要性が増した<ref name="君塚(2007)44">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.44</ref>。 |
|||
1842年頃からヴィクトリアは公文書作成にあたってアルバートの助力を得るようになり、また大臣引見の際にもアルバートを同席させるようになった。これ以降イギリスはヴィクトリアとアルバートの共同統治に近い状態と化した<ref name="川本(2006)23">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.23</ref><ref name="君塚(2007)42">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.42</ref>。アルバートはメルバーン子爵やホイッグ党に肩入れするヴィクトリアに対して「君主は党派争いを超越した存在にならなければならない」と諌め、王権の中立化に努めた<ref>[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.23-25</ref>{{#tag:ref|ただしアルバートは立憲君主を志向した人物ではなくホイッグ党([[自由党 (イギリス)|自由党]])が政権につこうとトーリー党([[保守党 (イギリス)|保守党]])が政権に付こうと王権が影響力を発揮できる状態、つまり王権強化を考えていた<ref name="川本(2006)26">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.26</ref>。彼の王権強化思想はアルバートの顧問になっていた[[クリスティアン・フリードリヒ・フォン・シュトックマー]]([[:de:Christian Friedrich von Stockmar|de]])男爵の影響であった<ref name="ヒバート(1998)169">[[#ヒバート(1998)|ヒバート(1998)]] p.169</ref>。|group=#}}。 |
|||
アルバートは宮中での自身の影響力の増大にも努めた。1842年にはヴィクトリアの幼い頃からの側近であるレーツェンを宮廷から去らせた<ref name="ストレイチイ(1953)121">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.121</ref>。さらに1844年にはピール首相の反対を押し切って二大政党の綱引きで雁字搦めになっていた王室管理機構の改革にあたり、{{仮リンク|宮内長官 (イギリス)|label=宮内長官|en|Lord Chamberlain}}、{{仮リンク|家政長官 (イギリス)|label=家政長官|en|Lord Steward}}、{{仮リンク|主馬頭 (イギリス)|label=主馬頭|en|Master of the Horse}}の分掌体制を{{仮リンク|王室家政長官 (イギリス)|label=王室家政長官|en|Master of the Household}}の下に一元化した<ref>[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.134-135</ref>。 |
|||
{{Gallery |
|||
|File:Victoria Marriage01.jpg|1840年2月10日のヴィクトリアとアルバートの結婚式を描いたジョージ・ハイターの絵画 |
|||
|File:Windsor Castle in Modern Times. 1841-1845.jpg|[[ウィンザー城]]のアルバート公子とヴィクトリア女王を描いた[[エドウィン・ランドシーア]]の絵画 |
|||
|File:Franz Xaver Winterhalter Family of Queen Victoria.jpg|[[アルフレート (ザクセン=コーブルク=ゴータ公)|次男アルフレート]]、[[エドワード7世 (イギリス王)|長男アルバート・エドワード]]、ヴィクトリア女王、[[アルバート (ザクセン=コーブルク=ゴータ公子)|夫アルバート公]]、[[アリス (ヘッセン大公妃)|次女アリス]]、[[ヘレナ (イギリス王女)|三女ヘレナ]]、[[ヴィクトリア (ドイツ皇后)|長女ヴィクトリア]] |
|||
}} |
|||
{{-}} |
|||
==== ピールの改革支援 ==== |
|||
1841年8月末にメルバーン子爵が首相を辞職し、いよいよピールを首相に任命せねばならなくなった。ヴィクトリアはこの時点でもピールを首相にする事を渋っていたが、アルバートが彼女を説得し、ピールに首相の大命降下を与えた<ref name="君塚(2007)45">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.45</ref>。 |
|||
ヴィクトリアは過去の経緯やそのそわそわした態度からピールを嫌っていた。ピールの方も宮殿に居心地の悪さを感じて長時間宮殿に滞在しようとはせず、ヴィクトリアと疎遠になった。しかしアルバートは宮廷策謀より首相の職務に全力を挙げているとしてピールの態度を高く評価した<ref name="ワイントラウブ(1993)上261">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.261</ref>。首相ピールはアルバートの支持のもと関税の大幅減税、所得税導入などの改革を推進した<ref name="君塚(2007)46">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.46</ref>。やがてヴィクトリアもアルバートとともにピールに全幅の信頼を寄せるようになった<ref name="ワイントラウブ(1993)上267">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.267</ref>。保守党内部にはピールの改革に反発もあったが、アルバートとヴィクトリアがピールを支持した事により、ピールは長らく抵抗勢力を押し込むことができた<ref name="君塚(2007)46">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.46</ref>。 |
|||
ピール首相が[[ミッドランド]]地方([[:en:Midlands (England)|en]])の紡績工場主だった関係でヴィクトリアは外国との過当競争や需要低下に苦しむ織物産業に関心を持つようになり、イングランド織物の宣伝のために1842年5月12日に14世紀の絹織工業をテーマにした「[[プランタジネット]]舞踏会」を開催した。アルバートは[[エドワード3世 (イングランド王)|エドワード3世]]、ヴィクトリアは[[フィリッパ・オブ・エノー|フィリッパ王妃]]の仮装をした。しかしこの舞踏会はエドワード3世を侵略者として憎むフランス人の反発を買って英仏関係をギクシャクさせたばかりか、イギリスのマスコミからも失業者が飢えている時に何をやっているのか、という強い批判に晒され、ヴィクトリア夫妻にとってあまり思い出したくない黒歴史になった<ref>[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.263-264</ref>。 |
|||
{{Gallery |
|||
|File:Edwin Henry Landseer - Queen Victoria and Prince Albert at the Bal Costumé of 12 May 1842.JPG|1842年5月12日のプランタジネット舞踏会におけるヴィクトリアとアルバートを描いた[[エドウィン・ランドシーア]]の絵画 |
|||
|File:Sir robert peel.jpg|首相[[ロバート・ピール|サー・ロバート・ピール]]。 |
|||
}} |
|||
{{-}} |
|||
==== じゃがいも飢饉と保守党の分裂 ==== |
|||
[[File:Famine memorial dublin.jpg|thumb|200px|[[ダブリン]]市にあるじゃがいも飢饉追悼記念像。]] |
|||
1845年夏に[[アイルランド]]で[[ジャガイモ飢饉]]が発生した。これによりアイルランドでは100万人が餓死もしくは[[栄養失調]]で病死した<ref name="ヒバート(1998)166">[[#ヒバート(1998)|ヒバート(1998)]] p.166</ref><ref name="モリス(2008)上226">[[#モリス(2008)上|モリス(2008) 上巻]] p.226</ref>。さらに100万人が新天地アメリカやカナダへ移民することを余儀なくされた<ref name="ヒバート(1998)166">[[#ヒバート(1998)|ヒバート(1998)]] p.166</ref><ref>[[#モリス(2008)上|モリス(2008) 上巻]] p.253-256</ref>。1841年時に800万人だったアイルランド人口が1851年には650万人に減るという惨状だった<ref name="モリス(2008)上226"/>。 |
|||
ヴィクトリアは{{仮リンク|ライオネル・デ・ロスチャイルド|en|Lionel de Rothschild}}が主宰する「アイルランドとスコットランドの貧民のための英国救貧協会」に2000ポンドの寄付をしている<ref name="ワイントラウブ(1993)上297">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.297</ref>。これは同協会に寄せられた寄付金額の第一位であり、第二位のロスチャイルドと{{仮リンク|ウィリアム・キャヴェンディッシュ (第6代デヴォンシャー公爵)|label=デヴォンシャー公爵|en|William Cavendish, 6th Duke of Devonshire}}の寄付金額1000ポンドを大きく引き離す額だった<ref name="ワイントラウブ(1993)上297">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.297</ref>。 |
|||
じゃがいも飢饉の深刻さを受け止めたピール首相はアイルランド人が安い価格の輸入穀物を購入できるよう、保護貿易主義の穀物法を廃止する決意をした。ヴィクトリア夫妻も貧しい民衆もそれを支持した<ref>[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.296-297</ref>。しかし地主貴族など保守党内の抵抗勢力が穀物の自由貿易に強く反発したため、ピールは穀物法廃止法案と刺し違える形で1846年6月に辞職を余儀なくされた<ref name="君塚(2007)49">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.49</ref>。 |
|||
この騒ぎで保守党はピールを筆頭とする自由貿易派と[[エドワード・スミス=スタンリー (第14代ダービー伯爵)|ダービー伯爵]]を筆頭とする保護貿易派に分裂し、ピール派が自由党(ホイッグ党)と連携したことで自由党が議会の多数派になり、自由党党首である[[ジョン・ラッセル (初代ラッセル伯)|ジョン・ラッセル卿]]が首相の大命降下を受けることになった<ref name="君塚(2007)51">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.51</ref><ref>[[#ヒバート(1998)|ヒバート(1998)]] p.166-167</ref>。ヴィクトリアはラッセル卿の内閣で外相になった[[ヘンリー・ジョン・テンプル (第3代パーマストン子爵)|パーマストン子爵]]が親仏外交でアイルランド貧困問題を無視するようになるのではと心配していた<ref>[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.297-299</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
==== チャーティズム運動 ==== |
|||
[[File:Chartist meeting, Kennington Common.jpg|thumb|200px|[[1848年]][[ケンジントン・パーク]]([[:en:Kennington Park|en]])で開催されたチャーティストの集会]] |
|||
ヴィクトリア女王夫妻、メルバーン子爵、ピールらによる自由主義的な改革は裕福なブルジョワには歓迎されたが、貧しい労働者階級には期待はずれであり、社会改革を求める[[チャーティズム]]運動が高まった<ref name="ヒバート(1998)165">[[#ヒバート(1998)|ヒバート(1998)]] p.165</ref>。 |
|||
1848年には大陸で[[1848年革命]]が発生し、イギリスでもチャーティズム運動が勢いを増した。「[[共和制]]万歳」を叫ぶ者たちがバッキンガム宮殿の外のランプを破壊する騒ぎがあり、ヴィクトリアは恐怖のあまり泣き出してしまったという。身の危険を感じたヴィクトリアら王族は[[ワイト島]]の[[オズボーン・ハウス]]へ一時的に避難した<ref name="ヒバート(1998)167">[[#ヒバート(1998)|ヒバート(1998)]] p.167</ref><ref>[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.312-313</ref>。 |
|||
しかし比較的自由主義的な政府があり、不十分とはいえ一定の改革を行ったイギリスでは絶対主義的な君主国家ばかりの大陸ほど革命は燃え広がらず、やがてチャーティズム運動も下火になっていった<ref name="君塚(2007)50">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.50</ref><ref name="ヒバート(1998)167">[[#ヒバート(1998)|ヒバート(1998)]] p.167</ref>。ヴィクトリアは「労働者たちはプロの扇動家、犯罪者、クズどもに扇動されただけで王室への従順さを失っていなかった」と述べて胸をなでおろした<ref name="ヒバート(1998)168">[[#ヒバート(1998)|ヒバート(1998)]] p.168</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
==== ロンドン万博 ==== |
|||
1851年の[[ロンドン万国博覧会 (1851年)|第1回ロンドン万国博覧会]]の準備はアルバートが取り仕切った<ref name="君塚(2007)55">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.55</ref>。ロンドン万博の会場として[[ハイド・パーク]]にデヴォンシャー公爵所有の豪邸{{仮リンク|チャッツワース・ハウス|en|Chatsworth House}}の温室をモデルにデザインされた全面ガラス張りの巨大な[[水晶宮]](クリスタル・パレス)が建設された<ref>[[#長島(1989)|長島(1989)]] p.142-143</ref><ref name="ヒバート(1998)169">[[#ヒバート(1998)|ヒバート(1998)]] p.169</ref>。 |
|||
開会宣言はヴィクトリアが行った。女王暗殺を警戒して開会宣言を内輪で行うべきとの意見もあったが、最終的にはヴィクトリア自身が公開して行うと決めた<ref name="ワイントラウブ(1993)上345">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.345</ref>。水晶宮には世界各地から集められた10万点の展示物が飾られた<ref name="ヒバート(1998)169">[[#ヒバート(1998)|ヒバート(1998)]] p.169</ref>。ヴィクトリアは万博開催中の数ヶ月間、気分が高揚してロンドン万博以外のことはほとんど頭になくなっていた<ref name="ワイントラウブ(1993)上358">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.358</ref>。万博のすべてを見学しようと1週間に数回という頻度で水晶宮を訪れている<ref name="ワイントラウブ(1993)上348">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.348</ref>。 |
|||
ロンドン万博は140日の期間中にのべ600万人も訪れたという。これは当時のイギリス人の人口の3分の1に相当する<ref name="長島(1989)142">[[#長島(1989)|長島(1989)]] p.142</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)上347">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.347</ref>。収益も相当な額に上り、その収益と議会の創設した基金とでケンジントン地区再開発を行い、{{仮リンク|エクサビション・ロード|en|Exhibition Road}}や{{仮リンク|クロムウェル・ロード|en|Cromwell Road}}、{{仮リンク|クイーンズ・ゲート|en|Queen's Gate}}などの道路が整備された(道路の名前は全てアルバートが命名した)<ref name="ヒバート(1998)169">[[#ヒバート(1998)|ヒバート(1998)]] p.169</ref>。さらに1850年代にも万博実行委員会所有の土地を使って[[ロイヤル・アルバート・ホール]]、[[ヴィクトリア&アルバート博物館]]、[[ロンドン自然史博物館]]、[[サイエンス・ミュージアム]]などを続々と創設した<ref name="ヒバート(1998)169">[[#ヒバート(1998)|ヒバート(1998)]] p.169</ref>。 |
|||
ヴィクトリアは1851年7月18日付けの日記に「我が愛する夫と我が国の功績に対して寄せられた平和の祈りと親善が大勝利を収めた」と書いている<ref name="ワイントラウブ(1993)上348">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.348</ref>。 |
|||
{{Gallery |
|||
|File:Kristallpalast Sydenham 1851 aussen.png|ロンドン万国博覧会が開催された水晶宮外観。 |
|||
|File:John Absolon, Crystal Palace, General View, lithograph, coloured by hand.jpg|水晶宮内部を描いた絵画 |
|||
|ファイル:Crystal Palace - Queen Victoria opens the Great Exhibition.jpg|水晶宮で万国博覧会の開催宣言を行うヴィクトリア。 |
|||
}} |
|||
{{-}} |
|||
==== 政党政治の混迷の後二大政党が確立 ==== |
|||
{| class="wikitable" style="float:right" |
|||
|+ ヴィクトリア朝の首相一覧 |
|||
! 名前 !! 首相就任日 |
|||
|- |
|||
! [[メルボルン子爵ウィリアム・ラム|メルバーン子爵]]([[自由党 (イギリス)|自由党]]) |
|||
| [[1835年]][[4月18日]] |
|||
|- |
|||
! [[ロバート・ピール]]([[保守党 (イギリス)|保守党]]) |
|||
| [[1841年]][[8月30日]] |
|||
|- |
|||
! [[ジョン・ラッセル (初代ラッセル伯)|ラッセル伯爵]](自由党) |
|||
| [[1846年]][[7月6日]] |
|||
|- |
|||
! [[エドワード・スミス=スタンリー (第14代ダービー伯爵)|ダービー伯爵]](保守党) |
|||
| [[1852年]][[2月23日]] |
|||
|- |
|||
! [[ジョージ・ハミルトン=ゴードン (第4代アバディーン伯)|アバディーン伯爵]]([[:en:Peelite|ピール派]]) |
|||
| 1852年[[12月28日]] |
|||
|- |
|||
! [[ヘンリー・ジョン・テンプル (第3代パーマストン子爵)|パーマストン子爵]](自由党) |
|||
| [[1855年]][[2月8日]] |
|||
|- |
|||
! ダービー伯爵(保守党) |
|||
| [[1858年]][[2月25日]] |
|||
|- |
|||
! パーマストン子爵(自由党) |
|||
| [[1859年]][[6月12日]] |
|||
|- |
|||
! ラッセル伯爵(自由党) |
|||
| [[1865年]][[10月30日]] |
|||
|- |
|||
! ダービー伯爵(保守党) |
|||
| [[1866年]][[7月6日]] |
|||
|- |
|||
! [[ベンジャミン・ディズレーリ|ディズレーリ]](保守党) |
|||
| [[1868年]][[2月27日]] |
|||
|- |
|||
! [[ウィリアム・グラッドストン|グラッドストン]](自由党) |
|||
| 1868年[[12月9日]] |
|||
|- |
|||
! ディズレーリ(保守党) |
|||
| [[1874年]][[2月20日]] |
|||
|- |
|||
! グラッドストン(自由党) |
|||
| 1880年[[4月28日]] |
|||
|- |
|||
! [[ロバート・ガスコイン=セシル (第3代ソールズベリー侯)|ソールズベリー侯爵]](保守党) |
|||
| [[1885年]][[6月24日]] |
|||
|- |
|||
! グラッドストン(自由党) |
|||
| [[1886年]][[2月3日]] |
|||
|- |
|||
! ソールズベリー侯爵(保守党) |
|||
| 1886年[[8月3日]] |
|||
|- |
|||
! グラッドストン(自由党) |
|||
| [[1892年]][[8月16日]] |
|||
|- |
|||
! [[アーチボルド・プリムローズ (第5代ローズベリー伯)|ローズベリー伯爵]](自由党) |
|||
| [[1894年]][[3月6日]] |
|||
|- |
|||
! ソールズベリー侯爵(保守党) |
|||
| [[1895年]][[6月28日]] |
|||
|- |
|||
|} |
|||
ジョン・ラッセルは1851年2月に労働者階級に選挙権を拡大する更なる選挙法改正法案を議会に提出したが、下院の反対で退けられた。この件でラッセルはヴィクトリアに辞表を提出した。ヴィクトリアは自由党に次ぐ勢力である保守党保護貿易派の指導者[[エドワード・スミス=スタンリー (第14代ダービー伯爵)|ダービー伯爵]]に首相の大命降下をくだしたが、保守党の議席は過半数に程遠く、また実務経験のある政治家が党分裂でほとんどピール派に移っていたこともあってダービー伯爵はこれを拝辞し、自由党とピール派に政権を担当させるようヴィクトリアに具申した。ヴィクトリアはその通りにしようとしたが、この二勢力には自由貿易しか共通点がなく、カトリック規制など他の問題で様々な対立を抱えていたため、連立政権を作れなかった<ref name="君塚(2007)52">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.52</ref>。ヴィクトリアは{{仮リンク|ヘンリー・ペティ=フィッツモーリス (第3代ランズダウン侯爵)|label=ランズダウン侯爵|en|Henry Petty-Fitzmaurice, 3rd Marquess of Lansdowne}}やウェリントン公爵など元老たちにどう対処すべきか諮問し、結果ラッセルを首相に戻すこととした<ref name="君塚(2007)54">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.54</ref>。迷走ぶりを露わにした政党政治の力は減退し、王権の担い手たるアルバート公子の存在感は一層増していった<ref name="君塚(2007)54"/>。 |
|||
1852年2月にヴィクトリアは伯父であるベルギー王レオポルドに宛てて「アルバートは日増しに政治が好きになっていますが、彼の洞察力や勇気はそうした仕事には非常に向いています。一方私は日増しに仕事が嫌になっています。私たち女性は「統治」するようには創られていません。善良な女性であるなら、そのような仕事は好きにはなれないのです。」と書いている<ref name="川本(2006)63">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.63</ref>。 |
|||
1850年代を通じて政党政治の混迷は続き、5回も政権交代があった(1852年2月に保守党の[[エドワード・スミス=スタンリー (第14代ダービー伯爵)|ダービー伯爵]]、1852年12月にピール派の[[ジョージ・ハミルトン=ゴードン (第4代アバディーン伯)|アバディーン伯爵]]、1855年2月のホイッグ党の[[ヘンリー・ジョン・テンプル (第3代パーマストン子爵)|パーマストン子爵]]、1858年2月のダービー伯爵再任、1859年6月にパーマストン子爵再任)<ref name="君塚(2007)77">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.77</ref><ref name="秦(2001)509">[[#秦(2001)|秦(2001)]] p.509</ref>。 |
|||
1859年6月にホイッグ党、ピール派、急進派の三派が合同して[[自由党 (イギリス)|自由党]]を結成したことで[[二大政党制]]への道が開かれ、政党政治が安定化するようになった。自由党は早速議会に内閣不信任案を可決させ、保守党のダービー伯爵を辞職させ、パーマストン子爵を首相とする自由党長期政権を樹立した。こうして1860年代以降には1850年代のようにヴィクトリアが長老政治家に諮問して首相を選定するようなことも減っていった<ref name="君塚(2007)78-79">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.78-79</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
==== アルバート薨去 ==== |
|||
[[File:Queen Victoria and Prince Albert 1861.jpg|thumb|200px|1861年のアルバートとヴィクトリア]] |
|||
アルバートは1857年に議会から王配殿下(Prince Consort)の称号を受けていたが<ref name="森(1986)564">[[#森(1986)|森(1986)]] p.564</ref>、1850年代後半から徐々に健康を害するようになっていた<ref name="君塚(2007)82">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.82</ref>。若い頃には美男だった外見もいつしか髪が薄くなり、引き締まっていた身体もすっかり肥満していた<ref name="君塚(2007)82"/>。 |
|||
ヴィクトリアによると夫妻が溺愛していた自慢の長女[[ヴィクトリア (ドイツ皇后)|ヴィッキー]]が1858年にプロイセン王子[[フリードリヒ3世 (ドイツ皇帝)|フリードリヒ]]に嫁いでからアルバートの元気がなくなったという<ref name="君塚(2007)82">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.82</ref>。夫妻が愚鈍と評価していた皇太子[[エドワード7世 (イギリス王)|バーティ]]の不良行為や問題行動にもアルバートは随分頭を悩まされ、胃痛がひどくなり、[[リューマチ]]も患うようになった<ref name="君塚(2007)83-84">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.83-84</ref>。 |
|||
1861年11月22日にアルバートはヴィクトリアが止めるのも聞かず、豪雨の中[[サンドハースト王立陸軍士官学校]]の新校舎竣工式に出席し、続けて[[ケンブリッジ大学]]で校則破りを繰り返す皇太子に説教するためにケンブリッジを訪問し、体調を悪化させた<ref name="ストレイチイ(1953)205-206">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.205-206</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)上460">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.460</ref>。12月に入ると食事もほとんど取れないほどに衰弱した<ref name="ワイントラウブ(1993)上463">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.463</ref>。そうした中でもアルバートは最期の力を振り絞って[[トレント号事件]]をめぐってのパーマストン子爵の対米強硬姿勢を穏健化させて英米戦争を回避することに尽力した<ref name="ストレイチイ(1953)206">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.206</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)上462">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.462</ref>。 |
|||
侍従医は特に気になる症状はないとしており、ヴィクトリアは侍従医を全面的に信頼していたので、首相パーマストン子爵が他の医者に見せることを提案しても拒否した<ref name="ワイントラウブ(1993)上463">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.463</ref>。だがアルバートの病状は悪化する一方で12月11日にはヴィクトリアも他の医師に診せることを承諾した<ref name="ワイントラウブ(1993)上467">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.467</ref>。召集されたワトソン医師はすでに手遅れの[[腸チフス]]と診断した<ref name="ストレイチイ(1953)207">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.207</ref>。 |
|||
12月13日午後遅く、アルバートは危篤状態に陥り、ヴィクトリア女王はじめ家族が集められた。その日の晩ヴィクトリアはヒステリック状態に陥り、落涙と祈祷を繰り返していた<ref name="ワイントラウブ(1993)上469">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.469</ref>。ヴィクトリアがアルバートの枕元に近づくと彼女の存在に気付いたアルバートは彼女にキスをして手を握り、弱弱しい声ながら「gutes Fraüchen(私の可愛い小さな奥さん)」と声をかけたという<ref name="ワイントラウブ(1993)上469">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.469</ref>。翌14日朝にはアルバートは回復に向かっているように見えたが、正午までにはほとんど動けなくなった。アルバートの息が荒くなるとヴィクトリアは彼に駆け寄り、「Es ist Fraüchen(貴方の小さな奥さんですよ)」と囁き、彼とキスをしたという<ref name="ストレイチイ(1953)208">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.208</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)上471">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.471</ref>。 |
|||
ヴィクトリア女王ら家族が見守る中、アルバートは42歳にして薨去した<ref name="君塚(2007)85">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.85</ref>。ヴィクトリアは冷たくなった夫の手をしばらく握り続けていたが、やがて部屋を飛び出して泣き崩れたという<ref name="ワイントラウブ(1993)上471"/>。 |
|||
ヴィクトリアは伯父ベルギー王レオポルドに宛てて「生後8カ月で父を亡くした赤ん坊は、42歳で打ちひしがれた未亡人となってしまいました。私の幸せな人生は終わりました。私がまだ生きなければならないとしたら、それは父を失った哀れな子らのため、彼を喪うことで全てを失った我が国のため、また私だけが知る彼の希望を実現するためです。彼は私の傍らにいつもいてくれるのです。」と書いている<ref name="ストレイチイ(1953)213">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.213</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)下10">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.10</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
==== 喪服時代 ==== |
|||
[[ファイル:Queen Victoria at Osborne House.jpg|thumb|250px|1865年[[オズボーン・ハウス]]でのヴィクトリア女王と馬係[[ジョン・ブラウン (使用人)|ジョン・ブラウン]]を描いた[[エドウィン・ランドシーア]]の絵画。]] |
|||
ヴィクトリアの悲しみは深く、その後彼女は10年以上にわたって隠遁生活をはじめた。日々を[[ワイト島]]の[[オズボーン・ハウス]]や[[スコットランド]]の[[バルモラル城]]などで過ごしてロンドンには滅多に近寄らなくなった。国の儀式にも社交界にもまったく臨御しなくなった<ref name="ストレイチイ(1953)215">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.215</ref>。たまに人に姿を見せる時には常に喪服姿であった<ref name="森(1986)564">[[#森(1986)|森(1986)]] p.564</ref>。自分だけではなく侍従や女官、奉公人に至るまで宮殿で働く者全員に喪服の着用を命じていた<ref name="ワイントラウブ(1993)下17">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.17</ref>。ヴィクトリアによればアルバートを失った直後の3年間は死を希望する心境にさえなっていたという<ref name="ワイントラウブ(1993)下17">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.17</ref>。 |
|||
政治家たちにとってはヴィクトリアがこれまで散々行ってきた政治への介入を止めさせる絶好のチャンスであり、「喪」に復したいという彼女の意思を支持した<ref name="ワイントラウブ(1993)下31">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.31</ref>。だがヴィクトリアは「喪」に復することに全力をあげるために政権交代を阻止しようとするようになった。アルバート薨去直後の頃、パーマストン子爵の政権運営が危なくなっていた時期だったが、ヴィクトリアは野党党首ダービー伯爵に対して「今の自分は政権交代などという心労に耐えられる状態ではない。もし貴下が政権打倒を目指しているのならば、それは私の命を奪うか、精神を狂わせる行為である。」という脅迫的な手紙を送っている<ref name="ストレイチイ(1953)214-215">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.214-215</ref>。これを見たダービー伯爵は思わず「女王陛下がそんなに奴らをお気に入りだったとは驚いたな」と述べたという<ref name="ストレイチイ(1953)215">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.215</ref>。 |
|||
1862年に再び[[ロンドン万国博覧会 (1862年)|ロンドン万博]]が開催されたが、彼女はアルバートのことを思いだして居た堪れなくなるとして欠席した<ref name="君塚(2007)89">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.89</ref>。 |
|||
国民ははじめヴィクトリアに同情する人が多かったが、やがていつまでも公務に出席しない彼女を批判する論調が増えていった。特にヴィクトリアが三女[[アリス (ヘッセン大公妃)|アリス]]の結婚式をまるで葬式のようにやらせたのを機に女王批判が強まっていった<ref name="ワイントラウブ(1993)下32">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.32</ref>。親王室派の『[[タイムズ]]』紙さえも「女王の喪はいつになったら明けるのか」という不満の論調を載せている<ref name="伊藤(2004)254">[[#伊藤(2004)|伊藤・川田編(2004)]] p.254</ref>。女王のあまりの引きこもりぶりに「女王などいらない」として[[共和主義者]]が台頭し始める始末となった<ref name="君塚(2007)108">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.108</ref><ref name="ベイカー(1997)166">[[#ベイカー(1997)|ベイカー(1997)]] p.166</ref><ref name="森(1986)565">[[#森(1986)|森(1986)]] p.565</ref>。 |
|||
首相パーマストン子爵はこれ以上国民が共和主義に傾くのを避けるため、皇太子バーティを議会に頻繁に出席させることで王室の活動を世に示したがっていたが、ヴィクトリアが強く反対して阻止した<ref name="伊藤(2004)254">[[#伊藤(2004)|伊藤・川田編(2004)]] p.254</ref>。この「出来そこない」の息子のせいでアルバートが過労になったと考えていたヴィクトリアはバーティには重要なことは何も任せないつもりでいた<ref name="伊藤(2004)254"/>。 |
|||
引きこもってばかりいると身体に悪いという侍医の薦めでヴィクトリアは乗馬や馬車で出かけるようになり、その関係でバルモラル城でのアルバートの馬係であったスコットランド人[[ジョン・ブラウン (使用人)|ジョン・ブラウン]]と関わる機会が増え、彼を寵愛するようになった<ref name="君塚(2007)106-107">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.106-107</ref>。ブラウンは事実上ヴィクトリアの秘書、ボディーガードとなっていき、王族や首相といえどもブラウンを介さなければヴィクトリアに謁見できなくなった<ref name="川本(2006)193">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.193</ref>。この女王とブラウンとの関係をマスコミが面白半分に取り上げ、二人が秘密結婚したなどという噂が流れるに至り、ヴィクトリアは「ミセス・ブラウン」などと呼ばれるようになった<ref name="川本(2006)193-194">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.193-194</ref><ref name="君塚(2007)107-108">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.107-108</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)下127-128">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.127-128</ref>。二人の間にセックスの関係があったのかについては歴史家の間で意見が分かれており定かではない<ref name="川本(2006)194">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.194</ref>。ヴィクトリアとブラウンの親密な関係は1883年のブラウンの死まで続いたが、その頃にはすっかり肥満した老婆になっていたヴィクトリアはあまりゴシップのネタにならず、ブラウンも勤勉な世話係として評価されるようになっていた<ref name="ワイントラウブ(1993)下143">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.143</ref>。 |
|||
ただこの時期にもヴィクトリアは外交には強い興味を持ち、パーマストン子爵の内閣が[[イタリア統一]]、アメリカ[[南北戦争]]、[[ポーランド立憲王国|ポーランド]][[1月蜂起]]、[[シュレースヴィヒ=ホルシュタイン問題]]など他の欧米諸国の問題に介入を企む姿勢を見せるとヴィクトリアは不介入を政府に指示してブレーキをかけた。また逆にパーマストン子爵の後継であるダービー伯爵の他のヨーロッパ諸国への不介入方針に対してはルクセンブルク問題のようにヨーロッパの平和が脅かされる恐れがある問題については積極的に介入するべきであると発破をかける役割を担った<ref name="君塚(2007)97-103">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.97-103</ref>。 |
|||
最終的にヴィクトリアを[[引きこもり]]生活から立ち直らせたのは[[ベンジャミン・ディズレーリ]]であった<ref name="森(1986)565">[[#森(1986)|森(1986)]] p.565</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
==== ディズレーリを寵愛 ==== |
|||
[[File:Disraeli.jpg|thumb|150px|[[ベンジャミン・ディズレーリ]]。1876年以降ビーコンズフィールド伯爵。]] |
|||
1867年になると保守党の首相ダービー伯爵が病気でほとんど執務できなくなり、大蔵大臣・下院院内総務[[ベンジャミン・ディズレーリ]]が事実上首相職を代行するようになり<ref name="ワイントラウブ(1993)下75">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.75</ref>、1868年2月下旬には正式に首相に就任した<ref name="ワイントラウブ(1993)下75">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.75</ref>。この[[ユダヤ人]]首相はヴィクトリアのお気に入りだった<ref name="ストレイチイ(1953)231">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.231</ref>。 |
|||
ヴィクトリアはもともと[[ロバート・ピール]]を失脚に追い込んだディズレーリに好感を持っていなかったが<ref name="ストレイチイ(1953)230">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.230</ref>、第一次ダービー伯爵内閣の時に大蔵大臣として入閣したディズレーリが送ってくる報告書の小説家的な面白さで彼に注目するようになった<ref name="川本(2006)191">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.191</ref>。その頃のヴィクトリアはディズレーリについて「青白い顔、黒い目とまつ毛、黒い巻き毛の髪という典型的なユダヤ人風の容貌であり、その表情は不快感を覚える。しかし話してみるとそうでもなかった。」と書いている<ref name="川本(2006)191"/>。ヴィクトリアがディズレーリに本格的に好感を抱くようになったのはアルバート薨去の際にディズレーリがアルバートの人格を称え、[[アルバート記念碑]]の創設に尽力したことだった<ref name="川本(2006)196">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.196</ref>。ヴィクトリアによれば「アルバートの薨去後、多く者が私を憐れんでくれたが、私の悲しみを本当の意味で理解してくれた者はディズレーリだけだった。」という<ref name="ストレイチイ(1953)230">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.230</ref>。ディズレーリが首相を代行するようになった頃にはディズレーリの政策面(アイルランド国教廃止に反対する見解、対ロシア強硬政策、選挙法改正や国民意識を強める帝国主義政策などの「トーリー民主主義」的施政)にも共感を感じることが多くなり<ref name="川本(2006)203-205">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.203-205</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)下75">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.75</ref>、また彼のロマンチックで独特な雰囲気と巧みな話術に惹かれるようになっていた<ref name="ワイントラウブ(1993)下76">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.76</ref>。ヴィクトリアはヴィッキー宛ての手紙の中で「彼は詩的で創造的で騎士道精神を持っている。私の手にキスをするため跪いた時、私の手を包み込むようにして『忠誠と信頼の心に愛をこめて』と語ってくれた」と書いている<ref name="ワイントラウブ(1993)下76"/>。1868年春頃からヴィクトリアは自らが摘んだ花束をディズレーリへ送り、ディズレーリはお礼に自分の小説をヴィクトリアへ送るという関係になった<ref name="川本(2006)198">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.198</ref><ref name="ストレイチイ(1953)232">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.232</ref>。 |
|||
保守党政権が危機的な政治情勢の中、ディズレーリはヴィクトリアを公務に復帰させ、彼女の大御心によって政権を存続させようと考えていた。彼はヴィクトリア本人に「政治が重大な時局にある時は国民も君主に備わる"威厳"を再認識すべきであります。同時に政府もそのような時局における内閣の存立は女王陛下の大御心次第だという事を了解するのが賢明というものです。」という立憲政治を否定するに近い上奏を行っている<ref name="ワイントラウブ(1993)下78">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.78</ref>。ヴィクトリアもまんざらではなく、ディズレーリを助けるために徐々に公務に復帰するようになった<ref name="ワイントラウブ(1993)下78">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.78</ref>。しかし二人の蜜月には反発も多く、ディズレーリと同じ保守党の政治家である[[ロバート・ガスコイン=セシル (第3代ソールズベリー侯)|ソールズベリー侯]]が「女王陛下はすっかり『例のユダヤ人』の手先になってしまわれた。彼は女王陛下の要請によって政権に留まれる準備をした後に見せかけの辞表を提出して事態を収拾するつもりでいる。玉座に君臨しているのは女性であり、ユダヤ人の野心家は彼女を幻惑する術を心得ている」と危機感を露わにするほどだった<ref name="ワイントラウブ(1993)下79">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.79</ref>。 |
|||
だが第二次選挙法改正により有権者数が前回より2倍増えた1868年秋の総選挙において保守党は惨敗した。これを受けてディズレーリは辞職し、自由党の[[ウィリアム・グラッドストン]]が後任の首相に就任した<ref name="君塚(2007)104-105">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.104-105</ref>。これはイギリス史上初めての選挙による政権交代であった<ref name="君塚(2007)105">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.105</ref>。この後しばらくディズレーリは野党党首に甘んじたが、ヴィクトリアとディズレーリの親密な関係は続いた<ref name="ストレイチイ(1953)230">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.230</ref>。{{-}} |
|||
[[File:Old disraeli.jpg|thumb|150px|ヴィクトリア女王とディズレーリ首相を描いた絵。]] |
|||
総選挙での保守党の勝利を経て1874年2月にディズレーリが政権に復帰した。このディズレーリの二期目においてヴィクトリアはいよいよ彼への寵愛を深め、不偏不党を崩してディズレーリびいき、保守党びいきになっていった<ref name="伊藤(2004)256">[[#伊藤(2004)|伊藤・川田編(2004)]] p.256</ref>。その寵愛ぶりはかつてのメルバーン子爵をも超えるものがあった<ref name="ストレイチイ(1953)230">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.230</ref>。ヴィクトリアはディズレーリの帝国主義政策を全面的にバックアップし、1876年5月にはインド女帝に即位し、以降ヴィクトリアは「'''Victoria R&I'''{{#tag:ref|[[ラテン語]]の"Reginaet"(女王)と"Imperatrix"(女帝)の略<ref name="君塚(2007)135">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.135</ref>。|group=#}}」と署名するようになった<ref name="ワイントラウブ(1993)下78">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.78</ref> |
|||
1876年にはディズレーリを{{仮リンク|ビーコンズフィールド伯爵|en|Earl of Beaconsfield}}に叙した。さらに[[ベルリン会議]]で[[キプロス]]を獲得して「エンパイア・ルート」を完成させた恩賞としてディズレーリに[[ガーター勲章]]と[[公爵]](Duke)位を与えようとしたが、公爵位についてはディズレーリの方から辞退している<ref name="伊藤(2004)257">[[#伊藤(2004)|伊藤・川田編(2004)]] p.257</ref>。 |
|||
1880年4月の総選挙にディズレーリ率いる保守党が敗れたため、ディズレーリは辞職を余儀なくされた。ディズレーリは病を患っており、もはや首相職に復帰する日は来ないと覚悟していたが、ヴィクトリアは出来るだけ早くディズレーリが首相に返り咲く日を期待していた<ref name="ワイントラウブ(1993)下218">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.218</ref>。ヴィクトリアはディズレーリに「これが永遠の別れになるなどと思ってはいけませんよ。私は必ず近況を貴方に知らせますから貴方もそうすると約束してください」という手紙を送っている<ref name="ワイントラウブ(1993)下218"/>。ディズレーリは女王と文通を続け、ウィンザー城にも足繁く通ったが、1881年4月には死去した<ref name="ワイントラウブ(1993)下219-221">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.219-221</ref>。 |
|||
ヴィクトリアは彼の訃報にだいぶショックを受けたようだった。彼女はディズレーリの遺言執行人に「ディズレーリほど厚い忠誠心で私に仕えてくれた大臣、また私に誠意を尽くしてくれた友人はいない。」という手紙を書いた<ref name="ワイントラウブ(1993)下221">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.221</ref>。またディズレーリの墓がある{{仮リンク|ヒューエンデン|en|Hughenden Valley}}に「君主であり友人であるヴィクトリアR&Iから、感謝と親愛をこめて」と刻んだ[[大理石]]の記念碑を建てさせた<ref name="ワイントラウブ(1993)下221"/>。 |
|||
{{-}} |
|||
==== グラッドストンとの対立 ==== |
|||
[[File:William Ewart Gladstone - 1866.jpg|thumb|150px|1866年の[[ウィリアム・グラッドストン]]]] |
|||
[[ウィリアム・グラッドストン]]は1868年秋の総選挙における自由党の勝利によって第一次グラッドストン内閣を組閣をした。アイルランドで反英運動・分離運動が高まりを見せていた中、グラッドストンはアイルランド土地法によりアイルランド小作農たちの権利を保護し、またアイルランド国教会を廃止した。しかし前者は地主貴族、後者はヴィクトリア女王の強い反発を買った<ref name="君塚(2007)117">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.117</ref><ref name="ストレイチイ(1953)233">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.233</ref>。1869年初めにグラッドストンはアイルランドにも女王の居城を置いて積極的にアイルランドを訪問するべきと進言したが、ヴィクトリアは拒否した<ref name="君塚(2007)117"/><ref name="ワイントラウブ(1993)下82">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.82</ref>。 |
|||
1874年の総選挙での自由党の敗北により、グラッドストンは首相職をディズレーリに譲り、1875年に自由党党首職からも退いたが、その後も自由党の実質的な指導者であり続け、ディズレーリ保守党政権批判の急先鋒として「人民のウィリアム」などと呼ばれた。自分のお気に入りの首相を攻撃しまくるグラッドストンへの女王の嫌悪感はいよいよ強まり<ref name="君塚(2007)164">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.164</ref>、ヴィッキーに宛てた手紙の中で彼を「狂人」などと評した<ref name="川本(2006)208">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.208</ref><ref name="君塚(2007)174">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.174</ref>。 |
|||
1880年4月の総選挙にディズレーリ率いる保守党が敗れたため、再びグラッドストンに大命降下せねばならない事態となったが、ヴィクトリアは自由党政権を誕生させるとしてもグラッドストンの首相就任だけは阻止したいと願い、自由党下院指導者{{仮リンク|スペンサー・キャヴェンディッシュ (第8代デヴォンシャー公爵)|label=ハーティントン侯爵|en|Spencer Cavendish, 8th Duke of Devonshire}}を首相にしようと画策したが、自由党内からの反発を招き、結局第二次グラッドストン内閣を誕生させることを余儀なくされた<ref name="君塚(2007)104-105">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.160-162</ref>{{#tag:ref|ヴィクトリアはグラッドストンの提出した閣僚人事のうち[[チャールズ・ディルク|サー・チャールズ・ディルク]]([[:en:Sir Charles Dilke, 2nd Baronet]])の大臣任命については彼が共和主義者であるとして拒否した。ディルクは「私が共和主義者だったのは若いころだけで今は立憲君主制論者です」という誓文をヴィクトリアに提出し、それに満足したヴィクトリアは二度と王室費にケチを付けないよう命じたうえでディルクを外務政務次官に任じた<ref name="君塚(2007)165-166">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.165-166</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)下223">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.223</ref>。|group=#}}。 |
|||
グラッドストンには君主は象徴的役割に限定されるべきという持論があり、「女王の忠臣」ディズレーリ時代を機に本格的に政治に介入し始めていたヴィクトリアを再び政治から遠ざけようと図った<ref name="ワイントラウブ(1993)下224">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.224</ref>。彼はアイルランド問題についてヴィクトリアの意見を聞くつもりはなかった。ヴィクトリアは皇太子バーティ宛ての手紙の中で「女王である私に相談すべき大問題なのに私を完全に無視するこの恐るべき急進的政府には仮面を付けた共和主義者が大勢いる。彼らはアイルランド自治派に頭が上がらない。グラッドストンは計り知れない過ちを犯している。」と怒りを露わにしている<ref name="君塚(2007)175">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.175</ref><ref name="ヒバート(1998)173">[[#ヒバート(1998)|ヒバート(1998)]] p.173</ref>。 |
|||
1884年、地方の炭鉱などの労働者にまで選挙権を広げる第三次選挙法改正法案が議会に提出されたが、地方に基盤を持つ自由党と都市部に基盤を持つ保守党の間で紛糾し、8月にはグラッドストンもヴィクトリアに仲裁を依頼する羽目になった。女王がグラッドストンと保守党党首[[ロバート・ガスコイン=セシル (第3代ソールズベリー侯)|ソールズベリー侯爵]]の間を取り持った結果、11月に自由党と保守党の妥協が成立し、第三次選挙法改正法案が可決されて有権者数が更に増加した<ref name="君塚(2007)179-183">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.179-183</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)下253-255">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.253-255</ref>。これにはグラッドストンも女王の強力な仲裁に深く感謝した<ref name="君塚(2007)183">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.183</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)下255">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.255</ref>。 |
|||
1885年6月に予算案が否決されたことでグラッドストン内閣が辞職し、保守党のソールズベリー侯爵に大命降下した<ref name="君塚(2007)191-193">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.191-193</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)下265">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.265</ref>。ヴィクトリアはグラッドストン辞職を心より喜んだが、11月の総選挙は自由党とアイルランド国民党が勝利した。グラッドストンはソールズベリー侯爵内閣の倒閣のためアイルランド国民党と手を組もうといよいよアイルランド自治を主張し始めた<ref name="君塚(2007)193-194">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.193-194</ref>。グラッドストンが再び首相に就任することを恐れるヴィクトリアは自由党内のアイルランド自治反対派をソールズベリー侯爵と連携させようとした<ref name="君塚(2007)194">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.194</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)下270">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.270</ref>。さらにソールズベリー侯爵内閣に「王室のお墨付き」を与えようと1886年の議会開会式に10年ぶりに出席した(これがヴィクトリア最後の議会開会式出席となった)<ref name="君塚(2007)194"/><ref name="ワイントラウブ(1993)下270">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.270</ref>。 |
|||
しかしこうした女王の工作もむなしく、自由党とアイルランド国民党の共同はなり、ソールズベリー侯爵は議会で敗北して辞職に追い込まれた<ref name="君塚(2007)195">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.195</ref>。ヴィクトリアはアイルランド自治に反対する自由党議員{{仮リンク|ジョージ・ゴッシェン|en|George Goschen, 1st Viscount Goschen}}を召集して後継首相について諮問することでなおもグラッドストンに大命降下するのを阻止しようとしたが、ゴッシェンが参内を拒否したため、1886年2月1日グラッドストンに三度目の大命降下を与えることを余儀なくされた<ref name="君塚(2007)196">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.196</ref>。ヴィクトリアはただちにグラッドストン内閣倒閣に動き、保守党と自由党内アイルランド自治法反対派が党を割って創設した自由統一党の連携の仲介を取り、その結果6月にアイルランド自治法案は僅差で否決された。続く解散総選挙もグラッドストンの自由党の敗北、保守党の勝利におわり、グラッドストンは辞職した<ref name="君塚(2007)200-201">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.200-201</ref><ref>[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.286、288-289</ref>。 |
|||
しかし1892年7月の総選挙で保守党が敗北した結果、8月にグラッドストンに四度目の大命降下を与える羽目となった<ref name="君塚(2007)202">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.202</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)下346-349">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.346-349</ref>。グラッドストンはライフワークのアイルランド自治法案をまた提出した。今回は自由党内が一つにまとまっており、またアイルランド国民党が指導者を失って立場が弱い時期だったため無条件に自由党に協力した結果、庶民院で同法案が可決された。しかしソールズベリー侯爵の尽力で貴族院が圧倒的多数で否決した。ヴィクトリアはソールズベリー侯爵の功績を称えている<ref name="君塚(2007)204">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.204</ref>。グラッドストンももはや高齢であり、ついにアイルランド自治法案を諦め、1894年に引退を決意して辞職を願い出た<ref name="君塚(2007)204">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.204</ref>。ヴィクトリアは二度とグラッドストンの顔を見ずに済むことに大喜びした<ref name="君塚(2007)205">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.205</ref>。彼の最後の伺候にも労いの言葉はまったくかけなかった<ref name="川本(2006)209">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.209</ref>。 |
|||
グラッドストンは1898年に死去したが、ヴィクトリアは弔意を出すことを求められても「嫌ですよ。私はあの男が好きではありません。気の毒と思っていないのにどうして気の毒などと言えるでしょうか」と述べて断っている<ref name="ヒバート(1998)175">[[#ヒバート(1998)|ヒバート(1998)]] p.175</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
==== 在位50周年・60周年記念式典 ==== |
|||
1887年6月20日にヴィクトリア女王は在位半世紀を迎え、世界各国の要人がロンドンに集められて{{仮リンク|ヴィクトリア女王在位50年記念式典|label=在位50周年記念式典|en|Golden Jubilee of Queen Victoria}}が挙行された。[[ベルギー]]([[レオポルド2世 (ベルギー王)|レオポルド2世]])、[[デンマーク]]([[クリスチャン9世 (デンマーク王)|クリスチャン9世]])、[[ギリシャ]]([[ゲオルギオス1世 (ギリシャ王)|ゲオルギオス1世]])、[[ザクセン王国|ザクセン]]([[アルベルト (ザクセン王)|アルベルト]])の四か国は国王が自ら出席し、それ以外の国々も高位の王族・皇族が出席した。[[日本]]からは[[小松宮彰仁親王]]が出席した<ref name="君塚(2007)222">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.222</ref>。 |
|||
1897年6月の[[ヴィクトリア女王在位60周年記念式典|在位60年周年記念式典]]は世界各地の植民地首相や駐留連隊代表者も出席し、まさに「帝国の祭典」の様相を呈していた<ref name="川本(2006)IV">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.IV</ref>。この式典でヴィクトリアは「愛する臣民たちに感謝する。神の御加護があらんことを。」と一言だけ挨拶した<ref name="モリス(2006)上19">[[#モリス(2006)上|モリス(2006) 上巻]] p.19</ref>。 |
|||
{{Gallery |
|||
|File:William Ewart Lockhart, Queen Victoria's Golden Jubilee Service, Westminster Abbey, 21 June 1887 (1887–1890).jpg|1887年のヴィクトリア女王在位50周年記念式典を描いた{{仮リンク|ウィリアム・エワート・ロックハート|en|William Ewart Lockhart}}の絵画。 |
|||
|File:Queen Victoria 60. crownjubilee.jpg|1897年、在位60年を迎えたヴィクトリア女王。 |
|||
}} |
|||
{{-}} |
|||
==== 消極的な晩年 ==== |
|||
[[File:Queen Victoria - Von Angeli 1899.jpg|thumb|150px|1899年のヴィクトリアを描いた{{仮リンク|ハインリヒ・フォン・アンゲリ|de|Heinrich von Angeli}}の肖像画]] |
|||
通常女王は退任する首相に推挙する後任の首相を下問するのが慣例だったが、グラッドストン第四期目の退任の際にヴィクトリアは彼に一切下問せずにお気に入りの[[アーチボルド・プリムローズ (第5代ローズベリー伯)|ローズベリー伯爵]]を独断で後任の首相に任じた<ref name="君塚(2007)205">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.205</ref><ref name="ベイカー(1997)168">[[#ベイカー(1997)|ベイカー(1997)]] p.168</ref>。 |
|||
ローズベリー伯爵はエジプトと南アフリカに大きな利権を持つライオネル・デ・ロスチャイルドの妹を妻に迎えており、熱心な帝国主義者であった<ref name="川本(2006)272-273">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.272-273</ref>。彼はただちにヴィクトリアに海軍増強を提案してヴィクトリアの帝国主義の矜持を満足させた<ref name="ワイントラウブ(1993)下377">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.377</ref>。一方でローズベリーも自由党の政治家であり、貴族院批判を行ったり[[相続税]]値上げなどグラッドストンと似通った傾向も多々あり、ヴィクトリアもやや警戒していたが<ref name="ワイントラウブ(1993)下378/382">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.378/382</ref>、結局ローズベリー伯爵は貴族院改革にもアイルランド自治にもそれほど熱を入れなかったのでヴィクトリアも安堵した<ref name="ワイントラウブ(1993)下385">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.385</ref>。1895年6月に陸軍大臣の減給をめぐる採決で自由党は分裂して過半数を割り、ローズベリー伯爵は辞表を提出した。ヴィクトリアとローズベリー伯爵は必ずしも意見は一致しなかったが、それでも彼女は政権交代を残念がっていた<ref name="ワイントラウブ(1993)下389-390">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.389-390</ref>。 |
|||
保守党のソールズベリー侯爵が第三次内閣を組閣した。以降ヴィクトリアの崩御まで彼が首相を務めた。ソールズベリー侯爵は民主主義を進展させることを拒否し、貴族の特権を守るために全力を尽くす極めて保守的な人物だった<ref name="モリス(2006)上362-363">[[#モリス(2006)上|モリス(2006) 上巻]] p.362-363</ref>。かつてのディズレーリのような壮大な帝国主義構想は持たなかったが、利害関係には異様に執着し、熱心な帝国主義者[[ジョゼフ・チェンバレン]]を植民相として新帝国主義政策に乗り出した<ref name="モリス(2006)上364-369">[[#モリス(2006)上|モリス(2006) 上巻]] p.364-369</ref>。ヴィクトリアはソールズベリー侯爵には安心して国政を任せることができ、彼女が政治に口を出すこともあまりなくなっていき、芝居見物など趣味に興じることが増えた<ref name="ワイントラウブ(1993)下335">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.335</ref>。 |
|||
加えてヴィクトリア朝末期、女王は高齢で体力が低下していき、政府に対する影響力を減少させ続けた<ref name="ワイントラウブ(1993)下492">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.492</ref>。女王の旅行の際に女官の切符の手配が忘れられるという事態さえ発生した<ref name="ワイントラウブ(1993)下492"/>。1900年には七男[[アーサー (コノート公)|コノート公アーサー]]を{{仮リンク|ガーネット・ヴォルズリー (初代ヴォルズリー子爵)|label=サー・ガーネット・ヴォルズリー|en|Garnet Wolseley, 1st Viscount Wolseley}}に代わる{{仮リンク|陸軍総司令官 (イギリス)|label=陸軍総司令官|en|Commander-in-Chief of the Forces}}に任命しようとしたが、ソールズベリー侯の推挙が優先されて{{仮リンク|フレデリック・ロバーツ (初代ロバーツ伯爵)|label=ロバーツ卿|en|Frederick Roberts, 1st Earl Roberts}}がその任についた<ref name="ワイントラウブ(1993)下490-491">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.490-491</ref>。さらに同年ソールズベリー侯は首相の職に専念するとして彼が兼務していた外務大臣職に陸軍大臣[[ヘンリー・ペティ=フィッツモーリス (第5代ランズダウン侯爵)||ランズダウン侯爵]]を就任させた。ランズダウン侯爵はかつて陸軍のスキャンダルを公表した人物だったのでヴィクトリアは嫌っていたが、この時も彼女の反対は何の効力も発揮せず、彼女にできたのは日記に不満を書くことだけだった<ref name="ワイントラウブ(1993)下492">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.492</ref>。 |
|||
{{Gallery |
|||
|File:Four generations QV colour.jpg|1898年イギリス王室四代。第6代女王ヴィクトリア、皇太子[[エドワード7世 (イギリス王)|バーティ(第7代国王エドワード7世)]]、[[ジョージ5世 (イギリス王)|ヨーク公ジョージ(第8代国王ジョージ5世)]]、[[エドワード8世 (イギリス王)|エドワード王子(第9代国王エドワード8世)]] |
|||
|File:Queen Victoria Vanity Fair 17 June 1897.jpg|1897年、南フランスを旅行中のヴィクトリア女王を描いた絵 |
|||
}} |
|||
{{-}} |
|||
=== 外交 === |
|||
==== 帝国主義 ==== |
|||
[[File:The Secret of England's Greatness' (Queen Victoria presenting a Bible in the Audience Chamber at Windsor) by Thomas Jones Barker.jpg|thumb|230px|{{仮リンク|トーマス・ジョネス・バーカー|en|Thomas Jones Barker}}画『イングランドの偉大さの秘訣』。イングランドの偉大さの秘訣を聞いたアフリカ黒人王に[[聖書]]を手渡すヴィクトリアを描いた絵。実際の出来事ではないとされるが、「文明化する使命」へのイギリス人の強い自負心を象徴する絵画である<ref>[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.318-320</ref>。]] |
|||
ヴィクトリア朝64年の間に大英帝国は世界中の非白人国家・民族集団に対して覇道の限りを尽くし、その領土を10倍以上に拡大させ、地球の全陸地面積の4分の1、世界全人口の4分の1(4億人)を支配する史上最大の帝国となるに至った<ref name="中西(1997)154">[[#中西(1997)|中西(1997)]] p.154</ref><ref name="モリス(2008)下413">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.413</ref>。大英帝国の維持・拡大のためにヴィクトリアとその政府は世界各地で頻繁に戦争を行い、ヴィクトリア朝全期を通じてイギリスが戦争をしていない時期は稀であった(ヴィクトリア朝64年間にイギリス軍が全く戦闘しなかった時期は2年だけだったといわれる)<ref>[[#モリス(2008)上|モリス(2008) 上巻]] p.120/203</ref>。 |
|||
ヴィクトリアは非白人国家に対する帝国主義には全面的に賛成していた。「帝国主義には二種類あり、一つは皇帝専制などの誤った帝国主義。もう一つは平和を維持し、現地民を教化し、飢餓から救い、世界各地の臣民を忠誠心によって結び付け、世界から尊敬される英国の帝国主義である。英国の領土拡張は弱い者イジメではなく、英国の諸制度と健全な影響を必要とあれば武力をもって世界に押し広げるものである。」とする[[ベンジャミン・ディズレーリ|ディズレーリ]]内閣植民相{{仮リンク|ヘンリー・ハーバート (第4代カーナーヴォン伯爵)|label=カーナーヴォン伯爵|en|Henry Herbert, 4th Earl of Carnarvon}}の見解を熱烈に支持していたためである<ref name="モリス(2008)下175-176">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.175-176</ref>。 |
|||
[[イングランド人]]、[[スコットランド人]]、[[アイルランド人]]、[[ボーア人]]、[[アフリカ人]]、[[アラブ人]]、[[インド人]]、[[中国人]]、[[ビルマ人]]、[[アボリジニ]]、[[マオリ]]、[[ポリネシア人]]、[[インディアン]]、[[エスキモー]]など無数の人種、また[[三大宗教]]をはじめとする様々な宗教を版図におさめる大英帝国には統一感はまるでなかったが、その彼らを「女王陛下の臣民」として一つに結び付け、統合の象徴の役割を果たしたのがヴィクトリア女王であった<ref name="モリス(2008)下228">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.228</ref>。 |
|||
この時期の英国君主が女性であったことは大英帝国の成功の秘訣であった。ヴィクトリアが「帝国の母」としてその「子供」たちである世界中の臣民たちに慈愛を注ぐイメージが被支配民の間にも広まり、大英帝国の支配への抵抗心を和らげたのである<ref name="川本(2006)38">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.38</ref>。カナダのインディアンの[[スー族]]や[[クリー族]]はヴィクトリアを「白い母」と呼んで敬意を払っていた<ref name="モリス(2008)下91">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.91</ref>。あるインド藩王はヴィクトリアのインド女帝即位にあたってのデリーでの大謁見式(ヴィクトリアは欠席)において「ああ、母上。ロンドンの宮殿にいます親愛なる陛下。」と呼びかけている<ref name="モリス(2008)下93">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.93</ref>。1865年に反乱を起こしたジャマイカの黒人たちもヴィクトリア女王個人には忠誠を誓っており、裁判所を襲撃して囚人を解放した際に「我々はヴィクトリア女王陛下に反乱を起こしているわけではないから、陛下の所有物を略奪してはならない」として囚人服を置いていかせたという<ref name="モリス(2008)下56">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.56</ref>。 |
|||
ヴィクトリア自身も支配下におさめた非白人国家の王や首長の子供たちを後見したり、教育を与えたり、自分の名前(男性の場合はヴィクトリアの男性名ヴィクターや夫の名前アルバートなど)を与えるなどして「女王は人種に寛大」というイメージを守ることに努めた<ref>[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.284-285</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
===== アフガニスタン戦争 ===== |
|||
[[File:Great Game cartoon from 1878.jpg|thumb|200px|クマ(ロシア)とライオン(イギリス)に狙われたアフガニスタンの風刺画([[パンチ (雑誌)|パンチ誌]])]] |
|||
ヴィクトリアが即位したばかりの頃、[[イギリス東インド会社]]支配下の{{仮リンク|イギリス東インド会社支配下のインド|label=インド|en|Company rule in India}}の北西が大英帝国の弱点となっていた。イギリスは[[シク教国]]と連携して[[インダス川]]まで勢力を伸ばしたものの、[[ロシア帝国]]も[[ブハラ・ハン国]]、[[ヒヴァ・ハン国]]を事実上の勢力下におさめ、ついで[[バーラクザイ朝|アフガニスタン王国]]を窺っていた。そのためアフガニスタンがイギリスとロシアの中央アジア覇権争い(「[[グレート・ゲーム]]」)の中心舞台になろうとしていた<ref name="モリス(2008)上126">[[#モリス(2008)上|モリス(2008) 上巻]] p.126</ref>。 |
|||
ヴィクトリアの戴冠式から間もない1838年10月、イギリス軍はアフガニスタンへ侵攻を開始し、首都[[カブール]]を陥落させた。アフガン王([[アミール]])[[ドースト・ムハンマド・ハーン]]は北方ブハラ・ハン国へ亡命したため、イギリスは[[シュジャー・シャー]]を傀儡の王に即位させた<ref>[[#モリス(2008)上|モリス(2008) 上巻]] p.132-135</ref>。しかし1841年11月カブールで反英闘争が激化し、掌握不可能となり、それに乗じてトルキスタンに亡命していた前王の息子{{仮リンク|アクバル・ハーン|ps|سردار محمد اکبر خان}}が[[ウズベク族]]を率いてカブールへ戻ってきたため、イギリス軍は降伏を余儀なくされた。アクバルはイギリス軍の安全な撤退を保障したが、約束が守られることなく、現地部族民が略奪をしかけてきてイギリス軍は大量の死者を出しながら撤退する羽目となった。結局カブール駐留イギリス軍で生き残ったのは軍医の{{仮リンク|ウィリアム・ブライドン|en|William Brydon}}のみであった([[アフガニスタン戦争|第一次アフガン戦争]])<ref name="モリス(2008)上132-152">[[#モリス(2008)上|モリス(2008) 上巻]] p.132-152</ref>。 |
|||
イギリスという後ろ盾を失ったシュジャー・シャー王は殺害され、ドーストがアフガンに戻ってアミールの座を取り戻した。イギリスは敗北したとはいえ、すでにアフガン南西部を半植民地状態にしていることは変わらなかった<ref name="君塚(2007)147">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.147</ref>。結局ドーストは外交権を事実上イギリスに委ねざるをえなかった<ref name="前田(2002)64">[[#前田(2002)|前田・山根(2002)]] p.64</ref>。1864年のドーストの崩御後、[[シール・アリー・ハーン]]、{{仮リンク|モハメド・アフザル・ハーン|en|Mohammad Afzal Khan}}、{{仮リンク|モハメド・アザム・ハーン|en|Mohammad Azam Khan}}の三兄弟が王位継承争いを起こしてアフガンに内戦が発生した。インド総督はアフガン弱体化を狙い、内戦を煽ろうと不干渉を建前に「兄弟のうち王位を固めた者を承認する」と宣言した<ref name="前田(2002)77">[[#前田(2002)|前田・山根(2002)]] p.77</ref>。イギリスの狙い通り内戦は激化し、王位の奪い合いの末、最終的には1869年にシール・アリー・ハーンが王位を固めた<ref name="前田(2002)78">[[#前田(2002)|前田・山根(2002)]] p.78</ref>。 |
|||
一方ロシア帝国は1868年に[[ブハラ・ハン国]]、1873年に[[ヒヴァ・ハン国]]、1875年に[[コーカンド・ハン国]]を攻め滅ぼし、中央アジアの3ハーン国をすべて保護領としていた<ref name="前田(2002)79">[[#前田(2002)|前田・山根(2002)]] p.79</ref>。警戒したイギリスはアフガン支配強化の必要性を感じ、シール王に対してイギリス外交団をカブールに常駐させるよう求めた<ref name="前田(2002)80">[[#前田(2002)|前田・山根(2002)]] p.80</ref>。しかしシール王はこれを認めず、逆に1878年8月にロシア皇帝から送られてきたロシア将校団の使節の受け入れを認めた。イギリス人はこの扱いの差に激怒した<ref name="君塚(2007)147-148">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.147-148</ref>。 |
|||
ヴィクトリアの怒りも激しく、彼女はアフガニスタン懲罰の必要性を感じたが、第一次アフガン戦争の苦い思い出もあり、外交圧力をかけて解決させるようディズレーリ首相に指示している<ref name="君塚(2007)148">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.148</ref>。しかし現地インド軍は早々にアフガニスタンへ侵攻を開始していた。ヴィクトリアもやむなくインド軍を全面支援するよう首相と外相に要求した<ref name="君塚(2007)148"/>。アフガンはロシアの援助を期待したが、ロシアは[[露土戦争 (1877年-1878年)|露土戦争]]の戦後処理国際会議[[ベルリン会議]]で孤立していることに焦り、安易な出兵をして孤立を深めたくない時期だったため、アフガンは見殺しにされた<ref name="前田(2002)80-81">[[#前田(2002)|前田・山根(2002)]] p.80-81</ref>。 |
|||
こうしてはじまった第二次アフガン戦争はアフガン軍の[[ゲリラ戦]]に苦しめられながらもイギリス軍が勝利をおさめ、1879年6月に{{仮リンク|モハメド・ヤクブ・ハーン|en|Mohammad Yaqub Khan}}王に[[ガンダマク条約]]を締結させて戦争は終結した<ref name="前田(2002)81">[[#前田(2002)|前田・山根(2002)]] p.81</ref>。イギリスはロシアでの長い亡命生活でロシアからの信頼も厚い[[アブドゥッラフマーン・ハーン]]をアミールに即位させ、外交を完全にイギリスが掌握しつつ内政は彼に任せてアフガンから撤収していった<ref name="前田(2002)80-82">[[#前田(2002)|前田・山根(2002)]] p.82</ref>。 |
|||
{{Gallery |
|||
|File:Last-stand.jpg|1842年[[第一次アフガニスタン戦争]]で全滅する直前のイギリス第44連隊を描いた絵画 |
|||
|File:Battle in Afghanistan.jpg|[[第二次アフガニスタン戦争]]で[[カンダハール]]を攻略する{{仮リンク|イギリス陸軍第92歩兵連隊|label=イギリス陸軍第92歩兵連隊「ゴードン・ハイランダー」|en|92nd (Gordon Highlanders) Regiment of Foot}}を描いた{{仮リンク|リチャード・カートン・ウッドヴィレー|en|Richard Caton Woodville}}の絵画 |
|||
|File:Royal Horse Artillery fleeing from Afghan attack at the Battle of Maiwand.jpg|{{仮リンク|マイワンドの戦い|en|Battle of Maiwand}}で突撃をかける{{仮リンク|イギリス王立騎馬砲兵|en|Royal Horse Artillery}}を描いたリチャード・カートン・ウッドヴィレーの絵画 |
|||
}} |
|||
{{-}} |
|||
===== 中国半植民地化 ===== |
|||
[[ファイル:18th Royal Irish at Amoy.jpg|thumb|230px|1841年8月[[廈門の戦い]]([[:en:Battle of Amoy|en]])で清軍を蹴散らすイギリス軍を描いた絵画]] |
|||
清は[[広東]]港でのみヨーロッパ諸国と交易を行い、{{仮リンク|公行|zh|公行}}という清政府の特許を得た商人にしかヨーロッパ商人との交易を認めてこなかった([[広東貿易]]制度)。しかしインド産アヘンはこの枠外であり、イギリス商人が密貿易によって中国人アヘン商人に売っていたため清国内にアヘンが大量流入していた。1823年にはアヘンがインド綿花を越えて清の輸入品の第一位となり、清は輸入超過(銀流出)を恐れるようになった<ref name="横井(1988)48-50">[[#横井(1988)|横井(1988)]] p.48-50</ref>。1839年に清がアヘン取り締まりを強化したことで英清関係は緊張し、小競り合いが発生するようになった<ref name="横井(1988)55-58">[[#横井(1988)|横井(1988)]] p.55-58</ref>。 |
|||
1840年6月に大規模なイギリス艦隊や陸軍兵力が[[広東]]に集結して軍事行動を開始し、沿岸地域を占領しながら北上して[[北京]]を窺ったが、清側が交渉を求め、また[[モンスーン]]の接近や[[舟山諸島]]占領軍の病の流行で9月に一時撤収した<ref>[[#横井(1988)|横井(1988)]] p.64-67</ref>。しかし英軍が撤収するや北京政府内で強硬派が盛り返したため、交渉は難航し、イギリス軍は1841年1月から再度軍事行動を開始した。イギリス艦隊は再び[[廈門市|廈門]]、[[舟山諸島]]、[[寧波市|寧波]]など[[揚子江]]以南の沿岸地域を占領した<ref name="横井(1988)74">[[#横井(1988)|横井(1988)]] p.74</ref>。[[モンスーン]]に備えて冬の間は停止したが、1842年春に軍事行動を再開し、揚子江へ入って[[南京]]を窺った。ここに至って清政府も完全に戦意を喪失した<ref name="横井(1988)69">[[#横井(1988)|横井(1988)]] p.69</ref>。 |
|||
清に[[南京条約]]、{{仮リンク|五港通商章程|zh|中英五口通商章程}}、[[虎門寨追加条約]]など[[不平等条約]]を締結させ、それまでの広東貿易制度や公行制度を廃止させ、清はイギリスの世界自由貿易体制の底辺に組み込まれる形となった<ref name="横井(1988)46">[[#横井(1988)|横井(1988)]] p.45-50</ref>。アヘン輸入も一層拡大され<ref name="長島(1989)83">[[#長島(1989)|長島(1989)]] p.83</ref>、[[香港]]がイギリス領として割譲されることになった<ref name="君塚(2007)29-30">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.29-30</ref>。東アジアでの更なる覇権確立の足場の確保にヴィクトリアも喜び、伯父ベルギー王レオポルドに宛てた手紙の中で「[[ヴィクトリア (ドイツ皇后)|ヴィクトリア]](1840年に生まれたばかりの長女)を香港大公女(Princess of Hong Kong)に叙そうかと考えています。」と冗談交じりに書いている<ref name="君塚(2007)30">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.30</ref>。 |
|||
その後[[広東]]で反英闘争が激化し、1850年代になるとイギリスは再度の武力行使を決意した。[[クリミア戦争]]を経て同盟関係を深めていたフランス皇帝[[ナポレオン3世]]もそれに賛同し、1856年10月8日の[[アロー号事件]]を機に英仏軍は広東攻撃を開始した。英仏軍は広東を占領して北上し、1858年5月に[[大沽砲台]]を占領して北京を窺い、6月に清に[[天津条約]]を締結させることに成功した<ref name="横井(1988)128">[[#横井(1988)|横井(1988)]] p.128</ref>。だが清にとってこの条約は北京陥落を防ぐための便宜的手段であり、条約を守る姿勢を見せなかったため、一度撤収した英仏軍は再び北進を開始し、1860年8月に大沽砲台を再度陥落させ、北京を占領した。改めて清に[[北京条約]]を締結させた<ref name="横井(1988)132">[[#横井(1988)|横井(1988)]] p.132</ref>。 |
|||
これにより中国半植民地化は決定的となったが、同時に清朝そのものの弱体化も決定的となり、[[太平天国の乱]]が活発になり、イギリスが内政干渉(清朝支持)をせねばならない機会が増加した。また統治能力のない清政府に代わってイギリスが中国沿岸ほぼ全域の防衛を担当せねばならなくなり、その負担は大きかった<ref name="横井(1988)135">[[#横井(1988)|横井(1988)]] p.135</ref>。しかも[[清仏戦争]]・[[日清戦争]]後には他の列強も続々と中国植民地化に乗り出し、イギリス、フランス、ロシア、日本、ドイツの列強間での中国分割が熾烈になっていった<ref name="世界大百科事典清">[[#世界大百科事典|世界大百科事典]]「清」の項目</ref>。とりわけ近年急速に台頭し始めたヨーロッパ外帝国主義勢力である日本の中国諸港獲得にはヴィクトリアも強い危機感を持ち、[[東京]]へ圧力をかけたがるようになった<ref name="ワイントラウブ(1993)上383">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.383</ref>。一方でヴィクトリアはアフリカ分割であれ、中国分割であれ、植民地を一人占めしようという意思はなかった。彼女は第一大蔵卿[[アーサー・バルフォア]]に対して「我々が我々以外の何者にも植民地を渡すつもりがないという印象を列強に与えないように注意しなければならない。しかし同時に我が国の権利と影響は死守せねばならない」と訓令している<ref name="君塚(2007)255">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.255</ref>。 |
|||
{{Gallery |
|||
|File:Interior chinese lodging house, san francisco.JPG|阿片を吸う中国人 |
|||
|ファイル:HKStamp96cents.jpg|イギリス植民地[[香港]]で発効されたヴィクトリア女王が描かれた96セント切手 |
|||
|ファイル:China imperialism cartoon.jpg|列強による中国植民地化を描いた風刺画。孫にあたるドイツ皇帝[[ヴィルヘルム2世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム2世]]と睨みあうヴィクトリア女王。 |
|||
}} |
|||
{{-}} |
|||
===== インド大反乱とインド統治 ===== |
|||
[[ファイル:Vereshchagin-Blowing from Guns in British India.jpg|thumb|230px||[[インド大反乱]]に参加したインド人を[[大砲で吹き飛ばす死刑]]([[:en:Blowing from a gun|en]])に処すイギリス軍を描いた絵画。]] |
|||
1857年初頭、インドの[[セポイ]]たちが[[ヒンズー教]]の教えに従って牛脂や豚脂が塗油として使われるイギリス軍ライフル銃の弾薬筒の使用を拒否し、これに対してイギリス軍はこのセポイたちを事実上の死刑である重労働刑に処した。彼らの解放を求める運動が起こり、やがてそれは全インドの大反乱に拡大した([[インド大反乱|インド大反乱(セポイの反乱)]])<ref name="ワイントラウブ(1993)上408-409">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.408-409</ref>。 |
|||
反乱がおきて最初の数カ月、英軍は反乱軍におされぎみで首相パーマストン子爵は弱腰になっていたが、ヴィクトリアは毅然とした態度を崩さず、現地に植民している臣民たちを守らねばならないとして主戦論を唱え、政府に発破をかけ続けた<ref name="ワイントラウブ(1993)上409-410">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.409-410</ref>。反乱軍に陥落させられた[[コーンポー]]駐屯地でイギリス人婦女子が虐殺されたことがイギリス人の怒りに火を付けた。ヴィクトリアも「気の毒な婦人と子供たちに対して犯されたこの恐るべき行為は大昔ならともかく現代ではとても考えられない。誰もが血の凍る思いである」と怒りをあらわにしている<ref name="ベイカー(1997)178">[[#ベイカー(1997)|ベイカー(1997)]] p.178</ref>。復讐に燃えるイギリス軍はインド人を大量に虐殺する残虐な鎮圧を行った<ref>[[#モリス(2008)上|モリス(2008) 上巻]] p.364-365</ref>。反乱者の死刑は大砲に括りつけて身体を吹き飛ばす方法によって行われた<ref name="モリス(2008)上366">[[#モリス(2008)上|モリス(2008) 上巻]] p.366</ref>。インド人の心はすっかり折られ、彼らが大英帝国の支配に対して武装蜂起を起こすことは二度となかった<ref name="モリス(2008)上362">[[#モリス(2008)上|モリス(2008) 上巻]] p.362</ref>。 |
|||
反乱鎮圧後の1858年8月2日にヴィクトリアはインドを自らの直接統治下に置く法律に署名した<ref name="ワイントラウブ(1993)上410">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.410</ref>。これによりインド統治は東インド会社ではなくイギリス政府が行うこととなった<ref name="長島(1989)84">[[#長島(1989)|長島(1989)]] p.84</ref>。(実質的にはとっくに滅んでいた)[[ムガル帝国]]は形式的にも崩壊し、以降ヴィクトリアは「インド女帝(Empress of India)」と俗称されるようになった。ヴィクトリアは「巨大な帝国に対して直接責任を負う事に大きな満足感と誇りを覚える」と書いている<ref name="ワイントラウブ(1993)上410">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.410</ref>。 |
|||
一方でヴィクトリアは再反乱を防ぐには自らの「慈悲深い母」のイメージを前面に出すべきであると考え、[[信仰の自由]]を保障することをインド臣民たちに布告した<ref>[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.36-37</ref>。またヴィクトリアは「インド王侯たちを君主(ヴィクトリア)との個人的な結びつきによって引き付けるべきである。そのためにインドにも高位の[[勲爵士]]を置くべきである。」と主張し<ref name="君塚(2004)95">[[#君塚(2004)|君塚(2004)]] p.95</ref>、アルバート公や政府、インド総督の協力を得て{{仮リンク|スター・オブ・インディア勲章|en|Order of the Star of India}}を制定した<ref>[[#君塚(2004)|君塚(2004)]] p.95-103</ref>。 |
|||
ディズレーリ時代にはヴィクトリアはインドに強い興味を示すようになり、[[ヒンディー語]]の勉強を始めるようになり、またインド人を侍従として側近くに置くようになった。とりわけ「ムンシ」こと{{仮リンク|アブドル・カリム|hi|:मुंशी अब्दुल करीम}}を寵愛し、彼は[[ジョン・ブラウン (使用人)|ジョン・ブラウン]]の死後にブラウンに取って代わったと言っても過言ではない存在となった<ref name="ストレイチイ(1953)289">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.289</ref>。 |
|||
ヴィクトリアはかねてよりロシア、オーストリアが世界一の大国の君主である自分を差し置いて皇帝号(Emperor)を名乗っているのが気に入らなかった。最近ではプロイセンまでドイツ皇帝を名乗り始めており、イギリス君主も皇帝号を得る時だと考えるようになった<ref name="君塚(2007)133">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.133</ref>。またドイツ皇帝[[ヴィルヘルム1世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム1世]]の高齢化が進むと、ヴィクトリアはその皇太子フリードリヒ([[フリードリヒ3世 (ドイツ皇帝)|フリードリヒ3世]])に嫁がせた長女ヴィクトリアが近いうちに「Queen」より上格の「Empress(皇后,女帝)」号を得ることを懸念するようになった。娘より下に置かれるわけにはいかないと考えたヴィクトリアは「インド女帝(Empress of India)」号を公式に得たがるようになった。1876年1月に首相[[ベンジャミン・ディズレーリ]]にその旨を指示し、彼に議会との折衝にあたらせた結果、4月に王室称号法によって「インド女帝」の称号を公式に獲得した<ref name="川本(2006)206">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.206</ref><ref name="君塚(2007)134-135">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.134-135</ref>。彼女はその日の日記に嬉々として「これで私は今後署名する時に『女王および女帝』と書く事ができる」と書いている<ref name="君塚(2007)134">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.134</ref>。 |
|||
1877年1月1日に[[デリー]]でインド[[藩王]]たちが召集されてヴィクトリアの女帝即位宣言式「大謁見式(Great Durbar)」が開催された。もちろんヴィクトリア本人がデリーを訪れることはなく(彼女は生涯ヨーロッパ以外の地域を訪れることはなかった<ref name="モリス(2008)下91">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.91</ref>)、インド総督[[ヴィクター・ブルワー=リットン]]伯爵がその名代を務めた<ref name="君塚(2007)134">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.134</ref>。 |
|||
{{Gallery |
|||
|File:Star of India Insignia.JPG|スター・オブ・インディア勲章 |
|||
|File:Victoria Disraeli cartoon.jpg|女帝位を欲しがるヴィクトリア女王を皮肉った風刺画。インド人の格好をした[[ベンジャミン・ディズレーリ|ディズレーリ]]がヴィクトリアとインド帝冠とイギリス王冠の交換をしている。 |
|||
|File:Munshi.jpg|ヴィクトリア女帝のインド人侍従アブドル・カリム。 |
|||
}} |
|||
{{-}} |
|||
===== アシャンティ族との戦い ===== |
|||
イギリス人は1820年代から[[西アフリカ]]の[[英領ゴールド・コースト]]においてその周辺の最強の部族である[[アシャンティ王国|アシャンティ族]]と小競り合いを続けてきた。アシャンティ族は天から授かったという伝承の[[レガリア]]「黄金の丸椅子」を崇拝し、生贄をささげる風習のある部族だった。生贄は王(アシャンタヘネ)の代替わりや戦争などの緊急事態の際に捧げられ、時に何百人という数に及んだ(生贄にささげられるのは基本的にはその時のために生かされている囚人だった。戦争の場合はその場で無造作に生贄が決定された)<ref name="モリス(2008)下186">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.186</ref>。ヨーロッパの価値観からは到底認めることのできない文化であり、イギリス人は「迷信深い野蛮な民族」と看做して軽蔑していた。アシャンティ族もイギリス人を「二枚舌の卑怯者」と看做して嫌った<ref name="モリス(2008)下190">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.190</ref>。 |
|||
1872年に好戦的な{{仮リンク|コフィ・カリカリ|en|Kofi Karikari}}がアシャンタヘネとなり、またオランダが黄金海岸から撤収する際にアシャンティ族が領有権を主張していた[[エルミナ城]]をイギリスに売却したことでイギリスとアシャンティの対立が深まった。エルミナ城と[[ケープ・コースト城]]が一時アシャンティ族に包囲されるもイギリス軍がこれを撃退し、アシャンティ族はヨーロッパ人宣教師を数名捕虜にして撤退した<ref>[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.190-191</ref>。 |
|||
これに対してヴィクトリアの委任を受けた{{仮リンク|ガーネット・ヴォルズリー (初代ヴォルズリー子爵)|label=サー・ガーネット・ヴォルズリー|en|Garnet Wolseley, 1st Viscount Wolseley}}将軍率いるイギリス軍が1873年11月からアシャンティ族討伐を開始した。これはイギリス軍とアフリカ現地民の組織的な軍隊との最初の本格的な武力衝突となった<ref name="モリス(2008)下195">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.195</ref>。イギリス軍は1874年2月にはアシャンティ族の首都[[クマシ]]を占領し、アシャンティ族の心を折るためここを全て爆破解体した。生贄をささげる「死の木立」も切り倒された。コフィ・カリカリも大英帝国に背くことを諦め、巨額の賠償、捕虜の解放、エルミナ城の所有権の放棄、生贄の風習の根絶を受け入れた<ref name="モリス(2008)下197">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.197</ref>。 |
|||
普仏戦争でプロイセン軍の快進撃を見せつけられたイギリス陸軍や国民は自国陸軍に自信を無くしていた時期であったが、この軍事的成功にイギリス陸軍もいざとなれば迅速な作戦行動ができるのだという自信を強め、以降点在するアフリカの黒人王国に対して積極的に戦争を仕掛けるようになった<ref>[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.199-202</ref>。 |
|||
{{Gallery |
|||
|File:Bonnat Aschantidorf.jpg|アシャンティ族の生活 |
|||
|File:Anglo-Ashanti war 1.jpg|アシャンティ族に発砲するイギリス軍 |
|||
|File:Anglo-Ashanti war 2.jpg|アシャンティ族との戦争を描いた絵 |
|||
}} |
|||
{{-}} |
|||
===== ズールー族との戦い ===== |
|||
[[File:Isandhlwana.jpg|thumb|250px|[[イサンドルワナの戦い]]([[:en:Battle of Isandlwana|en]])でズールー族に全滅させられる直前のイギリス軍を描いた絵。]] |
|||
同じころ[[南アフリカ]]には英国植民地が2つ([[ケープ植民地]]、[[ナタール]])、オランダ人植民者の子孫でイギリス支配に反発して[[グレート・トレック]]で内陸部へ移住した[[ボーア人]]による国家が2つ([[オレンジ自由国]]、[[トランスヴァール共和国]])、計4つの白人植民者共同体があった<ref name="中西(1997)158">[[#中西(1997)|中西(1997)]] p.158</ref><ref name="モリス(2008)下230">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.230</ref>。オレンジ自由国は比較的親英的で英国と協力関係にあったが、トランスヴァール共和国は反英的だった<ref name="モリス(2008)下230"/>。 |
|||
そしてその周囲に白人植民者の20倍にも及ぶ数の原住民である黒人が暮らしていた。黒人たちの中では[[ズールー族]]が大きな勢力であった。このズールー族はイギリス・ボーア人問わず現地の白人が最も恐れた戦闘民族だった。ズールー族の独立国家[[ズールー王国]]は国民皆兵をとっており、男子は槍を血で洗うまで一人前と認められず、また戦闘で敵を一人殺すか傷つけるまで妻帯が認められないという風習があったため、非常に好戦的だった<ref name="モリス(2008)下239">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.239</ref>。銃はほとんどもっておらず、昔ながらの投げ槍を武器にしていた<ref name="モリス(2008)下239"/>。 |
|||
このズールー族の脅威や1876年の{{仮リンク|ペディ族|en|Pedi people}}との戦争、財政難などによりトランスヴァール共和国は1877年4月12日に(この時には何の抵抗もなく)イギリスに併合された<ref name="梶谷(1981)41-42">[[#梶谷(1981)|梶谷(1981)]] p.41-42</ref><ref name="林(1995)11-12">[[#林(1995)|林(1995)]] p.11-12</ref><ref name="モリス(2008)下230">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.237</ref>。大英帝国の一員となったボーア人とズールー族の間で国境争いが起こる中、英領ナタール行政府の長である高等弁務官バートル・フレアはズールー族を武力で制圧することを決意した。イギリス本国に応援を頼みつつ、その到着を待たずに1879年1月にズールー王国に対して「軍隊を廃棄し、非人道的な法・慣習を廃し、首都に英国人を監視役に置くことを認めるなら国境争いになっている土地を譲る」という[[最後通牒]]を送った<ref name="君塚(2007)151">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.151</ref><ref name="モリス(2008)下241">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.241</ref>。ズールー族からの返事はなく、現地イギリス軍は本国に独断で[[ズールー戦争]]を開始した。装備のうえではイギリス軍が圧倒的に優位だったにもかかわらず、ズールー族は勇敢に戦い、{{仮リンク|イサンドルワナの戦い|en|Battle of Isandlwana}}において現地イギリス軍を全滅させた<ref name="君塚(2007)152">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.152</ref><ref>[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.244-246</ref>。 |
|||
本国から増援が送り込まれることとなったが、この際にイギリス亡命中の[[フランス第二帝政]]時代の元フランス皇太子[[ナポレオン・ウジェーヌ・ルイ・ボナパルト|ナポレオン4世]]がイギリスに恩返しがしたいと従軍を希望した。首相ディズレーリは[[フランス第三共和政]]の反発を恐れて慎重だったが、イギリス軍最高司令官ヴィクトリアがこれを許可した。しかし結局ナポレオン4世は現地でズールー族の槍を食らって戦死した。ヴィクトリアは悲しみにくれる[[ウジェニー・ド・モンティジョ|元フランス皇后ウジェニー]]を慰めつつ、ズールー族を倒す決意を新たにした<ref name="君塚(2007)154">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.154</ref>。 |
|||
ナポレオン4世の葬儀から10日後にヴィクトリアは植民地の軍備増強を怠った政府の責任であるという叱責の書簡をディズレーリ首相に送った<ref>[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.153-154</ref>。これを受けてディズレーリ首相は更なる大部隊を現地に送りこみ、ついに1879年8月末にズールー王国首都[[ウルンディ]]を陥落させ、ズールー族をイギリス支配下に組み込んだ<ref name="君塚(2007)154">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.154</ref>。 |
|||
しかしズールー族の脅威がなくなったことでボーア人がトランスヴァール共和国再独立を求めてイギリスに対して蜂起し、現地イギリス軍はこれに敗れた結果、首相[[ウィリアム・グラッドストン]]はヴィクトリアと保守党の不興を買いながらもトランスヴァールからの撤退を決意した。ヴィクトリア女王の宗主権という条件付きで1881年8月に[[トランスヴァール共和国]]独立を認めることとなった<ref name="モリス(2008)下265">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.265</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)下229">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.229</ref>。 |
|||
{{Gallery |
|||
|ファイル:Mort du prince imperial.jpg|ズールー族の戦士たちに殺害される直前の[[ナポレオン・ウジェーヌ・ルイ・ボナパルト|ナポレオン4世]]を描いた絵。 |
|||
|File:Kambula 1.jpg|{{仮リンク|カンブラの戦い|en|Battle of Kambula}}でズールー族を撃破したイギリス軍を描いた絵。 |
|||
|File:The burning of Ulundi.jpg|イギリス軍に焼き払われるズールー王国の首都ウルンディを描いた絵。 |
|||
}} |
|||
{{-}} |
|||
===== エジプト保護国化 ===== |
|||
1875年にディズレーリ首相はイギリス船籍の[[喜望峰]]ルートに代わって増えていくエジプトからインドへ向かうルートを確保するため、フランス資本で作られた[[スエズ運河]]に注目するようになった<ref name="モリス(2008)下219-222">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.219-222</ref>。ディズレーリは友人のライオネル・デ・ロスチャイルド男爵に協力を依頼してエジプト副王からスエズ運河を買収し、ヴィクトリア女王に「陛下、これでスエズ運河は貴女の物です。フランスに作戦勝ちしました」と報告した<ref name="モリス(2008)下223-225">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.223-225</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)下186">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.186</ref>。 |
|||
スエズ運河買収でエジプトが財政的に破綻し、1876年にはエジプト財政は英仏の共同管理下に置かれることになり、イギリス人・フランス人がエジプトの財政担当の閣僚として入閣していった<ref name="梶谷(1981)47">[[#梶谷(1981)|梶谷(1981)]] p.47</ref><ref name="君塚(2007)184">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.184</ref>。エジプトの名目上の宗主国[[オスマン帝国|オスマン=トルコ帝国]]は手に負えないエジプトの宗主権をイギリスに譲渡したがっていたが、イギリスとしては「インドへの道」エジプトがフランス一国の影響下に置かれないようにすることだけが目的だったので面倒な地域の領有は望まなかった<ref name="梶谷(1981)47">[[#梶谷(1981)|梶谷(1981)]] p.47</ref>。 |
|||
1881年2月にエジプト人将校の待遇をトルコ人将校と同じにすることを求める{{仮リンク|アフマド・オラービー|ar|احمد عرابى}}大佐の指揮の下に[[ウラービー革命|オラービー革命]]が発生し、エジプト副王[[タウフィーク]]は1882年2月にオラービーを陸相とする「祖国党」内閣を誕生させることを余儀なくされた<ref name="梶谷(1981)45">[[#梶谷(1981)|梶谷(1981)]] p.45</ref>。オラービーは反トルコ、反ヨーロッパ的な民族主義者であり、ヨーロッパ人株主への支払いを停止し<ref name="ワイントラウブ(1993)下235">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.235</ref>、さらに1882年4月にオラービー暗殺を企てたとして50名のトルコ人将校を逮捕した。オラービー政府と副王・英仏勢力の対立は深刻化した<ref name="梶谷(1981)47">[[#梶谷(1981)|梶谷(1981)]] p.47</ref>。 |
|||
6月11日、[[アレクサンドリア]]でヨーロッパ人50人がオラービー軍に虐殺される事件が発生した。これについてヴィクトリアは「キリスト教徒が咎めなくして殺されている」と主張してグラッドストンに武力介入を要求し、グラッドストンもしぶしぶ武力介入を決定した<ref name="ワイントラウブ(1993)下235">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.235</ref>。この戦いは9月13日の{{仮リンク|テル・エル・ケビールの戦い|en|Battle of Tel el-Kebir}}においてイギリス軍がオラービー軍を壊滅させた結果、オラービーがイギリスに降伏して終結した<ref name="梶谷(1981)48">[[#梶谷(1981)|梶谷(1981)]] p.48</ref>。 |
|||
この戦いに皇太子バーティが従軍を希望していたが、ヴィクトリアはこの不健康な肥満体の皇太子がそんな不衛生な土地へ行ったらすぐに病を患ってくるだろうと心配していた<ref name="ワイントラウブ(1993)下235">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.235</ref>。それにそもそもヴィクトリアは皇太子の能力をまったく信用していなかった<ref name="君塚(2007)184">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.184</ref>。ヴィクトリアは皇太子の代わりにアーサー王子を王家代表で出征させた<ref name="君塚(2007)184">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.184</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)下236">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.236</ref>。アーサー王子らエジプト遠征軍が帰還するとヴィクトリアは彼らが持ち帰ってきたオラービーが使用していた絨毯の上に立って勝利を誇示し、アーサー王子らに勲章を与えた<ref name="君塚(2007)185">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.185</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)下237-238">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.237-238</ref>。 |
|||
この戦いの後もエジプトは形式的には[[オスマン帝国]]に忠誠を誓う副王の統治下にあったが、実質的支配権はイギリス総領事{{仮リンク|エヴェリン・バーリング (初代クローマー伯爵)|label=クローマー伯爵|en|Evelyn Baring, 1st Earl of Cromer}}が握るようになった<ref name="モリス(2006)下301">[[#モリス(2006)下|モリス(2006) 下巻]] p.301</ref>。彼の下にインド勤務経験のある英国人チームが結成され、エジプト政府の各部署に助言役として配置された。エジプト政府は全面的に彼らに依存した<ref name="モリス(2006)下302">[[#モリス(2006)下|モリス(2006) 下巻]] p.302</ref>。イギリス人らは副王[[アッバース・ヒルミー2世|アッバース2世]]を傀儡にして税制改革から[[ナイル川]]の運航スケジュールまであらゆることを自ら決定した<ref name="モリス(2006)下301">[[#モリス(2006)下|モリス(2006) 下巻]] p.301</ref>。スーダンで発生した[[マフディーの反乱]]の鎮圧にエジプト軍が動員された際、アッバース2世には何も知らされず、彼は出兵の翌日になって酔っ払った英国軍将校からそれを聞かされるような始末だった<ref name="モリス(2006)下302">[[#モリス(2006)下|モリス(2006) 下巻]] p.302</ref>。 |
|||
{{Gallery |
|||
|File:PortSaid Canal 1880.jpg|1880年のスエズ運河。 |
|||
|File:Tel-el-Kebir.JPG|テル・エル・ケビールの戦いでオラービー軍に突撃をかけるイギリス軍を描いた絵 |
|||
|File:Alexandria-June-11-1882.jpg|オラービー軍を蹴散らして[[アレクサンドリア]]を制圧するイギリス軍の配下エジプト正規軍 |
|||
}} |
|||
{{-}} |
|||
===== マフディーの反乱、ゴードン将軍の死 ===== |
|||
[[File:General Gordon's Last Stand.jpg|thumb|200px|マフディー軍に殺害されるゴードン将軍を描いた絵画]] |
|||
ついで1882年にはエジプト支配下[[スーダン]]でイギリスに支配されたエジプトに対する反発が強まり、マフディー(救世主)を名乗った{{仮リンク|ムハンマド・アフマド|ar|محمد أحمد المهدي}}による[[マフディーの反乱]]が発生した<ref name="梶谷(1981)57-58">[[#梶谷(1981)|梶谷(1981)]] p.57-58</ref><ref name="君塚(2007)185">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.185</ref><ref name="モリス(2008)下340">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.340</ref>。 |
|||
反乱の第一報を聞いたヴィクトリアはエジプトの反乱と同様にこれも武力で鎮圧すべきと考えたが<ref name="君塚(2007)186">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.186</ref>、グラッドストンはスーダンに大して関心を示さず、「エジプト問題とスーダン問題は別問題」としてできる限り不干渉の方針を取った<ref name="梶谷(1981)59">[[#梶谷(1981)|梶谷(1981)]] p.59</ref>。1883年9月イギリス軍将軍ヒックス率いるエジプト軍がマフディー軍に惨敗したが<ref name="モリス(2008)下340"/><ref name="梶谷(1981)59"/><ref name="君塚(2007)186">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.186</ref>、それでもグラッドストンにはイギリス本国軍やインド軍を派遣する意思はなく<ref name="梶谷(1981)60">[[#梶谷(1981)|梶谷(1981)]] p.60</ref>、エジプト守備軍のスーダンからの撤退を指揮する人物として「チャイニーズ・ゴードン」{{#tag:ref|ゴードンはアロー戦争で活躍し、アロー戦争後に清政府の依頼で清軍の司令官となり、[[太平天国の乱]]を平定したためこのあだ名が付いた<ref>[[#中西(1997)|中西(1997)]] p.106-108</ref>。|group=#}}の異名を取っていた[[チャールズ・ゴードン]]少将をスーダン総督に任じて[[ハルトゥーム]]に派遣した<ref name="君塚(2007)186"/><ref>[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.341-342</ref><ref name="梶谷(1981)62">[[#梶谷(1981)|梶谷(1981)]] p.62</ref>。 |
|||
だがゴードン将軍にはそもそも撤退の意思がなく、またマフディー軍により電線が切られて本国からの指示を受け取れなくなったことにより、グラッドストン政府の意思に反して同地に留まり、マフディー軍に包囲された<ref name="中西(1997)119">[[#中西(1997)|中西(1997)]] p.119</ref><ref name="君塚(2007)186">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.186</ref>。イギリス世論はゴードン救出を求める声に沸き立ち<ref name="中西(1997)119"/>、ヴィクトリアもゴードン救出を政府に命じたが、グラッドストンは応じなかった<ref name="君塚(2007)186">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.186</ref>。しかしこれについては閣内でも意見が分裂しており<ref name="梶谷(1981)65-66">[[#梶谷(1981)|梶谷(1981)]] p.65-66</ref>、やがて陸相{{仮リンク|スペンサー・キャヴェンディッシュ (第8代デヴォンシャー公爵)|label=ハーティントン侯爵|en|Spencer Cavendish, 8th Duke of Devonshire}}が焦燥しはじめ、辞職を盾にゴードン救出を求めた結果、ついにグラッドストンも折れ、8月にスーダン遠征軍派遣が決定された<ref name="梶谷(1981)66">[[#梶谷(1981)|梶谷(1981)]] p.66</ref>。 |
|||
しかし遠征軍は間に合わず、1885年1月26日にハルトゥームは陥落してゴードンはマフディー軍に殺害された。この報を聞いたヴィクトリアは激怒して暗号電文ではなく通常電文でグラッドストン政府を叱責する電報を送った<ref name="梶谷(1981)67">[[#梶谷(1981)|梶谷(1981)]] p.67</ref><ref name="君塚(2007)189">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.189</ref><ref name="ストレイチイ(1953)266">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.266</ref>。ヴィクトリアは2月末に何としてもスーダンを奪還してゴードンの仇を取るべしと命じたが、グラッドストンは4月の閣議で「マフディー軍は意気揚々としており、今はスーダン奪還の時期ではない」と決定した<ref name="君塚(2007)190">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.190</ref>。グラッドストンの態度に怒り心頭になったヴィクトリアはディズレーリの命日にあたって「親愛なるビーコンズフィールド伯爵が生きていてくれたなら」と日記上で嘆いている<ref name="君塚(2007)190">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.190</ref>。 |
|||
ゴードンの戦死で世論や議会はグラッドストンへの不満を高め、彼の第三次内閣が崩壊する一因となった。ゴードンは「帝国の殉教者」に祭り上げられ、イギリスがエジプト支配を手放すことはプライドにかけてできなくなった<ref name="中西(1997)120">[[#中西(1997)|中西(1997)]] p.120</ref>。1895年頃からイギリスはスーダン奪回を最優先課題とするようになり<ref name="林(1995)62">[[#林(1995)|林(1995)]] p.62</ref>、結局ゴードン戦死から13年後の1898年になってイギリス軍はスーダンに軍を送ってマフディー軍を撃破している<ref name="中西(1997)121">[[#中西(1997)|中西(1997)]] p.121</ref>。そのためにそれ以外の地域の植民地争いを一時的に収束させようと「[[栄光ある孤立]]」を再考さえした。具体的には1898年にロシアが提唱する中国分割案、ドイツが提唱するトルコ分割案をそれぞれ承諾し、彼らに譲歩する姿勢を示した<ref name="林(1995)62">[[#林(1995)|林(1995)]] p.62</ref>。 |
|||
===== セシル・ローズとジェームソン侵入事件 ===== |
|||
[[File:Cecil Rhodes portrait LAC CANADA.jpg|thumb|150px|セシル・ローズの肖像画。]] |
|||
[[ケープ植民地]]では1890年より[[セシル・ローズ]]が首相を務めていた。彼はトランスヴァール共和国の北方に[[ローデシア]]と呼ばれるイギリス植民地を作り、最大規模のイギリス特許会社を創設した男だった。ヴィクトリアと謁見した際に最近何をしていたのか下問されると「陛下の御料地に属州を二つ追加しておりました」と大真面目に述べるような強烈な帝国主義者だった<ref name="モリス(2008)下394">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.394</ref>。 |
|||
ローズには北アフリカのエジプト・カイロと南アフリカのケープ植民地を鉄道で繋いでアフリカ大陸を横断する大英帝国通商路を建設するという壮大な計画があった<ref name="モリス(2008)下394-395">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.394-395</ref>。だがこの計画に邪魔なのは反英的な[[ボーア人]]国家[[トランスヴァール共和国]]であった。トランスヴァールは隣接する[[ポルトガル領モザンビーク]]の港と鉄道で通じており、英国領土を通商路に使う必要がない国だった<ref name="モリス(2008)下396">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.396</ref>。折しもトランスヴァール共和国の[[ウィットウォーターズランド]]で[[金鉱]]が発掘され、[[ヨハネスブルグ]]の町が建設されてトランスヴァール共和国は潤い始めていた<ref name="モリス(2008)下376">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.376</ref>。ローズはウィットウォーターズランドの金鉱を奪うべきことをヴィクトリアに上奏していた<ref name="ワイントラウブ(1993)下394">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.394</ref>。だがイギリス本国政府は1890年代に入っても白人国家に対しては露骨な帝国主義を行う気にはなれず、トランスヴァール共和国に対しては弱腰だった<ref name="モリス(2008)下396">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.396</ref>。 |
|||
1895年末から1896年初頭にかけてローズの友人であるローデシア行政官{{仮リンク|レアンダー・スター・ジェームソン|en|Leander Starr Jameson}}率いる500名ほどの騎馬警察隊が突然トランスヴァール共和国へ侵入を開始したが、計画があまりに杜撰すぎて早々に包囲されて降伏した({{仮リンク|ジェームソン侵入事件|en|Jameson Raid}})<ref name="中西(1997)159">[[#中西(1997)|中西(1997)]] p.159</ref><ref name="林(1995)30">[[#林(1995)|林(1995)]] p.30</ref><ref name="モリス(2008)下398-401">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.398-401</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)下394-395">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.394-395</ref>。イギリス政府は公式にはこのジェームソンの行動を批判し、セシル・ローズも「20年来の友人にこんな事件を起こされて破滅させられるとは」と語って無関係を装ったが、彼は退任を余儀なくされた<ref name="モリス(2008)下401">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.401</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)下395">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.395</ref>。ドイツ皇帝[[ヴィルヘルム2世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム2世]]はトランスヴァール共和国大統領[[ポール・クリューガー]]に宛てて祝電を送っている<ref name="ワイントラウブ(1993)下395"/><ref name="モリス(2008)下402">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.402</ref>。 |
|||
だがイギリスの国民世論はローズやジェームソンたちの行動を称賛していた。ヴィクトリアも複雑な思いでおり、とりあえず祝電を送ったヴィルヘルム2世に対して「貴方がいつも多大な愛情を捧げ、また手本にしていると言ってくれている祖母より」との書き出しで「貴方の書状が英国民に悪い印象を与えている」とする忠告文を送った<ref name="ワイントラウブ(1993)下396">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.396</ref>。イギリス政府が処罰を行う事を条件にトランスヴァール共和国はジェームソンらを釈放した。これを聞いたヴィクトリアはクリューガー大統領に「貴方の寛大な処置は南アフリカの平和に寄与するでしょう」というメッセージを送っている<ref name="ワイントラウブ(1993)下397">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.397</ref>。 |
|||
{{Gallery |
|||
|File:Rhodes.Africa.jpg|[[ケープ植民地]]と[[カイロ]]を繋ぐと豪語した[[セシル・ローズ]]の風刺画 |
|||
|File:Leander Starr Jameson00.jpg|トランスヴァール共和国へ侵入するレアンダー・スター・ジェームソンらイギリス人たちを描いた絵。 |
|||
}} |
|||
{{-}} |
|||
===== ボーア戦争 ===== |
|||
しかしジェームソン侵入事件以降、イギリスとトランスヴァール共和国の関係は悪化の一途をたどった。1898年2月のトランスヴァール共和国大統領選挙でクリューガーが四選すると[[ケープ植民地]]高等弁務官[[アルフレッド・ミルナー]]はトランスヴァールとの交渉による和解の見込みはないと判断してトランスヴァールとの戦争を煽るようになった<ref name="林(1995)70">[[#林(1995)|林(1995)]] p.70</ref>。ミルナーの高圧的な要求に激怒しクリューガー大統領は同じ[[ボーア人]]国家[[オレンジ自由国]]と結託してイギリスと戦争する決意をした<ref name="君塚(2007)256">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.256</ref>。 |
|||
ボーア人の祖先の国であるオランダの女王[[ウィルヘルミナ (オランダ女王)|ウィルヘルミナ]]が戦争回避を望む手紙をヴィクトリアに送ったが、ヴィクトリアは「私も戦争は避けたいですが、私に保護を求めてくる臣民を私は見捨てることはできません。すべてはクリューガー大統領次第です」と回答した<ref name="君塚(2007)256-257">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.256-257</ref>。1899年10月9日トランスヴァール共和国から高圧的な最後通牒を受けてソールズベリー侯爵は同国との交渉打ち切りを決意し、開戦やむなしとの結論を下した。ヴィクトリア女王もそれを支持した<ref name="君塚(2007)256-258">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.256-258</ref>。 |
|||
かくして19世紀イギリス最後の戦争[[ボーア戦争]]がはじまった。イギリス軍は6週間でケリを付けるつもりであったが、ボーア人のゲリラ戦術に苦しめられ、勝利を得るまでに2年6カ月もかかった<ref name="林(1995)59">[[#林(1995)|林(1995)]] p.59</ref><ref name="中西(1997)161">[[#中西(1997)|中西(1997)]] p.161</ref>。ボーア戦争の損害は甚大であった。2億3000万ポンドという膨大な戦費が費やされて、イギリス人・ボーア人側双方とも戦死者・戦病死者2万人を超え、またイギリスはボーア人ゲリラへの支援を防ぐため各地に[[強制収容所]]を創設してボーア人婦女子を収容した結果、そこでも2万人もの死者が出た<ref name="中西(1997)164-166">[[#中西(1997)|中西(1997)]] p.164-166</ref><ref name="林(1995)59">[[#林(1995)|林(1995)]] p.59</ref>。 |
|||
多くのイギリス人兵士が死傷しているという報告を受けたヴィクトリアはインド人兵士を戦わせるべきであると考え、インド藩王たちに高位の勲章を与える代わりにインド人兵士を南アフリカの戦地へ続々と送らせた<ref name="君塚(2007)259">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.259</ref>。 |
|||
この悲惨な戦争はこれまで成功に継ぐ成功で帝国主義に輝かしいイメージしか持たなかったイギリス人の心が初めて折れた戦争となった<ref name="中西(1997)164-166">[[#中西(1997)|中西(1997)]] p.164-166</ref>。ボーア戦争は1902年5月に終わったが、その時にはヴィクトリアはすでに崩御していた。 |
|||
{{Gallery |
|||
|File:Armoured train 1899-2.jpg|1899年12月11日、{{仮リンク|マガースフォンテインの戦い|en|Battle of Magersfontein}}で装甲列車から銃撃するイギリス軍 |
|||
|File:British casualties, Spionkop, 1900.jpg|1900年1月24日、{{仮リンク|スピオンコップの戦い|en|Battle of Spion Kop}}で戦死したイギリス兵たち |
|||
|File:Konsentrasiekamp Krugersdorp.jpg|ボーア人強制収容所 |
|||
}} |
|||
{{-}} |
|||
==== 対ヨーロッパ外交 ==== |
|||
===== ナポレオン3世の登場とクリミア戦争 ===== |
|||
[[File:Adolphe Yvon - Portrait of Napoleon III - Walters 3795.jpg|thumb|180px|フランス皇帝[[ナポレオン3世]]。]] |
|||
[[フランス第二共和政]]で大統領に選出されたルイ・ナポレオン・ボナパルトは議会と対立を深める中で1851年にクーデタを起こして成功させ、1852年に皇帝に即位して[[ナポレオン3世]]となった<ref name="君塚(2007)57">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.57</ref>。ナポレオン3世のクーデタの際にイギリスは中立を宣言していたが、パーマストン外相が独断でナポレオン3世にクーデタ成功の祝電を送ったため、ヴィクトリアはラッセル首相に彼の解任を求め、首相もそれに応じた<ref name="君塚(2007)58">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.58</ref><ref name="ストレイチイ(1953)170">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.170</ref>。1852年12月にロンドンで締結された秘密議定書によってイギリス、プロイセン、オーストリア、ロシアは皇帝ナポレオン3世を承認したが、ロシア皇帝[[ニコライ1世]]はナポレオン3世に王号を認めず、ナポレオン3世を苛立たせた<ref name="ワイントラウブ(1993)上363">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.363</ref>。 |
|||
[[ロシア帝国]]は当時崩壊寸前だった[[オスマン帝国|オスマン=トルコ帝国]]の切片を拾い上げる目的で当時オスマン領だった[[バルカン半島]]に在住する[[ロシア正教会|ロシア正教徒]]の保護権を求めてオスマンと対立を深めていた。これに対抗してナポレオン3世はオスマンに加担するようになり、オスマンから[[エルサレム]]のローマ・カトリック教徒の保護権を認められた<ref name="ワイントラウブ(1993)上363"/><ref name="君塚(2007)59">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.59</ref>。オスマンの態度に激怒したロシア軍は1853年7月からオスマン領へ侵攻を開始した<ref name="君塚(2007)59">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.59</ref>。11月に両国が宣戦布告して[[クリミア戦争]]が始まった<ref name="君塚(2007)60">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.60</ref>。 |
|||
[[ジョージ・ハミルトン=ゴードン (第4代アバディーン伯)|アバディーン伯爵]]内閣は閣内分裂状態で初めどちらに付くべきか結論が出なかった<ref name="君塚(2007)60">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.60</ref>。だが海洋の覇者イギリスとしてはロシアが[[黒海]]から[[地中海]]に出てきたり、あるいは北方の[[バルト海]]を支配することは避けたかった<ref name="ワイントラウブ(1993)上372">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.372</ref>。ヴィクトリアもロシア軍の地中海南下に危機感を露わにしていた<ref name="君塚(2007)63">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.63</ref>。ナポレオン3世が英仏共同でロシアに最後通牒を突きつけようと提案してきたこともあり、結局イギリスはそれに乗ることになった<ref name="君塚(2007)63">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.63</ref>。最後通牒で一カ月以内の占領地からの撤収をロシアに求めたが、ロシア皇帝はこれを無視したため英仏はオスマン側で参戦した<ref name="君塚(2007)63-64">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.63-64</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)上372"/>。 |
|||
しかし40年間ヨーロッパでの戦闘経験がないイギリス陸軍は脆弱であり、しかも英仏軍は[[ナポレオン戦争]]を引きずってどこかギクシャクしていた<ref name="ワイントラウブ(1993)上374">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.374</ref>。戦争は泥沼化し、前線は多くの死傷者、病人を出した。ヴィクトリアは王女や女官たちとともに前線の兵士たちのためにマフラーや手袋を編んだ<ref name="ワイントラウブ(1993)上379">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.379</ref>。戦死者の寡婦に弔慰状を書く事にも精を出した<ref name="ワイントラウブ(1993)上379"/>。1854年には{{仮リンク|クリミア・メダル|en|Crimea Medal}}を制定し、閲兵式において兵士たちに自ら授与した。負傷兵の慰問にも出かけた。またプロイセン王[[フリードリヒ・ヴィルヘルム4世 (プロイセン王)|フリードリヒ・ヴィルヘルム4世]]に書状を送り、最低でも中立を保つよう依頼した<ref name="ワイントラウブ(1993)上372-373">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.372-373</ref>。 |
|||
クリミア戦争中の1855年4月16日にナポレオン3世と皇后[[ウジェニー・ド・モンティジョ|ウジェニー]]が訪英した。ヴィクトリアの伯父レオポルド王が[[ルイ・フィリップ (フランス王)|ルイ・フィリップ王]]の娘[[ルイーズ=マリー・ドルレアン|ルイーズ]]と結婚していた関係でヴィクトリアは親[[オルレアン家]]であり、[[フランス革命|革命]]から生まれ出た[[ボナパルト家]]を嫌っていたが、ナポレオン3世とウジェニーのことはすっかり気に入ったようだった<ref name="ワイントラウブ(1993)上386-388">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.386-388</ref>。二人と別れる際にはヴィクトリアは涙ぐんでお別れの言葉を述べた<ref name="ワイントラウブ(1993)上391">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.391</ref>。同年8月に返礼としてヴィクトリアとアルバート、ヴィッキー、バーティが訪仏した。ヴィクトリアは子供たちも皇帝が好きになったと日記に書いている。バーティはナポレオン3世に「貴方の息子だったらよかったのに」と語ったという<ref name="ワイントラウブ(1993)上397">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.397</ref>。 |
|||
一方前線では[[セヴァストポリの戦い (クリミア戦争)|セヴァストポリ要塞攻防戦]]でロシア軍と英仏軍が激戦を繰り広げていた。ヴィクトリアは外相クラレンドン伯爵に「ここを陥落させればオーストリアとプロイセンもこちら側で参戦するはず。文明世界を食らう野蛮国ロシアは周辺の列強全てで封じ込めなければいけません」と語った<ref name="君塚(2007)65">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.65</ref>。1855年9月にセヴァストポリ要塞が陥落したことでロシア皇帝[[アレクサンドル2世]]は戦意を喪失し、ナポレオン3世の提唱するパリ講和会議を受け入れ、1856年3月30日に[[パリ条約 (1856年)|パリ条約]]が締結されて終戦した<ref name="君塚(2007)67-68">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.67-68</ref>。だがこれはイギリスの意に反する形で行われ、ヴィクトリアはナポレオン3世に不信感を持つようになった<ref name="君塚(2007)100">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.100</ref>。とはいえイギリスも一人で粘るわけにはいかず結局この条約に追従する羽目になった<ref name="君塚(2007)68">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.68</ref>。 |
|||
しかしパリ条約は双方利益が少なく、これでは何のために多くのイギリス人の命が失われたのか分からないとヴィクトリアは不満だった。伯父レオポルド王に宛てて「イギリスの目的は野蛮大国ロシアの危険な野望からヨーロッパを救う事です。オーストリアとプロイセンが1853年の段階でロシアに断固たる姿勢をとっていたらこんなことにはならなかったのに」と書いた<ref name="君塚(2007)68">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.68</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
{{Gallery |
|||
|File:Eugene Lami 001.jpg|1855年パリ。訪仏したヴィクトリアとアルバートの歓迎式典を描いた{{仮リンク|ウジェーヌ・ラミ|fr|Eugène Lami}}の絵画 |
|||
|File:Queen Victoria's First Visit to her Wounded Soldiers by Jerry Barrett.jpg|クリミア戦争の負傷者を慰問するヴィクトリア、アルバート、バーティ皇太子、アルフレッド王子を描いた{{仮リンク|ジェリー・バレット|en|Jerry Barrett}}の絵画 |
|||
|File:Robert Gibb - The Thin Red Line.jpg|ロシア軍の突撃を防ぐ第93歩兵連隊の「[[シン・レッド・ライン]]」を描いた{{仮リンク|ロバート・ギブ|en|Robert Gibb}}の絵画 |
|||
}} |
|||
{{-}} |
|||
===== ビスマルク、ナポレオン3世との対立 ===== |
|||
[[File:OttovanBismarck1.jpg|thumb|180px|[[ドイツ帝国]]・[[プロイセン王国]]宰相[[オットー・フォン・ビスマルク]]。]] |
|||
ヴィクトリアの長女[[ヴィクトリア (ドイツ皇后)|ヴィッキー]]は1858年に[[プロイセン王国]]国王代理ヴィルヘルム王子(後の[[ヴィルヘルム1世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム1世]])の長男フリードリヒ王子(後の[[フリードリヒ3世 (ドイツ皇帝)|フリードリヒ3世]])と結婚した。1861年にヴィルヘルム1世がプロイセン王に即位し、1862年9月には[[オットー・フォン・ビスマルク]]がプロイセン宰相となり、プロイセンは軍拡・ドイツ統一に乗り出した。 |
|||
だがドイツ統一をめぐっては[[大ドイツ主義]]([[オーストリア帝国|オーストリア]]中心の統一)と[[小ドイツ主義]](プロイセン中心の統一)の対立があった。1863年にオーストリアは大ドイツ主義的な[[ドイツ連邦]]改革を行おうと[[フランクフルト]]でドイツ連邦諸侯会議を開催するもプロイセンが反発して出席を拒否し対立が深まった。ヴィクトリアは1863年8月にアルバートの銅像の完成記念に[[ザクセン=コーブルク=ゴータ公国]]を訪問したが、この際にコーブルクまで彼女に会いにやってきたプロイセン王ヴィルヘルム1世やオーストリア皇帝[[フランツ・ヨーゼフ1世]]と会見した。ヴィクトリアは両国君主に協調を求めたが、ヴィルヘルム1世もフランツ・ヨーゼフ1世もにべもなく自国の譲歩を拒否した<ref name="君塚(2007)95">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.95</ref>。 |
|||
1863年11月にデンマーク王に即位した[[クリスチャン9世 (デンマーク王)|クリスチャン9世]]がロンドン議定書に違反してシュレースヴィヒ公国へのデンマーク憲法の適用を強行したのに対して、プロイセンとオーストリアはデンマークにロンドン議定書を守らせるとして[[シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争]]を開始した。皇太子バーティはデンマーク王女を妃に迎えており、一方長女ヴィッキーはプロイセン皇太子の妃となっていた<ref name="君塚(2007)98">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.98</ref>。だがヴィクトリアにとって決定的なことは生前アルバートがシュレースヴィヒ=ホルシュタイン問題で常にプロイセンを支持してきたことであり、彼女もその立場を踏襲した。大臣たちに対して「ヨーロッパの平和のため重要なことは一つ。自らこの事態を招いたデンマークを支援しないことです」と主張した<ref name="ストレイチイ(1953)218">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.218</ref>。閣内でも「平和派」が主導権を握り、最終的にイギリスはデンマークを見殺しにすることになった<ref name="ストレイチイ(1953)218">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.218</ref>。 |
|||
だがプロイセンへの肩入れもそこまでだった。その後のヴィクトリアはプロイセンへの警戒感を強めた。彼女はシュレースヴィヒやホルシュタインを併合しようとしているプロイセンに強い怒りを感じていた。ヴィルヘルム1世に宛てて「この恐ろしい時期に私も口を閉ざすわけにはいきません。貴方はある男に騙されているのです。」と書いて送った<ref name="ワイントラウブ(1993)下65">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.65</ref>。1865年には伯父レオポルド王への手紙の中で「プロイセンは極悪非道の限りを尽くしています。不愉快千万です」と怒りを露わにしている<ref name="君塚(2007)99">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.99</ref>。プロイセンは小ドイツ主義統一を確固なものとするため1866年に[[普墺戦争]]を起こし、オーストリアを打倒して[[北ドイツ連邦]]を樹立した。この際に従兄妹である[[ゲオルク5世 (ハノーファー王)|ゲオルク5世]](カンバーランド公)が国王として君臨する[[ハノーファー王国]]はプロイセンに併合された<ref name="ワイントラウブ(1993)下66">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.66</ref>。 |
|||
一方ナポレオン3世は1863年に彼の伯父を否定する[[ウィーン体制]]を破壊しようと1815年の[[ウィーン議定書]]と[[パリ条約 (1815年)|パリ条約]]の改正のためにパリで国際会議を開催することを提唱した。もともとクリミア戦争末の裏切りでナポレオン3世に不信感をもっていたヴィクトリアはこれによって本格的に彼を嫌うようになった。ヴィクトリアはこのナポレオン3世の提案を「無礼千万」と非難している<ref name="君塚(2007)100">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.100</ref>。 |
|||
ヴィクトリアはビスマルクとナポレオン3世の二人こそがウィーン体制を破壊する元凶と確信した<ref name="君塚(2007)101">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.101</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
{{Gallery |
|||
|File:Victoria and Frederick.jpg|1858年、結婚したばかりの頃の長女[[ヴィクトリア (ドイツ皇后)|ヴィッキー]]と娘婿[[フリードリヒ3世 (ドイツ皇帝)|フリードリヒ]](プロイセン王子) |
|||
|File:III. Frigyes és családja.jpg|1862年、プロイセン皇太子フリードリヒと皇太子妃ヴィッキー。彼らの子供である[[ヴィルヘルム2世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム王子]]と[[シャルロッテ・フォン・プロイセン (1860-1919)|シャルロッテ王女]]とともに。 |
|||
}} |
|||
{{-}} |
|||
===== 普仏戦争 ===== |
|||
1867年春にルクセンブルクをめぐって普仏戦争の危機が高まる中、ヴィクトリアは介入に消極的なダービー伯爵首相やスタンリー外相に喝を入れてロンドン会議を開催させ、ルクセンブルクを永世中立国にすることで危機を収束させた。だがビスマルクは南ドイツ諸国を取り込むためにフランスとの戦争を欲していた。結局スペイン王位継承問題を利用したビスマルクの策動で1870年にナポレオン3世はプロイセンへの宣戦布告に追い込まれ、[[普仏戦争]]が勃発した<ref name="ワイントラウブ(1993)下94">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.94</ref>。ナポレオン3世は緒戦でプロイセン軍の捕虜となり、完全に失脚した。ビスマルクは戦争で高揚したドイツ・ナショナリズムを背景にプロイセン王ヴィルヘルム1世をドイツ皇帝に即位させて[[ドイツ帝国]]を樹立した。 |
|||
この間ヴィクトリアにできたことはベルギーの中立を守ることをプロイセン、フランス双方に約束させること<ref name="君塚(2007)103">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.103</ref>、イギリスへの亡命を希望するウジェニー皇后を受け入れてやること<ref name="ワイントラウブ(1993)下95">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.95</ref>、そして新生ドイツ帝国がフリッツやヴィッキーの望む形になる事を祈ることのみだった<ref name="ワイントラウブ(1993)下95">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.95</ref>。1871年3月にプロイセン軍から釈放されたナポレオン3世の亡命も受け入れた。彼はウィンザー城でヴィクトリアと会見したが、落胆しきって涙ぐんでいたといい、ヴィクトリアは日記に「前回(1855年)勝利者としてここにやってきた時の彼と何という違いか」と書いている<ref name="ワイントラウブ(1993)下96-97">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.96-97</ref>。 |
|||
===== 露土戦争 ===== |
|||
1877年に[[バルカン半島]]支配権をめぐってロシア・トルコ間で発生した[[露土戦争 (1877年-1878年)|露土戦争]]でディズレーリ首相は親トルコの立場を取ったが、トルコのキリスト教徒への残虐行為から議会から強い反発を受けた。ディズレーリを寵愛するヴィクトリアさえもがディズレーリに「なぜトルコのキリスト教徒虐殺に抗議しないのか」と詰め寄っている<ref name="ワイントラウブ(1993)下191">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.191</ref>。一方でヴィクトリアはトルコ批判者が主張するようなトルコを処罰してその国土を分割せよというような案はロシアを利するだけとして否定的だった<ref name="ワイントラウブ(1993)下191">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.191</ref>。また「トルコの野蛮性」を盛んに主張する英国世論が「ロシアの野蛮性」を主張しないことも不可思議に思っていた<ref name="ワイントラウブ(1993)下194">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.194</ref>。 |
|||
露土戦争は終始ロシア軍の優位で進み、ヴィクトリアはロシアに対する危機感を強めた。1878年1月にはディズレーリに宛てた書状の中で「私が男だったら自ら出ていって、あの憎たらしいロシア人どもをぶちのめしてやるのに」と激昂している<ref name="ワイントラウブ(1993)下197-198">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.197-198</ref>。ソールズベリー侯爵夫人はこの頃のヴィクトリアの状態を「自制心を失っており、閣僚たちをこづきまわしては戦争へ持っていこうとした」と評している<ref name="ワイントラウブ(1993)下194-195">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.194-195</ref>。 |
|||
結局イギリスは臨戦態勢に入りながらも参戦しないまま、3月にはトルコとロシアの間に[[サン・ステファノ条約]]が締結され、バルカン半島にロシア衛星国[[大ブルガリア公国]]が置かれることになった<ref name="ワイントラウブ(1993)下198">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.198</ref>。さらにロシアはドイツの支持を当て込んでビスマルクが提唱する露土戦争の戦後処理国際会議[[ベルリン会議]]の開催に賛同した。ディズレーリは自らがベルリン会議に出席する決意を固めたが、ヴィクトリアは「ディズレーリは健康を害している。彼の命は私と我が国にとって重要な価値があり、危険に晒されることは許されない」として反対した。だがディズレーリは「鉄血宰相」と対決できる者は自分しかいないと主張して女王を説得した<ref name="ワイントラウブ(1993)下200">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.200</ref>。 |
|||
ベルリン会議でディズレーリはアジアに通じる大英帝国通商路を守るために全力を尽くし、さらに[[キプロス]]を獲得して東地中海航路を確保した<ref name="ワイントラウブ(1993)下201">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.201</ref>。これにはビスマルクも「あのユダヤ人の老人はまさに硬骨漢だ」と驚嘆したという<ref name="ワイントラウブ(1993)下200">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.200</ref>。 |
|||
===== ビスマルクとの会見と娘婿の死 ===== |
|||
1888年3月にドイツ皇帝[[ヴィルヘルム1世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム1世]]が崩御し、娘婿フリッツが[[フリードリヒ3世 (ドイツ皇帝)|フリードリヒ3世]]としてドイツ皇帝に即位した。しかし彼は[[喉頭癌]]を患っており、先は長くなかった。4月にヴィクトリアはフリードリヒ3世のお見舞いも兼ねてイタリア、オーストリア、ドイツ歴訪の外遊に出た<ref name="君塚(2007)229">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.229</ref>。 |
|||
ドイツに到着すると宰相[[オットー・フォン・ビスマルク]]を引見した。ヴィクトリアはビスマルクが噂に聞くより紳士的であったことに驚いたという<ref name="君塚(2007)231">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.231</ref>。ビスマルクはオーストリアがロシアに攻撃されたらドイツはオーストリアを助けねばならない。ロシアはフランスと組むであろうから、そうなるとイギリスが重要になってくると述べた。これに対してヴィクトリアはフランスは政権が不安定なので早々戦争には乗り出さないだろうと無難に返事をした<ref name="君塚(2007)231">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.231</ref>。またヴィクトリアはヴィッキーとフリッツを支えてほしいと依頼した。ビスマルクは自由主義者のこの二人を全く信用していなかったが、その場の口先ではもちろんですと返答した<ref name="君塚(2007)232">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.232</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)下306">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.306</ref>。フリッツとヴィッキーの長男である皇太子ヴィルヘルム(愛称ウィリー)についても話が及び、ヴィクトリアは「ウィリーはまだ未熟であり、イングランド以外にも外遊させて見聞を広げさせるべきではないか」と述べたが、ビスマルクは「殿下はまだ文政をご存じでないですが、もともと頭の良い方なので水の中で放っておいて差し上げればすぐにも泳げるようになりましょう」と回答した<ref name="君塚(2007)232"/><ref name="ワイントラウブ(1993)下306"/>。 |
|||
ついでフリードリヒ3世に面会したが、彼はすでに死にかけの状態でしゃべることはできなかった。ヴィクトリアは彼に接吻し、回復したら是非イングランドへ訪問をと要請した。また駅まで出迎えに出たヴィッキーを慰めた。ヴィクトリアは日記に「ゆっくりと駅を離れる汽車の窓越しに顔をくしゃくしゃにしたヴィッキーを見ながら、私はあの子を待ち受ける恐ろしい運命を思ってぞっとした。哀れな我が子よ。貴女の苦難を少しでも軽くするためなら私はどんなことを厭いません。」と書いている<ref name="ワイントラウブ(1993)下306">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.306</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
===== ヴィルヘルム2世との対立 ===== |
|||
[[File:EmporerWilhelm2.jpg|thumb|180px|ヴィクトリアの孫であるドイツ皇帝[[ヴィルヘルム2世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム2世]]。]] |
|||
1888年6月、フリードリヒ3世が在位99日にして崩御し、ウィリーがヴィルヘルム2世として第三代ドイツ皇帝に即位した<ref name="ワイントラウブ(1993)下307">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.307</ref>。ヴィクトリアは早速この孫に「私は断腸の思いでいます。気の毒な貴方のお母さんのために出来るだけのことをしなさい。また高貴で慈愛にあふれ、この世で最も偉大であった貴方のお父さんを手本となさい」という手紙を送った<ref name="ワイントラウブ(1993)下307">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.307</ref>。この時にはヴィルヘルム2世も「最愛のおばあちゃま」宛てに「母の願い事を叶えるために最大の努力をしているところです」と母を重んじているかのような返信をした<ref name="ワイントラウブ(1993)下307"/>。だが反自由主義者のヴィルヘルム2世とビスマルクはヴィッキーを「イギリス女」として冷遇していた。ついにヴィッキーはイギリスに帰りたいと吐露する手紙をヴィクトリアに送るようになり、それを読んだヴィクトリアは日記に「腸が煮えくりかえる思いである」と書いている<ref name="ワイントラウブ(1993)下309">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.309</ref>。 |
|||
ビスマルクの外交手腕でドイツ帝国はヨーロッパ政治の中枢になっていたが、海軍力ではイギリスに溝を空けられていた。ドイツの工業力は飛躍的に伸びており、強力な海軍を建設することも不可能ではなかったが、ビスマルクはあくまで外交で各国を操ってドイツの国際的地位を優位にしようと考えていたため、他国に警戒感を強めさせる過大な軍事力は邪魔だった。一方ヴィルヘルム2世はいつまでもドイツの海軍力をイギリスの下にしておくつもりはなく、イギリスを越える大植民地帝国を創り上げるつもりだった。それを邪魔立てするつもりなら祖母の国との対決も辞さない覚悟だった<ref name="君塚(2007)234-235">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.234-235</ref>。ヴィクトリアはヴィルヘルム2世が6歳の頃「『あの恐ろしいプロイセン流の誇りと野心』を持たないよう育ってほしい」と日記の中で祈願していたが、その願いは叶わなかった<ref name="朝倉(1996)123">[[#朝倉(1996)|朝倉・三浦(1996)]] p.123</ref>。 |
|||
1889年4月、ヴィルヘルム2世がウィーンを訪問していた際に英国皇太子バーティもウィーンを訪問し、バーティは甥に会談を申し込んだが、ヴィルヘルム2世は自分がまず会見して敬意を表すべき相手は[[オーストリア皇帝]][[フランツ・ヨーゼフ1世|フランツ・ヨーゼフ]]であり、まだ皇太子に過ぎないバーティではないとして拒否した。この件にヴィクトリアもバーティも「叔父にあたる者に対して無礼である」と激怒した<ref name="君塚(2007)235-236">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.235-236</ref>。この騒動は8月にヴィルヘルム2世が訪英してバーティと和解することで何とか解決したが、ヴィクトリアは英独関係に不安を感じるようになり、ビスマルクに自分の肖像画を送るなどして彼を引き込もうとし、ヴィルヘルム2世を抑えさせようとしたが、ビスマルクは1890年にヴィルヘルム2世により辞職に追いやられた<ref name="君塚(2007)236-237">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.236-237</ref>。 |
|||
ヴィルヘルム2世はヴィクトリアやバーティが尊属として上から目線で語ってくることが気にくわず、「イギリスは自分を皇帝として処遇していない」と批判するようになった。それに対してヴィクトリアは「私と皇太子は、孫であり甥である彼とは親密な関係にあった。にもかかわらず『皇帝陛下』としての待遇を公私問わずに要求してくるとは狂気の沙汰である。」と怒り心頭に語っている<ref name="ワイントラウブ(1993)下308">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.308</ref>。しかしこうした見解はヴィルヘルム2世だけのものではなく、多くのドイツ国民も自分たちの皇帝を子供扱いするイギリス女王に無礼なりと感じている人が多かった<ref name="ワイントラウブ(1993)下309">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.309</ref>。 |
|||
ヴィルヘルム2世は年に一度訪英したが、ヴィクトリアにとっては煩わしい行事になり、外務官僚たちにとっても外交儀礼に苦心させられる行事となった<ref name="ワイントラウブ(1993)下337">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.337</ref>。前述したようにヴィルヘルム2世は1896年ジェームソン侵入事件の際にトランスヴァール共和国大統領クリューガーに祝電を送った。「イギリスに悪気があってしたのではない」というヴィルヘルム2世の弁明をヴィクトリアも一応受け入れたが、ヴィクトリアの内心の怒りは強く、その後様々な理由を付けてヴィルヘルム2世の訪英を拒否するようになった。ようやくヴィクトリアの勘気が解けてヴィルヘルム2世が訪英を許されるようになったのは1899年になってのことだった<ref name="ワイントラウブ(1993)下404">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.404</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
=== 崩御 === |
|||
[[File:Osborne House - geograph.org.uk - 22302.jpg|thumb|200px|ヴィクトリア女王崩御の地[[ワイト島]]の[[オズボーン・ハウス]]。]] |
|||
ヴィクトリアは1900年4月のアイルランド訪問でだいぶ疲労した様子を見せるようになった<ref name="ストレイチイ(1953)294">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.294</ref>。同年晩夏頃からは不眠症に苦しむようになり<ref name="ワイントラウブ(1993)下490">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.490</ref>、やがて食事もあまり取れなくなっていった<ref name="ワイントラウブ(1993)下493">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.493</ref>。さらに[[失語症]]を患うようになった<ref name="ストレイチイ(1953)294"/><ref name="ワイントラウブ(1993)下497">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.497</ref>。そのような状態でもヴィクトリアは日々増えるボーア戦争の戦死者の遺族に慰問状を書く激務に励んだ<ref name="ストレイチイ(1953)294-295">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.294-295</ref>。だが日記の中では「私もそろそろ休息が許されてもいい頃です。81歳でしかも疲れ果てているのですからね」と弱音を吐くこともあった<ref name="君塚(2007)236-265">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.265</ref>。 |
|||
1901年に入ると[[脳出血]]を起こすようになった<ref name="君塚(2007)267">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.267</ref>。1901年1月16日、オズボーン・ハウスにおいてヴィクトリアはベッドから起き上がれなくなった<ref name="ワイントラウブ(1993)下502">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.502</ref>。侍従医たちは崩御が近いと看做し、1月18日にヴィクトリアの子らに召集がかかった。この時七男[[アーサー (コノート公)|コノート公アーサー]]は[[ベルリン]]滞在中で、[[ヴィルヘルム2世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム2世]]はその報を聞くと「ホーエンツォレルン王朝200年祭」を放り出してコノート公とともに緊急訪英した<ref name="ワイントラウブ(1993)下504">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.504</ref>。 |
|||
四女[[ルイーズ (アーガイル公爵夫人)|ルイーズ]]によると1月21日にヴィクトリアは「まだ死にたくない。私にはしなければならないことがまだ残っている。」と述べたという<ref name="ワイントラウブ(1993)下505">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.505</ref>。1月22日正午頃、枕元にすすり泣きながら立つ皇太子バーティの存在に気付いたヴィクトリアは、手を広げるような仕草をして「バーティ」と呟いたという。これが判別できる彼女の最期の言葉だった<ref name="ワイントラウブ(1993)下505">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.505</ref>。同日午後4時頃、ヴィクトリアの息遣いが荒くなったため、侍従医リードと買ってでたヴィルヘルム2世の二人掛かりで、ヴィクトリアが息をしやすいように頭を支え、崩御までの2時間半その体勢でいた<ref name="ワイントラウブ(1993)下506">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.506</ref>。{{仮リンク|ウィンチェスター主教|en|Bishop of Winchester}}{{仮リンク|ランダル・デーヴィッドソン|en|Randall Davidson}}が祈祷を捧げ、子供たちや孫たちが見守る中、6時半頃、ヴィクトリアは81歳で崩御した<ref name="ワイントラウブ(1993)下506">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.506</ref>。 |
|||
ヴィクトリアの崩御とともにイギリス国王となったバーティは最初の枢密院を開くため、1月23日早朝にオズボーン・ハウスを発ってロンドンの[[セント・ジェームズ宮殿]]へ向かった。バーティがロンドン滞在で不在の間オズボーン・ハウスの管理はヴィルヘルム2世に任された。イギリス王室の宮殿が非公式にとはいえ外国君主に委ねられるのは極めて異例だった。ヴィルヘルム2世は彼女の棺の製作と棺を安置する部屋の模様替えを指揮した。この際に彼はウィンチェスター主教に対して「彼女と一緒にいる時、祖母であるという事は常に意識してきた。祖母として愛そうという思いもずっとあった。しかし話が政治に絡むとその瞬間から私たちは君主同士として対等の関係となった。」と語っている<ref name="ワイントラウブ(1993)下508">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.508</ref>。 |
|||
バーティは枢密院会議で自らの王名をエドワード7世に定めると発表した。ファーストネームの「アルバート」にしなかったのは「アルバートといえば誰もが父を思いだすようにしたかった」からだという<ref name="ワイントラウブ(1993)下508">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.508</ref>。枢密院会議を終えたエドワード7世は1月24日午後にはオズボーン・ハウスへ戻った<ref name="ワイントラウブ(1993)下508">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.508</ref>。エドワード7世とコノート公の二人がかりでヴィクトリアの遺体を持ちあげて棺の中に入れた。チャペルに保管された棺にはヴィルヘルム2世の発案でイギリス国旗[[ユニオンジャック]]が掛けられ、ヴィルヘルム2世は記念としてその国旗をもらって帰った<ref name="ワイントラウブ(1993)下509">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.509</ref>。 |
|||
[[大葬]]はヴィクトリアの希望通り[[軍葬]]で行われた。2月1日、ヴィクトリアの棺は霊柩船で[[ポーツマス (イングランド)|ポーツマス]]、特別列車で[[ヴィクトリア駅]]まで移送された。そこからエドワード7世とヴィルヘルム2世を先頭にした軍隊の葬列を伴って馬車で[[セント・ジェームズ宮殿]]まで移送された<ref name="ワイントラウブ(1993)下510-511">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.510-511</ref>。 |
|||
女王の大葬は2月4日まで行われた。大葬後、エドワード7世の意向で「ムンシ」はじめインド人侍従たちは全てインドへ送り返されることになり、また「ムンシ」に関する文書も焼却処分された。ジョン・ブラウンの銅像も奥深くに隠された<ref name="ワイントラウブ(1993)下513">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.513</ref>。それ以外にもヴィクトリア思い出の品々が次々と宮殿内から片付けられていった<ref name="ワイントラウブ(1993)下513"/>。 |
|||
ヴィクトリアがエドワード7世に引き渡した王位は、彼女がウィリアム4世から引き継いだ時の王位よりも政治権力の面では大きく弱体化した物ではあったが、国民からの人気はかつてないほど大きくなっていった<ref name="川本(2006)IV"/>。 |
|||
{{Gallery |
|||
|File:Victoria Statue in Victoria Square Birmingham.jpg|イギリス・[[バーミンガム]]にあるヴィクトリア像 |
|||
|File:Square Victoria.JPG|[[カナダ]]・[[モントリオール]]にあるヴィクトリア女王像 |
|||
|File:Queen Victoria's statue inside the memorial in Kolkata.jpg|[[インド]]・[[コルカタ]]にあるヴィクトリア女王像 |
|||
|File:QueenVictoria HK Statue.jpg|[[中華人民共和国|中国]][[香港]]にあるヴィクトリア女王像 |
|||
}} |
|||
{{-}} |
|||
== 人物 == |
|||
[[File:The Town Hall at Barrow-in-Furness - geograph.org.uk - 1513505.jpg|thumb|200px|[[バロー・イン・ファーネス]]市役所にあるヴィクトリアの胸像]] |
|||
=== 体格・体質 === |
|||
ヴィクトリアの身長は145センチ足らずであった。一方体重はアルバートとの結婚前にすでに56キロ、1880年代には76キロになっていた<ref name="川本(2006)55">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.55</ref>。 |
|||
ヴィクトリアは大変な暑がりであり、宮殿内では女王臨御の際には必ず侍従たちが前もって窓を開けておくのが常であった<ref name="川本(2006)55"/>。 |
|||
=== 直情径行 === |
|||
ヴィクトリアは直情径行、我がまま、短気で、理屈は通らない人物だった<ref name="川本(2006)269">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.269</ref><ref name="世界大百科事典ハノーバー朝">[[#世界大百科事典|世界大百科事典]]「ビクトリア女王」の項目</ref>。 |
|||
それについてアルバートは「ヴィクトリアは短気で激昂しやすい。私の言う事を聞かずにいきなり怒りだして、私が彼女に信頼を強要している、私が野心を抱いている、と非難しまくって私を閉口させる。そういう時私は黙って引き下がるか(私にとっては母親にしかられて冷遇に甘んじる小学生のような心境だが)、あるいは多少乱暴な手段に出る(ただし修羅場になるのでやりたくない)しかない。」と語っている<ref name="ワイントラウブ(1993)上253">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.253</ref>。ヴィクトリア自身も自らが「矯正不可能」なほど「意見されると感情が激高しやすい性格」であることを語ったことがある<ref name="ワイントラウブ(1993)上253">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.253</ref>。 |
|||
ヴィクトリアから寵愛を受け続けたディズレーリは「女王陛下とうまく付き合うコツは、決して拒まず、決して反対せず、時々物忘れをすることだ」と語っている<ref name="ベイカー(1997)182">[[#ベイカー(1997)|ベイカー(1997)]] p.182</ref>。 |
|||
=== 教養の浅薄さ === |
|||
またアルバートは自分に比べてヴィクトリアの教養が浅薄であることを気にかけていた。アルバートは科学や技術に精通していたが、ヴィクトリアはその分野の知識は皆無であり、、そういう話題を避けたがった。芸術や音楽の分野には多少精通していたものの、それもやはりアルバートの高い教養には遠く及ばないレベルだった。アルバートはこれをヴィクトリアの[[ガヴァネス]]だった{{仮リンク|ルイーゼ・レーツェン|de|Louise Lehzen}}の教育のせいであると考えており、それもアルバートがレーツェンを宮廷から追放した理由であった<ref name="ワイントラウブ(1993)上255">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.255</ref>。 |
|||
=== 「ドイツ人」のイギリス女王 === |
|||
ヴィクトリアにはイギリスよりドイツの血の方がはるかに濃く流れている。計算上ヴィクトリアに流れる[[ステュアート家]]の血は256分の1に過ぎず、残りはほとんどドイツ人の血であった<ref name="森(1986)567-568">[[#森(1986)|森(1986)]] p.567-568</ref>。 |
|||
そのためかヴィクトリアは日ごろから親独派だった<ref name="世界大百科事典ビクトリア女王">[[#世界大百科事典|世界大百科事典]]「ビクトリア女王」の項目</ref>。ドイツから来た夫アルバートも同様であったので女王夫妻はドイツ語を日常会話にすることが多かった<ref name="ワイントラウブ(1993)上362">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.362</ref>。アルバートはヴィクトリア以上にドイツ人としての意識が強く、彼は最終的にドイツ諸国、イギリス、ベルギー、デンマーク、スイスなど「ドイツ民族諸国」を一つにして、ロシア、フランス、およびヨーロッパの民主化の風潮に対抗する勢力にしたいと考えていたという<ref name="川本(2006)254">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.254</ref>。 |
|||
女王夫妻はイギリスの国益を無視してプロイセンを支援しドイツ統一に協力していると疑うイングランド人も多かった<ref name="ワイントラウブ(1993)上362-363">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.362-363</ref>。 |
|||
=== 「立憲君主」について === |
|||
彼女が即位した際の英国王位はいまだ大きな政治的権力を備えていた。アルバート公存命期に王権は伸長したが、彼の死とともに王権は弱体化し、ヴィクトリア朝末期にはイギリス史上かつてないほど王権は小さくなり、立憲君主制が確立されることになった。しかしヴィクトリア当人は自分が持っている物を手放すことに非常に抵抗感を感じる性質であり<ref name="モリス(2006)上375">[[#モリス(2006)上|モリス(2006) 上巻]] p.375</ref>、立憲君主になる意思などなく、受動的にそうなってしまっただけであった<ref name="ストレイチイ(1953)287">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.287</ref>。 |
|||
女王が意見する権利は法律で認められているが、ヴィクトリアはその枠に留まるつもりはなく、首相や陸軍大臣を無視して退任した首相や軍部などに政治について積極的に諮問した<ref name="ヒバート(1998)168">[[#ヒバート(1998)|ヒバート(1998)]] p.168</ref>。また政府が気に入らない法案を推し進めると退位すると脅迫し、自らを批判する者に対しては怒り狂って反撃した<ref name="ヒバート(1998)169">[[#ヒバート(1998)|ヒバート(1998)]] p.169</ref>。政府や議会の決定を阻止することができないとしても、その頑固さによって遅延させた<ref name="ワイントラウブ(1993)下322">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.322</ref>。 |
|||
特に女王に独断で政治を進める傾向があったパーマストン子爵に対して「女王の下僕(公務員)や大臣が女王に何も相談せずに行動を起こすことは許さない」という戒めの手紙を送ったことがあった<ref name="川本(2006)249">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.249</ref>。またその時のパーマストンの上司ジョン・ラッセル首相に対して「1、外務大臣は何を行おうとしているか女王に明確に述べること、女王が何に裁可を与えたか把握するためである。2、一度女王が裁可を与えた場合にはそれ以降外務大臣は独断で政策を変更・修正してはならない。そのような行為は王冠に対する不誠実であり、行われた場合には大臣罷免の[[イギリスの憲法|憲法]]上の権限を行使するであろう」と通達している<ref name="川本(2006)254-255">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.254-255</ref><ref name="ストレイチイ(1953)166">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.166</ref>。 |
|||
アルバートもまた立憲君主の枠に収められるつもりはなかった。彼の側近{{仮リンク|クリスティアン・フリードリヒ・フォン・シュトックマー|de|Christian Friedrich von Stockmar}}男爵は「首相は一時的な指導者に過ぎず、君主こそが永遠の指導者である」と考えており、国王には首相を罷免する権限があると考えていた。アルバートは王に首相を罷免する権利があるかどうかは分からないが、あったとしても罷免を実行すれば最終的に王権が危うくなると考えていたと言われる<ref name="ヒバート(1998)169">[[#ヒバート(1998)|ヒバート(1998)]] p.169</ref>。 |
|||
ヴィクトリアは君主としての能力が乏しかったが、アルバートにはその能力があった。アルバートは薨去直前の段階ですでに政府にとっても議会にとってもなくてはならない存在となっていた。その彼がもっと長く生存していたならば、イギリスは立憲君主制とはならなかったのではないかという指摘もある<ref name="ストレイチイ(1953)210">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.210</ref>。ディズレーリは「アルバート殿下の薨去によって我々は我々の君主を埋めたのである。このドイツ人君主は歴代イギリス王が誰も持たなかった知力と精力でもって21年間我が国を統治した。彼が我が国の長老政治家たちより長生きしたとすれば、彼は我々に絶対君主制をプレゼントしてくれただろう」と語っている<ref name="ストレイチイ(1953)211">[[#ストレイチイ(1953)|ストレイチイ(1953)]] p.211</ref>。 |
|||
アルバートの死後、ヴィクトリアの王権は低下する一方であった。それはなんといっても大臣たちの優秀さの賜物であった。彼らは「政治の素人」の彼女が政治に口を出そうとするのを適切に拒否したのである<ref name="世界大百科事典ビクトリア女王">[[#世界大百科事典|世界大百科事典]]「ビクトリア女王」の項目</ref>。晩年の彼女は電報を送る権利さえ奪われそうになった{{#tag:ref|[[マフディーの反乱]]の最中の1885年1月に[[アブクレアの戦い]]でイギリス軍がマフディー軍に勝利すると、ヴィクトリアは大喜びして司令官ヴォルズリー将軍に祝電を送ったのだが、それに対して陸相ハーティントン侯爵が女王が陸軍軍人に対してメッセージを出すには陸軍大臣の許可を得て行わなければならないと抗議した。ヴィクトリアは「私が将軍たちに直接伝えたほうが彼らも喜びます。女王が彼女の将軍に対して電報を送る事は何の問題もありません。ハーティントン侯爵は差し出がましく生意気です。女王は相手がだれであろうとも自由に祝電を打つ権利があり、指図を受ける気はありません。女王は機械ではありません」と怒りを露わにした<ref name="君塚(2007)188">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.188</ref>。|group=#}}。 |
|||
=== ユダヤ人について === |
|||
[[File:Disraeli receiving Order of the Garter.gif|thumb|200px|ユダヤ人の首相ベンジャミン・ディズレーリをビーコンズフィールド伯爵に叙するヴィクトリア女王]] |
|||
ヴィクトリア即位の頃にイギリス・ユダヤ人は3万人ほどで、うち半数がロンドンで暮らしていたが、ユダヤ人はキリスト教的な価値観や金融業者のイメージのせいで蔑視され、いまだ政治的に差別的な扱いを受けていた<ref name="川本(2006)238">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.238</ref>。 |
|||
ヴィクトリアはヒステリックな反ユダヤ主義者ではなく、ユダヤ人への爵位・[[ナイト爵]]の授与はヴィクトリア朝時代から開始された。即位間もない1837年11月9日にロンドン市を公式訪問した際、ユダヤ人市長{{仮リンク|モーゼス・モンテフィオリ|en|Moses Montefiore}}にナイト爵を授けたのがその最初である<ref name="川本(2006)238">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.238</ref>。このイギリス史上初のユダヤ人へのナイト爵授与についてヴィクトリアは日記に「正しいと思う事を当然のこととして実行したのは私が最初である。とても嬉しかった。」と書いている<ref name="川本(2006)238"/>。 |
|||
彼女がとりわけ気に入っていたユダヤ人は首相[[ベンジャミン・ディズレーリ]]である。ディズレーリは出世のために少年時代にキリスト教に改宗していたが、ユダヤ人をユダヤ教徒ではなく人種(race)ととらえており、自分はユダヤ人種であること、そしてユダヤ人種の優秀性を公言していた<ref name="川本(2006)258">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.258</ref>。一方[[ウィリアム・グラッドストン]]はキリスト教主義的な立場からどこか反ユダヤ主義的であり、ディズレーリ批判を繰り返していたが(たとえばディズレーリの親トルコ外交を「トルコのキリスト教徒虐殺に加担したがっているユダヤ人の本性に根ざしたもの」と批判するなど)、ヴィクトリアはこういうグラッドストンのキリスト教主義的思想を嫌っていた<ref name="川本(2006)260">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.260</ref>。 |
|||
一方で1869年にグラッドストンが自由党所属の庶民院議員ライオネル・デ・ロスチャイルドに爵位を与えるべきことを進言してきた際にはヴィクトリアは「ユダヤ貴族は認められない」「貴族は伝統的に地主であるべきで企業家・投機家であってはならない」「[[准男爵]](貴族ではない)までなら許可する」として[[男爵]]位以上の授与は拒否している<ref name="川本(2006)266">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.266</ref>。 |
|||
しかし1885年7月9日にヴィクトリアはライオネルの息子である{{仮リンク|ナサニエル・ロスチャイルド (初代ロスチャイルド男爵)|label=ナサニエル・ロスチャイルド|en|Nathan Rothschild, 1st Baron Rothschild}}に男爵位を与えている。この頃にはロスチャイルド家は所領を手放した貴族たちの土地を買収するようになっており、領民をたくさん従える領主のイメージも付いてきていたため、ヴィクトリアの反発も弱まったものと思われる。先の却下理由の一つである「ユダヤ人貴族は認められない」という点についてはいまだクリアーできていなかったが、恐らくそちらの理由は彼女の中で大きな問題ではなかったのだと思われる<ref name="川本(2006)270-271">[[#川本(2006)|川本(2006)]] p.270-271</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
=== 切り裂きジャック事件について === |
|||
ヴィクトリアは[[切り裂きジャック]]の{{仮リンク|ホワイトチャペル連続殺人事件|en|Whitechapel murders}}について興味を持ち、首相ソールズベリー侯爵、内務大臣{{仮リンク|ヘンリー・マシューズ (初代ランダッフ子爵)|label=ヘンリー・マシューズ|en|Henry Matthews, 1st Viscount Llandaff}}に対して1887年に[[コナン・ドイル]]の小説で登場したばかりの[[シャーロック・ホームズ]]のような捜査を求めた<ref name="ワイントラウブ(1993)下309-310">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.309-310</ref>。 |
|||
ヴィクトリアはマシューズに対して夜に婦人ばかりが襲われていることから一人住まいの男を中心に聞き込みすべきだと主張し、また犯人の逃亡ルートを探すため船に対する捜査や夜警の徹底を求めた<ref name="ワイントラウブ(1993)下310">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.310</ref>。 |
|||
なお皇太子バーティの長男[[アルバート・ヴィクター (クラレンス公)|エディ王子]]を切り裂きジャックとする噂が巷に流れていたが、恐らくヴィクトリア女王の耳には入れられていない<ref name="ワイントラウブ(1993)下310">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.310</ref>。 |
|||
=== その他逸話 === |
|||
*カナダの首都はヴィクトリア女王が選定したが、この時彼女は目をつぶって地図にピンを突き刺した場所を首都に選び、それが[[オタワ]]だったという<ref name="モリス(2006)下206">[[#モリス(2006)下|モリス(2006) 下巻]] p.206</ref>。 |
|||
*写真好きであり、自分と家族の写真を多く残した。映画フィルムに残っている最初の英国王でもある<ref name="森(1986)567-568">[[#森(1986)|森(1986)]] p.567-568</ref>。 |
|||
== 家族 == |
|||
=== 子女 === |
|||
[[File:Queen Victoria Prince Albert and their nine children.JPG|thumb|right|280px|女王夫妻と9人の子供たち]] |
|||
夫[[アルバート (ザクセン=コーブルク=ゴータ公子)|アルバート]]との間に4男5女の9子を儲けた。子供達をドイツを中心とした各国に嫁がせ、晩年には「[[ヨーロッパの祖母]]」と呼ばれるに至る。しかしヴィクトリアは[[血友病]]の因子を持っており、子孫の男子が次々と発病した。ヴィクトリアに連なる3代18人の男子のうち10人までが血友病で命を落としている<ref name="世界大百科事典血友病">[[#世界大百科事典|世界大百科事典]]「血友病」の項目</ref>。四男[[レオポルド (オールバニ公)|レオポルド]]<ref name="ワイントラウブ(1993)上354">[[#ワイントラウブ(1993)上|ワイントラウブ(1993) 上巻]] p.354</ref>と曾孫のロシア皇太子[[アレクセイ・ニコラエヴィチ (ロシア皇太子)|アレクセイ]]が血友病患者として知られる。 |
|||
*第一子(長女) [[ヴィクトリア (ドイツ皇后)|ヴィクトリア(愛称ヴィッキー)]]([[1840年]]-[[1901年]]) - [[ドイツ帝国|ドイツ]][[ドイツ皇帝|皇帝]][[フリードリヒ3世 (ドイツ皇帝)|フリードリヒ3世]]皇后 |
|||
*第二子(長男) [[エドワード7世 (イギリス王)|アルバート・エドワード(愛称バーティ)]]([[1841年]]-[[1910年]]) - ハノーヴァー朝第7代英国王[[エドワード7世 (イギリス王)|エドワード7世]] |
|||
*第三子(次女) [[アリス (ヘッセン大公妃)|アリス]]([[1843年]]-[[1878年]]) - [[ヘッセン大公国|ヘッセン大公]][[ルートヴィヒ4世 (ヘッセン大公)|ルートヴィヒ4世]]大公妃 |
|||
*第四子(次男) [[アルフレート (ザクセン=コーブルク=ゴータ公)|アルフレッド]]([[1844年]]-[[1900年]]) - [[ザクセン=コーブルク=ゴータ公国|ザクセン=コーブルク=ゴータ公]]・[[エディンバラ公|エディンバラ公爵]] |
|||
*第五子(三女) [[ヘレナ (イギリス王女)|ヘレナ]]([[1846年]]-[[1922年]]) - シュレースヴィヒ=ホルシュタイン公子[[クリスティアン・フォン・シュレースヴィヒ=ホルシュタイン=ゾンダーブルク=アウグステンブルク|クリスティアン]]夫人 |
|||
*第六子(四女) [[ルイーズ (アーガイル公爵夫人)|ルイーズ]]([[1848年]]-[[1939年]]) - [[ジョン・キャンベル (第9代アーガイル公爵)|アーガイル公爵ジョン・ダグラス・サザーランド・キャンベル]]夫人 |
|||
*第七子(三男) [[アーサー (コノート公)|アーサー]]([[1850年]]-[[1942年]]) - [[コノート|コノート公爵]] |
|||
*第八子(四男) [[レオポルド (オールバニ公)|レオポルド]]([[1853年]]-[[1884年]]) - [[オールバニ|オールバニ公爵]] |
|||
*第九子(五女) [[ベアトリス (イギリス王女)|ベアトリス]]([[1857年]]-[[1944年]]) - [[バッテンベルク家|バッテンベルク公]][[ヘンリー・オブ・バッテンバーグ|ハインリヒ・モーリッツ]]公妃 |
|||
=== ドイツ皇室・ロシア皇室との関係 === |
|||
{{familytree/start}} |
|||
{{familytree | | | | | | My |~|y|~| husband1 | |My=第6代<br>英国女王<br>'''ヴィクトリア'''|husband1=[[王配]]<br>[[アルバート (ザクセン=コーブルク=ゴータ公子)|アルバート]]}} |
|||
{{familytree | |,|-|-|-|-|-|-|-|+|-|-|-|.| }} |
|||
{{familytree | daughter1 |y| husband2 | | son1 | | daughter2 |y| husband3 | daughter1=ドイツ皇后<br>[[ヴィクトリア (ドイツ皇后)|ヴィクトリア]]|husband2=第2代<br>[[ドイツ皇帝]]<br>[[フリードリヒ3世 (ドイツ皇帝)|フリードリヒ3世]]|son1=第7代<br>英国王<br>[[エドワード7世 (イギリス王)|エドワード7世]]|daughter2=ヘッセン<br>大公妃<br>[[アリス (ヘッセン大公妃)|アリス]]|husband3=[[ヘッセン大公]]<br>[[ルートヴィヒ4世 (ヘッセン大公)|ルートヴィヒ4世]]}} |
|||
{{familytree | | | |!| | | | | | | | | | | |!| | }} |
|||
{{familytree | | | grandson1 | | | | | | husband4 |y| granddaughter1 |grandson1=第3代<br>ドイツ皇帝<br>[[ヴィルヘルム2世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム2世]]|granddaughter1=ロシア皇后<br>[[アレクサンドラ・フョードロヴナ (ニコライ2世皇后)|アレクサンドラ]]|husband4=第14代<br>ロシア皇帝<br>[[ニコライ2世]]}} |
|||
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |!| }} |
|||
{{familytree | | | | | | | | | | | | | greatgrandchild1 | greatgrandchild1=ロシア皇太子<br>[[アレクセイ・ニコラエヴィチ (ロシア皇太子)|アレクセイ]]}} |
|||
{{familytree/end}} |
|||
== 栄典 == |
== 栄典 == |
||
=== イギリス勲章 === |
|||
ヴィクトリアが外国から授与された勲章は以下の通りである<ref>君塚直隆著『女王陛下のブルーリボン』NTT出版、2004年。以下、国名五十音順。カッコ内の年代は授与された年。</ref>。 |
|||
* |
*[[ガーター勲章]](1826年)<ref name="君塚(2007)14"/> |
||
* {{ESP1785}}:[[マリア・ルイーザ勲章]](1834年)、[[カルロス3世勲章]] |
|||
=== 外国勲章 === |
|||
* {{SRB1882}}:[[タコヴォ勲章]](1882年)、[[白鷲勲章]](1883年)、[[聖サヴァ勲章]](1897年) |
|||
64年の長きにわたって世界一の大国イギリスの王座に君臨したヴィクトリアだが、女性であるためにいずれの国からも最高勲章は授与されず、勲爵士の称号が伴わない勲章のみを授与されている<ref name="君塚(2004)71">[[#君塚(2004)|君塚(2004)]] p.71</ref>。最高勲章は彼女の夫であるアルバートが代わりに受けていた<ref name="君塚(2004)71"/>。ヴィクトリア自身も同じ女性君主だからと[[ガーター勲章]]を贈るようなことはせず、スペイン女王[[イザベル2世]]がガーター勲章を授与してほしいと打診してきた際にも「私自身もそうであるように騎士の称号を伴う外国の勲章を女性君主は受けることができないのが慣習である」として拒否している<ref name="君塚(2004)70">[[#君塚(2004)|君塚(2004)]] p.70</ref>。 |
|||
* {{THA1855}}:[[白象勲章]](1880年)、[[チャクリ王家勲章]](1897年) |
|||
* {{Flagicon|Hawaii}} [[ハワイ王国|ハワイ]]:[[カメハメハ勲章]](1881年) |
|||
* [[File:Flagge Großherzogtum Hessen ohne Wappen.svg|border|25x20px]] [[ヘッセン大公国|ヘッセン]]:[[金獅子勲章]](1862年?) |
|||
* [[File:Flag_of_Empire_of_Brazil_(1847-1889).svg|border|25x20px]] [[ブラジル帝国|ブラジル]]:[[ペドロ1世勲章]](1872年) |
|||
* {{Flagicon|BGR}} [[ブルガリア王国 (近代)|ブルガリア]]:[[赤十字勲章]](1886年) |
|||
* {{PRU}}:[[ルイーゼ勲章]](1857年) |
|||
* [[File:Amir Kabir Flag.svg|border|25x20px]] [[ガージャール朝|ペルシア]]:[[太陽勲章]](1873年) |
|||
* {{PRT1830}}:[[聖イサベル勲章]](1836年)、[[我らが貴婦人ヴィラ・ヴィコサ勲章]] |
|||
* {{MNE1876}}:[[ダニーロ1世勲章]](1897年) |
|||
* {{RUS1858}}:[[聖エカチェリーナ勲章]](1839年) |
|||
ヴィクトリアが外国から授与された勲章は以下の通りである<ref name="君塚(2004)303">[[#君塚(2004)|君塚(2004)]] p.303</ref>。以下、国名五十音順。カッコ内の年代は授与された年。 |
|||
== 人物・逸話 == |
|||
*[[エチオピア帝国]]:{{仮リンク|ソロモン勲章|en|Order of Solomon}}(1897年) |
|||
[[File:Queen Victoria at Osborne House.jpg|thumb|180px|[[ジョン・ブラウン (使用人)|ジョン・ブラウン]]と]] |
|||
*[[スペイン王国]]:{{仮リンク|マリア・ルイーザ勲章|es|Orden de las Damas Nobles de María Luisa}}(1834年)、{{仮リンク|カルロス3世勲章|es|Orden de Carlos III}} |
|||
*ヴィクトリアが母方の従弟に当たる[[ザクセン=コーブルク=ゴータ家|ザクセン=コーブルク=ゴータ公子]]アルバート と初めて会ったのは16歳のときである。血縁関係の他に、2人は同じ主治医にかかっており、そこから交際が深まった。ちなみに、ヴィクトリアは自分からアルバートに求婚した。女王に求婚することは許されなかったからである。結婚式は[[1840年]][[2月10日]]に行われた。 |
|||
*[[セルビア王国 (近代)|セルビア王国]]:{{仮リンク|タコヴォ勲章|sr|Орден Таковског крста}}(1882年)、{{仮リンク|白鷲勲章|sr|Орден белог орла}}(1883年)、{{仮リンク|聖サヴァ勲章|sr|Орден Светог Саве}}(1897年) |
|||
*身長は約5フィート(150cm程度)で、小柄な女性であった。 |
|||
*[[タイ王国]]:[[白象勲章]](1880年)、[[大チャクリー勲章]](1897年) |
|||
* 趣味は、[[乗馬]]と[[日記]]だった。乗馬好きが高じて馬産も手がけ、[[1849年]]にはハンプトンコート王室牧場を再開させた。[[競走馬]]は持たないという夫との約束で生産した馬はすべて売却していたが、[[三冠 (競馬)#イギリス牝馬クラシック三冠|英牝馬三冠]]を制した名馬[[ラフレッシュ]]の生産者としても名を残している。また、[[汽車]]による旅行を好んだという。 |
|||
*[[ハワイ王国]]:{{仮リンク|カメハメハ勲章|en|Royal Order of Kamehameha I (decoration)}}(1881年) |
|||
* アルバート死後の服喪時代、馬丁(従僕)の[[ジョン・ブラウン (使用人)|ジョン・ブラウン]]を寵愛し、恋仲にあると噂されて「ブラウン夫人」と呼ばれた。 |
|||
*[[ヘッセン大公国]]:{{仮リンク|金獅子勲章|de|Hausorden vom Goldenen Löwen}}(1862年?) |
|||
* 純白のウェディングドレスを初めて着用した人物であり、またイギリスにクリスマスツリーを飾る習慣を広めた。 |
|||
*[[ブラジル帝国]]:{{仮リンク|ペドロ1世勲章|pt|Imperial Ordem de Pedro Primeiro}}(1872年) |
|||
*[[ブルガリア王国 (近代)|ブルガリア王国]]:[[赤十字勲章]](1886年) |
|||
*[[プロイセン王国]]:{{仮リンク|ルイーゼ勲章|de|Louisenorden}}(1857年) |
|||
*[[ガージャール朝|ペルシア王国]] :{{仮リンク|太陽勲章|fa|نشان آفتاب}}(授与1873年) |
|||
*[[ポルトガル王国]]:{{仮リンク|聖イサベル勲章|pt|Ordem Real de Santa Isabel}}(1836年)、{{仮リンク|我らが貴婦人ヴィラ・ヴィコサ勲章|pt|Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa}} |
|||
*[[モンテネグロ公国]]:{{仮リンク|ダニーロ1世勲章|sr|Орден књаза Данила I}}(1897年) |
|||
*[[ロシア帝国]]:{{仮リンク|聖エカチェリーナ勲章|ru|Орден Святой Екатерины}}(1839年) |
|||
== ヴィクトリア女王を題材にした作品 == |
== ヴィクトリア女王を題材にした作品 == |
||
| 148行目: | 789行目: | ||
* [[ヴィクトリア女王 世紀の愛]] - 2009年、イギリス映画 |
* [[ヴィクトリア女王 世紀の愛]] - 2009年、イギリス映画 |
||
:ヴィクトリア役:[[エミリー・ブラント]] |
:ヴィクトリア役:[[エミリー・ブラント]] |
||
== 伝記(日本語文献) == |
|||
* ヴィクトリア女王([[リットン・ストレイチー]]/[[小川和夫]]訳、[[冨山房]]百科文庫) |
|||
* ヴィクトリア女王(スタンリー・ワイントラウブ/[[平岡緑]]訳、[[中央公論社]] 上下巻/ [[中公文庫]] 全3巻) |
|||
* ヴィクトリア女王-[[大英帝国]]の戦う女王([[君塚直隆]]、[[中公新書]]) |
|||
== 脚注 == |
== 脚注 == |
||
=== 注釈 === |
|||
{{脚注ヘルプ}} |
|||
{{ |
{{reflist|group=#|1}} |
||
=== 出典 === |
|||
<div class="references-small"><!-- references/ -->{{reflist|4}}</div> |
|||
== 参考文献 == |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[朝倉治彦]]、[[三浦一郎]]|date=1996年(平成8年)|title=世界人物逸話大事典|publisher=[[角川書店]]|isbn=978-4040319001|ref=朝倉(1996)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[伊藤之雄]] (編)、[[川田稔]](編)|date=2004年(平成16年)|title=二〇世紀日本の天皇と君主制―国際比較の視点から一八六七~一九四七|publisher=[[吉川弘文館]]|isbn=978-4642037624|ref=伊藤(2004)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[梶谷素久]]|date=1981年(昭和56年)|title=大英帝国とインド―press and empire|publisher=[[第三文明社]]|asin=B000J7UYDM|ref=梶谷(1981)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[川本静子]]|date=2006年(平成18年)|title=ヴィクトリア女王―ジェンダー・王権・表象|series=MINERVA歴史・文化ライブラリー9|publisher=[[ミネルヴァ書房]]|isbn=978-4623046607|ref=川本(2006)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[君塚直隆]]|date=2004年(平成16年)|title=女王陛下のブルーリボン―ガーター勲章とイギリス外交|publisher=[[NTT出版]]|isbn=978-4757140738|ref=君塚(2004)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[君塚直隆]]|date=2007年(平成19年)|title=ヴィクトリア女王―大英帝国の“戦う女王”|publisher=[[中央公論新社]]|isbn=978-4121019165|ref=君塚(2007)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[リットン・ストレイチー|リットン・ストレイチイ]]|date=1953年(昭和28年)|title=ヴィクトリア女王|series=[[角川文庫]]601|translator=[[小川和夫]]|publisher=[[角川書店]]|asin=B000JB9WHM|ref=ストレイチイ(1953)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[長島伸一]]|date=1989年(平成元年)|title=大英帝国 最盛期イギリスの社会史|series=[[講談社現代新書]]934|publisher=[[講談社]]|isbn=978-4061489349|ref=長島(1989)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[中西輝政]]|date=1997年(平成9年)|title=大英帝国衰亡史|publisher=[[PHP研究所]]|isbn=978-4569554761|ref=中西(1997)}} |
|||
*{{Cite book|和書|date=2001年(平成13年)|title=世界諸国の組織・制度・人事 1840―2000|editor=[[秦郁彦]]編|publisher=[[東京大学出版会]]|isbn=978-4130301220|ref=秦(2001)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[林光一]]|date=1995年(平成7年)|title=イギリス帝国主義とアフリカーナー・ナショナリズム―1867~1948|publisher=[[創成社]]|isbn=978-4794440198|ref=川本(2006)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[クリストファー・ヒバート]]([[:en:Christopher Hibbert|en]])|date=1998年(平成10年)|title=図説 イギリス物語|translator=[[小池滋]]、[[植松靖夫]]|publisher=[[東洋書林]]|isbn=978-4887213012|ref=ヒバート(1998)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[ケネス・ベイカー]]([[:en:Kenneth Baker|en]])|date=1997年(平成9年)|title=英国王室スキャンダル史|translator=[[樋口幸子]]|other=[[森護]](監修)|publisher=[[河出書房新社]]|isbn=978-4309223193|ref=ベイカー(1998)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[前田耕作]]、[[山根聡]]|date=2002年(平成14年)|title=アフガニスタン史|publisher=[[河出書房新社]]|isbn=978-4309223926|ref=前田(2002)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[森護]]|date=1986年(昭和61年)|title=英国王室史話|publisher=[[大修館書店]]|isbn=978-4469240900|ref=森(1986)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[ジャン・モリス]]([[:en:Jan Morris|en]])|date=2006年(平成18年)|title=パックス・ブリタニカーー大英帝国最盛期の群像 上巻|translator=椋田直子|publisher=[[講談社]]|isbn=978-4062132633|ref=モリス(2006)上}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=ジャン・モリス|date=2006年(平成18年)|title=パックス・ブリタニカーー大英帝国最盛期の群像 下巻|translator=椋田直子|publisher=講談社|isbn=978-4062132640|ref=モリス(2006)下}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=ジャン・モリス|date=2008年(平成20年)|title=ヘブンズ・コマンド―大英帝国の興隆 上巻|translator=[[椋田直子]]|publisher=講談社|isbn=978-4062138901|ref=モリス(2008)上}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=ジャン・モリス|date=2008年(平成20年)|title=ヘブンズ・コマンド―大英帝国の興隆 下巻|translator=椋田直子|publisher=講談社|isbn=978-4062138918|ref=モリス(2008)下}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[横井勝彦]]|date=1988年(昭和63年)|title=アジアの海の大英帝国|publisher=[[同文館]]|isbn=9784495852719|ref=横井(1988)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[スタンリー・ワイントラウブ]]([[:en:Stanley Weintraub|en]])|date=2007年(平成19年)|title=ヴィクトリア女王〈上〉|translator=[[平岡緑]]|publisher=[[中央公論新社]]|isbn=978-4120022340|ref=ワイントラウブ(1993)上}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[スタンリー・ワイントラウブ]]([[:en:Stanley Weintraub|en]])|date=2007年(平成19年)|title=ヴィクトリア女王〈下〉|translator=[[平岡緑]]|publisher=[[中央公論新社]]|isbn=978-4120022432|ref=ワイントラウブ(1993)下}} |
|||
*{{Cite book|和書|title=[[世界大百科事典]]|publisher=[[平凡社]]|isbn=978-4582027006|ref=世界大百科事典}} |
|||
== 関連項目 == |
== 関連項目 == |
||
{{commonscat|Victoria of the United Kingdom}} |
{{commonscat|Victoria of the United Kingdom}} |
||
| 163行目: | 825行目: | ||
* [[マリア・テレジア]] |
* [[マリア・テレジア]] |
||
* [[ヨーロッパの祖母]] - [[血友病]] |
* [[ヨーロッパの祖母]] - [[血友病]] |
||
* [[ヴィクトリア (戦艦)]] |
|||
== 外部リンク == |
== 外部リンク == |
||
* [http:// |
* [http://www.vssj.jp/ 日本ヴィクトリア朝文化研究学会] |
||
{{s-start}} |
{{s-start}} |
||
| 172行目: | 834行目: | ||
{{s-ttl|title={{flagicon|GBR}} [[イギリス君主一覧|連合王国女王]]|years=第4代:[[1837年]][[6月20日]] - 1901年1月22日}} |
{{s-ttl|title={{flagicon|GBR}} [[イギリス君主一覧|連合王国女王]]|years=第4代:[[1837年]][[6月20日]] - 1901年1月22日}} |
||
{{s-aft|rows=4|after=[[エドワード7世 (イギリス王)|エドワード7世]]}} |
{{s-aft|rows=4|after=[[エドワード7世 (イギリス王)|エドワード7世]]}} |
||
|- |
|||
{{s-non|rows=2|reason=(創設)}} |
|||
{{s-ttl|title={{flagicon|CAN}} [[カナダ国王|カナダ女王]]|years=初代:1901年[[1月1日]] - 1月22日}} |
|||
|- |
|||
{{s-ttl|title={{flagicon|AUS}} [[オーストラリア国王|オーストラリア女王]]|years=初代:1901年1月1日 - 1月22日}} |
|||
|- |
|- |
||
{{s-bef|before=[[バハードゥル・シャー2世]]<br />([[ムガル帝国]]皇帝)}} |
{{s-bef|before=[[バハードゥル・シャー2世]]<br />([[ムガル帝国]]皇帝)}} |
||
| 184行目: | 841行目: | ||
{{DEFAULTSORT:ういくとりあ}} |
{{DEFAULTSORT:ういくとりあ}} |
||
[[Category:連合王国の君主]] |
[[Category:連合王国の君主]] |
||
[[Category:女性君主]] |
|||
[[Category:ハノーヴァー家]] |
[[Category:ハノーヴァー家]] |
||
[[Category:女性君主]] |
|||
[[Category:インド皇帝]] |
[[Category:インド皇帝]] |
||
[[Category:ロンドン出身の人物]] |
|||
[[Category:1819年生]] |
[[Category:1819年生]] |
||
[[Category:1901年没]] |
[[Category:1901年没]] |
||
2012年5月7日 (月) 19:37時点における版
| ヴィクトリア Victoria | |
|---|---|
| イギリス女王 | |
 1887年 | |
| 在位 | 1837年6月20日[1] - 1901年1月22日[1] |
| 戴冠式 | 1838年6月28日[1]、於ウェストミンスター寺院[2] |
| 別号 | インド女帝 |
| 全名 |
アレクサンドリナ・ヴィクトリア 英語: Alexandrina Victoria |
| 出生 |
1819年5月24日 |
| 死去 |
1901年1月22日(81歳没) |
| 埋葬 |
1901年2月2日 ウィンザー フロッグモア |
| 配偶者 | アルバート・オブ・サクス=コバーグ・アンド・ゴータ |
| 子女 | 一覧参照 |
| 家名 | ハノーヴァー家 |
| 王朝 | ハノーヴァー朝 |
| 父親 | ケント公爵エドワード・オーガスタス |
| 母親 | ヴィクトリア・オブ・サクス=コバーグ=ザールフィールド |
| 宗教 | イギリス国教会 |
| サイン |
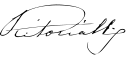 |
ヴィクトリア(英語: Victoria、1819年5月24日 - 1901年1月22日)は、イギリス・ハノーヴァー朝の第6代女王(在位:1837年6月20日 - 1901年1月22日)、初代インド女帝(在位:1877年1月1日 - 1901年1月22日)。世界各地を植民地化・半植民地化して繁栄を極めた大英帝国を象徴する女王として知られ、その治世はヴィクトリア朝と呼ばれる。在位は63年7か月にも及び、歴代イギリス国王の中でも最長である[# 1]。
概要
イギリス・ハノーヴァー朝第3代国王ジョージ3世の第四王子であるケント公エドワードの一人娘。3人の伯父たちが嫡出子を残さなかったため、1837年に18歳でハノーヴァー朝第6代女王に即位する。
ハノーヴァー朝の国王は代々ドイツのハノーファー王国(選帝侯国)の君主を兼ねていたが、ハノーファーではサリカ法典による継承法を取っており、女性の統治が認められていない。そのためヴィクトリアはハノーファー王位を継承せず、叔父エルンスト・アウグストがその地位を継ぎ、イギリスとハノーファーの同君連合は解消された[4]。
はじめホイッグ党の首相メルバーン子爵を偏愛したが、1840年に母方の従姉弟にあたるザクセン=コーブルク=ゴータ公国公子アルバートと結婚すると彼の忠告に従って王権の中立化に努めるようになった。その後もしばしば政治に影響力を行使しながらも基本的に議会の状況に基づいて首相を選ぶようになった。国王の政治的影響力の面ではアルバートがヴィクトリアに代わって重きをなすようになっていったが、彼はその権威が絶対的になる前の1861年に薨去した。これによりイギリスに立憲君主制の道が開かれることとなった。
一方悲しみにくれるヴィクトリアはその後10年以上にわたって喪服し、公務に姿を見せなくなったが、1870年代に保守党の首相ベンジャミン・ディズレーリに励まされて公務に復帰し、彼の帝国主義政策を全面的に支援し、大英帝国の最盛期を築き上げた。1876年には「インド女帝」に即位した。ディズレーリを偏愛する一方、ディズレーリと並んでヴィクトリア朝を代表する自由党首相ウィリアム・グラッドストンのことは一貫して嫌っていた。彼のアイルランド自治法案の阻止に全力を挙げた。晩年には老衰で政治的な活動は少なくなり、立憲君主化が一層進展した。
1901年に崩御し、王位は長男であるエドワード7世に受け継がれた。
彼女の63年7か月の治世はヴィクトリア朝と呼ばれ、政治・経済のみならず、文化・技術面でも優れた成果を上げた。この時代の物は政治であれ、外交であれ、軍事であれ、文学であれ、科学であれ、家具であれ「ヴィクトリア朝の~」という形容をされることが多い[5]。
この時代、イギリスは世界各地を植民地化して一大植民地帝国を築き上げた。その名残で ヴィクトリア湖(ケニア、ウガンダ、タンザニア)、ヴィクトリア滝(ジンバブエ・ザンビア)、ヴィクトリア・ハーバー(香港)、ヴィクトリア・パーク(世界各地)など、女王の名に因んだ命名も少なくない。
子女が欧州各国の王室・皇室と婚姻を結んだ結果、ヨーロッパの祖母と呼ばれるに至った[6]。ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世とロシア皇后アレクサンドラ(ロシア皇帝ニコライ2世妃)は孫にあたる[7]。
生涯
生誕
ヴィクトリアは1819年5月24日午後4時15分頃にロンドンのケンジントン宮殿で生まれた[8]
父はケント公爵エドワード(ハノーヴァー朝第3代英国王ジョージ3世の四男)。母はその妃ヴィクトリア(ザクセン=コーブルク=ザールフェルト公国の公フランツの娘)[# 2]。
父ケント公は借金まみれであり、物価の高いイギリスでは暮らしていけないと言って、ベルギーやドイツ内を転々として暮らしていたが、妃の出産が近くなると、生まれてくる子を「ロンドン出生」にするため流産の危険を冒してでも一時帰国し[10][11][12][# 3]、ケンジントン宮殿を兄の摂政皇太子ジョージ(後の英国王ジョージ4世)から借り受けていた[14]。
生誕時の王位継承における立場
ハノーヴァー王家はドイツの邦国ハノーファー王国の君主の家柄であるが、旧イギリス王家ステュアート家と縁戚関係があり、その関係でステュアート家が絶えた後、ハノーファー王が同君連合でイギリス王位も継承した。ハノーファー王室はサリカ法の適用を受けるため、女子の王位継承が認められていないが、イギリス王室にはサリカ法の適用がないため、女子にも継承権があった[15]。イギリス王位継承はコモン・ローに基づいて定められており、王の最年長の男子が継承するのが基本だが、男子がなく女子のみある場合には最年長の女子が王位を継承する[15][16]。
生誕時のヴィクトリアのイギリス王位継承順位は3人の伯父、摂政皇太子ジョージ、ヨーク公フレデリック、クラレンス公ウィリアム(後の英国王ウィリアム4世)と父ケント公に次ぐ第5位であった[17]。
かつて摂政皇太子ジョージにはシャーロットという嫡出子がおり、いずれ彼女が王位を継ぐものと目されていたが、1817年11月6日に身ごもった子供を死産させた際に薨去したため次々世代の王位継承者が消滅した[18][19]。というのもこの1817年の時点ではジョージ3世の王子らは摂政皇太子を除いて誰も嫡出子を持っていなかったからである[19]。
これに焦った摂政皇太子と議会は結婚していない王子たちに資金援助をちらつかせて、しかるべき君主家の娘を正妃に迎えて嫡出子作りを促した。借金まみれのケント公もそれが目当てでドイツの小邦国の君主の娘と結婚してヴィクトリアを儲けたのであった。ヴィクトリアが生まれる二か月ほど前に伯父クラレンス公にも嫡出子シャルロッテが生まれていたが、その子は出生後すぐに薨去したため、ヴィクトリア誕生の時点ではヴィクトリアが次々世代の王位継承最有力候補者であった[20]。とはいえクラレンス公妃はまだ十分に子を産めそうであり、またヴィクトリアの母ケント公妃もまだ子が産めそうであったため、これから弟が生まれる可能性もあり、そうした場合には第四王子の女子に過ぎないヴィクトリアの王位継承は一気に遠のくという不安定な立場であった[21]。
| イギリス王 ハノーファー王 ジョージ3世 | 王妃 シャーロット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摂政皇太子 ジョージ 1位(1位) | ヨーク公 フレデリック 2位(2位) | クラレンス公 ウィリアム 3位(3位) | ケント公 エドワード 4位(4位) | カンバーランド公 アーネスト 6位(5位) | サセックス公 オーガスタス 7位(6位) | ケンブリッジ公 アドルファス 8位(7位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャーロット | シャルロッテ | ヴィクトリア 5位(-) | ジョージ 9位(8位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗礼式の命名をめぐる騒動
6月24日に行われたヴィクトリアの洗礼式において代父となったのは、摂政皇太子ジョージ、ロシア皇帝アレクサンドル1世(イギリス訪問中で、ジョージとも仲が良かった)。代母は、ケント公爵夫人ヴィクトリアの実母アウグスタ、ヴュルテンベルク公妃シャルロット(伯母)だった。
ケント公は娘に「ジョージアナ(ジョージの女性名)」や「エリザベス」といった将来の英国女王としてふさわしい名前を付けたがっていたが[20][21]、ケント公と仲の悪い摂政皇太子ジョージは命名権は自分にあると主張して譲らなかった[22]。摂政皇太子はできればクラレンス公夫妻に再び嫡出子を作らせて、その子に王位を継がせたかった[23]。
洗礼式当日にカンタベリー大主教が「何という名で祝福するか」王族たちに尋ねると摂政皇太子は「アレクサンドリナ」(ロシア皇帝の名前アレクサンドルの女性名)と答えた[20][21][12]。それに対してケント公はミドルネームに「エリザベス」を加えるよう訴えたが、摂政皇太子は拒否し、母と同じ「ヴィクトリア」をミドルネームとさせた[17]。
こうして彼女の名前は「アレクサンドリナ・ヴィクトリア」というイギリス人になじみが薄いロシア名とドイツ名になった(ヴィクトリアの名がイギリスの一般的な名前になるのは彼女が女王に即位した後のことである)[20]。王女時代にはアレクサンドリナという名から「ドリナ」と愛称された[20][17]。
ジョージ4世治世下の幼女時代

1820年1月23日、ヴィクトリアが生後8ヶ月のとき、父ケント公が薨去した[24][25][26]。時期同じくして1月29日には国王ジョージ3世が崩御し、摂政皇太子ジョージがジョージ4世としてハノーヴァー朝第4代国王に即位した[24][27]。
夫が残した莫大な借金を背負わされた母ケント公妃はヴィクトリアを連れて英国を離れることも考えたが、兄レオポルド(亡きシャーロットの夫で1831年にベルギー王に即位するまで英国に滞在し続けていた)から資金援助を受け、ジョージ4世からそのまま住むことを認められていたケンジントン宮殿に留まることにした[28][29]。
1820年12月にはクラレンス公が娘エリザベスを儲けたため、ヴィクトリアの王位継承は一時遠のいた[20][30]。しかしこのエリザベスは1821年春に生後4カ月で薨去したため、再びヴィクトリアの王位継承の可能性が高まった[31][25][32]。
ヴィクトリアはケンジントン宮殿で母ケント公妃に大事に育てられた。ヴィクトリアは何歳になっても個室を与えられず、母と同じ寝室で寝起きして母の監視を受けた[33][34]。母はケント公爵家家令サー・ジョン・コンロイの影響を強く受けており[35]、ヴィクトリアもコンロイの娘ヴィクトワールとよく一緒に遊んだ[36]。
母はドイツ語を母語としていたので、ヴィクトリアも3歳までドイツ語のみを話す生活を送った。幼児期に英語とフランス語の学習を始め、やがて三ヶ国語を自由に話せるようになった。後にはイタリア語とラテン語も少し使えるようになった[33]。ヴィクトリアは5歳まで反抗してアルファベットの勉強をしようとしなかったというが、5歳の頃イギリスと同君連合のハノーファー王国出身のルイーゼ・レーツェンがガヴァネスに付くと反抗も落ち着いてきて勉強をするようになったという[37]。このレーツェンはヴィクトリアに非常に大きな影響を与えた[38]。
6歳の頃には自らの高貴な身分を自覚していたといい、臣民の友人が身分をわきまえずに自分のおもちゃに触ろうとしたり、自分の名前を呼び捨てにするとたしなめるようになったという[36][39]。
国王ジョージ4世は相変わらずケント公妃を嫌っていたが、同時にこの頃にはヴィクトリアの王位継承は避けられないと考えるようにもなっていた。1825年にケント公爵家の年金が6000ポンド増額され、1826年にヴィクトリアは7歳にしてガーター勲章を与えられ、以降国王は頻繁に彼女を引見するようになった[40]。国王の釣り船に乗せてもらった際に国王が軍楽隊に何を弾かせるかヴィクトリアに尋ねると彼女は『神よ、国王陛下を守りたまえ』をリクエストしたという[41]。
ウィリアム4世治世下の少女時代

1830年6月26日、国王ジョージ4世が子のないまま崩御した。国王の次弟ヨーク公はすでになく、三弟クラレンス公ウィリアムがウィリアム4世としてハノーヴァー朝第5代国王に即位した[42]。ウィリアム4世は即位時すでに65歳であり、新しい嫡出子を儲けることはほとんど諦めており、ヴィクトリアに王位継承の期待を寄せるようになっていた[25]。ただ彼はヴィクトリアの母であるケント公妃のことを非常に嫌っていた[43]。
ウィリアム4世即位にあたってヴィクトリアは議会から「暫定王位継承者」に認定され[25][41]、彼女の帝王教育も強化された[42]。乗馬や舞踏、絵画、音楽など上流階級のたしなみを身に付けていった。とりわけスケッチが好きであり、彼女は生涯にわたって絵を描き続けた。歴代英国首相やフランス皇帝ナポレオン3世を描いたヴィクトリアの絵が現代のロイヤル・コレクションの中にも残っている[42]。
「暫定王位継承者」になったとはいえヴィクトリアはいまだ自らが王位継承者であることを教えられていなかった。この年ヴィクトリアは11歳であったが、母ケント公妃はカンタベリー大主教ら聖職者たちの助言に従ってヴィクトリアに女王となる定めであることを告げることを決心した。歴史の授業の際に保母が英国王室系譜表を本の中に隠しておき、それをヴィクトリアに発見させ、いかなる立場にあるのか説明させたという。それを聞いたヴィクトリアはしばらく口をつぐんでいたが、やがて「良い人になるようにしますわ」と述べたという。そしてその後一人で大泣きしたという[44]。
この頃、トーリー党(保守党)の政権が崩壊し、ホイッグ党(自由党)が政権を掌握して政府が自由主義的な色彩を持つようになった[41]。亡き父ケント公は兄との対立からホイッグ党に肩入れしており、ケント公妃も夫に従って同じ党派に属していた[45]。そのためヴィクトリアは保守的な叔父カンバーランド公アーネストと対比される形で自由主義者の期待を一身に受けていた[46]。一方国王ウィリアム4世はホイッグ党の大臣たちと対立を深めていき、その黒幕と看做したケント公妃をより憎むようになった[47]。
ヴィクトリアが暫定王位継承者になると母ケント公妃はしばしば摂政同然にふるまうようになった。帝王教育の一環でヴィクトリアはケント公妃に連れられてイギリス各地を旅行するようになったが、ヴィクトリアを差し置いてケント公妃の摂政然とした態度が目立ったという[48]。ソレント海峡の旅行ではケント公妃は海峡沿岸の砲台や軍艦に王礼砲を行う事を要求したが、これに国王は激怒し、王と王妃以外への礼砲を禁じる緊急勅令を下している[49][48]。
また国王はケント公妃が実家ザクセン=コーブルク家の公子たちをやたらとヴィクトリアに引き会わせようとすることに苛立ち、その阻止に全力を尽くした[43][47]。またケント公妃の兄であるベルギー王レオポルドが頻繁にヴィクトリアに手紙を送ってくることも気にくわなかった。国王にはザクセン=コーブルク家をあげてイギリス王室を乗っ取ろうとしているように思えた[50]。
1837年5月24日にヴィクトリアは18歳になり、成人した。国王はお祝いとして彼女の年金を1万ポンド増額させるとともに新宮殿を与えるので母親から独立してはどうかと勧めたが、ケント公妃の反対によりヴィクトリアは辞退した[51]。
-
伯父である国王ウィリアム4世。ヴィクトリアをケント公妃から引き離したがっていた。
-
1830年のスケッチをするヴィクトリアを描いた絵画(リチャード・ウェスタール画)
-
1832年のヴィクトリアを描いた絵画(ロイヤル・コレクションの絵画)
-
1833年のヴィクトリアを描いた絵画(ジョージ・ハイター画)
英国女王に即位

1837年6月20日午前2時20分にウィリアム4世はウィンザー城で崩御した。これによりヴィクトリアが18歳にしてハノーヴァー朝第6代女王に即位した[# 4]。
宮内長官カニンガム卿とカンタベリー大主教ウィリアム・ハウリは新女王に即位の報告をするためロンドン・ケンジントン宮殿へと向かった。ヴィクトリアは午前6時に母ケント公妃に起こされ、カニンガム卿とカンタベリー大主教を引見した。カニンガム卿は彼女に国王崩御を報告し、その場に跪いて新女王の手に口づけした[52]。
ついで午前9時と午前11時に首相であるメルバーン子爵がケンジントン宮殿を訪問してヴィクトリアの引見を受け、彼女の手に口づけした[53]。ヴィクトリアは彼に引き続き国政を任せると述べた[54]。
午前11時半よりケンジントン宮殿内の赤の大広間において最初の枢密院会議を開いた。出席した枢密顧問官たちは新女王の優雅な物腰、毅然とした態度、堂々たる勅語に感服したという[55][56][57]。ウェリントン公爵はその光景を「彼女はその肉体で自らの椅子を満たし、その精神で部屋全体を満たしていた」と表した[58]。またジョン・ラッセル卿は「ヴィクトリア女王の治世は後代まで、また世界万国に対して不滅の光を放つであろう」と予言した[59]。
イギリスではピューリタン革命や名誉革命、またハノーヴァー朝初代国王ジョージ1世(ハノーファー選帝侯ゲオルク1世)がハノーファーばかりに関心を持ち、イギリスにほとんど関心を示さなかったことなどにより、他国の君主に比べると君主権がやや弱く、内閣や議会の力が強い傾向があった。とはいえ19世紀半ばのイギリス王はいまだ巨大な国王大権を有しており、いざという時には強権発動が可能であった。大臣の任免、議会の招集・解散、国教会の聖職者と判事の任免、宣戦布告などは国王の大権であった。前王ウィリアム4世も自分と対立した首相をクビにしている。彼女が受け継いだ王位とはそうした巨大な権力であった[60]。
ヴィクトリアは即位の日の日記に「私が王位につくのが神の思し召しなら私は全力を挙げて国に対する義務を果たすだろう。私は若いし、多くの点で未経験者である。だが正しいことをしようという善意・欲望においては誰にも負けないと信じている。」と抱負を書いている[54]。
即位の日に行った引見はいずれも母の同席なしで行った。この日以来彼女は家族絡みの会見以外はすべて一人で行うようになった[52]。母もヴィクトリアとともにケンジントン宮殿からバッキンガム宮殿へ移っているが、ヴィクトリアは母が自分に干渉してこないよう、母の部屋を自分の部屋から遠ざけた[61][62]。家令サー・ジョン・コンロイに至っては今後の目通りは一切叶わない旨を通達している[61]。一方レーツェンは自分の部屋の隣に留め置いて相談役として重用した[63]。また伯父ベルギー王レオポルドの側近であるコーブルク家臣クリスティアン・フリードリヒ・フォン・シュトックマー男爵がレオポルドとの連絡役としてバッキンガム宮殿に勤務するようになり、ヴィクトリアの新たな助言役となっていった[64]。しかしベルギーに肩入れするよう求めるレオポルドの要請に対してはヴィクトリアは慎重に回避し続けた[65]。
女王として年金38万5000ポンド、ランカスター公としてランカスター公領からの収入2万7000ポンドを受けるようになり、そのお金で父親が残した巨額の借金を返済し、何不自由ない生活を送るようになった[66]。
翌6月21日にセント・ジェームズ宮殿で君主宣言の儀を行い、勅命によって王名を「ヴィクトリア」と定め、以降「アレクサンドリナ」は使用されなくなった[52][67]。
戴冠式は即位後1年後の1938年6月28日にロンドン・ウェストミンスター寺院において挙行した。ウェストミンスター寺院までの道すがら、「女王陛下万歳」を叫ぶ群衆たちの中を黄金馬車で通過した。ヴィクトリアはその日の日記に「このような国民たちの女王となることをいかに誇りに思うことか」と書いている[2]。
-
新女王の御前に跪いてその手に口づけする宮内長官カニンガム卿とカンタベリー大主教ウィリアム・ハウリ。
-
即位当日、最初の枢密院会議を開くヴィクトリア女王を描いたデヴィッド・ヴィルキーの絵画。ヴィクトリアが純白の服を着ているが、これは彼女を目立たせるためであり、実際には黒い喪服を着ていた[68]。
-
ウェストミンスター寺院でのヴィクトリア女王の戴冠式を描いたジョン・マーティンの絵画
-
戴冠式。カンタベリー大主教から聖油を注がれるヴィクトリアを描いた絵画。
内政
メルバーン子爵を寵愛

首相メルバーン子爵は保守主義者であったが、機会主義者でもあったのでホイッグ党に所属し、本心では反対だったにもかかわらず選挙法改正などの改革を押し進めた[69]。彼は前王ウィリアム4世との関係は悪かったが、シュトックマー男爵がメルバーン子爵の良い評判をヴィクトリアに聞かせていたため、ヴィクトリアからは早々に気に入られることとなった[70][71][72]。
国王秘書官の職が廃され、メルバーン子爵がこれを兼務し、彼は首相であると同時に女王の第一の側近となった[73]。メルバーン子爵は洗練されたマナーと話術の持ち主でヴィクトリアを魅了して止まなかった[74]。二人は君臣の関係を越えて、まるで父娘のような関係になっていった[70]。女王の日記には毎日のように「メルバーン卿」「M卿」の名前が登場するようになる[70][75]。
しかし1839年にホイッグ党の右派が離党してトーリー党に合流し、また左派もメルバーン批判を強めた結果、メルバーンは議会において苦しい立場に立たされた[76]。1839年5月初めに英領ジャマイカの奴隷制度廃止法案をめぐってトーリー党と現地の農場主から攻撃を受けたメルバーンは5月7日にヴィクトリアに辞表を提出した[77]。ヴィクトリアの衝撃は大きく、泣き崩れたという[78][79]。
トーリー党の指導者である貴族院議長ウェリントン公爵を召し、ウェリントン公爵の勧めに従ってロバート・ピールに首相の大命降下を下した[80][78][81]。この際にヴィクトリアはウェリントン公爵やピールに対して今後もメルバーン卿に諮問して良いかと下問した[80]。ウェリントン公爵はこれを承諾しているが、ピールは拒絶した。枢密院や議会においてではなく、宮中で野党党首が個人的に女王の側近になるなど前代未聞のことであった[82]。
これがきっかけでヴィクトリアはピールに嫌悪感を持つようになり、ピールが宮中の女官(ほとんどがホイッグ党の政治家の家族)をトーリー党の者に刷新する案をヴィクトリアに献策した際にヴィクトリアは「一人たりとも辞めさせない」と言って頑強に退けた[6][83][84]。結局ピールはこのために首相職を辞退し、メルバーンが首相に戻ることとなった(寝室女官事件[83]。
ヴィクトリアは女官の人事は女王の私的人事であることを強調したが、政権交代のたびに宮廷内の役人も入れ替わるのが慣例であった[82][84][85]。マスコミはヴィクトリアのきまぐれが立憲政治の確立を妨げていると批判し、彼女を諌める夫が必要だという議論を加速させた[86]。ヴィクトリア本人は後年に寝室女官事件について「あの頃の私は非常に若かった。あの一件を今やり直せるとしたら、私は違った行動を取るだろう。」と語っている[86][6]。
アルバート公子との結婚と「共同統治」

ザクセン=コーブルク=ゴータ公エルンスト1世(母ケント公妃の兄)の次男であるアルベルト(英語名アルバート)がヴィクトリアの婿の最有力候補だった。この二人の結婚はエルンスト1世、母ケント公妃、ベルギー王レオポルドとザクセン=コーブルク家をあげて推進していた[6][87]。
ヴィクトリアは1836年にアルバートと会ったことがあり、その時の日記の中でアルバートを「目は綺麗な碧眼、美しい鼻と口。顔の魅力はその表情によってうっとりする。同時に善良さと甘美さと知的さを持っている」と絶賛していた[88][89]。
もっとも1839年4月にヴィクトリアはメルバーン子爵に対して「私は当面いかなる結婚もしたくない」と語っている[90]。アルバートのことは嫌いではなかったが、周囲が勝手にアルバートとのお見合いを進めているのが気に入らなかったという[91]。だが結局周囲に流される形で1839年10月10日にウィンザーを訪れたアルバートを引見することになった。この頃アルバートは一層美男になっており、ヴィクトリアはすっかり彼に一目ぼれした。引見の翌日に彼女はメルバーン子爵に対して「結婚に対する意見を変えた」と述べ、さらに翌々日には「アルバートと結婚する意志を固めた」と述べた[92]。
後日再びアルバートを召し、君主である彼女の方からプロポーズを行った。「貴方が私の(結婚の)望みを叶えてくれたらどんなに幸せでしょう」と言ってプロポーズしたという[93][92]。
ヴィクトリアとアルバートは1840年2月10日にロンドンのセント・ジェームズ宮殿で結婚式を挙行した[94]。その翌日のベルギー王レオポルドへの手紙でヴィクトリアは「世界で私ほど幸せな人間はいないと思います。彼は天使のようです。昨日の披露宴は楽しくて熱気にあふれていました。ロンドン市内では群衆が果てしなく沿道に続いていました」と書いている[6]。
ヴィクトリアのハードスケジュールのため、新婚旅行はウィンザーまでのわずか42キロで済まされた。アルバートがそれについて不満を述べるとヴィクトリアは「貴方は私が君主であることをお忘れなのね。今は議会の会期中であり、私が行わねばならない執務も山のようにあります。ほんの2、3日であっても私がロンドンを離れることは許されないのです」と反論したという[95][96][97]。

1840年6月、ヴィクトリアとアルバートが馬車でコンスティテューション・ヒルを通過中、見物人の一人が女王に向けて発砲する事件が発生した。一発目は外れ、続けて二発目が撃たれる直前にアルバートはヴィクトリアを馬車のなかに引き倒して彼女を守った[98]。アルバートの行動は新聞に称賛され、ヴィクトリアとアルバートが行くところ国民の万歳の声があがるようになった[98]。
しかし貴族社会や社交界からはアルバートは「外国人」として疎まれていた[99]。ヴィクトリアも結婚初期にはアルバートが公文書を見ることを許可しなかったが[100]、1840年11月に生まれた長女ヴィクトリア(愛称ヴィッキー)、1841年11月に生まれた長男アルバート・エドワード(愛称バーティ)を筆頭に1840年代にヴィクトリアが出産を繰り返したため、アルバートが補佐役を務める必要性が増した[101]。
1842年頃からヴィクトリアは公文書作成にあたってアルバートの助力を得るようになり、また大臣引見の際にもアルバートを同席させるようになった。これ以降イギリスはヴィクトリアとアルバートの共同統治に近い状態と化した[100][96]。アルバートはメルバーン子爵やホイッグ党に肩入れするヴィクトリアに対して「君主は党派争いを超越した存在にならなければならない」と諌め、王権の中立化に努めた[102][# 5]。
アルバートは宮中での自身の影響力の増大にも努めた。1842年にはヴィクトリアの幼い頃からの側近であるレーツェンを宮廷から去らせた[105]。さらに1844年にはピール首相の反対を押し切って二大政党の綱引きで雁字搦めになっていた王室管理機構の改革にあたり、宮内長官、家政長官、主馬頭の分掌体制を王室家政長官の下に一元化した[106]。
-
1840年2月10日のヴィクトリアとアルバートの結婚式を描いたジョージ・ハイターの絵画
-
ウィンザー城のアルバート公子とヴィクトリア女王を描いたエドウィン・ランドシーアの絵画
ピールの改革支援
1841年8月末にメルバーン子爵が首相を辞職し、いよいよピールを首相に任命せねばならなくなった。ヴィクトリアはこの時点でもピールを首相にする事を渋っていたが、アルバートが彼女を説得し、ピールに首相の大命降下を与えた[107]。
ヴィクトリアは過去の経緯やそのそわそわした態度からピールを嫌っていた。ピールの方も宮殿に居心地の悪さを感じて長時間宮殿に滞在しようとはせず、ヴィクトリアと疎遠になった。しかしアルバートは宮廷策謀より首相の職務に全力を挙げているとしてピールの態度を高く評価した[108]。首相ピールはアルバートの支持のもと関税の大幅減税、所得税導入などの改革を推進した[109]。やがてヴィクトリアもアルバートとともにピールに全幅の信頼を寄せるようになった[110]。保守党内部にはピールの改革に反発もあったが、アルバートとヴィクトリアがピールを支持した事により、ピールは長らく抵抗勢力を押し込むことができた[109]。
ピール首相がミッドランド地方(en)の紡績工場主だった関係でヴィクトリアは外国との過当競争や需要低下に苦しむ織物産業に関心を持つようになり、イングランド織物の宣伝のために1842年5月12日に14世紀の絹織工業をテーマにした「プランタジネット舞踏会」を開催した。アルバートはエドワード3世、ヴィクトリアはフィリッパ王妃の仮装をした。しかしこの舞踏会はエドワード3世を侵略者として憎むフランス人の反発を買って英仏関係をギクシャクさせたばかりか、イギリスのマスコミからも失業者が飢えている時に何をやっているのか、という強い批判に晒され、ヴィクトリア夫妻にとってあまり思い出したくない黒歴史になった[111]。
-
1842年5月12日のプランタジネット舞踏会におけるヴィクトリアとアルバートを描いたエドウィン・ランドシーアの絵画
-
首相サー・ロバート・ピール。
じゃがいも飢饉と保守党の分裂

1845年夏にアイルランドでジャガイモ飢饉が発生した。これによりアイルランドでは100万人が餓死もしくは栄養失調で病死した[112][113]。さらに100万人が新天地アメリカやカナダへ移民することを余儀なくされた[112][114]。1841年時に800万人だったアイルランド人口が1851年には650万人に減るという惨状だった[113]。
ヴィクトリアはライオネル・デ・ロスチャイルドが主宰する「アイルランドとスコットランドの貧民のための英国救貧協会」に2000ポンドの寄付をしている[115]。これは同協会に寄せられた寄付金額の第一位であり、第二位のロスチャイルドとデヴォンシャー公爵の寄付金額1000ポンドを大きく引き離す額だった[115]。
じゃがいも飢饉の深刻さを受け止めたピール首相はアイルランド人が安い価格の輸入穀物を購入できるよう、保護貿易主義の穀物法を廃止する決意をした。ヴィクトリア夫妻も貧しい民衆もそれを支持した[116]。しかし地主貴族など保守党内の抵抗勢力が穀物の自由貿易に強く反発したため、ピールは穀物法廃止法案と刺し違える形で1846年6月に辞職を余儀なくされた[117]。
この騒ぎで保守党はピールを筆頭とする自由貿易派とダービー伯爵を筆頭とする保護貿易派に分裂し、ピール派が自由党(ホイッグ党)と連携したことで自由党が議会の多数派になり、自由党党首であるジョン・ラッセル卿が首相の大命降下を受けることになった[118][119]。ヴィクトリアはラッセル卿の内閣で外相になったパーマストン子爵が親仏外交でアイルランド貧困問題を無視するようになるのではと心配していた[120]。
チャーティズム運動

ヴィクトリア女王夫妻、メルバーン子爵、ピールらによる自由主義的な改革は裕福なブルジョワには歓迎されたが、貧しい労働者階級には期待はずれであり、社会改革を求めるチャーティズム運動が高まった[121]。
1848年には大陸で1848年革命が発生し、イギリスでもチャーティズム運動が勢いを増した。「共和制万歳」を叫ぶ者たちがバッキンガム宮殿の外のランプを破壊する騒ぎがあり、ヴィクトリアは恐怖のあまり泣き出してしまったという。身の危険を感じたヴィクトリアら王族はワイト島のオズボーン・ハウスへ一時的に避難した[122][123]。
しかし比較的自由主義的な政府があり、不十分とはいえ一定の改革を行ったイギリスでは絶対主義的な君主国家ばかりの大陸ほど革命は燃え広がらず、やがてチャーティズム運動も下火になっていった[124][122]。ヴィクトリアは「労働者たちはプロの扇動家、犯罪者、クズどもに扇動されただけで王室への従順さを失っていなかった」と述べて胸をなでおろした[125]。
ロンドン万博
1851年の第1回ロンドン万国博覧会の準備はアルバートが取り仕切った[126]。ロンドン万博の会場としてハイド・パークにデヴォンシャー公爵所有の豪邸チャッツワース・ハウスの温室をモデルにデザインされた全面ガラス張りの巨大な水晶宮(クリスタル・パレス)が建設された[127][104]。
開会宣言はヴィクトリアが行った。女王暗殺を警戒して開会宣言を内輪で行うべきとの意見もあったが、最終的にはヴィクトリア自身が公開して行うと決めた[128]。水晶宮には世界各地から集められた10万点の展示物が飾られた[104]。ヴィクトリアは万博開催中の数ヶ月間、気分が高揚してロンドン万博以外のことはほとんど頭になくなっていた[129]。万博のすべてを見学しようと1週間に数回という頻度で水晶宮を訪れている[130]。
ロンドン万博は140日の期間中にのべ600万人も訪れたという。これは当時のイギリス人の人口の3分の1に相当する[131][132]。収益も相当な額に上り、その収益と議会の創設した基金とでケンジントン地区再開発を行い、エクサビション・ロードやクロムウェル・ロード、クイーンズ・ゲートなどの道路が整備された(道路の名前は全てアルバートが命名した)[104]。さらに1850年代にも万博実行委員会所有の土地を使ってロイヤル・アルバート・ホール、ヴィクトリア&アルバート博物館、ロンドン自然史博物館、サイエンス・ミュージアムなどを続々と創設した[104]。
ヴィクトリアは1851年7月18日付けの日記に「我が愛する夫と我が国の功績に対して寄せられた平和の祈りと親善が大勝利を収めた」と書いている[130]。
政党政治の混迷の後二大政党が確立
| 名前 | 首相就任日 |
|---|---|
| メルバーン子爵(自由党) | 1835年4月18日 |
| ロバート・ピール(保守党) | 1841年8月30日 |
| ラッセル伯爵(自由党) | 1846年7月6日 |
| ダービー伯爵(保守党) | 1852年2月23日 |
| アバディーン伯爵(ピール派) | 1852年12月28日 |
| パーマストン子爵(自由党) | 1855年2月8日 |
| ダービー伯爵(保守党) | 1858年2月25日 |
| パーマストン子爵(自由党) | 1859年6月12日 |
| ラッセル伯爵(自由党) | 1865年10月30日 |
| ダービー伯爵(保守党) | 1866年7月6日 |
| ディズレーリ(保守党) | 1868年2月27日 |
| グラッドストン(自由党) | 1868年12月9日 |
| ディズレーリ(保守党) | 1874年2月20日 |
| グラッドストン(自由党) | 1880年4月28日 |
| ソールズベリー侯爵(保守党) | 1885年6月24日 |
| グラッドストン(自由党) | 1886年2月3日 |
| ソールズベリー侯爵(保守党) | 1886年8月3日 |
| グラッドストン(自由党) | 1892年8月16日 |
| ローズベリー伯爵(自由党) | 1894年3月6日 |
| ソールズベリー侯爵(保守党) | 1895年6月28日 |
ジョン・ラッセルは1851年2月に労働者階級に選挙権を拡大する更なる選挙法改正法案を議会に提出したが、下院の反対で退けられた。この件でラッセルはヴィクトリアに辞表を提出した。ヴィクトリアは自由党に次ぐ勢力である保守党保護貿易派の指導者ダービー伯爵に首相の大命降下をくだしたが、保守党の議席は過半数に程遠く、また実務経験のある政治家が党分裂でほとんどピール派に移っていたこともあってダービー伯爵はこれを拝辞し、自由党とピール派に政権を担当させるようヴィクトリアに具申した。ヴィクトリアはその通りにしようとしたが、この二勢力には自由貿易しか共通点がなく、カトリック規制など他の問題で様々な対立を抱えていたため、連立政権を作れなかった[133]。ヴィクトリアはランズダウン侯爵やウェリントン公爵など元老たちにどう対処すべきか諮問し、結果ラッセルを首相に戻すこととした[134]。迷走ぶりを露わにした政党政治の力は減退し、王権の担い手たるアルバート公子の存在感は一層増していった[134]。
1852年2月にヴィクトリアは伯父であるベルギー王レオポルドに宛てて「アルバートは日増しに政治が好きになっていますが、彼の洞察力や勇気はそうした仕事には非常に向いています。一方私は日増しに仕事が嫌になっています。私たち女性は「統治」するようには創られていません。善良な女性であるなら、そのような仕事は好きにはなれないのです。」と書いている[135]。
1850年代を通じて政党政治の混迷は続き、5回も政権交代があった(1852年2月に保守党のダービー伯爵、1852年12月にピール派のアバディーン伯爵、1855年2月のホイッグ党のパーマストン子爵、1858年2月のダービー伯爵再任、1859年6月にパーマストン子爵再任)[136][137]。
1859年6月にホイッグ党、ピール派、急進派の三派が合同して自由党を結成したことで二大政党制への道が開かれ、政党政治が安定化するようになった。自由党は早速議会に内閣不信任案を可決させ、保守党のダービー伯爵を辞職させ、パーマストン子爵を首相とする自由党長期政権を樹立した。こうして1860年代以降には1850年代のようにヴィクトリアが長老政治家に諮問して首相を選定するようなことも減っていった[138]。
アルバート薨去

アルバートは1857年に議会から王配殿下(Prince Consort)の称号を受けていたが[139]、1850年代後半から徐々に健康を害するようになっていた[140]。若い頃には美男だった外見もいつしか髪が薄くなり、引き締まっていた身体もすっかり肥満していた[140]。
ヴィクトリアによると夫妻が溺愛していた自慢の長女ヴィッキーが1858年にプロイセン王子フリードリヒに嫁いでからアルバートの元気がなくなったという[140]。夫妻が愚鈍と評価していた皇太子バーティの不良行為や問題行動にもアルバートは随分頭を悩まされ、胃痛がひどくなり、リューマチも患うようになった[141]。
1861年11月22日にアルバートはヴィクトリアが止めるのも聞かず、豪雨の中サンドハースト王立陸軍士官学校の新校舎竣工式に出席し、続けてケンブリッジ大学で校則破りを繰り返す皇太子に説教するためにケンブリッジを訪問し、体調を悪化させた[142][143]。12月に入ると食事もほとんど取れないほどに衰弱した[144]。そうした中でもアルバートは最期の力を振り絞ってトレント号事件をめぐってのパーマストン子爵の対米強硬姿勢を穏健化させて英米戦争を回避することに尽力した[145][146]。
侍従医は特に気になる症状はないとしており、ヴィクトリアは侍従医を全面的に信頼していたので、首相パーマストン子爵が他の医者に見せることを提案しても拒否した[144]。だがアルバートの病状は悪化する一方で12月11日にはヴィクトリアも他の医師に診せることを承諾した[147]。召集されたワトソン医師はすでに手遅れの腸チフスと診断した[148]。
12月13日午後遅く、アルバートは危篤状態に陥り、ヴィクトリア女王はじめ家族が集められた。その日の晩ヴィクトリアはヒステリック状態に陥り、落涙と祈祷を繰り返していた[149]。ヴィクトリアがアルバートの枕元に近づくと彼女の存在に気付いたアルバートは彼女にキスをして手を握り、弱弱しい声ながら「gutes Fraüchen(私の可愛い小さな奥さん)」と声をかけたという[149]。翌14日朝にはアルバートは回復に向かっているように見えたが、正午までにはほとんど動けなくなった。アルバートの息が荒くなるとヴィクトリアは彼に駆け寄り、「Es ist Fraüchen(貴方の小さな奥さんですよ)」と囁き、彼とキスをしたという[150][151]。
ヴィクトリア女王ら家族が見守る中、アルバートは42歳にして薨去した[152]。ヴィクトリアは冷たくなった夫の手をしばらく握り続けていたが、やがて部屋を飛び出して泣き崩れたという[151]。
ヴィクトリアは伯父ベルギー王レオポルドに宛てて「生後8カ月で父を亡くした赤ん坊は、42歳で打ちひしがれた未亡人となってしまいました。私の幸せな人生は終わりました。私がまだ生きなければならないとしたら、それは父を失った哀れな子らのため、彼を喪うことで全てを失った我が国のため、また私だけが知る彼の希望を実現するためです。彼は私の傍らにいつもいてくれるのです。」と書いている[153][154]。
喪服時代

ヴィクトリアの悲しみは深く、その後彼女は10年以上にわたって隠遁生活をはじめた。日々をワイト島のオズボーン・ハウスやスコットランドのバルモラル城などで過ごしてロンドンには滅多に近寄らなくなった。国の儀式にも社交界にもまったく臨御しなくなった[155]。たまに人に姿を見せる時には常に喪服姿であった[139]。自分だけではなく侍従や女官、奉公人に至るまで宮殿で働く者全員に喪服の着用を命じていた[156]。ヴィクトリアによればアルバートを失った直後の3年間は死を希望する心境にさえなっていたという[156]。
政治家たちにとってはヴィクトリアがこれまで散々行ってきた政治への介入を止めさせる絶好のチャンスであり、「喪」に復したいという彼女の意思を支持した[157]。だがヴィクトリアは「喪」に復することに全力をあげるために政権交代を阻止しようとするようになった。アルバート薨去直後の頃、パーマストン子爵の政権運営が危なくなっていた時期だったが、ヴィクトリアは野党党首ダービー伯爵に対して「今の自分は政権交代などという心労に耐えられる状態ではない。もし貴下が政権打倒を目指しているのならば、それは私の命を奪うか、精神を狂わせる行為である。」という脅迫的な手紙を送っている[158]。これを見たダービー伯爵は思わず「女王陛下がそんなに奴らをお気に入りだったとは驚いたな」と述べたという[155]。
1862年に再びロンドン万博が開催されたが、彼女はアルバートのことを思いだして居た堪れなくなるとして欠席した[159]。
国民ははじめヴィクトリアに同情する人が多かったが、やがていつまでも公務に出席しない彼女を批判する論調が増えていった。特にヴィクトリアが三女アリスの結婚式をまるで葬式のようにやらせたのを機に女王批判が強まっていった[160]。親王室派の『タイムズ』紙さえも「女王の喪はいつになったら明けるのか」という不満の論調を載せている[161]。女王のあまりの引きこもりぶりに「女王などいらない」として共和主義者が台頭し始める始末となった[162][163][164]。
首相パーマストン子爵はこれ以上国民が共和主義に傾くのを避けるため、皇太子バーティを議会に頻繁に出席させることで王室の活動を世に示したがっていたが、ヴィクトリアが強く反対して阻止した[161]。この「出来そこない」の息子のせいでアルバートが過労になったと考えていたヴィクトリアはバーティには重要なことは何も任せないつもりでいた[161]。
引きこもってばかりいると身体に悪いという侍医の薦めでヴィクトリアは乗馬や馬車で出かけるようになり、その関係でバルモラル城でのアルバートの馬係であったスコットランド人ジョン・ブラウンと関わる機会が増え、彼を寵愛するようになった[165]。ブラウンは事実上ヴィクトリアの秘書、ボディーガードとなっていき、王族や首相といえどもブラウンを介さなければヴィクトリアに謁見できなくなった[166]。この女王とブラウンとの関係をマスコミが面白半分に取り上げ、二人が秘密結婚したなどという噂が流れるに至り、ヴィクトリアは「ミセス・ブラウン」などと呼ばれるようになった[167][168][169]。二人の間にセックスの関係があったのかについては歴史家の間で意見が分かれており定かではない[170]。ヴィクトリアとブラウンの親密な関係は1883年のブラウンの死まで続いたが、その頃にはすっかり肥満した老婆になっていたヴィクトリアはあまりゴシップのネタにならず、ブラウンも勤勉な世話係として評価されるようになっていた[171]。
ただこの時期にもヴィクトリアは外交には強い興味を持ち、パーマストン子爵の内閣がイタリア統一、アメリカ南北戦争、ポーランド1月蜂起、シュレースヴィヒ=ホルシュタイン問題など他の欧米諸国の問題に介入を企む姿勢を見せるとヴィクトリアは不介入を政府に指示してブレーキをかけた。また逆にパーマストン子爵の後継であるダービー伯爵の他のヨーロッパ諸国への不介入方針に対してはルクセンブルク問題のようにヨーロッパの平和が脅かされる恐れがある問題については積極的に介入するべきであると発破をかける役割を担った[172]。
最終的にヴィクトリアを引きこもり生活から立ち直らせたのはベンジャミン・ディズレーリであった[164]。
ディズレーリを寵愛

1867年になると保守党の首相ダービー伯爵が病気でほとんど執務できなくなり、大蔵大臣・下院院内総務ベンジャミン・ディズレーリが事実上首相職を代行するようになり[173]、1868年2月下旬には正式に首相に就任した[173]。このユダヤ人首相はヴィクトリアのお気に入りだった[174]。
ヴィクトリアはもともとロバート・ピールを失脚に追い込んだディズレーリに好感を持っていなかったが[175]、第一次ダービー伯爵内閣の時に大蔵大臣として入閣したディズレーリが送ってくる報告書の小説家的な面白さで彼に注目するようになった[176]。その頃のヴィクトリアはディズレーリについて「青白い顔、黒い目とまつ毛、黒い巻き毛の髪という典型的なユダヤ人風の容貌であり、その表情は不快感を覚える。しかし話してみるとそうでもなかった。」と書いている[176]。ヴィクトリアがディズレーリに本格的に好感を抱くようになったのはアルバート薨去の際にディズレーリがアルバートの人格を称え、アルバート記念碑の創設に尽力したことだった[177]。ヴィクトリアによれば「アルバートの薨去後、多く者が私を憐れんでくれたが、私の悲しみを本当の意味で理解してくれた者はディズレーリだけだった。」という[175]。ディズレーリが首相を代行するようになった頃にはディズレーリの政策面(アイルランド国教廃止に反対する見解、対ロシア強硬政策、選挙法改正や国民意識を強める帝国主義政策などの「トーリー民主主義」的施政)にも共感を感じることが多くなり[178][173]、また彼のロマンチックで独特な雰囲気と巧みな話術に惹かれるようになっていた[179]。ヴィクトリアはヴィッキー宛ての手紙の中で「彼は詩的で創造的で騎士道精神を持っている。私の手にキスをするため跪いた時、私の手を包み込むようにして『忠誠と信頼の心に愛をこめて』と語ってくれた」と書いている[179]。1868年春頃からヴィクトリアは自らが摘んだ花束をディズレーリへ送り、ディズレーリはお礼に自分の小説をヴィクトリアへ送るという関係になった[180][181]。
保守党政権が危機的な政治情勢の中、ディズレーリはヴィクトリアを公務に復帰させ、彼女の大御心によって政権を存続させようと考えていた。彼はヴィクトリア本人に「政治が重大な時局にある時は国民も君主に備わる"威厳"を再認識すべきであります。同時に政府もそのような時局における内閣の存立は女王陛下の大御心次第だという事を了解するのが賢明というものです。」という立憲政治を否定するに近い上奏を行っている[182]。ヴィクトリアもまんざらではなく、ディズレーリを助けるために徐々に公務に復帰するようになった[182]。しかし二人の蜜月には反発も多く、ディズレーリと同じ保守党の政治家であるソールズベリー侯が「女王陛下はすっかり『例のユダヤ人』の手先になってしまわれた。彼は女王陛下の要請によって政権に留まれる準備をした後に見せかけの辞表を提出して事態を収拾するつもりでいる。玉座に君臨しているのは女性であり、ユダヤ人の野心家は彼女を幻惑する術を心得ている」と危機感を露わにするほどだった[183]。
だが第二次選挙法改正により有権者数が前回より2倍増えた1868年秋の総選挙において保守党は惨敗した。これを受けてディズレーリは辞職し、自由党のウィリアム・グラッドストンが後任の首相に就任した[184]。これはイギリス史上初めての選挙による政権交代であった[185]。この後しばらくディズレーリは野党党首に甘んじたが、ヴィクトリアとディズレーリの親密な関係は続いた[175]。

総選挙での保守党の勝利を経て1874年2月にディズレーリが政権に復帰した。このディズレーリの二期目においてヴィクトリアはいよいよ彼への寵愛を深め、不偏不党を崩してディズレーリびいき、保守党びいきになっていった[186]。その寵愛ぶりはかつてのメルバーン子爵をも超えるものがあった[175]。ヴィクトリアはディズレーリの帝国主義政策を全面的にバックアップし、1876年5月にはインド女帝に即位し、以降ヴィクトリアは「Victoria R&I[# 6]」と署名するようになった[182]
1876年にはディズレーリをビーコンズフィールド伯爵に叙した。さらにベルリン会議でキプロスを獲得して「エンパイア・ルート」を完成させた恩賞としてディズレーリにガーター勲章と公爵(Duke)位を与えようとしたが、公爵位についてはディズレーリの方から辞退している[188]。
1880年4月の総選挙にディズレーリ率いる保守党が敗れたため、ディズレーリは辞職を余儀なくされた。ディズレーリは病を患っており、もはや首相職に復帰する日は来ないと覚悟していたが、ヴィクトリアは出来るだけ早くディズレーリが首相に返り咲く日を期待していた[189]。ヴィクトリアはディズレーリに「これが永遠の別れになるなどと思ってはいけませんよ。私は必ず近況を貴方に知らせますから貴方もそうすると約束してください」という手紙を送っている[189]。ディズレーリは女王と文通を続け、ウィンザー城にも足繁く通ったが、1881年4月には死去した[190]。
ヴィクトリアは彼の訃報にだいぶショックを受けたようだった。彼女はディズレーリの遺言執行人に「ディズレーリほど厚い忠誠心で私に仕えてくれた大臣、また私に誠意を尽くしてくれた友人はいない。」という手紙を書いた[191]。またディズレーリの墓があるヒューエンデンに「君主であり友人であるヴィクトリアR&Iから、感謝と親愛をこめて」と刻んだ大理石の記念碑を建てさせた[191]。
グラッドストンとの対立

ウィリアム・グラッドストンは1868年秋の総選挙における自由党の勝利によって第一次グラッドストン内閣を組閣をした。アイルランドで反英運動・分離運動が高まりを見せていた中、グラッドストンはアイルランド土地法によりアイルランド小作農たちの権利を保護し、またアイルランド国教会を廃止した。しかし前者は地主貴族、後者はヴィクトリア女王の強い反発を買った[192][193]。1869年初めにグラッドストンはアイルランドにも女王の居城を置いて積極的にアイルランドを訪問するべきと進言したが、ヴィクトリアは拒否した[192][194]。
1874年の総選挙での自由党の敗北により、グラッドストンは首相職をディズレーリに譲り、1875年に自由党党首職からも退いたが、その後も自由党の実質的な指導者であり続け、ディズレーリ保守党政権批判の急先鋒として「人民のウィリアム」などと呼ばれた。自分のお気に入りの首相を攻撃しまくるグラッドストンへの女王の嫌悪感はいよいよ強まり[195]、ヴィッキーに宛てた手紙の中で彼を「狂人」などと評した[196][197]。
1880年4月の総選挙にディズレーリ率いる保守党が敗れたため、再びグラッドストンに大命降下せねばならない事態となったが、ヴィクトリアは自由党政権を誕生させるとしてもグラッドストンの首相就任だけは阻止したいと願い、自由党下院指導者ハーティントン侯爵を首相にしようと画策したが、自由党内からの反発を招き、結局第二次グラッドストン内閣を誕生させることを余儀なくされた[184][# 7]。
グラッドストンには君主は象徴的役割に限定されるべきという持論があり、「女王の忠臣」ディズレーリ時代を機に本格的に政治に介入し始めていたヴィクトリアを再び政治から遠ざけようと図った[200]。彼はアイルランド問題についてヴィクトリアの意見を聞くつもりはなかった。ヴィクトリアは皇太子バーティ宛ての手紙の中で「女王である私に相談すべき大問題なのに私を完全に無視するこの恐るべき急進的政府には仮面を付けた共和主義者が大勢いる。彼らはアイルランド自治派に頭が上がらない。グラッドストンは計り知れない過ちを犯している。」と怒りを露わにしている[201][202]。
1884年、地方の炭鉱などの労働者にまで選挙権を広げる第三次選挙法改正法案が議会に提出されたが、地方に基盤を持つ自由党と都市部に基盤を持つ保守党の間で紛糾し、8月にはグラッドストンもヴィクトリアに仲裁を依頼する羽目になった。女王がグラッドストンと保守党党首ソールズベリー侯爵の間を取り持った結果、11月に自由党と保守党の妥協が成立し、第三次選挙法改正法案が可決されて有権者数が更に増加した[203][204]。これにはグラッドストンも女王の強力な仲裁に深く感謝した[205][206]。
1885年6月に予算案が否決されたことでグラッドストン内閣が辞職し、保守党のソールズベリー侯爵に大命降下した[207][208]。ヴィクトリアはグラッドストン辞職を心より喜んだが、11月の総選挙は自由党とアイルランド国民党が勝利した。グラッドストンはソールズベリー侯爵内閣の倒閣のためアイルランド国民党と手を組もうといよいよアイルランド自治を主張し始めた[209]。グラッドストンが再び首相に就任することを恐れるヴィクトリアは自由党内のアイルランド自治反対派をソールズベリー侯爵と連携させようとした[210][211]。さらにソールズベリー侯爵内閣に「王室のお墨付き」を与えようと1886年の議会開会式に10年ぶりに出席した(これがヴィクトリア最後の議会開会式出席となった)[210][211]。
しかしこうした女王の工作もむなしく、自由党とアイルランド国民党の共同はなり、ソールズベリー侯爵は議会で敗北して辞職に追い込まれた[212]。ヴィクトリアはアイルランド自治に反対する自由党議員ジョージ・ゴッシェンを召集して後継首相について諮問することでなおもグラッドストンに大命降下するのを阻止しようとしたが、ゴッシェンが参内を拒否したため、1886年2月1日グラッドストンに三度目の大命降下を与えることを余儀なくされた[213]。ヴィクトリアはただちにグラッドストン内閣倒閣に動き、保守党と自由党内アイルランド自治法反対派が党を割って創設した自由統一党の連携の仲介を取り、その結果6月にアイルランド自治法案は僅差で否決された。続く解散総選挙もグラッドストンの自由党の敗北、保守党の勝利におわり、グラッドストンは辞職した[214][215]。
しかし1892年7月の総選挙で保守党が敗北した結果、8月にグラッドストンに四度目の大命降下を与える羽目となった[216][217]。グラッドストンはライフワークのアイルランド自治法案をまた提出した。今回は自由党内が一つにまとまっており、またアイルランド国民党が指導者を失って立場が弱い時期だったため無条件に自由党に協力した結果、庶民院で同法案が可決された。しかしソールズベリー侯爵の尽力で貴族院が圧倒的多数で否決した。ヴィクトリアはソールズベリー侯爵の功績を称えている[218]。グラッドストンももはや高齢であり、ついにアイルランド自治法案を諦め、1894年に引退を決意して辞職を願い出た[218]。ヴィクトリアは二度とグラッドストンの顔を見ずに済むことに大喜びした[219]。彼の最後の伺候にも労いの言葉はまったくかけなかった[220]。
グラッドストンは1898年に死去したが、ヴィクトリアは弔意を出すことを求められても「嫌ですよ。私はあの男が好きではありません。気の毒と思っていないのにどうして気の毒などと言えるでしょうか」と述べて断っている[221]。
在位50周年・60周年記念式典
1887年6月20日にヴィクトリア女王は在位半世紀を迎え、世界各国の要人がロンドンに集められて在位50周年記念式典が挙行された。ベルギー(レオポルド2世)、デンマーク(クリスチャン9世)、ギリシャ(ゲオルギオス1世)、ザクセン(アルベルト)の四か国は国王が自ら出席し、それ以外の国々も高位の王族・皇族が出席した。日本からは小松宮彰仁親王が出席した[222]。
1897年6月の在位60年周年記念式典は世界各地の植民地首相や駐留連隊代表者も出席し、まさに「帝国の祭典」の様相を呈していた[223]。この式典でヴィクトリアは「愛する臣民たちに感謝する。神の御加護があらんことを。」と一言だけ挨拶した[224]。
-
1887年のヴィクトリア女王在位50周年記念式典を描いたウィリアム・エワート・ロックハートの絵画。
-
1897年、在位60年を迎えたヴィクトリア女王。
消極的な晩年

通常女王は退任する首相に推挙する後任の首相を下問するのが慣例だったが、グラッドストン第四期目の退任の際にヴィクトリアは彼に一切下問せずにお気に入りのローズベリー伯爵を独断で後任の首相に任じた[219][225]。
ローズベリー伯爵はエジプトと南アフリカに大きな利権を持つライオネル・デ・ロスチャイルドの妹を妻に迎えており、熱心な帝国主義者であった[226]。彼はただちにヴィクトリアに海軍増強を提案してヴィクトリアの帝国主義の矜持を満足させた[227]。一方でローズベリーも自由党の政治家であり、貴族院批判を行ったり相続税値上げなどグラッドストンと似通った傾向も多々あり、ヴィクトリアもやや警戒していたが[228]、結局ローズベリー伯爵は貴族院改革にもアイルランド自治にもそれほど熱を入れなかったのでヴィクトリアも安堵した[229]。1895年6月に陸軍大臣の減給をめぐる採決で自由党は分裂して過半数を割り、ローズベリー伯爵は辞表を提出した。ヴィクトリアとローズベリー伯爵は必ずしも意見は一致しなかったが、それでも彼女は政権交代を残念がっていた[230]。
保守党のソールズベリー侯爵が第三次内閣を組閣した。以降ヴィクトリアの崩御まで彼が首相を務めた。ソールズベリー侯爵は民主主義を進展させることを拒否し、貴族の特権を守るために全力を尽くす極めて保守的な人物だった[231]。かつてのディズレーリのような壮大な帝国主義構想は持たなかったが、利害関係には異様に執着し、熱心な帝国主義者ジョゼフ・チェンバレンを植民相として新帝国主義政策に乗り出した[232]。ヴィクトリアはソールズベリー侯爵には安心して国政を任せることができ、彼女が政治に口を出すこともあまりなくなっていき、芝居見物など趣味に興じることが増えた[233]。
加えてヴィクトリア朝末期、女王は高齢で体力が低下していき、政府に対する影響力を減少させ続けた[234]。女王の旅行の際に女官の切符の手配が忘れられるという事態さえ発生した[234]。1900年には七男コノート公アーサーをサー・ガーネット・ヴォルズリーに代わる陸軍総司令官に任命しようとしたが、ソールズベリー侯の推挙が優先されてロバーツ卿がその任についた[235]。さらに同年ソールズベリー侯は首相の職に専念するとして彼が兼務していた外務大臣職に陸軍大臣|ランズダウン侯爵を就任させた。ランズダウン侯爵はかつて陸軍のスキャンダルを公表した人物だったのでヴィクトリアは嫌っていたが、この時も彼女の反対は何の効力も発揮せず、彼女にできたのは日記に不満を書くことだけだった[234]。
-
1897年、南フランスを旅行中のヴィクトリア女王を描いた絵
外交
帝国主義

ヴィクトリア朝64年の間に大英帝国は世界中の非白人国家・民族集団に対して覇道の限りを尽くし、その領土を10倍以上に拡大させ、地球の全陸地面積の4分の1、世界全人口の4分の1(4億人)を支配する史上最大の帝国となるに至った[237][238]。大英帝国の維持・拡大のためにヴィクトリアとその政府は世界各地で頻繁に戦争を行い、ヴィクトリア朝全期を通じてイギリスが戦争をしていない時期は稀であった(ヴィクトリア朝64年間にイギリス軍が全く戦闘しなかった時期は2年だけだったといわれる)[239]。
ヴィクトリアは非白人国家に対する帝国主義には全面的に賛成していた。「帝国主義には二種類あり、一つは皇帝専制などの誤った帝国主義。もう一つは平和を維持し、現地民を教化し、飢餓から救い、世界各地の臣民を忠誠心によって結び付け、世界から尊敬される英国の帝国主義である。英国の領土拡張は弱い者イジメではなく、英国の諸制度と健全な影響を必要とあれば武力をもって世界に押し広げるものである。」とするディズレーリ内閣植民相カーナーヴォン伯爵の見解を熱烈に支持していたためである[240]。
イングランド人、スコットランド人、アイルランド人、ボーア人、アフリカ人、アラブ人、インド人、中国人、ビルマ人、アボリジニ、マオリ、ポリネシア人、インディアン、エスキモーなど無数の人種、また三大宗教をはじめとする様々な宗教を版図におさめる大英帝国には統一感はまるでなかったが、その彼らを「女王陛下の臣民」として一つに結び付け、統合の象徴の役割を果たしたのがヴィクトリア女王であった[241]。
この時期の英国君主が女性であったことは大英帝国の成功の秘訣であった。ヴィクトリアが「帝国の母」としてその「子供」たちである世界中の臣民たちに慈愛を注ぐイメージが被支配民の間にも広まり、大英帝国の支配への抵抗心を和らげたのである[242]。カナダのインディアンのスー族やクリー族はヴィクトリアを「白い母」と呼んで敬意を払っていた[243]。あるインド藩王はヴィクトリアのインド女帝即位にあたってのデリーでの大謁見式(ヴィクトリアは欠席)において「ああ、母上。ロンドンの宮殿にいます親愛なる陛下。」と呼びかけている[244]。1865年に反乱を起こしたジャマイカの黒人たちもヴィクトリア女王個人には忠誠を誓っており、裁判所を襲撃して囚人を解放した際に「我々はヴィクトリア女王陛下に反乱を起こしているわけではないから、陛下の所有物を略奪してはならない」として囚人服を置いていかせたという[245]。
ヴィクトリア自身も支配下におさめた非白人国家の王や首長の子供たちを後見したり、教育を与えたり、自分の名前(男性の場合はヴィクトリアの男性名ヴィクターや夫の名前アルバートなど)を与えるなどして「女王は人種に寛大」というイメージを守ることに努めた[246]。
アフガニスタン戦争

ヴィクトリアが即位したばかりの頃、イギリス東インド会社支配下のインドの北西が大英帝国の弱点となっていた。イギリスはシク教国と連携してインダス川まで勢力を伸ばしたものの、ロシア帝国もブハラ・ハン国、ヒヴァ・ハン国を事実上の勢力下におさめ、ついでアフガニスタン王国を窺っていた。そのためアフガニスタンがイギリスとロシアの中央アジア覇権争い(「グレート・ゲーム」)の中心舞台になろうとしていた[247]。
ヴィクトリアの戴冠式から間もない1838年10月、イギリス軍はアフガニスタンへ侵攻を開始し、首都カブールを陥落させた。アフガン王(アミール)ドースト・ムハンマド・ハーンは北方ブハラ・ハン国へ亡命したため、イギリスはシュジャー・シャーを傀儡の王に即位させた[248]。しかし1841年11月カブールで反英闘争が激化し、掌握不可能となり、それに乗じてトルキスタンに亡命していた前王の息子アクバル・ハーンがウズベク族を率いてカブールへ戻ってきたため、イギリス軍は降伏を余儀なくされた。アクバルはイギリス軍の安全な撤退を保障したが、約束が守られることなく、現地部族民が略奪をしかけてきてイギリス軍は大量の死者を出しながら撤退する羽目となった。結局カブール駐留イギリス軍で生き残ったのは軍医のウィリアム・ブライドンのみであった(第一次アフガン戦争)[249]。
イギリスという後ろ盾を失ったシュジャー・シャー王は殺害され、ドーストがアフガンに戻ってアミールの座を取り戻した。イギリスは敗北したとはいえ、すでにアフガン南西部を半植民地状態にしていることは変わらなかった[250]。結局ドーストは外交権を事実上イギリスに委ねざるをえなかった[251]。1864年のドーストの崩御後、シール・アリー・ハーン、モハメド・アフザル・ハーン、モハメド・アザム・ハーンの三兄弟が王位継承争いを起こしてアフガンに内戦が発生した。インド総督はアフガン弱体化を狙い、内戦を煽ろうと不干渉を建前に「兄弟のうち王位を固めた者を承認する」と宣言した[252]。イギリスの狙い通り内戦は激化し、王位の奪い合いの末、最終的には1869年にシール・アリー・ハーンが王位を固めた[253]。
一方ロシア帝国は1868年にブハラ・ハン国、1873年にヒヴァ・ハン国、1875年にコーカンド・ハン国を攻め滅ぼし、中央アジアの3ハーン国をすべて保護領としていた[254]。警戒したイギリスはアフガン支配強化の必要性を感じ、シール王に対してイギリス外交団をカブールに常駐させるよう求めた[255]。しかしシール王はこれを認めず、逆に1878年8月にロシア皇帝から送られてきたロシア将校団の使節の受け入れを認めた。イギリス人はこの扱いの差に激怒した[256]。
ヴィクトリアの怒りも激しく、彼女はアフガニスタン懲罰の必要性を感じたが、第一次アフガン戦争の苦い思い出もあり、外交圧力をかけて解決させるようディズレーリ首相に指示している[257]。しかし現地インド軍は早々にアフガニスタンへ侵攻を開始していた。ヴィクトリアもやむなくインド軍を全面支援するよう首相と外相に要求した[257]。アフガンはロシアの援助を期待したが、ロシアは露土戦争の戦後処理国際会議ベルリン会議で孤立していることに焦り、安易な出兵をして孤立を深めたくない時期だったため、アフガンは見殺しにされた[258]。
こうしてはじまった第二次アフガン戦争はアフガン軍のゲリラ戦に苦しめられながらもイギリス軍が勝利をおさめ、1879年6月にモハメド・ヤクブ・ハーン王にガンダマク条約を締結させて戦争は終結した[259]。イギリスはロシアでの長い亡命生活でロシアからの信頼も厚いアブドゥッラフマーン・ハーンをアミールに即位させ、外交を完全にイギリスが掌握しつつ内政は彼に任せてアフガンから撤収していった[260]。
-
1842年第一次アフガニスタン戦争で全滅する直前のイギリス第44連隊を描いた絵画
-
マイワンドの戦いで突撃をかけるイギリス王立騎馬砲兵を描いたリチャード・カートン・ウッドヴィレーの絵画
中国半植民地化

清は広東港でのみヨーロッパ諸国と交易を行い、公行という清政府の特許を得た商人にしかヨーロッパ商人との交易を認めてこなかった(広東貿易制度)。しかしインド産アヘンはこの枠外であり、イギリス商人が密貿易によって中国人アヘン商人に売っていたため清国内にアヘンが大量流入していた。1823年にはアヘンがインド綿花を越えて清の輸入品の第一位となり、清は輸入超過(銀流出)を恐れるようになった[261]。1839年に清がアヘン取り締まりを強化したことで英清関係は緊張し、小競り合いが発生するようになった[262]。
1840年6月に大規模なイギリス艦隊や陸軍兵力が広東に集結して軍事行動を開始し、沿岸地域を占領しながら北上して北京を窺ったが、清側が交渉を求め、またモンスーンの接近や舟山諸島占領軍の病の流行で9月に一時撤収した[263]。しかし英軍が撤収するや北京政府内で強硬派が盛り返したため、交渉は難航し、イギリス軍は1841年1月から再度軍事行動を開始した。イギリス艦隊は再び廈門、舟山諸島、寧波など揚子江以南の沿岸地域を占領した[264]。モンスーンに備えて冬の間は停止したが、1842年春に軍事行動を再開し、揚子江へ入って南京を窺った。ここに至って清政府も完全に戦意を喪失した[265]。
清に南京条約、五港通商章程、虎門寨追加条約など不平等条約を締結させ、それまでの広東貿易制度や公行制度を廃止させ、清はイギリスの世界自由貿易体制の底辺に組み込まれる形となった[266]。アヘン輸入も一層拡大され[267]、香港がイギリス領として割譲されることになった[268]。東アジアでの更なる覇権確立の足場の確保にヴィクトリアも喜び、伯父ベルギー王レオポルドに宛てた手紙の中で「ヴィクトリア(1840年に生まれたばかりの長女)を香港大公女(Princess of Hong Kong)に叙そうかと考えています。」と冗談交じりに書いている[269]。
その後広東で反英闘争が激化し、1850年代になるとイギリスは再度の武力行使を決意した。クリミア戦争を経て同盟関係を深めていたフランス皇帝ナポレオン3世もそれに賛同し、1856年10月8日のアロー号事件を機に英仏軍は広東攻撃を開始した。英仏軍は広東を占領して北上し、1858年5月に大沽砲台を占領して北京を窺い、6月に清に天津条約を締結させることに成功した[270]。だが清にとってこの条約は北京陥落を防ぐための便宜的手段であり、条約を守る姿勢を見せなかったため、一度撤収した英仏軍は再び北進を開始し、1860年8月に大沽砲台を再度陥落させ、北京を占領した。改めて清に北京条約を締結させた[271]。
これにより中国半植民地化は決定的となったが、同時に清朝そのものの弱体化も決定的となり、太平天国の乱が活発になり、イギリスが内政干渉(清朝支持)をせねばならない機会が増加した。また統治能力のない清政府に代わってイギリスが中国沿岸ほぼ全域の防衛を担当せねばならなくなり、その負担は大きかった[272]。しかも清仏戦争・日清戦争後には他の列強も続々と中国植民地化に乗り出し、イギリス、フランス、ロシア、日本、ドイツの列強間での中国分割が熾烈になっていった[273]。とりわけ近年急速に台頭し始めたヨーロッパ外帝国主義勢力である日本の中国諸港獲得にはヴィクトリアも強い危機感を持ち、東京へ圧力をかけたがるようになった[274]。一方でヴィクトリアはアフリカ分割であれ、中国分割であれ、植民地を一人占めしようという意思はなかった。彼女は第一大蔵卿アーサー・バルフォアに対して「我々が我々以外の何者にも植民地を渡すつもりがないという印象を列強に与えないように注意しなければならない。しかし同時に我が国の権利と影響は死守せねばならない」と訓令している[275]。
インド大反乱とインド統治

1857年初頭、インドのセポイたちがヒンズー教の教えに従って牛脂や豚脂が塗油として使われるイギリス軍ライフル銃の弾薬筒の使用を拒否し、これに対してイギリス軍はこのセポイたちを事実上の死刑である重労働刑に処した。彼らの解放を求める運動が起こり、やがてそれは全インドの大反乱に拡大した(インド大反乱(セポイの反乱))[276]。
反乱がおきて最初の数カ月、英軍は反乱軍におされぎみで首相パーマストン子爵は弱腰になっていたが、ヴィクトリアは毅然とした態度を崩さず、現地に植民している臣民たちを守らねばならないとして主戦論を唱え、政府に発破をかけ続けた[277]。反乱軍に陥落させられたコーンポー駐屯地でイギリス人婦女子が虐殺されたことがイギリス人の怒りに火を付けた。ヴィクトリアも「気の毒な婦人と子供たちに対して犯されたこの恐るべき行為は大昔ならともかく現代ではとても考えられない。誰もが血の凍る思いである」と怒りをあらわにしている[278]。復讐に燃えるイギリス軍はインド人を大量に虐殺する残虐な鎮圧を行った[279]。反乱者の死刑は大砲に括りつけて身体を吹き飛ばす方法によって行われた[280]。インド人の心はすっかり折られ、彼らが大英帝国の支配に対して武装蜂起を起こすことは二度となかった[281]。
反乱鎮圧後の1858年8月2日にヴィクトリアはインドを自らの直接統治下に置く法律に署名した[282]。これによりインド統治は東インド会社ではなくイギリス政府が行うこととなった[283]。(実質的にはとっくに滅んでいた)ムガル帝国は形式的にも崩壊し、以降ヴィクトリアは「インド女帝(Empress of India)」と俗称されるようになった。ヴィクトリアは「巨大な帝国に対して直接責任を負う事に大きな満足感と誇りを覚える」と書いている[282]。
一方でヴィクトリアは再反乱を防ぐには自らの「慈悲深い母」のイメージを前面に出すべきであると考え、信仰の自由を保障することをインド臣民たちに布告した[284]。またヴィクトリアは「インド王侯たちを君主(ヴィクトリア)との個人的な結びつきによって引き付けるべきである。そのためにインドにも高位の勲爵士を置くべきである。」と主張し[285]、アルバート公や政府、インド総督の協力を得てスター・オブ・インディア勲章を制定した[286]。
ディズレーリ時代にはヴィクトリアはインドに強い興味を示すようになり、ヒンディー語の勉強を始めるようになり、またインド人を侍従として側近くに置くようになった。とりわけ「ムンシ」ことアブドル・カリムを寵愛し、彼はジョン・ブラウンの死後にブラウンに取って代わったと言っても過言ではない存在となった[287]。
ヴィクトリアはかねてよりロシア、オーストリアが世界一の大国の君主である自分を差し置いて皇帝号(Emperor)を名乗っているのが気に入らなかった。最近ではプロイセンまでドイツ皇帝を名乗り始めており、イギリス君主も皇帝号を得る時だと考えるようになった[288]。またドイツ皇帝ヴィルヘルム1世の高齢化が進むと、ヴィクトリアはその皇太子フリードリヒ(フリードリヒ3世)に嫁がせた長女ヴィクトリアが近いうちに「Queen」より上格の「Empress(皇后,女帝)」号を得ることを懸念するようになった。娘より下に置かれるわけにはいかないと考えたヴィクトリアは「インド女帝(Empress of India)」号を公式に得たがるようになった。1876年1月に首相ベンジャミン・ディズレーリにその旨を指示し、彼に議会との折衝にあたらせた結果、4月に王室称号法によって「インド女帝」の称号を公式に獲得した[289][290]。彼女はその日の日記に嬉々として「これで私は今後署名する時に『女王および女帝』と書く事ができる」と書いている[291]。
1877年1月1日にデリーでインド藩王たちが召集されてヴィクトリアの女帝即位宣言式「大謁見式(Great Durbar)」が開催された。もちろんヴィクトリア本人がデリーを訪れることはなく(彼女は生涯ヨーロッパ以外の地域を訪れることはなかった[243])、インド総督ヴィクター・ブルワー=リットン伯爵がその名代を務めた[291]。
-
スター・オブ・インディア勲章
-
女帝位を欲しがるヴィクトリア女王を皮肉った風刺画。インド人の格好をしたディズレーリがヴィクトリアとインド帝冠とイギリス王冠の交換をしている。
-
ヴィクトリア女帝のインド人侍従アブドル・カリム。
アシャンティ族との戦い
イギリス人は1820年代から西アフリカの英領ゴールド・コーストにおいてその周辺の最強の部族であるアシャンティ族と小競り合いを続けてきた。アシャンティ族は天から授かったという伝承のレガリア「黄金の丸椅子」を崇拝し、生贄をささげる風習のある部族だった。生贄は王(アシャンタヘネ)の代替わりや戦争などの緊急事態の際に捧げられ、時に何百人という数に及んだ(生贄にささげられるのは基本的にはその時のために生かされている囚人だった。戦争の場合はその場で無造作に生贄が決定された)[292]。ヨーロッパの価値観からは到底認めることのできない文化であり、イギリス人は「迷信深い野蛮な民族」と看做して軽蔑していた。アシャンティ族もイギリス人を「二枚舌の卑怯者」と看做して嫌った[293]。
1872年に好戦的なコフィ・カリカリがアシャンタヘネとなり、またオランダが黄金海岸から撤収する際にアシャンティ族が領有権を主張していたエルミナ城をイギリスに売却したことでイギリスとアシャンティの対立が深まった。エルミナ城とケープ・コースト城が一時アシャンティ族に包囲されるもイギリス軍がこれを撃退し、アシャンティ族はヨーロッパ人宣教師を数名捕虜にして撤退した[294]。
これに対してヴィクトリアの委任を受けたサー・ガーネット・ヴォルズリー将軍率いるイギリス軍が1873年11月からアシャンティ族討伐を開始した。これはイギリス軍とアフリカ現地民の組織的な軍隊との最初の本格的な武力衝突となった[295]。イギリス軍は1874年2月にはアシャンティ族の首都クマシを占領し、アシャンティ族の心を折るためここを全て爆破解体した。生贄をささげる「死の木立」も切り倒された。コフィ・カリカリも大英帝国に背くことを諦め、巨額の賠償、捕虜の解放、エルミナ城の所有権の放棄、生贄の風習の根絶を受け入れた[296]。
普仏戦争でプロイセン軍の快進撃を見せつけられたイギリス陸軍や国民は自国陸軍に自信を無くしていた時期であったが、この軍事的成功にイギリス陸軍もいざとなれば迅速な作戦行動ができるのだという自信を強め、以降点在するアフリカの黒人王国に対して積極的に戦争を仕掛けるようになった[297]。
ズールー族との戦い

同じころ南アフリカには英国植民地が2つ(ケープ植民地、ナタール)、オランダ人植民者の子孫でイギリス支配に反発してグレート・トレックで内陸部へ移住したボーア人による国家が2つ(オレンジ自由国、トランスヴァール共和国)、計4つの白人植民者共同体があった[298][299]。オレンジ自由国は比較的親英的で英国と協力関係にあったが、トランスヴァール共和国は反英的だった[299]。
そしてその周囲に白人植民者の20倍にも及ぶ数の原住民である黒人が暮らしていた。黒人たちの中ではズールー族が大きな勢力であった。このズールー族はイギリス・ボーア人問わず現地の白人が最も恐れた戦闘民族だった。ズールー族の独立国家ズールー王国は国民皆兵をとっており、男子は槍を血で洗うまで一人前と認められず、また戦闘で敵を一人殺すか傷つけるまで妻帯が認められないという風習があったため、非常に好戦的だった[300]。銃はほとんどもっておらず、昔ながらの投げ槍を武器にしていた[300]。
このズールー族の脅威や1876年のペディ族との戦争、財政難などによりトランスヴァール共和国は1877年4月12日に(この時には何の抵抗もなく)イギリスに併合された[301][302][299]。大英帝国の一員となったボーア人とズールー族の間で国境争いが起こる中、英領ナタール行政府の長である高等弁務官バートル・フレアはズールー族を武力で制圧することを決意した。イギリス本国に応援を頼みつつ、その到着を待たずに1879年1月にズールー王国に対して「軍隊を廃棄し、非人道的な法・慣習を廃し、首都に英国人を監視役に置くことを認めるなら国境争いになっている土地を譲る」という最後通牒を送った[303][304]。ズールー族からの返事はなく、現地イギリス軍は本国に独断でズールー戦争を開始した。装備のうえではイギリス軍が圧倒的に優位だったにもかかわらず、ズールー族は勇敢に戦い、イサンドルワナの戦いにおいて現地イギリス軍を全滅させた[305][306]。
本国から増援が送り込まれることとなったが、この際にイギリス亡命中のフランス第二帝政時代の元フランス皇太子ナポレオン4世がイギリスに恩返しがしたいと従軍を希望した。首相ディズレーリはフランス第三共和政の反発を恐れて慎重だったが、イギリス軍最高司令官ヴィクトリアがこれを許可した。しかし結局ナポレオン4世は現地でズールー族の槍を食らって戦死した。ヴィクトリアは悲しみにくれる元フランス皇后ウジェニーを慰めつつ、ズールー族を倒す決意を新たにした[307]。
ナポレオン4世の葬儀から10日後にヴィクトリアは植民地の軍備増強を怠った政府の責任であるという叱責の書簡をディズレーリ首相に送った[308]。これを受けてディズレーリ首相は更なる大部隊を現地に送りこみ、ついに1879年8月末にズールー王国首都ウルンディを陥落させ、ズールー族をイギリス支配下に組み込んだ[307]。
しかしズールー族の脅威がなくなったことでボーア人がトランスヴァール共和国再独立を求めてイギリスに対して蜂起し、現地イギリス軍はこれに敗れた結果、首相ウィリアム・グラッドストンはヴィクトリアと保守党の不興を買いながらもトランスヴァールからの撤退を決意した。ヴィクトリア女王の宗主権という条件付きで1881年8月にトランスヴァール共和国独立を認めることとなった[309][310]。
エジプト保護国化
1875年にディズレーリ首相はイギリス船籍の喜望峰ルートに代わって増えていくエジプトからインドへ向かうルートを確保するため、フランス資本で作られたスエズ運河に注目するようになった[311]。ディズレーリは友人のライオネル・デ・ロスチャイルド男爵に協力を依頼してエジプト副王からスエズ運河を買収し、ヴィクトリア女王に「陛下、これでスエズ運河は貴女の物です。フランスに作戦勝ちしました」と報告した[312][313]。
スエズ運河買収でエジプトが財政的に破綻し、1876年にはエジプト財政は英仏の共同管理下に置かれることになり、イギリス人・フランス人がエジプトの財政担当の閣僚として入閣していった[314][315]。エジプトの名目上の宗主国オスマン=トルコ帝国は手に負えないエジプトの宗主権をイギリスに譲渡したがっていたが、イギリスとしては「インドへの道」エジプトがフランス一国の影響下に置かれないようにすることだけが目的だったので面倒な地域の領有は望まなかった[314]。
1881年2月にエジプト人将校の待遇をトルコ人将校と同じにすることを求めるアフマド・オラービー大佐の指揮の下にオラービー革命が発生し、エジプト副王タウフィークは1882年2月にオラービーを陸相とする「祖国党」内閣を誕生させることを余儀なくされた[316]。オラービーは反トルコ、反ヨーロッパ的な民族主義者であり、ヨーロッパ人株主への支払いを停止し[317]、さらに1882年4月にオラービー暗殺を企てたとして50名のトルコ人将校を逮捕した。オラービー政府と副王・英仏勢力の対立は深刻化した[314]。
6月11日、アレクサンドリアでヨーロッパ人50人がオラービー軍に虐殺される事件が発生した。これについてヴィクトリアは「キリスト教徒が咎めなくして殺されている」と主張してグラッドストンに武力介入を要求し、グラッドストンもしぶしぶ武力介入を決定した[317]。この戦いは9月13日のテル・エル・ケビールの戦いにおいてイギリス軍がオラービー軍を壊滅させた結果、オラービーがイギリスに降伏して終結した[318]。
この戦いに皇太子バーティが従軍を希望していたが、ヴィクトリアはこの不健康な肥満体の皇太子がそんな不衛生な土地へ行ったらすぐに病を患ってくるだろうと心配していた[317]。それにそもそもヴィクトリアは皇太子の能力をまったく信用していなかった[315]。ヴィクトリアは皇太子の代わりにアーサー王子を王家代表で出征させた[315][319]。アーサー王子らエジプト遠征軍が帰還するとヴィクトリアは彼らが持ち帰ってきたオラービーが使用していた絨毯の上に立って勝利を誇示し、アーサー王子らに勲章を与えた[320][321]。
この戦いの後もエジプトは形式的にはオスマン帝国に忠誠を誓う副王の統治下にあったが、実質的支配権はイギリス総領事クローマー伯爵が握るようになった[322]。彼の下にインド勤務経験のある英国人チームが結成され、エジプト政府の各部署に助言役として配置された。エジプト政府は全面的に彼らに依存した[323]。イギリス人らは副王アッバース2世を傀儡にして税制改革からナイル川の運航スケジュールまであらゆることを自ら決定した[322]。スーダンで発生したマフディーの反乱の鎮圧にエジプト軍が動員された際、アッバース2世には何も知らされず、彼は出兵の翌日になって酔っ払った英国軍将校からそれを聞かされるような始末だった[323]。
-
1880年のスエズ運河。
-
テル・エル・ケビールの戦いでオラービー軍に突撃をかけるイギリス軍を描いた絵
-
オラービー軍を蹴散らしてアレクサンドリアを制圧するイギリス軍の配下エジプト正規軍
マフディーの反乱、ゴードン将軍の死

ついで1882年にはエジプト支配下スーダンでイギリスに支配されたエジプトに対する反発が強まり、マフディー(救世主)を名乗ったムハンマド・アフマドによるマフディーの反乱が発生した[324][320][325]。
反乱の第一報を聞いたヴィクトリアはエジプトの反乱と同様にこれも武力で鎮圧すべきと考えたが[326]、グラッドストンはスーダンに大して関心を示さず、「エジプト問題とスーダン問題は別問題」としてできる限り不干渉の方針を取った[327]。1883年9月イギリス軍将軍ヒックス率いるエジプト軍がマフディー軍に惨敗したが[325][327][326]、それでもグラッドストンにはイギリス本国軍やインド軍を派遣する意思はなく[328]、エジプト守備軍のスーダンからの撤退を指揮する人物として「チャイニーズ・ゴードン」[# 8]の異名を取っていたチャールズ・ゴードン少将をスーダン総督に任じてハルトゥームに派遣した[326][330][331]。
だがゴードン将軍にはそもそも撤退の意思がなく、またマフディー軍により電線が切られて本国からの指示を受け取れなくなったことにより、グラッドストン政府の意思に反して同地に留まり、マフディー軍に包囲された[332][326]。イギリス世論はゴードン救出を求める声に沸き立ち[332]、ヴィクトリアもゴードン救出を政府に命じたが、グラッドストンは応じなかった[326]。しかしこれについては閣内でも意見が分裂しており[333]、やがて陸相ハーティントン侯爵が焦燥しはじめ、辞職を盾にゴードン救出を求めた結果、ついにグラッドストンも折れ、8月にスーダン遠征軍派遣が決定された[334]。
しかし遠征軍は間に合わず、1885年1月26日にハルトゥームは陥落してゴードンはマフディー軍に殺害された。この報を聞いたヴィクトリアは激怒して暗号電文ではなく通常電文でグラッドストン政府を叱責する電報を送った[335][336][337]。ヴィクトリアは2月末に何としてもスーダンを奪還してゴードンの仇を取るべしと命じたが、グラッドストンは4月の閣議で「マフディー軍は意気揚々としており、今はスーダン奪還の時期ではない」と決定した[338]。グラッドストンの態度に怒り心頭になったヴィクトリアはディズレーリの命日にあたって「親愛なるビーコンズフィールド伯爵が生きていてくれたなら」と日記上で嘆いている[338]。
ゴードンの戦死で世論や議会はグラッドストンへの不満を高め、彼の第三次内閣が崩壊する一因となった。ゴードンは「帝国の殉教者」に祭り上げられ、イギリスがエジプト支配を手放すことはプライドにかけてできなくなった[339]。1895年頃からイギリスはスーダン奪回を最優先課題とするようになり[340]、結局ゴードン戦死から13年後の1898年になってイギリス軍はスーダンに軍を送ってマフディー軍を撃破している[341]。そのためにそれ以外の地域の植民地争いを一時的に収束させようと「栄光ある孤立」を再考さえした。具体的には1898年にロシアが提唱する中国分割案、ドイツが提唱するトルコ分割案をそれぞれ承諾し、彼らに譲歩する姿勢を示した[340]。
セシル・ローズとジェームソン侵入事件

ケープ植民地では1890年よりセシル・ローズが首相を務めていた。彼はトランスヴァール共和国の北方にローデシアと呼ばれるイギリス植民地を作り、最大規模のイギリス特許会社を創設した男だった。ヴィクトリアと謁見した際に最近何をしていたのか下問されると「陛下の御料地に属州を二つ追加しておりました」と大真面目に述べるような強烈な帝国主義者だった[342]。
ローズには北アフリカのエジプト・カイロと南アフリカのケープ植民地を鉄道で繋いでアフリカ大陸を横断する大英帝国通商路を建設するという壮大な計画があった[343]。だがこの計画に邪魔なのは反英的なボーア人国家トランスヴァール共和国であった。トランスヴァールは隣接するポルトガル領モザンビークの港と鉄道で通じており、英国領土を通商路に使う必要がない国だった[344]。折しもトランスヴァール共和国のウィットウォーターズランドで金鉱が発掘され、ヨハネスブルグの町が建設されてトランスヴァール共和国は潤い始めていた[345]。ローズはウィットウォーターズランドの金鉱を奪うべきことをヴィクトリアに上奏していた[346]。だがイギリス本国政府は1890年代に入っても白人国家に対しては露骨な帝国主義を行う気にはなれず、トランスヴァール共和国に対しては弱腰だった[344]。
1895年末から1896年初頭にかけてローズの友人であるローデシア行政官レアンダー・スター・ジェームソン率いる500名ほどの騎馬警察隊が突然トランスヴァール共和国へ侵入を開始したが、計画があまりに杜撰すぎて早々に包囲されて降伏した(ジェームソン侵入事件)[347][348][349][350]。イギリス政府は公式にはこのジェームソンの行動を批判し、セシル・ローズも「20年来の友人にこんな事件を起こされて破滅させられるとは」と語って無関係を装ったが、彼は退任を余儀なくされた[351][352]。ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世はトランスヴァール共和国大統領ポール・クリューガーに宛てて祝電を送っている[352][353]。
だがイギリスの国民世論はローズやジェームソンたちの行動を称賛していた。ヴィクトリアも複雑な思いでおり、とりあえず祝電を送ったヴィルヘルム2世に対して「貴方がいつも多大な愛情を捧げ、また手本にしていると言ってくれている祖母より」との書き出しで「貴方の書状が英国民に悪い印象を与えている」とする忠告文を送った[354]。イギリス政府が処罰を行う事を条件にトランスヴァール共和国はジェームソンらを釈放した。これを聞いたヴィクトリアはクリューガー大統領に「貴方の寛大な処置は南アフリカの平和に寄与するでしょう」というメッセージを送っている[355]。
ボーア戦争
しかしジェームソン侵入事件以降、イギリスとトランスヴァール共和国の関係は悪化の一途をたどった。1898年2月のトランスヴァール共和国大統領選挙でクリューガーが四選するとケープ植民地高等弁務官アルフレッド・ミルナーはトランスヴァールとの交渉による和解の見込みはないと判断してトランスヴァールとの戦争を煽るようになった[356]。ミルナーの高圧的な要求に激怒しクリューガー大統領は同じボーア人国家オレンジ自由国と結託してイギリスと戦争する決意をした[357]。
ボーア人の祖先の国であるオランダの女王ウィルヘルミナが戦争回避を望む手紙をヴィクトリアに送ったが、ヴィクトリアは「私も戦争は避けたいですが、私に保護を求めてくる臣民を私は見捨てることはできません。すべてはクリューガー大統領次第です」と回答した[358]。1899年10月9日トランスヴァール共和国から高圧的な最後通牒を受けてソールズベリー侯爵は同国との交渉打ち切りを決意し、開戦やむなしとの結論を下した。ヴィクトリア女王もそれを支持した[359]。
かくして19世紀イギリス最後の戦争ボーア戦争がはじまった。イギリス軍は6週間でケリを付けるつもりであったが、ボーア人のゲリラ戦術に苦しめられ、勝利を得るまでに2年6カ月もかかった[360][361]。ボーア戦争の損害は甚大であった。2億3000万ポンドという膨大な戦費が費やされて、イギリス人・ボーア人側双方とも戦死者・戦病死者2万人を超え、またイギリスはボーア人ゲリラへの支援を防ぐため各地に強制収容所を創設してボーア人婦女子を収容した結果、そこでも2万人もの死者が出た[362][360]。
多くのイギリス人兵士が死傷しているという報告を受けたヴィクトリアはインド人兵士を戦わせるべきであると考え、インド藩王たちに高位の勲章を与える代わりにインド人兵士を南アフリカの戦地へ続々と送らせた[363]。
この悲惨な戦争はこれまで成功に継ぐ成功で帝国主義に輝かしいイメージしか持たなかったイギリス人の心が初めて折れた戦争となった[362]。ボーア戦争は1902年5月に終わったが、その時にはヴィクトリアはすでに崩御していた。
-
1899年12月11日、マガースフォンテインの戦いで装甲列車から銃撃するイギリス軍
-
1900年1月24日、スピオンコップの戦いで戦死したイギリス兵たち
-
ボーア人強制収容所
対ヨーロッパ外交
ナポレオン3世の登場とクリミア戦争

フランス第二共和政で大統領に選出されたルイ・ナポレオン・ボナパルトは議会と対立を深める中で1851年にクーデタを起こして成功させ、1852年に皇帝に即位してナポレオン3世となった[364]。ナポレオン3世のクーデタの際にイギリスは中立を宣言していたが、パーマストン外相が独断でナポレオン3世にクーデタ成功の祝電を送ったため、ヴィクトリアはラッセル首相に彼の解任を求め、首相もそれに応じた[365][366]。1852年12月にロンドンで締結された秘密議定書によってイギリス、プロイセン、オーストリア、ロシアは皇帝ナポレオン3世を承認したが、ロシア皇帝ニコライ1世はナポレオン3世に王号を認めず、ナポレオン3世を苛立たせた[367]。
ロシア帝国は当時崩壊寸前だったオスマン=トルコ帝国の切片を拾い上げる目的で当時オスマン領だったバルカン半島に在住するロシア正教徒の保護権を求めてオスマンと対立を深めていた。これに対抗してナポレオン3世はオスマンに加担するようになり、オスマンからエルサレムのローマ・カトリック教徒の保護権を認められた[367][368]。オスマンの態度に激怒したロシア軍は1853年7月からオスマン領へ侵攻を開始した[368]。11月に両国が宣戦布告してクリミア戦争が始まった[369]。
アバディーン伯爵内閣は閣内分裂状態で初めどちらに付くべきか結論が出なかった[369]。だが海洋の覇者イギリスとしてはロシアが黒海から地中海に出てきたり、あるいは北方のバルト海を支配することは避けたかった[370]。ヴィクトリアもロシア軍の地中海南下に危機感を露わにしていた[371]。ナポレオン3世が英仏共同でロシアに最後通牒を突きつけようと提案してきたこともあり、結局イギリスはそれに乗ることになった[371]。最後通牒で一カ月以内の占領地からの撤収をロシアに求めたが、ロシア皇帝はこれを無視したため英仏はオスマン側で参戦した[372][370]。
しかし40年間ヨーロッパでの戦闘経験がないイギリス陸軍は脆弱であり、しかも英仏軍はナポレオン戦争を引きずってどこかギクシャクしていた[373]。戦争は泥沼化し、前線は多くの死傷者、病人を出した。ヴィクトリアは王女や女官たちとともに前線の兵士たちのためにマフラーや手袋を編んだ[374]。戦死者の寡婦に弔慰状を書く事にも精を出した[374]。1854年にはクリミア・メダルを制定し、閲兵式において兵士たちに自ら授与した。負傷兵の慰問にも出かけた。またプロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世に書状を送り、最低でも中立を保つよう依頼した[375]。
クリミア戦争中の1855年4月16日にナポレオン3世と皇后ウジェニーが訪英した。ヴィクトリアの伯父レオポルド王がルイ・フィリップ王の娘ルイーズと結婚していた関係でヴィクトリアは親オルレアン家であり、革命から生まれ出たボナパルト家を嫌っていたが、ナポレオン3世とウジェニーのことはすっかり気に入ったようだった[376]。二人と別れる際にはヴィクトリアは涙ぐんでお別れの言葉を述べた[377]。同年8月に返礼としてヴィクトリアとアルバート、ヴィッキー、バーティが訪仏した。ヴィクトリアは子供たちも皇帝が好きになったと日記に書いている。バーティはナポレオン3世に「貴方の息子だったらよかったのに」と語ったという[378]。
一方前線ではセヴァストポリ要塞攻防戦でロシア軍と英仏軍が激戦を繰り広げていた。ヴィクトリアは外相クラレンドン伯爵に「ここを陥落させればオーストリアとプロイセンもこちら側で参戦するはず。文明世界を食らう野蛮国ロシアは周辺の列強全てで封じ込めなければいけません」と語った[379]。1855年9月にセヴァストポリ要塞が陥落したことでロシア皇帝アレクサンドル2世は戦意を喪失し、ナポレオン3世の提唱するパリ講和会議を受け入れ、1856年3月30日にパリ条約が締結されて終戦した[380]。だがこれはイギリスの意に反する形で行われ、ヴィクトリアはナポレオン3世に不信感を持つようになった[381]。とはいえイギリスも一人で粘るわけにはいかず結局この条約に追従する羽目になった[382]。
しかしパリ条約は双方利益が少なく、これでは何のために多くのイギリス人の命が失われたのか分からないとヴィクトリアは不満だった。伯父レオポルド王に宛てて「イギリスの目的は野蛮大国ロシアの危険な野望からヨーロッパを救う事です。オーストリアとプロイセンが1853年の段階でロシアに断固たる姿勢をとっていたらこんなことにはならなかったのに」と書いた[382]。
-
1855年パリ。訪仏したヴィクトリアとアルバートの歓迎式典を描いたウジェーヌ・ラミの絵画
-
クリミア戦争の負傷者を慰問するヴィクトリア、アルバート、バーティ皇太子、アルフレッド王子を描いたジェリー・バレットの絵画
-
ロシア軍の突撃を防ぐ第93歩兵連隊の「シン・レッド・ライン」を描いたロバート・ギブの絵画
ビスマルク、ナポレオン3世との対立

ヴィクトリアの長女ヴィッキーは1858年にプロイセン王国国王代理ヴィルヘルム王子(後のヴィルヘルム1世)の長男フリードリヒ王子(後のフリードリヒ3世)と結婚した。1861年にヴィルヘルム1世がプロイセン王に即位し、1862年9月にはオットー・フォン・ビスマルクがプロイセン宰相となり、プロイセンは軍拡・ドイツ統一に乗り出した。
だがドイツ統一をめぐっては大ドイツ主義(オーストリア中心の統一)と小ドイツ主義(プロイセン中心の統一)の対立があった。1863年にオーストリアは大ドイツ主義的なドイツ連邦改革を行おうとフランクフルトでドイツ連邦諸侯会議を開催するもプロイセンが反発して出席を拒否し対立が深まった。ヴィクトリアは1863年8月にアルバートの銅像の完成記念にザクセン=コーブルク=ゴータ公国を訪問したが、この際にコーブルクまで彼女に会いにやってきたプロイセン王ヴィルヘルム1世やオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世と会見した。ヴィクトリアは両国君主に協調を求めたが、ヴィルヘルム1世もフランツ・ヨーゼフ1世もにべもなく自国の譲歩を拒否した[383]。
1863年11月にデンマーク王に即位したクリスチャン9世がロンドン議定書に違反してシュレースヴィヒ公国へのデンマーク憲法の適用を強行したのに対して、プロイセンとオーストリアはデンマークにロンドン議定書を守らせるとしてシュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争を開始した。皇太子バーティはデンマーク王女を妃に迎えており、一方長女ヴィッキーはプロイセン皇太子の妃となっていた[384]。だがヴィクトリアにとって決定的なことは生前アルバートがシュレースヴィヒ=ホルシュタイン問題で常にプロイセンを支持してきたことであり、彼女もその立場を踏襲した。大臣たちに対して「ヨーロッパの平和のため重要なことは一つ。自らこの事態を招いたデンマークを支援しないことです」と主張した[385]。閣内でも「平和派」が主導権を握り、最終的にイギリスはデンマークを見殺しにすることになった[385]。
だがプロイセンへの肩入れもそこまでだった。その後のヴィクトリアはプロイセンへの警戒感を強めた。彼女はシュレースヴィヒやホルシュタインを併合しようとしているプロイセンに強い怒りを感じていた。ヴィルヘルム1世に宛てて「この恐ろしい時期に私も口を閉ざすわけにはいきません。貴方はある男に騙されているのです。」と書いて送った[386]。1865年には伯父レオポルド王への手紙の中で「プロイセンは極悪非道の限りを尽くしています。不愉快千万です」と怒りを露わにしている[387]。プロイセンは小ドイツ主義統一を確固なものとするため1866年に普墺戦争を起こし、オーストリアを打倒して北ドイツ連邦を樹立した。この際に従兄妹であるゲオルク5世(カンバーランド公)が国王として君臨するハノーファー王国はプロイセンに併合された[388]。
一方ナポレオン3世は1863年に彼の伯父を否定するウィーン体制を破壊しようと1815年のウィーン議定書とパリ条約の改正のためにパリで国際会議を開催することを提唱した。もともとクリミア戦争末の裏切りでナポレオン3世に不信感をもっていたヴィクトリアはこれによって本格的に彼を嫌うようになった。ヴィクトリアはこのナポレオン3世の提案を「無礼千万」と非難している[381]。
ヴィクトリアはビスマルクとナポレオン3世の二人こそがウィーン体制を破壊する元凶と確信した[389]。
普仏戦争
1867年春にルクセンブルクをめぐって普仏戦争の危機が高まる中、ヴィクトリアは介入に消極的なダービー伯爵首相やスタンリー外相に喝を入れてロンドン会議を開催させ、ルクセンブルクを永世中立国にすることで危機を収束させた。だがビスマルクは南ドイツ諸国を取り込むためにフランスとの戦争を欲していた。結局スペイン王位継承問題を利用したビスマルクの策動で1870年にナポレオン3世はプロイセンへの宣戦布告に追い込まれ、普仏戦争が勃発した[390]。ナポレオン3世は緒戦でプロイセン軍の捕虜となり、完全に失脚した。ビスマルクは戦争で高揚したドイツ・ナショナリズムを背景にプロイセン王ヴィルヘルム1世をドイツ皇帝に即位させてドイツ帝国を樹立した。
この間ヴィクトリアにできたことはベルギーの中立を守ることをプロイセン、フランス双方に約束させること[391]、イギリスへの亡命を希望するウジェニー皇后を受け入れてやること[392]、そして新生ドイツ帝国がフリッツやヴィッキーの望む形になる事を祈ることのみだった[392]。1871年3月にプロイセン軍から釈放されたナポレオン3世の亡命も受け入れた。彼はウィンザー城でヴィクトリアと会見したが、落胆しきって涙ぐんでいたといい、ヴィクトリアは日記に「前回(1855年)勝利者としてここにやってきた時の彼と何という違いか」と書いている[393]。
露土戦争
1877年にバルカン半島支配権をめぐってロシア・トルコ間で発生した露土戦争でディズレーリ首相は親トルコの立場を取ったが、トルコのキリスト教徒への残虐行為から議会から強い反発を受けた。ディズレーリを寵愛するヴィクトリアさえもがディズレーリに「なぜトルコのキリスト教徒虐殺に抗議しないのか」と詰め寄っている[394]。一方でヴィクトリアはトルコ批判者が主張するようなトルコを処罰してその国土を分割せよというような案はロシアを利するだけとして否定的だった[394]。また「トルコの野蛮性」を盛んに主張する英国世論が「ロシアの野蛮性」を主張しないことも不可思議に思っていた[395]。
露土戦争は終始ロシア軍の優位で進み、ヴィクトリアはロシアに対する危機感を強めた。1878年1月にはディズレーリに宛てた書状の中で「私が男だったら自ら出ていって、あの憎たらしいロシア人どもをぶちのめしてやるのに」と激昂している[396]。ソールズベリー侯爵夫人はこの頃のヴィクトリアの状態を「自制心を失っており、閣僚たちをこづきまわしては戦争へ持っていこうとした」と評している[397]。
結局イギリスは臨戦態勢に入りながらも参戦しないまま、3月にはトルコとロシアの間にサン・ステファノ条約が締結され、バルカン半島にロシア衛星国大ブルガリア公国が置かれることになった[398]。さらにロシアはドイツの支持を当て込んでビスマルクが提唱する露土戦争の戦後処理国際会議ベルリン会議の開催に賛同した。ディズレーリは自らがベルリン会議に出席する決意を固めたが、ヴィクトリアは「ディズレーリは健康を害している。彼の命は私と我が国にとって重要な価値があり、危険に晒されることは許されない」として反対した。だがディズレーリは「鉄血宰相」と対決できる者は自分しかいないと主張して女王を説得した[399]。
ベルリン会議でディズレーリはアジアに通じる大英帝国通商路を守るために全力を尽くし、さらにキプロスを獲得して東地中海航路を確保した[400]。これにはビスマルクも「あのユダヤ人の老人はまさに硬骨漢だ」と驚嘆したという[399]。
ビスマルクとの会見と娘婿の死
1888年3月にドイツ皇帝ヴィルヘルム1世が崩御し、娘婿フリッツがフリードリヒ3世としてドイツ皇帝に即位した。しかし彼は喉頭癌を患っており、先は長くなかった。4月にヴィクトリアはフリードリヒ3世のお見舞いも兼ねてイタリア、オーストリア、ドイツ歴訪の外遊に出た[401]。
ドイツに到着すると宰相オットー・フォン・ビスマルクを引見した。ヴィクトリアはビスマルクが噂に聞くより紳士的であったことに驚いたという[402]。ビスマルクはオーストリアがロシアに攻撃されたらドイツはオーストリアを助けねばならない。ロシアはフランスと組むであろうから、そうなるとイギリスが重要になってくると述べた。これに対してヴィクトリアはフランスは政権が不安定なので早々戦争には乗り出さないだろうと無難に返事をした[402]。またヴィクトリアはヴィッキーとフリッツを支えてほしいと依頼した。ビスマルクは自由主義者のこの二人を全く信用していなかったが、その場の口先ではもちろんですと返答した[403][404]。フリッツとヴィッキーの長男である皇太子ヴィルヘルム(愛称ウィリー)についても話が及び、ヴィクトリアは「ウィリーはまだ未熟であり、イングランド以外にも外遊させて見聞を広げさせるべきではないか」と述べたが、ビスマルクは「殿下はまだ文政をご存じでないですが、もともと頭の良い方なので水の中で放っておいて差し上げればすぐにも泳げるようになりましょう」と回答した[403][404]。
ついでフリードリヒ3世に面会したが、彼はすでに死にかけの状態でしゃべることはできなかった。ヴィクトリアは彼に接吻し、回復したら是非イングランドへ訪問をと要請した。また駅まで出迎えに出たヴィッキーを慰めた。ヴィクトリアは日記に「ゆっくりと駅を離れる汽車の窓越しに顔をくしゃくしゃにしたヴィッキーを見ながら、私はあの子を待ち受ける恐ろしい運命を思ってぞっとした。哀れな我が子よ。貴女の苦難を少しでも軽くするためなら私はどんなことを厭いません。」と書いている[404]。
ヴィルヘルム2世との対立

1888年6月、フリードリヒ3世が在位99日にして崩御し、ウィリーがヴィルヘルム2世として第三代ドイツ皇帝に即位した[405]。ヴィクトリアは早速この孫に「私は断腸の思いでいます。気の毒な貴方のお母さんのために出来るだけのことをしなさい。また高貴で慈愛にあふれ、この世で最も偉大であった貴方のお父さんを手本となさい」という手紙を送った[405]。この時にはヴィルヘルム2世も「最愛のおばあちゃま」宛てに「母の願い事を叶えるために最大の努力をしているところです」と母を重んじているかのような返信をした[405]。だが反自由主義者のヴィルヘルム2世とビスマルクはヴィッキーを「イギリス女」として冷遇していた。ついにヴィッキーはイギリスに帰りたいと吐露する手紙をヴィクトリアに送るようになり、それを読んだヴィクトリアは日記に「腸が煮えくりかえる思いである」と書いている[406]。
ビスマルクの外交手腕でドイツ帝国はヨーロッパ政治の中枢になっていたが、海軍力ではイギリスに溝を空けられていた。ドイツの工業力は飛躍的に伸びており、強力な海軍を建設することも不可能ではなかったが、ビスマルクはあくまで外交で各国を操ってドイツの国際的地位を優位にしようと考えていたため、他国に警戒感を強めさせる過大な軍事力は邪魔だった。一方ヴィルヘルム2世はいつまでもドイツの海軍力をイギリスの下にしておくつもりはなく、イギリスを越える大植民地帝国を創り上げるつもりだった。それを邪魔立てするつもりなら祖母の国との対決も辞さない覚悟だった[407]。ヴィクトリアはヴィルヘルム2世が6歳の頃「『あの恐ろしいプロイセン流の誇りと野心』を持たないよう育ってほしい」と日記の中で祈願していたが、その願いは叶わなかった[408]。
1889年4月、ヴィルヘルム2世がウィーンを訪問していた際に英国皇太子バーティもウィーンを訪問し、バーティは甥に会談を申し込んだが、ヴィルヘルム2世は自分がまず会見して敬意を表すべき相手はオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフであり、まだ皇太子に過ぎないバーティではないとして拒否した。この件にヴィクトリアもバーティも「叔父にあたる者に対して無礼である」と激怒した[409]。この騒動は8月にヴィルヘルム2世が訪英してバーティと和解することで何とか解決したが、ヴィクトリアは英独関係に不安を感じるようになり、ビスマルクに自分の肖像画を送るなどして彼を引き込もうとし、ヴィルヘルム2世を抑えさせようとしたが、ビスマルクは1890年にヴィルヘルム2世により辞職に追いやられた[410]。 ヴィルヘルム2世はヴィクトリアやバーティが尊属として上から目線で語ってくることが気にくわず、「イギリスは自分を皇帝として処遇していない」と批判するようになった。それに対してヴィクトリアは「私と皇太子は、孫であり甥である彼とは親密な関係にあった。にもかかわらず『皇帝陛下』としての待遇を公私問わずに要求してくるとは狂気の沙汰である。」と怒り心頭に語っている[411]。しかしこうした見解はヴィルヘルム2世だけのものではなく、多くのドイツ国民も自分たちの皇帝を子供扱いするイギリス女王に無礼なりと感じている人が多かった[406]。
ヴィルヘルム2世は年に一度訪英したが、ヴィクトリアにとっては煩わしい行事になり、外務官僚たちにとっても外交儀礼に苦心させられる行事となった[412]。前述したようにヴィルヘルム2世は1896年ジェームソン侵入事件の際にトランスヴァール共和国大統領クリューガーに祝電を送った。「イギリスに悪気があってしたのではない」というヴィルヘルム2世の弁明をヴィクトリアも一応受け入れたが、ヴィクトリアの内心の怒りは強く、その後様々な理由を付けてヴィルヘルム2世の訪英を拒否するようになった。ようやくヴィクトリアの勘気が解けてヴィルヘルム2世が訪英を許されるようになったのは1899年になってのことだった[413]。
崩御

ヴィクトリアは1900年4月のアイルランド訪問でだいぶ疲労した様子を見せるようになった[414]。同年晩夏頃からは不眠症に苦しむようになり[415]、やがて食事もあまり取れなくなっていった[416]。さらに失語症を患うようになった[414][417]。そのような状態でもヴィクトリアは日々増えるボーア戦争の戦死者の遺族に慰問状を書く激務に励んだ[418]。だが日記の中では「私もそろそろ休息が許されてもいい頃です。81歳でしかも疲れ果てているのですからね」と弱音を吐くこともあった[419]。
1901年に入ると脳出血を起こすようになった[420]。1901年1月16日、オズボーン・ハウスにおいてヴィクトリアはベッドから起き上がれなくなった[421]。侍従医たちは崩御が近いと看做し、1月18日にヴィクトリアの子らに召集がかかった。この時七男コノート公アーサーはベルリン滞在中で、ヴィルヘルム2世はその報を聞くと「ホーエンツォレルン王朝200年祭」を放り出してコノート公とともに緊急訪英した[422]。
四女ルイーズによると1月21日にヴィクトリアは「まだ死にたくない。私にはしなければならないことがまだ残っている。」と述べたという[423]。1月22日正午頃、枕元にすすり泣きながら立つ皇太子バーティの存在に気付いたヴィクトリアは、手を広げるような仕草をして「バーティ」と呟いたという。これが判別できる彼女の最期の言葉だった[423]。同日午後4時頃、ヴィクトリアの息遣いが荒くなったため、侍従医リードと買ってでたヴィルヘルム2世の二人掛かりで、ヴィクトリアが息をしやすいように頭を支え、崩御までの2時間半その体勢でいた[424]。ウィンチェスター主教ランダル・デーヴィッドソンが祈祷を捧げ、子供たちや孫たちが見守る中、6時半頃、ヴィクトリアは81歳で崩御した[424]。
ヴィクトリアの崩御とともにイギリス国王となったバーティは最初の枢密院を開くため、1月23日早朝にオズボーン・ハウスを発ってロンドンのセント・ジェームズ宮殿へ向かった。バーティがロンドン滞在で不在の間オズボーン・ハウスの管理はヴィルヘルム2世に任された。イギリス王室の宮殿が非公式にとはいえ外国君主に委ねられるのは極めて異例だった。ヴィルヘルム2世は彼女の棺の製作と棺を安置する部屋の模様替えを指揮した。この際に彼はウィンチェスター主教に対して「彼女と一緒にいる時、祖母であるという事は常に意識してきた。祖母として愛そうという思いもずっとあった。しかし話が政治に絡むとその瞬間から私たちは君主同士として対等の関係となった。」と語っている[425]。
バーティは枢密院会議で自らの王名をエドワード7世に定めると発表した。ファーストネームの「アルバート」にしなかったのは「アルバートといえば誰もが父を思いだすようにしたかった」からだという[425]。枢密院会議を終えたエドワード7世は1月24日午後にはオズボーン・ハウスへ戻った[425]。エドワード7世とコノート公の二人がかりでヴィクトリアの遺体を持ちあげて棺の中に入れた。チャペルに保管された棺にはヴィルヘルム2世の発案でイギリス国旗ユニオンジャックが掛けられ、ヴィルヘルム2世は記念としてその国旗をもらって帰った[426]。
大葬はヴィクトリアの希望通り軍葬で行われた。2月1日、ヴィクトリアの棺は霊柩船でポーツマス、特別列車でヴィクトリア駅まで移送された。そこからエドワード7世とヴィルヘルム2世を先頭にした軍隊の葬列を伴って馬車でセント・ジェームズ宮殿まで移送された[427]。
女王の大葬は2月4日まで行われた。大葬後、エドワード7世の意向で「ムンシ」はじめインド人侍従たちは全てインドへ送り返されることになり、また「ムンシ」に関する文書も焼却処分された。ジョン・ブラウンの銅像も奥深くに隠された[428]。それ以外にもヴィクトリア思い出の品々が次々と宮殿内から片付けられていった[428]。
ヴィクトリアがエドワード7世に引き渡した王位は、彼女がウィリアム4世から引き継いだ時の王位よりも政治権力の面では大きく弱体化した物ではあったが、国民からの人気はかつてないほど大きくなっていった[223]。
人物

体格・体質
ヴィクトリアの身長は145センチ足らずであった。一方体重はアルバートとの結婚前にすでに56キロ、1880年代には76キロになっていた[429]。
ヴィクトリアは大変な暑がりであり、宮殿内では女王臨御の際には必ず侍従たちが前もって窓を開けておくのが常であった[429]。
直情径行
ヴィクトリアは直情径行、我がまま、短気で、理屈は通らない人物だった[430][4]。
それについてアルバートは「ヴィクトリアは短気で激昂しやすい。私の言う事を聞かずにいきなり怒りだして、私が彼女に信頼を強要している、私が野心を抱いている、と非難しまくって私を閉口させる。そういう時私は黙って引き下がるか(私にとっては母親にしかられて冷遇に甘んじる小学生のような心境だが)、あるいは多少乱暴な手段に出る(ただし修羅場になるのでやりたくない)しかない。」と語っている[431]。ヴィクトリア自身も自らが「矯正不可能」なほど「意見されると感情が激高しやすい性格」であることを語ったことがある[431]。
ヴィクトリアから寵愛を受け続けたディズレーリは「女王陛下とうまく付き合うコツは、決して拒まず、決して反対せず、時々物忘れをすることだ」と語っている[5]。
教養の浅薄さ
またアルバートは自分に比べてヴィクトリアの教養が浅薄であることを気にかけていた。アルバートは科学や技術に精通していたが、ヴィクトリアはその分野の知識は皆無であり、、そういう話題を避けたがった。芸術や音楽の分野には多少精通していたものの、それもやはりアルバートの高い教養には遠く及ばないレベルだった。アルバートはこれをヴィクトリアのガヴァネスだったルイーゼ・レーツェンの教育のせいであると考えており、それもアルバートがレーツェンを宮廷から追放した理由であった[432]。
「ドイツ人」のイギリス女王
ヴィクトリアにはイギリスよりドイツの血の方がはるかに濃く流れている。計算上ヴィクトリアに流れるステュアート家の血は256分の1に過ぎず、残りはほとんどドイツ人の血であった[433]。
そのためかヴィクトリアは日ごろから親独派だった[434]。ドイツから来た夫アルバートも同様であったので女王夫妻はドイツ語を日常会話にすることが多かった[435]。アルバートはヴィクトリア以上にドイツ人としての意識が強く、彼は最終的にドイツ諸国、イギリス、ベルギー、デンマーク、スイスなど「ドイツ民族諸国」を一つにして、ロシア、フランス、およびヨーロッパの民主化の風潮に対抗する勢力にしたいと考えていたという[436]。
女王夫妻はイギリスの国益を無視してプロイセンを支援しドイツ統一に協力していると疑うイングランド人も多かった[437]。
「立憲君主」について
彼女が即位した際の英国王位はいまだ大きな政治的権力を備えていた。アルバート公存命期に王権は伸長したが、彼の死とともに王権は弱体化し、ヴィクトリア朝末期にはイギリス史上かつてないほど王権は小さくなり、立憲君主制が確立されることになった。しかしヴィクトリア当人は自分が持っている物を手放すことに非常に抵抗感を感じる性質であり[438]、立憲君主になる意思などなく、受動的にそうなってしまっただけであった[439]。
女王が意見する権利は法律で認められているが、ヴィクトリアはその枠に留まるつもりはなく、首相や陸軍大臣を無視して退任した首相や軍部などに政治について積極的に諮問した[125]。また政府が気に入らない法案を推し進めると退位すると脅迫し、自らを批判する者に対しては怒り狂って反撃した[104]。政府や議会の決定を阻止することができないとしても、その頑固さによって遅延させた[440]。
特に女王に独断で政治を進める傾向があったパーマストン子爵に対して「女王の下僕(公務員)や大臣が女王に何も相談せずに行動を起こすことは許さない」という戒めの手紙を送ったことがあった[441]。またその時のパーマストンの上司ジョン・ラッセル首相に対して「1、外務大臣は何を行おうとしているか女王に明確に述べること、女王が何に裁可を与えたか把握するためである。2、一度女王が裁可を与えた場合にはそれ以降外務大臣は独断で政策を変更・修正してはならない。そのような行為は王冠に対する不誠実であり、行われた場合には大臣罷免の憲法上の権限を行使するであろう」と通達している[442][443]。
アルバートもまた立憲君主の枠に収められるつもりはなかった。彼の側近クリスティアン・フリードリヒ・フォン・シュトックマー男爵は「首相は一時的な指導者に過ぎず、君主こそが永遠の指導者である」と考えており、国王には首相を罷免する権限があると考えていた。アルバートは王に首相を罷免する権利があるかどうかは分からないが、あったとしても罷免を実行すれば最終的に王権が危うくなると考えていたと言われる[104]。
ヴィクトリアは君主としての能力が乏しかったが、アルバートにはその能力があった。アルバートは薨去直前の段階ですでに政府にとっても議会にとってもなくてはならない存在となっていた。その彼がもっと長く生存していたならば、イギリスは立憲君主制とはならなかったのではないかという指摘もある[444]。ディズレーリは「アルバート殿下の薨去によって我々は我々の君主を埋めたのである。このドイツ人君主は歴代イギリス王が誰も持たなかった知力と精力でもって21年間我が国を統治した。彼が我が国の長老政治家たちより長生きしたとすれば、彼は我々に絶対君主制をプレゼントしてくれただろう」と語っている[445]。
アルバートの死後、ヴィクトリアの王権は低下する一方であった。それはなんといっても大臣たちの優秀さの賜物であった。彼らは「政治の素人」の彼女が政治に口を出そうとするのを適切に拒否したのである[434]。晩年の彼女は電報を送る権利さえ奪われそうになった[# 9]。
ユダヤ人について

ヴィクトリア即位の頃にイギリス・ユダヤ人は3万人ほどで、うち半数がロンドンで暮らしていたが、ユダヤ人はキリスト教的な価値観や金融業者のイメージのせいで蔑視され、いまだ政治的に差別的な扱いを受けていた[447]。
ヴィクトリアはヒステリックな反ユダヤ主義者ではなく、ユダヤ人への爵位・ナイト爵の授与はヴィクトリア朝時代から開始された。即位間もない1837年11月9日にロンドン市を公式訪問した際、ユダヤ人市長モーゼス・モンテフィオリにナイト爵を授けたのがその最初である[447]。このイギリス史上初のユダヤ人へのナイト爵授与についてヴィクトリアは日記に「正しいと思う事を当然のこととして実行したのは私が最初である。とても嬉しかった。」と書いている[447]。
彼女がとりわけ気に入っていたユダヤ人は首相ベンジャミン・ディズレーリである。ディズレーリは出世のために少年時代にキリスト教に改宗していたが、ユダヤ人をユダヤ教徒ではなく人種(race)ととらえており、自分はユダヤ人種であること、そしてユダヤ人種の優秀性を公言していた[448]。一方ウィリアム・グラッドストンはキリスト教主義的な立場からどこか反ユダヤ主義的であり、ディズレーリ批判を繰り返していたが(たとえばディズレーリの親トルコ外交を「トルコのキリスト教徒虐殺に加担したがっているユダヤ人の本性に根ざしたもの」と批判するなど)、ヴィクトリアはこういうグラッドストンのキリスト教主義的思想を嫌っていた[449]。
一方で1869年にグラッドストンが自由党所属の庶民院議員ライオネル・デ・ロスチャイルドに爵位を与えるべきことを進言してきた際にはヴィクトリアは「ユダヤ貴族は認められない」「貴族は伝統的に地主であるべきで企業家・投機家であってはならない」「准男爵(貴族ではない)までなら許可する」として男爵位以上の授与は拒否している[450]。
しかし1885年7月9日にヴィクトリアはライオネルの息子であるナサニエル・ロスチャイルドに男爵位を与えている。この頃にはロスチャイルド家は所領を手放した貴族たちの土地を買収するようになっており、領民をたくさん従える領主のイメージも付いてきていたため、ヴィクトリアの反発も弱まったものと思われる。先の却下理由の一つである「ユダヤ人貴族は認められない」という点についてはいまだクリアーできていなかったが、恐らくそちらの理由は彼女の中で大きな問題ではなかったのだと思われる[451]。
切り裂きジャック事件について
ヴィクトリアは切り裂きジャックのホワイトチャペル連続殺人事件について興味を持ち、首相ソールズベリー侯爵、内務大臣ヘンリー・マシューズに対して1887年にコナン・ドイルの小説で登場したばかりのシャーロック・ホームズのような捜査を求めた[452]。
ヴィクトリアはマシューズに対して夜に婦人ばかりが襲われていることから一人住まいの男を中心に聞き込みすべきだと主張し、また犯人の逃亡ルートを探すため船に対する捜査や夜警の徹底を求めた[453]。
なお皇太子バーティの長男エディ王子を切り裂きジャックとする噂が巷に流れていたが、恐らくヴィクトリア女王の耳には入れられていない[453]。
その他逸話
- カナダの首都はヴィクトリア女王が選定したが、この時彼女は目をつぶって地図にピンを突き刺した場所を首都に選び、それがオタワだったという[454]。
- 写真好きであり、自分と家族の写真を多く残した。映画フィルムに残っている最初の英国王でもある[433]。
家族
子女

夫アルバートとの間に4男5女の9子を儲けた。子供達をドイツを中心とした各国に嫁がせ、晩年には「ヨーロッパの祖母」と呼ばれるに至る。しかしヴィクトリアは血友病の因子を持っており、子孫の男子が次々と発病した。ヴィクトリアに連なる3代18人の男子のうち10人までが血友病で命を落としている[455]。四男レオポルド[456]と曾孫のロシア皇太子アレクセイが血友病患者として知られる。
- 第一子(長女) ヴィクトリア(愛称ヴィッキー)(1840年-1901年) - ドイツ皇帝フリードリヒ3世皇后
- 第二子(長男) アルバート・エドワード(愛称バーティ)(1841年-1910年) - ハノーヴァー朝第7代英国王エドワード7世
- 第三子(次女) アリス(1843年-1878年) - ヘッセン大公ルートヴィヒ4世大公妃
- 第四子(次男) アルフレッド(1844年-1900年) - ザクセン=コーブルク=ゴータ公・エディンバラ公爵
- 第五子(三女) ヘレナ(1846年-1922年) - シュレースヴィヒ=ホルシュタイン公子クリスティアン夫人
- 第六子(四女) ルイーズ(1848年-1939年) - アーガイル公爵ジョン・ダグラス・サザーランド・キャンベル夫人
- 第七子(三男) アーサー(1850年-1942年) - コノート公爵
- 第八子(四男) レオポルド(1853年-1884年) - オールバニ公爵
- 第九子(五女) ベアトリス(1857年-1944年) - バッテンベルク公ハインリヒ・モーリッツ公妃
ドイツ皇室・ロシア皇室との関係
| 第6代 英国女王 ヴィクトリア | 王配 アルバート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドイツ皇后 ヴィクトリア | 第2代 ドイツ皇帝 フリードリヒ3世 | 第7代 英国王 エドワード7世 | ヘッセン 大公妃 アリス | ヘッセン大公 ルートヴィヒ4世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3代 ドイツ皇帝 ヴィルヘルム2世 | 第14代 ロシア皇帝 ニコライ2世 | ロシア皇后 アレクサンドラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロシア皇太子 アレクセイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄典
イギリス勲章
外国勲章
64年の長きにわたって世界一の大国イギリスの王座に君臨したヴィクトリアだが、女性であるためにいずれの国からも最高勲章は授与されず、勲爵士の称号が伴わない勲章のみを授与されている[457]。最高勲章は彼女の夫であるアルバートが代わりに受けていた[457]。ヴィクトリア自身も同じ女性君主だからとガーター勲章を贈るようなことはせず、スペイン女王イザベル2世がガーター勲章を授与してほしいと打診してきた際にも「私自身もそうであるように騎士の称号を伴う外国の勲章を女性君主は受けることができないのが慣習である」として拒否している[458]。
ヴィクトリアが外国から授与された勲章は以下の通りである[459]。以下、国名五十音順。カッコ内の年代は授与された年。
- エチオピア帝国:ソロモン勲章(1897年)
- スペイン王国:マリア・ルイーザ勲章(1834年)、カルロス3世勲章
- セルビア王国:タコヴォ勲章(1882年)、白鷲勲章(1883年)、聖サヴァ勲章(1897年)
- タイ王国:白象勲章(1880年)、大チャクリー勲章(1897年)
- ハワイ王国:カメハメハ勲章(1881年)
- ヘッセン大公国:金獅子勲章(1862年?)
- ブラジル帝国:ペドロ1世勲章(1872年)
- ブルガリア王国:赤十字勲章(1886年)
- プロイセン王国:ルイーゼ勲章(1857年)
- ペルシア王国 :太陽勲章(授与1873年)
- ポルトガル王国:聖イサベル勲章(1836年)、我らが貴婦人ヴィラ・ヴィコサ勲章
- モンテネグロ公国:ダニーロ1世勲章(1897年)
- ロシア帝国:聖エカチェリーナ勲章(1839年)
ヴィクトリア女王を題材にした作品
映画
- Queen Victoria 至上の恋 - 1997年、イギリス映画
- ヴィクトリア役:ジュディ・デンチ
- ヴィクトリア女王 世紀の愛 - 2009年、イギリス映画
- ヴィクトリア役:エミリー・ブラント
脚注
注釈
- ^ 二番目に在位が長いのは現英国女王エリザベス2世であり、彼女は2012年2月6日に在位60周年を迎えた[3]。外国の君主で在位年数が、ヴィクトリアに匹敵するのは(近代以降では)オーストリアのフランツ・ヨーゼフ1世帝(在位68年)、日本の昭和天皇(在位62年+摂政宮5年)、タイのラーマ9世(※1946年より在位中)がいる。
- ^ 母のザクセン=コーブルク=ザールフェルト公家は11世紀以来エルベ川畔地域を支配したマイセン辺境伯ヴェッティン家の分家エルネスティン家の一流であり、人口6万ほどの小公国の君主であった[9]。
- ^ マーガレット・サッチャー首相による1981年の国籍法改正(父か母がイギリス国籍でなければイギリス国籍は認められない)以前のイギリスでは基本的にイギリス国王の領土内に生まれた者にイギリス国籍が認められていた[13]。
- ^ これまでハノーヴァー朝はイギリス王位とハノーファー王位を兼ねてきたが、ハノーファー王位はサリカ法により男性しか継げないため、ヴィクトリアはイギリス王位しか継げず、ハノーファー王位は叔父カンバーランド公アーネストがエルンスト・アウグストとして受け継いだ。
- ^ ただしアルバートは立憲君主を志向した人物ではなくホイッグ党(自由党)が政権につこうとトーリー党(保守党)が政権に付こうと王権が影響力を発揮できる状態、つまり王権強化を考えていた[103]。彼の王権強化思想はアルバートの顧問になっていたクリスティアン・フリードリヒ・フォン・シュトックマー(de)男爵の影響であった[104]。
- ^ ラテン語の"Reginaet"(女王)と"Imperatrix"(女帝)の略[187]。
- ^ ヴィクトリアはグラッドストンの提出した閣僚人事のうちサー・チャールズ・ディルク(en:Sir Charles Dilke, 2nd Baronet)の大臣任命については彼が共和主義者であるとして拒否した。ディルクは「私が共和主義者だったのは若いころだけで今は立憲君主制論者です」という誓文をヴィクトリアに提出し、それに満足したヴィクトリアは二度と王室費にケチを付けないよう命じたうえでディルクを外務政務次官に任じた[198][199]。
- ^ ゴードンはアロー戦争で活躍し、アロー戦争後に清政府の依頼で清軍の司令官となり、太平天国の乱を平定したためこのあだ名が付いた[329]。
- ^ マフディーの反乱の最中の1885年1月にアブクレアの戦いでイギリス軍がマフディー軍に勝利すると、ヴィクトリアは大喜びして司令官ヴォルズリー将軍に祝電を送ったのだが、それに対して陸相ハーティントン侯爵が女王が陸軍軍人に対してメッセージを出すには陸軍大臣の許可を得て行わなければならないと抗議した。ヴィクトリアは「私が将軍たちに直接伝えたほうが彼らも喜びます。女王が彼女の将軍に対して電報を送る事は何の問題もありません。ハーティントン侯爵は差し出がましく生意気です。女王は相手がだれであろうとも自由に祝電を打つ権利があり、指図を受ける気はありません。女王は機械ではありません」と怒りを露わにした[446]。
出典
- ^ a b c 秦(2001) p.507
- ^ a b 君塚(2007) p.25
- ^ 朝日新聞2012年(平成24年)2月6日夕刊2面。朝日新聞デジタル
- ^ a b 世界大百科事典「ハノーバー朝」の項目 引用エラー: 無効な
<ref>タグ; name "世界大百科事典ハノーバー朝"が異なる内容で複数回定義されています - ^ a b ベイカー(1997) p.182
- ^ a b c d e 朝倉・三浦(1996) p.122
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.524-525
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.67
- ^ ストレイチイ(1953) p.19
- ^ 川本(2006) p.244
- ^ ストレイチイ(1953) p.21-22
- ^ a b 森(1986) p.552
- ^ 川本(2006) p.227-229
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.63-64
- ^ a b 川本(2006) p.3
- ^ 君塚(2007) p.6-7
- ^ a b c ワイントラウブ(1993) 上巻 p.71
- ^ 君塚(2007) p.5-6
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 上巻 p.47
- ^ a b c d e f 君塚(2007) p.10
- ^ a b c ストレイチイ(1953) p.23
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.69
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.73
- ^ a b 君塚(2007) p.11
- ^ a b c d 森(1986) p.553
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.79-80
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.81
- ^ 君塚(2007) p.12
- ^ ストレイチイ(1953) p.26
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.86
- ^ ストレイチイ(1953) p.27
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.87
- ^ a b ストレイチイ(1953) p.36
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.92
- ^ ストレイチイ(1981) p.44
- ^ a b ストレイチイ(1953) p.30
- ^ ストレイチイ(1953) p.29
- ^ ストレイチイ(1953) p.38
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.100
- ^ a b 君塚(2007) p.14
- ^ a b c ストレイチイ(1953) p.32
- ^ a b c 君塚(2007) p.15
- ^ a b 君塚(2007) p.17
- ^ ストレイチイ(1953) p.35
- ^ ストレイチイ(1953) p.27-28
- ^ ストレイチイ(1953) p.27-28
- ^ a b ストレイチイ(1953) p.45
- ^ a b 森(1986) p.554
- ^ ストレイチイ(1953) p.44-45
- ^ 君塚(2007) p.18
- ^ 君塚(2007) p.19
- ^ a b c 君塚(2007) p.20
- ^ ストレイチイ(1953) p.52-53
- ^ a b ストレイチイ(1953) p.53
- ^ 君塚(2007) p.21-22
- ^ ストレイチイ(1953) p.53-55
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.156-158
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.158
- ^ ストレイチイ(1953) p.55
- ^ 君塚(2007) p.23-24
- ^ a b ストレイチイ(1953) p.57
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.159-160
- ^ ストレイチイ(1953) p.58
- ^ ストレイチイ(1953) p.59-61
- ^ ストレイチイ(1953) p.78-81
- ^ ストレイチイ(1953) p.70
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.161
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.156-157
- ^ ストレイチイ(1953) p.65
- ^ a b c 君塚(2007) p.31
- ^ ストレイチイ(1953) p.68
- ^ 森(1986) p.558
- ^ 伊藤・川田(2004) p.247
- ^ 森(1986) p.559
- ^ ストレイチイ(1953) p.71-74
- ^ 君塚(2007) p.32
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.192
- ^ a b ストレイチイ(1953) p.87
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.193
- ^ a b 君塚(2007) p.33
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.194
- ^ a b 伊藤・川田編(2004) p.248
- ^ a b 君塚(2007) p.34
- ^ a b ストレイチイ(1953) p.89
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.196
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 上巻 p.197
- ^ ストレイチイ(1953) p.99
- ^ 君塚(2007) p.38
- ^ ストレイチイ(1953) p.41
- ^ ストレイチイ(1953) p.96
- ^ ストレイチイ(1953) p.97
- ^ a b ストレイチイ(1953) p.98
- ^ 川本(2006) p.7
- ^ 君塚(2007) p.39
- ^ 川本(2006) p.62
- ^ a b 君塚(2007) p.42
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.219
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 上巻 p.231
- ^ 森(1986) p.561
- ^ a b 川本(2006) p.23
- ^ 君塚(2007) p.44
- ^ 川本(2006) p.23-25
- ^ 川本(2006) p.26
- ^ a b c d e f g ヒバート(1998) p.169
- ^ ストレイチイ(1953) p.121
- ^ 川本(2006) p.134-135
- ^ 君塚(2007) p.45
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.261
- ^ a b 君塚(2007) p.46
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.267
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.263-264
- ^ a b ヒバート(1998) p.166
- ^ a b モリス(2008) 上巻 p.226
- ^ モリス(2008) 上巻 p.253-256
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 上巻 p.297
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.296-297
- ^ 君塚(2007) p.49
- ^ 君塚(2007) p.51
- ^ ヒバート(1998) p.166-167
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.297-299
- ^ ヒバート(1998) p.165
- ^ a b ヒバート(1998) p.167
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.312-313
- ^ 君塚(2007) p.50
- ^ a b ヒバート(1998) p.168
- ^ 君塚(2007) p.55
- ^ 長島(1989) p.142-143
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.345
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.358
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 上巻 p.348
- ^ 長島(1989) p.142
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.347
- ^ 君塚(2007) p.52
- ^ a b 君塚(2007) p.54
- ^ 川本(2006) p.63
- ^ 君塚(2007) p.77
- ^ 秦(2001) p.509
- ^ 君塚(2007) p.78-79
- ^ a b 森(1986) p.564
- ^ a b c 君塚(2007) p.82
- ^ 君塚(2007) p.83-84
- ^ ストレイチイ(1953) p.205-206
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.460
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 上巻 p.463
- ^ ストレイチイ(1953) p.206
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.462
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.467
- ^ ストレイチイ(1953) p.207
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 上巻 p.469
- ^ ストレイチイ(1953) p.208
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 上巻 p.471
- ^ 君塚(2007) p.85
- ^ ストレイチイ(1953) p.213
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.10
- ^ a b ストレイチイ(1953) p.215
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 下巻 p.17
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.31
- ^ ストレイチイ(1953) p.214-215
- ^ 君塚(2007) p.89
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.32
- ^ a b c 伊藤・川田編(2004) p.254
- ^ 君塚(2007) p.108
- ^ ベイカー(1997) p.166
- ^ a b 森(1986) p.565
- ^ 君塚(2007) p.106-107
- ^ 川本(2006) p.193
- ^ 川本(2006) p.193-194
- ^ 君塚(2007) p.107-108
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.127-128
- ^ 川本(2006) p.194
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.143
- ^ 君塚(2007) p.97-103
- ^ a b c ワイントラウブ(1993) 下巻 p.75
- ^ ストレイチイ(1953) p.231
- ^ a b c d ストレイチイ(1953) p.230
- ^ a b 川本(2006) p.191
- ^ 川本(2006) p.196
- ^ 川本(2006) p.203-205
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 下巻 p.76
- ^ 川本(2006) p.198
- ^ ストレイチイ(1953) p.232
- ^ a b c ワイントラウブ(1993) 下巻 p.78
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.79
- ^ a b 君塚(2007) p.104-105 引用エラー: 無効な
<ref>タグ; name "君塚(2007)104-105"が異なる内容で複数回定義されています - ^ 君塚(2007) p.105
- ^ 伊藤・川田編(2004) p.256
- ^ 君塚(2007) p.135
- ^ 伊藤・川田編(2004) p.257
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 下巻 p.218
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.219-221
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 下巻 p.221
- ^ a b 君塚(2007) p.117
- ^ ストレイチイ(1953) p.233
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.82
- ^ 君塚(2007) p.164
- ^ 川本(2006) p.208
- ^ 君塚(2007) p.174
- ^ 君塚(2007) p.165-166
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.223
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.224
- ^ 君塚(2007) p.175
- ^ ヒバート(1998) p.173
- ^ 君塚(2007) p.179-183
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.253-255
- ^ 君塚(2007) p.183
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.255
- ^ 君塚(2007) p.191-193
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.265
- ^ 君塚(2007) p.193-194
- ^ a b 君塚(2007) p.194
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 下巻 p.270
- ^ 君塚(2007) p.195
- ^ 君塚(2007) p.196
- ^ 君塚(2007) p.200-201
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.286、288-289
- ^ 君塚(2007) p.202
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.346-349
- ^ a b 君塚(2007) p.204
- ^ a b 君塚(2007) p.205
- ^ 川本(2006) p.209
- ^ ヒバート(1998) p.175
- ^ 君塚(2007) p.222
- ^ a b 川本(2006) p.IV
- ^ モリス(2006) 上巻 p.19
- ^ ベイカー(1997) p.168
- ^ 川本(2006) p.272-273
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.377
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.378/382
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.385
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.389-390
- ^ モリス(2006) 上巻 p.362-363
- ^ モリス(2006) 上巻 p.364-369
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.335
- ^ a b c ワイントラウブ(1993) 下巻 p.492
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.490-491
- ^ 川本(2006) p.318-320
- ^ 中西(1997) p.154
- ^ モリス(2008) 下巻 p.413
- ^ モリス(2008) 上巻 p.120/203
- ^ モリス(2008) 下巻 p.175-176
- ^ モリス(2008) 下巻 p.228
- ^ 川本(2006) p.38
- ^ a b モリス(2008) 下巻 p.91
- ^ モリス(2008) 下巻 p.93
- ^ モリス(2008) 下巻 p.56
- ^ 川本(2006) p.284-285
- ^ モリス(2008) 上巻 p.126
- ^ モリス(2008) 上巻 p.132-135
- ^ モリス(2008) 上巻 p.132-152
- ^ 君塚(2007) p.147
- ^ 前田・山根(2002) p.64
- ^ 前田・山根(2002) p.77
- ^ 前田・山根(2002) p.78
- ^ 前田・山根(2002) p.79
- ^ 前田・山根(2002) p.80
- ^ 君塚(2007) p.147-148
- ^ a b 君塚(2007) p.148
- ^ 前田・山根(2002) p.80-81
- ^ 前田・山根(2002) p.81
- ^ 前田・山根(2002) p.82
- ^ 横井(1988) p.48-50
- ^ 横井(1988) p.55-58
- ^ 横井(1988) p.64-67
- ^ 横井(1988) p.74
- ^ 横井(1988) p.69
- ^ 横井(1988) p.45-50
- ^ 長島(1989) p.83
- ^ 君塚(2007) p.29-30
- ^ 君塚(2007) p.30
- ^ 横井(1988) p.128
- ^ 横井(1988) p.132
- ^ 横井(1988) p.135
- ^ 世界大百科事典「清」の項目
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.383
- ^ 君塚(2007) p.255
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.408-409
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.409-410
- ^ ベイカー(1997) p.178
- ^ モリス(2008) 上巻 p.364-365
- ^ モリス(2008) 上巻 p.366
- ^ モリス(2008) 上巻 p.362
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 上巻 p.410
- ^ 長島(1989) p.84
- ^ 川本(2006) p.36-37
- ^ 君塚(2004) p.95
- ^ 君塚(2004) p.95-103
- ^ ストレイチイ(1953) p.289
- ^ 君塚(2007) p.133
- ^ 川本(2006) p.206
- ^ 君塚(2007) p.134-135
- ^ a b 君塚(2007) p.134
- ^ モリス(2008) 下巻 p.186
- ^ モリス(2008) 下巻 p.190
- ^ モリス(2008) 下巻 p.190-191
- ^ モリス(2008) 下巻 p.195
- ^ モリス(2008) 下巻 p.197
- ^ モリス(2008) 下巻 p.199-202
- ^ 中西(1997) p.158
- ^ a b c モリス(2008) 下巻 p.230 引用エラー: 無効な
<ref>タグ; name "モリス(2008)下230"が異なる内容で複数回定義されています - ^ a b モリス(2008) 下巻 p.239
- ^ 梶谷(1981) p.41-42
- ^ 林(1995) p.11-12
- ^ 君塚(2007) p.151
- ^ モリス(2008) 下巻 p.241
- ^ 君塚(2007) p.152
- ^ モリス(2008) 下巻 p.244-246
- ^ a b 君塚(2007) p.154
- ^ 君塚(2007) p.153-154
- ^ モリス(2008) 下巻 p.265
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.229
- ^ モリス(2008) 下巻 p.219-222
- ^ モリス(2008) 下巻 p.223-225
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.186
- ^ a b c 梶谷(1981) p.47
- ^ a b c 君塚(2007) p.184
- ^ 梶谷(1981) p.45
- ^ a b c ワイントラウブ(1993) 下巻 p.235
- ^ 梶谷(1981) p.48
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.236
- ^ a b 君塚(2007) p.185
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.237-238
- ^ a b モリス(2006) 下巻 p.301
- ^ a b モリス(2006) 下巻 p.302
- ^ 梶谷(1981) p.57-58
- ^ a b モリス(2008) 下巻 p.340
- ^ a b c d e 君塚(2007) p.186
- ^ a b 梶谷(1981) p.59
- ^ 梶谷(1981) p.60
- ^ 中西(1997) p.106-108
- ^ モリス(2008) 下巻 p.341-342
- ^ 梶谷(1981) p.62
- ^ a b 中西(1997) p.119
- ^ 梶谷(1981) p.65-66
- ^ 梶谷(1981) p.66
- ^ 梶谷(1981) p.67
- ^ 君塚(2007) p.189
- ^ ストレイチイ(1953) p.266
- ^ a b 君塚(2007) p.190
- ^ 中西(1997) p.120
- ^ a b 林(1995) p.62
- ^ 中西(1997) p.121
- ^ モリス(2008) 下巻 p.394
- ^ モリス(2008) 下巻 p.394-395
- ^ a b モリス(2008) 下巻 p.396
- ^ モリス(2008) 下巻 p.376
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.394
- ^ 中西(1997) p.159
- ^ 林(1995) p.30
- ^ モリス(2008) 下巻 p.398-401
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.394-395
- ^ モリス(2008) 下巻 p.401
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 下巻 p.395
- ^ モリス(2008) 下巻 p.402
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.396
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.397
- ^ 林(1995) p.70
- ^ 君塚(2007) p.256
- ^ 君塚(2007) p.256-257
- ^ 君塚(2007) p.256-258
- ^ a b 林(1995) p.59
- ^ 中西(1997) p.161
- ^ a b 中西(1997) p.164-166
- ^ 君塚(2007) p.259
- ^ 君塚(2007) p.57
- ^ 君塚(2007) p.58
- ^ ストレイチイ(1953) p.170
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 上巻 p.363
- ^ a b 君塚(2007) p.59
- ^ a b 君塚(2007) p.60
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 上巻 p.372
- ^ a b 君塚(2007) p.63
- ^ 君塚(2007) p.63-64
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.374
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 上巻 p.379
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.372-373
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.386-388
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.391
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.397
- ^ 君塚(2007) p.65
- ^ 君塚(2007) p.67-68
- ^ a b 君塚(2007) p.100
- ^ a b 君塚(2007) p.68
- ^ 君塚(2007) p.95
- ^ 君塚(2007) p.98
- ^ a b ストレイチイ(1953) p.218
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.65
- ^ 君塚(2007) p.99
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.66
- ^ 君塚(2007) p.101
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.94
- ^ 君塚(2007) p.103
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 下巻 p.95
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.96-97
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 下巻 p.191
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.194
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.197-198
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.194-195
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.198
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 下巻 p.200
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.201
- ^ 君塚(2007) p.229
- ^ a b 君塚(2007) p.231
- ^ a b 君塚(2007) p.232
- ^ a b c ワイントラウブ(1993) 下巻 p.306
- ^ a b c ワイントラウブ(1993) 下巻 p.307
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 下巻 p.309
- ^ 君塚(2007) p.234-235
- ^ 朝倉・三浦(1996) p.123
- ^ 君塚(2007) p.235-236
- ^ 君塚(2007) p.236-237
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.308
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.337
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.404
- ^ a b ストレイチイ(1953) p.294
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.490
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.493
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.497
- ^ ストレイチイ(1953) p.294-295
- ^ 君塚(2007) p.265
- ^ 君塚(2007) p.267
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.502
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.504
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 下巻 p.505
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 下巻 p.506
- ^ a b c ワイントラウブ(1993) 下巻 p.508
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.509
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.510-511
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 下巻 p.513
- ^ a b 川本(2006) p.55
- ^ 川本(2006) p.269
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 上巻 p.253
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.255
- ^ a b 森(1986) p.567-568
- ^ a b 世界大百科事典「ビクトリア女王」の項目
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.362
- ^ 川本(2006) p.254
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.362-363
- ^ モリス(2006) 上巻 p.375
- ^ ストレイチイ(1953) p.287
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.322
- ^ 川本(2006) p.249
- ^ 川本(2006) p.254-255
- ^ ストレイチイ(1953) p.166
- ^ ストレイチイ(1953) p.210
- ^ ストレイチイ(1953) p.211
- ^ 君塚(2007) p.188
- ^ a b c 川本(2006) p.238
- ^ 川本(2006) p.258
- ^ 川本(2006) p.260
- ^ 川本(2006) p.266
- ^ 川本(2006) p.270-271
- ^ ワイントラウブ(1993) 下巻 p.309-310
- ^ a b ワイントラウブ(1993) 下巻 p.310
- ^ モリス(2006) 下巻 p.206
- ^ 世界大百科事典「血友病」の項目
- ^ ワイントラウブ(1993) 上巻 p.354
- ^ a b 君塚(2004) p.71
- ^ 君塚(2004) p.70
- ^ 君塚(2004) p.303
参考文献
- 朝倉治彦、三浦一郎『世界人物逸話大事典』角川書店、1996年(平成8年)。ISBN 978-4040319001。
- 伊藤之雄 (編)、川田稔(編)『二〇世紀日本の天皇と君主制―国際比較の視点から一八六七~一九四七』吉川弘文館、2004年(平成16年)。ISBN 978-4642037624。
- 梶谷素久『大英帝国とインド―press and empire』第三文明社、1981年(昭和56年)。ASIN B000J7UYDM。
- 川本静子『ヴィクトリア女王―ジェンダー・王権・表象』ミネルヴァ書房〈MINERVA歴史・文化ライブラリー9〉、2006年(平成18年)。ISBN 978-4623046607。
- 君塚直隆『女王陛下のブルーリボン―ガーター勲章とイギリス外交』NTT出版、2004年(平成16年)。ISBN 978-4757140738。
- 君塚直隆『ヴィクトリア女王―大英帝国の“戦う女王”』中央公論新社、2007年(平成19年)。ISBN 978-4121019165。
- リットン・ストレイチイ 著、小川和夫 訳『ヴィクトリア女王』角川書店〈角川文庫601〉、1953年(昭和28年)。ASIN B000JB9WHM。
- 長島伸一『大英帝国 最盛期イギリスの社会史』講談社〈講談社現代新書934〉、1989年(平成元年)。ISBN 978-4061489349。
- 中西輝政『大英帝国衰亡史』PHP研究所、1997年(平成9年)。ISBN 978-4569554761。
- 秦郁彦編 編『世界諸国の組織・制度・人事 1840―2000』東京大学出版会、2001年(平成13年)。ISBN 978-4130301220。
- 林光一『イギリス帝国主義とアフリカーナー・ナショナリズム―1867~1948』創成社、1995年(平成7年)。ISBN 978-4794440198。
- クリストファー・ヒバート(en) 著、小池滋、植松靖夫 訳『図説 イギリス物語』東洋書林、1998年(平成10年)。ISBN 978-4887213012。
- ケネス・ベイカー(en) 著、樋口幸子 訳『英国王室スキャンダル史』河出書房新社、1997年(平成9年)。ISBN 978-4309223193。
- 前田耕作、山根聡『アフガニスタン史』河出書房新社、2002年(平成14年)。ISBN 978-4309223926。
- 森護『英国王室史話』大修館書店、1986年(昭和61年)。ISBN 978-4469240900。
- ジャン・モリス(en) 著、椋田直子 訳『パックス・ブリタニカーー大英帝国最盛期の群像 上巻』講談社、2006年(平成18年)。ISBN 978-4062132633。
- ジャン・モリス 著、椋田直子 訳『パックス・ブリタニカーー大英帝国最盛期の群像 下巻』講談社、2006年(平成18年)。ISBN 978-4062132640。
- ジャン・モリス 著、椋田直子 訳『ヘブンズ・コマンド―大英帝国の興隆 上巻』講談社、2008年(平成20年)。ISBN 978-4062138901。
- ジャン・モリス 著、椋田直子 訳『ヘブンズ・コマンド―大英帝国の興隆 下巻』講談社、2008年(平成20年)。ISBN 978-4062138918。
- 横井勝彦『アジアの海の大英帝国』同文館、1988年(昭和63年)。ISBN 9784495852719。
- スタンリー・ワイントラウブ(en) 著、平岡緑 訳『ヴィクトリア女王〈上〉』中央公論新社、2007年(平成19年)。ISBN 978-4120022340。
- スタンリー・ワイントラウブ(en) 著、平岡緑 訳『ヴィクトリア女王〈下〉』中央公論新社、2007年(平成19年)。ISBN 978-4120022432。
- 『世界大百科事典』平凡社。ISBN 978-4582027006。
関連項目
外部リンク
ヴィクトリア
ヴェルフ家分家
| ||
| 先代 ウィリアム4世 |
第4代:1837年6月20日 - 1901年1月22日 |
次代 エドワード7世 |
| 先代 バハードゥル・シャー2世 (ムガル帝国皇帝) |
初代:1877年1月1日 - 1901年1月22日 | |
Template:Link FA Template:Link FA Template:Link FA Template:Link GA Template:Link FA Template:Link FA












![即位当日、最初の枢密院会議を開くヴィクトリア女王を描いたデヴィッド・ヴィルキー(英語版)の絵画。ヴィクトリアが純白の服を着ているが、これは彼女を目立たせるためであり、実際には黒い喪服を着ていた[68]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/Victoria_Privy_Council_%28Wilke%29.jpg/180px-Victoria_Privy_Council_%28Wilke%29.jpg)












































