「フリードリヒ・エンゲルス」の版間の差分
m編集の要約なし |
|||
| (63人の利用者による、間の160版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{別人|x1=「[[エンゲル係数]]」を提唱した統計学者|エルンスト・エンゲル}} |
|||
{{参照方法|date=2013年6月15日 (土) 14:55 (UTC)}} |
|||
{{Infobox_哲学者 |
{{Infobox_哲学者 |
||
<!-- 分野 --> |
<!-- 分野 --> |
||
| 6行目: | 6行目: | ||
|color = #B0C4DE |
|color = #B0C4DE |
||
<!-- 画像 --> |
<!-- 画像 --> |
||
|image_name = Friedrich Engels.jpg |
|image_name = Friedrich Engels portrait (cropped).jpg |
||
|image_caption = |
|image_caption = |
||
<!-- 人物情報 --> |
<!-- 人物情報 --> |
||
|名前 = フリードリヒ・エンゲルス |
|名前 = フリードリヒ・エンゲルス |
||
|生年月日 = {{生年月日と年齢|1820|11|28|no}} |
|生年月日 = {{生年月日と年齢|1820|11|28|no}} |
||
| birth_place = {{PRU1803}}・ユーリヒ=クレーフェ=ベルク州{{仮リンク|バルメン|de|Barmen}} |
|||
|没年月日 = {{死亡年月日と没年齢|1820|11|28|1895|8|5}} |
|没年月日 = {{死亡年月日と没年齢|1820|11|28|1895|8|5}} |
||
| death_place = {{GBR3}}・[[イングランド]]・[[ロンドン]] |
|||
|学派 = [[唯物論]]<br />[[マルクス主義]] |
|||
|配偶者=[[メアリー・バーンズ]]、[[リディア・バーンズ]] |
|||
|研究分野 = [[政治哲学]]、[[歴史哲学]]、[[経済学]]、[[階級闘争]]、[[資本主義]] |
|||
| school_tradition = [[大陸哲学]]、[[唯物論]]、[[マルクス主義|科学的社会主義]]、[[共産主義]]、若いころは[[青年ヘーゲル派]] |
|||
| main_interests = [[自然哲学]]、[[唯物論]]、[[自然科学]]、[[歴史哲学]]、[[倫理学]]、[[社会哲学]]、[[政治哲学]]、[[法哲学]]、[[経済学]]、各国の近現代史、[[政治学]]、[[社会学]]、[[資本主義]][[経済]]の分析 |
|||
| notable_ideas = [[唯物弁証法|弁証法的唯物論]]、[[唯物史観|史的唯物論]]、[[疎外]]、[[労働価値説]]、[[階級闘争]]、[[剰余価値]]の[[搾取]]、[[価値形態]] |
|||
|影響を受けた人物 = [[イマヌエル・カント]]、[[ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル]]、[[ルートヴィヒ・アンドレアス・フォイエルバッハ]]、[[マックス・シュティルナー]]、[[アダム・スミス]]、[[デヴィッド・リカード]]、[[ジャン=ジャック・ルソー]]、[[ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ]]、[[シャルル・フーリエ]]、[[モーゼス・ヘス]]、[[ルイス・ヘンリー・モーガン]] |
|影響を受けた人物 = [[イマヌエル・カント]]、[[ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル]]、[[ルートヴィヒ・アンドレアス・フォイエルバッハ]]、[[マックス・シュティルナー]]、[[アダム・スミス]]、[[デヴィッド・リカード]]、[[ジャン=ジャック・ルソー]]、[[ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ]]、[[シャルル・フーリエ]]、[[モーゼス・ヘス]]、[[ルイス・ヘンリー・モーガン]] |
||
|影響を与えた人物 = [[マックス・ヴェーバー]]、[[ジャン=ポール・サルトル]]、[[ギー・ドゥボール]]、[[フランクフルト学派]]、多くの[[マルクス主義者]] |
|影響を与えた人物 = [[マックス・ヴェーバー]]、[[ジャン=ポール・サルトル]]、[[ギー・ドゥボール]]、[[フランクフルト学派]]、多くの[[マルクス主義者]] |
||
|特記すべき概念 = [[マルクス主義|科学的社会主義]]の共同創設者([[カール・マルクス]]と共に)、[[マルクス主義における疎外|疎外]] ([[:en:Marx's theory of alienation|Marx's theory of alienation]]) と労働者の搾取、[[唯物史観|史的唯物論]] |
|||
|配偶者=[[リディア・バーンズ]] |
|||
|署名 = Friedrich Engels Signature.svg |
|署名 = Friedrich Engels Signature.svg |
||
}} |
}} |
||
'''フリードリヒ・エンゲルス'''(Friedrich Engels、[[1820年]][[11月28日]] - [[1895年]][[8月5日]])は、[[ドイツ]]の[[社会思想|社会思想家]]、[[政治思想|政治思想家]]、[[ジャーナリスト]]、[[実業家]]、[[共産主義者]]、軍事評論家、[[革命家]]、国際的な[[労働運動]]の指導者。 |
|||
{{共産主義のサイドバー}} |
|||
[[カール・マルクス]]と協力して[[科学的社会主義]]の世界観を構築、[[プロレタリアート|労働者階級]]の歴史的使命を明らかにし、[[労働者階級]]の[[革命]]による資本主義がもたらした発達した生産力の継承と[[資本主義]]そのものの廃絶、[[共産主義]]社会の構築による人類の持続的発展を構想し、世界の労働運動、革命運動、共産主義運動の発展に指導的な役割を果たした。 |
|||
{{社会主義}} |
|||
'''フリードリヒ・エンゲルス'''({{lang-de|Friedrich Engels}}、[[1820年]][[11月28日]] - [[1895年]][[8月5日]])は、 [[プロイセン王国]]の[[社会思想|社会思想家]]、[[政治哲学|政治思想家]]、[[ジャーナリスト]]、[[実業家]]、軍事評論家、[[革命家]]、国際的な[[労働運動]]の指導者。 |
|||
== 人物像 == |
|||
{{独自研究|section=1|date=2015年12月18日 (金) 06:17 (UTC)}} |
|||
盟友である[[カール・マルクス]]と協力して[[科学的社会主義]]の世界観を構築し、[[プロレタリアート|労働者階級]]の歴史的使命を明らかにした。マルクスを公私にわたり支え、世界の[[労働運動]]、[[革命]]運動、共産主義運動の発展に指導的な役割を果たした。 |
|||
若い頃より活動的で、正義感と勇気があり、終生マルクスの誠実な友人であったと共に、病にあって苦しんだ死の間際まで、周囲への思いやりと闊達なユーモアを欠かさなかった。工場経営者として地元経済界との交流もそつなくこなし、その間ではエンゲルスは[[酒]]のよくわかる、[[乗馬]]好きの快活な大男だった。 |
|||
== 概要 == |
|||
エンゲルスは、[[軍事]]の分野に特に通暁し、マルクスは、その軍事分野への造詣と博学、軍事的な国際関係の分析力に敬意を表して「マンチェスターの[[将軍]]」と呼んでいた。マルクスが持ち込んだ[[百科事典]]『ニュー・アメリカン・エンサイクロペディア』の原稿執筆の仕事を2人で分担した際には、エンゲルスは「軍隊」の項目を担当し、その知識を総動員して長大な軍事史を執筆した。マルクスは、その原稿を評して「その分量には頭に一撃をくらったような思い」と述べ、また、当初記事は匿名であったために、「これを執筆したのは[[ウィンフィールド・スコット|スコット]]将軍であろう」という噂が流れたという。 |
|||
フリードリヒ・エンゲルスは、1820年にドイツ西部の繊維産業都市{{仮リンク|バルメン|de|Barmen}}(現在の[[ヴッパータール]]市の一部)の紡績工場主の息子として生まれ、父の願いでギムナジウム(中高等学校)を退学して生家の仕事を実習した。フリードリヒは成人してもなお学問の志を捨てきれずにいたが、この時期[[ベルリン]]で砲兵隊の訓練生として軍に参加することとなり、実家を離れ父の監督から解放される機会が巡った。軍務のかたわらベルリン大学で聴講生として反[[ヘーゲル]]派で反動的知識人として知られた教授[[シェリング]]の講義を聞き、哲学の世界へと関心を広げていく。やがて急進的な改革や宗教批判で知られた[[青年ヘーゲル派]]に傾倒していくようになる。 |
|||
また、エンゲルスは[[語学]]に堪能であった。コミューンのある戦士は「エンゲルスは20か国語で言葉を詰まらせる」と述べた。エンゲルスのマルクスへの手紙の中には、マルクスの[[ロシア語]]の習熟を喜ぶエンゲルスの言葉を見ることができるほどである。エンゲルスの語学力は、[[マンチェスター]]時代のビジネスにおいても大いに役立った。エンゲルスは、商売にかかわる諸国への通信業務について、数カ国語を操り、会社の発展に大きく貢献した。エンゲルスは、実務面からのみならず、学問的にも言語に関心を持ち、ドイツの古語のほか、エンゲルスのヨーロッパ諸国の言語に関する知識は[[方言]]にまで及んだ。 |
|||
1842年、イギリスの工業都市[[マンチェスター]]で父の商会に赴任する途中[[ケルン]]に立ち寄り、22歳の時[[カール・マルクス]]と初めて会う。その後、マンチェスターで実業に携わりながら、「国民経済学批判大綱」を発表したほか、[[アイルランド]]人女工[[メアリー・バーンズ]]の協力を得て『{{仮リンク|イギリスにおける労働者階級の状態|de|Die Lage der arbeitenden Klasse in England}}』を執筆して名を挙げていくこととなる。1844年に帰国する途上、[[パリ]]でマルクスに再会する。エンゲルスはケルンでの『{{仮リンク|ライン新聞|en|Rheinische Zeitung}}』、『[[独仏年誌]]』と誌上を飾った「{{仮リンク|ヘーゲル法哲学批判序説|de|Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie}}」を、マルクスは古典経済学への批評家としてのエンゲルスを高く評価していた。この再開を契機に二人は急速に親交を深め、『[[聖家族 (政治思想書)|聖家族]]』を共同で執筆して青年ヘーゲル派の批判を開始していく。これ以降、マルクスとエンゲルスは終生変わらぬ友情と協力関係を築いていくようになる。1845-47年にかけて二人は、[[ブリュッセル]]に移って近くに住み、『[[ドイツ・イデオロギー]]』を共同執筆してヘーゲルの[[歴史哲学講義|歴史哲学]]を変革して、[[弁証法的唯物論]]の世界観を構築していった。これ以後、マルクスはエンゲルスの協力を受けて[[唯物史観]]の将来的展望を描く[[社会主義]]理論の体系化に努めていった。エンゲルスが革命理論の体系を問答形式で記した『{{仮リンク|共産主義の原理|en|Principles of Communism}}』を改定して、[[共産主義者同盟]]の綱領『[[共産党宣言]]』をマルクスとともに共同起草した。 |
|||
エンゲルスは、科学的社会主義を継承する後輩たちに対して、年老いてなお、若々しい精神で接した。時には教師として、時には謙虚に、その博学と戦士の魂とを以て、志高き青年たちに刺激を与え、激励し、鼓舞した。[[フランツ・メーリング]]は、老エンゲルスのその若さに感嘆し、「エンゲルスの最盛期は老年時代だった」と述べた。後にエンゲルスと思想的に逆の立場に立った[[コンラート・シュミット]]は、エンゲルスとの邂逅について、「学者的な杓子定規も、もったいぶって偉そうに見せる内気も、うぬぼれも全くなかった」と、エンゲルスの死後、思い出を語っている。 |
|||
1848年、[[ドイツにおける1848年革命|ドイツの三月革命]]において、エンゲルスは義勇軍に参加して軍事的才能を発揮したが、敗れて[[ロンドン]]に逃れ、ひと足早く亡命していたマルクスの近くへと亡命していった。1850年、革命の失敗原因を過去の歴史の教訓にもとめた研究『{{仮リンク|ドイツ農民戦争 (歴史書)|en|The Peasant War in Germany}}』を発表した。エンゲルスは革命への参加のゆえに勘当されていたが、生活難の打開のために父に頭を下げて事業に復帰を果たす。その後マルクスに経済援助を続け、1850年から69年にかけて自らは事業に励んでその研究を助けていく。1864年に英仏の労働者が結束して「国際労働者協会」[[第一インターナショナル]]を組織すると、エンゲルスはマルクスが活動に参加して理論的指導をおこない、内部の各派閥を整理統合するよう促した。マルクスは1867年『[[資本論]]』を発表、[[資本主義]]経済内部で資本がどのように労働を搾取して利潤を作り出すか、経済の運動法則を明らかにした。エンゲルスは実業の世界を引退してロンドンに転居し、マルクスとともに1869年にドイツで結成された{{仮リンク|社会民主労働者党|de|Sozialdemokratische Arbeiterpartei (Deutschland)}}の指導にあたった。エンゲルスは自然科学の研究にも熱心に取り組んで『{{仮リンク|自然の弁証法|de|Dialektik der Natur}}』の準備を進めたほか、1878年には『[[反デューリング論]]』を執筆して、マルクス理論の擁護者として理論を誤解するものや逸脱するものに対する批判に力を注いだ。 |
|||
1883年にマルクスが世を去ると、エンゲルスは「第二ヴァイオリン」から「第一ヴァイオリン」としてロンドンで[[社会主義]]運動を指導することを決意を定め、1884年にはマルクスが残したノートをもとに『[[家族・私有財産・国家の起源]]』を発表した。そして、未刊のまま残されていた『資本論』第二巻・第三巻の完成、翻訳、刊行に全力を注ぎ、マルクス理論を世に広めていった。1889年には[[第二インターナショナル]]の名誉会長に就任、各国の革命家たちが社会主義政党を結成するのを理論面資金面で援助していく。しかし、晩年には喉頭癌を患って、1895年にロンドンで死去、遺灰は遺言により[[ドーヴァー海峡]]に散骨された<ref>水村光男編 『世界史のための人名辞典』 山川出版社 1991年。 p.43</ref>。 |
|||
== 生涯 == |
== 生涯 == |
||
[[File:280505 001 Engelshaus Barmen.jpg|thumb|エンゲルスの生家(再建)]] |
|||
=== 生い立ち === |
=== 生い立ち === |
||
[[1820年]][[11月28日]]、フリードリヒ・エンゲルスは、[[プロイセン王国]]ユーリヒ・クレーフェ・ベルク州のバルメンに生まれた<ref name="大内(1964)103">{{Harvtxt|大内|1964}} p.103</ref><ref name="土屋(1995)8">{{Harvtxt|土屋保男|1995}} p.8</ref><ref name="ハント(2016)19-20">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.19-20</ref>。同姓同名の父{{仮リンク|フリードリヒ・エンゲルス(父)|de|Friedrich Engels (Fabrikant)}}(1796-1860、以下、父と略記)と母エリザベート・フンラツィスカ・マウリーツィア(1797-1873)のもとに生まれ、三人の弟と四人の妹からなる八人兄弟の長男であった<ref name="土屋(1995)8"/>。エンゲルスは、信仰心の篤い地域社会と厳格な父に反発を覚えながらも、弟と、特に母と妹に対しては終生愛情を持ち続けた<ref name="土屋(1995)8-9">{{Harvtxt|土屋保男|1995}} pp.8-9</ref><ref name="ハント(2016)29-31">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.29-31</ref>。 |
|||
==== 出身地と一門 ==== |
|||
バルメンは18世紀には[[神聖ローマ帝国]]の[[ユーリヒ=クレーフェ=ベルク連合公国]]に属した地域で、[[ナポレオン戦争]]時には[[フランス帝国]]の属領[[ベルク公国]]であったが、[[ナポレオン]]の追放後、[[ウィーン議定書|ウィーン条約]]に基づきプロイセン領となった。ユーリヒ・クレーフェ・ベルク州から{{仮リンク|ライン州|en|Rhine Province}}へと編入され統合されていく。現在は[[ヴッパータール]]と呼ばれ、[[ノルトライン=ヴェストファーレン州]]の州都[[デュッセルドルフ]]の東に40キロいったヴッパー河畔にある中規模の都市である。川を隔てて[[エルバーフェルト]]と相対している。 |
|||
バルメンは18世紀にはすでに紡績業で繁栄した工場町でヴッパー川に面して半円形の都市を形成し、1810年には1万6000人だった人口はエンゲルスの青年期である1840年には4万人になっていた。町の人口構成は染色職人が1100人、紡績工が2000人、織工が1万2500人、リボン織工が1万6000人で大多数が小さな工房で働く職人たちであった。この町は「ドイツの[[マンチェスター]]」と呼ばれ、バルメン製の織物はイギリス、アメリカ、西インドなど世界各地で有名であった<ref name="ハント(2016)22-23">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.22-23</ref>。エンゲルス少年はこうした職人たちと近しい環境の中で成長し、[[階級]]的な思考に固着しない自由な思想と性格を形成していく<ref name="ハント(2016)21">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.21</ref>。 |
|||
エンゲルス家は16世紀末に一門の起源が見出される。 |
|||
18世紀半ば、ヨハン・カスパー・エンゲルス1世(1715-1787)は元は[[ライン地方]]の農民であったが、わずかな銀貨を携えてベルク地方に移住した。移住先に選んだ町は繊維業で栄えていたバルメンであった。ヨハンは繊維業に転身し、麻布の漂白を生業とし、やがて漂白場を備えた[[紡績]]工場を有する企業「カスパー・エンゲルス・ウント・ゾーネ商会」の経営を手掛けるようになる。同社は企業の利潤追求だけでなく社会貢献に関しても意欲的な企業であった。従業員に住宅・菜園・学校を提供し、食糧不足に備えて組合を整備した<ref name="ハント(2016)20-21">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.20-21</ref>。 |
|||
エンゲルス家はバルメンを代表する名士の一人となっていき、2代目{{仮リンク|ヨハン・カスパー・エンゲルス2世|de|Johann Caspar Engels}}は、1808年、市会議員に任命された他、バルメンの[[福音主義]]教会の設立者の一人となっている<ref name="ハント(2016)22">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.22</ref>。しかし、3代目継承の際に一族内で紛争が起こり、くじ引きによる決裁でエンゲルスの父フリードリヒは継承から外れてしまう。だが、父フリードリヒは二人のオランダ人ゴッドフリートとペーター・エルメンとともに紡績企業「エルメン&エンゲルス商会」を設立し、共同経営することになる。麻布の漂白から紡績へと事業を拡大させ、[[マンチェスター]]へと進出、縫糸工場を建設して海外市場に打って出ることになる<ref name="ハント(2016)22"/>。 |
|||
==== 学校教育期間と萌芽 ==== |
|||
エンゲルスは裕福な家庭なので当時は家庭教師による教育で十分なのだが、中等教育を当初は地元のシュタットシューレ(商業高校)で受けた。しかし、商業高校では知的好奇心を満足させることはできず、1834年、14歳からはエルバーフェルトの[[ギムナジウム]](普通科高校)に転校することになる<ref name="土屋(1995)9">{{Harvtxt|土屋保男|1995}} p.9</ref><ref name="ハント(2016)31">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.31</ref>。 |
|||
少年期のエンゲルスは、学問が優秀でありながら、書斎に引きこもることを好まない、活発で社交的で好奇心旺盛であった<ref name="大内(1964)104">{{Harvtxt|大内|1964}} p.104</ref>。語学に長けており成績は優秀で、勉学だけでなく、音楽や美術、スポーツなどにも才を発揮し、絵もうまく漫画を描いたりもしていた。地理歴史科の教員ヨハン・クリストフ・クラウゼン先生のもとでドイツの古典文学の教育を受け、中世の[[騎士]]物語「射手[[ウィリアム・テル]]」や「[[十字軍]]の戦う騎士[[ゴドフロワ・ド・ブイヨン|ブイヨン]]」、そして『[[ニーベルンゲンの歌]]』に親しんだ。[[ロマン主義]]的な文学運動に感化されており、将来大学では法律を勉強して公務員になるか、文学を学んで詩人になりたいと考えていた<ref name="大内(1964)104"/><ref name="土屋(1995)10">{{Harvtxt|土屋保男|1995}} p.10</ref><ref name="ハント(2016)31-38">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.31-38</ref>。 |
|||
しかし、息子のそうした文学への傾倒を父フリードリヒは許さなかった<ref name="土屋(1995)10"/>。バルメンは[[プロテスタント]]の信仰が強い地域で禁欲、勤勉、実直、敬虔さが重んじられる町であった。商人は天職たる仕事に人生を捧げ、神に従い誉れある信仰生活を全うすることを人生の目標としていた<ref name="大内(1964)104"/><ref name="ハント(2016)23-28">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.23-28</ref>。父は息子を実業の世界に進ませたいと考えていた上、[[カルヴァン|保守的]]な[[敬虔主義]]を信条としていたため、青春の夢や理想を謳歌する息子に理解を示すどころか、1837年に学校を退学させてしまう<ref name="土屋(1995)10"/><ref name="大内(1964)105">{{Harvtxt|大内|1964}} p.105</ref><ref name="ハント(2016)38">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.38</ref>。 |
|||
{{main|ロマン主義|プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神}} |
|||
=== 青年期と批判精神 === |
|||
==== ブレーメン時代 ==== |
|||
[[File:Engels-1836.jpg|thumb|190px|エンゲルス19歳の自画像]] |
|||
父の反対からエルバーフェルトの[[ギムナジウム]]を中退したエンゲルスは、17歳から家の仕事を手伝うようになる<ref name="土屋(1995)10"/><ref name="ハント(2016)38"/>。麻や綿の素材の性質や漂白と染色、そして、紡績や織機に関する知識を教え込まれた。1838年には絹の販売と生糸の調達の現場を見るため、父と[[マンチェスター]]に出張に赴いて商売のスキルを叩き込まれていった。また、貿易港[[ブレーメン]]のロイボルド商会でも見習い事務員として働き、輸出入や[[関税]]、[[為替]]など外国[[貿易]]に関わる諸々の業務を習得した<ref name="ハント(2016)39-40">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.39-40</ref>。この出張の経験で獲得した貿易や商業に関する知識は国際的視野を広げる有意義な機会になった<ref name="土屋(1995)10"/>。 |
|||
しかし、父親の監督のない状況ではエンゲルスは模範的な見習い実業家ではなかった。退屈な事務処理にすっかり飽きてしまい、職場にビールを持ち込んで怠け、二階でハンモックに揺られながら葉巻を吸って自堕落に過ごした<ref name="ハント(2016)39">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.39</ref>。そして、外出してはブレーメンの[[リベラル]]な環境で父に禁じられた青春を楽しむようになる。詩に対する関心をさらに深めたほか、フェンシングや水泳などの趣味の楽しみを満喫し、女性を目当てにダンスやコンサートなど社交を楽しむようになった。エンゲルスは感じのよい好青年となっており、若い女性は格好のターゲットであった<ref name="ハント(2016)39-41">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.39-41</ref>。 |
|||
エンゲルスはブレーメン時代から口髭を生やし始めている<ref name="ハント(2016)41">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.41</ref>。髭はエンゲルスの反抗心の表れであった<ref name="ハント(2016)42">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.42</ref>。 |
|||
1810年代、[[神聖ローマ帝国]]を復活させただけの名目的国家連合体[[ドイツ連邦]]に反発し、 統一ドイツを希求する[[ナショナリズム]]運動が盛んであった。1819年、[[ウィーン体制]]を主導した[[オーストリア帝国]]宰相の[[メッテルニヒ]]は、ナショナリスト学生によるコッツェブー刺殺事件を受けて[[カールスバート決議]]を採択し、学生組合[[ブルシェンシャフト]]を解散させ、急進的な青年運動を封じ込めようとした。[[プロイセン王国]]もこの決議に賛同し、反動的な言論統制を布いていた。エンゲルスの青年時代、1840年代にもこの反動体制が存在しており、文章に対する[[検閲]]だけにとどまらず、服装や記章といった要素まで取り締まりの対象となっていた。口髭は[[愛国主義|愛国的]][[ドイツにおける1848年革命|共和主義]]の表象であった。[[バイエルン王国]]では口髭が違法とされていたという<ref name="ハント(2016)42"/>。 |
|||
エンゲルスの口髭は彼の政治信条が明確となってきたことを意味している。[[保守主義]]への強烈な反感である<ref name="ハント(2016)45">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.45</ref>。 |
|||
1821年[[ギリシャ独立戦争]]が勃発し、ギリシア人は[[オスマン帝国]]からの支配から脱却する。また、1830年にはフランスで[[七月革命]]が、その余波を受けて[[ベルギー独立革命]]が発生した<ref name="ハント(2016)48">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.48</ref>。1831年、[[マッツィーニ]]はオーストリア支配からの[[イタリア]]の解放を目指して[[青年イタリア]]という急進的な革命派集団を組織した。革命の志はヨーロッパ各地に木霊し、様々なタイプの急進主義的な青年組織の結成を促していく。ドイツにも[[青年ドイツ]]という共和主義的で反体制的な文化運動が誕生し、[[ウィーン体制]]の[[反動主義]]の中に自由と進歩と革命の精神を種を播いた[[ルートヴィッヒ・ベルネ]]、[[ハインリヒ・ハイネ]]、[[カール・グツコー]]といった若き新星の文化人が現れ出た<ref name="ハント(2016)44-45">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.44-45</ref>。彼らにとっては[[ゲーテ]]であってもドイツの旧体制的産物でしかなかった<ref name="ハント(2016)44">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.44</ref>。青年ドイツにとっての共通目標は、憲法を制定して国民の政治参加の扉を開き、農奴やユダヤ人を解放し、宗教的強制を排して世襲的貴族制度を根絶することにあった<ref name="ハント(2016)45"/>。 |
|||
エンゲルスは、青年イングランドの[[パーシー・ビッシュ・シェリー|シェリー]]の『マブ女王』({{lang-en|''Queen Mab''}})や[[ヒューマニズム]]と自由について謳った詩歌を好んだ<ref name="ハント(2016)46-47">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.46-47</ref>。とりわけ、影響を受けたのはカール・グツコーである。彼は『懐疑するヴァリー』({{lang-de|''Wally die Zweiflerin''}})という批判小説を世に送り出した。女ヴァリーの奔放さ、性の解放、宗教批判を含んだこの小説は、[[ビーダーマイヤー]]的な暮らし([[ブルジョア]]的な中流市民生活)を軽侮して世に一大センセーショナルを巻き起こし、グツコーは投獄された<ref name="ハント(2016)45"/>。こうした文化的潮流に刺激を受けてエンゲルスはロマン主義に混在していた中世懐古を次第に嫌悪し、青年ドイツが[[保守主義|封建主義]]を拒絶したことに共感を抱くようになった<ref name="ハント(2016)45"/>。 |
|||
エンゲルスは、厳格な家庭環境と父親に自分の人生を決められたことに日ごろ憤慨していた。1839年、『[[ニーベルンゲンの歌]]』に登場する英雄[[ジークフリード]]とその父[[シグムンド|ジークムント]]の葛藤を描く叙事詩的戯曲を執筆している。この作品はまさにエンゲルス家における親子の職業選択をめぐる確執を作品化したものであった<ref name="ハント(2016)50-51">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.50-51</ref>。これに続き、エンゲルスは『ベドウィン』という詩を[[ブレーメン]]の新聞に投稿した。この作品は東洋の古き異国情緒をロマンチックに描き、産業社会への移行とその悲哀を対比的に表現する詩であり、エンゲルス初の活字化された作品であった<ref name="ハント(2016)50">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.50</ref>。この頃のエンゲルスは「フリードリヒ・オズヴァルド」というペンネームで活動し、グツコーが発行者となった雑誌『テレグラフ』({{lang-de|''Telegraph für Deutschland''}})に寄稿して自己表現を楽しんだ<ref name="ハント(2016)51">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.51</ref>。『テレグラフ』はプロイセン王国の言論統制に対して批判精神の発露を巧みに盛り込んだ文芸活動を通じて主張を図った。若きエンゲルスはこのような文化的環境で自己形成を促し、やがて愛国的共和主義の信徒にして急進的社会批判の信奉者となっていた<ref name="ハント(2016)45,48">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.45,48</ref>。 |
|||
{{main|青年ドイツ|青年ヨーロッパ}} |
|||
==== 『ヴッパータルたより』 ==== |
|||
[[File:Barmen (1870).jpg|thumb|250px|1870年のヴッパータールの様子]] |
|||
1830年代、フランスやベルギーなどヨーロッパ各国は[[産業革命]]への道筋を歩み始め、その余波はドイツ西部の産業地域[[ヴッパータール]](バルメン・エルバーフェルト)にも及び始めていた。ライン地方とルール地方の伝統的な繊維産業は、家内工房での職人たちの手織による製品によって支えられていたのだが、英国の進んだ繊維産業が工場で機械生産した大量の製品の輸出との国際競合に晒されるようになり、大陸市場から次第に駆逐されて衰退への道を辿りはじめていた<ref name="ハント(2016)52">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.52</ref>。 |
|||
また、1833年にようやく[[プロイセン王国]] の主導で[[ドイツ関税同盟]]が発足してドイツ国内の市場統合が開始した。市場統合はヴッパタールに不利に働いた。[[ザクセン]]や[[シレジア]]といったドイツ東部の産業との競争が始まり、国際市場と国内市場の二正面競争の中で疲弊していく<ref name="ハント(2016)52"/>。この頃、ヴッパータールはフランスへの織物の輸出が堅調であったことからその衰退傾向は緩慢なものに留まっていたが、繊維産業は確実に先細りへと向かっていた。地域経済のこうした逆境はエンゲルス家による温情的家父長主義([[パターナリズム]])の家風にも影響を与え、職人たちとの社会的経済的絆は揺らぎ始めた<ref name="ハント(2016)53">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.53</ref>。 |
|||
ドイツに[[産業革命]]とそれに伴う[[階級]]分化が顕在化していった。技術革新によって機械化が進行して熟練の崩壊が始まり、[[ギルド]]が解散されて職人たちの労働条件が悪化、人材育成のための徒弟制度が機能不全に陥り、賃金体系が安定を失い動揺していった。産業革命による社会経済的変化は、独立した職人層を解体して不安定な非正規雇用を転々とする労働者階級([[プロレタリアート]])の形成を促し、ヴッパータールには貧困者が溢れるようになる<ref name="ハント(2016)53-55">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.53-55</ref>。失業中、非正規雇用の貧困者が各地の都市に押し寄せ、[[ケルン]]では人口の20~30%が救貧を受けていたと言われている<ref name="ハント(2016)53"/>。 |
|||
これまで文学に夢を見ていた青年エンゲルスは、社会の現実を描いた[[ルポタージュ]]作品を世に送り出すことになった。それが1839年に世に出たエンゲルス初の本格的作品'''『ヴッパータルたより』'''だった<ref name="土屋(1995)11">{{Harvtxt|土屋保男|1995}} p.11</ref>。 |
|||
エンゲルスは、染料の廃液によって汚染され紅に染まった河川と閉塞的な環境で暮らす人々の姿を見つめて心を痛め、冒頭から廃液と排煙による汚染や健康被害を指摘し、環境破壊に比例して深刻化する人心の荒廃、文化の形骸化といった問題を指摘していった。ヴッパータールの変わり映えしない町並みと古色蒼然とした風土を批判し、厳格な宗教信条に凝り固まり、陰鬱な雰囲気を呈する町の雰囲気が社会環境の悪化を招いていると断じた。工場を経営する紳士たち([[ブルジョアジー]])は、安価な人員として児童を労働者として使役して彼らの堕落を促しながら困窮する労働者([[プロレタリアート]])の暮らしぶりを卑しむ一方、自分たちは毎週の教会通いによって敬虔さを誇示して、俗物的で上辺だけの暮らしぶりを享受していた。エンゲルスは労働者の窮状を克明に描写して社会矛盾の深刻さを伝え、ヴッパータールの人々が理性と科学が新時代の扉を開く近代の潮流に逆行して聖書かアルコールにのみ救いを求め、酒浸りの日々を酩酊と牧師の説教が流布した迷信の中を生きていると警鐘を鳴らした。矛盾だらけの社会に批判を加えて、社会のあるべき理想像を提示するという課題を浮かび上がらせていった。『ヴッパータルたより』はエンゲルスの思想形成のスタート地点となった。 |
|||
=== ベルリン時代 === |
|||
[[ファイル:Friedrich_Engels-1840-cropped.jpg|thumb|若き日のエンゲルス(1840年)]] |
[[ファイル:Friedrich_Engels-1840-cropped.jpg|thumb|若き日のエンゲルス(1840年)]] |
||
==== ヘーゲル哲学との出会い ==== |
|||
[[紡績]][[工場]]を共同経営する父親のもと、バルメン・エルバーフェルト(現在の[[ヴッパータール]])に生まれた。8人兄弟の長男である。青年期は、学問が優秀でありながら、[[書斎]]に引きこもることを好まない、活発で社交的で好奇心旺盛であった。エンゲルスは、封建的遺習の残る地域社会に反発を覚えながらも、弟と、特に母と妹に対しては終生愛情を持ち続けた。 |
|||
エンゲルスはヴッパータールの人々に見られる偽善的な敬虔主義を強く嫌悪した<ref name="ハント(2016)58-59">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.58-59</ref>。 |
|||
1837年、[[エルバーフェルト]]の[[ギムナジウム]]を中退し、独立した父の仕事を手伝うようになる。のちに、[[ブレーメン]]のロイボルド商会でも働いた。1841年、[[兵役]]義務として[[ベルリン]]近衛[[砲兵]][[旅団]]に入る。軍務の合間に[[フンボルト大学ベルリン|ベルリン大学]]で聴講し、[[ヘーゲル左派]]に加わった。 |
|||
エンゲルスは[[キリスト教]]に関する文献を読み漁り、その中で特に1834年に刊行された[[ダーフィト・シュトラウス]](1807-1874年)の『イエスの生涯:その批判的検証』という書に強く刺激を受けた。この著作は聖書の真実性と[[イエス・キリスト|イエス]]の奇跡ストーリーを否定し、聖書を当時の文化的背景で書かれた文書であって、そこで描かれたイエスは[[史的イエス|歴史的]]に捉え直されなければならないと訴えるものであった<ref name="ハント(2016)59-60">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.59-60</ref>。エンゲルスはこの書物に触発されて、[[青年ヘーゲル派]](ヘーゲル左派とも)の思想に関心を持つとともに、キリスト教に対する信仰を捨てる決意をした<ref name="ハント(2016)61">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.61</ref>。やがて、エンゲルスは「哲学と批判的神学とで忙しい」[[無神論]]者になっていった<ref name="土屋(1995)11"/><ref name="ハント(2016)43">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.43</ref>。 |
|||
=== マルクスとの出会い === |
|||
[[ファイル:Marx+Family and Engels.jpg|thumb|マルクス一家と]] |
|||
[[1842年]]、父は、[[イギリス]]・[[マンチェスター]]で共同経営する綿工場に従事させるために、彼をマンチェスターのエルメン・アンド・エンゲルス商会に送った。そこで彼は、[[都市]]の広範囲に拡がった[[貧困]]に衝撃を受けた。エンゲルスは都市の貧困の中で暮らす人々の生活の中に入り込み、取材と調査を進め、都市の[[人口]]やその状態の詳細などを考察した報告を執筆した。この報告は、後に[[1845年]]に『イギリスにおける労働者階級の状態』(''[http://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/condition-working-class/index.htm Condition of the Working Class in England in 1844]'') として出版され、[[カール・マルクス]]によって労働者階級に関する歴史的な文献として極めて高い評価を与えられることとなった。エンゲルスはすでにこの頃より、持ち前の好奇心と行動力によって活発な取材を展開し、[[ジャーナリスト]]としての才を示している。 |
|||
また、[[ドイツ観念論]]を代表する哲学者[[ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル|ヘーゲル]]の文献のなかで、ヘーゲル没後に刊行された'''『[[歴史哲学講義]]』'''({{lang-de|''Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte''}})を読み込み、歴史を動かす原動力に対して関心を抱くようになる<ref name="ハント(2016)62-63">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.62-63</ref>。ヘーゲルの歴史観は、人間の精神を歴史の原動力と位置付け、歴史を精神が自由を獲得しようと闘争していく過程であると見た<ref name="ハント(2016)62-63"/>。エンゲルスは多年に及ぶ思想形成を経て、ヘーゲルの観念的な[[歴史哲学]]の批判者となっていった。青年ドイツ、シュトラウス、ヘーゲル哲学、そしてドイツの産業革命がエンゲルスを文学青年から急進主義の若き思想家へと成長させていった。 |
|||
1842年にマルクスと初めて面会した時は、マルクスの誤解もあって、そっけないものであった。しかし交信はその後も続き、1844年にエンゲルスがイギリスよりドイツへ帰る途中、[[パリ]]で二人は再会し、お互いが[[資本主義]]に関する同じ考え方を共有していることを認識し、仕事面でも親密な関係を築いていった。 |
|||
{{main|ヘーゲル|歴史哲学講義}} |
|||
[[1845年]]、エンゲルスは後にパリでマルクスによって編集・出版される『独仏年誌』(''Franco-German Annals'') という雑誌に、当時最先端の経済学であった[[古典派経済学]]を批判的に検討した自らの論文「国民経済学批判大綱」を寄稿した。この論文は、その執筆当時においては[[経済学]]の分野の研究においてマルクスに先んじていることを示しており、マルクスが経済学の道へ本格的につき進む契機となるとともに、のちのマルクスによって、経済学に対する歴史的パースペクティブから、その歴史的価値を高く評価された。 |
|||
1841年3月、エンゲルスは二年半に及ぶブレーメンでの修行生活を終えて故郷に戻ったが、既にバルメンでの生活に嫌気が差していた。読書にまい進する生活に没頭していたちょうどこの時期、軍から招集がかかり兵役に就くよう求められる。兵役免除の願いを聞き入れられず軍に入隊することが決まり、地元を離れることになった<ref name="ハント(2016)65">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.65</ref>。エンゲルスは[[ベルリン]]近衛砲兵旅団第12中隊に配属となり砲術を学んでいたが、すぐに訓練や砲弾の弾道計算に飽きていった<ref name="ハント(2016)78">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.78</ref>。地元を離れ厳格な父の監督から解放されたことで元々好きだった文学や哲学の研究にますます没頭してしまい、九か月で昇進するのが普通のところを仮病を使って訓練をサボって、大学の講義に出席したり読書室に入り浸っていたり町に繰り出して飲み歩いていため、結局退役時に形式的な表彰を受けたものの昇進はできなかった。軍務を抜け出しては[[フンボルト大学ベルリン|ベルリン大学]]で聴講し、反動的な考えに挑戦するべく独習を重ね、エンゲルス自身は自分の思想形成に集中していたと語っている<ref name="土屋(1995)11"/><ref name="ハント(2016)67,69">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.67,69</ref>。エンゲルスのベルリン暮らしはバルメンには無い新思潮の文化に接することができる刺激的なものであった。とりわけ熱中していたのはヘーゲル哲学であった。裕福な家庭出身の志願兵だったため兵舎に入らず、[[スパニエル]]種の犬を飼って兵舎近くのドロテーエン街のアパートで下宿生活をしていた<ref name="ハント(2016)79">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.79</ref>。 |
|||
1845年1月、マルクスが[[フランス]]政府当局から強制国外退去を命じられた後、二人は[[ヨーロッパ]]の他の国よりも比較的[[表現の自由]]が保証されていた[[ベルギー]]に活動の場を移した。[[1846年]]1月、エンゲルスとマルクスは[[ブリュッセル]]において、来るべき[[革命]]期に備えヨーロッパ各地の[[社会主義]]運動を団結させることを狙いとして、共産主義通信委員会 (''Communist Correspondence Committee'') を設立した。マルクスの思想に影響を受けたイギリスの[[社会主義者]]たちが、自分たちで新しく組織を形成した[[共産主義者同盟 (1847年)|共産主義者同盟]]([[1847年]] - [[1850年]])と呼ばれる会議を[[ロンドン]]で開き、エンゲルスは代表として出席、その成熟した活動の戦略の形成に大きな影響を与えた。 |
|||
ベルリンはプロイセン王国の首都であり、19世紀初頭のプロイセンは宰相[[ハインリヒ・フリードリヒ・フォン・シュタイン|シュタイン]](任1807-1808年)と[[カール・アウグスト・フォン・ハルデンベルク|ハルデンベルク]](任1810-1822年)による[[自由主義]]的な{{仮リンク|プロイセン改革|en|Prussian Reform Movement (1806–1815)}}を試みるなど一時は開明的な近代化政策を模索していたが<ref name="ハント(2016)71-72">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.71-72</ref>、改革が一定の成果を上げると一転、1840年には[[王権神授説]]を信奉する[[フリードリヒ・ヴィルヘルム4世]]が即位して反動的な[[権威主義]]へと逆行していた<ref name="ハント(2016)72-73, 68-69">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.72-73, pp.68-69</ref>。 |
|||
[[1848年]]、エンゲルスとマルクスは[[共産主義]]の概要に関する大衆的な[[パンフレット]]を執筆した。エンゲルスの『共産主義の原理』に基づいて書かれたその12,000語あまりのパンフレットは6週間で完成。『[[共産党宣言]]』と題されたこの文献は1848年2月に出版された。同年3月、エンゲルスとマルクスはベルギーを追放されてドイツの[[ケルン]]に移り、急進的な新聞『[[新ライン新聞]]』(''Neue Rheinische Zeitung'') を発刊した。 |
|||
新王は憲法制定や議会開設による王権の制限を嫌悪しており<ref name="ハント(2016)72-73">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.72-73</ref>、プロイセン王国の反動は国家が信奉する[[イデオロギー]]にも表れていた。[[フンボルト大学ベルリン|ベルリン大学]]には進歩的なヘーゲル学派が形成されていたが、政府の方針によりヘーゲルのかつての友人であり当時は論敵となっていた[[フリードリヒ・シェリング]]がベルリン大学の教授となっていた。シェリングの講義では宗教的で直感的な[[啓示]]の観点から超越的な神の絶対性とその実在性が論じられ、汎論理主義(ヘーゲル自身は違っていたが無神論と同義)的と見なされたヘーゲル哲学への批判が盛んに論じられていた。エンゲルスはヘーゲル哲学の真価を見出すべく、シェリングの講義を熱心に聴講していた<ref name="土屋(1995)11"/><ref name="ハント(2016)66">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.66</ref>。教室には[[ヤーコプ・ブルクハルト|ブルクハルト]]、[[セーレン・キェルケゴール|キェルケゴール]]、[[ミハイル・バクーニン|バクーニン]]といった後に思想界を主導した青年たちが集っていた<ref name="ハント(2016)67">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.67</ref>。エンゲルスはヘーゲル哲学に立ちながら社会の変革を目指す[[青年ヘーゲル派]]に加わるようになる。 |
|||
=== イギリス時代 === |
|||
[[1849年]]までに、二人はドイツのみならず大陸各国から追放され、やむなくイギリスに渡った。[[プロイセン]]当局はイギリス政府に対して、エンゲルスとマルクスを追放するように圧力をかけたものの、当時の英国首相[[初代ラッセル伯ジョン・ラッセル|ジョン・ラッセル]]は表現の自由に関して[[リベラル]]な考え方を持っていたため、その要請を拒否した。 |
|||
{{main|シェリング|フリードリヒ・ヴィルヘルム4世}} |
|||
[[1848年]]の革命の機運が収束しヨーロッパの革命的情勢が後退して以降、イギリスは、エンゲルスにとってその後の生活の拠点となった。エンゲルスは、父親の工場のあるマンチェスターでエルメン・アンド・エンゲルス商会の経営に参画することとなった。1850年から1860年は一般社員、1860年から1864年まで業務代理人、そして1864年から1869年は支配人として勤め、最終的には共同経営者の地位にまで上り詰めた。 |
|||
==== 青年ヘーゲル派と新思潮 ==== |
|||
昼間は工場経営に従事する一方、夜は科学的社会主義の研究を進めた。政治経済情勢については、多くの新聞と雑誌からの情報収集を通じて分析を継続した。殊に、世界の戦争に関する軍事情勢分析には抜群の才を発揮し、この分野では、時にはマルクスに代わって情勢論文をマルクスの名で新聞社に寄稿することもあった。 |
|||
[[File:Feuerbach Ludwig.jpg|thumb|200px|青年ヘーゲル派の巨匠ルートヴィヒ・フォイエルバッハ]] |
|||
青年ヘーゲル派の学生たちの精神的支柱であったヘーゲルは、19世紀初頭期のプロイセン王国の国家改革に自由の理念が実現される姿を見出してベルリン大学の教授に就任し、生前はプロイセンの国家擁護者となっていた<ref name="ハント(2016)71-72"/>。しかし、1831年にヘーゲルが世を去った後、時代は大きく変わっていた。1840年代のプロイセン王国は産業の発達と産業革命期の社会変動に直面しながらも、[[憲法]]も[[議会]]もなく近代化は遅れており、依然として封建的な君公国としての性格を留めていた<ref name="ハント(2016)72-73"/>。 |
|||
エンゲルスは、マルクスの頭脳の偉大さを認め、早い時期からマルクスの理論の発展に対して重要な助言者の役割を担ってきたが、マンチェスター時代には、エンゲルスは、マルクスの主著『[[資本論]]』を完成させる上でこの上なく重要な助言者となった。資本主義経済の渦中で有能な経営者として頭角を現しつつあったエンゲルスは、マルクスに対してしばしば現実の経営の実情、資本家の実務や慣例について情報を提供した。時には、マルクスの要請に応じて、『資本論』の原稿に対して経営者の観点から助言や指摘を行った。 |
|||
青年ヘーゲル派の学生たちは、自由と秩序を重んじるヘーゲルの思想から進歩的な側面に刺激を受け、プロイセン王国の反動を強く非難するとともに、更なる改革を通じて自由の理念がより一層実現されるよう訴えていた。彼らの格好の批判対象は[[神学]]であった。1842年、エンゲルスは'''「シェリングと啓示」'''({{lang-de|''Schelling und die Offenbarung- Kritik des neuesten Reaktionsversuchs gegen die freie Philosophie,1842''}})という論文を匿名で公表し、キリスト教の神聖性を批判してキリスト教のあらゆる側面が理性による批判を受けるべきだと檄を飛ばした<ref name="土屋(1995)11-12">{{Harvtxt|土屋保男|1995}} pp.11-12</ref><ref name="ハント(2016)75">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.75</ref>。 |
|||
エンゲルスは、マルクスの手で完成を見た[[唯物史観]]の普遍性を社会から自然の領域に拡張することを試みた。政治経済と並んで[[自然科学]]についても学び、[[哲学]]的な[[唯物論]]の立場から、自然の[[弁証法]]の解明と論理的把握を試みた。エンゲルスの書き残した自然の弁証法に関する論考は、最新の自然科学が常に(今日でも)直面する哲学的危機に対して、重要な、多くの示唆を与えている。 |
|||
シュトラウスの批判的な聖書学は、[[ブルーノ・バウアー]](1809-1882年)による哲学的な批判によってさらなる一歩を踏み出す。 |
|||
このようなマンチェスター時代の「二重生活」は、約20年間に及ぶこととなったが、その間に得た報酬の少なくない部分をマルクスに[[仕送り]]して、生活を支援した。[[亡命]]者として政府の監視の下貧困の極みにあったロンドンのマルクスとその家族の生活を何度となく救ったのはエンゲルスの財政的支援であった。1870年には、自らもロンドンに移住した。 |
|||
[[ボン大学]]の私講師であった[[ブルーノ・バウアー]]はシュトラウスよりも急進的な無神論者で、[[神]]を虚構とする立場から[[宗教]]を神話的な創作物として見ていた。'''『ヨハネによる福音書の史的批判』'''({{lang-de|''Kritik der evangelischen Geschichte des Johannes, 1840''}})において、バウアーは無神論的立場をヘーゲル哲学の「[[疎外]]」という概念によって用いることでより洗練された[[宗教社会学]]的な見解として打ち出すことになる<ref name="ハント(2016)75"/>。この見解は[[ルートヴィヒ・アンドレアス・フォイエルバッハ|フォイエルバッハ]](1804-1872年)へと継承され、「神が人間をつくったのではなく、人間が神を自らに似せて作ったのだ」とする投影理論として理論化されて発展を遂げていく<ref name="土屋(1995)12">{{Harvtxt|土屋保男|1995}} p.12</ref><ref name="ハント(2016)76">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.76</ref>。 |
|||
1841年、フォイエルバッハは『'''[[キリスト教の本質]]'''』({{lang-de|''Das Wesen des Christentums, Leipzig 1841''}})を世に送り出す。人間は自らの本質を自分の外に表出させて、理想化した自画像を神として打ち立てて崇拝をはじめ、やがて宗教組織や教義に服従することによって人間の自己疎外が制度化される、こうした疎外の過程が宗教だと指摘した。フォイエルバッハはバウアーの疎外論を利用して唯物論から宗教の本質を論じ、それが人間性の自己疎外であったことを解明した。観念論から唯物論、神学から人間学への移行によって学問体系を転換することを訴えた<ref name="ハント(2016)76-78">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.76-78</ref>。 |
|||
{{main|青年ヘーゲル派|ブルーノ・バウアー|ルートヴィヒ・アンドレアス・フォイエルバッハ}} |
|||
==== マルクスとの出会い ==== |
|||
[[Image:Skiz-hegel.png|thumb|230px|エンゲルスによる風刺画。青年ヘーゲル派の人物が描かれている{{#tag:ref|このスケッチに描かれているのは[[青年ヘーゲル派]]フライエンの代表人物である。左から[[アーノルド・ルーゲ]]と彼に拳を挙げて向かう[[ブルーノ・バウアー]]、机を叩く[[エトガー・バウアー]]、煙草を吹かす[[マックス・シュティルナー]]と席について様子を眺める[[カール・ケッペン]]がいる。そして争う人々の上にはプロイセンの文部大臣アイヒホルンをもじったリス(独語でアイヒヒョーヒェン)とギロチンが描かれている。|group=注釈}}<ref name="ハント(2016)80">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.80</ref>。]] |
|||
1842年、エンゲルスはベルリン暮らしを満喫していた。愛犬に「ナーメンローザ」(名無しという意)という名をつけ、昼は大学の講義、夕べには帰宅して犬の散歩がてらに町を歩き、酒場で夕飯を食べる暮らしをしていた<ref name="ハント(2016)79"/>。青年ヘーゲル派の知識人たち、ブルーノ・バウアー、弟[[エトガー・バウアー]]、そして[[マックス・シュティルナー]]らと交流を重ね、エンゲルスはこれらの知識人の一派として認知されるようになった<ref name="土屋(1995)13">{{Harvtxt|土屋保男|1995}} p.13</ref>。しかし、青年ヘーゲル派の知識人たちは中産階級的なライフスタイルへの反感から自由人を指す「フライエン」を称して犬儒的な快楽主義者を気取る素行不良なものも多かった<ref name="ハント(2016)80"/>。エンゲルスも危険思想に傾倒している青年として周囲から、そして両親からも心配されていた。 |
|||
1842年はエンゲルスにとって重要な年となった。この年の11月、後にエンゲルスの「第一バイオリン」となる[[カール・マルクス]]と出会うのである。きっかけはこの時期、エンゲルスが初期の[[社会主義]]者[[モーゼス・ヘス]](1812-1875年)や[[ローレンツ・シュタイン]](1815-1890年)の活動に刺激を受けたことにある。 |
|||
[[ファイル:Moses-Hess.jpg|thumb|230px|1846年のモーゼス・ヘス]] |
|||
[[モーゼス・ヘス]]は[[ボン]]でユダヤ系の製糖業者の家に生まれた人物で、エンゲルスと同様、父親の家業を継ぐことや厳格な宗教伝統への嫌悪感から無神論者となり、宗教に代わる思想としてフランスの[[アンリ・ド・サン=シモン|サン・シモン]]の思想や[[オーギュスト・ブランキ|ブランキ]]の革命運動論に影響を受けた。1837年には『神聖な人類史』において貧困層と富裕なブルジョアとの社会的格差を前に、[[フランソワ・ノエル・バブーフ|バブーフ]]が提唱した財産共有に基づく共産社会が道徳的に望ましい社会であると早くも訴えた。1840年代に入ると、フォイエルバッハの[[唯物主義]]的ヒューマニズムをバブーフが説く平等主義と結びつけた[[社会主義]]思想を模索した。また、ヘスはヘーゲル哲学を分析や批判の道具から行動と変革の実践的理論へと変換させようと試みたポーランド人のチェフコースキの著作『歴史知識体系序文』により青年ヘーゲル派の思想に刺激を受け、社会主義と[[革命]]思想とを結合させた。[[資本主義]]内部の社会矛盾を革命に転化させることを論じ、工業化の進んだブリテンで[[社会主義革命]]が起こることを感じた最初の人物であり、マルクスとエンゲルスの思想形成に大きな影響を与えた。 |
|||
エンゲルスはドイツ社会主義の先駆者であるヘスのマルクスに対する賛辞から将来有望な青年思想家の存在を知り、ベルリンからの帰郷の途上ヘスが創刊した『ライン新聞』の事務所に立ち寄り、そこでマルクスと初めて面会した。このときの出会いはマルクスの誤解もあって、実に素気ないものであった<ref name="土屋(1995)12"/><ref name="ハント(2016)90-91">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.90-91</ref>。 |
|||
この頃、マルクスは穏健な改革主義者として『{{仮リンク|ライン新聞|en|Rheinische Zeitung}}』({{lang-de|''Rheinische Zeitung''}})の編集長として活動しており、自分の思想と行動が品性に欠く青年ヘーゲル派の知識人たちの活動と同一視されて哲学とジャーナリズムに対する偏見が強まり、政府の監視と検閲で仕事ができなくなることを警戒していた<ref name="ハント(2016)90">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.90</ref>。そのため、当初のところ後に盟友となるエンゲルスに対しても警戒感を抱いていたのである。また、マルクスは嫉妬心の強い性格で、二歳年下のエンゲルスが文壇で活躍していることに妬んでいた<ref name="ハント(2016)91">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.91</ref>。しかし、マルクスとの交信はその後も続き、後の深い友情と信頼の基礎を築いていく。 |
|||
エンゲルスは一年の兵役期間を終えて、ベルリンを離れることとなる。父フリードリヒは息子の急進的な思想に危機感を感じ、再び家業を任せて現実的で堅実な生き方ができるよう、「エルメン&エンゲルス商会」のソルフォード支社を管理する立場に据えることにした。エンゲルスは[[マンチェスター]]に発つことになった。 |
|||
{{main|モーゼス・ヘス|カール・マルクス}} |
|||
=== マンチェスター時代 === |
|||
==== 『イギリスにおける労働者階級の状態』 ==== |
|||
[[File:Cottonopolis1.jpg|thumb|300px|1840年代のマンチェスター遠景]] |
|||
[[File:Die Lage der arbeitenden Klasse in England.png|thumb|200px|『イギリスにおける労働者階級の状態』の扉]] |
|||
[[1842年]]11月下旬、父は[[マンチェスター]]西部ソルフォードに立地する「エルメン&エンゲルス商会」の紡績工場「ヴィクトリア工場」で経営に従事させるため、彼をマンチェスターに送った<ref name="土屋(1995)84">{{Harvtxt|土屋保男|1995}} p.84</ref>。マンチェスターは[[イングランド]]北部を代表する当時人口40万人の工業都市であり、多数の世界的な紡績工場と市場、証券取引所を抱え、「コットンポリス」と称された<ref name="ハント(2016)109-110">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.109-110</ref>。エンゲルスは以降20カ月、紡績工場で400名の労働者と共に働き、[[産業革命]]をいち早く遂げたブリテン[[資本主義]]による[[搾取]]の最前線で[[共産主義]]的理想との矛盾した立場に置かれる<ref name="ハント(2016)117">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.117</ref>。しかし、エンゲルスは持ち前の行動的な姿勢を通じてこの問題と向き合おうと努める。すなわち、労働者との交流と彼らの貧困に関するフィールドワークである。 |
|||
エンゲルスは『'''{{仮リンク|イギリスにおける労働者階級の状態|en|The Condition of the Working Class in England|de|Die Lage der arbeitenden Klasse in England}}'''』({{lang-de|''Die Lage der arbeitenden Klasse in England,1845''}}[http://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/condition-working-class/index.htm]) 序文で、このときの調査を「圧制者の社会的・政治的権力に対する労働者の闘争をこの目で見たい」という考えのもと、「中間階級の会合や宴会、ポートワイン、シャンパンを断念して、自由な時間をほとんどすべて普通の労働者との交際に費やして」、労働者を「諸君の住宅にたずね、日常生活を観察し、生活条件や苦悩について語りあい」、「本当の生活を知り」、「抑圧され中傷されている階級を公平に扱う機会を得る」とともに「中間階級の残忍さを知った」と語った<ref name="マルクス・エンゲルス全集 2巻(1960)225">全集 2巻(1960) p.225</ref>。 |
|||
{{main|マンチェスター}} |
|||
[[File:Portrait of Robert Owen (1771 - 1858) by John Cranch, 1845.jpg|thumb|200px|1845年のロバート・オウエン]] |
|||
[[File:ChartistRiot.jpg|thumb|300px|チャーティスト暴動]] |
|||
まず、労働者との交友を見てみよう。このとき、エンゲルスは工業化の進展とともに悪化した労働者の生活状況の描写に力を注いだ。案内役としてブラッドフォードで事務員をしていた亡命共産主義者ゲオログ・ヴェートルがエンゲルスと同行していた<ref name="ハント(2016)128">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.128</ref>。この時期のエンゲルスは[[メアリー・バーンズ]]という愛人をつくっている。彼女は[[アイルランド]]系の紡績女工で教育は無かったが、エンゲルスを不衛生で危険が伴う貧しきアイルランド移民の世界へと招待する役割を果たしている<ref name="ハント(2016)129">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.129</ref>。そこで彼は、「イングランドのプロレタリアートと、その努力、苦しみと悲しみを知る」べく[[スラム]]街へと足を運んで都市貧民の生活に入り込んで取材と調査を進め、[[都市]]の広範囲に拡がった[[貧困]]に衝撃を受けて労働者の状態を伝える詳細な報告を執筆した。 |
|||
また、労働者は社会環境の悪化に抵抗すべく自衛のために活発な社会運動を発展させたが、エンゲルスはマンチェスターで初めて革命的プロレタリアートの運動を目の当たりにして強い刺激を受けた。それが[[ロバート・オウエン]]による社会主義運動([[空想的社会主義]])と『人民憲章』を旗印に普通選挙権獲得を目指し民主化運動を展開していた[[チャーティスト運動]]{{#tag:ref|ブリテンでは19世紀に入り[[産業革命]]の本格的進展によって各地の産業構造に変化が生じ、南部の農村地帯から北部の工業地帯へと人口移動がおこっていた。その結果、北部の工業都市に移住した多数の労働者が政治的権利のない二級市民の立場に置かれていた。それまで合理性があった旧来の選挙制度は急速に時代にそぐわないものとなっていた。イギリスでは議会制度の腐敗が進み、改革は避けがたいものとなっていたこうして大規模な社会変動、政治変動が始まる。1832年、[[第一次選挙法改正]]が実現した。このときの改革では、都市選挙区に居住する10ポンド以上の家屋・店舗を占有する戸主、州選挙区に居住する10ポンド以上の長期(60年)自由土地保有者、50ポンド以上の短期(20年)自由土地保有者に選挙権が与えられ、議席再配分によって[[腐敗選挙区]]の廃止と工業都市への選挙区の割り振りが実施された。だが、労働者には選挙権は与えられず、改革は未解決のままに残され、議会改革問題は[[チャーティズム|チャーティスト運動]]へと引き継がれる<ref name="古賀秀男(1980)3-4,54-55">{{Harvtxt|古賀秀男|1980}} pp.3-4,54-55</ref>。南部のロンドンからエンゲルスがいたイングランド北部マンチャスターに連なる工業都市がチャーティスト運動の一大拠点となっていた<ref name="古賀秀男(1980)87-89">{{Harvtxt|古賀秀男|1980}} pp.87-89</ref>。|group=注釈}}であった。 |
|||
オウエンは、産業の発達を真に担ったのは労働者であり、その労働者が貧しいのは資本家が搾取するためである、従って、労働者救済のために強固な組合組織と教育活動による社会の改良が必要であると考えていた。こうした考えは協同組合運動への労働者の結集へとつながっていく<ref name="古賀秀男(1980)51-53">{{Harvtxt|古賀秀男|1980}} pp.51-53</ref>。 |
|||
一方、チャーティストも民主主義の実現によって労働者を解放し、労働者を基盤にした人民の政府によって資本主義の諸矛盾の解決策を模索するという展望を持って、労働者を民主化運動のもとに集結させようとしていた。両派は競合関係にあったが、チャーティスト運動が次第に優勢になっていった<ref name="ハント(2016)123">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.123</ref>。エンゲルスはオウエン派の共産村集落に出かけたり、社会主義を信奉する多くの人々が交流会を楽しんでいたオウエン科学館を訪問し、合唱会や催眠術の披露といった催しものにも参加した<ref name="ハント(2016)118-123">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.118-123</ref>。エンゲルスは各地で運動を展開するチャーティストやオウエン主義者の集会に参加し、チャーティスト有力誌{{仮リンク|『ノーザン・スター』|en|Northern Star (Chartist newspaper)}}({{lang-en|''Northern Star''}})やオウエン派新聞{{仮リンク|『ニュー・モラル・ワールド』|en|New Moral World}}({{lang-en|''New Moral World''}})の熱心な購読者となってイギリス社会主義の情勢を研究するようになる。マンチェスターの地を踏んだ1842年はチャーティスト運動の全盛期に当たり、彼の到着の半年前、プレストンにて{{仮リンク|点火栓抜き暴動|en|1842 General Strike}}という大規模な騒擾が発生し、警察と群衆の衝突も発生していた。ブリテン産業界は混乱状態に陥るが、体制による弾圧政策によって工場操業の危機を脱した。このときエンゲルスが属す「エルメン&エンゲルス商会」は騒擾を鎮圧した警察に感謝の意を表す広告を新聞に掲示するなど体制側の対応を歓迎した。こうした事情からチャーティストによる騒擾は工場経営に影響する現実的な危機として考えられており、エンゲルス個人にとっても時代の潮流に無関心ではいられなかったのである<ref name="ハント(2016)105-107">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.105-107</ref>。 |
|||
危機的状況に置かれていた1843年秋、エンゲルスは[[リーズ]]の『ノーザン・スター』事務所に赴き、チャーティスト運動の急進的活動家であった{{仮リンク|ジョージ・ジュリアン・ハーニー|en|George Julian Harney}}と出会っている。エンゲルスはハーニーの議会主義的傾向に反発し、たびたび衝突しながらも若き頃の革命の同志として半世紀近く親密な関係を築いていく。ハーニー等チャーティストはウェストミンスター議会が「人民憲章」を採択して[[民主主義]]を実現することがブリテン社会に根差した階級支配の病根を治療する最善策であり、人民の革命によって国家という盗賊を懲罰せねばならないとして考えていた。 |
|||
しかし、エンゲルスは[[資本主義]]社会に内在する矛盾を解消するということは民主主義によって実現する問題ではないと見た<ref name="ハント(2016)124-126">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.124-126</ref>。これについては[[トーマス・カーライル]]など著名な文学者たちの批判的な意見に刺激を受けるところが大きかった。カーライルはブリテンの社会病理は資本主義という経済的構造にその病根があると見ており、政治的変革では根治しえないと考えていた<ref name="ハント(2016)126-128">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.126-128</ref>。エンゲルスはカーライルの社会観を引き継ぎ、資本主義という社会病理の研究のために、まずその社会的実態の把握に注力した。資本主義の矛盾点を描写し、人間を回復する道筋を資本主義社会の現実を研究する方向に求めていったのである。彼は週末になるとマンチェスターを離れて[[リヴァプール]]や[[ロンドン]]に出かけ、労働者の状況を示した統計調査や議会資料、工場監督官や医師の報告書などの資料調査をおこない、科学的手順に基づき綿密な研究を実施した<ref name="大内(1964)108">{{Harvtxt|大内|1964}} p.108</ref>。社会の避けがたい現実の側面であった都市の貧困に関する研究は、エンゲルスに様々な知見をもたらした。そして、「財産とは盗みである」と指摘した[[プルードン]]の思想に触れて、資本主義の病理である貧困の根底には私有財産の制度が存在することを発見していく<ref name="ハント(2016)134-135">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.134-135</ref>。 |
|||
この報告は、後に[[1845年]]に『イギリスにおける労働者階級の状態』として出版され、[[カール・マルクス]]や後継者の[[ウラジーミル・レーニン]]によって労働者階級に関する歴史的な文献として極めて高い評価を与えられることとなった<ref name="大内(1964)108-109">{{Harvtxt|大内|1964}} pp.108-109</ref>。エンゲルスはすでにこの頃より、持ち前の好奇心と行動力によって活発な取材を展開し、[[ジャーナリスト]]としての才を示している。 |
|||
{{main|ロバート・オウエン|空想的社会主義|チャーティスト運動}} |
|||
==== 共産主義に向かって ==== |
|||
1843年10月、マルクスと妊娠中の妻[[イェニー・マルクス]]が[[パリ]]に到着した。この転居には事情があった。ロシアのツアーリ[[ニコライ1世 (ロシア皇帝)|ニコライ1世]]がヘスとマルクスが主宰する『ライン新聞』にあって、ロシアを批判する記事を目にして不快感を表明し、同盟国プロイセンに圧力をかけて、新聞の発行許可を取り消すように要望したのである。これにより『ライン新聞』は廃刊に追い込まれ、マルクスは失職してしまう。しかし、この後幸運にも[[アーノルド・ルーゲ]]から新しい新聞の立ち上げの話を持ちかけられ、マルクスはこれを承諾した。新新聞の発行地はドイツ人亡命者が多いフランスの首都パリに定められ、これを受けてマルクスもパリに移ることとなった<ref name="ハント(2016)155">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.155</ref>。1844年2月、エンゲルスは[[カール・マルクス|マルクス]]によって編集・出版された『[[独仏年誌]]』({{lang-de|''Deutsch–Französische Jahrbücher''}}) という雑誌が創刊される。マルクスは、「'''[[ユダヤ人問題によせて]]'''」と「'''{{仮リンク|ヘーゲル法哲学批判序説|de|Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie}}'''」の二編の論文を投稿している。 |
|||
この論文中では「大事なことは政治的解放(国家が政治的権利や自由を与える)ではなく、市民社会(資本主義経済)からの人間的解放だ」<ref name="小牧(1966)113">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.113</ref>、「哲学が批判すべきは宗教ではなく、人々が宗教という阿片に頼らざるを得ない人間疎外の状況を作っている国家、市民社会、そしてそれを是認するヘーゲル哲学である」と論じた<ref name="小牧(1966)115">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.115</ref>。「徹底的な非人間状態に置かれ」、「市民社会の階級でありながら市民から疎外されているプロレタリアート階級」を新時代の「心臓」とする「人間解放」を行うべきだと喝破した<ref>[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.116-117</ref><ref name="ハント(2016)156">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.156</ref>。 |
|||
マルクスはパリの労働者集会にも参加し、[[労働運動]]の可能性を感じ始めた。 |
|||
1844年8月、フォイエルバッハへの手紙では「フランスの労働者の集会に一度出席なさるといいでしょう。そうすればこうした酷使された人々の間に、若さあふれる溌剌感や高貴さが満ち溢れていることを信じられるはずです」と語っている。マルクスはパリでの体験を通じて「われわれの文明社会にいるこの未開人たちのあいだで、歴史は人間の解放のために活動する実際的分子を準備している」と考えるようになった。プロレタリアートによる人間の解放に強い希望を感じるようになり、マルクスはより一層、青年ヘーゲル派に距離を置き始め、共産主義者へと変貌し始めていった<ref name="ハント(2016)155"/>。 |
|||
エンゲルスも、同誌に当時最先端の経済学であった[[古典派経済学]]を批判的に検討した自らの論文'''「国民経済学批判大綱」'''({{lang-de|''Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie,1844''}})を寄稿し、創刊号を飾った。エンゲルスはこの中でブリテンの完成した産業資本主義に触れた経験から私有財産制やそれを正当化する[[アダム・スミス]]、[[デヴィッド・リカード]]、[[ジャン=バティスト・セイ]]を批判した。古典派経済学を資本主義がもつ法則性を研究したと評価する一方、現状を無批判に肯定して社会の病理を覆い隠すものとして糾弾したのである<ref name="城塚(1970)128">城塚(1970) p.128</ref><ref name="大内(1964)114">{{Harvtxt|大内|1964}} p.114</ref>。同論文の内容は[[ピエール・プルードン]]の影響を受けて、貧困の根源を成している私有財産制度の問題点を指摘するものであった<ref name="ハント(2016)134-135"/>。伝記筆者のトラストラム・ハントは本論文を『イギリスにおける労働者階級の状態』と加えて「青年ヘーゲル派の疎外の概念を、ヴィクトリア朝時代のイギリスの物質的現実にあてはめ、そこから科学的社会主義の思想面の構造を作り出し」、革命によるブルジョワの打倒の道が準備されているという認識を明示するものと位置付けた他、同様にエンゲルス研究者の土屋保男は「労働者に彼らのあらゆる苦難の根源である経済関係を明らかにし、資本と労働の対立と闘争のよってきたる基本的関係―生産手段の所有と無所有―を見極めて、この関係の打倒こそが労働者に新しい未来を開く」のだという点を明示し、マルクス主義の理論形成に重要な意義を持っている作品として高く評価した<ref name="ハント(2016)148-152">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.148-152</ref><ref name="土屋(1995)89">{{Harvtxt|土屋保男|1995}} p.89</ref>。これはヘスや後に衝突するヴァイトリングが主導した道徳的で、かつメシア的共産主義運動を超克し、経済法則に社会現象の根底を見出し、人類史の巨大なうねりの中でプロレタリアートの勝利を導きだす史的唯物論―唯物主義的な共産主義―の理論的確立に貢献するものであった<ref name="土屋(1995)90">{{Harvtxt|土屋保男|1995}} p.90</ref>。また、経済学の分野の研究においてエンゲルスがマルクスに先んじていることを示しており、マルクスが経済学の道へ本格的につき進む契機となって、経済学に対する歴史的パースペクティブからのちのマルクスによってその歴史的価値を高く評価された。エンゲルスに感化されたマルクスは経済学や社会主義、フランス革命についての研究を本格的に行うようになっていく<ref name="ハント(2016)155-156">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.155-156</ref>。これ以降、マルクスは[[アンリ・ド・サン=シモン|サン・シモン]]、[[シャルル・フーリエ]]、[[ロバート・オウエン]]といった社会主義者の文献を批判的に検討し、社会主義の必要性と可能性の探求を進めた<ref name="小牧(1966)122">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.122</ref>。マルクスはエンゲルスの示唆から着想を受けて宗教による疎外の問題から資本主義社会における現実の問題へと関心を移していく。 |
|||
1844年8月から『[[1844年の経済哲学手稿|'''経済学・哲学草稿''']]』({{lang-de|''Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844''}})の本格的な執筆に入る。本書にあって、マルクスは階級に基づく資本主義的生産の体制と私的所有の制度は近代市民社会において不可分の関係であり、この両者は資本家による搾取とその帰結である労働者の貧困と自己疎外を生み出す根源であることを指摘した。そして、私的所有の制度を廃止することによって資本主義という階級支配の社会的機構を乗り越え、プロレタリアートは人間性を回復することができると結論付けた。[[共産主義]]こそ人間解放の真髄である、これがマルクスとエンゲルスの生涯を通じての信念となっていく。両者はやがて固い絆を築いていくことになる<ref name="小牧(1966)123-125">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] pp.123-125</ref>。 |
|||
=== マルクスとの共同研究の開始 === |
|||
==== パリ時代―青年ヘーゲル派批判 ==== |
|||
[[File:Holybookmarxengels.gif|thumb|170px|『聖家族』の扉]] |
|||
[[Image:Bruno Bauer.jpg|thumb|170px|ブルーノ・バウアー]] |
|||
1844年、『独仏年誌』への論文投稿を通じてマルクスとエンゲルスは手紙を交わすようになっており、両者の関係は急激に縮まっていった<ref name="ハント(2016)156"/><ref name="大内(1964)115">{{Harvtxt|大内|1964}} p.115</ref>。 |
|||
8月、エンゲルスはマンチェスターからドイツに帰る目処を着ける。帰国の途中でエンゲルスは[[パリ]]でマルクスと再会し、お互いが思想面で[[資本主義]]に関する同じ考え方を共有していることを認識して、二年前の冷ややかな対面とは打って変わり仕事面でも親密な関係を築き、強い友情で結ばれていくようになった<ref name="ハント(2016)156-157">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.156-157</ref><ref name="大内(1964)111-112,115">{{Harvtxt|大内|1964}} pp.111-112,115</ref><ref name="土屋(1995)95">{{Harvtxt|土屋保男|1995}} p.95</ref>。エンゲルスはパリに立ち寄って8月から9月にかけての10日間マルクスの自宅に滞在し、ドイツの哲学界を酒の肴に連日飲み交わし、翌年出版した論争の書'''『[[聖家族 (政治思想書)|聖家族]] 批判的批判の批判―ブルーノ・バウアーとその伴侶を駁す』'''({{lang-de|''Die heilige Familie, oder Kritik der Kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer & Consorten, (mit Marx) 1845''}})を共同執筆している<ref name="大内(1964)115"/><ref name="土屋(1995)95"/><ref name="ハント(2016)159">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.159</ref>。 |
|||
この書ではヘーゲル哲学の中心的な方法論となっていた「[[弁証法]]」が評価される一方で、[[観念論]]に基づいた「精神」中心の世界解釈に限界があることを指摘している。「ヘーゲルの弁証法は素晴らしいが、一切の本質を人間ではなく精神に持ってきたのは誤りである。神と人間が逆さまになっていたように精神と人間が逆さまになっている。だからこれをひっくり返した新しい弁証法を確立せねばならない」と訴えた。 |
|||
また、マルクスのかつての盟友である[[ブルーノ・バウアー]]やフォイエルバッハの宗教批判や文化批評に特化した旧来的な[[唯物論]]に対して批判が加えられている。青年ヘーゲル派は哲学に人間解放の理想を追求しているものの、ブルジョワ的な思考に固着しており、人間そのもの、殊に困窮するプロレタリアートに近づこうとはしなかった。マルクスは人間解放の希望を抑圧を受け苦難を背負ったプロレタリアートに見出すとともに、こうした青年ヘーゲル派の超然的な姿勢を糾弾した。 |
|||
マルクスとエンゲルスはヘーゲルとバウアー、フォイエルバッハの歴史観に関して容赦しなかった。「歴史は何もせず、莫大な富を持たず、どんな戦いも仕掛けない」、「財産を所有し行動を起こし、戦争をするのは〈歴史〉ではなく、生身の人間なのだ。己の目的を達成するに人間を利用する、〈歴史〉と呼ばれる独立した存在などない。歴史は単に、目的を持った人間の活動に過ぎない」と指摘した。この歴史観はヘーゲルの歴史哲学を批判するものであり、青年ヘーゲル派の人間主義を批判するものであった。マルクスとエンゲルスによって初めて提示されたこの思想は'''[[史的唯物論]]'''へと発展を遂げていく。 |
|||
{{main|聖家族 (政治思想書)}} |
|||
9月中旬、エンゲルスはマルクスにしばしの別れを告げてバルメンに帰郷することとなった。しかし、エンゲルスは備忘録として個人的に書き残した大事な草稿をマルクス宅に置き忘れてしまう。マルクスがこの草稿を発見するやいなや即座に自身の見解を盛り込んで共著という体裁で公表してしまったのである。そのタイトルは『批判的批判の批判』であったが、新たに『聖家族』と変更された<ref name="ハント(2016)160">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.160</ref>。これは敬虔主義を奉ずる信仰心の篤いエンゲルス家にショックを与えた。エンゲルスの家庭内での立場はますます悪化し、憤慨する父は息子の給金を減額して応酬した。エンゲルスは激怒する父親の制裁に怯まなかった<ref name="ハント(2016)161">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.161</ref>。 |
|||
1844年はドイツにとって政情不安が蔓延した年で、各地で民衆騒擾が発生していた。 |
|||
代表的なものとして1844年6月にシレジア地方ペーターズヴァルダウで発生した職工による一揆が挙げられる<ref name="ハント(2016)162-163">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.162-163</ref>。世情の緊迫化はエンゲルスの士気を鼓舞するものとなった。ラインラントにも初期の[[共産主義]]運動が浸透し始め、エンゲルスはバルメンに帰郷すると、共産主義を宣伝する集会を開催して講演者を務めた<ref name="ハント(2016)163">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.163</ref><ref name="土屋(1995)96-97">{{Harvtxt|土屋保男|1995}} pp.96-97</ref>。エンゲルスは[[資本主義]]の不公正によって貧富の格差が広がり、中産階級が消滅して[[階級]]間の緊張が激化し、やがて社会に蓄積された緊張は階級闘争へと発展して[[革命]]を引き起こすと喧伝した。 |
|||
この革命はプロレタリアートによる[[社会主義]]の革命であり、古い階級支配を廃止して、新秩序を打ち立てることになる。資本主義に対して共産主義が取って代わり、資本と労働は政府の管理によって効率的に配分され、生産性が高まって共産主義が貧困に勝利を収めて、全市民に[[福祉]]を提供してすべての人間が平等な社会―すなわち共産主義社会が実現されると約束した<ref name="ハント(2016)165">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.165</ref>。こうした主張は後の'''『[[共産党宣言]]』'''の中心的内容を占めていく。 |
|||
だが、エンゲルスの扇動的な主張は治安当局の危機感を煽るものであった。エンゲルスは[[警察]]から要注意人物の認定を受け、警察は「在バルメンのフリードリヒ・エンゲルス(父)は真に信頼できる人物であるが、同人には、たちの悪い共産主義者で文士として放浪している息子がいる」として[[内務省]]に通報、エンゲルスとその一派に対する処遇の検討に入る。プロイセンの内務大臣とライン州の首相の名をもって共産主義の集会を開くことが禁じられてしまう<ref name="ハント(2016)166">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.166</ref><ref name="土屋(1995)98">{{Harvtxt|土屋保男|1995}} p.98</ref>。恥をかいた父親はますます憤慨し、息子に対して勘当同然の扱いをした。親子関係はさらに険悪化したが、エンゲルスの意志は固かった。1844年11月から翌1845年1月にかけて、エンゲルスは自室に籠って『'''{{仮リンク|イングランドにおける労働者階級の状態|en|The Condition of the Working Class in England|de|Die Lage der arbeitenden Klasse in England}}'''』の執筆に取り掛かる。エンゲルスは家族と別れを告げてでも信念を全うする覚悟を固めていた<ref name="ハント(2016)166-167">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.166-167</ref><ref name="土屋(1995)102">{{Harvtxt|土屋保男|1995}} p.102</ref>。 |
|||
==== ブリュッセル時代―史的唯物論の形成 ==== |
|||
1845年1月、マルクスは[[フランス]]政府当局から強制国外退去を命じられた後、[[ヨーロッパ]]の他の国よりも比較的[[表現の自由]]が保証されていた[[ベルギー]]に活動の場を移した<ref name="ハント(2016)167">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.167</ref><ref name="大内(1964)117">{{Harvtxt|大内|1964}} p.117</ref>。エンゲルスもマルクスと活動を共にするため、故郷を離れる決断を下す。このときの心境をエンゲルスはマルクスに語っている。 |
|||
{{Quotation|「こういう小銭稼ぎはやりきれない。バルメンはやりきれない。ここの人間の暮らしはやりきれない。しかし、何よりやりきれないのは、ただのブルジョワ以上に、工場主として、本当のブルジョワとして、正面切ってプロレタリアートに対抗することくらいやりきれないものはない。僕はここで親父の工場に数日座っていて、いまさらのように、そう思った。前にはこれほどには思わなかったのにだ。……。人間は、……事業をして、小銭を稼いで、その上に共産主義のプロパガンダをやろうというのは、とても駄目だ!ぼくはイースターにはここを逃げ出す。こんな退屈な生活に加えて、実に完全にやかましいプロイセンの宗教的家庭とは仕方がないものだ。下手をするとぼくはドイツの無教養な俗物になりそうだ。そして俗物主義を共産主義の内に持ち込みそうだ。」<ref name="大内(1964)116">{{Harvtxt|大内|1964}} p.116</ref><ref name="土屋(1995)99">{{Harvtxt|土屋保男|1995}} p.99</ref>}} |
|||
実家を去ったエンゲルスはマルクスと共にブリテンへと視察旅行に行く。二人は連日マンチェスターのチータム図書館に通った。日当たりの良い弓なりの出窓にお決まりの席を見つけて、経済学の著作を精読すると共に公文書を閲覧し、資料収集を進めた<ref name="ハント(2016)167-168">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.167-168</ref>。この視察は短期間で目的を果たし、1845年4月にはエンゲルスもベルギーの首都ブリュッセルに移住、二人はアパートの隣同士で部屋を借り暮らすことにした。ブリュッセルにはマルクス以外にもドイツからの亡命共産主義者が多く滞在しており、[[モーゼス・ヘス]]、ゲオログ・ヴェートル、{{仮リンク|シュテファン・ボルン|de|Stephan Born}}、カール・ハインツェン、詩人[[フェルディナント・フライリヒラート]]、元プロイセン軍将校のジャーナリストである{{仮リンク|ヨーゼフ・ヴァイデマイヤー|de|Joseph Weydemeyer}}、学校教師の{{仮リンク|ヴィルヘルム・ヴォルフ|de|Wilhelm Wolff (Publizist)}}、マルクスの義弟{{仮リンク|エドガー・フォン・ヴェストファーレン|de|Edgar von Westphalen}}などが近隣に居住し、彼らは夜な夜な酒場に繰り出しては哲学談義を華を咲かせる飲み仲間でもあった<ref name="ハント(2016)168">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.168</ref>。こうした環境で、出版社が見つからなかったため1923年まで未公刊にあったが、マルクスとエンゲルスは共著で'''『[[ドイツ・イデオロギー]]』'''({{lang-de|''Die deutsche Ideologie, (mit Marx) 1845''}})という偉大な草稿を製作していく<ref name="ハント(2016)171">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.171</ref>。 |
|||
マルクスは、青年ヘーゲル派も含めドイツの思想は[[ヘーゲル]]哲学に由来する観念的な[[イデオロギー]]であることを指摘した<ref name="ハント(2016)171"/>。ヘーゲル派は自由を意識する精神が支配と闘争しながら歴史を前進させ、社会を合理的に編成していったという考え方を支持し、歴史を観念的な理想が実現される過程と見なした。だが、マルクスとエンゲルスは思弁的な[[歴史哲学講義|歴史哲学]]を頭と四肢とを転倒させるようなグロテスクな考えであると見た。これに対して、[[唯物論]]を「天から地へと降りてくるドイツの哲学とは好対照に、これは地から天へと昇る」問題なのだと語り、唯物論は「生身の人間に到達するために、人が言ったり、想像したり、考えたりすることから始めるのではなく、現実に行動する人間から始め、生活過程のイデオロギー的反映や反響の展開を明らかにする実際の生活過程に基づくものである」と語って新思想の意義を評価した<ref name="マルクス・エンゲルス全集 3巻(1960)22">全集 3巻(1963) p.22</ref>。だが、唯物論のすべてを評価したわけでなく、[[フォイエルバッハ]]の唯物論に対しては痛烈な批判を加えた。フォイエルバッハは哲学によって神と対置されてきた生身の人間を考察し、宗教によって貶められてきた人間性の価値を再評価したが、唯物論を完成させることはできなかった。[[マックス・シュティルナー]]も人間の独立性を重んじ、絶対的[[自我]]の尊重を説くエゴイスティックな考えを提示したが、この両者は人間の存在を語りえたとしても人間の「歴史」を議論することができなかったのである<ref name="マルクス・エンゲルス全集 3巻(1960)15">全集 3巻(1963) p.15</ref>。「歴史」について考察する新たな唯物論を提示することが喫緊の課題となっていた<ref name="ハント(2016)172-173">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.172-173</ref>。 |
|||
{{main|ヘーゲル|歴史哲学講義|イデオロギー}} |
|||
マルクスとエンゲルスの関心の中心は人類史は如何に成立するのか、そして社会の歴史的な活動は何に基づいているのかという問題関心に置かれた。 |
|||
{{Quotation|「われわれが出発点としてとるところの諸前提は、……、現実的諸個人であり、および彼らの物質的生活諸条件―既存の生活諸条件ならびに彼ら自身の行動によって産出された生活諸条件―である。」<ref name="マルクス・エンゲルス全集 3巻(1960)15-16">全集 3巻(1963) pp.15-16</ref>}} |
|||
マルクスは歴史の出発点を現実に生きる人間の存在を支える物質的活動に求めた。ここで、マルクスが明らかにしたのは人類史を成立させるのは、存在のとりわけ物質的生活条件であってそれを支える生活手段の生産にあるということである。人類史は現に生きている人間が生活の糧を手に入れる生産の活動からはじまる。人間活動が歴史を創るわけだが、その活動の根源は現実の生のための必要物の創出、存在を規定する物質的諸条件の形成を意味する生産活動にあることを指摘した<ref name="マルクス・エンゲルス全集 3巻(1960)15-16">全集 3巻(1963) pp.15-16</ref>。 |
|||
{{Quotation|「かくて事実はこうである。すなわち特定の仕方で生産的に働いている特定の諸個人はある特定の社会的および政治的関係を結ぶ。経験的考察はそれぞれ個々の場合に社会的および政治的編成と生産の関連を経験的に、そして、ごまかしも思弁もなしに示すはずである。社会的編成と国家はたえず特定の諸個人の生活過程から出てくる。諸観念、諸表象の生産、意識の生産はさしあたり初めに人間たちの物質的活動や物質的交通―現実的生活の言語―に編みこまれている。人間たちの表象作用や思惟作用、彼らの精神的交通はここではまだ彼らの物質的ふるまいの直接的な流出として現われる。一民族の政治、法、道徳、宗教、形而上学、等々の言語のうちに現れるような精神的生産についても同様である。人間たちが彼らの諸表象や諸理念の生産者であるが、……、意識は意識された存在以外の何ものかでありうるためしはなく、そして人間たちの存在とは彼らの現実的生活過程のことである。」<ref name="マルクス・エンゲルス全集 3巻(1960)21-22">全集 3巻(1963) pp.21-22</ref>}} |
|||
マルクスは「意識が生活を規定するのではなく、生活が意識を規定する」と述べた<ref name="マルクス・エンゲルス全集 3巻(1960)22"/>。また、社会の生産力が進歩するとともに人々の物質的生産の様式が変容してそれに相応しい社会関係、政治的編成を作り上げ、物質的生産の状態が固有の政治機関を形成するようになると考えた。しかし、一旦、精神的労働が独立した活動を始めるとある時代に特徴的な法律、政治、意識の形態が問題になっている。既存の社会構造を弁護する強力な働きを始める。たとえば、[[古代]]では農業が社会の発展を促し、[[ラティフンディア]]における奴隷主と奴隷からなる[[奴隷制]]が普及して、奴隷を使役する体制を擁護する[[ローマ法]]や[[ギリシア哲学|古典哲学]]が誕生した。[[中世]]では[[三圃制]]農業が浸透し、領主が[[農奴]]を使役する[[封建制]]が存在、[[キリスト教]]と[[スコラ哲学]]が発達し、[[王権神授説]]が流布した。さらに、[[近代]]では[[蒸気機関]]が発明され工場制機械工業が確立し、[[資本家]]が[[労働者]]を使役する[[資本主義]]が発達して、産業を主導した[[ブルジョワジー]]によって[[古典派経済学]]と[[自由主義]]の思想が発展した。意識は存在から生まれ、やがて「経済」という物質的現実から独立した「文化」の世界を作り上げ、思想にまで発展した意識が歴史を支配する過程を描いた<ref name="マルクス・エンゲルス全集 3巻(1960)18-21">全集 3巻(1963) pp.18-21</ref>。 |
|||
マルクスは人類の歴史を労働の組織化の形態あるいは物質的な生産体制の変遷として理解して「古代奴隷制・中世封建制・近代資本制」という図式で捉えていった。この歴史的運動を支えていたのが生産力である<ref name="マルクス・エンゲルス全集 3巻(1960)25">全集 3巻(1963) p.25</ref>。生産力は道具や技術や知識の増加に比例して常に増大し続ける発展性が内在する。しかし、マルクスによると、人間は生産力と交通形態(生産関係)とのタイアップによって経済活動をして、この経済活動に従って歴史をつくりだしているが故に、生産力の発展性は社会の関係の組織編制(生産関係)のあり方に依存している。経済構造(生産関係)は一定の歴史期間内において合理性を有して生産力を刺激する。だが、生産力の発展という量的変化の増大に伴って生産関係に内在的な[[矛盾]]が蓄積されて、やがて社会の硬直化が進んで生産力の発展に対応することができず足かせとなっていく。そして、その矛盾が限界に達すると、生産関係も質的変化を遂げることを余儀なくされ[[革命]]が生じていく。その結果、[[下部構造]](経済)は変化して[[上部構造]](哲学・宗教・政治)を革命によって変革させると考えたのである<ref name="マルクス・エンゲルス全集 3巻(1960)65 69-70">全集 3巻(1963) p.65, pp.69-70</ref><ref name="マルクス・エンゲルス全集 4巻(1960)480">全集 4巻(1960) p.480</ref>。 |
|||
こうして、マルクスは意識を主題として歴史を捉えた[[歴史哲学講義|ヘーゲル的歴史観]]を批判的に乗り越えた。マルクスは『[[ドイツ・イデオロギー]]』において'''[[史的唯物論]]'''の理論化を進め、歴史の把握をめぐる謎に解答を与えるに至った。このときの業績は1848年の'''『[[共産党宣言]]』'''、1859年に刊行された'''『[[経済学批判]]』の序文'''({{lang-de|''Zur Kritik der politischen Ökonomie,1859''}})において史的唯物論として公式化され、マルクス主義を構成する重要理論の地位を占めるようになった。マルクスはこの理論を自らの「導きの糸」と呼んだ。その内容は以下の通りである。 |
|||
{{quotation|「人間は、その生活の社会的生産において、一定の、必然的な、かれらの意思から独立した諸関係を、つまりかれらの物質的生産諸力の一定の発生段階に対応する生産諸関係を、とりむすぶ。この生産諸関係の総体は社会の経済的機構を形づくっており、これが現実の土台となって、そのうえに、法律的、政治的上部構造がそびえたち、また、一定の社会的意識諸形態は、この現実の土台に対応している。物質的生活の生産様式は、社会的、政治的、精神的生活諸過程一般を制約する。人間の意識がその存在を規定するのではなくて、逆に、人間の社会的存在がその意識を規定するのである。 |
|||
社会の物質的生産諸力は、その発展がある段階にたっすると、いままでそれがそのなかで動いてきた既存の生産諸関係、あるいはその法的表現にすぎない所有諸関係と矛盾するようになる。これらの諸関係は、生産諸力の発展諸形態からその桎梏へと一変する。このとき社会革命の時期がはじまるのである。経済的基礎の変化につれて、巨大な上部構造全体が、徐々にせよ急激にせよ、くつがえる。 |
|||
このような諸変革を考察するさいには、経済的な生産諸条件におこった物質的な、自然科学的な正確さで確認できる変革と、人間がこの衝突を意識し、それと決戦する場となる法律、政治、宗教、芸術、または哲学の諸形態、つづめていえばイデオロギーの諸形態とを常に区別しなければならない。ある個人を判断するのに、かれが自分自身をどう考えているのかということにはたよれないのと同様、このような変革の時期を、その時代の意識から判断することはできないのであって、むしろ、この意識を、物質的生活の諸矛盾、社会的生産諸力と社会的生産諸関係とのあいだに現存する衝突から説明しなければならないのである。 |
|||
一つの社会構成は、すべての生産諸力がその中ではもう発展の余地がないほどに発展しないうちは崩壊することはけっしてなく、また新しいより高度な生産諸関係は、その物質的な存在諸条件が古い社会の胎内で孵化しおわるまでは、古いものにとってかわることはけっしてない。だから人間が立ちむかうのはいつも自分が解決できる問題だけである、というのは、もしさらに、くわしく考察するならば、課題そのものは、その解決の物質的諸条件がすでに現存しているか、またはすくなくともそれができはじめているばあいにかぎって発生するものだ、ということがつねにわかるであろうから。 |
|||
大ざっぱにいって経済的社会構成が進歩してゆく段階として、アジア的、古代的、封建的、および近代ブルジョア的生活様式をあげることができる。ブルジョア的生産諸関係は、社会的生産過程の敵対的な、といっても個人的な敵対の意味ではなく、諸個人の社会的生活諸条件から生じてくる敵対という意味での敵対的な、形態の最後のものである。しかし、ブルジョア社会の胎内で発展しつつある生産諸力は、同時にこの敵対関係の解決のための物質的諸条件をもつくりだす。だからこの社会構成をもって、人間社会の前史はおわりをつげるのである。」<ref name="経済学批判(1956)13-14">|経済学批判(1956) pp.13-14</ref>}} |
|||
{{main|ドイツ・イデオロギー|経済学批判|史的唯物論}} |
|||
=== 『共産党宣言』とエンゲルス === |
|||
==== 「共産主義者同盟」の発足 ==== |
|||
『フォイエルバッハに関するテーゼ』の結びで、マルクスとエンゲルスは次のように宣している。「哲学者はただ世界をさまざまに解釈してきたにすぎない。肝要なのは、世界を変革することである。」 |
|||
1845年以降、マルクスはこの言葉通り、エンゲルスとともに[[ブリュッセル]]において、革命運動に参加していくことになる<ref name="ハント(2016)175">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.175</ref>。 |
|||
1846年1月には来るべき革命期に備えヨーロッパ各地の[[社会主義]]運動を団結させるべく、ドイツ人共産主義者の団体「[[正義者同盟]]」({{lang-de|''der Bund der Gerechten''}})と提携する道を探る。「正義者同盟」はフランスに亡命したドイツ人共産主義者を構成員に1830年代に発足した秘密結社で、1839年5月パリで革命家[[オーギュスト・ブランキ]]とともに蜂起に参加するも失敗し、[[カール・シャッパー]]、{{仮リンク|ハインリヒ・バウアー|en|Heinrich Bauer (revolutionary)}}、{{仮リンク|ヨーゼフ・モル|de|Maximilien Joseph Moll}}ら三名の指導者はロンドンに亡命して、「ドイツ人労働者教育協会」({{lang-de|Deutscher Arbeiterbildungsverein}})という偽装組織を樹立していた。マルクスとエンゲルスはイギリスを視察旅行し、急進的なチャーティスト団体「友愛民主主義協会」({{lang-en|Fraternal Democrats}})との提携関係を築き、急進的な革命勢力の結集を試みるようになる。このとき選んだのが「正義者同盟」で、[[モーゼス・ヘス]]、義弟{{仮リンク|エドガー・フォン・ヴェストファーレン|de|Edgar von Westphalen}}、[[フェルディナント・フライリヒラート]]、{{仮リンク|ヨーゼフ・ヴァイデマイヤー|de|Joseph Weydemeyer}}、[[ヴィルヘルム・ヴァイトリング]]、{{仮リンク|ヘルマン・クリーゲ|de|Hermann Kriege}}、{{仮リンク|エルンスト・ドロンケ|de|Ernst Dronke (Schriftsteller)}}、{{仮リンク|シュテファン・ボルン|de|Stephan Born}}らとともに「正義者同盟」との連絡組織として「'''共産主義通信委員会'''」({{lang-en|Communist Correspondence Committee}})をブリュッセルに創設し、共産主義の旗のもとに革命の同志たちを結集させようと試みた<ref name="ハント(2016)175"/><ref name="大内(1964)124-125">{{Harvtxt|大内|1964}} pp.124-125</ref>。マルクスは[[民主主義]]の実現を目指し、貴族による封建的支配を崩壊させて民主主義を[[共産主義]]の入口にすることを運動の目標としていた<ref name="ハント(2016)176">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.176</ref>。 |
|||
[[image:WilhelmWeitling.jpg|thumb|200px|[[ヴィルヘルム・ヴァイトリング]]]] |
|||
マルクスは当面はブルジョア民主主義革命に向かって活動を展開した。マルクスはチャーティストと同盟し、フランスの革命派と協力して選挙法を改正することを当座の目標として掲げ、フランスとドイツの貴族勢力の闘争を想定し、ブルジョワジーとの提携の道も模索していた<ref name="ハント(2016)176"/>。 |
|||
しかし、マルクスの組織運営は独裁的と批判された。実際、マルクスは組織を創設してすぐに意見が異なるヴァイトリングとクリーゲを痛切に批判して、二人を強引な方法で除名へと追い込んでいった。 |
|||
ヴァイトリングは[[フランソワ・ノエル・バブーフ|バブーフ]]主義と[[キリスト教]]千年王国思想を融合させた素朴な共産主義を信奉していた人物であった。だが、マルクスが念頭に置くような科学的厳密さを無視して理想を語り、四万人の前科者を結集して武装して無鉄砲な蜂起論を唱えていた。かつてヴァイトリングはマルクスの目に英雄的革命家と評価されていたが、この時期には危険な大法螺吹きに映った。したがって、マルクスは「委員会」の会合時、ヴァイトリングに「これまでおろか者が人を救ったためしはない!」と怒鳴り付けた後組織から追放、ヴァイトリング一派を粛清している<ref name="ハント(2016)177-182">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.177-182</ref>。そのあと、すぐモーゼス・ヘスも道徳主義と優柔不断で一貫性の欠如した主義主張で糾弾され、個人的諍い(エンゲルスの「女性関係」を参照)の後に、除名される前に辞任した<ref name="ハント(2016)188-190">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.188-190</ref>。 |
|||
エンゲルスはマルクス主義理論の司法官的で異端審問官的な役割を果たして敵対路線とその思想を炙り出し、マルクスを支えて「委員会」におけるイデオロギー的路線を守ることに力を注いだ<ref name="ハント(2016)180">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.180</ref>。'''『{{仮リンク|共産主義の原理|en|Principles of Communism}}』'''({{lang-de|''Grundsätze des Kommunismus,1847''}})という教理問答式の小冊子を刊行した<ref name="ハント(2016)193">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.193</ref>。 |
|||
この後、マルクスは1840年6月に『財産とは何か』を執筆し、社会主義運動において一躍注目を浴びていた[[ピエール・ジョゼフ・プルードン|プルードン]]を「委員会」に招待している。だが、プルードンはマルクスの独裁的姿勢を嫌い、この申し出を拒絶している。 |
|||
マルクスはプルードンにひどく幻滅して敵意を抱くようになり、プルードンが1846年に『経済的矛盾の体系、または貧困の哲学』({{lang-fr|''Système des contradictions économiques, ou Philosophie de la misère''}})を刊行すると、1847年'''『[[哲学の貧困]]』'''({{lang-fr|''La misère de la philosophie''}})を執筆してすぐさま攻撃している。プルードンの思想は、政治不参加主義を掲げる小市民的、職人的な協同組合主義のイデオロギーで、資本主義の本質分析について歴史的背景とその展望を見据える視点に欠け、資本主義崩壊の契機とプロレタリアートの解放を提示することができない不完全な理論であった。マルクスはプルードン派メンバー[[カール・グリューン]]を除名した<ref name="ハント(2016)180-181">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.180-181</ref>。 |
|||
相次ぐ粛清の結果で会員が減少して活動が停滞に陥るなか、転機は訪れる。 |
|||
1847年6月、「正義者同盟」はマルクスの思想に影響を受け、ロンドンで大会を開催する。そして、「正義者同盟」は組織名を改称して新たに「'''[[共産主義者同盟 (1847年)|共産主義者同盟]]'''」({{lang-de|''der Bund der Kommunisten''}})([[1847年]] - [[1850年]])を呼称することとなる<ref name="ハント(2016)190-191">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.190-191</ref>。この大会にマルクスは財政的な事情で参加できなかったが、エンゲルスが参加してマルクスとエンゲルスは同盟の新会員となり、エンゲルスはパリ支部の代表に就任した。エンゲルスはパリ代表としてその成熟した活動の戦略の形成に大きな影響を与えた。[[1848年]]、エンゲルスとマルクスは[[共産主義]]の概要に関する大衆的な[[パンフレット]]を執筆した。エンゲルスが前年に刊行した『共産主義の原理』に基づいて書かれたその12,000語あまりのパンフレットは6週間で完成させ、これをもとに'''『[[共産党宣言]]』'''({{lang-de|''Manifest der Kommunistischen Partei, 1848''}})と題されたこの文献は1848年2月に出版された<ref name="ハント(2016)194-195">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.194-195</ref>。同年3月、エンゲルスとマルクスはベルギーを追放されてドイツの[[ケルン]]に移り、急進的な新聞『[[新ライン新聞]]』({{lang-de|''Neue Rheinische Zeitung''}}) を発刊した<ref name="ハント(2016)199">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.199</ref>。 |
|||
==== 『共産党宣言』 ==== |
|||
[[File:Communist-manifesto.png|thumb|200px|『共産党宣言』の扉]] |
|||
マルクスは『共産党宣言』において人類史を俯瞰して「歴史」というものが何であるかを明示した。 |
|||
{{Quotation|「今日までのあらゆる社会の歴史は、階級闘争の歴史である。 |
|||
封建社会の没落からうまれた近代ブルジョア社会は、階級対立を廃止しなかった。この社会はただ、新しい階級、抑圧の新しい条件、闘争の新しい形態を、古いものとおきかえたにすぎない。全社会は、敵対する二大陣営、たがいに直接に対立する二大階級にますます分裂しつつある。すなわち、ブルジョア階級とプロレタリア階級に、だんだんわかれていく。……ブルジョア階級が封建制度をうちたおすのにもちいたその武器が、いまや、ブルジョア階級自身にむけられている。……だが、ブルジョア階級は、…この武器をとるべき人々をもつくりだした。―すなわち、近代的労働者、プロレタリアを。 |
|||
ブルジョア階級すなわち資本が発達するに比例して、プロレタリアすなわち近代労働者の階級も発達する。彼らは、…自分の身を切り売りしなければならないこれらの労働者は、他のあらゆる売買される品物と同じように、一つの商品である。したがってまた、同じように、あらゆる競争の浮沈、あらゆる市場の変動にさらされている。だが、工業の発展とともに、プロレタリアは…大きな集団に結集され、その力は増大し、そしてますます自分らの力を感じるようになる。機械がますます労働の差異をけしさり、賃金をほとんどいたるところで同一の低い水準にひきさげるため、プロレタリアの内部の利害も生活状態も、ますます均等になってくる。ブルジョア相互の競争の増大と、そこからおこる商品恐慌とは、労働者の賃金をますます不定なものとする。ますます急速にすすむ絶え間ない機械の改良は、労働者の全生計をいよいよ不安定なものとする。……さらに、すでに見たように、工業の発展によって支配階級の多くの組成分子がプロレタリア階級にけおとされるか、あるいはすくなくともその生活条件をおびやかされる。彼らもまた、プロレタリア階級に教養のための多くの要素を供給する。 |
|||
最後に、階級闘争が決戦に近づく時期には、支配階級の内部、全旧社会の内部の解体過程は、きわめて激しい、鋭い性質をおび、……ブルジョア思想家の一部が、プロレタリアのがわにうつってくる。今日ブルジョアジーに対立しているすべての階級のなかで、ひとりプロレタリアだけが、真に革命的な階級である。その他の階級は、大工業とともにおとろえ没落する。プロレタリアは大工業のもっとも特有な産物である。個々の労働者と個々のブルジョアとの衝突は、ますます二つの階級の衝突の性質をおびてくる。……現代社会の最下層であるプロレタリアが起き上がり立ち上がることができるためには、公的社会を構成する諸層の全上部構造を空中に消し飛ばさなければならない。……おのおの国のプロレタリアも、まず自国のブルジョアジーを片付けなければならない。……それが公然たる革命となって爆発し、そしてプロレタリアがブルジョアジーを暴力的に転覆して、自己の支配権をうちたてるところまで到達した。 |
|||
これまでのすべての社会は、圧迫する階級と圧迫される階級との対立のうえに立っていた。しかし、一つの階級を抑圧しうるためには、抑圧される階級に、すくなくとも奴隷的な生存をつづけられるだけの条件が保障されていなければならない。……これに反して近代の労働者は、工業の進歩とともに向上する代わりに、彼ら自身の階級の生存条件以下にますますしずんでゆく。労働者は貧窮者となり、貧窮は人口や富の増大よりもっと急速に発展する。このことから……社会は、もはやブルジョア階級のもとでは生存することができない。すなわち、ブルジョア階級の生存は、もはや社会と相容れないのである。……工業の進歩の…担い手はブルジョア階級であるが、この進歩は、競争による労働者の孤立化の代わりに、結合による労働者の革命的団結をつくりだす。だから、大工業の発展とともに、ブルジョア階級の…土台そのものが取り去られる。ブルジョア階級は、何よりもまず自分自身の墓堀人を生産する。ブルジョアの没落とプロレタリア階級の勝利とは、ともに不可避である。」<ref name="マルクス・エンゲルス全集 4巻(1960)475-487">|全集 3巻(1960) pp.475-487</ref>}} |
|||
以上、『共産党宣言』は「今日までのあらゆる社会の歴史は、階級闘争の歴史である。」という章句から書き出しが始まり、ブルジョア資本主義の形成を歴史的に辿り、資本主義の帰結がなにをもたらしていくかを明らかにしている。資本主義の発達と成長の結果、ブルジョワジーによる国民経済の掌握、政治的支配権の獲得は揺るぎないものとなり、資本による覇権が人民を抑圧するようになる。ブルジョワジーとプロレタリアートの階級闘争は激化し、生き残りをかけた熾烈な闘争の末、プロレタリアートはブルジョワジーを打ち負かして革命が成就し、歴史的時代区分としての資本主義の時代が終焉を迎える。マルクスは既存の章句「人類はみな兄弟」の代わりとして、最後に「'''万国の労働者よ。団結せよ!'''」との呼びかけで結んでいる。 |
|||
『共産党宣言』はマルクス主義の記念碑的作品であるが、この著作のエンゲルスの役割は非常に大きかったと評価されている。エンゲルスの伝記を記した[[グスタフ・マイヤー]]はエンゲルスの果たした役割について次のように語った。 |
|||
{{Quotation|「『共産党宣言』はマルクスの天才の作である。意味深長で示唆に富む文章は、たとえば熔鉄が鋳型に流れ込むような勢いであった。こういう文章を書いたものはマルクスに違いないが、この鉄鉱を集めて来たのはエンゲルスであって、その功はマルクスに劣るものではない。というのは、『共産党宣言』の思想はすべて共著の『ドイツ・イデオロギー』(このとき未刊)に含まれているからである。そしてまたその形こそ違え、『宣言』とエンゲルスの『原理』には何の違いもないからである。」<ref name="大内(1964)126">{{Harvtxt|大内|1964}} p.126</ref>}} |
|||
エンゲルスは、ブルジョワジーとプロレタリアートの形成と階級対立の歴史的構図を経済学に関する明晰な分析力と実社会で得た経験から導き出す力に溢れていた。マルクスの理論的体系化の天才を借りながら、エンゲルスは経済法則の原動力に沿って展開する歴史の歩みの中でプロレタリアートがブルジョワジーに取って代わる歴史的必然性を強調するとともに、『イギリスにおける労働者階級の状態』で描きだしたプロレタリアートの窮状を人類史の内部にその位置づけを提示することに成功した。 |
|||
{{main|共産党宣言}} |
|||
=== 1848年革命の概略 === |
|||
[[File:Europe_1848_map_en.png|300px|thumb|[[1848年革命]]のヨーロッパ。]] |
|||
==== 革命のはじまり==== |
|||
1845年から48年にかけて、ヨーロッパに貧農の主食となっていた[[ジャガイモ]]を枯らす病気、胴枯れ病が蔓延し、ヨーロッパ中に大飢饉が発生した。民衆の飢饉暴動が頻発し、ヨーロッパ各国で産業革命による貧困の拡大と飢餓の発生、食糧価格の高騰により深刻な社会不安が広がっていた<ref name="河野(1982)16-17">{{Harvtxt|河野健二|1982}} pp.16-17</ref>。 |
|||
1848年1月、[[シチリア]]の[[パレルモ]]で暴動が起こり、[[両シチリア王国]]からの分離独立と憲法制定が要求され、これを第一波として革命がイタリア各地に波及した。この騒乱は[[ブルボン家]]の国王[[フェルディナンド2世 (両シチリア王)|フェルディナンド2世]]にシチリアの自治と憲法制定を受諾させ、革命が成就した。イタリア発の革命の余波はフランスへと到達した。南イタリアにおける地方的騒乱はドミノ倒し状に連鎖して「ゴールの雄鶏の鳴き声」とともに[[1848年革命]]と呼ばれる欧州動乱へと発展する<ref name="ハント(2016)200">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.200</ref>。 |
|||
{{main|1848年革命}} |
|||
==== フランス二月革命==== |
|||
1830年の[[七月革命]]の結果誕生した[[オルレアン朝|オルレアン王政]]では、選挙権の拡大が行われたものの納税額による制限選挙自体は維持されていた。そのため、議員の選挙は数百人の投票によって決定され、フランス政治は特権階級による権力の独占という様相を濃くし、密室政治と利権政治へと堕落していた。選挙権をもたない労働者・農民層の不満が高まった<ref name="河野(1982)35">{{Harvtxt|河野健二|1982}} p.35</ref>。こうした不満のはけ口は改革宴会という集会によってある程度のガス抜きが行われていた。 |
|||
1848年2月22日、政府がある改革宴会に対して解散命令を出すと、これに憤慨した労働者・農民・学生による[[デモ]]、[[ストライキ]]が起こった。翌23日には首相の[[フランソワ・ギゾー]]が辞任して事態の沈静化を図ったが、24日には武装蜂起へと発展し、ついに国王[[ルイ=フィリップ]]が退位、[[ロンドン]]に亡命して王政が崩壊した。[[1848年のフランス革命|二月革命]]である<ref name="ハント(2016)201">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.201</ref>。同日、穏健な共和主義者であった[[アルフォンス・ド・ラマルティーヌ|ラマルティーヌ]]が指導してオルレアン左派、ブルジョワ共和派、急進革命派など左派を結集、臨時政府が組織された<ref name="河野(1982)52-58">{{Harvtxt|河野健二|1982}} pp.52-58</ref>。翌25日には臨時政府によって共和制が宣言され、フランスは[[フランス第二共和政|第二共和政]]に移行する。 |
|||
[[File:Meissonier Barricade.jpg|180px|thumb|パリの[[6月蜂起]]でフランス軍に殲滅された蜂起労働者たちの死体を描いた絵画]] |
|||
ラマルティーヌは、革命を前進させたい左派と既得権を守りたい右派の両派からの攻勢を受けながら、誕生間もない共和政を守らなければならなかった<ref name="河野(1982)59-60">{{Harvtxt|河野健二|1982}} pp.59-60</ref>。翌26日、ラマルティーヌは労働者階級の懐柔を図るべく高給を約束して機動隊の新兵募集を布告し、さらに[[国立作業場]]と呼ばれるモデル工場の設立に取り組み、失業問題の解決に新政府は本腰を入れることとなった<ref name="河野(1982)64-65">{{Harvtxt|河野健二|1982}} pp.64-65</ref>。 |
|||
3月2日、6ヶ月以上の居住資格をもつ21歳以上の男子が参政権を認められ、革命前の25万人から最終的に900万人を有権者とする成人男子選挙制の布告のもと、憲法制定国民議会の招集が決定された<ref name="河野(1982)66">{{Harvtxt|河野健二|1982}} p.66</ref>。ラマルティーヌは、民主主義によって労働者の不満を政治的に吸収し、[[オーギュスト・ブランキ]]ら極左の革命派による蜂起を予防することを意図した<ref name="河野(1982)59-60"/>。総選挙による保守派中心の新政府発足を予期した左派は、総選挙に猛烈に反発して選挙の実施延期を要求した。ラマルティーヌは左派の要求を拒絶し、国民の信託を受けた新政府を早期に発足させ、共和政を革命的急進主義から防衛しようとした<ref name="河野(1982)68">{{Harvtxt|河野健二|1982}} p.68</ref>。 |
|||
4月23日の選挙の結果、ルイ・ブランが辛うじて当選したもののルルーやカベなど急進革命派や社会主義者が大敗する一方、[[アドルフ・ティエール|ティエール]]率いる秩序党(オルレアン派)をはじめ地方出身の保守派が大勝した。かくして、臨時政府の陸相[[ルイ=ウジェーヌ・カヴェニャック|カヴェニャック]]将軍が中心人物となっていたブルジョワ共和派など保守勢力が多数を占める新政権が発足した<ref name="河野(1982)91">{{Harvtxt|河野健二|1982}} p.91</ref>。小市民、労働者の反対を抑え、新議会は[[1848年憲法]]を制定する<ref name="河野(1982)94">{{Harvtxt|河野健二|1982}} p.94</ref>。 |
|||
これ以降、革命を前進させようとするプロレタリアートと革命を終息させようとするブルジョワの階級対立が先鋭化していった。 |
|||
5月15日、国民議会の解散を要求するデモが組織されるが、政府と国民衛兵の弾圧により解散され、これに反発する革命家の[[オーギュスト・ブランキ]]とその一党は臨時政府と対立し、議会乱入を指導して逮捕されるという騒乱が起こる<ref name="河野(1982)100-103">{{Harvtxt|河野健二|1982}} pp.100-103</ref>。また、[[ルイ・ブラン]]が貧困対策として立案し失業者を雇用した[[国立作業場]]が採算が合わないとして閉鎖されたことを契機に、6月23日から数日、パリの労働者が大規模な武装蜂起を起こした。これがいわゆる[[六月蜂起]](六月暴動)である。「パンか死か」、「労働か死か」と叫び投石する民衆に対して、カヴェニャックの指揮のもと国民衛兵は4日間の流血戦を展開した。蜂起は鎮圧され、国立作業場は閉鎖、労働者側で1,500人が殺害された他、15,000人の政治犯が[[アルジェリア]]に追放された<ref name="河野(1982)102-112">{{Harvtxt|河野健二|1982}} pp.102-112</ref>。 |
|||
{{main|1848年のフランス革命}} |
|||
==== ドイツ三月革命 ==== |
|||
[[ファイル:Ereignisblatt aus den revolutionären Märztagen 18.-19. März 1848 mit einer Barrikadenszene aus der Breiten Strasse, Berlin 01.jpg|thumb|ベルリン三月革命]] |
|||
[[ファイル:1848 berlin barrikaden.jpg|thumb|180px|ベルリン市内のバリケード戦に参加する少年兵]] |
|||
ドイツでも情勢は風雲急を告げていた。 |
|||
1840年代、ドイツでは産業ブルジョワジーの成長によって、自由主義的な反政府運動が盛んに展開された。[[ドイツ連邦]]の主要大国[[プロイセン王国]]でも1845年に憲法制定の要望が声高に叫ばれていた。特に産業化の著しいライン州のブルジョワジーが憲法制定国民運動の先頭に立ち、その代表的人物に[[ケルン]]商業会議所会頭[[ルドルフ・カンプハウゼン|カンプハウゼン]]や[[アーヘン]]商業会議所会頭{{仮リンク|ハンゼマン|de|David Hansemann}}がいた。彼らは革命的気運の中で重要な役割を果たす<ref name="望月(1998)29">望月(1998) p.29</ref>。 |
|||
1848年2月27日、[[1848年のフランス革命]]に触発され、[[マンハイム]]の民衆集会が「三月要求」を策定し、[[ドイツにおける1848年革命]]の狼煙が上がった。3月1日、[[バーデン大公国]]議会の議事堂が占拠され、三月革命が始まっていく。3月4日、[[ミュンヘン]]で民衆蜂起が起こり、[[バイエルン王国]]における三月革命が始まった。革命はドイツ中を連鎖的に波及して、3月6日、ベルリンで最初の暴動が起こり、[[プロイセン王国]]における三月革命が始まった<ref name="望月(1998)29-31">望月(1998) pp.29-31</ref>。 |
|||
また、中央ヨーロッパの大国[[オーストリア帝国]]にも革命が波及した。3月13日、学生の一部が議事堂に押しかけて[[クレメンス・フォン・メッテルニヒ|メッテルニヒ]]の退陣と憲法の制定を要求し、[[ウィーン]]市内に暴動が拡大した。宮廷内でも、かねてからメッテルニヒに批判的であった皇帝[[フェルディナント1世 (オーストリア皇帝)|フェルディナント1世]]の叔父ヨハン大公がメッテルニヒの辞任を要求し、1815年[[ウィーン会議]]以来の反動政治の立役者であったメッテルニヒはついに辞任、ロンドンに亡命した。ウィーン三月革命である。メッテルニヒ亡命はオーストリア帝国支配下に置かれた北[[イタリア]]諸地域―[[ロンバルディア]]地方の[[ミラノ]]、[[ヴェネティア]]、[[サルディニア王国]]領の[[ピエモンテ]]―に伝搬し、[[イタリア統一運動]]を刺激した。しかし、イタリア動乱はオーストリアのラデツキー将軍の弾圧により鎮圧され、オーストリアによる再支配が布かれる<ref name="ハント(2016)202">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.202</ref>。 |
|||
3月18日、プロイセン王国でも事態は緊迫化した。国王[[フリードリヒ・ヴィルヘルム4世]]はメッテルニヒ失脚の報に触れると動揺し、すぐさま改革を決断する<ref name="望月(1998)31">望月(1998) p.31</ref>。 |
|||
そして、ベルリン王宮前に集まった群衆に向かって、プロイセンの改革に関する勅令を発した<ref name="ハント(2016)205">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.205</ref>。しかし、国王はこれまで国民の改革要求に穏健な姿勢を取っていた開明派軍人[[エルンスト・フォン・プフェル|ピュール]]を解任し、保守派の{{仮リンク|カール・フォン・プリットヴィッツ|de|Karl von Prittwitz|label=プリットヴィッツ}}をベルリン守備司令官に任命、万が一の革命に備えさせていた。 |
|||
勅令発表の際、最初は穏やかな雰囲気であったが、やがてベルリンからの守備隊の撤退を要求する革命的スローガンの声が大きくなる。プリットヴィッツはこれを革命の始まりと捉え、国王を守るべく群衆に解散を命じた。このとき、2発の銃弾が発射され、デモ隊の雰囲気が一転し、群衆の抵抗は軍隊に矛先を転じる<ref name="望月(1998)31"/>。{{仮リンク|ベルリン三月革命|de|Barrikadenaufstand}}の火蓋が切られた。激昂した群衆によって[[アレキサンダー広場]]にバリケードが築かれ、激しい市街戦の末、死者数百人が発生した。掃討作戦は困難を極め、軍の士気低下と命令拒否が見られたため、バリケードの撤去を条件に守備隊の撤退を決定、国王は革命に譲歩を示した<ref name="望月(1998)31"/><ref name="ハント(2016)206">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.206</ref>。 |
|||
19日、国王は王宮中庭で殉難者の棺の前で脱帽するよう強制され、21日には「黒・赤・金」三色旗{{#tag:ref|「黒・赤・金」三色旗は現在、ドイツ国旗に採用されている。その起源は古く、1832年のハンバッハ祭が例に挙げられる。ハンバッハ祭は、重税や政治的抑圧に対する社会不安の高まりを反映して挙行された祭典だが、共和主義者がドイツ統一運動とドイツ人の連帯の象徴として黒・赤・金(ドイツ語版)の三色を採用したことが注目に値する。「黒・赤・金」三色旗は民主的、共和主義的、国民主義的なドイツ共和国の表象となっていった。|group=注釈}}の記章を身に着けてベルリン市内の騎馬行進を行い、「ドイツの自由、ドイツの統一」を望む旨を宣言する。国王は連合州議会の召集、検閲の廃止による思想・言論・出版の自由の保障、憲法の制定を認め、ドイツ連邦の改革を認めた。こうして国民運動の指導者であったカンプハウゼンに組閣大命が下り、[[自由主義]]を奉ずる産業ブルジョワジーによる臨時政権が成立した<ref name="望月(1998)32">望月(1998) p.32</ref>。 |
|||
[[ファイル:Berliner Zeughaussturm (1848).jpg|thumb|300px|{{仮リンク|ベルリン兵器庫襲撃|de|Berliner Zeughaussturm}}]] |
|||
しかし、国王・軍部が自由主義的改革に対して終始反対であったことには変わりなかった。プロイセンの東部[[ボーゼン]]の[[ポーランド]]人の蜂起や[[シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州|シュレースヴィヒ・ホルシュタイン]]公国のドイツ人の蜂起と[[デンマーク王国]]との[[第一次シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争]]は[[フリードリヒ・フォン・ヴランゲル|ヴランゲル]]将軍の活躍により優勢を保って停戦に至った<ref name="望月(1998)32-33">望月(1998) pp.32-33</ref>。こうした軍事衝突事件は軍部に対する世論の信任を回復させ、カンプハウゼン内閣の逆風となっていく。反革命を標榜し精強を誇っていた軍部に対する臨時政府の統制権は機能せず、政権土台の不安定化を進めた<ref name="望月(1998)32"/>。またブルジョワジーの保守派への転向も相まって、革命を終わらせようとするブルジョワジー対革命を推進しようとするプロレタリアートとの階級対立が激化、改革派の分裂が始まり保守派に付入られる隙を作ってしまう<ref name="望月(1998)33-34">望月(1998) pp.33-34</ref>。 |
|||
5月25日、プロイセン国民議会で軍制問題の審議がなされる中、改革派内部の溝は広がり続けた。常備軍の廃止と市民軍の創設の是非を巡る問題で決定的状況が生じる。プロレタリアートを支持母体とする急進派は全人民の武装を要求、臨時政権がこれを拒絶したため、6月14日、労働者はベルリンの兵器庫を襲撃する<ref name="望月(1998)35">望月(1998) p.35</ref>。 |
|||
このときの襲撃は鎮定されたが、{{仮リンク|ベルリン兵器庫襲撃|de|Berliner Zeughaussturm}}の責任をとって[[ルドルフ・カンプハウゼン|カンプハウゼン]]が辞任に追い込まれる<ref name="望月(1998)35"/>。その後、保守系政府と軍部の主導権争いの中で数度にわたる政権交代が見られ、11月2日、国王は[[フリードリヒ・ヴィルヘルム・フォン・ブランデンブルク|ブランデンブルク]]を首相に大命を下し、首相は内相[[オットー・テオドール・フォン・マントイフェル|マントイフェル]]とともに組閣をおこなって、ここにブランデンブルク=マントイフェル反動内閣が成立した。11月14日にヴランゲル将軍はプロイセン国民議会を解散させ、改革の息の根を止めた。また、12月5日に国王[[フリードリヒ・ヴィルヘルム4世]]は国王大権を温存する欽定憲法を発布し、1849年5月30日に保守派に有利な三級選挙法を制定した<ref name="望月(1998)36-39">望月(1998) pp.36-39</ref>。 |
|||
=== 1848年革命とエンゲルス === |
|||
==== 『新ライン新聞』とマルクス、エンゲルス ==== |
|||
マルクスとエンゲルスは、1848年革命にすぐさま反応し、革命運動に参加していった<ref name="ハント(2016)198">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.198</ref>。 |
|||
彼らは1848年革命が全ヨーロッパ諸国を巻き込んだブルジョア[[市民革命]]として完遂され、その後に続くプロレタリアート革命への移行と発展の条件になることを期待した。フランス二月革命の勃発の報に触れると、マルクスは亡父の遺産を使って武器の調達を進め、蜂起に備えようと計画を進めた<ref name="ハント(2016)202"/>。しかし、[[ベルギー]]国王[[レオポルド1世 (ベルギー王)|レオポルド1世]]は警戒のために諜報を強化して危険分子の摘発に力を注ぐよう叱咤した。やがて、マルクスの蜂起計画はベルギー官憲の関知するところとなり、マルクスは検挙されてしまう。マルクスはベルギーからの24時間以内の国外退去処分を申し渡され、革命直後のパリへと逃れることとなった<ref name="ハント(2016)202"/>。パリへと退去したマルクスとエンゲルスは、フランス臨時政府のメンバーとなっていた社会主義者[[ルイ・ブラン]]と急進派のジャーナリスト{{仮リンク|フェルディナン・フロコン|fr|Ferdinand Flocon}}から熱烈な歓待を受けることとなる。エンゲルスはフロコンが発行する『ラ・レフォルム』({{lang-fr-short|''la Réforme''}})に寄稿しており、パリでは英雄扱いとなっていた<ref name="ハント(2016)203">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.203</ref>。 |
|||
その頃、マルクスはドイツに革命を輸出する方法を模索していた。「共産主義者同盟」は、3月下旬から4月上旬にかけてメンバーを次々とドイツ各地に工作員として送り込んだ<ref name="ウィーン(2002)157">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.157</ref><ref name="ハント(2016)203-204">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.203-204</ref>。亡命ドイツ人は[[ライン川]]を次々に越え、祖国に民主共和国を実現させようと帰国していった。幸いフランス臨時政府フロコンの協力を得て、亡命ドイツ人は一日50サンチールの支給を受けて活動をすることが可能となり、「同盟」は亡命ドイツ人を「ドイツ労働者クラブ」のもとに組織し最終的に300人を[[ラインラント]]に送りこむことに成功した<ref name="石浜(1931)171">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.171</ref><ref name="ハント(2016)204">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.204</ref>。エンゲルスは父と父の友人となっていた資本家たちから革命資金を募ろうと[[ヴッパータール]]に向かった<ref name="ウィーン(2002)158">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.158</ref>。マルクスとエンゲルスはドイツ革命運動急進派の最[[左翼]]として[[革命]]に参加しようと試み、言論運動を展開しようとする。 |
|||
しかし、ドイツはイギリスやフランスのような二国とは異なり、[[産業革命]]が遅かったためブルジョワジーの経済覇権の掌握も政治的支配権の獲得も遅れ、ようやく[[ウィーン会議]]の反動体制を克服したばかりで、封建君主に止めの一撃を加えてはいなかった。したがって、マルクスは即座の共産主義の実現に慎重論を唱え、'''『[[ドイツにおける共産党の要求]]』'''を執筆、軽挙妄動を制止しようと試み、まずはブルジョア民主主義を導入しようと考えた。マルクスの政治的立場はブルジョワ[[市民革命]]を経由してのプロレタリアート[[社会主義革命]]を目指す'''二段階革命論'''に根差していた。したがって、当面はカンプハウゼン臨時政府と提携してプロイセンの脆弱なブルジョワ勢力を強化し、体制改革を推進しながらプロイセン王国の封建的[[アンシャン・レジーム|旧体制]]を打破することに専念する、それが活動目標であった<ref name="ハント(2016)204"/>。 |
|||
[[ファイル:Neue Rheinische Zeitung N.jpg|170px|right|thumb|『新ライン新聞』1848年7月19日号]] |
|||
ドイツにおける革命の動きは当初期待通りに展開した。2月以降、テュイルリー宮放火事件、飢餓の蔓延、食糧価格の高騰などが深刻な社会不安を醸成し、ついに革命はバーデン大公国やバイエルン王国に飛び火し、ベルリンも一足触発の状況を呈するようになり、ベルリン三月革命へと至る。そんな中、マルクスとその家族は4月上旬にプロイセン領ライン地方の大都市[[ケルン]]に入った<ref name="ウィーン(2002)158"/>。革命扇動を行うための新たな新聞の発行準備を開始したが、苦労したのはやはり出資者を募ることだった。ヴッパータールへ資金集めにいったエンゲルスはほとんど成果を上げられずに戻ってきた<ref name="石浜(1931)173">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.173</ref><ref name="メーリング(1974,1)268">[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.268</ref>。結局マルクス自らが駆け回って4月中旬までには自由主義を奉じるブルジョワの出資者を複数見つけることができた<ref name="石浜(1931)173"/><ref name="カー(1956)86">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.86</ref>。新たな新聞の名前は『[[新ライン新聞]] - 民主主義の機関紙』({{lang-de-short|''Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie.''}})と決まった。創刊予定日は当初7月1日に定められていたが、封建勢力の反転攻勢を阻止するためには一刻の猶予も許されないと焦っていたマルクスは、創刊日を6月1日に早めさせた<ref name="カー(1956)86"/><ref name="ウィーン(2002)159">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.159</ref>。同紙はマルクスを編集長として、エンゲルスやシャッパー、ドロンケ、フライリヒラート、ヴォルフなどが編集員として参加した<ref name="石浜(1931)173"/><ref name="ウィーン(2002)159"/>。また、『新ライン新聞』は競合紙の『ケルン新聞』よりも安価で発行され、しだいに大衆の心を掴んでいく<ref name="ハント(2016)208">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.208</ref>。 |
|||
とはいえ、マルクスとエンゲルスの前に立ちはだかる障害物もあった。それは例の如くであったが、体制派の柔軟な妥協であり、ブルジョワの不甲斐なさであり、そしてプロレタリアの不統一であった。同じ急進的革命派の中にも対立構造はあり、{{仮リンク|ケルン労働者連合|de|Kölner Arbeiterverein}}を組織していた職人革命家{{仮リンク|アンドレア・ゴットシャルク|de|Andreas Gottschalk}}の素朴共産主義の運動と衝突する。ゴットシャルクの立場は史的唯物論などの理論的見地に基づくものではなく、即座の革命によってプロレタリアの支配を確立し、協同組合による共同体生活を想定したプルードン主義的な共産主義思想であった。マルクスはゴットシャルクの運動を封じるために対抗組織として「ケルン民主主義協会」を設立、穏健なブルジョワ民主主義の政治目標を掲げてプロイセン政府に対する非難の声をあげた<ref name="ハント(2016)207">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.207</ref>。ドイツの革命における真の敵は封建主義勢力だったのである<ref name="ハント(2016)209">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.209</ref>。 |
|||
だが、1848年4月には[[チャーティズム|チャーティスト]]による国民請願が早くも棄却され、フランスでは4月23日の総選挙では保守派が復活を遂げる一方で社会主義者が惨敗した他、反革命派の巻き返しによって情勢は急速に反動化していく<ref name="ハント(2016)210">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.210</ref>。 |
|||
{{main|チャーティズム}} |
|||
==== 革命の反動化と流転のはじまり ==== |
|||
ベルリン兵器庫襲撃事件と6月蜂起以降、革命の反動化と共に、『新ライン新聞』への逆風が強まり、マルクスは治安判事から出頭命令が発せられ、毎週のように裁判所に呼び出されていた。[[7月7日]]には検事侮辱および反乱扇動の容疑でマルクスの事務所に強制捜査が入り、起訴されるに至る<ref name="ウィーン(2002)164">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.164</ref>。だが、マルクスとエンゲルスは自分の立場を堅持した。ケルンでは革命の機運が高まっており、労働者は治安委員会を設置し、フーリンガーハイデで大規模な集会を開催、プロイセン政府との対決姿勢を強めた。9月17日、8000人の労働者と社会主義者がライン川を上ってケルンに集結し、決起の時期を待っていた。こうした情勢にあってプロイセン政府は先手を打ち、[[9月25日]]にケルンに戒厳令を発した。集会は禁止、市民軍は解散され、新聞発行に停止命令が出された<ref name="ハント(2016)213">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.213</ref>。「共産主義者同盟」のメンバー、『新ライン新聞』の発行者に逮捕状が出された。シャッパーやベッカーが逮捕され、エンゲルスにも逮捕状が出たが、彼は行方をくらました<ref name="ハント(2016)214">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.214</ref>。 |
|||
だが、エンゲルスはバルメンに立ち寄った後、ベルギーに向かい{{仮リンク|エルンスト・ドロンケ|de|Ernst Dronke (Schriftsteller)}}と共に潜伏していたところをベルギー官憲に逮捕されてしまう。1848年10月5日、パリ行の列車で移送され、フランスへと追放されることとなる<ref name="ハント(2016)214-215">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.214-215</ref>。11月に入る頃、フランスでは[[1848年憲法]]が制定され、[[ルイ・ナポレオン]]が大統領候補に立候補する情勢にあり、確実に共和派勢力は衰退する方向に向かっていた。オーストリアでも軍が議会を解散し、[[チェコ]]の中心地[[プラハ]]や北イタリア諸国に侵攻し、革命派の一掃を図った。エンゲルスは革命の前途に失望してパリを離れ、反革命に向かうヨーロッパを流離う逃亡生活に入る<ref name="ハント(2016)215">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.215</ref>。ただし、エンゲルスにとって逃亡は惨めではなかった。その逃亡生活の実態は[[フランス]]から[[スイス]]に向かっての気ままな徒歩旅行であった。エンゲルスは[[ブルゴーニュ=フランシュ=コンテ地域圏|ブルゴーニュ]]の美しい風景とワイン、美食を堪能し、宿泊した先々で出会う女性を次々と口説いて旅を楽しんでいた。エンゲルスはフランス紀行誌を書きながら南に向かって歩き、楽しみ、飲んで食べて、美しいブルゴーニュ女性を愛する旅の人となっていた<ref name="ハント(2016)216-217">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.216-217</ref>。息子を心配する母からの仕送りに頼りながら、エンゲルスはスイスに入って潜伏生活を送ることになる<ref name="ハント(2016)218">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.218</ref>。 |
|||
ケルンではマルクスが『新ライン新聞』の発行を続け、革命派に最期の抵抗を呼びかけていた。プロイセン政府は革命派を追い詰めるためにラインに軍を派遣し、戒厳令を出し、新聞を発行停止にしたが、マルクスはこの動きに猛然と反発し、闘争心に欠くブルジョワ勢力を見限り、政府の弾圧に対して[[テロ]]による応酬を主張した。マルクスの不屈の姿勢は潜伏中にあったエンゲルスを励ました<ref name="ハント(2016)222">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.222</ref>。エンゲルスは[[コシュート・ラヨシュ]]による[[ハンガリー革命 (1848年)|1848年ハンガリー革命]]に関心を注ぎ、[[ナショナリズム]]の高揚によって、[[ハプスブルク]]支配と闘争する諸国民の民族運動に鼓舞された。エンゲルスは騎士や革命家、英雄的な軍人指導者に憧れがありコシュートの活躍に熱狂してしまう<ref name="ハント(2016)218-219">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.218-219</ref>。ハンガリーやシュレスビッヒ地方での各地の紛争について『新ライン新聞』に寄稿し、ナショナリズムは歴史的大義であるとする論評をおこなった<ref name="ハント(2016)219-220">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.219-220</ref>。元来活動派のエンゲルスはスイスでの自由な亡命生活にすぐに飽きていたため、しだいに革命運動への復帰を願うようになる。12月にはエンゲルスはゴットシャルク、{{仮リンク|フリッツ・アネケ|de|Fritz Anneke}}など革命の同志たちが釈放されたという情報を得て、ドイツに帰郷する決意を固める<ref name="ハント(2016)221-222">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.221-222</ref>。『新ライン新聞』はエンゲルスの期待通り、以前より攻撃的な革命論を展開しており、同紙の急進化を歓迎した<ref name="ハント(2016)222"/>。 |
|||
==== 革命運動とエンゲルス ==== |
|||
1849年1月、エンゲルスがスイスでの潜伏地を離れてケルンに戻ってきた<ref name="ハント(2016)222"/>。 |
|||
[[File:Dresdner Maiaufstand.jpg|250px|right|thumb|5月蜂起におけるバリケード戦]] |
|||
その頃、『新ライン新聞』はブルジョワとの迎合を批判し、大衆蜂起と革命、ゲリラ戦により抵抗を呼びかけ、プロイセンとの対決姿勢を強めていた<ref name="ハント(2016)222"/>。3月、[[フランクフルト国民議会]]は[[パウロ教会憲法]]を制定し、国王[[フリードリヒ・ヴィルヘルム4世]]に帝冠を授けることを決定する。しかし、[[王権神授説]]を信奉するフリードリヒ・ヴィルヘルム4世は[[立憲君主制]]を嫌悪しており、この申し出を拒絶した<ref name="ハント(2016)223">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.223</ref>。革命派の最後の希望は絶たれることとなる。これを機にライン地方は急激に革命化していく。ライン地方からバーデン大公国に至る西南ドイツは共産主義者による暴力革命の機運が高まった。さらに決定的な事件が東ドイツの[[ザクセン王国]]で発生した。4月28日、ザクセン王[[フリードリヒ・アウグスト2世]]が議会を解散するとこれをきっかけに[[ドレスデン]]で革命騒擾[[ドレスデン五月蜂起|5月蜂起]]が発生した。[[ミハイル・バクーニン]]、{{仮リンク|シュテファン・ボルン|de|Stephan Born}}、[[リヒャルト・ワーグナー]]がこの闘争に参加している。しかし、ザクセン軍とプロイセン軍の部隊が鎮圧にあたり、蜂起は失敗に終わった<ref name="ハント(2016)224">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.224</ref>。 |
|||
{{main|フランクフルト国民議会}} |
|||
プロイセン政府はラインラントの情勢が安定しているという判断のもと、1849年春にヴェストファーレンとラインラントにおいて予備軍を召集した。兵員召集は戦時に限り実施されるもので、平時では違法と考えられていたため反発を招いた。プロイセン国王は、邦議会第二院が1949年3月27日にパウロ教会憲法草案への支持を表明したため議会を解散しており、大小ブルジョワジーとプロレタリアートを含むラインラント市民各層が、期待に反して反故にされた政治改革の擁護のために立ち上がっていく。5月蜂起を機に革命はライン地方に飛び火し、各地の都市では市民軍が組織され、プロイセンの守備軍に撤退要請が出されるなど反乱状態に陥っていく<ref name="ハント(2016)223-224">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.223-224</ref>。 |
|||
1849年5月9日、ラインラントの[[エルバーフェルト]](現[[ヴッパータール]])、[[デュッセルドルフ]]、[[イーザーローン]]、[[ゾーリンゲン]]市で蜂起が起こり、エンゲルスは故郷の地で盛んになった革命闘争に参加していく。翌10日デュッセルドルフが脱落するが、反乱地域一帯はプロイセン王国から離反を決め、各都市の街路にはバリケードが建設されていく。反乱を起こした市民を組織化するために、公安委員会 ({{lang-de-short|Sicherheitsausschuss}}) が市内に組織された<ref name="ハント(2016)224-226">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.224-226</ref>。公安委員会のメンバーには、エルバーフェルトの民主派弁護士のカール・ニコラウス・リオッテ、エルンスト・ヘルマン・ヘーヒスター (委員長に選出) 、エルバーフェルトで検事も務めた弁護士で自由主義者のアレクシス・ハインツマンが含まれていた<ref name="ハント(2016)227">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.227</ref>。エンゲルスは各地で購入した武器弾薬を持参して公安委員会に出頭し、革命家として名乗りを上げた。そして、各地の労働者に招集をかけて組織した土木工兵の一隊を率い、ヴッパー川に架かるハスペラー橋にバリケードを築き、市街の防衛力を強化した。しかし、エンゲルスは政治上の立場に関して公安委員会から審査を受けた際に共和派に順ずるという誓約を破っていく。彼はハスペラー橋のバリケードに無断で「黒・赤・金」のドイツ三色旗の代わりに赤旗を掲げた<ref name="ハント(2016)227"/>。公安委員会からのエンゲルス排斥が決まり、彼は立ち退き勧告を突きつけられて、ヴッパータールを離れることとなった<ref name="ハント(2016)227-228">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.227-228</ref>。一週間後、ヴッパタールはプロイセン軍が占領し、赤旗とバリケード群を撤去して、市民軍を武装解除させた<ref name="ハント(2016)228">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.228</ref>。 |
|||
[[ファイル:NGR RED.jpg|200px|right|thumb|『新ライン新聞』1849年5月19日付最終号]] |
|||
ドイツ革命の最終局面は南西ドイツの革命運動の激化にあった。 |
|||
[[バーデン大公国]]と[[バイエルン王国]]領[[プファルツ地方]]で発生した{{仮リンク|プファルツ蜂起|de|Pfälzischer Aufstand}}が拡大を見せていた<ref name="ハント(2016)229">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.229</ref>。とうとう、隣国バーデンの革命派が大公を追放するに及ぶ。亡命を余儀なくされた大公はプロイセン軍に介入を求めた。マルクスは『新ライン新聞』で各地の武装蜂起をドイツ革命の好機として報じ、プロイセンに対する抵抗を呼びかけた。5月16日、プロイセン政府は『新ライン新聞』のメンバーに国外追放処分を下し、新聞の出資者だったブルジョワ自由主義者もこの頃までにほとんどが逃げ出していた<ref>[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.164-166</ref>。ついに、同紙は廃刊を余儀なくされ、マルクスは5月18日の最終号を全面赤刷りで出版した<ref name="ハント(2016)228"/>。 |
|||
マルクスとエンゲルスはフランクフルトからバーデン大公国へと放浪し、プファルツでの反乱に加わる計画を立てた。二人は結局、バーデンの革命政府と合流したが、プロイセンの軍事介入の脅威を指摘したところ、スパイと誤認されて投獄された。二人はすぐに釈放されたが、マルクスはパリへと逃亡してしまう<ref name="ハント(2016)229"/>。 |
|||
エンゲルスもマルクスの後を追うことにしていたが、元プロイセン軍人{{仮リンク|アウグスト・ヴィリヒ|de|August Willich}}が[[カイザースラウテルン]]で800名の学生に軍事訓練をおこない武装蜂起したのである。エンゲルスはプファルツの革命派学生に共鳴して蜂起に参加、軍事に明るいエンゲルスはヴィリヒの副官として革命戦争に参加することになった<ref name="ハント(2016)230-231">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.230-231</ref>。革命軍は各地でプロイセン軍と抗戦し、バーデン第二の都市[[カールスルーエ]]南方に位置するラシュタット要塞に1万3千の兵力を結集して籠城した。プロイセン軍は4倍の兵力で要塞を攻略、このとき「共産主義者同盟」の創設メンバーの一人{{仮リンク|ヨーゼフ・モル|de|Maximilien Joseph Moll}}が戦死するなど、革命軍に多大な犠牲が生じた。エンゲルスは残党勢力を集め、南の[[シュヴァルツヴァルト]]を通って追手を交わしスイスへと逃亡した<ref name="ハント(2016)231">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.231</ref>。マルクスはエンゲルスの輝かしい軍歴を称えた<ref name="ハント(2016)232">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.232</ref>。エンゲルスは同志の賞賛に応えて1849年8月から50年2月にかけて'''『[[ドイツ国憲法戦役]]』'''({{lang-de-short|''Die deutsche Reichsverfassungskampagne'',1849-1850}})を執筆した。エンゲルスは革命時におけるブルジョワとの共闘路線と二段階革命論を放棄し、ブルジョワの反動化が見られた時点において革命を守るため封建勢力と共にブルジョワを打倒する必要性を説いた<ref name="ハント(2016)232"/>。マルクスもまた1850年に『'''{{仮リンク|フランスにおける階級闘争|en|The Class Struggles in France 1848-1850}}'''』({{lang-de-short|''Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850''}})を執筆、革命の契機と失敗に関する唯物弁証法に基づく洞察をおこなった。マルクスは6月蜂起とその後の反動を「労働者と資本の間の戦争」として描写し、二月革命を階級闘争の生成と敗北とする歴史認識を打ち出した<ref name="ハント(2016)212">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.212</ref>。 |
|||
6月初旬にマルクスはフランスに入国して逃亡生活をしていたが、フランス警察の外国人監視が強まり、[[ブルターニュ地方]]のポンティノ湿地に流刑に処すと脅されたため、フランスからも出国する覚悟を固めた。ドイツにもやベルギーにもスイスにも入国を拒否されていたマルクスを受け入れてくれる国はブリテン以外にはなかった。ピエモンテ経由でジェノヴァへ向かい、1849年8月27日、航路でロンドンに向かった。エンゲルスはスイス亡命中、執筆の傍らいつもの如く女と酒に溺れる日々を送っていたという。1849年10月5日、エンゲルスもジェノヴァから航路で大陸を離れ、11月12日にはエンゲルスもマルクスを追いかけるようにロンドンへと向かい、以降40年間をブリテンで生活することになった<ref name="ハント(2016)233">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.233</ref>。 |
|||
{{main|ドイツにおける1848年革命}} |
|||
=== 二度目のブリテン時代 === |
|||
==== 共産主義者同盟の壊滅 ==== |
|||
[[File:Nytrib1864.jpg|250px|thumb|1864年の『[[ニューヨーク・トリビューン]]』]] |
|||
[[1849年]]までに、二人はドイツのみならず大陸各国から追放され、やむなく英国に渡った。[[プロイセン]]当局は英国政府に対して、エンゲルスとマルクスを追放するように圧力をかけたものの、当時の英国首相[[初代ラッセル伯ジョン・ラッセル|ジョン・ラッセル]]は表現の自由に関して[[リベラル]]な考え方を持っていたためその要請を拒否した。 |
|||
[[1848年]]の革命の機運が収束しヨーロッパの革命的情勢が後退して以降、英国はその後の生活の拠点となった。しかし、マルクスとエンゲルスは経済的に困窮していた。マルクス一家は貧困外国人居住区だった[[ソーホー (ロンドン)|ソーホー]]区の{{仮リンク|ディーン通り|en|Dean Street}}28番の二部屋を賃借りての生活を余儀なくされた<ref name="カー(1956)123">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.123</ref><ref name="石浜(1931)206">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.206</ref><ref name="ウィーン(2002)199">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.199</ref>。生計を立てる手段が得られず、やがてマルクスは生計をエンゲルスからの定期的な仕送りに頼らざるを得なかった。しかし、ロンドンに移ったこの時期の窮乏状態は厳しく、三人の子どもを飢餓と病気で失っている。マルクスは、他の友人([[フェルディナント・ラッサール|ラッサール]]やフライリヒラート、[[ヴィルヘルム・リープクネヒト|リープクネヒト]]など)への不定期な金の無心、金融業者から借金、質屋通い、元[[シャルル・フーリエ|フーリエ]]派でアメリカの進歩的な奴隷解放論者が発行していた[[アメリカ]]の新聞『[[ニューヨーク・トリビューン]]』({{lang-en-short|''New-York Tribune''}})への寄稿でなんとか保った。エンゲルスはチェルシー、次いでソーホーのマックスフィールド通りに居住、一時的に自由な亡命者生活を満喫した。しかし、彼もまたロンドン亡命の直後はマルクスと同じく無収入の境遇に置かれ、プロイセンのスパイに監視される中で貧困生活に耐えることになった<ref name="ハント(2016)240-241">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.240-241</ref>が、マルクスとエンゲルスは[[1848年革命]]の理論的考察を加えて互いの執筆事業を進めた。 |
|||
1850年、ロンドンに移り住んで間もなくエンゲルスは『'''{{仮リンク|ドイツ農民戦争(歴史書)|en|The Peasant War in Germany}}'''』({{lang-de|''Der deutsche Bauernkrieg''}})を執筆した。本書にはエンゲルスの歴史観が描写された。1524年、[[トマス・ミュンツァー]]は現状維持を志向した[[ルター教会|ルター]]派の[[宗教改革]]運動に疑問を抱き、シュヴァーベンの貧しい農民による蜂起に合流して「地上における神の王国」を実現させる運動を展開する。これが[[ドイツ農民戦争]]である。1525年、貧しい農民([[農奴]])を解放して救済しようとするミュンツァーの闘いは[[シュヴァーベン]]の領主と同盟した[[マルティン・ルター]]によって打倒される。エンゲルスにとって象徴的意味を持った歴史事変であった。エンゲルスはこの闘いを[[階級闘争]]として捉え直していく。共産主義的な[[平等]]の王国を実現するには経済的準備が出来ておらず、時期尚早の蜂起であった。[[封建制|封建]]的な農業経済を産業革命によって脱却して、近代産業に基づく資本主義の確立によって自然的制約を超えた工業社会の到来の兆しを待たねばならず、時宜を得られなければ持つ者と持たざる者の闘争は現実性を持ち得ないという認識が語られている。したがって、ミュンツァーの闘いはルター派の鎮圧軍によって撃破され、多大な犠牲を出して屈服させられたわけである。ミュンツァーの闘いとその敗北は、[[革命]]には歴史的な時節の到来を待望する姿勢が必要であり、確かな歴史的展望を培って待機と備えをした上で、ブルジョワの裏切りに抵抗しなければならないという教訓史をなしていた。エンゲルスは[[ドイツ農民戦争]]を手がかりに、[[ヴィルヘルム・ヴァイトリング]]が説いた即時の共産主義実現という挑戦の無謀さと危険性を指摘し、経済的条件を持たない革命は決して成功しないという考えを同志たちに提示しようとしたのである<ref name="ハント(2016)281-282">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.281-282</ref>。 |
|||
{{main|ドイツ農民戦争|トマス・ミュンツァー}} |
|||
二人は「共産主義者同盟」の再建に取り組むことになる。 |
|||
しかし、組織再建は困難を極めた。「同盟」中央委の人事争い、ロンドンの「ドイツ人労働者教育協会」の会員資格問題、亡命者支援基金の分配金を巡る争いが再建を困難にした。さらに、1850年に採択された「中央委から同盟員への呼びかけ」で、エンゲルスは「ブルジョワの裏切り論」を下地に「永続革命」によるプロレタリアートの支配権確立のため闘争を継続するように訴えたが、闘争の方法論を巡って内部対立が生じていた。「同盟」には即時蜂起を求めるカール・シャッパーとアウグスト・ヴィリヒのグループと[[恐慌]]によってブルジョワ資本主義社会が破局する時節の到来を待望するマルクスとエンゲルスのグループに分裂していった<ref name="ハント(2016)238-239">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.238-239</ref>。マルクスは同盟中央委をドイツのケルンに移転させて政敵の干渉を最小限にしようとしたが、ドイツ側にもマルクスと剃りが合わないゴットフリート・キンメル、[[アーノルド・ルーゲ]]らのグループがおり、マルクスとエンゲルスは完全に孤立状態に置かれる。しかし、中央委の移転は「共産主義者同盟」の壊滅につながっていく。1851年5月から6月にかけて共産主義者同盟の著名なメンバー11人が大逆罪の容疑でプロイセン警察によって摘発された。ケルン共産党事件である。この事件を受けて、マルクスも「共産主義者同盟」の存続を諦め、1852年11月17日に正式に解散を決議した。 |
|||
[[File:RedRepublican.JPG|right|320 px|thumb|『レッド・リパブリカン』創刊号]] |
|||
==== ビジネスへの復帰と二重生活 ==== |
|||
エンゲルスはマルクス同様、困窮に苦しんでいた。エンゲルスの両親は、革命運動に傾倒したために、逮捕状が出され追われる身となった息子に手を焼いて金銭援助を止めざるを得ない状況に陥った。しかし、エンゲルスもついに音を上げて、自身と友人マルクスを救うために、渋々家族に頭を下げて仕事の面倒を見てもらうことにした。妹マリーが仲介役となって「兄も反省しているから」と言って父親を宥め、父親も「フリードリヒにとっては不本意であろうが、息子の復帰は家業のためになる」として息子の要望を受け入れ、遂に和解するに至った。かくして、エンゲルスは工場のあるマンチェスターで臨時働きのつもりで家業「エルメン&エンゲルス商会」に復帰した<ref name="ハント(2016)241">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.241</ref>。 |
|||
マンチェスターは[[チャーティズム]]の本拠地であり、英国社会主義の中心地であった。だが、1850年代の英国の経済は[[ヴィクトリア時代]]中葉の長い好景気のルートに入り、その過程でチャーティズムの崩壊が進んでブルジョワ支配は揺るぎのないものになっていった。『[[共産党宣言]]』の英訳がジョージ・ジュリアン・ハーニーが発行する{{仮リンク|『レッド・リパブリカン』|en|The Red Republican}}紙({{lang-en-short|''The Red Republican''}})に掲載されたものの反響は芳しくなかった。英国の労働者階級は好調な経済の恩恵を受けて熟練労働者を中心に所得を増やし、未熟練労働者との両極分解が進んでおり、階級的自己意識とその革命的性格を急速に喪失していたのである<ref name="ハント(2016)242-245">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.242-245</ref>。 |
|||
[[File:Engels 1856.jpg|thumb|1856年のエンゲルス]] |
|||
[[File:Karl Marx Frau.jpg|thumb|マルクスの妻[[イェニー・マルクス]]。彼女は知性にあふれた女性だったが、出自に恵まれていたため家計の管理に疎かった。]] |
|||
一方で好調な綿産業の発展とともに「エルメン&エンゲルス商会」も事業の成長に成功していった。「エルメン&エンゲルス商会」はペーター、ゴッドフリート、アントニーのエルメン兄弟とフリードリヒ・エンゲルス(父)との共同事業体であった。この共同事業は絶えず経営権を巡る社内対立を招き、この緊張関係は業績の伸長と共に次第に激化していった。フリードリヒ・エンゲルスは父の意を受けて社内の財務状況の調査を開始し、内部監査役として活躍して父親の経営権を擁護した。経営への参画を通じてエンゲルスは父親と和解していき、1851年6月には父親とマンチェスターで対面できるまでにその関係を改善させている<ref name="ハント(2016)249">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.249</ref>。 |
|||
エンゲルスは、会社の帳簿と対話する財務管理と工場経営に精勤して生活を再建させたが、1850年代のエンゲルスの給料は年100ポンドを超えることはなかったと見られている。また、父の代わりにマンチェスター工場の財務をやり繰りしなければならなかったので、マルクスに送る資金にも限度があったが、巧みな語学と持ち前の経営能力を発揮して1850年から1860年は一般社員、1860年から1864年まで業務代理人、そして1864年から1869年は支配人として勤め、共同経営者の地位にまで上り詰めた。最終的に年1500ポンドを稼ぐ富裕な中流階級の名士となり、マンチェスターのドイツ人社会の頂点に駆け上がった。彼は十数年の間に流浪の革命家から名誉ある高級社会の一員へと出世を果たしたのである<ref name="ハント(2016)249,251">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.249,p.251</ref>。[[フリードリヒ・フォン・シラー|シラー]]協会の会長を務め、高級馬を所有して名門有力者が集うチャンシャー・ハウンズにおけるキツネ狩りを楽しみ、名門のアルバート・クラブやブレイズノーズ・クラブの会員となっていた<ref name="ハント(2016)268-272">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.268-272</ref>。 |
|||
昼間は工場経営に従事する一方、夜は[[科学的社会主義]]の研究を進めるという望まぬ「二重生活」に入っていく。会社経営の実態、雇用や人事評価をめぐる精神面での矛盾とジレンマは深刻なものとなり、エンゲルスの心情を傷つけるものとなった<ref name="ハント(2016)249"/>。 |
|||
しかし、エンゲルスは、政治経済問題や国際情勢について多くの新聞と雑誌からの活発な情報収集を通じて秀逸な分析を継続した。殊に、世界の戦争に関する軍事情勢分析には抜群の才を発揮し、この分野では、時にはマルクスに代わって情勢論文をマルクスの名で新聞社に寄稿することもあった<ref name="ハント(2016)259,283">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.259,p.283</ref>。1860年代には自身も体調不良に苦しんでいたが<ref name="ハント(2016)272-275">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.272-275</ref>、マルクスの仕事のために情報収集と提供を依頼され、英作文が苦手なマルクスのために執筆を代行して彼の仕事に尽くしていた<ref name="ハント(2016)259">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.259</ref>。 |
|||
このようなマンチェスター時代の「二重生活」は、約20年間に及ぶこととなった。エンゲルスは、その間に得た報酬の半分以上を浪費癖の治らないマルクスに送金した{{#tag:ref|当時の価格で総額およそ2000~3000ポンド、現在の換算でも大金である。|group=注釈}}。マルクスは新聞への寄稿の謝礼に加えてエンゲルスからの送金で窮地を脱し、惨めなソーホーでの生活を抜け出し、中流階級が居住する郊外住宅で暮らすようになる。1856年、ロンドン北部{{仮リンク|ケンティッシュ・タウン|en|Kentish Town}}のグラフトン・テラス({{lang-en-short|Grafton Terrace}})9番に転居し、[[1864年]]3月にメイトランドパーク・モデナ・ヴィラズ1番({{lang-en-short|1 Modena Villas, Maitland Park}})の一戸建ての住居を借り、[[1875年]]春には近くのメイトランド・パーク・ロード41番に引っ越した。エンゲルスは度々の引っ越しと不相応に贅沢な暮しをしていたマルクス家の生活を支援した。[[亡命]]者として政府の監視の下で浪費と貧困の繰り返しの生活を営んでいたロンドンのマルクスとその家族の生活を何度となく救ったのはエンゲルスの財政的支援であった<ref name="ハント(2016)252-253">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.252-253</ref>。 |
|||
また、エンゲルスはマルクス家の家庭環境も守った<ref name="ハント(2016)264">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.264</ref>。1851年にマルクスはディーン通りの家でメイド{{仮リンク|ヘレーネ・デムート|de|Helena Demuth}}との間にフレデリック(フレディ)・デムートを儲けた。エンゲルスはマルクスの隠し子のためにファーストネームを与え、あたかもエンゲルスが本当の父親であるように偽装するなど公私に渡って犠牲を払った<ref name="ハント(2016)262-264">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.262-264</ref>。結局、フレディはエンゲルスにもマルクスにも子どもとして認知されず里子に出され、ロンドンで旋盤工として暮らしていくことになる<ref name="ハント(2016)263">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.263</ref>。 |
|||
=== 中年期以降の活動 === |
|||
==== 反動とのたたかい ==== |
|||
{{節スタブ}} |
|||
[[Image:Weydemeyer.jpg|thumb|{{仮リンク|ジョゼフ・ヴァイデマイヤー|en|Joseph Weydemeyer}}]] |
|||
[[ファイル:Franz Xaver Winterhalter Napoleon III.jpg|thumb|200px|[[フランツ・ヴィンターハルター|ヴィンターハルター]]画『ナポレオン3世の肖像』(ナポレオン博物館蔵)]] |
|||
1851年12月2日、フランスでは大統領ルイ・ナポレオンによるクーデターがあり、主だった議員が逮捕された。ルイ・ナポレオンは国民投票によってクーデターへの信任を得て、事件からちょうど一年後に皇帝に即位、[[ナポレオン3世]]を称して第二帝政を開始する。マルクスは『[[ルイ・ボナパルトのブリュメール18日]]』({{lang-de|''Der 18te Brumaire des Louis Bonaparte''}})を執筆した。 |
|||
上書執筆の経緯は、[[共産主義者同盟]]の古くからの同志であった{{仮リンク|ジョゼフ・ヴァイデマイヤー|en|Joseph Weydemeyer}}から、[[1851年12月2日のクーデター]]に関して[[ニューヨーク]]で発行を計画中の週刊誌への寄稿を求められたことに起因する<ref name="岩波文庫版(1954)7">岩波文庫版(1954) p.7</ref>。ヴァイデマイヤーはマルクスと同い年の友人で、[[プロイセン]]軍の士官であり、ジャーナリストであった。1846年には[[ブリュッセル]]で設立された共産主義通信委員会に参加し、正義者同盟から改称した[[共産主義者同盟]]にも参加していた。[[1848年革命]]に参加し、翌年49年『新ドイツ新聞』の編集者となった。1851年にアメリカに亡命した後は新雑誌『革命(ディ・レヴォルティオーン)』({{lang-de-short|''Die Revolution''}})の創刊を目指して活動し、マルクスに論文の寄稿を依頼した<ref name="平凡社版(2008)247">平凡社版(2008) p.247</ref>。12月16日、マルクスはマンチェスターにいたエンゲルスに相談を持ちかけたところ、エンゲルスから論文を執筆してみてはどうかという提案がなされた。そのときの手紙でエンゲルスは次のように語っている。 |
|||
{{quotation|「今日昼に受け取ったヴァイデマイヤーの手紙を同封する……金曜日の晩までにかれのところへ論文を送ってくれという要求はちと無理だ、―とくに今の状態では。しかし、今こそ人々はフランス史について論断とよりどころを切に求めているのだ。そして、ここで情勢について何かはっきりしたことをいうことができれば、それで彼の企画が最初の号で成功するということになろう。だが、厄介なのはそういうものを書くということだ、そしていつものように難しいことは君に任せる。僕が何を書くにしてもクラピュリンスキーのねらいうち(ボナパルトのクーデター)ではないことだけは確かだ。いずれにしてもそれについて君は彼に外交的に退路を残した画期的な論文を書いてやることができる」<ref name="岩波文庫版(1954)229">岩波文庫版(1954) p.229</ref>}} |
|||
マルクスとエンゲルスのナポレオン三世に対する敵意は根深く、彼をヨーロッパの革命を破滅させた張本人と見ていた。二人はフランスと全世界の自由に敵対するナポレオン三世を打倒することが革命の事情と考えた。マルクスはエンゲルスの助言で早速執筆に取り掛かり、12月19日、ヴァイデマイヤーに第一章を送付することを約束した。この約束は病気のために果たされなかったが、明けて1月1日に最初の原稿が、2月13日に続きが送られた。その間、ヴァイデマイヤーの週刊誌発刊の計画は資金面の障害により挫折していたが、マルクスは諦めずに執筆を続け、三月中で全部の原稿が送られた。5月、ヴァイデマイヤーの不定期雑誌『革命』第一号に掲載された<ref name="岩波文庫版(1954)229-230">岩波文庫版(1954) pp.229-230</ref>。 |
|||
==== 「将軍」エンゲルス ==== |
|||
[[ファイル:Giuseppe Garibaldi portrait2.jpg|thumb|200px|[[イタリア統一運動]]の英雄[[ジュゼッペ・ガリバルディ|ガリバルディ]]]] |
|||
エンゲルスは青年期に軍隊経験があり、1848-49年にはドイツ革命に参加し、プファルツ・バーデン革命政権を守るため革命戦争に従軍していた。こうした背景もあってとりわけ軍事史に強い関心を向けていた。多忙なビジネスライフの合間、軍事戦略や地政学、武器や軍事技術を研究するようになった。英雄史観を拒絶して[[唯物史観]]の体系化に尽力しながらも、[[アーサー・ウェルズリー (初代ウェリントン公爵)|ウェリントン公爵]]や{{仮リンク|チャールズ・ネイピア(海軍大将)|en|Charles Napier (Royal Navy officer)}}、[[ジュゼッペ・ガリバルディ|ガリバルディ]]などの軍事的英雄に対しては深い敬意を抱いて彼ら名将を崇拝していた<ref name="ハント(2016)283">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.283</ref>。 |
|||
クリミア戦争に関する評論は好評とはならなかったものの、地政学分析の書であった'''『ポー川からライン川』'''は優れた評論として高い評価を得た<ref name="ハント(2016)285">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.285</ref>。その論旨はドイツ統一の実現のために、ドイツ民族は軍事上重要な[[ポー川]]と[[ライン川]]をフランスから防衛しなければならないとするものであった。ナポレオン3世は[[1859年]]に[[サルデーニャ王国]]宰相[[カミッロ・カヴール]]と連携して[[ロンバルド=ヴェネト王国|北イタリア]]を支配するオーストリア帝国に対する戦争を開始した。[[イタリア統一戦争]]と呼ばれるこの戦争はフランスで反動政治をおこなう専制君主ナポレオン3世がやはり反動国家のオーストリアと衝突して、イタリア民族運動を支援するというもので[[ナショナリズム]]の前進には積極的意味があったが、ドイツ民族の敵がイタリアに勢力拡大を図っていると見なせるものであった<ref name="カー(1956)207">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.207</ref>。 |
|||
この戦争をめぐってエンゲルスは小冊子『ポー川とライン川』を執筆し、これをラッサールの斡旋でプロイセンのドゥンカー書店から出版した<ref name="メーリング(1974,2)126">[[#メーリング(1974,2)|メーリング(1974)2巻]] p.126</ref><ref>[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.224-225</ref>。この著作の中でエンゲルスは「確かにイタリア統一は正しいし、オーストリアが[[ポー川]](北イタリア)を支配しているのは不当だが、今度の戦争はナポレオン3世が自己の利益、あるいは反独的利益のために介入してきてるのが問題である。ナポレオン3世の最終目標は[[ライン川]](西ドイツ)であり、したがってドイツ人はライン川を守るために軍事上重要なポー川も守らねばならない」といった趣旨の主張を行い、オーストリアの戦争遂行を支持した。マルクスもこの見解を支持した<ref name="メーリング(1974,2)126-128">[[#メーリング(1974,2)|メーリング(1974)2巻]] p.126-128</ref>。しかし、二人の主張は軍事色を強めていくナポレオン3世を批判するあまり、イタリア統一運動を妨害して長年にわたって[[ハプスブルク家]]によってイタリア支配をおこなうオーストリア帝国を支持しているかのように感じさせものであった。このようなマルクスとエンゲルスの態度には社会主義者であったラッサールでさえもオーストリアによる諸民族のナショナリズム蹂躙という状況を肯定しているという悪印象を与えるものだった。 |
|||
社会主義者同士の不信感が高まるなか、大国間の対立もエスカレートしていた。ナポレオン3世のイタリア統一戦争への干渉は英仏間の対立も招いたのだ。 |
|||
政治的緊張の中でブリテン南部の沿岸部各地に義勇軍が集結していった。エンゲルスはこの義勇軍を高く評価した。しかし、義勇軍部隊の多くが富裕な市民で実態はクラブ活動のようなもので完全にブルジョア部隊であったが、エンゲルスは義勇軍の階級的性格を無視して絶賛していた。軍事的活動や戦争に関してエンゲルスは好戦的な性格が強く、[[ワーテルローの戦い]]のような決戦で勝敗と共に善悪が決する最終戦争が起こるのを密かに願っていた<ref name="ハント(2016)285-286">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.285-286</ref>。 |
|||
[[ナポレオン戦争]]が再来してナポレオン3世が破滅するという期待と見解は英仏戦争ではなく、[[普仏戦争]]という形態によって現実化した。普仏戦争に関するエンゲルスの分析は極めて優れたものであった。エンゲルスは布陣や会戦地点に関する予想を的確に分析し、予測を『{{仮リンク|ペル・メル・ガジェット|en|The Pall Mall Gazette}}』({{lang-en-short|''The Pall Mall Gazette''}})という雑誌に掲載した。その結果、エンゲルスは一流の軍事評論家として認められ、マルクスやその他の友人たちから「将軍」のニックネームで呼ばれるようになった<ref name="ハント(2016)288">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.288</ref>。下記「普仏戦争とエンゲルス」を参照のこと。一方、エンゲルスは[[帝国主義]]や[[植民地支配]]に反感を抱いていたことで知られている。これについても下記「危機と再編の時代」の項目で後述する。 |
|||
==== 『経済学批判』への協力 ==== |
|||
{{節スタブ}} |
|||
『経済学批判』序文への協力 |
|||
エンゲルスは、マルクスの頭脳の偉大さを認め、早い時期からマルクスの理論の発展に対して重要な助言者の役割を担ってきた。 |
|||
マンチェスター時代には、エンゲルスは、マルクスの主著『資本論』を完成させる上でこの上なく重要な助言者となった。[[資本主義]]経済の渦中で有能な経営者として頭角を現しつつあったエンゲルスは、マルクスに対してしばしば現実の経営の実情、資本家の実務や慣例について情報を提供した。時には、マルクスの要請に応じて、『資本論』の原稿に対して経営者の観点から助言や指摘を行った。 |
|||
(要執筆) |
|||
=== 危機と再編の時代へ === |
|||
==== 労働運動の再建 ==== |
|||
{{節スタブ}} |
|||
国際的な労働者運動は1860年代の国際危機に刺激され復活を遂げていく。 |
|||
1860年代[[大英帝国]]の世界支配が完成する一方、新興国の工業化、近代化が急速に進展し始めていた。この時代の動きはアメリカにおいて[[南北戦争]]、南欧で[[イタリア統一運動]]、東欧でポーランド蜂起([[1月蜂起]])となって現れる。これらの事象に対する労働者の反応が国際的な労働者組織([[第一インターナショナル]])を創立する直接的契機となった。 |
|||
1857年からの不況で企業が次々と倒産して失業者が増大したことでヨーロッパ諸国では労働運動が盛んになった<ref>[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.241-242</ref>。 |
|||
* 1857年経済危機 |
|||
1850年代の好景気により[[ロンドン]]では建築ラッシュを迎えたが、1857年の経済[[恐慌]]によって{{仮リンク|1859年のロンドン建築工ストライキ|en|London builders' strike (1859)}}が起こる<ref>Burgess, K. ''The Origins of British Industrial Relations: The Nineteenth Century Experience''. (London, 1975) pp.109-113</ref><ref name="飯田鼎(1996)58">[[#飯田(1966)|飯田鼎(1996)]] p.58</ref>。労働時間の短縮を要求する建築工のストライキは失敗に終わったものの、ストライキにおける労働者の団結と闘争を強化する目的で各業種ごとに職工たちが結集して組織した{{仮リンク|新モデル組合|label=合同組合|en|New Model Union}}が組織され、1860年5月には、{{仮リンク|ロンドン労働者協会|en|London Trades Council}}({{lang-en-short|London Trades Council}} 以下、LTCと表記)が発足し、多くの都市で労働運動の結集が進展した。後にLTCは、1865年に結成された[[改革連盟]]という成人男子選挙権を要求する熟練労働者([[労働貴族]])による政治団体の母体となり、また、各地で組織された同様の「地区労」を結びつけて[[労働組合会議]]({{lang-en-short|Trades Union Congress}})を開催し、全国的な労働組合の組織を作り上げた。 |
|||
フランスでは、1860年代以降、ナポレオン3世が「{{仮リンク|自由帝政|fr|Empire libéral}}」と呼ばれる自由主義化の改革を行うようになり<ref name="鹿島(2004)178">[[#鹿島(2004)|鹿島(2004)]] p.178</ref>、皇帝を支持する[[アンリ・ド・サン=シモン|サン・シモン主義者]]や労働者の団体「パレ・ロワイヤル・グループ」の結成が許可された<ref>[[#鹿島(2004)|鹿島(2004)]] p.369-370</ref>。プルードン派や[[ルイ・オーギュスト・ブランキ|ブランキ]]派の活動も盛んになった<ref name="石浜(1931)243">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.243</ref>。後述で詳しく紹介するが、ドイツでも1863年に[[フェルディナント・ラッサール|ラッサール]]が[[全ドイツ労働者同盟]]を結成した<ref name="江上(1972)210">[[#江上(1972)|江上(1972)]] p.210</ref>。 |
|||
[[1848年革命]]の挫折によって崩壊していた労働運動、革命運動が、世界各国で復活を遂げようとしていた。 |
|||
{{See also|改革連盟|パリ・コミューン}} |
|||
==== 南北戦争の余波 ==== |
|||
1861年、アメリカの南部諸州が連邦からの脱退を宣言して[[アメリカ連合国]]を結成し、アメリカを二分する内乱・[[南北戦争]](1861-1865年)が勃発した。 |
|||
エンゲルスは南北戦争とブリテンにおける北部支援運動に強い印象を受けた。北部合衆国主導の[[黒人奴隷]]の解放によって民主化と工業化が進展し、アメリカ大陸に新時代を開拓する強力な新興国が出現することを期待していた。北部合衆国は、南部連合の主要産業である綿花生産に打撃を加えるべく、[[北軍による海上封鎖|海上封鎖]]を実施した。その結果、[[綿花]]危機でヨーロッパの綿花関連の企業が原料不足による操業停止に追い込まれ、次々に倒産に追い込まれていく中、[[ランカシャー]]から[[マンチェスター]]にかけての膨大な数の労働者が大量失業と生活難に陥った。 |
|||
[[File:Thure de Thulstrup - L. Prang and Co. - Battle of Gettysburg - Restoration by Adam Cuerden (cropped).jpg|thumb|300px|1863年7月1‐3日の[[ゲティスバーグの戦い]]。北軍と南軍が総力を結集して南北戦争史上最大の激戦となった。この戦いが転換点となり北軍が優勢になった。]] |
|||
[[File:August Willich.jpg|thumb|200px|{{仮リンク|アウグスト・ヴィリヒ|de|August Willich}}。1863年の写真。1849年プファルツ・バーデン革命戦争に従軍していた頃のエンゲルスの上官。]] |
|||
エンゲルスは北部による奴隷解放を支持する立場を堅持していたものの、戦局の行方についてマルクスとは異なる見解を持っていた。エンゲルスは初戦における南部連合の戦勝から、1862年春に展開された東部戦線[[バレー方面作戦]]で活躍する[[ストーンウォール・ジャクソン]]など南軍将官の優秀性に感銘を受けており、当初のところ「北軍の将官は愚か者ばかり」で戦争は南部連合の勝利で終わると予想していた<ref name="『書簡集(上)』(2012)196">『書簡集(上)』(2012) p.196</ref>。しかし、マルクスはエンゲルスの軍事面に偏る分析に対して批判的な姿勢を取り、奴隷解放という歴史的大義を掲げた北部合衆国が最終的に勝利をおさめるという認識を示し続けた。マルクスは、1862年夏にエンゲルスと交わされた書簡において次のように述べている。 |
|||
{{quotation|「アメリカの内戦についての君の意見には全面的には賛成しない。僕は、万事休した、とは思わない。 |
|||
北部諸州人は当初から境界奴隷諸州に代表者たちに支配されていて、……、これに反して南部は始めから始めから一体となって行動していた。北部自身が奴隷制を、南部に反抗させないで、南部の軍事力に変えていた。南部は奴隷たちに生産的労働を任せていて、その全戦力を戦場に連れ出すことができた。南部は統一的な軍事指導権をもっていた。北部はそうではなかった。……。僕の見解からすれば、こんなことすべては方向を転ずるだろう。北部は最後には真剣に戦争をし、革命的手段をとらえて、境界奴隷諸州の政治家の上部支配を排除するだろう。たった一つの黒人連隊でも南部の神経に著しく作用するだろう。」<ref name="『書簡集(上)』(2012)198-199">『書簡集(上)』(2012) pp.198-199</ref>}} |
|||
{{quotation|「僕は、最後には北部が勝つ、という見解を相変わらず固辞している。南部は、ただ奴隷境界諸州を保持するという条件のもとでのみ講和を締結するだろうし、あるいはまた締結しうるだろう。……。だが、こんなことは不可能だし、起こりもしないだろう。……。現状を基礎としてのその間の休戦状態などは、せいぜい作戦の中休みを引き起こしうるだけであろう。……。もちろん、そのまえにまず一種の革命が北部そのもののなかで起きる、ということもありうる。{{仮リンク|アウグスト・ヴィリヒ|de|August Willich}}は旅団長で、……、シュテフェンも今度は(北部側で)戦争にでるそうだ。僕には君が少しばかり事態の軍事的様相によって意見を決めすぎているような気がするのだ。()内筆者補足。」<ref name="『書簡集(上)』(2012)200-201">『書簡集(上)』(2012) pp.200-201</ref>}} |
|||
マルクスの読み通り、1863年夏の[[ゲティスバーグの戦い]]以降、長期戦を強いられた南部連合は工業生産力の差から北部合衆国に対して守勢に立つようになり、1864年4月には南部連合の首都[[リッチモンド (バージニア州)|リッチモンド]]が陥落、まもなく北部合衆国の勝利が達成される。 |
|||
この戦争はブリテンのプロレタリアート階級に多大な犠牲を強いるものとなったが、マルクスは南北戦争を奴隷解放のみならず、やがて到来する労働者階級の解放の先駆けと見なした。アメリカにおける黒人奴隷制の廃止が全世界における賃金奴隷制の廃止の要求に発展し、労働者階級が搾取階級との闘争を歴史的運命として認識するようになる一助と考えたのである。 |
|||
エンゲルスもマルクスと同様に、南部の黒人が奴隷化されている現状は、アメリカをはじめ全欧州の白人労働者を隷属させる経済システムの長期化につながるものであって、早期に北部合衆国を勝利させて奴隷解放を実現させることが歴史的大義であると見ていた。エンゲルスは、ブリテンとアイルランドの労働者が騒擾や打ち壊しもせず自己犠牲的な「沈黙」を貫き、ブリテン政府が南部連合を救うべく北部合衆国に軍事介入を試みる企てを抑止したことに満足感を得ていた。 |
|||
==== 植民地主義との闘い ==== |
|||
一方、ヨーロッパ大陸の東ではポーランド蜂起([[1月蜂起]])が発生していた。 |
|||
[[ファイル:January Uprising Russian revision.PNG|250px|right|thumb|ポーランド貴族の館で略奪をはたらくロシア兵]] |
|||
エンゲルスは[[ポーランド]]解放をヨーロッパの老大国が強化する[[軍国主義]]の否定の契機として考えて蜂起を支持した。自由で民主主義的な[[ポーランド]]国家が中央ヨーロッパに再び登場すれば、[[ロシア帝国]]の[[専制|ツアーリズム]]と[[プロイセン]]の軍国主義に抵抗する「自由の砦」が建設されて、ヨーロッパ秩序の自由化・民主化が進行すると期待できた。 |
|||
エンゲルスは、ポーランド蜂起に加わった革命家の支援のためにマンチェスターで募金活動を組織するなど全力を注いだ。 |
|||
また、国際世論の啓発のために執筆活動にも取り組む姿勢を見せ、外交についてはマルクスが書き、軍事についてはエンゲルスが書くという共同事業で『ドイツとポーランド』という小冊子の作成を検討していた。この小冊子の作成の最中に蜂起の鎮圧が伝えられて計画に終わるが、二人は「他民族を抑圧する民族は、みずからを解放することはできない。他民族を抑圧する力は最終的につねに自国民に向けられるからだ」とする認識を一層強め、[[民主主義]]の実現、植民地解放と[[民族自決権]]の達成を呼び掛ける動機づけとなった<ref name="ハント(2016)292">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.292</ref>。 |
|||
また、英仏ではポーランドの窮状に対する同情の念が強まってポーランド支援の世論形成を促した。また、[[植民地主義]]に対する嫌悪感と戦争への恐怖心から、欧州の[[帝国主義]]諸国が引き起こす外交問題に懸念が深まり、外交危機に対する労働者階級の運命と役割への関心は次第に強まっていった。 |
|||
エンゲルスは1840年代には[[スラブ人]]や東洋人をヘーゲル的な意味での「非歴史的民族」として位置づける人種差別的感情を持っていたが、1860年代に入ると[[奴隷制度廃止運動|黒人奴隷の解放運動]]やポーランド独立運動に刺激を受けて、次第に植民地解放と民族自決権の擁護者となっていった<ref name="ハント(2016)293">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.293</ref>。 |
|||
[[File:PaulBogle-MorantBay.jpg|thumb|150px|right|[[ポール・ボーグル]]の記念碑]] |
|||
[[1865年]][[10月11日]]、[[ジャマイカ]]東部の[[セント・トーマス教区 (ジャマイカ)|セント・トーマス教区]]で、[[ポール・ボーグル]]が200人から300人の貧しい黒人男女を率いて{{仮リンク|モラント・ベイ|en|Morant Bay}}の市街へ乱入した。 |
|||
総督[[エドワード・ジョン・エア|エドワード・エア]]は軍を派遣し、軍は組織的な抵抗に遭遇しなかったが無差別に黒人を虐殺した。そのうちの多くはこうした暴動や反乱に関与していなかった。ある兵士の証言によると、「我々は我々の前にいるすべてを殺戮していった…男であれ女であれ、子供であれ」とのことである。この反乱事件は後にモラント湾の暴動([[ジャマイカ事件]])として知られるようになるが、事件はブリテン本国での大論争を引き起こした。事件はエンゲルスにも大きな影響を及ぼし、彼は「郵便が来るたびに、ジャマイカでのさらにひどい残虐行為のニュースがもたらされる。非武装の黒人を相手にした英雄行為を語るイギリス人士官たちの手紙は言語に絶する」と語って、エア総督の黒人虐殺に嫌悪感を示した<ref name="ハント(2016)293"/>。 |
|||
エンゲルスは、世界各地で発生する現地住民の抵抗に共感を抱くようになっていた。[[中国]]での[[アヘン戦争]]、[[インド大反乱]]などの事例に加え、[[アルジェリア]]や[[コンゴ]]での帝国主義列強諸国の「人類や文明、キリスト教の精神」に反する蛮行を非難した。「先住民が暮らし、単に支配を受けているインド、アルジェ、オランダやポルトガル、スペインの領地」のような国々は、「できる限り急速に独立」を果たし、革命を達成することが急務であると考えるようになった。エンゲルスによる抵抗思想の確立とともに、革命的プロレタリアート主導の植民地抵抗運動の展開というマルクス主義的外交戦略の展望が定まった<ref name="ハント(2016)293"/>。 |
|||
==== アイルランド独立闘争 ==== |
|||
[[ファイル:Famine memorial dublin.jpg|thumb|[[ジャガイモ飢饉]]の追悼碑。[[アイルランド]]、ダブリン。]] |
|||
エンゲルスは、[[アイルランド]]独立闘争の歩みに深い共感を抱いていた。 |
|||
エンゲルスがアイルランドを初めて旅行したのは1856年であった。エンゲルスは伴侶である[[メアリー・バーンズ]]とともに[[ダブリン]]から[[ゴールウェイ]]にかけて旅行し、アイルランドの自然や人々との出会いを堪能している。帰国後もエンゲルスはアイルランドに関心を示して、[[ゲール語]]を勉強、法律、歴史、地理、地質、文化を学習し、研究ノートを作成していった<ref name="ハント(2016)301">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.301</ref>。エンゲルスは、アイルランド農村について「飢饉がこれほど生々しく現実に感じられるとは思いもしなかった」と旅行中に綴り、続けて「村はまるごと放棄されていた。そうした村々のあいだに、まだそこで暮らしているほぼ唯一の人々である小規模な地主の素晴らしい庭園がある。大半は法律家だ。飢饉、海外への移住、そしてその合間の撤去が、こうした事態をもたらしたのだ」と語っている<ref name="ハント(2016)302">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.302</ref>。 |
|||
アイルランド農村は、1845年から1852年にかけて猛威をふるった[[ジャガイモ飢饉]]と牧草地転用のために展開された強制的な撤去、{{仮リンク|小作農立ち退き|en|Eviction}}によって牧畜経済が形成される一方、アイルランドの貧農層はかつてない窮状を余儀なくされた。飢饉による打撃で100万人の死者と100万人超の膨大な人口が{{仮リンク|アイルランド人の離散|label=離散|en|Irish diaspora}}を強いられてアイルランドの農村プロレタリアートは完全なる壊滅に至っていた<ref name="ハント(2016)302"/>。 |
|||
エンゲルスは、{{仮リンク|ブリテン支配|en|History of Ireland (1801–1923)}}を先進文明による野蛮の征服とは考えず、アイルランドの窮状に対して一貫して同情的であった。 |
|||
彼は、[[アイルランドの歴史|ノルマン人のアイルランド征服]]から[[クロムウェルのアイルランド侵略|クロムウェルの侵略]]を経て、アイルランドがイングランドによって組織的に略奪されたために惨めな敗者へと転落して「完全に落ちぶれた民族」となってしまったと捉えるようになっていた<ref name="ハント(2016)302"/>。マルクスが[[帝国主義]]理論を理論化するはるか前に、エンゲルスは「アイルランドはイングランドの最初の植民地と見なせるかもしれない」、「イングランド人の自由は各地の植民地の抑圧に基づいている」と分析し、アイルランド研究を通じて資本主義とブリテン帝国主義の侵略行為とを結び付けて考えた。後にマルクスも「アイルランドはイングランドの土地貴族の砦である」、「イングランドの貴族がイングランドの国内における支配力を維持するための重要手段」であると位置づけるようになった<ref name="ハント(2016)303">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.303</ref>。 |
|||
こうした状況下でアイルランドでは、革命組織{{仮リンク|アイルランド共和国同盟|en|Irish Republican Brotherhood}}による独立闘争が活発化していた。 |
|||
しかし、ダブリンでの1867年3月5日の{{仮リンク|フィニアン蜂起|en|Fenian Rising}}は失敗に終わってしまう。この事件は、イングランドを「悪の帝国」と見なし、アイルランドに自由で民主的な共和国を打ち立てるため、立ちあがった義勇兵たちの蜂起であった。蜂起に加わった活動家は逮捕され次々と収監されたが、革命派は脱獄計画を立て{{仮リンク|クラーケンウェル刑務所の爆破事件|en|Clerkenwell explosion}}を起した<ref name="ハント(2016)303-304">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.303-304</ref>。これらの事件はマルクスとエンゲルスが嫌っていた軽挙妄動に他ならなかったが、[[リディア・バーンズ]]の存在が二人の考え方を変化させた。リジーは[[マンチェスター]]で活動家{{仮リンク|トマス・ケリー|en|Thomas J. Kelly (Irish nationalist)}}と{{仮リンク|ティモシー・ディシー|en|Timothy Deasy}}{{仮リンク|1867年のマンチェスター護送車襲撃事件|label=護送中の車両を襲撃|en|Manchester Martyrs}}して警官を殺害した革命家たちを匿い、逃亡を手助けする謀議に関わっていた。警察もエンゲルスとリジーの動きを察知できず、犯人逮捕に手間取った<ref name="ハント(2016)305">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.305</ref>。五人の実行犯はまもなく逮捕され、そして三名に死刑判決が下り、処刑された。エンゲルス家ではリジー、マルクスの娘{{仮リンク|ジェニー・ロンゲ|label=ジェニー|en|Jenny Longuet}}、トゥシー([[エリノア・マルクス]])が喪服を着て緑(アイルランドのシンボルカラー)のリボンとポーランド十字架を身に付けたという<ref name="ハント(2016)305"/>。 |
|||
マルクスとエンゲルスは、ドイツの労働者階級の解放がポーランド解放にかかっていたのと同様、アイルランドはイングランドの最大の弱点であり、アイルランド独立によって[[大英帝国]]の解体が始まり、イングランドの[[階級闘争]]、世界各地で民族解放闘争の狼煙が上がると考えるようになった。 |
|||
==== ドイツでの情勢変化 ==== |
|||
[[画像:Фердинанд Лассаль.jpg|right|200px|thumb|フェルディナント・ラッサール]] |
|||
[[フェルディナント・ラッサール]]は、[[プロイセン王国]]の19世紀[[国家社会主義]]運動の指導者である。 |
|||
ラッサールは、1825年にプロイセン東部ブレスラウに裕福なユダヤ人の息子として生まれた。1844年、青年となったラッサールは故郷を離れてベルリン大学へ進学し、[[ヘーゲル]]哲学を研究した。交流のあった伯爵夫人の離婚問題からドイツの封建的制度への批判的立場を持ちはじめ、[[1848年革命]]に参加していった。ラッサールは哲学者[[ヘラクレイトス]]の思想を研究して成功を収め、哲学や革命運動で一時[[カール・マルクス|マルクス]]やエンゲルスとも親交していた。しかし、[[イタリア統一運動]]の指導者ガリバルディの影響を受けて政治の世界に参入した後は、ナポレオン3世によるイタリアの[[サルディニア王国]]支援に期待するとともに、プロイセン王国が進める[[小ドイツ主義]]に基づく[[ドイツ統一]]に期待をかけて、マルクスとは異なる立場を打ち出し対立していく<ref name="フォスター(1956)53">フォスター(1956) p.53</ref>。 |
|||
両者は労働者保護に関する志は共有していたが方法論に違いがあった。 |
|||
マルクスは、労賃に関してラッサールとは異なる見解を示していた。労賃は資本家の恣意で決定されているのだから、価格を上げなくても労賃を上げて生活水準を向上させることは可能であると見ていたのである。こうした賃金闘争のために[[労働組合]]は欠かすことのできない組織と位置付けて、その役割を積極的に評価していた。また、マルクスはイギリスやアメリカを例外として、「前衛政党」による暴力革命によって古い政府から国家権力を奪取し「[[プロレタリアート独裁]]」によって資本主義を打破する道を探っていた。 |
|||
これに対して、ラッサールは協同組合の相互扶助を重視し、賃金闘争によって人件費が上がるとコストがかかって物価が上がり結果的に生活水準は向上しないという盲目的な「[[賃金の鉄則]]」を支持していたため、労働組合や労働争議を否認していた<ref name="フォスター(1956)54">フォスター(1956) p.54</ref>。かれは国家の支援を得た協同組合の連合が資本主義に取って代わると考えており、革命ではなく「成人男子選挙権」を実現して議会進出を図るべきだと考えていた。1863年には最初の労働者政党[[全ドイツ労働者同盟]]を設立し、[[ビスマルク]]に積極的に協力しながらプロイセン議会の議席獲得を目指していく。 |
|||
1864年夏、エンゲルスは[[プロイセン王国]]を盟主とする[[北ドイツ連邦]]と[[デンマーク王国]]間で勃発した[[第二次シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争]](1864年2月1日-7月1日)後まもなく、軍事評論家として同地方への視察旅行をおこなった。この時の視察旅行でエンゲルスは[[ユトランド半島]]と[[スカンディナヴィア]]諸国の文化と歴史、そして人々との交流に大きな喜びを得る一方、[[プロイセン王国]]の膨張とその[[軍国主義]]に警戒感を高めていった<ref name="グムコー(下)(1972)6">{{Harvtxt|グムコー|1972}} p.6</ref>。 |
|||
帰国後、マンチェスターに戻ったエンゲルスを仰天させるニュースが飛び込んできた。 |
|||
一つは[[フェルディナント・ラッサール]]の死と二つは国際労働者運動の再生であった。ラッサールは1864年8月31日に恋愛問題に絡む決闘で命を落としたのである<ref name="江上(1972)261">[[#江上(1972)|江上(1972)]] p.261</ref>。訃報は[[フェルディナント・フライリヒラート|フライリヒラート]]からの電報ですぐさまマルクスとエンゲルスのもとに届けられた。ラッサールの死は思いがけないものの、弔意を示したマルクスに対して、9月4日の手紙でエンゲルスは冷淡な反応を示してこう述べた。 |
|||
{{quotation|「ラッサールは、人間的にも、著作の面でも、学問的にもあの通りの人物でしかなかろうとも、政治的には確かにドイツにおける極めて重要な男の一人であった。現在では彼は、われわれにとって、非常に危険な友人であったし、将来はかなりはっきりした敵になったであろう。いずれにせよ、ドイツが急進的な党派の多少とも有為の人物をことごとくだめにしてしまうのを見るのは、ひどい打撃だ。どんな歓声が工場主たちの間や進歩党の豚どもの間で上がることだろう。ラッサールは、なんといっても、彼らに不安を抱かせたドイツ本土における唯一の男だったのだ。それにしてもなんという奇妙な生命の捨て方だろう。バイエルン公使の娘に真剣に惚れ込んで、彼女と結婚しようとし、…ワラキアの詐欺師と衝突して、そいつに射殺されるとは。これはだたラッサールだけに起こりえることだ。まったく彼一人に固有だった、あの浮薄と感傷との、ユダヤ気質と騎士ぶりとの、奇妙な混合物だった彼だけに。」<ref name="『書簡集(上)』(2012)228-229">『書簡集(上)』(2012) pp.228-229</ref>}} |
|||
1864年に決闘でラッサールが世を去った後も「全ドイツ労働者協会」の求心力は強かった。ラッサール派はプロイセン支持に徹した国家擁護の立場だったので、[[第一インターナショナル]]には加盟しなかったが、ドイツ、チェコ、オーストリア、そしてドイツ系の移民先であったアメリカに支持者がおり、マルクス主義の主要なライヴァルとなった<ref name="フォスター(1956)55">フォスター(1956) p.55</ref>。 |
|||
=== インターナショナルの時代 === |
|||
==== 第一インターナショナルの発足 ==== |
|||
[[ファイル:International-founding-1864.jpg|right|300px|thumb|国際労働者協会発足集会、1864年9月28日]] |
|||
一方、マルクスがいるロンドンでも一大変化があった。 |
|||
英仏労働者がポーランド蜂起の支援を目的として結集を誓い、世界初の労働者の国際政治結社「国際労働者協会」('''[[第一インターナショナル]]''',以下IWAと略記)が結成されたのである。ブリテン側の世話人は製靴工の{{仮リンク|ジョージ・オッジャー|en|George Odger}}と大工の[[ウィリアム・ランダル・クリーマー|ランダル・クリーマー]]、フランス代表は青銅細工職人{{仮リンク|アンリ・トラン|en|Henri Tolain}}、議長は[[ロンドン大学]]教授の{{仮リンク|エドワード・ビーズリ|en|Edward Spencer Beesly}}だった。また、この集会には[[カール・マルクス|マルクス]]も同席していた。この集会はヨーロッパ各国の急進派が一堂に会する大規模なものとなった。マルクスはエンゲルスにこの集会とIWAについて以下のように伝えた。 |
|||
{{quotation|「少し前に、ロンドンの労働者が、パリの労働者に宛ててポーランドのことで呼びかけを送って、彼らにこの問題で共同行動を採るように要求してきた。……。[[1864年]][[9月28日]]を期して、公開集会が{{仮リンク|セント・マーティン・ホール|en|Queen's Theatre, Long Acre}}に招集された。……。ル・リュペスという男が僕のところに使いに来た。僕がドイツの労働者を代表して参加するかどうか、とくにドイツの労働者を一人代表してこの集会その他に派遣する気はないかというのだ。僕は{{仮リンク|エッカリウス|de|Johann Eccarius}}を派遣したが、彼は立派にやってのけた。僕も同じく出席してだんまり役として壇上に並んだ。今度はロンドン側からもパリ側からも本当の実力が出ていることを僕は知った。それで、この種の招請はなんでも断るという僕のいつもの決まりを捨てることに決めたのだ。」<ref name="グムコー(下)(1972)7">{{Harvtxt|グムコー|1972}} p.7</ref>}} |
|||
[[File:FRE-AIT.svg|200px|thumb|[[第一インターナショナル]](国際労働者協会)のロゴ]] |
|||
マルクスは国際的な労働者の結集点が登場したことを大いに喜び、エンゲルスも返信で同感であると述べた。 |
|||
マルクス、エンゲルスは[[1848年革命]]とその挫折からプロレタリアートが復活して、やがて[[資本主義]]に対する抵抗する政治的行動に結束する歴史的瞬間が再来するのを16年にわたり待ち望んでいた。9月28日の発足集会の決議に基づきロンドンに本部を設置することが定められ、「中央評議会」と年次大会を主軸としたIWAの組織が示された。しかし、エンゲルスは「この新しい協会は、諸問題がいくらか厳密に規定されるや否や、たちまちのうちに理論的に[[ブルジョア]]的要素と理論的に[[プロレタリアート]]的要素に分裂するだろうと僕は思う」と語り、各国のプロレタリアートの国際同盟の性格上、[[分派]]が生じる可能性があることを指摘して、マルクスによる包括的な理論的指導が重要になることを助言した<ref name="グムコー(下)(1972)8">{{Harvtxt|グムコー|1972}} p.8</ref>。 |
|||
そこで、マルクスは前もって作成された趣意宣言を「この駄文からなにかを作り出すことなど到底できない」として大幅に書き直すことにした。規約作成委員会での議事妨害と批評を通じて、1845年以来の労働者階級の運動を歴史的に総括する一節を加えることにより各派の思惑が加わった文言を次々と削除して、「[[権利]]、[[義務]]、[[真理]]、[[道徳]]、[[正義]]」といったブルジョア的な文言も重要個所から国際政治における[[帝国主義]]批判の項目等の「何ら害を及ぼせない位置に配置した」り、文言を移し替える等して、その内容を校訂して作り変えてしまった。 |
|||
こうして、マルクスは『'''[[第一インターナショナル創立宣言]]'''』と『規約』とを起草して、中央評議会で満場一致で採択されることに首尾よく成功している。マルクスはブルジョア的勢力の一掃のため、[[労働運動]]の支援、権力の獲得を目指す政治運動の展開を運動の中心に定めた。そして、IWA内のドイツ担当の一書記に過ぎなかったが、次第にIWAの実質的な指導権を獲得していった<ref name="フォスター(1956)41-42">フォスター(1956) pp.41-42</ref><ref name="グムコー(下)(1972)10-11">{{Harvtxt|グムコー|1972}} pp.10-11</ref>。 |
|||
IWAの組織は短期間で整備されたが、最期まで諸派の混在状態にあったため、当初、その意思決定は困難なものであった。近い立場の旧[[チャーティズム]]の信奉者、[[ブランキ]]主義者や[[ラッサール]]派の他に、IWAにおいて「権威」となったマルクスへの主な反対者として、ブリテンの労働組合指導者たちや[[プルードン]]や[[バクーニン]]、[[マッツィーニ]]らが存在した。マルクスは1871年アメリカ人会員のフリードリヒ・ボルテに宛てた手紙においてこう語っている。 |
|||
{{quotation|「インターナショナルが作られたのは、社会主義的、半社会主義的な宗派を労働者階級の本当の闘争組織でおきかえるためであった。これは最初の規約や創立宣言をみれば一目でわかる。……。インターナショナルの歴史は、労働者階級の本当の運動に逆らって…自分の地位を保とうとつとめた宗派やアマチュア実験に対する、総評議会のたえまない闘争であった」<ref name="フォスター(1956)47">フォスター(1956) p.47</ref>。}} |
|||
マンチェスターで「エルメン・エンゲルス商会」の経営に打ち込んでいたため、エンゲルスは中央評議会の重職を務めることはできなかったものの、日々の文通を通じてマルクスに状況報告とアドバイス提供に貢献した。マルクスはエンゲルスの助言に従い、IWA内部の雑多な勢力を整理していく算段であった。 |
|||
マルクスは『資本論』の執筆を前に『[[賃金、価格、利潤]]』という講演をおこなうなどますます多忙な生活を余儀なくされていた。しかし、プロレタリアートの国際的連帯の強化の促進とその理論的指導は、将来にわたる国際社会主義運動の方向性を指し示すものとなった。マルクスはブルジョア国家との共存を志向して階級闘争の推進を妨げ続けるプルードン派との論争、労働組合主義者への反駁、ラッサール派の打倒にエネルギーを注ぎ込んでいく。マルクスによって強化されたIWAはフランスでの[[パリ・コミューン]][[革命]]で活躍を見せ、ドイツでは[[アウグスト・ベーベル]]を中心とした[[社会主義]][[政党]]の結成へとつながっていく。 |
|||
[[ロンドン]]の{{仮リンク|セント・マーティン・ホール|en|Queen's Theatre, Long Acre}}での発足集会(1864年)にはじまり、 {{仮リンク|ジュネーヴ大会|en|Geneva Congress (1866)}}(1866年)、{{仮リンク|ローザンヌ大会|en|Lausanne Congress (1867)}}(1867年)、{{仮リンク|ブリュッセル大会|en|Brussels Congress (1868)}}(1868年)、{{仮リンク|バーゼル大会|en|Basle Congress (1869)}}(1869)、{{仮リンク|ハーグ大会|en|Hague Congress (1872)}}(1872年)が開催された。IWAは[[国際主義]]に立って国家的枠組みを超えた[[社会主義]]運動に関する決議を採択し各国政府に提言したほか、世界初の[[社会主義革命]]というべき[[パリ・コミューン]][[革命]]を支援するなど横断的な挑戦を試みた。 |
|||
{{See also|第一インターナショナル|第一インターナショナル創立宣言}} |
|||
==== 引退とロンドン暮らし ==== |
|||
エンゲルスのビジネスライフにはマルクスへの金銭面と知的交友面での自己犠牲の他に、自分自身の健康面への自己犠牲も伴った。 |
|||
1850年代末から60年代初頭期にかけて、エンゲルスは過労から深刻な体調不良に悩まされていた。1857年には膿瘍を患った他、膿瘍の回復も待たず続いて腺熱で倒れてもいる<ref name="ハント(2016)273">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.273</ref>。この病は妹マリーの看病によって早期に回復を見せ始め、1857年の経済危機の勃発により革命に近づいているという期待感と共に完治した<ref name="ハント(2016)274">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.274</ref>。しかし、病気による不運はエンゲルスではなく、彼の家族に及んだ。1860年には{{仮リンク|フリードリヒ・エンゲルス(父)|de|Friedrich Engels (Fabrikant)}}が世を去った。エンゲルスは嫌っていた父の死に対して特別な感情は抱かなかったが、エルメン一族との経営権をめぐる会社内の確執で神経をすり減らすことになった<ref name="ハント(2016)275">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.275</ref>。続いて母がチフスで倒れた際は母を深く愛していたエンゲルスも強い動揺に襲われた。さらに、弟のルドルフ、ヘルマンが長子フルードリヒを愛する母の病気に乗じて、エンゲルスから収益の大きい{{仮リンク|バルメン工場|en|Baumwollspinnerei Ermen & Engels}}の重要部門の経営権をはく奪しようと画策した。母も闘病生活の中で息子たちの衝突を仲裁することはできず、やむなくフリードリヒは弟たちに経営権を譲渡することになる。その結果、エンゲルスは自身の体調悪化も相まって病気がちとなっていたためビジネスから引退することを考えるようになっていく<ref name="ハント(2016)275-276">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.275-276</ref><ref name="グムコー(下)(1972)44">{{Harvtxt|グムコー|1972}} p.44</ref>。 |
|||
1863年冬、エンゲルスにとって大きな痛手が襲った。[[サルフォード]]の工場で下積みをしていた青年エンゲルスが見染めて、その後二十年に渡って連れ添った最愛の女性[[メアリー・バーンズ]]が41歳の若さで突如急逝したのである。あまりに突然のことだったため、エンゲルスはマルクスに手紙を送った。 |
|||
{{quotation|「親愛なるムーア。メアリーが死んだ。昨晩、彼女は早く床に就いたのだが、リジーが真夜中少し前に寝ようと思った時には、すでに息絶えていた。なんとも突然のことだ。心不全か脳卒中だろう。僕も今朝はまだ知らされていなかった。月曜の夜は、彼女もまだかなり元気だった。僕がどんな気持ちでいるかとても伝えることはできない。あの可哀そうな娘は僕を心底愛してくれた。」<ref name="ハント(2016)295">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.295</ref>}} |
|||
しかし、マルクスの反応はエンゲルスを落胆させた。メアリーの死に驚きを示しつつ、学費や家賃の支払いといった自分自身の経済状況に関する長文を廻らせ、急の資金援助を求めたのである<ref name="ハント(2016)295">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.295</ref>。さすがのエンゲルスも援助を断ったうえで、「こんなときにこのようなひどい話を君にする私は、恐ろしく利己的だ。しかし、これは同毒療法なんだ。何か悪いことがあれば、別の悪いことからは気が逸らされる。それでは!」と絶縁を想起させるような調子で綴り、マルクスに怒りを示した<ref name="ハント(2016)295">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.295</ref>。 |
|||
さらに、マルクスは五日も経ってからバツの悪い態度で返信したため、エンゲルスはさらに激高して「君はそれ(メアリーの死)を自分の〈私情をはさまない気質〉の優越性を主張するのにふさわしい場と考えたのだ。よろしい!」と言い放った<ref name="ハント(2016)296">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.296</ref>。ようやく、マルクスはエンゲルスを本当に怒らせたことに気づき、「君にあの手紙を書いたのは、私がひどく間違いだった。手紙を送ってすぐに後悔したよ。しかし、そうなったのは決して薄情さゆえではない」と述べ、傲慢なマルクスに似つかわしくはない素直さで丁重に謝罪した。エンゲルスもマルクスの謝罪の言葉に免じて、「一人の女性と何年間もずっと暮らせば、打撃を受けないはずはない。……。今回の手紙はその埋め合わせとなり、メアリーを失った挙句に、僕の一番古い親友までも失わずに済んだことをうれしく思う」と語り、その非礼を許した。エンゲルスは援助を乞うマルクスのためすぐに100ポンドを送金している<ref name="ハント(2016)296"/>。 |
|||
[[ファイル:Marx+Family and Engels.jpg|thumb|マルクスとエンゲルス。1864年、マルクス一家とともに。長女{{仮リンク|ジェニー・ロンゲ|label=ジェニー|en|Jenny Longuet}}。次女{{仮リンク|ジェニー・ラウラ・ラファルグ|label=ラウラ|de|Laura Lafargue}}、四女[[エリノア・マルクス|エリノア]]。]] |
|||
この出来事の背景には、マルクスがエンゲルスの愛人であるメアリーを良く思っていなかったことが考えられる。マルクスは学のないアイルランド女工のメアリーを内心では軽蔑しており、決して対等には見ていなかったのである<ref name="ハント(2016)296"/>。エンゲルスは労働者階級の素朴な女性を好んでいたため、マルクスと女性観・結婚観が大きく異なっていたと考えられる。二人はすれ違いのなかで絶縁寸前のところまで険悪となったが、再び正直な気持ちを打ち明けて和解した。 |
|||
その後、エンゲルスは妹のリディア・バーンズを家政婦からメアリーの代わりになる伴侶(内縁の妻)の立場に据えている。リジーは気性の激しいメアリーに比べて気さくで社交的だったため、マルクス家と親交が深く、とりわけ、マルクス家の末娘[[エリノア・マルクス|エリノア]]の回想から、マルクス家とエンゲルス家の絆を強める存在となっていたことがわかる<ref name="ハント(2016)296-297">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.296-297</ref>。成長していくマルクス家の三姉妹(長女{{仮リンク|ジェニー・ロンゲ|label=ジェニー|en|Jenny Longuet}}。次女{{仮リンク|ジェニー・ラウラ・ラファルグ|label=ラウラ|de|Laura Lafargue}}、四女[[エリノア・マルクス|エリノア]])、リジーとその姪パンプス(メアリー・エレン・バーンズ)、加えてマルクス家の家政婦ヘレーネとの交流がエンゲルスの心の安らぎ、マルクスとの友情の証になっていく<ref name="ハント(2016)299">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.299</ref>。 |
|||
だが、中年期のエンゲルスが実業と研究の両立ができなくなっていることに変化は生じなかった。 |
|||
1864年、会社の重役となっていたエンゲルスはエルメン・エンゲルス商会の経営権を完全に弟たちに売却する協定を結んでいる。エンゲルスは退職金をめぐる粘り強い交渉を重ねた後、1869年、1万2500ポンドを一括受取りする約束を受けて、ついに退職を果たした。かくして、エンゲルスは心身の苦痛を伴う工場経営の職から足を洗い、悠々自適な金利生活者になった<ref name="ハント(2016)312">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.312</ref>。立場の変化はエンゲルスの政治運動への復帰を可能にすると同時に、知的活動を大いに刺激して健康状態は劇的に好転した。翌7月1日の母親宛ての手紙でこう語っている。 |
|||
{{quotation|「お母さん。今日は自由の第一日です。この日の活用法としては、すぐさまあなたにお手紙を差し上げること以外にありえません。私は新しい自由を気に入ってます。私は昨日から全く別人になり、10歳若返っています。私は陰気な街ではなく、すばらしく晴れ渡った空のもと、数時間郊外へ出かけました。そして窓辺には花が置いてあり、家の前には木が数本ある……居心地よくしつらえてある部屋の中で、自分の文机に向かって、……倉庫の全く陰湿な部屋とはまったく違った気持で仕事をしています。」<ref name="グムコー(下)(1972)46-47">{{Harvtxt|グムコー|1972}} pp.46-47</ref>}} |
|||
エンゲルスは退職の日の爽快感についてよほど嬉しかったのであろう。マルクスにも「万歳!今日で愛しの仕事とおさらばだ、僕は自由の身だ!」と告げ、マルクスもエンゲルスの「出エジプト」を祝した。マルクスの娘[[エリノア・マルクス]]はこの日のエンゲルスの様子をこう描写した。 |
|||
{{quotation|「その朝であった。おでかけのため靴をはいていた、そして『ああ、これでおしまいだ』とエンゲルスがいった。それから数時間たって、エンゲルスはステッキをふりふり歌を歌いながら帰ってくるのが向こうのほうに見えた。その顔はほがらかに輝いていた。かれはテーブルの上にご馳走を並べて、いかにも嬉しそうにシャンペンを抜いた。この光景を見たのは私がまだ子供の時であったから、その意味がよく分からなかったが、今となって、あの日のことを思うと、わたくしは涙を止めることはできない。」<ref name="ハント(2016)312">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.312</ref>}} |
|||
[[File:Engel House in Primrose.jpg|thumb|[[ロンドン]]、[[プリムローズ・ヒル]]に位置するエンゲルスの家。エンゲルスの邸宅があったことを示す、ロンドン市議会のプレートが掲げられている<ref name="ハント(2016)318">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.318</ref>]] |
|||
1870年、エンゲルスは引退生活の場をマルクスが暮らしていた[[ロンドン]]に求め、[[喘息]]持ちのリジーのために、勾配の少ない地区で落ち着いた住宅地を探していた。マルクスの長女{{仮リンク|イエニー・マルクス|en|Jenny Longuet}}の紹介を受けて物件を見つけ出し、再開発によって北ロンドンの一等地となっていた[[リージェンツ・パーク]]近くに立地する[[プリムローズ・ヒル]]に居を構えることになった<ref name="ハント(2016)316-317">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.316-317</ref>。 |
|||
エンゲルスの邸宅は地下を含め五階建ての住宅で、地下にキッチンと浴室、一階に広々したリビングダイニングがあり、二階にはエンゲルスが一日の大半を過ごしていた応接室と書斎があり、三階と四階はリジーとエンゲルスの寝室、女中の部屋、リジーの姪のパンプスの部屋、来客用の部屋があった<ref name="ハント(2016)319">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.319</ref>。エンゲルスは社交的な雰囲気を好み、各国の社会主義者やバーンズ家の親族、マルクス家との家族ぐるみの付き合いを楽しんだ。エンゲルスは日々を規則正しく過ごし、午前中は研究時間と書簡の作成に割き、午後からは家から10分ほどのメイトランドパーク・モデナ・ヴィラズ1番地({{lang-en-short|1 Modena Villas, Maitland Park}})、1875年以降は近くのメイトランド・パーク・ロード41番地に住むマルクスを毎日訪ねていた<ref name="ハント(2016)319-320">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.319-320</ref>。[[エリノア・マルクス]]は二人の様子を次のように述べている。 |
|||
{{quotation|「エンゲルスは毎日うちの父に会いに来ました。一緒に散歩に出かけることもあったけれど、同じくらいよく父の部屋に籠もったまま、それぞれが部屋の片側をよくゆきつ戻りつして、隅で向きを変えるので、踵で穴が開きました。……。二人が黙ったまま行ったり来たりすることも度々でした。あるいはまた、そのとき自分が最も関心のあることをそれぞれが喋り、しまいに顔を合わせて大声で笑い、それまでの三十分間は正反対の計画について検討していたのだと認めたりするのだ。」<ref name="ハント(2016)319-320">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.319-320</ref>}} |
|||
1870年代に入り、大英帝国は産業革命後に世界の工場として君臨していた時代は過ぎ去り、帝国主義的な金融資本主義の国家へと変貌を遂げていった。こうした時代のなかで、引退後のエンゲルスは資産を株式購入に充てて運用し、金利生活を営む富裕な株主となっていた。皮肉にも「強欲で利己的な工場経営者」から「寄生的な金融資本家」へと変貌していたのである<ref name="ハント(2016)344-345">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.344-345</ref>。エンゲルスは、自分の立場の矛盾についてこう述べている。 |
|||
{{quotation|「人は証券取引人であるのと同時に、社会主義者にもなれるのであり、それゆえに証券取引人の階級を嫌い蔑むことにもまったく問題ない。……。自分がかつて工場主であった事実について、謝罪すべきだと思い立った試しがあろうか?その件で僕を攻めようとする人間は誰でも、手厚くもてなされるだろう!」<ref name="ハント(2016)345">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.345</ref>}} |
|||
==== 『資本論』第一巻刊行 ==== |
|||
{{節スタブ}} |
|||
==== バクーニンの登場 ==== |
|||
[[File:Bakuninfull.jpg|right|200px|thumb|ミハイル・バクーニン]] |
|||
[[ミハイル・バクーニン]]はロシア貴族の出であるが、役人になってロシアによるポーランド支配に当たるにつれて次第に政治に疑問を抱き、ついに革命家となっていった。 |
|||
[[1848年革命]]の混乱の中で革命運動に参加したことが角で死刑を宣告されたが、ロシア政府に引き渡されて1855年にはシベリアに流刑となっている。1861年、バクーニンは収容所を脱走して日本とアメリカを経てヨーロッパに帰還している。バクーニンはプルードンの弟子で、反権力の思想や自由な生産者の連帯にもとづく理想の未来社会というヴィジョンを柱とする[[アナーキズム]]思想を継承した<ref name="フォスター(1956)55"/>。 |
|||
ただ、バクーニンは労働組合の発展期のなかで労働運動の役割を評価する立場をとっており、生産組合を通じて共同体をつくり、その連合に新社会の基礎を見出していた。 |
|||
バクーニン主義の綱領は、[[無神論]]、国家の廃棄、[[暴力革命]]、労働組合を単位とする生産共同体、共同体の同盟による緩やかな統合を謳うものであった。また、バクーニンは反権力の立場から、マルクスの理論に反対して権力集中の危険性を説いた。マルクスは、移行段階の国家形態として、[[プロレタリアート]]が[[ブルジョア]]を逆[[搾取]]していくための国家形態「[[社会主義国|社会主義国家]]」を新社会のモデルに据えており、そのための政府モデルとして[[プロレタリアート独裁]]の概念を提唱していた。しかし、バクーニンは反権力に基づく自由な連合に基づく社会を理想とし、マルクスの中央集権的で革命独裁を含んだ国家理論に反対であった。バクーニンは、社会の末端の下層労働者が[[革命]]の担い手だと考えており、暴力革命による権力の転覆を支持する一方で、マルクスが説くような権力主導の理想([[社会主義国|社会主義国家]]を経由した[[共産主義|共産主義社会]]という[[ユートピア]])実現にはどうしても賛同できなかったのである。 |
|||
また、マルクスは、プロレタリアート独裁を提唱する傍ら自身が説く革命独裁には拘っておらず、[[議会]]や[[政府]]を通じて民主的な方法で[[社会主義]]政策を遂行する方向も認めていた。バクーニンはこうした現状肯定的な態度にも反対していた。彼はあくまでも暴力革命を説き、現状との妥協や支配階級に対する説得や交渉といった理性的手段には断固反対で、その思想には柔軟性には欠いた<ref name="フォスター(1956)56-59">フォスター(1956) pp.56-59</ref>。 |
|||
バクーニンはイタリアを中心に活動しており、{{仮リンク|平和自由連盟|en|League of Peace and Freedom}}の中央委メンバーとなっていたが、「連盟」から離脱し1868年新たな活動団体として{{仮リンク|国際社会民主同盟|en|International Alliance of Socialist Democracy}}を組織した。バクーニンは、[[無神論]]、階級の平等化、相続権の廃止、国家の廃棄、政治活動の拒否を唱えて支持者を集めていった<ref name="フォスター(1956)82">フォスター(1956) p.82</ref>。その活動は生活力のある労働者には差して支持は広まらなかったが、学生やインテリ、そして貧困労働者など社会的立場の乏しい人々に支持基盤があった。 |
|||
1868年、{{仮リンク|ヨハン・フィリップ・ベッカー|de|Johann Philipp Becker}}は国際社会民主同盟とバクーニン一派を代表して、IWAへの加入を申し入れるよう盛んに主張し始めた。だが、マルクスとエンゲルスはバクーニンが主張する秘密結社による陰謀や革命戦術を嫌い、警戒していた。同時に、ベッカーをバクーニンの傀儡に過ぎないと見ており、バクーニンが組織を乗っ取りを図っていて組織をスラブ主義的な陰謀団に変え、社会主義をロシアのテロリズムの道具にしようとしていると疑い始めていた。ロシアからの亡命者による報告の中で、結社を組織して基金を創設しながらその基金を横領した[[セルゲイ・ネチャーエフ]]というロシアの活動家とバクーニンが関係が深いことを知ると、マルクスはバクーニンへの嫌悪感を強めていった。マルクスは、テロを計画したり非合法な活動に熱中する陰謀団まがいの秘密結社とは連携を取らないように中央評議会に勧告した。これに基づき、12月にはIWAは国際社会民主同盟を解散させない限り認められないとして、1869年の{{仮リンク|バーゼル大会|en|Basle Congress (1869)}}では加入を断られていた<ref name="フォスター(1956)83">フォスター(1956) p.83</ref>。 |
|||
だが、バクーニン一派は組織を解散したように見せかけてIWAに密かに潜入して部内に分派を形成し始め、影響力を行使しようと試みるようになる。バクーニンの無政府主義、一揆的な革命主義はスペインや南イタリア、ロシアといった工業化が不十分な地域で支持を集めていた。スペインや南米諸国、南イタリア、ロシアでは労働組合は十分組織されておらず、抵抗運動のスタイルも秘密結社的な組織によるテロリズムが一般的であった。 |
|||
ただし、マルクス主義と無政府主義にはまだこの頃は類似点も多く、1868年の{{仮リンク|ブリュッセル大会|en|Brussels Congress (1868)}}で議論された土地国有化や労働組合に関する問題では、マルクス派とバクーニン派は協調してプルードン派などを抑える役割を果たしていた。しかし、マルクスはプルードン主義の脅威が去った今、新たな危険因子となるのはバクーニン主義であると考えるようになった。こうしてIWA内では[[アナルコ・サンディカリズム]]が台頭し始め、組織内で亀裂が生じていった<ref name="フォスター(1956)84">フォスター(1956) p.84</ref>。バクーニンとマルクスの思想的、運動実践上の相違はIWAを二分する論争へと発展、組織内で最大の衝突をもたらし、ついに組織の解体を招いていく<ref name="フォスター(1956)58-59">フォスター(1956) pp.58-59</ref>。 |
|||
{{See also|ミハイル・バクーニン}} |
|||
1870年、マルクスはバクーニン主義がまだ浸透していないドイツ中部の[[マインツ]]で大会を開催することを計画した。マルクスは総評議会での討議の流れを通じてバクーニン一派の除名への道すぎを開き、バクーニンを窮地に追い込むことを企図していた。マインツ大会の計画は突発的な普仏戦争開戦によって中止を余儀なくされたが、マルクスは内部闘争での勝利を確実にしようと執念を燃やした。その一つの表れが、エンゲルスがIWAの役職に就いてアナーキズム対策の役割を担ったことに見出される。 |
|||
1870年9月、総評議会は全権代表としてオーギュスト・セライエをパリに派遣した。セライエはパリでの革命に参加するためにフランスに帰国したのだが、彼が勤めていたスペイン連合評議会の担当書記が空席となってしまう。そこで、エンゲルスが10月4日総評議会の会合での指名を受け、スペイン連合評議会を任されることになった。エンゲルスは就任の挨拶をスペインに発し、その中でプロレタリアが既存の政治勢力に欺かれ吸収されようとしていることを指摘したうえで、既存政党から独立した労働者政党を樹立することが目下急務であることを表明した。 |
|||
{{quotation|「たしかに、古い諸政党の空虚な大言壮語が…人民の注意をあまりにも引き付けてしまって、そのために我々の宣言の大きい障害となっています。これはプロレタリア運動の初期ではどこでも起こりました。フランス、イギリス、ドイツで、社会主義達は貴族的であろうと、ブルジョワ的であろうと、また君主主義的であろうと、共和主義的であろうと古い諸政党の影響と闘う必要があったし、いまでもその必要があります。いたるところで経験は、古い諸政党のこの支配から労働者を解放する最良の方法が、各国に独自の政策、他の政党のそれと非常にはっきりと区別される政策―プロレタリア政党は労働者階級の解放の条件を表現しなければならぬのですから―をもつプロレタリア党を創立することであったことを証明しました。この政策の細かい点は、それぞれの国の特殊事情によって異なるでしょう。しかし、労働の資本に対する基本的関係はどこでも同一であり、有産階級の被搾取階級に対する政治的支配の事実はどこでも存在しますからプロレタリア政策の諸原則と目標とは、少なくとも西方諸国では同一であるでしょう。」}} |
|||
エンゲルスは、労働者の解放のためには各国が共通の目標を掲げたプロレタリア党を樹立することが必要であり、国際連携によってブルジョワ資本主義に対抗する共通の綱領と戦線を開くよう促している。エンゲルスはバクーニンの影響が強いスペインでアナーキズムと対決していくことなる。 |
|||
==== 普仏戦争とエンゲルス ==== |
|||
[[File:1870 bei Le Bourget.jpg|180px|thumb|普仏戦争で進軍するプロイセン軍。]] |
|||
[[画像:BismarckundNapoleonIII.jpg|thumb|right|300px|[[セダンの戦い]]の後、ナポレオン3世(左)とビスマルク(右)の会談の様子]] |
|||
マルクスとエンゲルスは、ヒューマニストとして戦争を憎んだ。彼らは、戦争を運命の産物や人間の無能力の結果で生じるものとしてではなく、社会矛盾、すなわち階級的搾取から生じる事象として捉えていた<ref name="グムコー(下)(1972)57">{{Harvtxt|グムコー|1972}} p.57</ref>。 |
|||
[[1870年]]夏に勃発した[[普仏戦争]]は、[[ビスマルク]]が狡猾な謀略工作[[エムス電報事件]]で[[ナポレオン3世]]を挑発して、フランスに宣戦布告へと踏み切らせた王朝戦争であった。しかし、ビスマルクは老練な政治力を駆使して、この戦争を[[北ドイツ連邦]]と南ドイツ諸国の同盟を強化して、全ドイツ的な同盟軍を動員する国民戦争とした。この開戦を機に、マルクスとエンゲルスはかねてから敵意を抱いていたナポレオン3世に復讐できる歴史的チャンスだと考えた。開戦に際してマルクスはこう語った。 |
|||
{{quotation|「フランス人たちは棍棒を必要としている。もしプロイセン人が勝てば、国家権力の集中はドイツの労働者階級の集中に有益だ。さらに、ドイツの優越は西ヨーロッパの労働運動の重心をフランスからドイツに移すことになるだろう。そして、これら両国における1866年から現在に至るまでの運動を比較してみただけでも、ドイツの労働者階級が理論的にも組織的にもフランスの労働者階級にも勝っていることを知るには、十分なのだ。世界の舞台におけるフランスの労働者階級に対するドイツの労働者階級の優越は、同時に、プルードンなどの理論に対する我々の理論の優越でもあるだろう。」<ref name="『書簡集(中)』(2012)89">『書簡集(中)』(2012) pp.77-78</ref>}} |
|||
エンゲルスに至っては「今度の戦争は明らかにドイツの守護天使がナポレオン的フランスのペテンをこれ限りにしてやろうと決心して起こしたものだ」と嬉々として語っている<ref>[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.296-297</ref>。 |
|||
しかし、公的には[[第一インターナショナル]]を代表したマルクスに対して、エンゲルスは労働者階級が採るべき戦略を五点の簡潔なテーゼとして提示した。 |
|||
{{quotation|「一、それがドイツの防衛に限られている間は、またその限りにおいて、(事情によっては、講話に至るまで攻勢であることを排除しない)、国民運動に加わる。二、その場合、ドイツ民族の利益と王朝的プロイセンの違いを明確にする。三、アルザス・ロレーヌのどんな併合にも反対運動をとる。四、パリで共和主義的な、[[排外主義]]的でない政府が政権を取ったらすぐに、それとの名誉ある講話を目指すこと。五、戦争を是認せず、また交戦もしないドイツを労働者とフランス労働者の利害の一致を絶えず力説すること。」<ref name="グムコー(下)(1972)58">{{Harvtxt|グムコー|1972}} p.58</ref>}} |
|||
要約すると、皇帝ナポレオン3世を打倒するまでは戦争を支持するが、打倒後は領土的要求はせずに停戦して和平を結ぶべきだというのがエンゲルスの立場であった。[[軍国主義]]の[[プロイセン王国]]を嫌悪していたものの、敵はあくまでもナポレオン3世による第二帝政だったのである。独仏の労働者には反戦と連帯、政治的進歩を求める運動に参加して、あくまでも母国の専制政治と侵略政策に反対し、政府に揺さぶりをかけなければならないと言明した。 |
|||
一方、普仏戦争の展開は諸国民の関心の的となっていた。 |
|||
ロンドンの『{{仮リンク|ペル・メル・ガジェット|en|The Pall Mall Gazette}}』({{lang-en-short|''The Pall Mall Gazette''}})紙がマルクスに軍事情勢に関する見解を論評してい欲しいと申し入れたのである。これに対して、マルクスは自分は専門外であるため、軍事に明るいエンゲルスを紹介し、彼ならば適任であると推薦した。今回はマルクスの推薦によってエンゲルスは同紙の軍事通信員として能力を活かせる最良の地位を占めることになった<ref name="ハント(2016)288"/>。「戦争時評」というタイトルで58回にわたる寄稿がおこなわれた。論文は大変秀逸な戦術分析を含んだものであった。 |
|||
エンゲルスの友人の縁者がプロイセン軍の前線部隊に所属していたため、分析に有益な情報を収集することができた。プロイセンの大将[[ヘルムート・フォン・モルトケ|モルトケ]]の作戦案を分析し、最初の戦闘地域が[[ザールブリュッケン]]付近となることを予測した。エンゲルスは特別記事をすぐさま執筆し、早馬車を走らせて記事を寄稿するなどいち早く特報した<ref name="ハント(2016)288"/>。 |
|||
また、1870年8月段階で[[セダンの戦い]]でのフランスの敗北とナポレオン3世の投降を予測した。エンゲルスの予想は見事に的中し、記事は世間からの評価を受けることとなる。マルクスもエンゲルスに宛て「ロンドンにおける第一級の軍事的権威者として認められる」であろうと語っている。しかし、このときの寄稿はエンゲルスが匿名で執筆したため、筆者が誰なのかについて数多くの憶測を呼んだ。この活躍によって軍事学の権威を示したエンゲルスは、マルクスから「将軍」という渾名を受けている。マルクスの妻[[イェニー・マルクス]]は「あなたの論説が当地でどんなにセンセーションを巻き起こしているか、ご想像できますまい!あなたはまったく素晴らしく明確にはっきりとお書きになっていらっしゃり、ですから私、あなたを若きモルトケとお呼びしないわけにはまいりません」と語るなど、エンゲルスに最大の賛辞を送っている<ref name="グムコー(下)(1972)60">{{Harvtxt|グムコー|1972}} p.60</ref>。 |
|||
エンゲルスの軍事理論は普仏戦争の分析を通じて発展された。エンゲルスは後に執筆する『[[反デューリング論]]』のなかで、対外戦争から人民革命への転化の可能性を指摘している。そして、大規模なゲリラ戦の抵抗からなる戦争論を提示し、共産主義革命理論を体系化した<ref name="ハント(2016)289-290">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.289-290</ref>。エンゲルスの革命論の下敷きとなったのがパリ・コミューンである。 |
|||
{{See also|普仏戦争}} |
|||
==== パリ・コミューン革命 ==== |
|||
[[ファイル:Gambetta proclaiming the Republic of France - Project Gutenberg eText 16910.jpg|thumb|200px|right|[[レオン・ガンベタ|ガンベタ]]の共和国宣言]] |
|||
戦況はプロイセン軍の圧勝に終わったのだが、敗北を喫したフランス側で政変が発生した。 |
|||
1870年9月4日、フランス立法院では{{仮リンク|パリカオ|en|Charles Cousin-Montauban, Comte de Palikao}}内閣が国防政府の樹立を提案して皇帝の退位要求に蓋をしようと試みていたが、ナポレオン帝政に対する不満は敗戦への怒りとなって爆発し、民衆は[[ブランキ]]派のエミール・ウードや{{仮リンク|エルネスト・グランジェ|en|Ernest Granger}}に導かれて立法院に殺到してきたのである。人々は「帝政を倒せ!立法院を倒せ!共和政万歳!」と叫び、[[フランス第二帝政]]の失権を迫った<ref name="桂圭男(1971)47">{{Harvtxt|桂圭男|1971}} p.47</ref><ref name="桂圭男(1981)67">{{Harvtxt|桂圭男|1981}} p.67</ref>。 |
|||
[[レオン・ガンベタ]]は市庁舎のバルコニーに立って共和国宣言を発し、{{仮リンク|ルイ・ジュール・トロシュ|en|Louis-Jules Trochu}}を首班とする{{仮リンク|国防仮政府|en|Government of National Defense}}の閣僚名簿を発表した<ref name="桂圭男(1971)51">{{Harvtxt|桂圭男|1971}} p.51</ref><ref name="柴田三千雄(1973)55">{{Harvtxt|柴田三千雄|1973}} p.55</ref><ref name="桂圭男(1981)68">{{Harvtxt|桂圭男|1981}} p.68</ref>。仮政府のもと、すぐにフランスでは国民総動員がかけられ[[国民衛兵]](フェデレ)の緊急招集が実施され、抵抗戦の継続が決定された。フランスは国防政府のもとで戦争を継続していくが、各地で次々と敗北して北フランス一帯を占領され、まもなくパリが包囲され籠城戦に入っていく。厳冬期に厳しい包囲戦を経験したパリ民衆は次第に急進化していったが、国防政府とプロイセンとの講和交渉に人々は憤慨した<ref name="ハント(2016)323-324">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.323-324</ref>。 |
|||
一方、マルクスとエンゲルスはパリに自制を説くとともに、プロイセンによる早期講和の締結と融和策を求めていた。当初、ビスマルクは戦争をドイツ統一を阻止せんとするナポレオン3世による干渉への報復のための防衛として語っていたが、ナポレオン3世の降伏後もフランス侵攻を継続させ、ついにパリに迫ろうとしていた。こうした動きは、普仏戦争をナポレオン3世に対する防衛戦とすべきと主張したマルクスとエンゲルスの立場に反するものであった。 |
|||
そのため、エンゲルスは戦況分析を戦争の軍事作戦に留まらず、ビスマルクが立案したドイツの安全保障戦略についても射程に置く分析を試みた。エンゲルスは、戦争の第一段階において、ドイツはフランスの排外主義に対して自国を防衛したが、いまや戦争は「しだいに、しかし、確実にドイツの排外主義のための戦争に」転化するであろうと分析した。統一されたドイツはアルデンヌ地方の森林地帯とライン川による地理的防御力によって十分にフランスの侵攻を撃退できるのだから、[[ストラスブール]]と[[メッス]]の占領を必要としないと主張した。マルクスもエンゲルスの見解に同調した。1870年9月9日、マルクスは第一インターナショナル中央評議会の『第二の呼びかけ』で、エンゲルスの上記の見解を公式見解として提示したうえで、プロイセンが「一九世紀後半期に侵略政策を復活させた」ことを非難した<ref name="グムコー(下)(1972)61">{{Harvtxt|グムコー|1972}} p.61</ref>。 |
|||
マルクスとエンゲルスは、ドイツの領土拡張戦争はフランスの復讐心を煽り、国際的孤立の中でドイツを再び大戦争に巻き込んでいくであろうと予測した。二人は将来のヨーロッパ史で[[第一次世界大戦]]が勃発すると予言したのである<ref name="フォスター(1956)90">フォスター(1956) p.90</ref>。 |
|||
パリ包囲戦中の1871年1月、ビスマルクは、[[ヴェルサイユ宮殿]]で南ドイツ諸国の北ドイツ連邦へと加盟させる形式でドイツ統一を取り決めた。[[ヴィルヘルム1世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム1世]]が[[ドイツ皇帝]]に戴冠され、これにより[[ドイツ帝国]]が樹立された。その10日後には、フランスに多額の賠償金の支払いを要求、[[アルザス]]=[[ロレーヌ]]の割譲、パリ占領という懲罰的な条件を盛り込んだ休戦協定を結ばせて普仏戦争を終結させた。これを聞いたエンゲルスは対仏強硬論を主張していた弟ルドルフに宛て、「現実には、人は目先のことしか見えないものだ」、「この先、多年にわたってフランスが間違いなく敵国であり続けるようにしたわけだ」と語った<ref name="ハント(2016)323">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.323</ref>。 |
|||
エンゲルスの懸念以上に歴史は急展開を見せた。 |
|||
国民衛兵は依然としてプロイセン軍のパリ入城への抵抗呼びかけていた。国民衛兵は武装解除を拒み、プロイセンに武器が押収されるのを防ぐため大砲を女子供も含んだ多数のパリ民衆と共に[[モンマルトル]]、ベルヴィールのなどの労働者地区へと移設していた。1871年3月1日、プロイセン軍は祝勝パレードのためにパリに入城した。弔旗が掲げられて静まり返るパリをプロイセン軍が3日にわたり占領した<ref name="桂圭男(1971)102">{{Harvtxt|桂圭男|1971}} p.102</ref><ref name="柴田三千雄(1973)90">{{Harvtxt|柴田三千雄|1973}} p.90</ref>。 |
|||
3月18日、[[フランス第三共和政|フランス共和国]]の行政長官に就任した[[アドルフ・ティエール]]は、武装解除のためパリ防衛の重要な堡塁[[モンマルトル]]陣地から国民衛兵が守備する大砲の撤去を命じた。 ルコント将軍とパチュレル将軍の指揮で大砲400門余の撤去を実施するが、これを偶然目撃した国民衛兵の女性兵士の一群が撤去に抵抗した。将軍は配下の兵に発砲を命じたが命令は空しく無視され、 ルコント将軍は離反した軍と国民衛兵により捕虜となった。捕えられた将軍のなかに[[1848年のフランス革命]]の[[六月蜂起]]で労働者の弾圧を行った{{仮リンク|クレマン・トマ|en|Jacques Leon Clément-Thomas}}将軍がいたため、{{仮リンク|クロウド・ルコント|en|Claude Lecomte}}将軍ともども猛る群集によって両将が殺害された<ref name="桂圭男(1971)112-117">{{Harvtxt|桂圭男|1971}} pp.112-117</ref><ref name="柴田三千雄(1973)97-98">{{Harvtxt|柴田三千雄|1973}} pp.97-98</ref><ref name="桂圭男(1981)138-140">{{Harvtxt|桂圭男|1981}} pp.138-140</ref>。 |
|||
[[File:Les hommes de la Commune.jpg|right|thumb|300px|コミューン政府の人々]] |
|||
この事件を機にパリでは「コミューン万歳!」の声が高まっていた。国民衛兵とコミューンに合流してパリの実権を奪取、ついに'''[[パリ・コミューン]][[革命]]'''が成就した。休戦協定に反発したパリ市民が武装蜂起した。一報を受けた[[アドルフ・ティエール]]は、[[1848年のフランス革命]]で果たせなかった計略を実行に移し、軍と政府関係者をひきつれてパリを放棄して[[ヴェルサイユ]]に逃走した<ref name="桂圭男(1971)115">{{Harvtxt|桂圭男|1971}} p.115</ref><ref name="柴田三千雄(1973)99">{{Harvtxt|柴田三千雄|1973}} p.99</ref>。3月28日にはコミューン選挙が実施されて、コミューン92名が普通選挙で選出されたが、そのうち17人は[[第一インターナショナル]]フランス連合評議会のメンバーだった<ref>[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.302-303</ref><ref name="ウィーン(2002)391">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.391</ref>。こうして世界初のプロレタリア政府[[パリ・コミューン]]が樹立された。 |
|||
マルクスはパリは無謀な蜂起するべきではないという立場をとっていたが、いざパリ・コミューン誕生の報に接すると、「なんという回復力、なんという歴史的前衛性、なんという犠牲の許容性を[[パリジャン]]は持っていることか!」「歴史上これに類する偉大な実例はかつて存在したことはない!」と{{仮リンク|ルートヴィヒ・クーゲルマン|de|Louis Kugelmann}}への手紙で支持を表明した<ref name="ウィーン(2002)391"/><ref name="メーリング(1974,3)97">[[#メーリング(1974,3)|メーリング(1974)3巻]] p.97</ref>。 |
|||
3月28日、パリ市庁舎前でコミューン政府の樹立が宣言され、以後5月20日まで二か月ほどの期間パリを統治することとなる。 |
|||
老{{仮リンク|シャルル・ベレー|fr|Charles Beslay}}を議長に、コミューン執行委員会を頂点として執行部、財務、軍事、司法、保安、食糧供給、労働・工業・交換、外務、公共事業、教育の10の各部実務機関が組織された<ref name="桂圭男(1971)141">{{Harvtxt|桂圭男|1971}} p.141</ref><ref name="桂圭男(1981)173">{{Harvtxt|桂圭男|1981}} p.173</ref>。フランスという国家機構から放棄されたパリ市民は、国民衛兵の補佐を受けつつ各執行部を通じて自発的に行政組織を再稼動させ、このときからコミューンは「代議體ではなく、執行権であって同時に立法権を兼ねた行動體」として活動をはじめた革命政府となった<ref name="マルクス(1952)95">マルクス(1952) p.95</ref>。その間、教育改革、行政の民主化、[[集会の自由]]、労働組合をはじめとする[[結社の自由]]、[[婦人参政権]]、[[言論の自由]]、[[信教の自由]]、[[政教分離]]、常備軍の廃止、失業や破産などによる生活困難者を対象とした[[生活保護]]、各種の[[社会保障]]など民主的な政策が打ち出され、暦も共和暦が用いられた。 |
|||
しかし、結局このパリ・コミューンは2カ月強しか持たなかった。ヴェルサイユに移ったティエール政府による「血の週間」という激しい攻撃を受けて5月終わり頃には滅亡したのである<ref name="ウィーン(2002)391"/><ref name="カー(1956)303">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.303</ref><ref name="小牧(1966)214">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.214</ref>。エンゲルスは「敗者は榴弾によって数百人単位で撃ち殺された」、「最後の大虐殺が実行された[[ペール・ラシェーズ墓地]]の〈フェデレの塀〉は、今日でも立っている。労働者階級が己の権利のために敢えて立ちあがった途端に支配階級が陥る狂気を、沈黙のなかで最も雄弁に語る証拠である」と描写した。 |
|||
{{See also|パリ・コミューン}} |
|||
==== コミューンの総括 ==== |
|||
パリ・コミューンはマルクスとエンゲルスの革命理論に大きな影響を与えた。 |
|||
マルクスは5月30日にもインターナショナルからパリ・コミューンに関する声明を出した。この声明を後に公刊したのが{{仮リンク|『フランスの内乱』|en|The Civil War in France}}({{lang-de-short|''Der Bürgerkrieg in Frankreich''}})である。その中でマルクスは「パリ・コミューンこそが真のプロレタリア政府である。収奪者に対する創造階級の闘争の成果であり、ついに発見された政治形態である」と絶賛した<ref name="石浜(1931)269">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.269</ref><ref name="メーリング(1974,3)103">[[#メーリング(1974,3)|メーリング(1974)3巻]] p.103</ref>。 |
|||
一方、その崩壊原因の分析も重要となった。二十年後の1891年、エンゲルスは『フランスの内乱』第三版の序文を執筆し、歴史的総括を試みている。エンゲルスはパリ・コミューンを「労働者と労働者代表からなる政府」として位置づけ、断固たるプロレタリアート的性質を持っていた」と断言し、コミューンが布告された諸政策の先進性を評価した。 |
|||
しかし、「コミューン議員は、多数派―国民衛兵中央委でもまた牛耳っていたあのブランキストと、少数派―[[プルードン]]社会主義学派の門弟からなる、国際労働者協会の会員とに分裂して」おり、マルクスの[[科学的社会主義]]に基づいて政策決定できるものは少なかった。とりわけ、顕著に表れているのが、[[フランス銀行]]に蓄えられた金融資産の差し押さえを実行しなかったことである。エンゲルスは、ヴェルサイユ政府に対して軍事的経済的手段の両面で断固たる措置を取らなかったブランキ派とプルードン派の過失を批判した。 |
|||
また、エンゲルスは工業を再編して労働者の生産組合を組織して、工業生産全体に連携させていくべきであったと語り、組織化された労働ではなく自由な労働を謳うプルードン流の経済運営は死んだことが明らかになったと主張した。同様に、ブランキ派は各地のコミューンの自由な連合を説いていたが、パリ・コミューンに全国的な権力を集中させるべきであった。軍隊、国家警察、官僚政治を打倒して古い国家権力を一掃し、公職の地位を一般投票で任命する任免権を人民に返還して、国家権力が支配者ではなく奉仕者となるよう、公職者の賃金を労働者の賃金と同水準に抑える措置をとることが肝要だと語った。まさにこうした試みが実践されたのが、パリ・コミューンである。 |
|||
エンゲルスは「'''パリ・コミューンを見よ。それこそは、 [[プロレタリアート独裁|プロレタリアートの独裁]]だったのだ'''」と言葉を発して結論とした。プロレタリアは国家の運営に参加し、通常の社会的事務と管理業務と同様に行政活動に加わり、国家の廃止という偉業を果たす歴史の局面に準備しなければならないと訴えた。マルクスとエンゲルスは、'''富裕層だけが利益を享受する旧来の[[ブルジョア民主主義]](ブルジョア独裁)を乗り超え、生産者・労働者が恩恵を受けられる[[大衆民主主義]](プロレタリアート独裁)が導入されなければならず、プロレタリアートの独裁によって大衆の政治参加を拡大しながら人民を訓練していくことが来るべき[[社会主義革命]]の役割だと説いた'''。二人はその後も積極的にコミューンを擁護する見解を発信し続け、革命へと至る歴史的潮流に人民を指導する[[前衛党]]の樹立が急務であると説き続けた。こうしたコミューン擁護活動を通じ、ティエール政府に弾圧された活動家たちは革命運動のネットワークを拠点にマルクスと緊密に連携するようになった。マルクスとエンゲルスが一時亡命を余儀なくされた活動家たちに資金援助を働きかけた結果、娘婿[[ポール・ラファルグ]]や[[ジュール・ゲード]]をはじめ二人の支援を受けた革命家は後に大成して、[[フランス労働党 (POF)|フランス労働党]]の一翼を形成することになった<ref name="カー(1956)307">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.307</ref>。 |
|||
しかし、このときマルクスとエンゲルス、そして新しい労働者政党が目指す革命と社会主義国家の樹立を妨害しようとする偽りの兄弟がいた。革命の理想に対する最大の障害物は[[アナーキズム]]である。 |
|||
==== アナーキズムとの対決 ==== |
|||
{{アナキズム}} |
|||
1871年9月17日から23日、ロンドンにおいて、17名の中央評議会の委員とマルクス、エンゲルスらをはじめとする23人の主席者で臨時会議が開かれた。ロンドン協議会での主たる討議内容は、IWA内部のバクーニン派勢力とアナーキズムの思想―とりわけ、「政治不参加主義」の駆逐であった。労働者政党の組織化を前提とした政治運動の必要性が再度唱えられた<ref name="フォスター(1956)104">フォスター(1956) p.104</ref>。 |
|||
エンゲルスはロンドン協議会で、政治不参加主義がインターナショナル内部に浸透して運動を分裂させ、組織を内部崩壊させようとしていると指摘した。 |
|||
エンゲルスは、[[全ドイツ労働者協会]]の党首{{仮リンク|ヨハン・シュヴァイツァー|de|Johann Baptist von Schweitzer}}が[[ビスマルク]]と提携して労働者を政府の政策に同調させようと試みて労働者運動を分断させてしまっていると告発した。また、「政治不参加主義の結果、9月4日には{{仮リンク|ジュール・ファーヴル|en|Jules Favre}}(国防仮政府の外相)、{{仮リンク|エルンスト・ピカール|en|Ernest Picard}}(国防仮政府の財務相、[[パリ・コミューン]]の弾圧者)その他が政権を横領した。3月18日には、この政治不参加のため、……、革命の強化のために充てなければならない革命後最初の数日を、わざとなにもしないで空費してしまった」ように、革命が勝利を収める機会を無駄にしたことを指摘した。一方、「イギリスでは労働者が国会に出ることはそう簡単ではない。国会議員には歳費が全然出ないし、労働者は自分で働いて生活を立てるほかないからである。だから国会は労働者の手には届かない。ブルジョアジーは、国会議員に手当を出すことを頑なに拒んでいるが、こうすれば労働者階級の代表は出られなくなることを知りぬいている」ため、運動には困難が伴っていた。 |
|||
しかし、エンゲルスは「労働者を国家に送ることをどうでもよいこと思ってはならない」と語って労働者を励ましている。「アメリカでは、最近開かれた労働者の大会が、政治問題に携わること、自分たちの代表として、職業的な政治家ではなく、自分たちと同じ労働者を送り、自分たちの階級の利益の擁護にあたらせることを決議し」、ドイツでは国会議員となった「ベーベルやリープクネヒトのようにこの演壇から発言できるなら、彼らの発言を全世界の人が聞く」のだと述べた。また、「普仏戦争に反対して…闘争を始めたとき、全ドイツが揺さぶられ、[[ビール]]の値段のためにしか革命をやらないような[[ミュンヘン]]でさえ、戦争の終結を求める大示威運動が起こった」ことに触れ、政治運動への参加の意義を説いた<ref name="『インタナショナル』(2010)202-205">{{Harvtxt|[[カール・マルクス|マルクス]],[[不破哲三]]|2010}} pp.202-205</ref>。加えて、エンゲルスはスペイン連合評議会に対して、こうも語っている。 |
|||
{{quotation|「政治問題への絶対的な不参加というのは不可能である。不参加主義の新聞もみな政治に関わっている。問題はただ、どういう仕方で政治に携わるか、どういう政治に携わるか、ということである。 |
|||
それに、我々の場合には、政治不参加というのは不可能である。たいていの国では、労働者党がすでに政党として存在している。政治不参加を説いてこの党をつぶすようなことは、我々のなすべきことではない。実生活の経験や、現存の政府があるいは政治的な、あるいは社会的な目的から労働者に加える政治的抑圧によって、労働者はいやおうなしに政治に携わざるをえなくなっている。労働者に政治不参加を説くことは、労働者をブルジョア政治の抱擁のなかへ押しやることになるだろう。とりわけ今は、プロレタリアートの政治活動を日程にのせたパリ・コミューンの直後であるだけに、政治不参加はまったく不可能である。 |
|||
われわれは階級を廃止したいと思っている。その手段はなにか?プロレタリアートの政治的支配である。この点では誰も異存はないのに、なおかつ、政治に口を出すなという人がいる!不参加主義者はみな革命家を自称している。……。しかし、革命とは政治の最高の行為である。革命を欲するものは、その手段をも欲しなければならない。すなわち、革命を準備し、革命のために労働者を教育する政治活動をも欲しなければならない。それがないかぎり、労働者の闘いの翌日には……たぶらかされてしまうだろう。……。労働者党は、なんらかのブルジョワ政党のしっぽとしてではなく、独自の目標と政策をもつ独立の政党として建設せねばならない。 |
|||
もろもろの政治的自由、集会、結社の権利、出版の自由、こうしたものはわれわれの武器である。……あらゆる政治的行為は現状を承認することを意味する、と言う。しかし、この現状がそれに抗議する手段をわれわれに与えている場合に、その手段を利用としたからといって、現状を承認することにはならないのである。」<ref name="『インタナショナル』(2010)207-210">{{Harvtxt|[[カール・マルクス|マルクス]],[[不破哲三]]|2010}} pp.207-210</ref>}} |
|||
バクーニン主義者はエンゲルスの演説に反抗し、政治運動の推進を擁護するという案件で評決を下さないように抵抗した。マルクスとコミューン戦士たちによる反駁によって、インターナショナルが革命的な政治運動を主導すること、そのために「労働者階級を政党に組織することが不可欠である」ことが確認された。しかし、パリ・コミューンの反乱は全ヨーロッパの保守的なマスコミや世論を震え上がらせており、各メディアから、マルクスたちが黒幕とするインターナショナル陰謀論、マルクス陰謀論、[[ユダヤ陰謀論]]が出回るようになった。 |
|||
こうした中、{{仮リンク|ジョージ・オッジャー|en|George Odger}}らイギリス人メンバーはインターナショナルとの関係をブルジョワ新聞からも自分たちの穏健な同志たちからも糾弾された。ついにオッジャーは1871年6月をもってインターナショナルから脱退してしまう<ref name="カー(1956)310">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.310</ref>。これによりマルクスのイギリス人メンバーに対する求心力は大きく低下した。マルクスの独裁にうんざりしたイギリス人メンバーは自分たちの事柄を処理できるブリテン連合評議会の設置を要求するようになった。自分の指導下から離脱しようという意図だと察知したマルクスは、当初これに反対したものの、もはや阻止できるだけの影響力はなく、最終的には彼らの主張を認めざるを得なかった。マルクスは少しでも自らの敗北を隠すべく、自分が提起者となってブリテン連合評議会を創設させた<ref name="カー(1956)309">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.309</ref>。 |
|||
マルクスの権威が低下していく中、追い打ちをかけるように[[ミハイル・バクーニン|バクーニン]]との闘争が熾烈を極め、いよいよインターナショナルは崩壊へと向かっていく<ref name="カー(1956)333">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.333</ref>。 |
|||
パリ・コミューン崩壊後、IWAに対する逆風は強まっていった。IWAは各国政府からテロ組織として見なされ、会員となった個人・団体は監視の対象となっていく。1871年、フランス政府はIWA加入を犯罪とする法令を発布した。加えて、この法律はコミューンの亡命戦士たちの引き渡しを要求していた。ドイツではベーベルとリープクネヒトが逮捕され、二年の禁固刑を宣告された。このようにマルクス派指導者が逮捕されて指導部を失ったため、IWA内部での対立も高まっていく。各国でも状況は悪化を辿り、アメリカでは全国労働総同盟が勢力を失い、イギリスでは分派が著しい状況に陥っていた<ref name="フォスター(1956)102-103">フォスター(1956) pp.102-103</ref>。 |
|||
バクーニン一派はパリ・コミューン革命に関する独自の見解を提示し、マルクス主義に対抗しようとしていた。すなわち、革命とは自然発生するもので、下層の民衆による蜂起による権力の転覆と廃止が本来の姿であると見なしたのである。パリ・コミューンはマルクスに社会主義国家像の形成を促す一方で、その闘争はアナーキズムの宣伝に活用されたのである。フランスのプルードン主義やブランキ主義が勢力を失うのにしたがってバクーニン主義は勢いを強めていった<ref name="フォスター(1956)103">フォスター(1956) p.103</ref>。バクーニンとその支持者であるスイスの{{仮リンク|ジュラ連合|en|Jura Federation}}に関する報告がなされたほか、選挙でのドイツ社会民主労働者党の勝利が祝された。バクーニン一派の追放が会議の眼目になっていた。これに対して、1871年12月、バクーニンもマルクス派に応酬すべく大会の即時招集を要求し、マルクスが牛耳る中央評議会の専制を非難する『ソンヴィリエ通達』という文書をあらゆる国の支部会に送った<ref name="フォスター(1956)104-105">フォスター(1956) pp.104-105</ref>。バクーニンは自由な政治組織による緩い連合を提案し、マルクスはその意図を疑い権威と規律を主張したが、この両雄の組織論はIWA大会{{仮リンク|ハーグ大会|en|Hague Congress (1872)}}で討議されることとなった。 |
|||
1872年9月2日、「IWAにとって生死の問題と化した」{{仮リンク|ハーグ大会|en|Hague Congress (1872)}}が開催された。さっそく大会では中央評議会に対する信任をめぐって対立し、40名のマルクス派代議員とその他24名の反対派に分裂した。イギリス代表はバクーニンの思想に反対していたが、マルクスの理論や中央統制とも相容れなかったため、中央評議会に対する信任に反対票を投じた<ref name="フォスター(1956)105">フォスター(1956) p.105</ref>。 |
|||
[[file:Marx_and_Engels_at_Hague_Congress.jpg|thumb|right|300px|1872年。マルクスとともに{{仮リンク|ハーグ大会|en|Hague Congress (1872)}}に臨むエンゲルス。]] |
|||
続いて、政治権力の問題についてはマルクス派29票対バクーニン派5票、棄権9票で、政治権力の破壊を主張するバクーニン派に対して政治権力の奪取を提唱するマルクス派の勝利に終わった<ref name="フォスター(1956)107">フォスター(1956) p.107</ref>。かくして、第7条付則として『規約』に「政党結成」と「政治権力奪取」が明記され、平和的な手段もありうるとして議会進出に意欲を示す文言が盛り込まれた<ref>「ハーグ大会についての演説」1872年9月 マルクス・エンゲルス全集(18) 158ページ、不破哲三『科学的社会主義における民主主義の探求』40ページ</ref>。さらに、これに終わらずマルクスは『インターナショナルのいわゆる分裂』という報告書において中央評議会に反対して無政府主義を掲げたバクーニンとその一派を除名するよう大会に対して勧告した。マルクスの動議を受けて、[[バクーニン]]、{{仮リンク|ジェーム・ギヨーム|en|James Guillaume}}、{{仮リンク|シュウィッツギューベル|en|Adhémar Schwitzguébel}}、ブーケ、マロン、マルシャンらがIWAから追放された<ref name="フォスター(1956)109">フォスター(1956) p.109</ref>。9月6日に中央評議会をロンドンからニューヨークに移転するという決議を採択した。同決議はIWAの運命を未来に切り開くことが期待されたが、皮肉にもIWAを衰弱させるものとなった<ref name="フォスター(1956)107-108">フォスター(1956) pp.107-108</ref>。 |
|||
ハーグ大会終了後、[[アムステルダム]]で公開集会が開催された。マルクスは人々を前に演説をおこない、「労働者階級は、政治の分野でも社会の分野でも、滅びつつある旧社会を攻撃する必要がある、と宣言した」と表明している<ref name="フォスター(1956)110">フォスター(1956) p.110</ref>。また、続けてこうも語った。 |
|||
{{quotation|「労働者は、新しい労働の組織を打ち立てるために、やがては'''政治権力を握らなければならない'''。労働者は、古い制度を支える古い政治を覆さなければならない。(ただし)それぞれの国の制度や習慣や伝統に特別な考慮をはらわなければならない。また、われわれはアメリカやイギリスのように、労働者が平和的手段でその目的を達成できると思われる国があることを、否定しない。……。が、たとえそうだとしても、たいていのヨーロッパ大陸諸国では、実力が革命の梃子とならねばならなぬだろうということを、認識すべきである。()内筆者補足。」<ref name="フォスター(1956)110">フォスター(1956) p.110</ref>}} |
|||
この演説は階級闘争の戦術面での相違や社会主義運動の多様性を示唆するものであった。各国市民の[[民主主義|政治的自由度]]によって「[[改革]]」と「[[革命]]」の適宜性が左右され、労働者の階級闘争の方向性も、労働者党の戦術や政治的な役割も定まっていくということを指摘した。 |
|||
==== 第一インターナショナルの崩壊 ==== |
|||
[[ファイル:Bakunin Nadar.jpg|thumb|200px|right|ミハイル・バクーニン]] |
|||
その後、最初の国際的政治団体にして労働者組織であるIWAはアナーキストによる執拗な解散運動に直面する。 |
|||
バクーニン派は、中央評議会の「政治活動への積極参加」条項に猛反発して独自見解を提唱し、分裂運動を画策したため、ハーグ大会で除名処分を受けたが、彼らは当然処分を承服したりはしなかった。そこで、彼らはIWA本部の[[ニューヨーク]]移転を機に、中央決定による組織運営を否認し、連絡と統計に基づく自由な連合体を作ろうと試み、独自のインターナショナル組織を作り始める。1872年9月15日バクーニン派は15名ほどの代表者がIWAの名を流用して[[スイス]]の{{仮リンク|サン・ティミエ|en|Saint-Imier}}で大会を開催した。そして「社会民主同盟」から継承した「連合」の原理と政治活動の拒絶が新組織の綱領として掲げて新組織を樹立する。ここではこのとき発足したバクーニン派の新組織を{{仮リンク|アナーキスト・インターナショナル|en|Anarchist St. Imier International}}と呼称する。この新組織は加盟団体を募ったが、参加を表明した連合は[[ベルギー]]と[[オランダ]]とイギリスの一部支部に留まった。大半の地方支部は元のIWAに残留を表明した<ref name="フォスター(1956)112-113">フォスター(1956) pp.112-113</ref>。 |
|||
無政府主義は社会主義の双子の兄弟と言える。アナーキズムは、革命の自然発生性を強調し、組織の中央統制に反対し、集団よりも個人の自由を価値として、暴力革命による急激な社会変革を求め、緩やかな「連合」による社会の統合を目指していた。その理想像はマルクスが目指した共産主義社会と何一つ変わるところはない。 |
|||
しかし、理想を共有していたものの無政府主義と社会主義には方法論において決定的な違いがあった。マルクスの社会主義は階級闘争が長引くこと、革命の機会は容易には訪れないという現実感覚、大衆の支持を背景に権力を革命あるいは選挙で政権を掌握して「[[プロレタリアート独裁]]」を確立すること、議席を得て社会立法を進め階級格差を是正し、工業および農業、そして商業の均衡発展の道を模索するという国家ヴィジョンがあった。こうした段階を追って共産主義の理念を実現させるという現実的な立場をとっていた。 |
|||
バクーニンらの無政府主義は反権力思想と自己完結型の共同体思想がもつ魅力によって、南欧の下層労働者やロシア、南米の貧農層を取り込んでいった<ref name="フォスター(1956)117-118">フォスター(1956) pp.117-118</ref>。 |
|||
19世紀当時は重税、貧困、疫病、言論統制、官憲の取り締まり、医療・福祉・教育の欠如といった苦痛と圧政が是とされた反動的な専制国家の時代であった。とりわけ、工業化は遅れた諸地域では無政府主義とその暴力的方法論が受け入れられていった。例外的に農業国でもあり個人を重んじ自由を尊重するアメリカやフランスでも支持を集めた。一方、先発工業国のドイツ、これに遅れてフランスが、そして、大不況期を経験したイギリスなど労働運動の歴史的中核国ではマルクス主義の影響力が次第に強まっていった。「アナーキスト・インターナショナル」は数度の年次大会を開催し、スペインの革命やイタリアで多くの暴動を画策したが失敗に終わる<ref name="フォスター(1956)114-115">フォスター(1956) pp.114-115</ref>。また、バクーニンが世を去ってその後の発展の糸口と反乱工作の機会を失ってしまう。19世紀末にイギリス、フランス、ドイツ、アメリカをはじめ各国が社会立法に力を注いで圧政を捨てていくにつれて、無政府主義はしだいに個人革命家のテロリズムの世界へと追いやられて衰退していく<ref name="フォスター(1956)119-120">フォスター(1956) pp.119-120</ref>。現実路線に即して、内部統制が強い組織を持った社会主義党を作り上げ、国家権力の掌握に力を注ぐ道を選んだことにより、マルクス主義は時代の選別に耐えて生き残ったのである。 |
|||
[[image:Friedrich Adolph Sorge.gif|thumb|right|200px|{{仮リンク|フリードリヒ・ゾルゲ|en|Friedrich Adolf Sorge}}。IWA崩壊期の中央評議会書記長である]] |
|||
一方、アメリカに目を転じるとここでも新しい局面があった。要となる人物はIWAのアメリカ支部書記長{{仮リンク|フリードリヒ・ゾルゲ|en|Friedrich Adolf Sorge}}である<ref name="フォスター(1956)122">フォスター(1956) p.122</ref>。 |
|||
IWAのマルクス派指導者は社会主義の分派勢力とのせめぎあいの中で巻き返しを図ろうと[[フィラデルフィア]]で大会を開催した。そこではアメリカ支部を中央評議会の直轄とする方針を定めて、中央評議会の権威で部内の刷新を図ることが決まった。しかし、無政府主義者の排斥とイギリス支部の脱落によって生じたIWAの空洞化によって、この決定はIWAを欧州の労働者協会からアメリカ合衆国の労働者協会へと変質させるものにつながった。また、無政府主義やラッサール主義政党の影響力を払拭するのは容易ではなく、アメリカにおける各支部の内部分裂がさらに激しくなっていった。1864年から65年の内紛の結果、ニューヨークの二つの支部が排斥されボルテなど主要メンバーが追放された。こうした情勢の中、内紛に疲れたゾルゲが書記長を辞任、すでに中核を失いって混乱をきたしたIWAは組織の命脈を保つことができなくなっていた。世界的にもIWAはもはや求心力を急速に失いつつあったのである。各国で社会主義政党の樹立と独自の政治運動が活発化し、国際的連帯を協議する局面ではなくなっていた<ref name="フォスター(1956)128-129">フォスター(1956) pp.128-129</ref>。 |
|||
1876年、中央評議会は時勢の困難さを鑑みて解散を内定したうえで、フィラデルフィアで最期の年次大会を開く決定をする。[[ドイツ社会主義労働者党]]の代表とアメリカ支部評議会の10名の委員会が解散手続きをすすめた。7月15日、「国際労働者協会中央評議会は解散する」との決議のもと、IWAは正式に解散する<ref name="フォスター(1956)130-131">フォスター(1956) p.130-131</ref>。 |
|||
{{Main|[[:en:International Workingmen's Association in America]]}} |
|||
=== 晩年の活動 === |
|||
==== ドイツ社会主義運動の再建 ==== |
|||
{{節スタブ}} |
|||
[[File:August Bebel 2.jpg|right|200px|thumb|若き日の[[アウグスト・ベーベル]]]] |
|||
[[第一インターナショナル]]の誕生と崩壊の後、社会主義は新たな発展期に入っていった。 |
|||
ドイツでは1867年[[ヴィルヘルム・リープクネヒト]]、[[アウグスト・ベーベル]]が[[ザクセン人民党]]を組織し、1869年8月にはドイツ統一の加速と歩調を合わせるかたちでリッティングハウゼン、{{仮リンク|ベルンヘルト・ベッカー|de|Bernhard Becker (Schriftsteller)}}、ヘスといった人物らとともに{{仮リンク|アイゼナハ綱領|de|Eisenacher Programm}}を採択、{{仮リンク|社会民主労働者党|de|Sozialdemokratische Arbeiterpartei (Deutschland)}}({{lang-de-short|Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP)}} 。通称「アイゼナハ派」と呼ばれる。後の'''[[ドイツ社会民主党]]'''の母体となる)を組織した。ラッサール主義に対峙する本格的なマルクス派の社会主義政党が発足したのである<ref name="フォスター(1956)80-81">フォスター(1956) pp.80-81</ref>。 |
|||
この時期の各国政府は労働者が選挙権を獲得していた。[[北ドイツ連邦]]では{{仮リンク|北ドイツ連邦議会|label=連邦議会|de|Reichstag (Norddeutscher Bund)}}が設置され、25歳以上で公的支援を受けていない男性有権者からなる成人男子選挙権が導入され、{{仮リンク|1867年8月北ドイツ連邦議会総選挙|label=1867年8月の連邦議会総選挙|de|Reichstagswahl August 1867}}が実施された。そのため、北ドイツ連邦では新たな有権者の票数確保の必要が生じ、政府が熱心に社会政策に取り組んだ。その一つが労働者の住宅問題の解決である。 |
|||
エンゲルスは、ミュールベルガーが住宅問題を論じたことを受けて反論記事「住宅問題」を、ドイツ社会民主労働党の機関紙『{{仮リンク|フォルクスシュタット|de|Der Volksstaat}}』({{lang-de-short|''Der Volksstaat''}})に掲載した。労働者の住宅問題を政府が解決策を提示して、社会主義者もこれに協力して、共に住宅問題を解決させよよいう見解であったが、エンゲルスは政府の社会改良政策への迎合に反対の立場を採った。労働者階級の住宅事情が良くないのは住宅がないからではなく、快適な住宅に居住できないような階級的地位の低さに起因することであり、住宅を安価に低金利で販売したとしても抜本的な解決策には至らない。対症療法として効果が出れば一時的に労働者の懐柔につながるが、増加し続ける労働者の旺盛な住宅需要を満たす必要が依然として残され、一時しのぎの政策を採用しても住宅問題がつねに課題となっていくことに変化はないと語った。住宅問題解決に政府が積極的な姿勢を見せても、労働者の階級的抑圧状態が解消されることはなく、[[社会改良主義]]的な政策は労働者の目暗ましにしかなっていないと指摘した。 |
|||
[[ファイル:Wilhelm Liebknecht.jpg|thumb|200px|[[ヴィルヘルム・リープクネヒト]]]] |
|||
一方、ドイツ社会主義運動の大きな転機が生じた。その転機はドイツの二つの労働者党(アイゼナハ派とラッサール派)の1875年の合同に求められる。 |
|||
両派の合同は1871年の[[普仏戦争]]の勝利を受けて[[ドイツ統一]]が実現したということが契機となっている。ラッサール派は[[プロイセン王国]]を基軸に労働運動を展開するのが有利であるとする政治戦術を採用していた。一方、アイゼナハ派はマルクスの指導によって[[反戦]]と[[国際主義]]の立場をとり、反プロイセン王国の立場に立って[[オーストリア]]を含む全ドイツ語圏の労働者の結集によって革命を起こして共和制の統一民族国家(大ドイツ民主共和国)を実現させるという構想を持っていた。ドイツの統一によって党派的分立の根拠が一つ解消されたため、ようやく両派は合同したのである。 |
|||
かくして、[[アウグスト・ベーベル]]、[[ウィルヘルム・リープクネヒト]]が率いる{{仮リンク|ドイツ社会民主労働党|de|Sozialdemokratische Arbeiterpartei (Deutschland)}}と[[フェルディナント・ラッサール]]が設立してドイツ内の労働者党の最大会派となっていた[[全ドイツ労働者協会]]が合同を果たす。1875年、[[ザクセン=コーブルク=ゴータ公国]]の[[ゴータ]]にて統一綱領「{{仮リンク|ゴータ綱領|de|Gothaer Programm}}」を採択して[[ドイツ社会主義労働者党]]({{lang|de|Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands}}, {{lang|de|SAPD}})が結成された<ref name="ハント(2016)339">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.339</ref>。 |
|||
だが、マルクスとエンゲルスは、ヴィルヘルム・リープクネヒトとアウグスト・ベーベルの政治的妥協を痛切に批判していく。[[帝国主義]]、[[軍国主義]]の[[ドイツ帝国]]をいかに近代化させるかという問題が依然として残されていたのである。成人男子選挙制度はあったが、復古的な三級選挙による議会制度を革新して、民主国家の道筋を開いていくことが課題であった。マルクスは『[[ゴータ綱領批判]]({{lang-de|''Kritik des Gothaer Programms''}})』を執筆して、賃金が上昇すると経済停滞を招いて労働者の生活水準が低下するという「賃金鉄則」なるラッサール派の誤謬と共存することはできないと主張した。また、政治的・社会的不平等の是正といった目標はブルジョワ政党の理念であって、革命的プロレタリアートによる社会主義運動の路線ではないと指摘した。マルクスは、革命によって資本主義を打倒して国家を廃止するという理念を提示できないラッサール主義との合流をプロレタリアートに対する背信行為だと厳しく糾弾した<ref name="ハント(2016)336">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.336</ref>。 |
|||
* 『ゴータ綱領批判』 |
|||
マルクスは党幹部に対してドイツ帝国下でのブルジョア国家権力との消極的共存に甘んじるのではなく、[[暴力革命]]によって全権力を帝国政府から奪取して[[プロレタリアート独裁]]を確立し、[[社会主義国|社会主義国家]]の建設を目指すように言明した。 |
|||
エンゲルスもベーベルに次のように警告した。 |
|||
{{quotation|「マルクスと私はそのような根拠による新党の結成は認めることはできないし、それに対してどんな態度を―公的にも私的にも―とるべきか、きわめて真剣に検討しなければならないであろう。国外ではわれわれが、ドイツ社会民主労働党のありとあらゆる声明と活動に責任をもたされていることを忘れないでくれ。」<ref name="ハント(2016)340">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.340</ref>}} |
|||
マルクスとエンゲルスの怒りの矛先は、党の運営や指導に関して理論創始者に事前に相談しなかったリープクネヒトに集中していった。だが、内輪の争いに長く拘ってはいられない状況となっていく。 |
|||
==== 社会主義者鎮圧法という逆風 ==== |
|||
[[File:Punch 1878 - Socialist jack in the box.png|180px|thumb|right|1878年[[パンチ (雑誌)|『パンチ』誌]]の風刺画。おもちゃの箱の中から飛び出そうとする社会主義者を押し戻そうとするビスマルク]] |
|||
1866年に社会民主労働党が結成されていたちょうどその頃、ドイツでは資本主義の成長とプロレタリアート階級の形成が本格化しはじめ、党は得票数を順調に伸ばしていた。{{仮リンク|1871年のドイツ帝国議会選挙|de|Reichstagswahl 1871}}で得票数12万4千票から{{仮リンク|1877年のドイツ帝国議会選挙|de|Reichstagswahl 1877}}では49万3千票を獲得、票数を5倍近く伸ばすことに成功した。 |
|||
[[ドイツ帝国]][[宰相]][[オットー・フォン・ビスマルク|ビスマルク]]は統一した労働者党に強い警戒感を抱くようになる。 |
|||
二人の[[テロリスト]]、1878年5月11日に{{仮リンク|マックス・ヘーデル|de|Max Hödel}}、6月2日に{{仮リンク|カール・ノービリング|de|Karl Nobiling}}によって、二度にわたり引き起こされた[[ドイツ皇帝]][[ヴィルヘルム1世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム1世]]の暗殺未遂事件は社会主義運動の鎮圧を図る絶好の口実となった。10月19日、ビスマルクの主導で悪名高い[[社会主義者鎮圧法]]が制定された。1890年の撤廃に至るまで同法により、「社会民主主義、社会主義、あるいは共産主義の活動によって既存の政治・社会秩序を覆そうとする」あらゆる組織が非合法とされた。社会主義者は無所属ならば自由に立候補できたが、社会主義を謳うあらゆる集会や出版が禁止され、SAPDに限らず労働組合が非合法とされ、党員の職場からの追放が義務付けられるなど、SAPDは激しい弾圧の対象となった。[[ベルリン]]、[[ハンブルク]]、[[ライプチヒ]]、[[フランクフルト]]といった主要都市では戒厳令が敷かれ、警察によってSAPD党員や支持者が次々と検挙された<ref name="ハント(2016)340-341">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.340-341</ref><ref name="土屋(1995)148">{{Harvtxt|土屋保男|1995}} p.148</ref>。 |
|||
こうした厳しい弾圧を前に脱落者も生じた。ハンブルクではSAPD幹部が取締り前に党の解散を宣言し、指導部と印刷所を残そうと考えるものが現れた。労働者の政治的権利を犠牲にして国家権力に恭順を示し、取締りを回避しようとする右翼的な日和見主義の風潮が広まり、革命を断念して闘争を放棄する動きが広がった。多くの都市で党組織が解党を決議したため、SAPDは存亡の危機に瀕した<ref name="土屋(1995)148"/>。 |
|||
[[File:Bernstein Eduard 1895.jpg|thumb|200px|[[エドゥアルト・ベルンシュタイン]](1895年)]] |
|||
こうした動きは理論面での逸脱につながっていき、ドイツ[[修正主義]]の土壌となっていく。 |
|||
スイスの[[チューリッヒ]]に亡命したSAPDの後援者{{仮リンク|カール・ヘーヒベルク|de|Karl Höchberg}}とその秘書[[エドゥアルト・ベルンシュタイン]]、シュラムの三名は、三星の署名を用いて『社会科学・社会政策年報』に「ドイツにおける社会主義運動の回顧」という論文を掲載し、マルクス主義の革命理論を公然と批判し始めたのである。修正主義者は[[階級闘争]]を否定して[[中流階級|中産階級]]の重視、[[プロレタリア独裁]]と[[暴力革命]]に反対して[[間接民主主義|議会制民主主義]]の枠内で[[福祉]]政策の推進を説いた点が挙げられる<ref name="土屋(1995)149">{{Harvtxt|土屋保男|1995}} p.149</ref>。 |
|||
エンゲルスは修正主義が党の結束を分断し、闘争の継続を困難にする理論的逸脱と見なして生涯をかけて糾弾を続ける。一方、迫害を受けた社会主義者にエンゲルスは資金援助をおこない、投獄された活動家に同情を示した。その一方で、合同後に妥協的となっていたSAPDが次第に左傾化していくことを歓迎し、「ビスマルク氏は七年の間、まるでこちらから礼金を支払っているかのように、われわれのために働いてくれ、いまや社会主義の到来を早めるための申し出を控えることができないようだ」と語っている<ref name="ハント(2016)341">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.341</ref>。 |
|||
社会主義者に対して強まっていく弾圧の中で実施された[[帝国議会 (ドイツ帝国)|ドイツ帝国議会]]の{{仮リンク|1881年のドイツ帝国議会選挙|de|Reichstagswahl 1881}}の結果、SAPDは三議席増やして12議席を獲得したという報は、エンゲルスにして「プロレタリアートがこれほど見事な振る舞いを見せたことはない」と言わしめ、彼を大いに喜ばせた。さらに、三年後の{{仮リンク|1884年のドイツ帝国議会選挙|de|Reichstagswahl 1884}}では議席を倍増させて24議席を獲得する快挙を成し遂げ、ついに、ドイツの労働者階級がイギリスやフランスからプロレタリアート運動の政治的理論的な主導権を取り戻す段階に到達したのである<ref name="ハント(2016)341"/>。しかし、エンゲルスは、次第に勢力を増して拡大していく党内部に日和見主義が入り込まないかを危惧し、党幹部の声明を入念に調べるなど監視の目を強めていった。こうした中で浮上した危険人物がオイゲン・デューリングである。 |
|||
==== 『反デューリング論』の執筆 ==== |
|||
エンゲルスは順調なロンドン生活の一方で、ドイツの[[社会主義]]運動の今後については憂慮を抱いていた。 |
|||
[[ファイル:Engels.jpg|thumb|エンゲルス(1877年)]] |
|||
ドイツの二つの[[労働者党]](アイゼナハ派とラッサール派)の1875年の合同が実現して社会主義運動の発展が続く一方で、党派的な対立が深刻化していたのである。とりわけ、党派的な影響を広げつつあったのが、ベルリン大学の視覚不自由者の私講師であった[[オイゲン・デューリング]]の学説だった。デューリングは[[カール・マルクス]]の理論を一つの仮想敵として位置づけ、暴力革命や中央集権制と計画経済の導入を否定して、[[プルードン]]や[[フェルディナント・ラッサール|ラッサール]]に似た独自の社会主義思想を作り出そうとしていた<ref name="ハント(2016)380-381">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.380-381</ref>。 |
|||
[[エドゥアルト・ベルンシュタイン|ベルンシュタイン]]もデューリングの学説に影響を受け、ベーベルらにデューリングの著作を送り、ベーベルもこれに呼応してデューリングを支持することを『{{仮リンク|フォルクスシュタット|de|Der Volksstaat}}』({{lang-de-short|''Der Volksstaat''}})誌上で表明した。マルクス主義に忠実なリープクネヒトは危機感を強めてデューリング批判の必要性をエンゲルスに説き、論文を執筆するように要請した。エンゲルスも「彼のまわりに一つの派閥、すなわち将来別個の党になる中核を公然とつくりはじめた」ことに懸念を感じたため、デューリングを批判する論文を機関紙『{{仮リンク|フォルウェルツ|de|Vorwärts (Deutschland)}}』({{lang-de-short|''Vorwärts''}})で連載した。デューリングは多方面にわたって精力的に論説を展開させていたため、エンゲルスはデューリング批判を全方面に拡大させていく必要に迫られていった<ref name="『反デューリング論〈上〉』(1980)314-316">『反デューリング論〈上〉』(1980) pp.314-316</ref>。 |
|||
その結果、[[ウラジーミル・レーニン]]が語るところの「哲学、自然科学および社会科学の諸領域に属する最大の諸問題が究明され」、「驚くべき内容豊富なまた教えるところの多い書物」が完成した<ref name="『反デューリング論〈上〉』(1980)323">『反デューリング論〈上〉』(1980) p.323</ref>。これが1878年に出版されて'''『[[反デューリング論]]』(正式名は『オイゲン・デューリング氏の科学の変革』、{{lang-de|''Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft''}})'''となった<ref name="ハント(2016)382">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.382</ref>。 |
|||
『反デューリング論』の中心軸は[[弁証法的唯物論]]であり、[[自然科学]]から[[社会科学]]・[[人文科学]]に至る広範な科学領域における[[弁証法]]の適用の試みとなっている<ref name="ハント(2016)382"/>。 |
|||
[[ウラジーミル・レーニン]]は、本書の位置づけを「最後まで一貫した唯物論か、それとも哲学的観念論のうそと混乱か、どちらかである。―これが『反デューリング論』の各パラグラフに与えられた問題提起である」と語っている。唯物弁証法が自然科学から社会科学に至る全領域にまたがる包括的な理論であることを立証することがその目的とされた。本書の内容は概ね次のとおりである。 |
|||
序論において[[ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル|ヘーゲル]]の弁証法が総論として整理され、[[観念論]]の克服と[[唯物論]]への転換の重要性が指摘されている<ref name="『反デューリング論〈上〉』(1980)323-324">『反デューリング論〈上〉』(1980) p.323-324</ref>。序論の後半部分はデューリングの野心と活動への敵意が表明され、彼の学説に対する宣戦布告となっている。 |
|||
次いで、エンゲルスは、第一編では[[自然科学]]分野への関心に留まらず、[[法]]や[[道徳]]、[[真理]]、[[平等]]や[[自由]]といった精神哲学の分野に踏み込んだ見解を提示していった。第五、第六章において弁証法が宇宙の秩序とどう関係するかが、第七、第八章で有機体、生体の働きに弁証法がどのように現れているか、デューリングの科学についての理解が如何に不十分なものであるかが論じられている。 |
|||
後半は道徳ならびに法哲学が論じられた。エンゲルスはデューリングの未熟な世界観を紹介しながら、道徳や真理は時代とともに歴史的に形成されるもので、固定的な万世不易の代物ではないと論じた。 |
|||
最後に弁証法理論が紹介されている。ヘーゲルの弁証法が総論として整理され、弁証法の核心部分が提示されている。物質や生物の世界で弁証法がどのように展開しているかを例示しながら、弁証法が1)「量から質への転化、ないしその逆の転化」、2)「対立物の相互浸透(統一)」、3)「否定の否定」の三つの構成要素から成り立っていることを明らかにしたのである<ref name="ハント(2016)383">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.383</ref>。弁証法と自然科学の関係性は『{{仮リンク|自然の弁証法|de|Dialektik der Natur}}』でさらに深く論じられていく予定であったが、エンゲルスがマルクス死後『資本論』の続編刊行の任に集中していたため、結局遺稿に終わった。エンゲルスは、自然科学分野への関心に留まらず、社会科学分野についての理論的考察を提示していった。 |
|||
第二編では[[社会科学]]の領域に踏み込み[[経済学]]を中心に、デューリングが重視した「暴力」や「経済」という切り口から人類社会における[[政治]]、[[階級]]、[[階級国家|国家]]、[[奴隷制]]、[[軍国主義]]が次々と論じられていく。私有制の発達から奴隷制や資本主義的階級制度の起源が論じられ、暴力による原初的秩序の形成というデューリングの見解が批判されていく。エンゲルスは、人類史における抑圧は経済システムの中核部分に存在する所有形態に起因するものであり、経済要因によって政治的支配の形態が変動していくという[[唯物史観]]の理論を紹介した。また、後半部分では[[マルクス主義]]の骨格部分に当たる[[剰余価値]]論の紹介に充てられている<ref name="『反デューリング論〈上〉』(1980)324">『反デューリング論〈上〉』(1980) p.324</ref>。 |
|||
最後に、第三編では社会主義思想の登場と発展を歴史的理論的な側面から概説がなされている。[[アンリ・ド・サン=シモン|サン・シモン]]、[[シャルル・フーリエ]]、[[ロバート・オウエン]]を取り上げ、思想の革新性と問題点を整理し、これらを[[空想社会主義]]として位置づけた。一方、[[産業革命]]の本格化に伴う[[資本主義]]の発達が進行すると、時代状況を反映する新しい社会主義の登場が現実になっていく。マルクスは[[ヘーゲル主義]]から弁証法を批判的に取り入れ、[[唯物論]]と結合させることにより、唯物弁証法に基づく歴史理論―[[史的唯物論]]を確立した。エンゲルスは、マルクスの理論的業績により経済学的アプローチから資本主義の盛衰と社会主義の到来の必然性を論じた[[科学的社会主義]]が確立を見たことを明示した。 |
|||
{{main|反デューリング論|弁証法的唯物論}} |
|||
==== 『空想から科学へ』 ==== |
|||
エンゲルスは、上述の歴史観を整理して「社会主義とはなにか?」という大衆の問題関心に応える章を追加した。『反デューリング論』はドイツ語だけであったのと、マルクスの娘婿で「フランス下院議員である[[ポール・ラファルグ]]の要請によって、私はこの本の3つの章をパンフレットにまとめ、それをラファルグが翻訳して、1880年に『空想的社会主義と科学的社会主義』という表題で出版した」。これが『[[空想から科学へ]]』というタイトルで知られている著作である<ref name="『反デューリング論〈上〉』(1980)19">『反デューリング論〈上〉』(1980) p.19</ref>。 |
|||
{{main|空想から科学へ}} |
|||
==== 『自然の弁証法』 ==== |
|||
エンゲルスは、1870年代から80年代にかけて、マルクスの手で完成を見た[[史的唯物論]]の普遍性を社会から自然の領域に拡張することを試みた。政治経済と並んで自然科学についても学び、哲学的な唯物論の立場から自然の弁証法の解明と論理的把握を試みた。1883年にエンゲルスの書き残した『{{仮リンク|自然の弁証法|de|Dialektik der Natur}}』に関する論考は、最新の自然科学が常に今日でも直面する哲学的危機に対して、多くの重要な示唆を与えている。同書で一章を構成した「{{仮リンク|猿が人間になるについての労働の役割|en|The Part Played by Labour in the Transition from Ape to Man}}」 (1876年)も注目に値する。 |
|||
==== ロシア革命の可能性 ==== |
|||
=== マルクスの死後 === |
=== マルクスの死後 === |
||
[[ファイル:Friedrich Engels (1891).jpg|thumb|晩年のエンゲルス(1891年)]] |
|||
[[1883年]]3月14日にマルクスが死去、葬儀は家族とエンゲルスら友人で計11人で行なわれた。このときのエンゲルスの弔辞は「カール・マルクスの葬儀」として残されている。 |
|||
エンゲルスの最晩年の到達は、『[[家族・私有財産・国家の起源]]』({{lang-de|''Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats''}})、『[[フォイエルバッハ論]](ルートヴィヒ・フォイエルバッハとドイツ古典哲学の終結)』({{lang-de|''Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie''}})、『フランスにおける階級闘争 1895年版序文』「エルフルト綱領草案批判」ほか多くの著述と、マルクスの死後、多くの人物に対して語られたエンゲルスの書簡の中の言葉に表現されている。 |
|||
マルクスの死後、エンゲルスは、『[[資本論]]』に関するマルクスの遺稿の編集、それまでのマルクスとエンゲルス自身の著作の諸言語への翻訳に尽力した。当時の諸情勢と全世界の労働運動における自らの位置とを考慮し、エンゲルスは的確にもマルクスの主著『資本論』の完成をマルクス亡き後の自らの最重要課題と位置付けた。 |
|||
それらの中でエンゲルスは、自分たちの大局的な展望と行動・運動の正しさを正当にも主張すると共に、自分たちの置かれた情勢の諸事情から不可避的に生じたそれぞれの局面での誤りや限定的な正当性について率直に述べている。そのような振り返りも、自分たちが作り上げてきた世界史的運動の後世の継承者たちへの思いやりをもって語られている。 |
|||
実際、マルクスの主著『資本論』の第2巻および第3巻の刊行は、エンゲルスの知力と実務力なしには為しえなかった。遺稿は膨大な量にのぼり(一説では数[[立方メートル|m<sup>3</sup>]]にのぼったともいわれる)、その筆跡は解読が難しいもので、しかもその内容は著作としての完全な筋道をなしていない部分が多かった。内容の難しさのみならず、原稿が未完成であったことも編集を困難にした。エンゲルスは、これらマルクスの遺稿の編集を、晩年の視力の衰えと闘い、全世界の労働運動の助言者としての激務の合間を縫いながら進めた。長く困難な数年にわたる編集作業の末、『資本論』第2巻は[[1885年]]に、第3巻は[[1894年]]に刊行、マルクスの「遺産」を世に送り出した。 |
|||
==== マルクスの死 ==== |
|||
エンゲルスは単なる『資本論』の編集者、マルクスの遺稿の整理執行人ではなかった。編集の最中に現れるマルクスの理論、殊に『資本論』に対する剽窃、中傷、誤解に対しては論陣を張った。『資本論』第2巻、第3巻のエンゲルスによる序文に、資本主義論の最前線でマルクスの理論の擁護に奮闘するエンゲルスの姿を垣間見ることができる。その中で、自分が構想を温めていたいくつかの著作(例えば、「自然の弁証法」)についてはその著述を諦めている。 |
|||
[[File:Lizzie Burns c1865.jpg|thumb|200px|エンゲルスの晩年期の伴侶(内縁の妻)[[リディア・バーンズ]]]] |
|||
エンゲルスの幸せはリジーの病状の悪化に伴って影が差すようになっていった。 |
|||
1870年代末、リジーは慢性的な[[喘息]]に加えて、[[膀胱]]の[[悪性腫瘍]]に冒されていた。エンゲルスはリジーを手厚く看病したほか、懸命に家事をこなしてリジーが安らかに最期を迎えられるように勤めた。1878年9月11日の晩、リジーは死に瀕する状態となっていた。この日エンゲルスは意を決してリジーへの愛を果たそうと大胆な事をしている。近所のセントマークス教会まで駆け出してギャロウェイ牧師を呼んできたのである。エンゲルスはベッドに横たわるリジーと[[英国国教会]]の儀式に則り、正式な夫婦として[[結婚]]の証を得ることになった。元来、エンゲルスは[[無神論]]者であり、結婚をブルジョワの偽善的慣行と見なしてきた。しかし、最期の瞬間にリジーが幸せであることを願い、結婚の儀式によって夫婦であることの承認を受け、二人で互いの愛を確認したのである<ref name="ハント(2016)348-349">{{Harvtxt|ハント|2016}} pp.348-349</ref>。 |
|||
まもなく、エンゲルスが心から愛する妻リディア・エンゲルスは息を引き取った。彼女はロンドン北西部のローマ・[[カトリック]]教会の{{仮リンク|セント・メアリー墓地|en|St Mary's Catholic Cemetery, Kensal Green}}に埋葬された。エンゲルスはリジー死去の知らせをマルクスのみならず友人たちに発信した。マルクスも今度は丁重に返事を送り、弔意を示している<ref name="ハント(2016)349">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.349</ref>。 |
|||
リジーの死以降、エンゲルスは身近な人を次々と失う悲しみの時期と持ち前の一層の力強さを発揮していく時代に踏み出していく。 |
|||
[[File:Marx old.jpg|200px|thumb|1882年のカール・マルクス]] |
|||
1880年代、60歳代に入ったマルクスとエンゲルスたちは最晩年に入りつつあった。とりわけ、マルクス夫妻の健康状態は厳しい状況になっていった。 |
|||
1881年の夏、マルクスの妻[[イェニー・マルクス]]は[[肝臓癌]]を患い、臨終の床にあった。だが、マルクスも[[腎臓]][[肝臓]]の障害に苦しみ、肋膜炎を抱えて病床にあったのである。12月2日、イエニーがこの世を去った時マルクスの容態も悪く、妻の葬儀に出席することもできなかった<ref name="ハント(2016)356">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.356</ref>。 |
|||
これ以降、マルクスは『[[資本論]]』の続編の刊行を継続できないことを悟り、研究から離れて身体の回復のために保養地での静養生活に入ることとなる。肝臓病の治療のために[[チェコ]]の[[カルロヴィ・ヴァリ]]といった[[温泉]]地を訪ねたほか、1882年2月から[[気管支炎]]治療のために温暖で乾燥した気候の土地を求めて、北アフリカの[[フランス植民地帝国|フランス植民地]][[フランス領アルジェリア|アルジェリア]]旅行に出かけ、中心地[[アルジェ]]を訪ねている。帰国したマルクスはイギリス南部の[[ワイト島]]の保養地{{仮リンク|ヴェントナー|en|Ventnor}}で過ごした<ref name="ハント(2016)357">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.357</ref>。エンゲルスは意欲低下に直面したマルクスを苦々しく感じていたのだが、マルクスも「エンゲルスの興奮ぶりがじつは私を苛立たせた」と語っている。落胆したエンゲルスは「イェニーが死んだ時、モール(マルクス)も死んだのだ」と述べた<ref name="ハント(2016)357"/><ref name="グムコー(下)(1972)128">{{Harvtxt|グムコー|1972}} p.128</ref>。マルクスは居心地の良い土地を求めて各国を放浪を続けたが、行く先々で悪天候に悩まされて気管支炎を拗らせていった。1883年1月、マルクスにさらなる悲報が襲う。マルクスの長女{{仮リンク|ジェニー・ロンゲ|en|Jenny Longuet}}が38歳の若さで急逝したのである<ref name="ハント(2016)357"/>。末娘[[エリノア・マルクス|エリノア]]が語るには、これが「最後の恐ろしい打撃」となった<ref name="佐藤(1984)27">佐藤(1984) p.27</ref>。 |
|||
2月に入るころには、マルクスは喉頭炎、[[肺炎]]を悪化させて急激に体力が衰弱、食事も喉を通らず、声も出せず、薬も効かない状態となっていた<ref name="佐藤(1984)28">佐藤(1984) p.28</ref>。エンゲルスは盟友の最期を覚悟し、マルクス邸に毎日見舞いに通った。しかし、[[1883年]]、カール・マルクスは周囲の手厚い看病の甲斐なく死去してしまう。[[3月14日]]、エンゲルスがいよいよ最期が近いということで、{{仮リンク|ヘレーネ・デムート|de|Helena Demuth}}に促されてマルクスの部屋に入った時、マルクスは既に脈もなく、この世を去っていたのである<ref name="ハント(2016)358">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.358</ref>。エンゲルスはマルクスの最後の瞬間を振り返りつつ、[[ニューヨーク]]の{{仮リンク|フリードリヒ・ゾルゲ|en|Friedrich Adolf Sorge}}にこう語った。 |
|||
{{quotation|「とにかく、人類は頭一つだけ低くなった。しかも、人類が持っている最も大事な頭一つだけ。プロレタリアートの運動はさらに前進を続けるが、その中心がなくなった。フランス人、ロシア人、アメリカ人、ドイツ人が決定的な瞬間にはおのずからそこに向かい、天才と完璧な専門知識をだけを与えられることのできる明瞭で、抗弁の余地のない助言をいつでも受けることができた、その中心がなくなった。……。最後の勝利は確実だ。だが、回り道、一時的な地方的踏み迷いは…いまやはるかに多く生じるであろう。さあ、我々はそれを始末しなければならん。このためにこそ、我々がいるのではないか?だから我々は決して勇気を失わないであろう。」<ref name="グムコー(下)(1972)129">{{Harvtxt|グムコー|1972}} p.129</ref>}} |
|||
マルクスの葬儀は家族のエリノア・マルクスと同志であるエンゲルス、{{仮リンク|シャルル・ロンゲ|en|Charles Longuet}}、[[ポール・ラファルグ]]、ヴィルヘルム・リープクネヒト、{{仮リンク|カール・ショルレンマー|en|Carl Schorlemmer}}、フリードリヒ・レスナーら古くからの友人達、計11人で行なわれた。このときのエンゲルスの弔辞は「カール・マルクスの葬儀」として残されている<ref name="グムコー(下)(1972)130">{{Harvtxt|グムコー|1972}} p.130</ref>。エンゲルスはマルクスの業績を次のように締め括った。 |
|||
[[File:Karl Marx First Grave.jpg|thumb|200px|マルクスのもともとの墓(ロンドン、[[ハイゲイト墓地]])]] |
|||
{{quotation|「ダーウィンが生物界の発展法則を発見したように、マルクスは人間の歴史の発展法則を発見しました。……。それだけではありません。マルクスは今日の資本主義的生産様式とそれが生み出したブルジョワ社会との特殊な運動法則をも発見しました。剰余価値の発見とともに、この分野に突然光が灯されました。しかるにこれまでの一切の研究はブルジョワ経済学者のそれも、社会主義的批判家のそれも、暗闇のなかを踏み迷っていたのでした。……。 |
|||
学識の徒としては上にあるとおりでした。でもこれは、まだこの人の半分をも示すものではありませんでした。マルクスにとって科学は歴史の動力、革命的な力でした。……。というのは、マルクスは、何よりも革命家だったからです。資本主義社会とそれによってつくりだされた国家制度との打倒に…協力すること、近代プロレタリアート…の地位と欲求とを意識させ、みずからを解放する条件を意識した近代プロレタリアートの解放に協力すること―これが彼の一生の使命でした。闘争は彼の本領でした。そして彼は、類いまれな情熱と粘り強さと成功をもって闘いました。……。 |
|||
そして、彼は、シベリアの鉱山から全ヨーロッパとアメリカを超えてカリフォルニアまでにわたって住む何百万という革命的同志から尊敬され、愛され、信頼されながら没しました。……。彼の名は幾世期にもわたってとどめられましょうし、その事業もまた然りでありましょう。」<ref name="グムコー(下)(1972)130-131">{{Harvtxt|グムコー|1972}} pp.130-131</ref><ref name="ハント(2016)362">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.362</ref><ref name="佐藤(1984)29-30">佐藤(1984) pp.29-30</ref>}} |
|||
エンゲルスに続き、リープクネヒトはこう語った。 |
|||
{{quotation|「我々の受けた打撃は大きい。だが、我々は悲しみはしない。故人は死んでいない。彼はプロレタリアートの心の中に生きており、その頭脳の中に生きています。……。死んでもなお生ける友よ!我々はあなたが示した道を、目的を達するまで歩むであろう。我々はあなたの墓の前にこのことを誓います。」<ref name="グムコー(下)(1972)131">{{Harvtxt|グムコー|1972}} p.131</ref>}} |
|||
マルクスが世を去り、エンゲルスは孤軍奮闘することを余儀なくされていく。エンゲルスは盟友の死を受け止めた後、マルクスの理論の確立を図るとともに社会主義運動の発展のために、残りの生涯のすべてを捧げようと決意を固めていった。1884年10月15日の友人宛ての書簡で心情を率直に吐露している。 |
|||
{{quotation|「僕は一生の間いつも第二ヴァイオリンばかりを弾いていた。これならば相当上手といったところまでやれたように思う。が、何といっても、マルクスという第一ヴァイオリンが上手であったのですっかり有頂天になっていた。これからはこの学説を代表して僕が第一ヴァイオリンを弾かねばならぬのだ。よほど用心をしなければ世間の物笑いになるかもしれない。」<ref name="大内(1964)113-114">{{Harvtxt|大内|1964}} pp.113-114</ref>}} |
|||
周囲はエンゲルスに親類縁者の多い大陸に戻り、スイスのような地で暮らすように勧めたが、マルクスの遺志を継ごうとするエンゲルスの決意は固かった。エンゲルスはロンドンを離れることを拒み、1883年4月末にはアウグスト・ベーベルに書簡を送り、マルクスの学問的偉業を継承することに全身全霊を注ぎこむ覚悟を示した。 |
|||
{{quotation|「ここ(ロンドン)だけに理論的な仕事を続けていくための平穏さがあるのだ。……。63歳になるいま、自分の山ほどある仕事、それに一年目の仕事として『資本論』第二巻、二年目の仕事としてマルクスの伝記のほかに、1843年から63年までのドイツの社会主義運動と64年から72年までのインターナショナルとの歴史を書く予定になっているいま、……1848年と49年のような事態にふたたびなるようなことがあれば、またもや馬にまたがるであろう。しかし、いまは……マルクスの書斎に自発的に集まってきた万国からの多くの連絡の糸を、私の力の及ぶ限り、どうしても断ち切らずおこうと思う。」<ref name="グムコー(下)(1972)132">{{Harvtxt|グムコー|1972}} p.132</ref>}} |
|||
[[File:Helene Demuth.jpg|thumb|200px|マルクス家の家政婦にして、晩年期のエンゲルスの友{{仮リンク|ヘレーネ・デムート|de|Helena Demuth}}]] |
|||
エンゲルスはマルクス主義の新しい中心となり、全世界の社会主義運動の発展のために残りの人生のすべてを賭けることになる。このとき、エンゲルスの力となったのはマルクス家の家政婦{{仮リンク|ヘレーネ・デムート|de|Helena Demuth}}である。ヘレーネはエンゲルス家に移ってマルクス遺稿の整理を助けると同時に、エンゲルス家の家政を担当して、エンゲルス家に参集した社会主義者へのもてなしをおこなうことで、エンゲルスを支えることになった。そして、二人でマルクスの手紙などの整理をする時間が、残された者の傷心を癒す貴重な時間となっていった<ref name="グムコー(下)(1972)133">{{Harvtxt|グムコー|1972}} p.133</ref><ref name="佐藤(1984)34-36">佐藤(1984) pp.34-36</ref>。 |
|||
==== マルクス遺稿の整理 ==== |
|||
[[File:Kapital manuskript.jpg|thumb|260px|[[カール・マルクス]]直筆の[[資本論]]原稿]] |
|||
かつてない重責がエンゲルスの双肩にかかっていったが、差し当たり直面した難題はマルクスの遺産相続の問題であった。 |
|||
マルクスは、膨大な書籍数を誇る書庫、膨大な量の未整理の草稿や書簡を保管していた<ref name="佐藤(1984)33">佐藤(1984) p.33</ref>。これらの遺産は第一に末娘のエリノアが相続人となり、第二にエンゲルスがエリノアの後見人として遺産管理人となって『資本論』の完成を目指すということが遺言により確認されていた。しかし、1883年6月、次女の{{仮リンク|ラウラ・ラファルグ|en|Laura Marx}}がこれに反発して異議を申し立てたのである。父から書類や文書を継承して遺稿を整理し、『資本論』や『インターナショナルの歴史』執筆の一端に加わるように言われていたことに言及して、自分にも遺産相続権があるのだとエンゲルスに執拗に要求した。これに対して、エンゲルスは『資本論』執筆の役目は自分にしか成し得ず、末娘のエリノアが指名されたのは彼女がイギリスに在住していたためで、ラウラを排除する意図はないと説明した。かくして、1883年8月、エリノアがマルクスの評価額250ポンドの遺産相続人となる正規の書面が交付された。エンゲルスはラウラに「マルクスの遺稿を出版するという共通の目的を達成するために協力しましょう」と語り、マルクスの書庫にあったフランス語文献は全てラウラに送るなどして姉妹間の紛争をなんとか調停し、ようやく万全の環境のもとでマルクスの業績の整理に着手することとなった<ref name="佐藤(1984)37-42">佐藤(1984) pp.37-42</ref>。 |
|||
マルクス死後のエンゲルスの仕事は二つの課題に絞られていた。 |
|||
すなわち、マルクス主義の体系化と理論を完成させること、そして、国際共産主義の運動を組織して社会主義革命の政治的準備を整えることである。エンゲルスは当面の仕事をマルクスの遺産の整理に費やした。エンゲルスは、『[[資本論]]』に関するマルクスの遺稿の編集、それまでのマルクスとエンゲルス自身の著作の諸言語への翻訳に尽力した。当時の諸情勢と全世界の労働運動における自らの位置とを考慮し、エンゲルスは的確にもマルクスの主著『資本論』の完成をマルクス亡き後の自らの最重要課題と位置付け、編集に取り組むことになった。 |
|||
実際、マルクスの主著『資本論』の第二巻および第三巻の刊行は、エンゲルスの豊富な知力と実務的能力なしには為しえなかった。 |
|||
マルクスの遺稿は第二部「資本の流通過程」、第三部「総過程の諸容姿」を合わせて二つ折り判で1000ページという膨大な量にのぼり(一説では数[[立方メートル|m<sup>3</sup>]]にのぼったともいわれる)、その筆跡は解読が難しいもので、しかもその内容は著作としての完全な筋道をなしていない部分が多かった。内容の難しさのみならず、原稿が未完成であったことも編集を困難にした。象形文字風の独特な略字によって綴られている文章を読み取りつつ、未整備のまま各所に散乱する典拠情報をまとめていく作業は至難を極めるものだったのである<ref name="佐藤(1984)53-54">佐藤(1984) pp.53-54</ref>。エンゲルスは、これらマルクスの遺稿の編集を晩年の視力の衰えと闘い、全世界の労働運動の助言者としての激務の合間を縫いながら進めた。 |
|||
1883年8月、エンゲルスはベーベルに宛てて作業が思うように進展しない苛立ちを打ち明け、「二つぐらいの章を別にすれば、すべてが下書きだ。典拠の引用は未整備で乱雑に山積みされており、あとで取捨選択しようとして集めるだけ集めたものだ。おまけに、絶対に僕しか読めない―それも苦労してやっと読める―あの[[悪筆]]だよ」と伝えている<ref name="佐藤(1984)54">佐藤(1984) p.54</ref>。 |
|||
マルクスの遺稿整理に追われ途方に暮れるエンゲルスに重要な発見があった。遺稿のなかから[[ルイス・ヘンリー・モーガン]]の[[文化人類学]]研究に関する研究ノートを発見したのである。 |
|||
==== 『家族・私有財産・国家の起源』 ==== |
|||
[[Image:Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staates.gif|thumb|220px|『家族・私有財産・国家の起源』の扉]] |
|||
エンゲルスは、[[カール・マルクス]]の史的唯物論の立証と世界史論の構築に情熱を傾けた。とりわけ重要な関心事となったのが、[[原始共産制]]に基づく先史時代の共同体の研究である。このような古代史への関心から執筆されたのが、'''『[[家族・私有財産・国家の起源]]』({{lang-de|''Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats'',1884}})'''である。本書は、エンゲルスの老年期における最高傑作のひとつである。 |
|||
本書執筆の経緯はマルクスの遺稿整理にその契機があった<ref name="『起源』(1965)273">『起源』(1965) p.273</ref>。マルクスは生前、古代社会や古い形態の共同体の研究に没頭していた。 |
|||
1870年代、最晩年に達したマルクスはロシア農村共同体の研究に着手し、やがて共同体一般への関心を高めていった。やがてマルクスは原始共同体への研究の手がかりを[[ルイス・ヘンリー・モーガン]]の[[文化人類学]]研究に求めた。モーガンは[[イロコイ]]・[[インディアン]]を調査研究した成果を『[[古代社会]]』にまとめていたが、マルクスはモーガンの著作とその周辺の関連文献を読み漁り、詳細なノートを作成していた。しかし、1883年にマルクスは研究の半ばで死去する。 |
|||
本書の序文に「以下の諸章は、ある程度まで遺言を執行したものである」とあるように、エンゲルスがマルクスの研究ノートを使って独自に仕上げたものである。エンゲルスはマルクスの中途に終わった人類学研究を継承し、ヘーゲル弁証法の方法論を加えて唯物史観に構築し直すプロジェクトに携わっていく。この頃、エンゲルスは青年期から関心を深めていた古代[[ゲルマン人]]の部族制社会の研究に邁進しており、『原始ゲルマン人の歴史』や『フランク時代』の二編の論文を執筆するなど古代史の研究で成果を出そうとしていた<ref name="『起源』(1965)274-275">『起源』(1965) pp.274-275</ref>。 |
|||
エンゲルスは、『[[空想から科学へ]]』の中で原始共産制社会の存在を指摘し、平等な共同体が有史以前に存在していたと考えていた<ref name="『起源』(1965)274">『起源』(1965) p.274</ref>。一方、ドイツでは[[カール・カウツキー]]による『家族と婚姻の歴史』の出版があり<ref name="『起源』(1965)274-275"/>、1879年には[[アウグスト・ベーベル]]による『[[婦人論]]』が刊行され、社会主義による女性と家族に関する理論的考察が試みられていた。しかし、これらの文献は女性の抑圧を人類史の宿命として位置付けるもので、社会主義による女性の解放を主張していたものの、エンゲルスにとっては不十分な研究でより完成度の高い研究が必要だと感じられた<ref name="ハント(2016)398, 401">{{Harvtxt|ハント|2016}} p.398, p.401</ref>。 |
|||
1884年2月、こうした研究活動の中でエンゲルスはマルクスによるモーガン研究のノートを発見した。 |
|||
エンゲルスは男性による女性への支配の構造が確立される有史時代以前の原始共産制社会を論じ、原始から古代の単婚制の奴隷制社会への移行過程を整理したのである。エンゲルスの研究は論文として[[ドイツ社会民主党]]の理論雑誌『[[ノイエ・ツァイト]]』({{lang-de-short|''Die Neue Zeit''}})に掲載する予定であったが、1884年4月から5月にかけての二か月に及ぶ執筆過程で原稿が膨らみ続けて膨大なものとなってしまう。そこで単著で刊行することとなり、「いわば(マルクスの)遺言を執行したもの」として1884年に『[[家族・私有財産・国家の起源]]』が刊行されることになった<ref name="『起源』(1965)275-276">『起源』(1965) pp.275-276</ref><ref name="佐藤(1984)57">佐藤(1984) p.57</ref>。 |
|||
本書の概要は三部分に整理することができる。一章から三章までの冒頭はモーガン説と古代の人類史の発展過程の紹介に充てられている。まず、原始の人類社会には新時代が到来し始めていた。 |
|||
第一章では文明期への移行の契機が整理されている。人間が「野蛮」から、「未開」をへて、「文明」にいたる、人類社会の発展図を略述した章である。[[採集]]・[[漁業]]・[[狩猟]]からなる野蛮段階から技術の取得によって新段階へと移行する発展のなかにあった<ref name="『起源』(1965)32-33">『起源』(1965) pp.32-33</ref>。人々は[[土器]]の製作をおこない、[[牧畜]][[農耕]]への未開段階へと移行を果たす。さらに人類はムラからクニへと社会編成を変えて、[[金属器]]の製作技術を高めて[[灌漑]][[農業]]や[[騎乗]][[遊牧]]生活を拡大させて、各地で有史時代へと移行を果たした<ref name="『起源』(1965)37-38">『起源』(1965) pp.37-38</ref>。第二章は、原始的な家族形態を復原して今日の[[資本主義]]社会における[[一夫一婦制]]の起源を明らかにする部分、[[階級社会]]における一夫一婦制の批判する部分、いかに婦人は解放されるのかという[[共産主義]]社会での家族と結婚という三つの部分が書かれている<ref name="『起源』(1965)31">『起源』(1965) p.31</ref>。 |
|||
第三章では、原始的な家族形態をなす[[イロコイ族]]の具体的事例が紹介されている。 |
|||
家族は社会の根幹であったが、野蛮段階では部族を構成する複数男女の集団婚であり、誰が子どもの父親であるか不確定だったため、母系制の共同体を形成していた。しかし、農牧業の発達による富の形成は土地の分割と私的所有をもたらしていく。未開段階の人類は、財産となる土地や家畜の所有を戦闘力に優れる男性の権限に移し替えていった。私有財産制度は、実子への財産の継承、即ち世襲原理を可能とするために、母系制の集団婚から父系制の対偶婚へと婚姻制度の変更を余儀なくさせた。これが画期となって、人類は古典古代へと移行していく。エンゲルスはここで「乱婚(無規律性交)→血族婚→プナルア婚→集団婚→対偶婚」という発展図式を考え、私有財産制度の成立とともに、母系制氏族社会が転覆され、「女性の世界史的敗北」が起きたとした<ref name="『起源』(1965)74-76">『起源』(1965) pp.74-76</ref>。 |
|||
私有財産は婚姻制度を家父長制から一夫一婦制へ移行させたが、それとともに一夫一婦婚そのものの内部に第二の対立が発展してくると語った。婚姻が法的制度として確立される一方で、不義密通が生じたのである。エンゲルスは、単婚制は姦通と[[娼婦]]制度によって補完されるとした。不貞は厳禁され厳罰に処されはするが、姦通が結婚制度の不可避な社会的制度になった。エンゲルスは、こうした矛盾は[[社会主義革命]]によって[[資本主義]]が倒壊すると私有財産制が廃止され、単婚制家族の崩壊が始まると歴史は一変革を経験すると予測した。エンゲルスは、私有財産の主要部分、すなわち、生産手段の私的所有の廃止されることで、財産の相続を目的にした一夫一婦制の基礎も消滅するのだと主張した<ref name="『起源』(1965)88-89">『起源』(1965) pp.88-89</ref>。 |
|||
第四章から第八章は[[古代ギリシア]]、[[古代ローマ]]、[[古代ゲルマン]]の氏族共同体が紹介されている。いずれも氏族は国家に先行する社会組織であり、史書や現行制度の痕跡からそれを証明しようとしている。ただし、一様なものではなく、民族ごとに豊かな形態があることをエンゲルスは叙述している。 |
|||
第九章は全体を理論的に結論づけてまとめた章である。[[国家]]の発生についての理論的総括がおこなわれ、この部分は[[マルクス主義]][[階級国家]]論の基礎の一つとなった。 |
|||
最後に、エンゲルスは「文明批判」をおこない、文明が金属貨幣と利子、商人、私的土地所有と抵当、[[奴隷制度]]を発明して、最終的に人類は[[奴隷]]の反乱を防止して[[階級闘争]]が内乱へと発展する[[革命]]的契機を回避する調停機関として[[国家]]を創造したと指摘した<ref name="『起源』(1965)226-227">『起源』(1965) pp.226-227</ref>。だが、[[社会主義革命]]によって[[生産手段]]が共同所有に移管されることによって、[[資本主義]]経済のもとで奴隷化されていた労働者階級の自立が進み、階級闘争が終わりを告げると役目を終えた国家は廃止されるとされた。そして、母系制氏族社会がつくりだした民主的な社会が[[共産主義]]になって高次の形で復元されると主張した<ref name="『起源』(1965)230">『起源』(1965) p.230</ref>。エンゲルスは、[[国家]]や[[一夫一婦制]]、[[私的所有権|私有財産]]を自明のものとするヘーゲル的な歴史観に対して、それらが歴史的なもの、すなわちある条件のなかで生成し、またその条件の解消にともなって消滅(変化)するにすぎないとする歴史観を提示した<ref name="『起源』(1965)225">『起源』(1965) p.225</ref>。 |
|||
{{main|家族・私有財産・国家の起源}} |
|||
==== 『資本論』編纂 ==== |
|||
1884年6月、エンゲルスは『起源』の執筆を終わらせ、ようやく『資本論』第二巻の編纂に取りかかることになった。 |
|||
『資本論』は前述に指摘した通り、断片的な草稿の集合体で、執筆箇所を加えて編纂を進めなければならなかった。だが、エンゲルスは既に高齢となっており、一日8時間から10時間の長時間デスクに向かい続けたために腰痛を悪化させて、医者からデスクワークを禁じられてしまう。そこでエンゲルスは植字工オスカー・アイゼンガルデンを秘書として雇い、口述筆記をさせることで仕事を継続させた。1884年6月から85年11月にかけての一年半をかけて執筆をすすめては毎晩読み返しをおこなうという日々であった<ref name="佐藤(1984)58-59">佐藤(1984) pp.58-59</ref>。エンゲルスは次女ラウラに宛ててこう語った。 |
|||
{{quotation|「土曜日(3月14日)には、ニムとタッシーがパンプスもろともハイゲートへ行くでしょう。僕は駄目です。身体を動かす力が依然として安定せず、じっとしているようにという簡単な注意書をたったいま受け取ったところです。どうせのこと、『資本論』の仕事を続けることにしましょう。これは彼自身の手でつくられた、彼のための記念碑になるでしょうし、また、他人がモールのために建てることのできるどんな記念碑よりもずっと素晴らしいものになるでしょう。この土曜日で二年が経ちますね!それでも、この本の仕事をしている間は、彼と心を通わせているのだ、と僕は本当にそういうことができます。」<ref name="佐藤(1984)61">佐藤(1984) p.61</ref>}} |
|||
『資本論』第二巻は[[1885年]]に刊行される。 |
|||
第三巻は長く困難な数年にわたる編集作業の末、[[1894年]]に刊行、マルクスの「遺産」を世に送り出した。エンゲルスは単なる『資本論』の編集者、マルクスの遺稿の整理執行人ではなかった。編集の最中に現れるマルクスの理論、殊に『資本論』に対する剽窃、中傷、誤解に対しては論陣を張った。 |
|||
『資本論』第二巻、第三巻のエンゲルスによる序文に、資本主義論の最前線でマルクスの理論の擁護に奮闘するエンゲルスの姿を垣間見ることができる。また、エンゲルスは、資本主義の最新の発展段階の諸現象を分析するとともに、資本主義社会と労働者階級の最新の発展を観察し、それまでの自分とマルクスの活動を振り返り、未来社会への道筋の新しい見地を提示した。かつての潤色な革命への展望は、『資本論』の登場とともにより一層確固たる世界観となった唯物史観と、まもなく独占資本主義、帝国主義の段階を迎えんとしていた資本主義の急速な発達の現実の政治経済情勢分析の蓄積とによって、現実的な、したがってより具体的かつ政治的な歴史変革の必然性と民主主義の発展とに関する展望に置き換えられた。 |
|||
==== 世紀転換期と社会主義の復活 ==== |
|||
ドイツとフランスの[[マルクス主義]]者たちが互いに呼びかけをおこない、[[フランス革命]]の起点となった[[バスティーユ襲撃]]の百周年にあたる[[1889年]][[7月14日]]、[[パリ]]の{{仮リンク|ペトレル通り|fr|Rue Pétrelle}}で{{仮リンク|第二インターナショナル第一回パリ大会|label=パリ創立大会|en|International Workers Congresses of Paris, 1889}}を開催した。正統派のマルクス主義者からなるこの集会では20カ国から400名に上る代表者が出席して、{{仮リンク|エドワール・ヴァイヤン|en|Édouard Vaillant}}とリープクネヒトが議長を務めて討議を進め、[[第二インターナショナル]]の発足が宣言された。 |
|||
[[ファイル:Bebel zürich 1893.jpg|thumb|300px|{{仮リンク|第二インターナショナル第三回大会|label=チューリヒ大会|en|Zürich Socialist and Labour Congress, 1893}}後の昼食会におけるエンゲルス(1893年)]] |
|||
この集会ではイギリス側から[[ケア・ハーディ]]、ドイツ側からは[[アウグスト・ベーベル]]、[[ヴィルヘルム・リープクネヒト]]、[[エドゥアルト・ベルンシュタイン]]といった人物が、フランス側からは[[ジュール・ゲード]]、[[ポール・ラファルグ]]、{{仮リンク|シャルル・ロンゲ|en|Charles Longuet}}、ヴァイヤンが、オーストリア側からは[[ヴィクトル・アドラー]]、アメリカからは[[サミュエル・ゴンパーズ]]、ロシア側から[[ゲオルギー・プレハーノフ]]が参加した。労働運動の国際的発展の段階に入り、各国で社会主義政党の時代が到来したという現状認識が確認され、ドイツ・フランス・イギリスで社会主義者の立候補と当選が次々と実現して、議会での勢力拡大が見られた。そして、一)、[[フランス]]における社会主義者たちを統一する。二)、[[8時間労働制]]を要求する。三)、[[常備軍]]を廃止して[[民兵]]制を導入する。四)、[[普通選挙]]の実現を要求し、社会主義者の[[議会]]への進出を図る。五)、[[メーデー]]を国際労働運動のための休日とする、といった以上の五点が決議された。 |
|||
パリでは、[[修正主義]]路線を説くイギリスの{{仮リンク|社会民主連盟|en|Social Democratic Federation}}の指導者[[ヘンリー・ハインドマン]]、フランスの{{仮リンク|ブノア・マロン|en|Benoît Malon}}といった可能派(ポッシビリスト)の集会も同時に開催されたが、二年後に両派の統合が確認され、国際労働運動の結集が果たされた。労働立法の推進と政治運動への参入が支持されるとともに、[[無政府主義]]の排除が確認され、ゼネスト戦略の採用を主張していたフランスの[[アナルコ・サンディカリズム]]が拒絶された。一方で、[[アメリカ労働総同盟]]が[[1890年]][[5月1日]]に[[8時間労働制]]の実現のためにゼネストが呼びかけられ、大規模なデモが実行されたことが集会で支持された。 |
|||
パリ創立大会はマルクス主義的方向を明確に定めた大会であったが、このとき発足した第二インターナショナルは中央評議会を備えた中央集権的機構にはなりえなかった。各国でマルクス主義路線の社会主義政党が発足しており、国際的な連絡と議論の場を設けて各国での議会戦略を練り上げていくことが主たる関心事であった。第二インターナショナルは、組織が樹立されて12年間にわたって、国際的な運動の指導に当たる中央委員会がなく、国際的な合同機関誌も持たず、正規の共同規約も統一綱領も、強制的拘束力のある決議もなく、正式の名称もない状態で活動していた。この点では、第二インターナショナルは第一インターナショナルには組織力として及ぶものではなかった。この組織力の欠如は、戦争の機運が生じてナショナリズムが高まると、[[国際主義]]を擁護して[[反戦]]を貫き、各国労働者の連帯を守るということができなかった主たる原因で組織崩壊を招く致命傷となった。 |
|||
[[1891年]]8月の{{仮リンク|第二インターナショナル第二回ブリュッセル大会|label=ブリュッセル大会|en|International Socialist Labor Congress of Brussels, 1891}}では、一)、労働条件のための立法を要求すること、二)、国際的な[[労働組合]]運動の組織化を推進することが議題にあがった。 |
|||
この間、エンゲルスは喫緊の政治情勢に対し諸国の労働者階級の組織に助力を与えた。勢力が増大したドイツにおいても、スペイン、ルーマニア、ロシアで新たな一歩を踏み出そうとする社会主義者からも、老エンゲルスの助言が求められた<ref>レーニン「フリードリヒ・エンゲルス」、『レーニン全集』第2巻上11-12頁。</ref>。ロシアの若い革命家[[ウラジーミル・レーニン|レーニン]]は、エンゲルスを、マルクス亡き後の「全文明世界における現代プロレタリアートのもっともひいでた学者であり教師」と目していた<ref>レーニン「フリードリヒ・エンゲルス」、『レーニン全集』第2巻上4頁。</ref>。 |
この間、エンゲルスは喫緊の政治情勢に対し諸国の労働者階級の組織に助力を与えた。勢力が増大したドイツにおいても、スペイン、ルーマニア、ロシアで新たな一歩を踏み出そうとする社会主義者からも、老エンゲルスの助言が求められた<ref>レーニン「フリードリヒ・エンゲルス」、『レーニン全集』第2巻上11-12頁。</ref>。ロシアの若い革命家[[ウラジーミル・レーニン|レーニン]]は、エンゲルスを、マルクス亡き後の「全文明世界における現代プロレタリアートのもっともひいでた学者であり教師」と目していた<ref>レーニン「フリードリヒ・エンゲルス」、『レーニン全集』第2巻上4頁。</ref>。 |
||
[[1893年]]8月の{{仮リンク|第二インターナショナル第三回大会|label=チューリヒ大会|en|Zürich Socialist and Labour Congress, 1893}}では、アナルコ・サンディカリズムに対して、主流派のマルクス主義の方針が勝利し、[[直接行動]]ではなく[[議会]]進出による条件改善に重きが置かれる。また、エンゲルスが第二インターナショナルの名誉会長に選ばれた<ref>[https://www.marxists.org/history/international/social-democracy/index.htm History of the Second International - Marxists Internet Archive]</ref>。 |
|||
また、エンゲルスは、資本主義の最新の発展段階の諸現象を分析するとともに、資本主義社会と労働者階級の最新の発展を観察し、それまでの自分とマルクスの活動を振り返り、未来社会への道筋の新しい見地を提示した。かつての潤色な革命への展望は、『資本論』の登場とともにより一層確固たる世界観となった唯物史観と、まもなく独占資本主義、帝国主義の段階を迎えんとしていた資本主義の急速な発達の現実の政治経済情勢分析の蓄積とによって、現実的な、したがってより具体的かつ政治的な歴史変革の必然性と民主主義の発展とに関する展望に置き換えられた。 |
|||
=== エンゲルスの最期 === |
|||
エンゲルスの最晩年の到達は、『[[家族・私有財産・国家の起源]]』『[[ルートヴィヒ・アンドレアス・フォイエルバッハ|フォイエルバッハ]]論(ルートヴィヒ・フォイエルバッハとドイツ古典哲学の終結)』『フランスにおける[[階級闘争]] 1895年版序文』『エルフルト綱領草案批判』ほか多くの著述と、マルクスの死後、多くの人物に対して語られたエンゲルスの書簡の中の言葉に表現されている。それらの中でエンゲルスは、自分たちの大局的な展望と行動・運動の正しさを正当にも主張すると共に、自分たちの置かれた情勢の諸事情から不可避的に生じたそれぞれの局面での誤りや限定的な正当性について率直に述べている。そのような振り返りも、自分たちが作り上げてきた世界史的運動の後世の継承者たちへの思いやりをもって語られている。 |
|||
{{出典の明記| date = 2018-06-13| section = 1}} |
|||
[[ファイル:Friedrich Engels (1891).jpg|thumb|晩年のエンゲルス(1891年)]] |
|||
1894年11月28日、フリードリヒ・エンゲルスは74回目の誕生日を迎えた。しかし、エンゲルスは74歳にしても「老人」ではなかった。鋭気に満ち、ステーキを食べワインを飲んで活発に活動する、失意も衰えも知らない「若き革命家」のままであった。12月17日、ラウラ・ラファルグに宛てた手紙でこう述べた。 |
|||
最晩年のエンゲルスは、減退する視力、そして困難な病と闘った。しかし、エンゲルスは、病床にあってもユーモアを絶やさず、明晰な頭脳を保ち続けた。声を出しての会話が困難になり、石板を使って対話をせざるを得なくなった最中にも、エンゲルスはなお、ユーモアと労働者階級に対する楽観的な展望を石板上に言葉として書き記すことによって、むしろ来客を勇気づけた。 |
|||
{{Quotation|「僕はヨーロッパの五大国と多くの小国ならびにアメリカ合衆国の運動を追ってゆかねばなりません。この目的のために、僕は日刊紙を、ドイツ語のものを三つ、英語のものを二つ、イタリア語のものを一つ、それに1月1日からはウィーンの日刊紙、合計七紙をとっています。週刊紙では、ドイツからは二つ、オーストリアからは七つ、フランスから一つ、アメリカから三つ、イタリア語のもの二つ、それにポーランド語、ブルガリア語、スペイン語、チェコ語のものをそれぞれ一つずつとっており、このうち三つは、僕がまだその国語を習得しつつあるものです。それにくわえて、ありとあらゆる種類の人たちの来訪とたえず増えてゆく文通者の群れ―これがインタナショナル当時よりも多いのです!。もし僕が僕自身を40歳のF.E(フリードリヒ・エンゲルス)と34歳のF.Eとに分けることができたら、……すぐにでもオーライでしょうに。」}} |
|||
[[第一インターナショナル]]崩壊後再建された[[第二インターナショナル]]では指導的役割を担いながら、エンゲルスは、『資本論』第3巻をようやく仕上げて約1年後の[[1895年]]8月5日、ロンドンで死去した。74歳であった。その遺灰は、エンゲルスの遺言により、イギリス南部の[[ドーバー海峡]]に面する風光明媚な彼のお気に入りの地イーストボーンの沖合いに[[散骨]]された。 |
|||
エンゲルスは冗談をいつものように語った。しかし、エンゲルスは現状に満足せず、「すくなくともモールの政治生活の主要な諸章。つまり、1842-1852年とインタナショナルを書きたい。後者は最も重要で急を要する。まず、それをやるつもりだ」と語り、マルクス伝とインターナショナルの歴史を著述することに意欲を見せた。 |
|||
ヴッパータールの生家は博物館「エンゲルスハウス」となっている<ref>【[[Nikkei Asian Review|NIKKEI ASIAN REVIEW]]から】マルクス生誕200年・故郷は叫ぶ 来たれ中国客/エンゲルス生家も周遊『[[日経産業新聞]]』2017年8月10日アジア・グローバル面</ref>。 |
|||
エンゲルスは人生を楽しみながらも死や老衰に悲観しなかった。エンゲルスは体力と知力に自信を持ち続け、エンゲルス家に同居しながら介助者となっていたルイーゼ・カウツキー・フライベルガーが健康状態を心配して過保護に扱うことに苛立ちながら、友人のパウル・シュトゥンプに宛ててこう語った。エンゲルスは、「なんとかして新しい世紀をのぞいてみたいと強く望んでいる。だがそうなると、1901年1月1日ごろには私もまったく役立たずになっており、そのときにはおさらばできる」と述べたように、後々の歴史の展開を見ていきたいと願っていた。しかし、この望みは果たされることはなかった。1895年の春エンゲルスを病が襲った。以後、最晩年のエンゲルスは、減退する視力、そして困難な病と闘った。「ほとんど仕事ができなくさせる、多くの苦痛と習慣的不眠を伴う不快な頸部リンパ腺腫瘍」の正体は[[喉頭癌]]であった。 |
|||
==主な著作== |
|||
* 『イギリスにおける労働者階級の状態』({{lang-de|''Die Lage der arbeitenden Klasse in England,1845''}}) |
|||
6月前半、エンゲルスは海風で苦痛を癒したいと考えて、[[ドーバー海峡]]に面した保養地[[イーストボーン]]に赴いた。海辺の保養地での療養生活にエンゲルスは喜んだが、[[癌]]の進行から苦痛は日々増して激痛となっていった。しかし、エンゲルスは、病床にあってもユーモアを絶やさず、明晰な頭脳を保ち続けた。 |
|||
* 『[[ドイツ・イデオロギー]]』(マルクスとの共著)({{lang-de|''Die deutsche Ideologie, (mit Marx) 1845''}}) |
|||
* 『[[聖家族]]』(マルクスとの共著)({{lang-de|''Die heilige Familie, oder Kritik der Kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer & Consorten, (mit Marx) 1845''}}) |
|||
エンゲルスは、1895年の闘病生活中で実に75通の手紙を書き、政治事件の分析を行い、友人や戦友たちの個人的相談にも乗り、党の革命戦略を練り、助言を与えていった。さらに、残りの力を振り絞って、死後の遺産分割に関する取り決めを定めていった。エンゲルスは相続人をマルクスの娘ラウラとエレノア、故人となった長女ジェニーの子供たち、そして、家政婦のヘレーネ・デムートを遺産相続人に指名した。また、家財の一部をルイーゼ・カウツキーに贈与するとともに、メアリーとリディアの姪パンプス(メアリー・エリン・ロッシャー)に対しても遺産金を提供した。さらに、エンゲルスは莫大な遺産の一部1000ポンドを[[ドイツ社会民主党]]の選挙資金のために提供することを定めた。エンゲルスはベーベルに「諸君が遺産を受け取ったら、それをプロイセン人につかみとられないように、とくに気をつけたまえ。そして、諸君がこの問題について決議したら、上等のワイン一瓶でもそのために飲んで、こうして私を思い出してくれたまえ」と語った。エンゲルスは、マルクスの通信文と書簡のすべての所有権をエレノア・マルクス・エイヴリングに委ねた。自分の文献と命令書の遺言執行人をアウグスト・ベーベル、エドュアルト・ベルンシュタインを指名、エンゲルスが所有していた膨大な蔵書や文献をドイツ社会民主党に寄贈すると表明した。 |
|||
7月23日、エンゲルスは自身の最期を悟ったのか、手術による回復を確信したのか、ラウラ・ラファルグに宛てた最後の手紙でこう語った。 |
|||
{{Quotation|「とうとう私の首のジャガイモ畑に峠がきつつあるらしいので、腫瘍を切開して楽になれるだろう。とうとう!こうしてこの長い小道の曲がり角にでる望みができている。それに食欲がないなどのために私はかなり衰弱しているので、もうそうすべき時でもある。……。長い手紙を書く気力がない。では、さようなら。」}} |
|||
ちょうどこの手紙を書いていた時、[[オーストリア]]の社会主義者[[ヴィクトル・アドラー]]がエンゲルスを訪ねていた。8月を過ぎるころには、声を出しての会話が困難になり、石板を使って対話をせざるを得なくなった最中にも、エンゲルスはなお、ユーモアと労働者階級に対する楽観的な展望を石板上に言葉として書き記すことによって、むしろ来客を勇気づけた。エンゲルスは病床にあったが、まだ面会する体力を保っており、アドラーに伴われてロンドンの自宅に戻っている。アドラーはエンゲルスの病状をドイツのベーベルに報告した。1895年8月5日、ベーベルはヴィルヘルム・リープクネヒトにこう伝えている。 |
|||
{{Quotation|「アドラーがそこへ[ロンドンへ]行った時、エンゲルスはまだ話せたし、半時間話したが、それができなくなった。彼は、石盤で気持ちを分からせるだけだが、それでも上機嫌で、希望をもち、彼の歳の人には、癌など思いもよらぬことなので、どこが悪いのか気づいていないとのことだ。また、彼は石盤に駄じゃれを書いた。こんな具合なのは本当に幸運だ。彼は食餌は、流動食しかとれないし、肉体的には甚だ衰えている。アドラーが立ち去る直前までは、彼はまだ自分自身のことはなんでもしたが、それもやはりできなくなった。彼は脱衣と着衣に人の手を借りなければならない。だから、彼の状態にはまだ一週間は続きうるが、毎日、同じように破局がやってきうるというような事態にある。われわれは、その覚悟をしなければならない。」}} |
|||
しかし、まさにこの[[1895年]][[8月5日]]にはエンゲルスは意識不明の危篤状態となっていた。22時30分ごろ、エンゲルスの脈は途切れてロンドンで死去。国際労働運動はその偉大な理論家であり闘士を失った。『資本論』第3巻をようやく仕上げて約1年後のことであった。 |
|||
エンゲルスの葬儀は、1895年8月10日、ウォータールーにあったロンドン・ネクロポリス鉄道駅内の合室で、ごく近い者でのみ執り行われた。[[エリノア・マルクス]]、{{仮リンク|エドワード・エイヴリング|en|Edward Aveling}}、[[ヴィルヘルム・リープクネヒト]]、[[アウグスト・ベーベル]]、[[エドゥアルト・ベルンシュタイン]]、[[カール・カウツキー]]、[[ポール・ラファルグ]]、フリードリヒ・レスナー、サミュエル・ムーアといった各国の社会主義指導者たちと近親者、およそ20名程度で営まれた。花輪と生花に飾り付けられた特別列車が、エンゲルスの棺を乗せてウェストミンスター駅を発車。棺をワーキングの火葬場へと運び、火葬に付された。その遺灰は、エンゲルスの遺言により、イギリス南部の[[ドーバー海峡]]に面する風光明媚な彼のお気に入りの地[[イーストボーン]]の沖合いに散骨された。8月27日、荒天のドーバーであった。 |
|||
== 主な著作 == |
|||
=== 生前刊の著書 === |
|||
* 『ヴッパータールだより』({{lang-de|''Briefe aus dem Wuppertal,1839''}}) |
|||
* 「シェリングと啓示」({{lang-de|''Schelling und die Offenbarung- Kritik des neuesten Reaktionsversuchs gegen die freie Philosophie,1842''}}) |
|||
* 「キリストの内なる哲学者シェリング」({{lang-de|''Schelling der Philosoph in Christo, oder die Verklärung der Weltweisheit zur Gottesweisheit,1842''}}) |
|||
* 「国民経済学批判大綱」『独仏年誌』({{lang-de|''''Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie,1844''}}) |
|||
* 『イングランドにおける労働者階級の状態』({{lang-de|''Die Lage der arbeitenden Klasse in England,1845''}}) |
|||
* 『[[聖家族 (政治思想書)|聖家族]] 批判的批判の批判―ブルーノ・バウアーとその伴侶を駁す』(マルクスとの共著)({{lang-de|''Die heilige Familie, oder Kritik der Kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer & Consorten, (mit Marx) 1845''}}) |
|||
* 『[[ドイツ・イデオロギー]]』(マルクスとの共著)({{lang-de|''Die deutsche Ideologie, (mit Marx) 1845''}}) |
|||
* 『共産主義の原理』({{lang-de|''Grundsätze des Kommunismus,1847''}}) |
* 『共産主義の原理』({{lang-de|''Grundsätze des Kommunismus,1847''}}) |
||
* 『[[共産党宣言]]』(マルクスとの共著)({{lang-de|''Manifest der Kommunistischen Partei, 1848''}}) |
* 『[[共産党宣言]]』(マルクスとの共著)({{lang-de|''Manifest der Kommunistischen Partei, 1848''}}) |
||
* 『ドイツ農民戦争』({{lang-de|''Der deutsche Bauernkrieg, 1850''}}) |
* 『ドイツ農民戦争』({{lang-de|''Der deutsche Bauernkrieg, 1850''}}) |
||
* 『革命と反革命』({{lang-de|''Revolution und Konterrevolution in Deutschland, 1851-1852''}}) |
* 『ドイツにおける革命と反革命』({{lang-de|''Revolution und Konterrevolution in Deutschland, 1851-1852''}}) |
||
* 『自然の弁証法』({{lang-de|''Dialektik der Natur,1873-1886''}}) |
* 『自然の弁証法』({{lang-de|''Dialektik der Natur,1873-1886''}}) |
||
* 『反デューリング論(オイゲン・デューリング氏の科学の変革)』({{lang-de|''Anti-Dühring, Herrn Eugen Dühringś Umwälzung der Wissenschaft. Philosophie, politische Oekonomie, Sozialismus, 1878''}}) |
* 『反デューリング論(オイゲン・デューリング氏の科学の変革)』({{lang-de|''Anti-Dühring, Herrn Eugen Dühringś Umwälzung der Wissenschaft. Philosophie, politische Oekonomie, Sozialismus, 1878''}}) |
||
| 102行目: | 1,155行目: | ||
* 『[[家族・私有財産・国家の起源]]』({{lang-de|''Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats, 1884''}}) |
* 『[[家族・私有財産・国家の起源]]』({{lang-de|''Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats, 1884''}}) |
||
* 『[[資本論]]第二巻』(エンゲルス編集)({{lang-de|''Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie, Band 2, 1885''}}) |
* 『[[資本論]]第二巻』(エンゲルス編集)({{lang-de|''Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie, Band 2, 1885''}}) |
||
* 『フォイエルバッハ論 |
* 『フォイエルバッハ論(ルートヴィッヒ・フォイエルバッハとドイツ古典哲学の終結)』({{lang-de|''Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, 1886''}}) |
||
* 『[[資本論]]第三巻』(エンゲルス編集)({{lang-de|''Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie Band 3, 1894''}}) |
* 『[[資本論]]第三巻』(エンゲルス編集)({{lang-de|''Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie Band 3, 1894''}}) |
||
===日本語訳=== |
|||
== 脚注 == |
== 脚注 == |
||
{{ |
{{脚注ヘルプ}} |
||
=== 注釈 === |
|||
{{Reflist|group="注釈"|1}} |
|||
=== 出典 === |
|||
{{Reflist|colwidth=20em}} |
|||
== 参考文献 == |
== 参考文献 == |
||
* {{Cite book|和書|author=飯田鼎|authorlink=飯田鼎|date=1966年|title=マルクス主義における革命と改良―第一インターナショナルにおける階級,体制および民族の問題|publisher=[[御茶の水書房]]|ref=飯田(1966)}} |
|||
*『マルクス・エンゲルス全集』(大月書店) |
|||
* {{Cite book|和書|author=石浜知行|authorlink=石浜知行|date =1931年(昭和6年)|title=マルクス伝|url={{NDLDC|1880408}}|series=偉人傳全集第6巻|publisher=[[改造社]]|ref=石浜(1931)}} |
|||
*『モールと将軍』(大月書店) |
|||
* {{Cite book|和書|author=江上照彦|authorlink=江上照彦|date=1972年(昭和47年)|title=ある革命家の華麗な生涯 フェルディナント・ラッサール|publisher=[[社会思想社]]|asin=B000J9G1V4|ref=江上(1972)}} |
|||
*『エンゲルス伝』(労働大学) |
|||
* {{Cite book|和書|author1=カール・マルクス|authorlink1=カール・マルクス|author2=フリードリヒ・エンゲルス|author3=マルクス=レーニン主義研究所|year=1959 |translator=[[大内兵衛]],[[細川嘉六]]|title=マルクス・エンゲルス全集 |publisher=[[大月書店]]|ref={{harvid|マルクス, エンゲルス|1959}}}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=カール・マルクス|authorlink=カール・マルクス|editor=不破哲三|editor-link=不破哲三|date=2010年|title=インタナショナル (科学的社会主義の古典選書)|publisher=[[新日本出版社]]|ref={{harvid|[[カール・マルクス|マルクス]],[[不破哲三]]|2010}}}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=カール・マルクス、フリードリヒ・エンゲルス|authorlink=カール・マルクス|editor=不破哲三|editor-link=不破哲三|date=2012年|title=マルクス、エンゲルス書簡選集(上)、(中) (科学的社会主義の古典選書)|publisher=[[新日本出版社]]|ref={{harvid|[[マルクス,不破哲三]]|2012}}}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=カール・マルクス|authorlink=カール・マルクス|editor=不破哲三|editor-link=不破哲三|date=2010年|title=インタナショナル (科学的社会主義の古典選書)|publisher=[[新日本出版社]]|ref={{harvid|[[カール・マルクス|マルクス]],[[不破哲三]]|2010}}}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=鹿島茂|authorlink=鹿島茂|date=2004年(平成16年)|title=怪帝ナポレオンIII世 第二帝政全史|publisher=[[講談社]]|isbn=978-4062125901|ref=鹿島(2004)}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=ジョナサン・スパーバー|authorlink=ジョナサン・スパーバー|translator=[[小原淳]] |year=2015 |title=マルクス(上)(下):ある十九世紀人の生涯|publisher=白水社 |ref={{harvid|スパーバー|2015}}}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=ハリンリヒ・グムコー,マルクス=レーニン主義研究所|year=1972 |translator=[[土屋保男]],[[松本洋子]]|title=フリードリヒ・エンゲルス 一伝記(上)、(下)|publisher=[[大月書店]]|ref={{harvid|グムコー|1972}}}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=ドイツ社会主義統一党中央委員会付属マルクス=レーニン主義研究所 |year=1976 |translator=[[栗原佑]] |title=モールと将軍 |publisher=大月書店}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=大内兵衛|authorlink=大内兵衛 |year=1964 |title=マルクス・エンゲルス小伝 |publisher=[[岩波書店]]|ref={{harvid|大内|1964}}}} |
|||
* {{Cite book|和書|author={{仮リンク|トリストラム・ハント|en|Tristram Hunt}} |translator=[[東郷えりか]] |year=2016 |title=エンゲルス: マルクスに将軍と呼ばれた男 |publisher=筑摩書房|ref={{harvid|ハント|2016}}}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=テレル・カーヴァー |translator=[[内田弘]], [[杉原四郎]] |year=1989 |title=エンゲルス |publisher=雄松堂出版|ref={{harvid|カーヴァー|1989}}}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=土屋保男|authorlink=土屋保男 |year=1995 |title=フリードリヒ・エンゲルス―若き日の思想と行動 |publisher=新日本出版社|ref={{harvid|[[土屋保男]]|1995}}}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=良知力|authorlink=良知力 |year=2009 |title=マルクスと批判者群像 |publisher=平凡社|ref={{harvid|[[良知力]]|2009}}}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=佐藤金三郎|authorlink=佐藤金三郎 |year=1989 |title=マルクス遺稿物語 |publisher=岩波書店|ref={{harvid|[[佐藤金三郎]]|1989}}}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=大井正|authorlink=大井正 |year=1981 |title=マルクスとヘーゲル学派 |publisher=福村出版|ref={{harvid|[[大井正]]|1981}}}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=河野健二|authorlink=河野健二 |year=1982 |title=現代史の幕あけ―ヨーロッパ1848年 |publisher=岩波書店|ref={{harvid|[[河野健二]]|1982}}}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=望田幸男|authorlink=望田幸男 |year=1992 |title=ドイツ統一戦争―ビスマルクとモルトケ |publisher=教育社|ref={{harvid|[[望田幸男]]|1992}}}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=柴田三千雄|date=1973年|title=パリ・コミューン|publisher=[[中央公論社]]|ref={{harvid|[[柴田三千雄]]|1973}}}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=桂圭男|authorlink=桂圭男|date=1971年|title=パリ・コミューン|publisher=[[岩波書店]]|ref={{harvid|[[桂圭男]]|1971}}}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=桂圭男|date=1981年|title=パリ・コミューン―パリが燃えた70日|publisher=[[教育社]]|ref={{harvid|[[桂圭男]]|1981}}}} |
|||
* {{Cite book|和書|author= ロイ・ウィトフィールド|translator=[[坂脇昭吉]], [[岡田光正 (経済学者)|岡田光正]] |year=2003 |title=マンチェスター時代のエンゲルス―その知られざる生活と友人たち |publisher=[[ミネルヴァ書房]]|ref={{harvid|ウィトフィールド|2003}}}} |
|||
* {{Cite book|和書|author={{仮リンク|フランシス・ウィーン|en|Francis Wheen}}|translator=[[田口俊樹]]|date=2002年(平成14年)|title=カール・マルクスの生涯|publisher=[[朝日新聞社]]|isbn=978-4022577740|ref=ウィーン(2002)}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=小牧治|authorlink=小牧治|date=1966年(昭和41年)|title=マルクス|series=人と思想20|publisher=[[清水書院]]|isbn=978-4389410209|ref=小牧(1966)}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=ジャック・アタリ|authorlink=ジャック・アタリ|translator=[[的場昭弘]]|date=2014年|title=世界精神マルクス|publisher=[[藤原書店]]|ref={{harvid|[[アタリ]]|2014}}}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=E・H・カー|authorlink=E・H・カー|translator=[[石上良平]]|date=1956年(昭和31年)|title=カール・マルクス その生涯と思想の形成|publisher=[[未来社]]|ref=カー(1956)}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=喜安朗|authorlink=喜安朗|date=1994年|title=夢と反乱のフォブール―1848年パリの民衆運動|publisher=[[山川出版社]]|ref={{harvid|喜安朗|1994}}}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=古賀秀男|authorlink=古賀秀男|date=1980年|title=チャーティスト運動―大衆運動の先駆|publisher=[[教育社]]|ref={{harvid|古賀秀男|1980}}}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=ジョージ=リューデ|authorlink=ジョージ=リューデ|date=1982年|translator=[[古賀秀男]] |title=歴史における群衆―英仏民衆運動史1730-1848|publisher=[[法律文化社]]|ref={{harvid|ジョージ=リューデ|1982}}}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=フランツ・メーリング|authorlink=フランツ・メーリング|translator=[[栗原佑]]|date =1974年(昭和49年)|title=マルクス伝1|series=[[国民文庫]]440a|publisher=[[大月書店]]|asin=B000J9D4WI|ref=メーリング(1974,1)}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=フランツ・メーリング|translator=栗原佑|date =1974年(昭和49年)|title=マルクス伝2|series=国民文庫440b|publisher=大月書店|asin=B000J9D4W8|ref=メーリング(1974,2)}} |
|||
* {{Cite book|和書|author=フランツ・メーリング|translator=栗原佑|date =1974年(昭和49年)|title=マルクス伝3|series=国民文庫440c|publisher=大月書店|asin=B000J9D4VY|ref=メーリング(1974,3)}} |
|||
* 『エンゲルス伝』(労働大学) |
|||
* [[ウラジーミル・レーニン|ウラジーミル・イリイチ・レーニン]]「フリードリヒ・エンゲルス」、[[ソビエト連邦共産党中央委員会付属マルクス・レーニン主義研究所|マルクス=エンゲルス=レーニン研究所]]編、[[マルクス・レーニン主義研究所|マルクス=レーニン主義研究所]]訳『レーニン全集』第2巻上、大月書店、1954年。原論文は1895年執筆、論集『ラポートニク』第1~2号に掲載。 |
* [[ウラジーミル・レーニン|ウラジーミル・イリイチ・レーニン]]「フリードリヒ・エンゲルス」、[[ソビエト連邦共産党中央委員会付属マルクス・レーニン主義研究所|マルクス=エンゲルス=レーニン研究所]]編、[[マルクス・レーニン主義研究所|マルクス=レーニン主義研究所]]訳『レーニン全集』第2巻上、大月書店、1954年。原論文は1895年執筆、論集『ラポートニク』第1~2号に掲載。 |
||
| 117行目: | 1,208行目: | ||
* [[マルクス主義関係の記事一覧]] |
* [[マルクス主義関係の記事一覧]] |
||
* [[フリードリヒ・エンゲルス衛兵連隊]] - [[ドイツ民主共和国]](東ドイツ)の儀仗兵部隊。 |
* [[フリードリヒ・エンゲルス衛兵連隊]] - [[ドイツ民主共和国]](東ドイツ)の儀仗兵部隊。 |
||
* 『[[マルクス・エンゲルス]]』(2017年の映画。若年期のマルクスとエンゲルスを描いた映画) |
|||
== 外部リンク == |
== 外部リンク == |
||
{{Wikisourcelang|de|Friedrich Engels}} |
|||
{{Wikiquotelang|de|Friedrich Engels}} |
|||
{{Commons&cat|Friedrich Engels|Friedrich Engels}} |
{{Commons&cat|Friedrich Engels|Friedrich Engels}} |
||
* {{青空文庫著作者|1139|エンゲルス フリードリッヒ}} |
* {{青空文庫著作者|1139|エンゲルス フリードリッヒ}} |
||
* {{gutenberg author|47}} |
|||
* {{Internet Archive author|name=Friedrich Engels}} |
|||
* {{DNB-Portal|118530380}} |
|||
* [https://www.project-archive.org/0/071.html フリードリヒ・エンゲルス「カール・マルクス葬送の辞」(1883年3月17日)] - ARCHIVE |
|||
* {{DDB|Person|118530380}} |
|||
* {{Zeno-Autor|Philosophie/M/Engels,+Friedrich}} |
|||
* {{Librivox author|id=769}} |
|||
* [https://www.marxists.org/archive/marx/index.htm フリードリヒ・エンゲルスの著作] - Marx Engels Archive |
|||
{{社会哲学と政治哲学}} |
|||
{{共産主義}} |
{{共産主義}} |
||
{{大陸哲学}} |
|||
{{マルクス=エンゲルスの著作}} |
|||
{{Normdaten}} |
{{Normdaten}} |
||
| 132行目: | 1,237行目: | ||
[[Category:ドイツの経済学者]] |
[[Category:ドイツの経済学者]] |
||
[[Category:ドイツの革命家]] |
[[Category:ドイツの革命家]] |
||
[[Category:ドイツの無神論活動家]] |
|||
[[Category:ドイツの反資本主義者]] |
|||
[[Category:社会主義の歴史]] |
[[Category:社会主義の歴史]] |
||
[[Category:ヨーロッパの社会主義]] |
[[Category:ヨーロッパの社会主義]] |
||
| 139行目: | 1,246行目: | ||
[[Category:無神論の哲学者]] |
[[Category:無神論の哲学者]] |
||
[[Category:男性のフェミニスト]] |
[[Category:男性のフェミニスト]] |
||
[[Category:マル |
[[Category:マルクス主義フェミニスト]] |
||
[[Category:ヴィクトリア朝の人物]] |
[[Category:ヴィクトリア朝の人物]] |
||
[[Category:ドイツ社会主義の人物]] |
[[Category:ドイツ社会主義の人物]] |
||
[[Category:イギリス社会主義の人物]] |
[[Category:イギリス社会主義の人物]] |
||
[[Category: |
[[Category:1848年革命の人物]] |
||
[[Category:ドイツの紙幣の人物]] |
|||
[[Category:ヴッパータール出身の人物]] |
[[Category:ヴッパータール出身の人物]] |
||
[[Category:1820年生]] |
[[Category:1820年生]] |
||
2024年12月19日 (木) 04:28時点における最新版
 | |
| 生誕 |
1820年11月28日 |
|---|---|
| 死没 |
1895年8月5日(74歳没) |
| 時代 | 19世紀哲学 |
| 地域 | 西洋哲学 |
| 配偶者 | メアリー・バーンズ、リディア・バーンズ |
| 学派 | 大陸哲学、唯物論、科学的社会主義、共産主義、若いころは青年ヘーゲル派 |
| 研究分野 | 自然哲学、唯物論、自然科学、歴史哲学、倫理学、社会哲学、政治哲学、法哲学、経済学、各国の近現代史、政治学、社会学、資本主義経済の分析 |
| 主な概念 | 弁証法的唯物論、史的唯物論、疎外、労働価値説、階級闘争、剰余価値の搾取、価値形態 |
|
影響を与えた人物
| |
| 署名 |
 |
| 共産主義 |
|---|
| 社会主義 |
|---|
フリードリヒ・エンゲルス(ドイツ語: Friedrich Engels、1820年11月28日 - 1895年8月5日)は、 プロイセン王国の社会思想家、政治思想家、ジャーナリスト、実業家、軍事評論家、革命家、国際的な労働運動の指導者。
盟友であるカール・マルクスと協力して科学的社会主義の世界観を構築し、労働者階級の歴史的使命を明らかにした。マルクスを公私にわたり支え、世界の労働運動、革命運動、共産主義運動の発展に指導的な役割を果たした。
概要
[編集]フリードリヒ・エンゲルスは、1820年にドイツ西部の繊維産業都市バルメン(現在のヴッパータール市の一部)の紡績工場主の息子として生まれ、父の願いでギムナジウム(中高等学校)を退学して生家の仕事を実習した。フリードリヒは成人してもなお学問の志を捨てきれずにいたが、この時期ベルリンで砲兵隊の訓練生として軍に参加することとなり、実家を離れ父の監督から解放される機会が巡った。軍務のかたわらベルリン大学で聴講生として反ヘーゲル派で反動的知識人として知られた教授シェリングの講義を聞き、哲学の世界へと関心を広げていく。やがて急進的な改革や宗教批判で知られた青年ヘーゲル派に傾倒していくようになる。
1842年、イギリスの工業都市マンチェスターで父の商会に赴任する途中ケルンに立ち寄り、22歳の時カール・マルクスと初めて会う。その後、マンチェスターで実業に携わりながら、「国民経済学批判大綱」を発表したほか、アイルランド人女工メアリー・バーンズの協力を得て『イギリスにおける労働者階級の状態』を執筆して名を挙げていくこととなる。1844年に帰国する途上、パリでマルクスに再会する。エンゲルスはケルンでの『ライン新聞』、『独仏年誌』と誌上を飾った「ヘーゲル法哲学批判序説」を、マルクスは古典経済学への批評家としてのエンゲルスを高く評価していた。この再開を契機に二人は急速に親交を深め、『聖家族』を共同で執筆して青年ヘーゲル派の批判を開始していく。これ以降、マルクスとエンゲルスは終生変わらぬ友情と協力関係を築いていくようになる。1845-47年にかけて二人は、ブリュッセルに移って近くに住み、『ドイツ・イデオロギー』を共同執筆してヘーゲルの歴史哲学を変革して、弁証法的唯物論の世界観を構築していった。これ以後、マルクスはエンゲルスの協力を受けて唯物史観の将来的展望を描く社会主義理論の体系化に努めていった。エンゲルスが革命理論の体系を問答形式で記した『共産主義の原理』を改定して、共産主義者同盟の綱領『共産党宣言』をマルクスとともに共同起草した。
1848年、ドイツの三月革命において、エンゲルスは義勇軍に参加して軍事的才能を発揮したが、敗れてロンドンに逃れ、ひと足早く亡命していたマルクスの近くへと亡命していった。1850年、革命の失敗原因を過去の歴史の教訓にもとめた研究『ドイツ農民戦争 (歴史書)』を発表した。エンゲルスは革命への参加のゆえに勘当されていたが、生活難の打開のために父に頭を下げて事業に復帰を果たす。その後マルクスに経済援助を続け、1850年から69年にかけて自らは事業に励んでその研究を助けていく。1864年に英仏の労働者が結束して「国際労働者協会」第一インターナショナルを組織すると、エンゲルスはマルクスが活動に参加して理論的指導をおこない、内部の各派閥を整理統合するよう促した。マルクスは1867年『資本論』を発表、資本主義経済内部で資本がどのように労働を搾取して利潤を作り出すか、経済の運動法則を明らかにした。エンゲルスは実業の世界を引退してロンドンに転居し、マルクスとともに1869年にドイツで結成された社会民主労働者党の指導にあたった。エンゲルスは自然科学の研究にも熱心に取り組んで『自然の弁証法』の準備を進めたほか、1878年には『反デューリング論』を執筆して、マルクス理論の擁護者として理論を誤解するものや逸脱するものに対する批判に力を注いだ。
1883年にマルクスが世を去ると、エンゲルスは「第二ヴァイオリン」から「第一ヴァイオリン」としてロンドンで社会主義運動を指導することを決意を定め、1884年にはマルクスが残したノートをもとに『家族・私有財産・国家の起源』を発表した。そして、未刊のまま残されていた『資本論』第二巻・第三巻の完成、翻訳、刊行に全力を注ぎ、マルクス理論を世に広めていった。1889年には第二インターナショナルの名誉会長に就任、各国の革命家たちが社会主義政党を結成するのを理論面資金面で援助していく。しかし、晩年には喉頭癌を患って、1895年にロンドンで死去、遺灰は遺言によりドーヴァー海峡に散骨された[1]。
生涯
[編集]
生い立ち
[編集]1820年11月28日、フリードリヒ・エンゲルスは、プロイセン王国ユーリヒ・クレーフェ・ベルク州のバルメンに生まれた[2][3][4]。同姓同名の父フリードリヒ・エンゲルス(父)(1796-1860、以下、父と略記)と母エリザベート・フンラツィスカ・マウリーツィア(1797-1873)のもとに生まれ、三人の弟と四人の妹からなる八人兄弟の長男であった[3]。エンゲルスは、信仰心の篤い地域社会と厳格な父に反発を覚えながらも、弟と、特に母と妹に対しては終生愛情を持ち続けた[5][6]。
出身地と一門
[編集]バルメンは18世紀には神聖ローマ帝国のユーリヒ=クレーフェ=ベルク連合公国に属した地域で、ナポレオン戦争時にはフランス帝国の属領ベルク公国であったが、ナポレオンの追放後、ウィーン条約に基づきプロイセン領となった。ユーリヒ・クレーフェ・ベルク州からライン州へと編入され統合されていく。現在はヴッパータールと呼ばれ、ノルトライン=ヴェストファーレン州の州都デュッセルドルフの東に40キロいったヴッパー河畔にある中規模の都市である。川を隔ててエルバーフェルトと相対している。
バルメンは18世紀にはすでに紡績業で繁栄した工場町でヴッパー川に面して半円形の都市を形成し、1810年には1万6000人だった人口はエンゲルスの青年期である1840年には4万人になっていた。町の人口構成は染色職人が1100人、紡績工が2000人、織工が1万2500人、リボン織工が1万6000人で大多数が小さな工房で働く職人たちであった。この町は「ドイツのマンチェスター」と呼ばれ、バルメン製の織物はイギリス、アメリカ、西インドなど世界各地で有名であった[7]。エンゲルス少年はこうした職人たちと近しい環境の中で成長し、階級的な思考に固着しない自由な思想と性格を形成していく[8]。
エンゲルス家は16世紀末に一門の起源が見出される。
18世紀半ば、ヨハン・カスパー・エンゲルス1世(1715-1787)は元はライン地方の農民であったが、わずかな銀貨を携えてベルク地方に移住した。移住先に選んだ町は繊維業で栄えていたバルメンであった。ヨハンは繊維業に転身し、麻布の漂白を生業とし、やがて漂白場を備えた紡績工場を有する企業「カスパー・エンゲルス・ウント・ゾーネ商会」の経営を手掛けるようになる。同社は企業の利潤追求だけでなく社会貢献に関しても意欲的な企業であった。従業員に住宅・菜園・学校を提供し、食糧不足に備えて組合を整備した[9]。
エンゲルス家はバルメンを代表する名士の一人となっていき、2代目ヨハン・カスパー・エンゲルス2世は、1808年、市会議員に任命された他、バルメンの福音主義教会の設立者の一人となっている[10]。しかし、3代目継承の際に一族内で紛争が起こり、くじ引きによる決裁でエンゲルスの父フリードリヒは継承から外れてしまう。だが、父フリードリヒは二人のオランダ人ゴッドフリートとペーター・エルメンとともに紡績企業「エルメン&エンゲルス商会」を設立し、共同経営することになる。麻布の漂白から紡績へと事業を拡大させ、マンチェスターへと進出、縫糸工場を建設して海外市場に打って出ることになる[10]。
学校教育期間と萌芽
[編集]エンゲルスは裕福な家庭なので当時は家庭教師による教育で十分なのだが、中等教育を当初は地元のシュタットシューレ(商業高校)で受けた。しかし、商業高校では知的好奇心を満足させることはできず、1834年、14歳からはエルバーフェルトのギムナジウム(普通科高校)に転校することになる[11][12]。
少年期のエンゲルスは、学問が優秀でありながら、書斎に引きこもることを好まない、活発で社交的で好奇心旺盛であった[13]。語学に長けており成績は優秀で、勉学だけでなく、音楽や美術、スポーツなどにも才を発揮し、絵もうまく漫画を描いたりもしていた。地理歴史科の教員ヨハン・クリストフ・クラウゼン先生のもとでドイツの古典文学の教育を受け、中世の騎士物語「射手ウィリアム・テル」や「十字軍の戦う騎士ブイヨン」、そして『ニーベルンゲンの歌』に親しんだ。ロマン主義的な文学運動に感化されており、将来大学では法律を勉強して公務員になるか、文学を学んで詩人になりたいと考えていた[13][14][15]。
しかし、息子のそうした文学への傾倒を父フリードリヒは許さなかった[14]。バルメンはプロテスタントの信仰が強い地域で禁欲、勤勉、実直、敬虔さが重んじられる町であった。商人は天職たる仕事に人生を捧げ、神に従い誉れある信仰生活を全うすることを人生の目標としていた[13][16]。父は息子を実業の世界に進ませたいと考えていた上、保守的な敬虔主義を信条としていたため、青春の夢や理想を謳歌する息子に理解を示すどころか、1837年に学校を退学させてしまう[14][17][18]。
青年期と批判精神
[編集]ブレーメン時代
[編集]
父の反対からエルバーフェルトのギムナジウムを中退したエンゲルスは、17歳から家の仕事を手伝うようになる[14][18]。麻や綿の素材の性質や漂白と染色、そして、紡績や織機に関する知識を教え込まれた。1838年には絹の販売と生糸の調達の現場を見るため、父とマンチェスターに出張に赴いて商売のスキルを叩き込まれていった。また、貿易港ブレーメンのロイボルド商会でも見習い事務員として働き、輸出入や関税、為替など外国貿易に関わる諸々の業務を習得した[19]。この出張の経験で獲得した貿易や商業に関する知識は国際的視野を広げる有意義な機会になった[14]。
しかし、父親の監督のない状況ではエンゲルスは模範的な見習い実業家ではなかった。退屈な事務処理にすっかり飽きてしまい、職場にビールを持ち込んで怠け、二階でハンモックに揺られながら葉巻を吸って自堕落に過ごした[20]。そして、外出してはブレーメンのリベラルな環境で父に禁じられた青春を楽しむようになる。詩に対する関心をさらに深めたほか、フェンシングや水泳などの趣味の楽しみを満喫し、女性を目当てにダンスやコンサートなど社交を楽しむようになった。エンゲルスは感じのよい好青年となっており、若い女性は格好のターゲットであった[21]。
エンゲルスはブレーメン時代から口髭を生やし始めている[22]。髭はエンゲルスの反抗心の表れであった[23]。
1810年代、神聖ローマ帝国を復活させただけの名目的国家連合体ドイツ連邦に反発し、 統一ドイツを希求するナショナリズム運動が盛んであった。1819年、ウィーン体制を主導したオーストリア帝国宰相のメッテルニヒは、ナショナリスト学生によるコッツェブー刺殺事件を受けてカールスバート決議を採択し、学生組合ブルシェンシャフトを解散させ、急進的な青年運動を封じ込めようとした。プロイセン王国もこの決議に賛同し、反動的な言論統制を布いていた。エンゲルスの青年時代、1840年代にもこの反動体制が存在しており、文章に対する検閲だけにとどまらず、服装や記章といった要素まで取り締まりの対象となっていた。口髭は愛国的共和主義の表象であった。バイエルン王国では口髭が違法とされていたという[23]。
エンゲルスの口髭は彼の政治信条が明確となってきたことを意味している。保守主義への強烈な反感である[24]。
1821年ギリシャ独立戦争が勃発し、ギリシア人はオスマン帝国からの支配から脱却する。また、1830年にはフランスで七月革命が、その余波を受けてベルギー独立革命が発生した[25]。1831年、マッツィーニはオーストリア支配からのイタリアの解放を目指して青年イタリアという急進的な革命派集団を組織した。革命の志はヨーロッパ各地に木霊し、様々なタイプの急進主義的な青年組織の結成を促していく。ドイツにも青年ドイツという共和主義的で反体制的な文化運動が誕生し、ウィーン体制の反動主義の中に自由と進歩と革命の精神を種を播いたルートヴィッヒ・ベルネ、ハインリヒ・ハイネ、カール・グツコーといった若き新星の文化人が現れ出た[26]。彼らにとってはゲーテであってもドイツの旧体制的産物でしかなかった[27]。青年ドイツにとっての共通目標は、憲法を制定して国民の政治参加の扉を開き、農奴やユダヤ人を解放し、宗教的強制を排して世襲的貴族制度を根絶することにあった[24]。
エンゲルスは、青年イングランドのシェリーの『マブ女王』(英語: Queen Mab)やヒューマニズムと自由について謳った詩歌を好んだ[28]。とりわけ、影響を受けたのはカール・グツコーである。彼は『懐疑するヴァリー』(ドイツ語: Wally die Zweiflerin)という批判小説を世に送り出した。女ヴァリーの奔放さ、性の解放、宗教批判を含んだこの小説は、ビーダーマイヤー的な暮らし(ブルジョア的な中流市民生活)を軽侮して世に一大センセーショナルを巻き起こし、グツコーは投獄された[24]。こうした文化的潮流に刺激を受けてエンゲルスはロマン主義に混在していた中世懐古を次第に嫌悪し、青年ドイツが封建主義を拒絶したことに共感を抱くようになった[24]。
エンゲルスは、厳格な家庭環境と父親に自分の人生を決められたことに日ごろ憤慨していた。1839年、『ニーベルンゲンの歌』に登場する英雄ジークフリードとその父ジークムントの葛藤を描く叙事詩的戯曲を執筆している。この作品はまさにエンゲルス家における親子の職業選択をめぐる確執を作品化したものであった[29]。これに続き、エンゲルスは『ベドウィン』という詩をブレーメンの新聞に投稿した。この作品は東洋の古き異国情緒をロマンチックに描き、産業社会への移行とその悲哀を対比的に表現する詩であり、エンゲルス初の活字化された作品であった[30]。この頃のエンゲルスは「フリードリヒ・オズヴァルド」というペンネームで活動し、グツコーが発行者となった雑誌『テレグラフ』(ドイツ語: Telegraph für Deutschland)に寄稿して自己表現を楽しんだ[31]。『テレグラフ』はプロイセン王国の言論統制に対して批判精神の発露を巧みに盛り込んだ文芸活動を通じて主張を図った。若きエンゲルスはこのような文化的環境で自己形成を促し、やがて愛国的共和主義の信徒にして急進的社会批判の信奉者となっていた[32]。
『ヴッパータルたより』
[編集]
1830年代、フランスやベルギーなどヨーロッパ各国は産業革命への道筋を歩み始め、その余波はドイツ西部の産業地域ヴッパータール(バルメン・エルバーフェルト)にも及び始めていた。ライン地方とルール地方の伝統的な繊維産業は、家内工房での職人たちの手織による製品によって支えられていたのだが、英国の進んだ繊維産業が工場で機械生産した大量の製品の輸出との国際競合に晒されるようになり、大陸市場から次第に駆逐されて衰退への道を辿りはじめていた[33]。
また、1833年にようやくプロイセン王国 の主導でドイツ関税同盟が発足してドイツ国内の市場統合が開始した。市場統合はヴッパタールに不利に働いた。ザクセンやシレジアといったドイツ東部の産業との競争が始まり、国際市場と国内市場の二正面競争の中で疲弊していく[33]。この頃、ヴッパータールはフランスへの織物の輸出が堅調であったことからその衰退傾向は緩慢なものに留まっていたが、繊維産業は確実に先細りへと向かっていた。地域経済のこうした逆境はエンゲルス家による温情的家父長主義(パターナリズム)の家風にも影響を与え、職人たちとの社会的経済的絆は揺らぎ始めた[34]。
ドイツに産業革命とそれに伴う階級分化が顕在化していった。技術革新によって機械化が進行して熟練の崩壊が始まり、ギルドが解散されて職人たちの労働条件が悪化、人材育成のための徒弟制度が機能不全に陥り、賃金体系が安定を失い動揺していった。産業革命による社会経済的変化は、独立した職人層を解体して不安定な非正規雇用を転々とする労働者階級(プロレタリアート)の形成を促し、ヴッパータールには貧困者が溢れるようになる[35]。失業中、非正規雇用の貧困者が各地の都市に押し寄せ、ケルンでは人口の20~30%が救貧を受けていたと言われている[34]。
これまで文学に夢を見ていた青年エンゲルスは、社会の現実を描いたルポタージュ作品を世に送り出すことになった。それが1839年に世に出たエンゲルス初の本格的作品『ヴッパータルたより』だった[36]。
エンゲルスは、染料の廃液によって汚染され紅に染まった河川と閉塞的な環境で暮らす人々の姿を見つめて心を痛め、冒頭から廃液と排煙による汚染や健康被害を指摘し、環境破壊に比例して深刻化する人心の荒廃、文化の形骸化といった問題を指摘していった。ヴッパータールの変わり映えしない町並みと古色蒼然とした風土を批判し、厳格な宗教信条に凝り固まり、陰鬱な雰囲気を呈する町の雰囲気が社会環境の悪化を招いていると断じた。工場を経営する紳士たち(ブルジョアジー)は、安価な人員として児童を労働者として使役して彼らの堕落を促しながら困窮する労働者(プロレタリアート)の暮らしぶりを卑しむ一方、自分たちは毎週の教会通いによって敬虔さを誇示して、俗物的で上辺だけの暮らしぶりを享受していた。エンゲルスは労働者の窮状を克明に描写して社会矛盾の深刻さを伝え、ヴッパータールの人々が理性と科学が新時代の扉を開く近代の潮流に逆行して聖書かアルコールにのみ救いを求め、酒浸りの日々を酩酊と牧師の説教が流布した迷信の中を生きていると警鐘を鳴らした。矛盾だらけの社会に批判を加えて、社会のあるべき理想像を提示するという課題を浮かび上がらせていった。『ヴッパータルたより』はエンゲルスの思想形成のスタート地点となった。
ベルリン時代
[編集]
ヘーゲル哲学との出会い
[編集]エンゲルスはヴッパータールの人々に見られる偽善的な敬虔主義を強く嫌悪した[37]。
エンゲルスはキリスト教に関する文献を読み漁り、その中で特に1834年に刊行されたダーフィト・シュトラウス(1807-1874年)の『イエスの生涯:その批判的検証』という書に強く刺激を受けた。この著作は聖書の真実性とイエスの奇跡ストーリーを否定し、聖書を当時の文化的背景で書かれた文書であって、そこで描かれたイエスは歴史的に捉え直されなければならないと訴えるものであった[38]。エンゲルスはこの書物に触発されて、青年ヘーゲル派(ヘーゲル左派とも)の思想に関心を持つとともに、キリスト教に対する信仰を捨てる決意をした[39]。やがて、エンゲルスは「哲学と批判的神学とで忙しい」無神論者になっていった[36][40]。
また、ドイツ観念論を代表する哲学者ヘーゲルの文献のなかで、ヘーゲル没後に刊行された『歴史哲学講義』(ドイツ語: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte)を読み込み、歴史を動かす原動力に対して関心を抱くようになる[41]。ヘーゲルの歴史観は、人間の精神を歴史の原動力と位置付け、歴史を精神が自由を獲得しようと闘争していく過程であると見た[41]。エンゲルスは多年に及ぶ思想形成を経て、ヘーゲルの観念的な歴史哲学の批判者となっていった。青年ドイツ、シュトラウス、ヘーゲル哲学、そしてドイツの産業革命がエンゲルスを文学青年から急進主義の若き思想家へと成長させていった。
1841年3月、エンゲルスは二年半に及ぶブレーメンでの修行生活を終えて故郷に戻ったが、既にバルメンでの生活に嫌気が差していた。読書にまい進する生活に没頭していたちょうどこの時期、軍から招集がかかり兵役に就くよう求められる。兵役免除の願いを聞き入れられず軍に入隊することが決まり、地元を離れることになった[42]。エンゲルスはベルリン近衛砲兵旅団第12中隊に配属となり砲術を学んでいたが、すぐに訓練や砲弾の弾道計算に飽きていった[43]。地元を離れ厳格な父の監督から解放されたことで元々好きだった文学や哲学の研究にますます没頭してしまい、九か月で昇進するのが普通のところを仮病を使って訓練をサボって、大学の講義に出席したり読書室に入り浸っていたり町に繰り出して飲み歩いていため、結局退役時に形式的な表彰を受けたものの昇進はできなかった。軍務を抜け出してはベルリン大学で聴講し、反動的な考えに挑戦するべく独習を重ね、エンゲルス自身は自分の思想形成に集中していたと語っている[36][44]。エンゲルスのベルリン暮らしはバルメンには無い新思潮の文化に接することができる刺激的なものであった。とりわけ熱中していたのはヘーゲル哲学であった。裕福な家庭出身の志願兵だったため兵舎に入らず、スパニエル種の犬を飼って兵舎近くのドロテーエン街のアパートで下宿生活をしていた[45]。
ベルリンはプロイセン王国の首都であり、19世紀初頭のプロイセンは宰相シュタイン(任1807-1808年)とハルデンベルク(任1810-1822年)による自由主義的なプロイセン改革を試みるなど一時は開明的な近代化政策を模索していたが[46]、改革が一定の成果を上げると一転、1840年には王権神授説を信奉するフリードリヒ・ヴィルヘルム4世が即位して反動的な権威主義へと逆行していた[47]。
新王は憲法制定や議会開設による王権の制限を嫌悪しており[48]、プロイセン王国の反動は国家が信奉するイデオロギーにも表れていた。ベルリン大学には進歩的なヘーゲル学派が形成されていたが、政府の方針によりヘーゲルのかつての友人であり当時は論敵となっていたフリードリヒ・シェリングがベルリン大学の教授となっていた。シェリングの講義では宗教的で直感的な啓示の観点から超越的な神の絶対性とその実在性が論じられ、汎論理主義(ヘーゲル自身は違っていたが無神論と同義)的と見なされたヘーゲル哲学への批判が盛んに論じられていた。エンゲルスはヘーゲル哲学の真価を見出すべく、シェリングの講義を熱心に聴講していた[36][49]。教室にはブルクハルト、キェルケゴール、バクーニンといった後に思想界を主導した青年たちが集っていた[50]。エンゲルスはヘーゲル哲学に立ちながら社会の変革を目指す青年ヘーゲル派に加わるようになる。
青年ヘーゲル派と新思潮
[編集]
青年ヘーゲル派の学生たちの精神的支柱であったヘーゲルは、19世紀初頭期のプロイセン王国の国家改革に自由の理念が実現される姿を見出してベルリン大学の教授に就任し、生前はプロイセンの国家擁護者となっていた[46]。しかし、1831年にヘーゲルが世を去った後、時代は大きく変わっていた。1840年代のプロイセン王国は産業の発達と産業革命期の社会変動に直面しながらも、憲法も議会もなく近代化は遅れており、依然として封建的な君公国としての性格を留めていた[48]。
青年ヘーゲル派の学生たちは、自由と秩序を重んじるヘーゲルの思想から進歩的な側面に刺激を受け、プロイセン王国の反動を強く非難するとともに、更なる改革を通じて自由の理念がより一層実現されるよう訴えていた。彼らの格好の批判対象は神学であった。1842年、エンゲルスは「シェリングと啓示」(ドイツ語: Schelling und die Offenbarung- Kritik des neuesten Reaktionsversuchs gegen die freie Philosophie,1842)という論文を匿名で公表し、キリスト教の神聖性を批判してキリスト教のあらゆる側面が理性による批判を受けるべきだと檄を飛ばした[51][52]。
シュトラウスの批判的な聖書学は、ブルーノ・バウアー(1809-1882年)による哲学的な批判によってさらなる一歩を踏み出す。
ボン大学の私講師であったブルーノ・バウアーはシュトラウスよりも急進的な無神論者で、神を虚構とする立場から宗教を神話的な創作物として見ていた。『ヨハネによる福音書の史的批判』(ドイツ語: Kritik der evangelischen Geschichte des Johannes, 1840)において、バウアーは無神論的立場をヘーゲル哲学の「疎外」という概念によって用いることでより洗練された宗教社会学的な見解として打ち出すことになる[52]。この見解はフォイエルバッハ(1804-1872年)へと継承され、「神が人間をつくったのではなく、人間が神を自らに似せて作ったのだ」とする投影理論として理論化されて発展を遂げていく[53][54]。
1841年、フォイエルバッハは『キリスト教の本質』(ドイツ語: Das Wesen des Christentums, Leipzig 1841)を世に送り出す。人間は自らの本質を自分の外に表出させて、理想化した自画像を神として打ち立てて崇拝をはじめ、やがて宗教組織や教義に服従することによって人間の自己疎外が制度化される、こうした疎外の過程が宗教だと指摘した。フォイエルバッハはバウアーの疎外論を利用して唯物論から宗教の本質を論じ、それが人間性の自己疎外であったことを解明した。観念論から唯物論、神学から人間学への移行によって学問体系を転換することを訴えた[55]。
マルクスとの出会い
[編集]
1842年、エンゲルスはベルリン暮らしを満喫していた。愛犬に「ナーメンローザ」(名無しという意)という名をつけ、昼は大学の講義、夕べには帰宅して犬の散歩がてらに町を歩き、酒場で夕飯を食べる暮らしをしていた[45]。青年ヘーゲル派の知識人たち、ブルーノ・バウアー、弟エトガー・バウアー、そしてマックス・シュティルナーらと交流を重ね、エンゲルスはこれらの知識人の一派として認知されるようになった[57]。しかし、青年ヘーゲル派の知識人たちは中産階級的なライフスタイルへの反感から自由人を指す「フライエン」を称して犬儒的な快楽主義者を気取る素行不良なものも多かった[56]。エンゲルスも危険思想に傾倒している青年として周囲から、そして両親からも心配されていた。
1842年はエンゲルスにとって重要な年となった。この年の11月、後にエンゲルスの「第一バイオリン」となるカール・マルクスと出会うのである。きっかけはこの時期、エンゲルスが初期の社会主義者モーゼス・ヘス(1812-1875年)やローレンツ・シュタイン(1815-1890年)の活動に刺激を受けたことにある。

モーゼス・ヘスはボンでユダヤ系の製糖業者の家に生まれた人物で、エンゲルスと同様、父親の家業を継ぐことや厳格な宗教伝統への嫌悪感から無神論者となり、宗教に代わる思想としてフランスのサン・シモンの思想やブランキの革命運動論に影響を受けた。1837年には『神聖な人類史』において貧困層と富裕なブルジョアとの社会的格差を前に、バブーフが提唱した財産共有に基づく共産社会が道徳的に望ましい社会であると早くも訴えた。1840年代に入ると、フォイエルバッハの唯物主義的ヒューマニズムをバブーフが説く平等主義と結びつけた社会主義思想を模索した。また、ヘスはヘーゲル哲学を分析や批判の道具から行動と変革の実践的理論へと変換させようと試みたポーランド人のチェフコースキの著作『歴史知識体系序文』により青年ヘーゲル派の思想に刺激を受け、社会主義と革命思想とを結合させた。資本主義内部の社会矛盾を革命に転化させることを論じ、工業化の進んだブリテンで社会主義革命が起こることを感じた最初の人物であり、マルクスとエンゲルスの思想形成に大きな影響を与えた。
エンゲルスはドイツ社会主義の先駆者であるヘスのマルクスに対する賛辞から将来有望な青年思想家の存在を知り、ベルリンからの帰郷の途上ヘスが創刊した『ライン新聞』の事務所に立ち寄り、そこでマルクスと初めて面会した。このときの出会いはマルクスの誤解もあって、実に素気ないものであった[53][58]。
この頃、マルクスは穏健な改革主義者として『ライン新聞』(ドイツ語: Rheinische Zeitung)の編集長として活動しており、自分の思想と行動が品性に欠く青年ヘーゲル派の知識人たちの活動と同一視されて哲学とジャーナリズムに対する偏見が強まり、政府の監視と検閲で仕事ができなくなることを警戒していた[59]。そのため、当初のところ後に盟友となるエンゲルスに対しても警戒感を抱いていたのである。また、マルクスは嫉妬心の強い性格で、二歳年下のエンゲルスが文壇で活躍していることに妬んでいた[60]。しかし、マルクスとの交信はその後も続き、後の深い友情と信頼の基礎を築いていく。
エンゲルスは一年の兵役期間を終えて、ベルリンを離れることとなる。父フリードリヒは息子の急進的な思想に危機感を感じ、再び家業を任せて現実的で堅実な生き方ができるよう、「エルメン&エンゲルス商会」のソルフォード支社を管理する立場に据えることにした。エンゲルスはマンチェスターに発つことになった。
マンチェスター時代
[編集]『イギリスにおける労働者階級の状態』
[編集]

1842年11月下旬、父はマンチェスター西部ソルフォードに立地する「エルメン&エンゲルス商会」の紡績工場「ヴィクトリア工場」で経営に従事させるため、彼をマンチェスターに送った[61]。マンチェスターはイングランド北部を代表する当時人口40万人の工業都市であり、多数の世界的な紡績工場と市場、証券取引所を抱え、「コットンポリス」と称された[62]。エンゲルスは以降20カ月、紡績工場で400名の労働者と共に働き、産業革命をいち早く遂げたブリテン資本主義による搾取の最前線で共産主義的理想との矛盾した立場に置かれる[63]。しかし、エンゲルスは持ち前の行動的な姿勢を通じてこの問題と向き合おうと努める。すなわち、労働者との交流と彼らの貧困に関するフィールドワークである。
エンゲルスは『イギリスにおける労働者階級の状態』(ドイツ語: Die Lage der arbeitenden Klasse in England,1845[1]) 序文で、このときの調査を「圧制者の社会的・政治的権力に対する労働者の闘争をこの目で見たい」という考えのもと、「中間階級の会合や宴会、ポートワイン、シャンパンを断念して、自由な時間をほとんどすべて普通の労働者との交際に費やして」、労働者を「諸君の住宅にたずね、日常生活を観察し、生活条件や苦悩について語りあい」、「本当の生活を知り」、「抑圧され中傷されている階級を公平に扱う機会を得る」とともに「中間階級の残忍さを知った」と語った[64]。


まず、労働者との交友を見てみよう。このとき、エンゲルスは工業化の進展とともに悪化した労働者の生活状況の描写に力を注いだ。案内役としてブラッドフォードで事務員をしていた亡命共産主義者ゲオログ・ヴェートルがエンゲルスと同行していた[65]。この時期のエンゲルスはメアリー・バーンズという愛人をつくっている。彼女はアイルランド系の紡績女工で教育は無かったが、エンゲルスを不衛生で危険が伴う貧しきアイルランド移民の世界へと招待する役割を果たしている[66]。そこで彼は、「イングランドのプロレタリアートと、その努力、苦しみと悲しみを知る」べくスラム街へと足を運んで都市貧民の生活に入り込んで取材と調査を進め、都市の広範囲に拡がった貧困に衝撃を受けて労働者の状態を伝える詳細な報告を執筆した。
また、労働者は社会環境の悪化に抵抗すべく自衛のために活発な社会運動を発展させたが、エンゲルスはマンチェスターで初めて革命的プロレタリアートの運動を目の当たりにして強い刺激を受けた。それがロバート・オウエンによる社会主義運動(空想的社会主義)と『人民憲章』を旗印に普通選挙権獲得を目指し民主化運動を展開していたチャーティスト運動[注釈 2]であった。
オウエンは、産業の発達を真に担ったのは労働者であり、その労働者が貧しいのは資本家が搾取するためである、従って、労働者救済のために強固な組合組織と教育活動による社会の改良が必要であると考えていた。こうした考えは協同組合運動への労働者の結集へとつながっていく[69]。
一方、チャーティストも民主主義の実現によって労働者を解放し、労働者を基盤にした人民の政府によって資本主義の諸矛盾の解決策を模索するという展望を持って、労働者を民主化運動のもとに集結させようとしていた。両派は競合関係にあったが、チャーティスト運動が次第に優勢になっていった[70]。エンゲルスはオウエン派の共産村集落に出かけたり、社会主義を信奉する多くの人々が交流会を楽しんでいたオウエン科学館を訪問し、合唱会や催眠術の披露といった催しものにも参加した[71]。エンゲルスは各地で運動を展開するチャーティストやオウエン主義者の集会に参加し、チャーティスト有力誌『ノーザン・スター』(英語: Northern Star)やオウエン派新聞『ニュー・モラル・ワールド』(英語: New Moral World)の熱心な購読者となってイギリス社会主義の情勢を研究するようになる。マンチェスターの地を踏んだ1842年はチャーティスト運動の全盛期に当たり、彼の到着の半年前、プレストンにて点火栓抜き暴動という大規模な騒擾が発生し、警察と群衆の衝突も発生していた。ブリテン産業界は混乱状態に陥るが、体制による弾圧政策によって工場操業の危機を脱した。このときエンゲルスが属す「エルメン&エンゲルス商会」は騒擾を鎮圧した警察に感謝の意を表す広告を新聞に掲示するなど体制側の対応を歓迎した。こうした事情からチャーティストによる騒擾は工場経営に影響する現実的な危機として考えられており、エンゲルス個人にとっても時代の潮流に無関心ではいられなかったのである[72]。
危機的状況に置かれていた1843年秋、エンゲルスはリーズの『ノーザン・スター』事務所に赴き、チャーティスト運動の急進的活動家であったジョージ・ジュリアン・ハーニーと出会っている。エンゲルスはハーニーの議会主義的傾向に反発し、たびたび衝突しながらも若き頃の革命の同志として半世紀近く親密な関係を築いていく。ハーニー等チャーティストはウェストミンスター議会が「人民憲章」を採択して民主主義を実現することがブリテン社会に根差した階級支配の病根を治療する最善策であり、人民の革命によって国家という盗賊を懲罰せねばならないとして考えていた。
しかし、エンゲルスは資本主義社会に内在する矛盾を解消するということは民主主義によって実現する問題ではないと見た[73]。これについてはトーマス・カーライルなど著名な文学者たちの批判的な意見に刺激を受けるところが大きかった。カーライルはブリテンの社会病理は資本主義という経済的構造にその病根があると見ており、政治的変革では根治しえないと考えていた[74]。エンゲルスはカーライルの社会観を引き継ぎ、資本主義という社会病理の研究のために、まずその社会的実態の把握に注力した。資本主義の矛盾点を描写し、人間を回復する道筋を資本主義社会の現実を研究する方向に求めていったのである。彼は週末になるとマンチェスターを離れてリヴァプールやロンドンに出かけ、労働者の状況を示した統計調査や議会資料、工場監督官や医師の報告書などの資料調査をおこない、科学的手順に基づき綿密な研究を実施した[75]。社会の避けがたい現実の側面であった都市の貧困に関する研究は、エンゲルスに様々な知見をもたらした。そして、「財産とは盗みである」と指摘したプルードンの思想に触れて、資本主義の病理である貧困の根底には私有財産の制度が存在することを発見していく[76]。
この報告は、後に1845年に『イギリスにおける労働者階級の状態』として出版され、カール・マルクスや後継者のウラジーミル・レーニンによって労働者階級に関する歴史的な文献として極めて高い評価を与えられることとなった[77]。エンゲルスはすでにこの頃より、持ち前の好奇心と行動力によって活発な取材を展開し、ジャーナリストとしての才を示している。
共産主義に向かって
[編集]1843年10月、マルクスと妊娠中の妻イェニー・マルクスがパリに到着した。この転居には事情があった。ロシアのツアーリニコライ1世がヘスとマルクスが主宰する『ライン新聞』にあって、ロシアを批判する記事を目にして不快感を表明し、同盟国プロイセンに圧力をかけて、新聞の発行許可を取り消すように要望したのである。これにより『ライン新聞』は廃刊に追い込まれ、マルクスは失職してしまう。しかし、この後幸運にもアーノルド・ルーゲから新しい新聞の立ち上げの話を持ちかけられ、マルクスはこれを承諾した。新新聞の発行地はドイツ人亡命者が多いフランスの首都パリに定められ、これを受けてマルクスもパリに移ることとなった[78]。1844年2月、エンゲルスはマルクスによって編集・出版された『独仏年誌』(ドイツ語: Deutsch–Französische Jahrbücher) という雑誌が創刊される。マルクスは、「ユダヤ人問題によせて」と「ヘーゲル法哲学批判序説」の二編の論文を投稿している。
この論文中では「大事なことは政治的解放(国家が政治的権利や自由を与える)ではなく、市民社会(資本主義経済)からの人間的解放だ」[79]、「哲学が批判すべきは宗教ではなく、人々が宗教という阿片に頼らざるを得ない人間疎外の状況を作っている国家、市民社会、そしてそれを是認するヘーゲル哲学である」と論じた[80]。「徹底的な非人間状態に置かれ」、「市民社会の階級でありながら市民から疎外されているプロレタリアート階級」を新時代の「心臓」とする「人間解放」を行うべきだと喝破した[81][82]。
マルクスはパリの労働者集会にも参加し、労働運動の可能性を感じ始めた。
1844年8月、フォイエルバッハへの手紙では「フランスの労働者の集会に一度出席なさるといいでしょう。そうすればこうした酷使された人々の間に、若さあふれる溌剌感や高貴さが満ち溢れていることを信じられるはずです」と語っている。マルクスはパリでの体験を通じて「われわれの文明社会にいるこの未開人たちのあいだで、歴史は人間の解放のために活動する実際的分子を準備している」と考えるようになった。プロレタリアートによる人間の解放に強い希望を感じるようになり、マルクスはより一層、青年ヘーゲル派に距離を置き始め、共産主義者へと変貌し始めていった[78]。
エンゲルスも、同誌に当時最先端の経済学であった古典派経済学を批判的に検討した自らの論文「国民経済学批判大綱」(ドイツ語: Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie,1844)を寄稿し、創刊号を飾った。エンゲルスはこの中でブリテンの完成した産業資本主義に触れた経験から私有財産制やそれを正当化するアダム・スミス、デヴィッド・リカード、ジャン=バティスト・セイを批判した。古典派経済学を資本主義がもつ法則性を研究したと評価する一方、現状を無批判に肯定して社会の病理を覆い隠すものとして糾弾したのである[83][84]。同論文の内容はピエール・プルードンの影響を受けて、貧困の根源を成している私有財産制度の問題点を指摘するものであった[76]。伝記筆者のトラストラム・ハントは本論文を『イギリスにおける労働者階級の状態』と加えて「青年ヘーゲル派の疎外の概念を、ヴィクトリア朝時代のイギリスの物質的現実にあてはめ、そこから科学的社会主義の思想面の構造を作り出し」、革命によるブルジョワの打倒の道が準備されているという認識を明示するものと位置付けた他、同様にエンゲルス研究者の土屋保男は「労働者に彼らのあらゆる苦難の根源である経済関係を明らかにし、資本と労働の対立と闘争のよってきたる基本的関係―生産手段の所有と無所有―を見極めて、この関係の打倒こそが労働者に新しい未来を開く」のだという点を明示し、マルクス主義の理論形成に重要な意義を持っている作品として高く評価した[85][86]。これはヘスや後に衝突するヴァイトリングが主導した道徳的で、かつメシア的共産主義運動を超克し、経済法則に社会現象の根底を見出し、人類史の巨大なうねりの中でプロレタリアートの勝利を導きだす史的唯物論―唯物主義的な共産主義―の理論的確立に貢献するものであった[87]。また、経済学の分野の研究においてエンゲルスがマルクスに先んじていることを示しており、マルクスが経済学の道へ本格的につき進む契機となって、経済学に対する歴史的パースペクティブからのちのマルクスによってその歴史的価値を高く評価された。エンゲルスに感化されたマルクスは経済学や社会主義、フランス革命についての研究を本格的に行うようになっていく[88]。これ以降、マルクスはサン・シモン、シャルル・フーリエ、ロバート・オウエンといった社会主義者の文献を批判的に検討し、社会主義の必要性と可能性の探求を進めた[89]。マルクスはエンゲルスの示唆から着想を受けて宗教による疎外の問題から資本主義社会における現実の問題へと関心を移していく。
1844年8月から『経済学・哲学草稿』(ドイツ語: Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844)の本格的な執筆に入る。本書にあって、マルクスは階級に基づく資本主義的生産の体制と私的所有の制度は近代市民社会において不可分の関係であり、この両者は資本家による搾取とその帰結である労働者の貧困と自己疎外を生み出す根源であることを指摘した。そして、私的所有の制度を廃止することによって資本主義という階級支配の社会的機構を乗り越え、プロレタリアートは人間性を回復することができると結論付けた。共産主義こそ人間解放の真髄である、これがマルクスとエンゲルスの生涯を通じての信念となっていく。両者はやがて固い絆を築いていくことになる[90]。
マルクスとの共同研究の開始
[編集]パリ時代―青年ヘーゲル派批判
[編集]

1844年、『独仏年誌』への論文投稿を通じてマルクスとエンゲルスは手紙を交わすようになっており、両者の関係は急激に縮まっていった[82][91]。
8月、エンゲルスはマンチェスターからドイツに帰る目処を着ける。帰国の途中でエンゲルスはパリでマルクスと再会し、お互いが思想面で資本主義に関する同じ考え方を共有していることを認識して、二年前の冷ややかな対面とは打って変わり仕事面でも親密な関係を築き、強い友情で結ばれていくようになった[92][93][94]。エンゲルスはパリに立ち寄って8月から9月にかけての10日間マルクスの自宅に滞在し、ドイツの哲学界を酒の肴に連日飲み交わし、翌年出版した論争の書『聖家族 批判的批判の批判―ブルーノ・バウアーとその伴侶を駁す』(ドイツ語: Die heilige Familie, oder Kritik der Kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer & Consorten, (mit Marx) 1845)を共同執筆している[91][94][95]。
この書ではヘーゲル哲学の中心的な方法論となっていた「弁証法」が評価される一方で、観念論に基づいた「精神」中心の世界解釈に限界があることを指摘している。「ヘーゲルの弁証法は素晴らしいが、一切の本質を人間ではなく精神に持ってきたのは誤りである。神と人間が逆さまになっていたように精神と人間が逆さまになっている。だからこれをひっくり返した新しい弁証法を確立せねばならない」と訴えた。
また、マルクスのかつての盟友であるブルーノ・バウアーやフォイエルバッハの宗教批判や文化批評に特化した旧来的な唯物論に対して批判が加えられている。青年ヘーゲル派は哲学に人間解放の理想を追求しているものの、ブルジョワ的な思考に固着しており、人間そのもの、殊に困窮するプロレタリアートに近づこうとはしなかった。マルクスは人間解放の希望を抑圧を受け苦難を背負ったプロレタリアートに見出すとともに、こうした青年ヘーゲル派の超然的な姿勢を糾弾した。
マルクスとエンゲルスはヘーゲルとバウアー、フォイエルバッハの歴史観に関して容赦しなかった。「歴史は何もせず、莫大な富を持たず、どんな戦いも仕掛けない」、「財産を所有し行動を起こし、戦争をするのは〈歴史〉ではなく、生身の人間なのだ。己の目的を達成するに人間を利用する、〈歴史〉と呼ばれる独立した存在などない。歴史は単に、目的を持った人間の活動に過ぎない」と指摘した。この歴史観はヘーゲルの歴史哲学を批判するものであり、青年ヘーゲル派の人間主義を批判するものであった。マルクスとエンゲルスによって初めて提示されたこの思想は史的唯物論へと発展を遂げていく。
9月中旬、エンゲルスはマルクスにしばしの別れを告げてバルメンに帰郷することとなった。しかし、エンゲルスは備忘録として個人的に書き残した大事な草稿をマルクス宅に置き忘れてしまう。マルクスがこの草稿を発見するやいなや即座に自身の見解を盛り込んで共著という体裁で公表してしまったのである。そのタイトルは『批判的批判の批判』であったが、新たに『聖家族』と変更された[96]。これは敬虔主義を奉ずる信仰心の篤いエンゲルス家にショックを与えた。エンゲルスの家庭内での立場はますます悪化し、憤慨する父は息子の給金を減額して応酬した。エンゲルスは激怒する父親の制裁に怯まなかった[97]。
1844年はドイツにとって政情不安が蔓延した年で、各地で民衆騒擾が発生していた。
代表的なものとして1844年6月にシレジア地方ペーターズヴァルダウで発生した職工による一揆が挙げられる[98]。世情の緊迫化はエンゲルスの士気を鼓舞するものとなった。ラインラントにも初期の共産主義運動が浸透し始め、エンゲルスはバルメンに帰郷すると、共産主義を宣伝する集会を開催して講演者を務めた[99][100]。エンゲルスは資本主義の不公正によって貧富の格差が広がり、中産階級が消滅して階級間の緊張が激化し、やがて社会に蓄積された緊張は階級闘争へと発展して革命を引き起こすと喧伝した。
この革命はプロレタリアートによる社会主義の革命であり、古い階級支配を廃止して、新秩序を打ち立てることになる。資本主義に対して共産主義が取って代わり、資本と労働は政府の管理によって効率的に配分され、生産性が高まって共産主義が貧困に勝利を収めて、全市民に福祉を提供してすべての人間が平等な社会―すなわち共産主義社会が実現されると約束した[101]。こうした主張は後の『共産党宣言』の中心的内容を占めていく。
だが、エンゲルスの扇動的な主張は治安当局の危機感を煽るものであった。エンゲルスは警察から要注意人物の認定を受け、警察は「在バルメンのフリードリヒ・エンゲルス(父)は真に信頼できる人物であるが、同人には、たちの悪い共産主義者で文士として放浪している息子がいる」として内務省に通報、エンゲルスとその一派に対する処遇の検討に入る。プロイセンの内務大臣とライン州の首相の名をもって共産主義の集会を開くことが禁じられてしまう[102][103]。恥をかいた父親はますます憤慨し、息子に対して勘当同然の扱いをした。親子関係はさらに険悪化したが、エンゲルスの意志は固かった。1844年11月から翌1845年1月にかけて、エンゲルスは自室に籠って『イングランドにおける労働者階級の状態』の執筆に取り掛かる。エンゲルスは家族と別れを告げてでも信念を全うする覚悟を固めていた[104][105]。
ブリュッセル時代―史的唯物論の形成
[編集]1845年1月、マルクスはフランス政府当局から強制国外退去を命じられた後、ヨーロッパの他の国よりも比較的表現の自由が保証されていたベルギーに活動の場を移した[106][107]。エンゲルスもマルクスと活動を共にするため、故郷を離れる決断を下す。このときの心境をエンゲルスはマルクスに語っている。
「こういう小銭稼ぎはやりきれない。バルメンはやりきれない。ここの人間の暮らしはやりきれない。しかし、何よりやりきれないのは、ただのブルジョワ以上に、工場主として、本当のブルジョワとして、正面切ってプロレタリアートに対抗することくらいやりきれないものはない。僕はここで親父の工場に数日座っていて、いまさらのように、そう思った。前にはこれほどには思わなかったのにだ。……。人間は、……事業をして、小銭を稼いで、その上に共産主義のプロパガンダをやろうというのは、とても駄目だ!ぼくはイースターにはここを逃げ出す。こんな退屈な生活に加えて、実に完全にやかましいプロイセンの宗教的家庭とは仕方がないものだ。下手をするとぼくはドイツの無教養な俗物になりそうだ。そして俗物主義を共産主義の内に持ち込みそうだ。」[108][109]
実家を去ったエンゲルスはマルクスと共にブリテンへと視察旅行に行く。二人は連日マンチェスターのチータム図書館に通った。日当たりの良い弓なりの出窓にお決まりの席を見つけて、経済学の著作を精読すると共に公文書を閲覧し、資料収集を進めた[110]。この視察は短期間で目的を果たし、1845年4月にはエンゲルスもベルギーの首都ブリュッセルに移住、二人はアパートの隣同士で部屋を借り暮らすことにした。ブリュッセルにはマルクス以外にもドイツからの亡命共産主義者が多く滞在しており、モーゼス・ヘス、ゲオログ・ヴェートル、シュテファン・ボルン、カール・ハインツェン、詩人フェルディナント・フライリヒラート、元プロイセン軍将校のジャーナリストであるヨーゼフ・ヴァイデマイヤー、学校教師のヴィルヘルム・ヴォルフ、マルクスの義弟エドガー・フォン・ヴェストファーレンなどが近隣に居住し、彼らは夜な夜な酒場に繰り出しては哲学談義を華を咲かせる飲み仲間でもあった[111]。こうした環境で、出版社が見つからなかったため1923年まで未公刊にあったが、マルクスとエンゲルスは共著で『ドイツ・イデオロギー』(ドイツ語: Die deutsche Ideologie, (mit Marx) 1845)という偉大な草稿を製作していく[112]。
マルクスは、青年ヘーゲル派も含めドイツの思想はヘーゲル哲学に由来する観念的なイデオロギーであることを指摘した[112]。ヘーゲル派は自由を意識する精神が支配と闘争しながら歴史を前進させ、社会を合理的に編成していったという考え方を支持し、歴史を観念的な理想が実現される過程と見なした。だが、マルクスとエンゲルスは思弁的な歴史哲学を頭と四肢とを転倒させるようなグロテスクな考えであると見た。これに対して、唯物論を「天から地へと降りてくるドイツの哲学とは好対照に、これは地から天へと昇る」問題なのだと語り、唯物論は「生身の人間に到達するために、人が言ったり、想像したり、考えたりすることから始めるのではなく、現実に行動する人間から始め、生活過程のイデオロギー的反映や反響の展開を明らかにする実際の生活過程に基づくものである」と語って新思想の意義を評価した[113]。だが、唯物論のすべてを評価したわけでなく、フォイエルバッハの唯物論に対しては痛烈な批判を加えた。フォイエルバッハは哲学によって神と対置されてきた生身の人間を考察し、宗教によって貶められてきた人間性の価値を再評価したが、唯物論を完成させることはできなかった。マックス・シュティルナーも人間の独立性を重んじ、絶対的自我の尊重を説くエゴイスティックな考えを提示したが、この両者は人間の存在を語りえたとしても人間の「歴史」を議論することができなかったのである[114]。「歴史」について考察する新たな唯物論を提示することが喫緊の課題となっていた[115]。
マルクスとエンゲルスの関心の中心は人類史は如何に成立するのか、そして社会の歴史的な活動は何に基づいているのかという問題関心に置かれた。
「われわれが出発点としてとるところの諸前提は、……、現実的諸個人であり、および彼らの物質的生活諸条件―既存の生活諸条件ならびに彼ら自身の行動によって産出された生活諸条件―である。」[116]
マルクスは歴史の出発点を現実に生きる人間の存在を支える物質的活動に求めた。ここで、マルクスが明らかにしたのは人類史を成立させるのは、存在のとりわけ物質的生活条件であってそれを支える生活手段の生産にあるということである。人類史は現に生きている人間が生活の糧を手に入れる生産の活動からはじまる。人間活動が歴史を創るわけだが、その活動の根源は現実の生のための必要物の創出、存在を規定する物質的諸条件の形成を意味する生産活動にあることを指摘した[116]。
「かくて事実はこうである。すなわち特定の仕方で生産的に働いている特定の諸個人はある特定の社会的および政治的関係を結ぶ。経験的考察はそれぞれ個々の場合に社会的および政治的編成と生産の関連を経験的に、そして、ごまかしも思弁もなしに示すはずである。社会的編成と国家はたえず特定の諸個人の生活過程から出てくる。諸観念、諸表象の生産、意識の生産はさしあたり初めに人間たちの物質的活動や物質的交通―現実的生活の言語―に編みこまれている。人間たちの表象作用や思惟作用、彼らの精神的交通はここではまだ彼らの物質的ふるまいの直接的な流出として現われる。一民族の政治、法、道徳、宗教、形而上学、等々の言語のうちに現れるような精神的生産についても同様である。人間たちが彼らの諸表象や諸理念の生産者であるが、……、意識は意識された存在以外の何ものかでありうるためしはなく、そして人間たちの存在とは彼らの現実的生活過程のことである。」[117]
マルクスは「意識が生活を規定するのではなく、生活が意識を規定する」と述べた[113]。また、社会の生産力が進歩するとともに人々の物質的生産の様式が変容してそれに相応しい社会関係、政治的編成を作り上げ、物質的生産の状態が固有の政治機関を形成するようになると考えた。しかし、一旦、精神的労働が独立した活動を始めるとある時代に特徴的な法律、政治、意識の形態が問題になっている。既存の社会構造を弁護する強力な働きを始める。たとえば、古代では農業が社会の発展を促し、ラティフンディアにおける奴隷主と奴隷からなる奴隷制が普及して、奴隷を使役する体制を擁護するローマ法や古典哲学が誕生した。中世では三圃制農業が浸透し、領主が農奴を使役する封建制が存在、キリスト教とスコラ哲学が発達し、王権神授説が流布した。さらに、近代では蒸気機関が発明され工場制機械工業が確立し、資本家が労働者を使役する資本主義が発達して、産業を主導したブルジョワジーによって古典派経済学と自由主義の思想が発展した。意識は存在から生まれ、やがて「経済」という物質的現実から独立した「文化」の世界を作り上げ、思想にまで発展した意識が歴史を支配する過程を描いた[118]。
マルクスは人類の歴史を労働の組織化の形態あるいは物質的な生産体制の変遷として理解して「古代奴隷制・中世封建制・近代資本制」という図式で捉えていった。この歴史的運動を支えていたのが生産力である[119]。生産力は道具や技術や知識の増加に比例して常に増大し続ける発展性が内在する。しかし、マルクスによると、人間は生産力と交通形態(生産関係)とのタイアップによって経済活動をして、この経済活動に従って歴史をつくりだしているが故に、生産力の発展性は社会の関係の組織編制(生産関係)のあり方に依存している。経済構造(生産関係)は一定の歴史期間内において合理性を有して生産力を刺激する。だが、生産力の発展という量的変化の増大に伴って生産関係に内在的な矛盾が蓄積されて、やがて社会の硬直化が進んで生産力の発展に対応することができず足かせとなっていく。そして、その矛盾が限界に達すると、生産関係も質的変化を遂げることを余儀なくされ革命が生じていく。その結果、下部構造(経済)は変化して上部構造(哲学・宗教・政治)を革命によって変革させると考えたのである[120][121]。
こうして、マルクスは意識を主題として歴史を捉えたヘーゲル的歴史観を批判的に乗り越えた。マルクスは『ドイツ・イデオロギー』において史的唯物論の理論化を進め、歴史の把握をめぐる謎に解答を与えるに至った。このときの業績は1848年の『共産党宣言』、1859年に刊行された『経済学批判』の序文(ドイツ語: Zur Kritik der politischen Ökonomie,1859)において史的唯物論として公式化され、マルクス主義を構成する重要理論の地位を占めるようになった。マルクスはこの理論を自らの「導きの糸」と呼んだ。その内容は以下の通りである。
「人間は、その生活の社会的生産において、一定の、必然的な、かれらの意思から独立した諸関係を、つまりかれらの物質的生産諸力の一定の発生段階に対応する生産諸関係を、とりむすぶ。この生産諸関係の総体は社会の経済的機構を形づくっており、これが現実の土台となって、そのうえに、法律的、政治的上部構造がそびえたち、また、一定の社会的意識諸形態は、この現実の土台に対応している。物質的生活の生産様式は、社会的、政治的、精神的生活諸過程一般を制約する。人間の意識がその存在を規定するのではなくて、逆に、人間の社会的存在がその意識を規定するのである。社会の物質的生産諸力は、その発展がある段階にたっすると、いままでそれがそのなかで動いてきた既存の生産諸関係、あるいはその法的表現にすぎない所有諸関係と矛盾するようになる。これらの諸関係は、生産諸力の発展諸形態からその桎梏へと一変する。このとき社会革命の時期がはじまるのである。経済的基礎の変化につれて、巨大な上部構造全体が、徐々にせよ急激にせよ、くつがえる。
このような諸変革を考察するさいには、経済的な生産諸条件におこった物質的な、自然科学的な正確さで確認できる変革と、人間がこの衝突を意識し、それと決戦する場となる法律、政治、宗教、芸術、または哲学の諸形態、つづめていえばイデオロギーの諸形態とを常に区別しなければならない。ある個人を判断するのに、かれが自分自身をどう考えているのかということにはたよれないのと同様、このような変革の時期を、その時代の意識から判断することはできないのであって、むしろ、この意識を、物質的生活の諸矛盾、社会的生産諸力と社会的生産諸関係とのあいだに現存する衝突から説明しなければならないのである。
一つの社会構成は、すべての生産諸力がその中ではもう発展の余地がないほどに発展しないうちは崩壊することはけっしてなく、また新しいより高度な生産諸関係は、その物質的な存在諸条件が古い社会の胎内で孵化しおわるまでは、古いものにとってかわることはけっしてない。だから人間が立ちむかうのはいつも自分が解決できる問題だけである、というのは、もしさらに、くわしく考察するならば、課題そのものは、その解決の物質的諸条件がすでに現存しているか、またはすくなくともそれができはじめているばあいにかぎって発生するものだ、ということがつねにわかるであろうから。
大ざっぱにいって経済的社会構成が進歩してゆく段階として、アジア的、古代的、封建的、および近代ブルジョア的生活様式をあげることができる。ブルジョア的生産諸関係は、社会的生産過程の敵対的な、といっても個人的な敵対の意味ではなく、諸個人の社会的生活諸条件から生じてくる敵対という意味での敵対的な、形態の最後のものである。しかし、ブルジョア社会の胎内で発展しつつある生産諸力は、同時にこの敵対関係の解決のための物質的諸条件をもつくりだす。だからこの社会構成をもって、人間社会の前史はおわりをつげるのである。」[122]
『共産党宣言』とエンゲルス
[編集]「共産主義者同盟」の発足
[編集]『フォイエルバッハに関するテーゼ』の結びで、マルクスとエンゲルスは次のように宣している。「哲学者はただ世界をさまざまに解釈してきたにすぎない。肝要なのは、世界を変革することである。」
1845年以降、マルクスはこの言葉通り、エンゲルスとともにブリュッセルにおいて、革命運動に参加していくことになる[123]。
1846年1月には来るべき革命期に備えヨーロッパ各地の社会主義運動を団結させるべく、ドイツ人共産主義者の団体「正義者同盟」(ドイツ語: der Bund der Gerechten)と提携する道を探る。「正義者同盟」はフランスに亡命したドイツ人共産主義者を構成員に1830年代に発足した秘密結社で、1839年5月パリで革命家オーギュスト・ブランキとともに蜂起に参加するも失敗し、カール・シャッパー、ハインリヒ・バウアー、ヨーゼフ・モルら三名の指導者はロンドンに亡命して、「ドイツ人労働者教育協会」(ドイツ語: Deutscher Arbeiterbildungsverein)という偽装組織を樹立していた。マルクスとエンゲルスはイギリスを視察旅行し、急進的なチャーティスト団体「友愛民主主義協会」(英語: Fraternal Democrats)との提携関係を築き、急進的な革命勢力の結集を試みるようになる。このとき選んだのが「正義者同盟」で、モーゼス・ヘス、義弟エドガー・フォン・ヴェストファーレン、フェルディナント・フライリヒラート、ヨーゼフ・ヴァイデマイヤー、ヴィルヘルム・ヴァイトリング、ヘルマン・クリーゲ、エルンスト・ドロンケ、シュテファン・ボルンらとともに「正義者同盟」との連絡組織として「共産主義通信委員会」(英語: Communist Correspondence Committee)をブリュッセルに創設し、共産主義の旗のもとに革命の同志たちを結集させようと試みた[123][124]。マルクスは民主主義の実現を目指し、貴族による封建的支配を崩壊させて民主主義を共産主義の入口にすることを運動の目標としていた[125]。

マルクスは当面はブルジョア民主主義革命に向かって活動を展開した。マルクスはチャーティストと同盟し、フランスの革命派と協力して選挙法を改正することを当座の目標として掲げ、フランスとドイツの貴族勢力の闘争を想定し、ブルジョワジーとの提携の道も模索していた[125]。
しかし、マルクスの組織運営は独裁的と批判された。実際、マルクスは組織を創設してすぐに意見が異なるヴァイトリングとクリーゲを痛切に批判して、二人を強引な方法で除名へと追い込んでいった。
ヴァイトリングはバブーフ主義とキリスト教千年王国思想を融合させた素朴な共産主義を信奉していた人物であった。だが、マルクスが念頭に置くような科学的厳密さを無視して理想を語り、四万人の前科者を結集して武装して無鉄砲な蜂起論を唱えていた。かつてヴァイトリングはマルクスの目に英雄的革命家と評価されていたが、この時期には危険な大法螺吹きに映った。したがって、マルクスは「委員会」の会合時、ヴァイトリングに「これまでおろか者が人を救ったためしはない!」と怒鳴り付けた後組織から追放、ヴァイトリング一派を粛清している[126]。そのあと、すぐモーゼス・ヘスも道徳主義と優柔不断で一貫性の欠如した主義主張で糾弾され、個人的諍い(エンゲルスの「女性関係」を参照)の後に、除名される前に辞任した[127]。
エンゲルスはマルクス主義理論の司法官的で異端審問官的な役割を果たして敵対路線とその思想を炙り出し、マルクスを支えて「委員会」におけるイデオロギー的路線を守ることに力を注いだ[128]。『共産主義の原理』(ドイツ語: Grundsätze des Kommunismus,1847)という教理問答式の小冊子を刊行した[129]。
この後、マルクスは1840年6月に『財産とは何か』を執筆し、社会主義運動において一躍注目を浴びていたプルードンを「委員会」に招待している。だが、プルードンはマルクスの独裁的姿勢を嫌い、この申し出を拒絶している。
マルクスはプルードンにひどく幻滅して敵意を抱くようになり、プルードンが1846年に『経済的矛盾の体系、または貧困の哲学』(フランス語: Système des contradictions économiques, ou Philosophie de la misère)を刊行すると、1847年『哲学の貧困』(フランス語: La misère de la philosophie)を執筆してすぐさま攻撃している。プルードンの思想は、政治不参加主義を掲げる小市民的、職人的な協同組合主義のイデオロギーで、資本主義の本質分析について歴史的背景とその展望を見据える視点に欠け、資本主義崩壊の契機とプロレタリアートの解放を提示することができない不完全な理論であった。マルクスはプルードン派メンバーカール・グリューンを除名した[130]。
相次ぐ粛清の結果で会員が減少して活動が停滞に陥るなか、転機は訪れる。
1847年6月、「正義者同盟」はマルクスの思想に影響を受け、ロンドンで大会を開催する。そして、「正義者同盟」は組織名を改称して新たに「共産主義者同盟」(ドイツ語: der Bund der Kommunisten)(1847年 - 1850年)を呼称することとなる[131]。この大会にマルクスは財政的な事情で参加できなかったが、エンゲルスが参加してマルクスとエンゲルスは同盟の新会員となり、エンゲルスはパリ支部の代表に就任した。エンゲルスはパリ代表としてその成熟した活動の戦略の形成に大きな影響を与えた。1848年、エンゲルスとマルクスは共産主義の概要に関する大衆的なパンフレットを執筆した。エンゲルスが前年に刊行した『共産主義の原理』に基づいて書かれたその12,000語あまりのパンフレットは6週間で完成させ、これをもとに『共産党宣言』(ドイツ語: Manifest der Kommunistischen Partei, 1848)と題されたこの文献は1848年2月に出版された[132]。同年3月、エンゲルスとマルクスはベルギーを追放されてドイツのケルンに移り、急進的な新聞『新ライン新聞』(ドイツ語: Neue Rheinische Zeitung) を発刊した[133]。
『共産党宣言』
[編集]
マルクスは『共産党宣言』において人類史を俯瞰して「歴史」というものが何であるかを明示した。
「今日までのあらゆる社会の歴史は、階級闘争の歴史である。封建社会の没落からうまれた近代ブルジョア社会は、階級対立を廃止しなかった。この社会はただ、新しい階級、抑圧の新しい条件、闘争の新しい形態を、古いものとおきかえたにすぎない。全社会は、敵対する二大陣営、たがいに直接に対立する二大階級にますます分裂しつつある。すなわち、ブルジョア階級とプロレタリア階級に、だんだんわかれていく。……ブルジョア階級が封建制度をうちたおすのにもちいたその武器が、いまや、ブルジョア階級自身にむけられている。……だが、ブルジョア階級は、…この武器をとるべき人々をもつくりだした。―すなわち、近代的労働者、プロレタリアを。
ブルジョア階級すなわち資本が発達するに比例して、プロレタリアすなわち近代労働者の階級も発達する。彼らは、…自分の身を切り売りしなければならないこれらの労働者は、他のあらゆる売買される品物と同じように、一つの商品である。したがってまた、同じように、あらゆる競争の浮沈、あらゆる市場の変動にさらされている。だが、工業の発展とともに、プロレタリアは…大きな集団に結集され、その力は増大し、そしてますます自分らの力を感じるようになる。機械がますます労働の差異をけしさり、賃金をほとんどいたるところで同一の低い水準にひきさげるため、プロレタリアの内部の利害も生活状態も、ますます均等になってくる。ブルジョア相互の競争の増大と、そこからおこる商品恐慌とは、労働者の賃金をますます不定なものとする。ますます急速にすすむ絶え間ない機械の改良は、労働者の全生計をいよいよ不安定なものとする。……さらに、すでに見たように、工業の発展によって支配階級の多くの組成分子がプロレタリア階級にけおとされるか、あるいはすくなくともその生活条件をおびやかされる。彼らもまた、プロレタリア階級に教養のための多くの要素を供給する。
最後に、階級闘争が決戦に近づく時期には、支配階級の内部、全旧社会の内部の解体過程は、きわめて激しい、鋭い性質をおび、……ブルジョア思想家の一部が、プロレタリアのがわにうつってくる。今日ブルジョアジーに対立しているすべての階級のなかで、ひとりプロレタリアだけが、真に革命的な階級である。その他の階級は、大工業とともにおとろえ没落する。プロレタリアは大工業のもっとも特有な産物である。個々の労働者と個々のブルジョアとの衝突は、ますます二つの階級の衝突の性質をおびてくる。……現代社会の最下層であるプロレタリアが起き上がり立ち上がることができるためには、公的社会を構成する諸層の全上部構造を空中に消し飛ばさなければならない。……おのおの国のプロレタリアも、まず自国のブルジョアジーを片付けなければならない。……それが公然たる革命となって爆発し、そしてプロレタリアがブルジョアジーを暴力的に転覆して、自己の支配権をうちたてるところまで到達した。
これまでのすべての社会は、圧迫する階級と圧迫される階級との対立のうえに立っていた。しかし、一つの階級を抑圧しうるためには、抑圧される階級に、すくなくとも奴隷的な生存をつづけられるだけの条件が保障されていなければならない。……これに反して近代の労働者は、工業の進歩とともに向上する代わりに、彼ら自身の階級の生存条件以下にますますしずんでゆく。労働者は貧窮者となり、貧窮は人口や富の増大よりもっと急速に発展する。このことから……社会は、もはやブルジョア階級のもとでは生存することができない。すなわち、ブルジョア階級の生存は、もはや社会と相容れないのである。……工業の進歩の…担い手はブルジョア階級であるが、この進歩は、競争による労働者の孤立化の代わりに、結合による労働者の革命的団結をつくりだす。だから、大工業の発展とともに、ブルジョア階級の…土台そのものが取り去られる。ブルジョア階級は、何よりもまず自分自身の墓堀人を生産する。ブルジョアの没落とプロレタリア階級の勝利とは、ともに不可避である。」[134]
以上、『共産党宣言』は「今日までのあらゆる社会の歴史は、階級闘争の歴史である。」という章句から書き出しが始まり、ブルジョア資本主義の形成を歴史的に辿り、資本主義の帰結がなにをもたらしていくかを明らかにしている。資本主義の発達と成長の結果、ブルジョワジーによる国民経済の掌握、政治的支配権の獲得は揺るぎないものとなり、資本による覇権が人民を抑圧するようになる。ブルジョワジーとプロレタリアートの階級闘争は激化し、生き残りをかけた熾烈な闘争の末、プロレタリアートはブルジョワジーを打ち負かして革命が成就し、歴史的時代区分としての資本主義の時代が終焉を迎える。マルクスは既存の章句「人類はみな兄弟」の代わりとして、最後に「万国の労働者よ。団結せよ!」との呼びかけで結んでいる。
『共産党宣言』はマルクス主義の記念碑的作品であるが、この著作のエンゲルスの役割は非常に大きかったと評価されている。エンゲルスの伝記を記したグスタフ・マイヤーはエンゲルスの果たした役割について次のように語った。
「『共産党宣言』はマルクスの天才の作である。意味深長で示唆に富む文章は、たとえば熔鉄が鋳型に流れ込むような勢いであった。こういう文章を書いたものはマルクスに違いないが、この鉄鉱を集めて来たのはエンゲルスであって、その功はマルクスに劣るものではない。というのは、『共産党宣言』の思想はすべて共著の『ドイツ・イデオロギー』(このとき未刊)に含まれているからである。そしてまたその形こそ違え、『宣言』とエンゲルスの『原理』には何の違いもないからである。」[135]
エンゲルスは、ブルジョワジーとプロレタリアートの形成と階級対立の歴史的構図を経済学に関する明晰な分析力と実社会で得た経験から導き出す力に溢れていた。マルクスの理論的体系化の天才を借りながら、エンゲルスは経済法則の原動力に沿って展開する歴史の歩みの中でプロレタリアートがブルジョワジーに取って代わる歴史的必然性を強調するとともに、『イギリスにおける労働者階級の状態』で描きだしたプロレタリアートの窮状を人類史の内部にその位置づけを提示することに成功した。
1848年革命の概略
[編集]
革命のはじまり
[編集]1845年から48年にかけて、ヨーロッパに貧農の主食となっていたジャガイモを枯らす病気、胴枯れ病が蔓延し、ヨーロッパ中に大飢饉が発生した。民衆の飢饉暴動が頻発し、ヨーロッパ各国で産業革命による貧困の拡大と飢餓の発生、食糧価格の高騰により深刻な社会不安が広がっていた[136]。
1848年1月、シチリアのパレルモで暴動が起こり、両シチリア王国からの分離独立と憲法制定が要求され、これを第一波として革命がイタリア各地に波及した。この騒乱はブルボン家の国王フェルディナンド2世にシチリアの自治と憲法制定を受諾させ、革命が成就した。イタリア発の革命の余波はフランスへと到達した。南イタリアにおける地方的騒乱はドミノ倒し状に連鎖して「ゴールの雄鶏の鳴き声」とともに1848年革命と呼ばれる欧州動乱へと発展する[137]。
フランス二月革命
[編集]1830年の七月革命の結果誕生したオルレアン王政では、選挙権の拡大が行われたものの納税額による制限選挙自体は維持されていた。そのため、議員の選挙は数百人の投票によって決定され、フランス政治は特権階級による権力の独占という様相を濃くし、密室政治と利権政治へと堕落していた。選挙権をもたない労働者・農民層の不満が高まった[138]。こうした不満のはけ口は改革宴会という集会によってある程度のガス抜きが行われていた。
1848年2月22日、政府がある改革宴会に対して解散命令を出すと、これに憤慨した労働者・農民・学生によるデモ、ストライキが起こった。翌23日には首相のフランソワ・ギゾーが辞任して事態の沈静化を図ったが、24日には武装蜂起へと発展し、ついに国王ルイ=フィリップが退位、ロンドンに亡命して王政が崩壊した。二月革命である[139]。同日、穏健な共和主義者であったラマルティーヌが指導してオルレアン左派、ブルジョワ共和派、急進革命派など左派を結集、臨時政府が組織された[140]。翌25日には臨時政府によって共和制が宣言され、フランスは第二共和政に移行する。

ラマルティーヌは、革命を前進させたい左派と既得権を守りたい右派の両派からの攻勢を受けながら、誕生間もない共和政を守らなければならなかった[141]。翌26日、ラマルティーヌは労働者階級の懐柔を図るべく高給を約束して機動隊の新兵募集を布告し、さらに国立作業場と呼ばれるモデル工場の設立に取り組み、失業問題の解決に新政府は本腰を入れることとなった[142]。
3月2日、6ヶ月以上の居住資格をもつ21歳以上の男子が参政権を認められ、革命前の25万人から最終的に900万人を有権者とする成人男子選挙制の布告のもと、憲法制定国民議会の招集が決定された[143]。ラマルティーヌは、民主主義によって労働者の不満を政治的に吸収し、オーギュスト・ブランキら極左の革命派による蜂起を予防することを意図した[141]。総選挙による保守派中心の新政府発足を予期した左派は、総選挙に猛烈に反発して選挙の実施延期を要求した。ラマルティーヌは左派の要求を拒絶し、国民の信託を受けた新政府を早期に発足させ、共和政を革命的急進主義から防衛しようとした[144]。
4月23日の選挙の結果、ルイ・ブランが辛うじて当選したもののルルーやカベなど急進革命派や社会主義者が大敗する一方、ティエール率いる秩序党(オルレアン派)をはじめ地方出身の保守派が大勝した。かくして、臨時政府の陸相カヴェニャック将軍が中心人物となっていたブルジョワ共和派など保守勢力が多数を占める新政権が発足した[145]。小市民、労働者の反対を抑え、新議会は1848年憲法を制定する[146]。
これ以降、革命を前進させようとするプロレタリアートと革命を終息させようとするブルジョワの階級対立が先鋭化していった。
5月15日、国民議会の解散を要求するデモが組織されるが、政府と国民衛兵の弾圧により解散され、これに反発する革命家のオーギュスト・ブランキとその一党は臨時政府と対立し、議会乱入を指導して逮捕されるという騒乱が起こる[147]。また、ルイ・ブランが貧困対策として立案し失業者を雇用した国立作業場が採算が合わないとして閉鎖されたことを契機に、6月23日から数日、パリの労働者が大規模な武装蜂起を起こした。これがいわゆる六月蜂起(六月暴動)である。「パンか死か」、「労働か死か」と叫び投石する民衆に対して、カヴェニャックの指揮のもと国民衛兵は4日間の流血戦を展開した。蜂起は鎮圧され、国立作業場は閉鎖、労働者側で1,500人が殺害された他、15,000人の政治犯がアルジェリアに追放された[148]。
ドイツ三月革命
[編集]

ドイツでも情勢は風雲急を告げていた。
1840年代、ドイツでは産業ブルジョワジーの成長によって、自由主義的な反政府運動が盛んに展開された。ドイツ連邦の主要大国プロイセン王国でも1845年に憲法制定の要望が声高に叫ばれていた。特に産業化の著しいライン州のブルジョワジーが憲法制定国民運動の先頭に立ち、その代表的人物にケルン商業会議所会頭カンプハウゼンやアーヘン商業会議所会頭ハンゼマンがいた。彼らは革命的気運の中で重要な役割を果たす[149]。
1848年2月27日、1848年のフランス革命に触発され、マンハイムの民衆集会が「三月要求」を策定し、ドイツにおける1848年革命の狼煙が上がった。3月1日、バーデン大公国議会の議事堂が占拠され、三月革命が始まっていく。3月4日、ミュンヘンで民衆蜂起が起こり、バイエルン王国における三月革命が始まった。革命はドイツ中を連鎖的に波及して、3月6日、ベルリンで最初の暴動が起こり、プロイセン王国における三月革命が始まった[150]。
また、中央ヨーロッパの大国オーストリア帝国にも革命が波及した。3月13日、学生の一部が議事堂に押しかけてメッテルニヒの退陣と憲法の制定を要求し、ウィーン市内に暴動が拡大した。宮廷内でも、かねてからメッテルニヒに批判的であった皇帝フェルディナント1世の叔父ヨハン大公がメッテルニヒの辞任を要求し、1815年ウィーン会議以来の反動政治の立役者であったメッテルニヒはついに辞任、ロンドンに亡命した。ウィーン三月革命である。メッテルニヒ亡命はオーストリア帝国支配下に置かれた北イタリア諸地域―ロンバルディア地方のミラノ、ヴェネティア、サルディニア王国領のピエモンテ―に伝搬し、イタリア統一運動を刺激した。しかし、イタリア動乱はオーストリアのラデツキー将軍の弾圧により鎮圧され、オーストリアによる再支配が布かれる[151]。
3月18日、プロイセン王国でも事態は緊迫化した。国王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世はメッテルニヒ失脚の報に触れると動揺し、すぐさま改革を決断する[152]。
そして、ベルリン王宮前に集まった群衆に向かって、プロイセンの改革に関する勅令を発した[153]。しかし、国王はこれまで国民の改革要求に穏健な姿勢を取っていた開明派軍人ピュールを解任し、保守派のプリットヴィッツをベルリン守備司令官に任命、万が一の革命に備えさせていた。
勅令発表の際、最初は穏やかな雰囲気であったが、やがてベルリンからの守備隊の撤退を要求する革命的スローガンの声が大きくなる。プリットヴィッツはこれを革命の始まりと捉え、国王を守るべく群衆に解散を命じた。このとき、2発の銃弾が発射され、デモ隊の雰囲気が一転し、群衆の抵抗は軍隊に矛先を転じる[152]。ベルリン三月革命の火蓋が切られた。激昂した群衆によってアレキサンダー広場にバリケードが築かれ、激しい市街戦の末、死者数百人が発生した。掃討作戦は困難を極め、軍の士気低下と命令拒否が見られたため、バリケードの撤去を条件に守備隊の撤退を決定、国王は革命に譲歩を示した[152][154]。
19日、国王は王宮中庭で殉難者の棺の前で脱帽するよう強制され、21日には「黒・赤・金」三色旗[注釈 3]の記章を身に着けてベルリン市内の騎馬行進を行い、「ドイツの自由、ドイツの統一」を望む旨を宣言する。国王は連合州議会の召集、検閲の廃止による思想・言論・出版の自由の保障、憲法の制定を認め、ドイツ連邦の改革を認めた。こうして国民運動の指導者であったカンプハウゼンに組閣大命が下り、自由主義を奉ずる産業ブルジョワジーによる臨時政権が成立した[155]。

しかし、国王・軍部が自由主義的改革に対して終始反対であったことには変わりなかった。プロイセンの東部ボーゼンのポーランド人の蜂起やシュレースヴィヒ・ホルシュタイン公国のドイツ人の蜂起とデンマーク王国との第一次シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争はヴランゲル将軍の活躍により優勢を保って停戦に至った[156]。こうした軍事衝突事件は軍部に対する世論の信任を回復させ、カンプハウゼン内閣の逆風となっていく。反革命を標榜し精強を誇っていた軍部に対する臨時政府の統制権は機能せず、政権土台の不安定化を進めた[155]。またブルジョワジーの保守派への転向も相まって、革命を終わらせようとするブルジョワジー対革命を推進しようとするプロレタリアートとの階級対立が激化、改革派の分裂が始まり保守派に付入られる隙を作ってしまう[157]。
5月25日、プロイセン国民議会で軍制問題の審議がなされる中、改革派内部の溝は広がり続けた。常備軍の廃止と市民軍の創設の是非を巡る問題で決定的状況が生じる。プロレタリアートを支持母体とする急進派は全人民の武装を要求、臨時政権がこれを拒絶したため、6月14日、労働者はベルリンの兵器庫を襲撃する[158]。
このときの襲撃は鎮定されたが、ベルリン兵器庫襲撃の責任をとってカンプハウゼンが辞任に追い込まれる[158]。その後、保守系政府と軍部の主導権争いの中で数度にわたる政権交代が見られ、11月2日、国王はブランデンブルクを首相に大命を下し、首相は内相マントイフェルとともに組閣をおこなって、ここにブランデンブルク=マントイフェル反動内閣が成立した。11月14日にヴランゲル将軍はプロイセン国民議会を解散させ、改革の息の根を止めた。また、12月5日に国王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世は国王大権を温存する欽定憲法を発布し、1849年5月30日に保守派に有利な三級選挙法を制定した[159]。
1848年革命とエンゲルス
[編集]『新ライン新聞』とマルクス、エンゲルス
[編集]マルクスとエンゲルスは、1848年革命にすぐさま反応し、革命運動に参加していった[160]。
彼らは1848年革命が全ヨーロッパ諸国を巻き込んだブルジョア市民革命として完遂され、その後に続くプロレタリアート革命への移行と発展の条件になることを期待した。フランス二月革命の勃発の報に触れると、マルクスは亡父の遺産を使って武器の調達を進め、蜂起に備えようと計画を進めた[151]。しかし、ベルギー国王レオポルド1世は警戒のために諜報を強化して危険分子の摘発に力を注ぐよう叱咤した。やがて、マルクスの蜂起計画はベルギー官憲の関知するところとなり、マルクスは検挙されてしまう。マルクスはベルギーからの24時間以内の国外退去処分を申し渡され、革命直後のパリへと逃れることとなった[151]。パリへと退去したマルクスとエンゲルスは、フランス臨時政府のメンバーとなっていた社会主義者ルイ・ブランと急進派のジャーナリストフェルディナン・フロコンから熱烈な歓待を受けることとなる。エンゲルスはフロコンが発行する『ラ・レフォルム』(仏: la Réforme)に寄稿しており、パリでは英雄扱いとなっていた[161]。
その頃、マルクスはドイツに革命を輸出する方法を模索していた。「共産主義者同盟」は、3月下旬から4月上旬にかけてメンバーを次々とドイツ各地に工作員として送り込んだ[162][163]。亡命ドイツ人はライン川を次々に越え、祖国に民主共和国を実現させようと帰国していった。幸いフランス臨時政府フロコンの協力を得て、亡命ドイツ人は一日50サンチールの支給を受けて活動をすることが可能となり、「同盟」は亡命ドイツ人を「ドイツ労働者クラブ」のもとに組織し最終的に300人をラインラントに送りこむことに成功した[164][165]。エンゲルスは父と父の友人となっていた資本家たちから革命資金を募ろうとヴッパータールに向かった[166]。マルクスとエンゲルスはドイツ革命運動急進派の最左翼として革命に参加しようと試み、言論運動を展開しようとする。
しかし、ドイツはイギリスやフランスのような二国とは異なり、産業革命が遅かったためブルジョワジーの経済覇権の掌握も政治的支配権の獲得も遅れ、ようやくウィーン会議の反動体制を克服したばかりで、封建君主に止めの一撃を加えてはいなかった。したがって、マルクスは即座の共産主義の実現に慎重論を唱え、『ドイツにおける共産党の要求』を執筆、軽挙妄動を制止しようと試み、まずはブルジョア民主主義を導入しようと考えた。マルクスの政治的立場はブルジョワ市民革命を経由してのプロレタリアート社会主義革命を目指す二段階革命論に根差していた。したがって、当面はカンプハウゼン臨時政府と提携してプロイセンの脆弱なブルジョワ勢力を強化し、体制改革を推進しながらプロイセン王国の封建的旧体制を打破することに専念する、それが活動目標であった[165]。

ドイツにおける革命の動きは当初期待通りに展開した。2月以降、テュイルリー宮放火事件、飢餓の蔓延、食糧価格の高騰などが深刻な社会不安を醸成し、ついに革命はバーデン大公国やバイエルン王国に飛び火し、ベルリンも一足触発の状況を呈するようになり、ベルリン三月革命へと至る。そんな中、マルクスとその家族は4月上旬にプロイセン領ライン地方の大都市ケルンに入った[166]。革命扇動を行うための新たな新聞の発行準備を開始したが、苦労したのはやはり出資者を募ることだった。ヴッパータールへ資金集めにいったエンゲルスはほとんど成果を上げられずに戻ってきた[167][168]。結局マルクス自らが駆け回って4月中旬までには自由主義を奉じるブルジョワの出資者を複数見つけることができた[167][169]。新たな新聞の名前は『新ライン新聞 - 民主主義の機関紙』(独: Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie.)と決まった。創刊予定日は当初7月1日に定められていたが、封建勢力の反転攻勢を阻止するためには一刻の猶予も許されないと焦っていたマルクスは、創刊日を6月1日に早めさせた[169][170]。同紙はマルクスを編集長として、エンゲルスやシャッパー、ドロンケ、フライリヒラート、ヴォルフなどが編集員として参加した[167][170]。また、『新ライン新聞』は競合紙の『ケルン新聞』よりも安価で発行され、しだいに大衆の心を掴んでいく[171]。
とはいえ、マルクスとエンゲルスの前に立ちはだかる障害物もあった。それは例の如くであったが、体制派の柔軟な妥協であり、ブルジョワの不甲斐なさであり、そしてプロレタリアの不統一であった。同じ急進的革命派の中にも対立構造はあり、ケルン労働者連合を組織していた職人革命家アンドレア・ゴットシャルクの素朴共産主義の運動と衝突する。ゴットシャルクの立場は史的唯物論などの理論的見地に基づくものではなく、即座の革命によってプロレタリアの支配を確立し、協同組合による共同体生活を想定したプルードン主義的な共産主義思想であった。マルクスはゴットシャルクの運動を封じるために対抗組織として「ケルン民主主義協会」を設立、穏健なブルジョワ民主主義の政治目標を掲げてプロイセン政府に対する非難の声をあげた[172]。ドイツの革命における真の敵は封建主義勢力だったのである[173]。
だが、1848年4月にはチャーティストによる国民請願が早くも棄却され、フランスでは4月23日の総選挙では保守派が復活を遂げる一方で社会主義者が惨敗した他、反革命派の巻き返しによって情勢は急速に反動化していく[174]。
革命の反動化と流転のはじまり
[編集]ベルリン兵器庫襲撃事件と6月蜂起以降、革命の反動化と共に、『新ライン新聞』への逆風が強まり、マルクスは治安判事から出頭命令が発せられ、毎週のように裁判所に呼び出されていた。7月7日には検事侮辱および反乱扇動の容疑でマルクスの事務所に強制捜査が入り、起訴されるに至る[175]。だが、マルクスとエンゲルスは自分の立場を堅持した。ケルンでは革命の機運が高まっており、労働者は治安委員会を設置し、フーリンガーハイデで大規模な集会を開催、プロイセン政府との対決姿勢を強めた。9月17日、8000人の労働者と社会主義者がライン川を上ってケルンに集結し、決起の時期を待っていた。こうした情勢にあってプロイセン政府は先手を打ち、9月25日にケルンに戒厳令を発した。集会は禁止、市民軍は解散され、新聞発行に停止命令が出された[176]。「共産主義者同盟」のメンバー、『新ライン新聞』の発行者に逮捕状が出された。シャッパーやベッカーが逮捕され、エンゲルスにも逮捕状が出たが、彼は行方をくらました[177]。
だが、エンゲルスはバルメンに立ち寄った後、ベルギーに向かいエルンスト・ドロンケと共に潜伏していたところをベルギー官憲に逮捕されてしまう。1848年10月5日、パリ行の列車で移送され、フランスへと追放されることとなる[178]。11月に入る頃、フランスでは1848年憲法が制定され、ルイ・ナポレオンが大統領候補に立候補する情勢にあり、確実に共和派勢力は衰退する方向に向かっていた。オーストリアでも軍が議会を解散し、チェコの中心地プラハや北イタリア諸国に侵攻し、革命派の一掃を図った。エンゲルスは革命の前途に失望してパリを離れ、反革命に向かうヨーロッパを流離う逃亡生活に入る[179]。ただし、エンゲルスにとって逃亡は惨めではなかった。その逃亡生活の実態はフランスからスイスに向かっての気ままな徒歩旅行であった。エンゲルスはブルゴーニュの美しい風景とワイン、美食を堪能し、宿泊した先々で出会う女性を次々と口説いて旅を楽しんでいた。エンゲルスはフランス紀行誌を書きながら南に向かって歩き、楽しみ、飲んで食べて、美しいブルゴーニュ女性を愛する旅の人となっていた[180]。息子を心配する母からの仕送りに頼りながら、エンゲルスはスイスに入って潜伏生活を送ることになる[181]。
ケルンではマルクスが『新ライン新聞』の発行を続け、革命派に最期の抵抗を呼びかけていた。プロイセン政府は革命派を追い詰めるためにラインに軍を派遣し、戒厳令を出し、新聞を発行停止にしたが、マルクスはこの動きに猛然と反発し、闘争心に欠くブルジョワ勢力を見限り、政府の弾圧に対してテロによる応酬を主張した。マルクスの不屈の姿勢は潜伏中にあったエンゲルスを励ました[182]。エンゲルスはコシュート・ラヨシュによる1848年ハンガリー革命に関心を注ぎ、ナショナリズムの高揚によって、ハプスブルク支配と闘争する諸国民の民族運動に鼓舞された。エンゲルスは騎士や革命家、英雄的な軍人指導者に憧れがありコシュートの活躍に熱狂してしまう[183]。ハンガリーやシュレスビッヒ地方での各地の紛争について『新ライン新聞』に寄稿し、ナショナリズムは歴史的大義であるとする論評をおこなった[184]。元来活動派のエンゲルスはスイスでの自由な亡命生活にすぐに飽きていたため、しだいに革命運動への復帰を願うようになる。12月にはエンゲルスはゴットシャルク、フリッツ・アネケなど革命の同志たちが釈放されたという情報を得て、ドイツに帰郷する決意を固める[185]。『新ライン新聞』はエンゲルスの期待通り、以前より攻撃的な革命論を展開しており、同紙の急進化を歓迎した[182]。
革命運動とエンゲルス
[編集]1849年1月、エンゲルスがスイスでの潜伏地を離れてケルンに戻ってきた[182]。

その頃、『新ライン新聞』はブルジョワとの迎合を批判し、大衆蜂起と革命、ゲリラ戦により抵抗を呼びかけ、プロイセンとの対決姿勢を強めていた[182]。3月、フランクフルト国民議会はパウロ教会憲法を制定し、国王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世に帝冠を授けることを決定する。しかし、王権神授説を信奉するフリードリヒ・ヴィルヘルム4世は立憲君主制を嫌悪しており、この申し出を拒絶した[186]。革命派の最後の希望は絶たれることとなる。これを機にライン地方は急激に革命化していく。ライン地方からバーデン大公国に至る西南ドイツは共産主義者による暴力革命の機運が高まった。さらに決定的な事件が東ドイツのザクセン王国で発生した。4月28日、ザクセン王フリードリヒ・アウグスト2世が議会を解散するとこれをきっかけにドレスデンで革命騒擾5月蜂起が発生した。ミハイル・バクーニン、シュテファン・ボルン、リヒャルト・ワーグナーがこの闘争に参加している。しかし、ザクセン軍とプロイセン軍の部隊が鎮圧にあたり、蜂起は失敗に終わった[187]。
プロイセン政府はラインラントの情勢が安定しているという判断のもと、1849年春にヴェストファーレンとラインラントにおいて予備軍を召集した。兵員召集は戦時に限り実施されるもので、平時では違法と考えられていたため反発を招いた。プロイセン国王は、邦議会第二院が1949年3月27日にパウロ教会憲法草案への支持を表明したため議会を解散しており、大小ブルジョワジーとプロレタリアートを含むラインラント市民各層が、期待に反して反故にされた政治改革の擁護のために立ち上がっていく。5月蜂起を機に革命はライン地方に飛び火し、各地の都市では市民軍が組織され、プロイセンの守備軍に撤退要請が出されるなど反乱状態に陥っていく[188]。
1849年5月9日、ラインラントのエルバーフェルト(現ヴッパータール)、デュッセルドルフ、イーザーローン、ゾーリンゲン市で蜂起が起こり、エンゲルスは故郷の地で盛んになった革命闘争に参加していく。翌10日デュッセルドルフが脱落するが、反乱地域一帯はプロイセン王国から離反を決め、各都市の街路にはバリケードが建設されていく。反乱を起こした市民を組織化するために、公安委員会 (独: Sicherheitsausschuss) が市内に組織された[189]。公安委員会のメンバーには、エルバーフェルトの民主派弁護士のカール・ニコラウス・リオッテ、エルンスト・ヘルマン・ヘーヒスター (委員長に選出) 、エルバーフェルトで検事も務めた弁護士で自由主義者のアレクシス・ハインツマンが含まれていた[190]。エンゲルスは各地で購入した武器弾薬を持参して公安委員会に出頭し、革命家として名乗りを上げた。そして、各地の労働者に招集をかけて組織した土木工兵の一隊を率い、ヴッパー川に架かるハスペラー橋にバリケードを築き、市街の防衛力を強化した。しかし、エンゲルスは政治上の立場に関して公安委員会から審査を受けた際に共和派に順ずるという誓約を破っていく。彼はハスペラー橋のバリケードに無断で「黒・赤・金」のドイツ三色旗の代わりに赤旗を掲げた[190]。公安委員会からのエンゲルス排斥が決まり、彼は立ち退き勧告を突きつけられて、ヴッパータールを離れることとなった[191]。一週間後、ヴッパタールはプロイセン軍が占領し、赤旗とバリケード群を撤去して、市民軍を武装解除させた[192]。

ドイツ革命の最終局面は南西ドイツの革命運動の激化にあった。
バーデン大公国とバイエルン王国領プファルツ地方で発生したプファルツ蜂起が拡大を見せていた[193]。とうとう、隣国バーデンの革命派が大公を追放するに及ぶ。亡命を余儀なくされた大公はプロイセン軍に介入を求めた。マルクスは『新ライン新聞』で各地の武装蜂起をドイツ革命の好機として報じ、プロイセンに対する抵抗を呼びかけた。5月16日、プロイセン政府は『新ライン新聞』のメンバーに国外追放処分を下し、新聞の出資者だったブルジョワ自由主義者もこの頃までにほとんどが逃げ出していた[194]。ついに、同紙は廃刊を余儀なくされ、マルクスは5月18日の最終号を全面赤刷りで出版した[192]。
マルクスとエンゲルスはフランクフルトからバーデン大公国へと放浪し、プファルツでの反乱に加わる計画を立てた。二人は結局、バーデンの革命政府と合流したが、プロイセンの軍事介入の脅威を指摘したところ、スパイと誤認されて投獄された。二人はすぐに釈放されたが、マルクスはパリへと逃亡してしまう[193]。
エンゲルスもマルクスの後を追うことにしていたが、元プロイセン軍人アウグスト・ヴィリヒがカイザースラウテルンで800名の学生に軍事訓練をおこない武装蜂起したのである。エンゲルスはプファルツの革命派学生に共鳴して蜂起に参加、軍事に明るいエンゲルスはヴィリヒの副官として革命戦争に参加することになった[195]。革命軍は各地でプロイセン軍と抗戦し、バーデン第二の都市カールスルーエ南方に位置するラシュタット要塞に1万3千の兵力を結集して籠城した。プロイセン軍は4倍の兵力で要塞を攻略、このとき「共産主義者同盟」の創設メンバーの一人ヨーゼフ・モルが戦死するなど、革命軍に多大な犠牲が生じた。エンゲルスは残党勢力を集め、南のシュヴァルツヴァルトを通って追手を交わしスイスへと逃亡した[196]。マルクスはエンゲルスの輝かしい軍歴を称えた[197]。エンゲルスは同志の賞賛に応えて1849年8月から50年2月にかけて『ドイツ国憲法戦役』(独: Die deutsche Reichsverfassungskampagne,1849-1850)を執筆した。エンゲルスは革命時におけるブルジョワとの共闘路線と二段階革命論を放棄し、ブルジョワの反動化が見られた時点において革命を守るため封建勢力と共にブルジョワを打倒する必要性を説いた[197]。マルクスもまた1850年に『フランスにおける階級闘争』(独: Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850)を執筆、革命の契機と失敗に関する唯物弁証法に基づく洞察をおこなった。マルクスは6月蜂起とその後の反動を「労働者と資本の間の戦争」として描写し、二月革命を階級闘争の生成と敗北とする歴史認識を打ち出した[198]。
6月初旬にマルクスはフランスに入国して逃亡生活をしていたが、フランス警察の外国人監視が強まり、ブルターニュ地方のポンティノ湿地に流刑に処すと脅されたため、フランスからも出国する覚悟を固めた。ドイツにもやベルギーにもスイスにも入国を拒否されていたマルクスを受け入れてくれる国はブリテン以外にはなかった。ピエモンテ経由でジェノヴァへ向かい、1849年8月27日、航路でロンドンに向かった。エンゲルスはスイス亡命中、執筆の傍らいつもの如く女と酒に溺れる日々を送っていたという。1849年10月5日、エンゲルスもジェノヴァから航路で大陸を離れ、11月12日にはエンゲルスもマルクスを追いかけるようにロンドンへと向かい、以降40年間をブリテンで生活することになった[199]。
二度目のブリテン時代
[編集]共産主義者同盟の壊滅
[編集]
1849年までに、二人はドイツのみならず大陸各国から追放され、やむなく英国に渡った。プロイセン当局は英国政府に対して、エンゲルスとマルクスを追放するように圧力をかけたものの、当時の英国首相ジョン・ラッセルは表現の自由に関してリベラルな考え方を持っていたためその要請を拒否した。
1848年の革命の機運が収束しヨーロッパの革命的情勢が後退して以降、英国はその後の生活の拠点となった。しかし、マルクスとエンゲルスは経済的に困窮していた。マルクス一家は貧困外国人居住区だったソーホー区のディーン通り28番の二部屋を賃借りての生活を余儀なくされた[200][201][202]。生計を立てる手段が得られず、やがてマルクスは生計をエンゲルスからの定期的な仕送りに頼らざるを得なかった。しかし、ロンドンに移ったこの時期の窮乏状態は厳しく、三人の子どもを飢餓と病気で失っている。マルクスは、他の友人(ラッサールやフライリヒラート、リープクネヒトなど)への不定期な金の無心、金融業者から借金、質屋通い、元フーリエ派でアメリカの進歩的な奴隷解放論者が発行していたアメリカの新聞『ニューヨーク・トリビューン』(英: New-York Tribune)への寄稿でなんとか保った。エンゲルスはチェルシー、次いでソーホーのマックスフィールド通りに居住、一時的に自由な亡命者生活を満喫した。しかし、彼もまたロンドン亡命の直後はマルクスと同じく無収入の境遇に置かれ、プロイセンのスパイに監視される中で貧困生活に耐えることになった[203]が、マルクスとエンゲルスは1848年革命の理論的考察を加えて互いの執筆事業を進めた。
1850年、ロンドンに移り住んで間もなくエンゲルスは『ドイツ農民戦争(歴史書)』(ドイツ語: Der deutsche Bauernkrieg)を執筆した。本書にはエンゲルスの歴史観が描写された。1524年、トマス・ミュンツァーは現状維持を志向したルター派の宗教改革運動に疑問を抱き、シュヴァーベンの貧しい農民による蜂起に合流して「地上における神の王国」を実現させる運動を展開する。これがドイツ農民戦争である。1525年、貧しい農民(農奴)を解放して救済しようとするミュンツァーの闘いはシュヴァーベンの領主と同盟したマルティン・ルターによって打倒される。エンゲルスにとって象徴的意味を持った歴史事変であった。エンゲルスはこの闘いを階級闘争として捉え直していく。共産主義的な平等の王国を実現するには経済的準備が出来ておらず、時期尚早の蜂起であった。封建的な農業経済を産業革命によって脱却して、近代産業に基づく資本主義の確立によって自然的制約を超えた工業社会の到来の兆しを待たねばならず、時宜を得られなければ持つ者と持たざる者の闘争は現実性を持ち得ないという認識が語られている。したがって、ミュンツァーの闘いはルター派の鎮圧軍によって撃破され、多大な犠牲を出して屈服させられたわけである。ミュンツァーの闘いとその敗北は、革命には歴史的な時節の到来を待望する姿勢が必要であり、確かな歴史的展望を培って待機と備えをした上で、ブルジョワの裏切りに抵抗しなければならないという教訓史をなしていた。エンゲルスはドイツ農民戦争を手がかりに、ヴィルヘルム・ヴァイトリングが説いた即時の共産主義実現という挑戦の無謀さと危険性を指摘し、経済的条件を持たない革命は決して成功しないという考えを同志たちに提示しようとしたのである[204]。
二人は「共産主義者同盟」の再建に取り組むことになる。
しかし、組織再建は困難を極めた。「同盟」中央委の人事争い、ロンドンの「ドイツ人労働者教育協会」の会員資格問題、亡命者支援基金の分配金を巡る争いが再建を困難にした。さらに、1850年に採択された「中央委から同盟員への呼びかけ」で、エンゲルスは「ブルジョワの裏切り論」を下地に「永続革命」によるプロレタリアートの支配権確立のため闘争を継続するように訴えたが、闘争の方法論を巡って内部対立が生じていた。「同盟」には即時蜂起を求めるカール・シャッパーとアウグスト・ヴィリヒのグループと恐慌によってブルジョワ資本主義社会が破局する時節の到来を待望するマルクスとエンゲルスのグループに分裂していった[205]。マルクスは同盟中央委をドイツのケルンに移転させて政敵の干渉を最小限にしようとしたが、ドイツ側にもマルクスと剃りが合わないゴットフリート・キンメル、アーノルド・ルーゲらのグループがおり、マルクスとエンゲルスは完全に孤立状態に置かれる。しかし、中央委の移転は「共産主義者同盟」の壊滅につながっていく。1851年5月から6月にかけて共産主義者同盟の著名なメンバー11人が大逆罪の容疑でプロイセン警察によって摘発された。ケルン共産党事件である。この事件を受けて、マルクスも「共産主義者同盟」の存続を諦め、1852年11月17日に正式に解散を決議した。

ビジネスへの復帰と二重生活
[編集]エンゲルスはマルクス同様、困窮に苦しんでいた。エンゲルスの両親は、革命運動に傾倒したために、逮捕状が出され追われる身となった息子に手を焼いて金銭援助を止めざるを得ない状況に陥った。しかし、エンゲルスもついに音を上げて、自身と友人マルクスを救うために、渋々家族に頭を下げて仕事の面倒を見てもらうことにした。妹マリーが仲介役となって「兄も反省しているから」と言って父親を宥め、父親も「フリードリヒにとっては不本意であろうが、息子の復帰は家業のためになる」として息子の要望を受け入れ、遂に和解するに至った。かくして、エンゲルスは工場のあるマンチェスターで臨時働きのつもりで家業「エルメン&エンゲルス商会」に復帰した[206]。
マンチェスターはチャーティズムの本拠地であり、英国社会主義の中心地であった。だが、1850年代の英国の経済はヴィクトリア時代中葉の長い好景気のルートに入り、その過程でチャーティズムの崩壊が進んでブルジョワ支配は揺るぎのないものになっていった。『共産党宣言』の英訳がジョージ・ジュリアン・ハーニーが発行する『レッド・リパブリカン』紙(英: The Red Republican)に掲載されたものの反響は芳しくなかった。英国の労働者階級は好調な経済の恩恵を受けて熟練労働者を中心に所得を増やし、未熟練労働者との両極分解が進んでおり、階級的自己意識とその革命的性格を急速に喪失していたのである[207]。


一方で好調な綿産業の発展とともに「エルメン&エンゲルス商会」も事業の成長に成功していった。「エルメン&エンゲルス商会」はペーター、ゴッドフリート、アントニーのエルメン兄弟とフリードリヒ・エンゲルス(父)との共同事業体であった。この共同事業は絶えず経営権を巡る社内対立を招き、この緊張関係は業績の伸長と共に次第に激化していった。フリードリヒ・エンゲルスは父の意を受けて社内の財務状況の調査を開始し、内部監査役として活躍して父親の経営権を擁護した。経営への参画を通じてエンゲルスは父親と和解していき、1851年6月には父親とマンチェスターで対面できるまでにその関係を改善させている[208]。
エンゲルスは、会社の帳簿と対話する財務管理と工場経営に精勤して生活を再建させたが、1850年代のエンゲルスの給料は年100ポンドを超えることはなかったと見られている。また、父の代わりにマンチェスター工場の財務をやり繰りしなければならなかったので、マルクスに送る資金にも限度があったが、巧みな語学と持ち前の経営能力を発揮して1850年から1860年は一般社員、1860年から1864年まで業務代理人、そして1864年から1869年は支配人として勤め、共同経営者の地位にまで上り詰めた。最終的に年1500ポンドを稼ぐ富裕な中流階級の名士となり、マンチェスターのドイツ人社会の頂点に駆け上がった。彼は十数年の間に流浪の革命家から名誉ある高級社会の一員へと出世を果たしたのである[209]。シラー協会の会長を務め、高級馬を所有して名門有力者が集うチャンシャー・ハウンズにおけるキツネ狩りを楽しみ、名門のアルバート・クラブやブレイズノーズ・クラブの会員となっていた[210]。
昼間は工場経営に従事する一方、夜は科学的社会主義の研究を進めるという望まぬ「二重生活」に入っていく。会社経営の実態、雇用や人事評価をめぐる精神面での矛盾とジレンマは深刻なものとなり、エンゲルスの心情を傷つけるものとなった[208]。
しかし、エンゲルスは、政治経済問題や国際情勢について多くの新聞と雑誌からの活発な情報収集を通じて秀逸な分析を継続した。殊に、世界の戦争に関する軍事情勢分析には抜群の才を発揮し、この分野では、時にはマルクスに代わって情勢論文をマルクスの名で新聞社に寄稿することもあった[211]。1860年代には自身も体調不良に苦しんでいたが[212]、マルクスの仕事のために情報収集と提供を依頼され、英作文が苦手なマルクスのために執筆を代行して彼の仕事に尽くしていた[213]。
このようなマンチェスター時代の「二重生活」は、約20年間に及ぶこととなった。エンゲルスは、その間に得た報酬の半分以上を浪費癖の治らないマルクスに送金した[注釈 4]。マルクスは新聞への寄稿の謝礼に加えてエンゲルスからの送金で窮地を脱し、惨めなソーホーでの生活を抜け出し、中流階級が居住する郊外住宅で暮らすようになる。1856年、ロンドン北部ケンティッシュ・タウンのグラフトン・テラス(英: Grafton Terrace)9番に転居し、1864年3月にメイトランドパーク・モデナ・ヴィラズ1番(英: 1 Modena Villas, Maitland Park)の一戸建ての住居を借り、1875年春には近くのメイトランド・パーク・ロード41番に引っ越した。エンゲルスは度々の引っ越しと不相応に贅沢な暮しをしていたマルクス家の生活を支援した。亡命者として政府の監視の下で浪費と貧困の繰り返しの生活を営んでいたロンドンのマルクスとその家族の生活を何度となく救ったのはエンゲルスの財政的支援であった[214]。
また、エンゲルスはマルクス家の家庭環境も守った[215]。1851年にマルクスはディーン通りの家でメイドヘレーネ・デムートとの間にフレデリック(フレディ)・デムートを儲けた。エンゲルスはマルクスの隠し子のためにファーストネームを与え、あたかもエンゲルスが本当の父親であるように偽装するなど公私に渡って犠牲を払った[216]。結局、フレディはエンゲルスにもマルクスにも子どもとして認知されず里子に出され、ロンドンで旋盤工として暮らしていくことになる[217]。
中年期以降の活動
[編集]反動とのたたかい
[編集]この節の加筆が望まれています。 |


1851年12月2日、フランスでは大統領ルイ・ナポレオンによるクーデターがあり、主だった議員が逮捕された。ルイ・ナポレオンは国民投票によってクーデターへの信任を得て、事件からちょうど一年後に皇帝に即位、ナポレオン3世を称して第二帝政を開始する。マルクスは『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』(ドイツ語: Der 18te Brumaire des Louis Bonaparte)を執筆した。
上書執筆の経緯は、共産主義者同盟の古くからの同志であったジョゼフ・ヴァイデマイヤーから、1851年12月2日のクーデターに関してニューヨークで発行を計画中の週刊誌への寄稿を求められたことに起因する[218]。ヴァイデマイヤーはマルクスと同い年の友人で、プロイセン軍の士官であり、ジャーナリストであった。1846年にはブリュッセルで設立された共産主義通信委員会に参加し、正義者同盟から改称した共産主義者同盟にも参加していた。1848年革命に参加し、翌年49年『新ドイツ新聞』の編集者となった。1851年にアメリカに亡命した後は新雑誌『革命(ディ・レヴォルティオーン)』(独: Die Revolution)の創刊を目指して活動し、マルクスに論文の寄稿を依頼した[219]。12月16日、マルクスはマンチェスターにいたエンゲルスに相談を持ちかけたところ、エンゲルスから論文を執筆してみてはどうかという提案がなされた。そのときの手紙でエンゲルスは次のように語っている。
「今日昼に受け取ったヴァイデマイヤーの手紙を同封する……金曜日の晩までにかれのところへ論文を送ってくれという要求はちと無理だ、―とくに今の状態では。しかし、今こそ人々はフランス史について論断とよりどころを切に求めているのだ。そして、ここで情勢について何かはっきりしたことをいうことができれば、それで彼の企画が最初の号で成功するということになろう。だが、厄介なのはそういうものを書くということだ、そしていつものように難しいことは君に任せる。僕が何を書くにしてもクラピュリンスキーのねらいうち(ボナパルトのクーデター)ではないことだけは確かだ。いずれにしてもそれについて君は彼に外交的に退路を残した画期的な論文を書いてやることができる」[220]
マルクスとエンゲルスのナポレオン三世に対する敵意は根深く、彼をヨーロッパの革命を破滅させた張本人と見ていた。二人はフランスと全世界の自由に敵対するナポレオン三世を打倒することが革命の事情と考えた。マルクスはエンゲルスの助言で早速執筆に取り掛かり、12月19日、ヴァイデマイヤーに第一章を送付することを約束した。この約束は病気のために果たされなかったが、明けて1月1日に最初の原稿が、2月13日に続きが送られた。その間、ヴァイデマイヤーの週刊誌発刊の計画は資金面の障害により挫折していたが、マルクスは諦めずに執筆を続け、三月中で全部の原稿が送られた。5月、ヴァイデマイヤーの不定期雑誌『革命』第一号に掲載された[221]。
「将軍」エンゲルス
[編集]
エンゲルスは青年期に軍隊経験があり、1848-49年にはドイツ革命に参加し、プファルツ・バーデン革命政権を守るため革命戦争に従軍していた。こうした背景もあってとりわけ軍事史に強い関心を向けていた。多忙なビジネスライフの合間、軍事戦略や地政学、武器や軍事技術を研究するようになった。英雄史観を拒絶して唯物史観の体系化に尽力しながらも、ウェリントン公爵やチャールズ・ネイピア(海軍大将)、ガリバルディなどの軍事的英雄に対しては深い敬意を抱いて彼ら名将を崇拝していた[222]。
クリミア戦争に関する評論は好評とはならなかったものの、地政学分析の書であった『ポー川からライン川』は優れた評論として高い評価を得た[223]。その論旨はドイツ統一の実現のために、ドイツ民族は軍事上重要なポー川とライン川をフランスから防衛しなければならないとするものであった。ナポレオン3世は1859年にサルデーニャ王国宰相カミッロ・カヴールと連携して北イタリアを支配するオーストリア帝国に対する戦争を開始した。イタリア統一戦争と呼ばれるこの戦争はフランスで反動政治をおこなう専制君主ナポレオン3世がやはり反動国家のオーストリアと衝突して、イタリア民族運動を支援するというものでナショナリズムの前進には積極的意味があったが、ドイツ民族の敵がイタリアに勢力拡大を図っていると見なせるものであった[224]。
この戦争をめぐってエンゲルスは小冊子『ポー川とライン川』を執筆し、これをラッサールの斡旋でプロイセンのドゥンカー書店から出版した[225][226]。この著作の中でエンゲルスは「確かにイタリア統一は正しいし、オーストリアがポー川(北イタリア)を支配しているのは不当だが、今度の戦争はナポレオン3世が自己の利益、あるいは反独的利益のために介入してきてるのが問題である。ナポレオン3世の最終目標はライン川(西ドイツ)であり、したがってドイツ人はライン川を守るために軍事上重要なポー川も守らねばならない」といった趣旨の主張を行い、オーストリアの戦争遂行を支持した。マルクスもこの見解を支持した[227]。しかし、二人の主張は軍事色を強めていくナポレオン3世を批判するあまり、イタリア統一運動を妨害して長年にわたってハプスブルク家によってイタリア支配をおこなうオーストリア帝国を支持しているかのように感じさせものであった。このようなマルクスとエンゲルスの態度には社会主義者であったラッサールでさえもオーストリアによる諸民族のナショナリズム蹂躙という状況を肯定しているという悪印象を与えるものだった。
社会主義者同士の不信感が高まるなか、大国間の対立もエスカレートしていた。ナポレオン3世のイタリア統一戦争への干渉は英仏間の対立も招いたのだ。
政治的緊張の中でブリテン南部の沿岸部各地に義勇軍が集結していった。エンゲルスはこの義勇軍を高く評価した。しかし、義勇軍部隊の多くが富裕な市民で実態はクラブ活動のようなもので完全にブルジョア部隊であったが、エンゲルスは義勇軍の階級的性格を無視して絶賛していた。軍事的活動や戦争に関してエンゲルスは好戦的な性格が強く、ワーテルローの戦いのような決戦で勝敗と共に善悪が決する最終戦争が起こるのを密かに願っていた[228]。
ナポレオン戦争が再来してナポレオン3世が破滅するという期待と見解は英仏戦争ではなく、普仏戦争という形態によって現実化した。普仏戦争に関するエンゲルスの分析は極めて優れたものであった。エンゲルスは布陣や会戦地点に関する予想を的確に分析し、予測を『ペル・メル・ガジェット』(英: The Pall Mall Gazette)という雑誌に掲載した。その結果、エンゲルスは一流の軍事評論家として認められ、マルクスやその他の友人たちから「将軍」のニックネームで呼ばれるようになった[229]。下記「普仏戦争とエンゲルス」を参照のこと。一方、エンゲルスは帝国主義や植民地支配に反感を抱いていたことで知られている。これについても下記「危機と再編の時代」の項目で後述する。
『経済学批判』への協力
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
『経済学批判』序文への協力
エンゲルスは、マルクスの頭脳の偉大さを認め、早い時期からマルクスの理論の発展に対して重要な助言者の役割を担ってきた。
マンチェスター時代には、エンゲルスは、マルクスの主著『資本論』を完成させる上でこの上なく重要な助言者となった。資本主義経済の渦中で有能な経営者として頭角を現しつつあったエンゲルスは、マルクスに対してしばしば現実の経営の実情、資本家の実務や慣例について情報を提供した。時には、マルクスの要請に応じて、『資本論』の原稿に対して経営者の観点から助言や指摘を行った。
(要執筆)
危機と再編の時代へ
[編集]労働運動の再建
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
国際的な労働者運動は1860年代の国際危機に刺激され復活を遂げていく。
1860年代大英帝国の世界支配が完成する一方、新興国の工業化、近代化が急速に進展し始めていた。この時代の動きはアメリカにおいて南北戦争、南欧でイタリア統一運動、東欧でポーランド蜂起(1月蜂起)となって現れる。これらの事象に対する労働者の反応が国際的な労働者組織(第一インターナショナル)を創立する直接的契機となった。
1857年からの不況で企業が次々と倒産して失業者が増大したことでヨーロッパ諸国では労働運動が盛んになった[230]。
- 1857年経済危機
1850年代の好景気によりロンドンでは建築ラッシュを迎えたが、1857年の経済恐慌によって1859年のロンドン建築工ストライキが起こる[231][232]。労働時間の短縮を要求する建築工のストライキは失敗に終わったものの、ストライキにおける労働者の団結と闘争を強化する目的で各業種ごとに職工たちが結集して組織した合同組合が組織され、1860年5月には、ロンドン労働者協会(英: London Trades Council 以下、LTCと表記)が発足し、多くの都市で労働運動の結集が進展した。後にLTCは、1865年に結成された改革連盟という成人男子選挙権を要求する熟練労働者(労働貴族)による政治団体の母体となり、また、各地で組織された同様の「地区労」を結びつけて労働組合会議(英: Trades Union Congress)を開催し、全国的な労働組合の組織を作り上げた。
フランスでは、1860年代以降、ナポレオン3世が「自由帝政」と呼ばれる自由主義化の改革を行うようになり[233]、皇帝を支持するサン・シモン主義者や労働者の団体「パレ・ロワイヤル・グループ」の結成が許可された[234]。プルードン派やブランキ派の活動も盛んになった[235]。後述で詳しく紹介するが、ドイツでも1863年にラッサールが全ドイツ労働者同盟を結成した[236]。
1848年革命の挫折によって崩壊していた労働運動、革命運動が、世界各国で復活を遂げようとしていた。
南北戦争の余波
[編集]1861年、アメリカの南部諸州が連邦からの脱退を宣言してアメリカ連合国を結成し、アメリカを二分する内乱・南北戦争(1861-1865年)が勃発した。
エンゲルスは南北戦争とブリテンにおける北部支援運動に強い印象を受けた。北部合衆国主導の黒人奴隷の解放によって民主化と工業化が進展し、アメリカ大陸に新時代を開拓する強力な新興国が出現することを期待していた。北部合衆国は、南部連合の主要産業である綿花生産に打撃を加えるべく、海上封鎖を実施した。その結果、綿花危機でヨーロッパの綿花関連の企業が原料不足による操業停止に追い込まれ、次々に倒産に追い込まれていく中、ランカシャーからマンチェスターにかけての膨大な数の労働者が大量失業と生活難に陥った。


エンゲルスは北部による奴隷解放を支持する立場を堅持していたものの、戦局の行方についてマルクスとは異なる見解を持っていた。エンゲルスは初戦における南部連合の戦勝から、1862年春に展開された東部戦線バレー方面作戦で活躍するストーンウォール・ジャクソンなど南軍将官の優秀性に感銘を受けており、当初のところ「北軍の将官は愚か者ばかり」で戦争は南部連合の勝利で終わると予想していた[237]。しかし、マルクスはエンゲルスの軍事面に偏る分析に対して批判的な姿勢を取り、奴隷解放という歴史的大義を掲げた北部合衆国が最終的に勝利をおさめるという認識を示し続けた。マルクスは、1862年夏にエンゲルスと交わされた書簡において次のように述べている。
「アメリカの内戦についての君の意見には全面的には賛成しない。僕は、万事休した、とは思わない。 北部諸州人は当初から境界奴隷諸州に代表者たちに支配されていて、……、これに反して南部は始めから始めから一体となって行動していた。北部自身が奴隷制を、南部に反抗させないで、南部の軍事力に変えていた。南部は奴隷たちに生産的労働を任せていて、その全戦力を戦場に連れ出すことができた。南部は統一的な軍事指導権をもっていた。北部はそうではなかった。……。僕の見解からすれば、こんなことすべては方向を転ずるだろう。北部は最後には真剣に戦争をし、革命的手段をとらえて、境界奴隷諸州の政治家の上部支配を排除するだろう。たった一つの黒人連隊でも南部の神経に著しく作用するだろう。」[238]
「僕は、最後には北部が勝つ、という見解を相変わらず固辞している。南部は、ただ奴隷境界諸州を保持するという条件のもとでのみ講和を締結するだろうし、あるいはまた締結しうるだろう。……。だが、こんなことは不可能だし、起こりもしないだろう。……。現状を基礎としてのその間の休戦状態などは、せいぜい作戦の中休みを引き起こしうるだけであろう。……。もちろん、そのまえにまず一種の革命が北部そのもののなかで起きる、ということもありうる。アウグスト・ヴィリヒは旅団長で、……、シュテフェンも今度は(北部側で)戦争にでるそうだ。僕には君が少しばかり事態の軍事的様相によって意見を決めすぎているような気がするのだ。()内筆者補足。」[239]
マルクスの読み通り、1863年夏のゲティスバーグの戦い以降、長期戦を強いられた南部連合は工業生産力の差から北部合衆国に対して守勢に立つようになり、1864年4月には南部連合の首都リッチモンドが陥落、まもなく北部合衆国の勝利が達成される。
この戦争はブリテンのプロレタリアート階級に多大な犠牲を強いるものとなったが、マルクスは南北戦争を奴隷解放のみならず、やがて到来する労働者階級の解放の先駆けと見なした。アメリカにおける黒人奴隷制の廃止が全世界における賃金奴隷制の廃止の要求に発展し、労働者階級が搾取階級との闘争を歴史的運命として認識するようになる一助と考えたのである。
エンゲルスもマルクスと同様に、南部の黒人が奴隷化されている現状は、アメリカをはじめ全欧州の白人労働者を隷属させる経済システムの長期化につながるものであって、早期に北部合衆国を勝利させて奴隷解放を実現させることが歴史的大義であると見ていた。エンゲルスは、ブリテンとアイルランドの労働者が騒擾や打ち壊しもせず自己犠牲的な「沈黙」を貫き、ブリテン政府が南部連合を救うべく北部合衆国に軍事介入を試みる企てを抑止したことに満足感を得ていた。
植民地主義との闘い
[編集]一方、ヨーロッパ大陸の東ではポーランド蜂起(1月蜂起)が発生していた。

エンゲルスはポーランド解放をヨーロッパの老大国が強化する軍国主義の否定の契機として考えて蜂起を支持した。自由で民主主義的なポーランド国家が中央ヨーロッパに再び登場すれば、ロシア帝国のツアーリズムとプロイセンの軍国主義に抵抗する「自由の砦」が建設されて、ヨーロッパ秩序の自由化・民主化が進行すると期待できた。
エンゲルスは、ポーランド蜂起に加わった革命家の支援のためにマンチェスターで募金活動を組織するなど全力を注いだ。
また、国際世論の啓発のために執筆活動にも取り組む姿勢を見せ、外交についてはマルクスが書き、軍事についてはエンゲルスが書くという共同事業で『ドイツとポーランド』という小冊子の作成を検討していた。この小冊子の作成の最中に蜂起の鎮圧が伝えられて計画に終わるが、二人は「他民族を抑圧する民族は、みずからを解放することはできない。他民族を抑圧する力は最終的につねに自国民に向けられるからだ」とする認識を一層強め、民主主義の実現、植民地解放と民族自決権の達成を呼び掛ける動機づけとなった[240]。
また、英仏ではポーランドの窮状に対する同情の念が強まってポーランド支援の世論形成を促した。また、植民地主義に対する嫌悪感と戦争への恐怖心から、欧州の帝国主義諸国が引き起こす外交問題に懸念が深まり、外交危機に対する労働者階級の運命と役割への関心は次第に強まっていった。
エンゲルスは1840年代にはスラブ人や東洋人をヘーゲル的な意味での「非歴史的民族」として位置づける人種差別的感情を持っていたが、1860年代に入ると黒人奴隷の解放運動やポーランド独立運動に刺激を受けて、次第に植民地解放と民族自決権の擁護者となっていった[241]。

1865年10月11日、ジャマイカ東部のセント・トーマス教区で、ポール・ボーグルが200人から300人の貧しい黒人男女を率いてモラント・ベイの市街へ乱入した。
総督エドワード・エアは軍を派遣し、軍は組織的な抵抗に遭遇しなかったが無差別に黒人を虐殺した。そのうちの多くはこうした暴動や反乱に関与していなかった。ある兵士の証言によると、「我々は我々の前にいるすべてを殺戮していった…男であれ女であれ、子供であれ」とのことである。この反乱事件は後にモラント湾の暴動(ジャマイカ事件)として知られるようになるが、事件はブリテン本国での大論争を引き起こした。事件はエンゲルスにも大きな影響を及ぼし、彼は「郵便が来るたびに、ジャマイカでのさらにひどい残虐行為のニュースがもたらされる。非武装の黒人を相手にした英雄行為を語るイギリス人士官たちの手紙は言語に絶する」と語って、エア総督の黒人虐殺に嫌悪感を示した[241]。
エンゲルスは、世界各地で発生する現地住民の抵抗に共感を抱くようになっていた。中国でのアヘン戦争、インド大反乱などの事例に加え、アルジェリアやコンゴでの帝国主義列強諸国の「人類や文明、キリスト教の精神」に反する蛮行を非難した。「先住民が暮らし、単に支配を受けているインド、アルジェ、オランダやポルトガル、スペインの領地」のような国々は、「できる限り急速に独立」を果たし、革命を達成することが急務であると考えるようになった。エンゲルスによる抵抗思想の確立とともに、革命的プロレタリアート主導の植民地抵抗運動の展開というマルクス主義的外交戦略の展望が定まった[241]。
アイルランド独立闘争
[編集]
エンゲルスは、アイルランド独立闘争の歩みに深い共感を抱いていた。
エンゲルスがアイルランドを初めて旅行したのは1856年であった。エンゲルスは伴侶であるメアリー・バーンズとともにダブリンからゴールウェイにかけて旅行し、アイルランドの自然や人々との出会いを堪能している。帰国後もエンゲルスはアイルランドに関心を示して、ゲール語を勉強、法律、歴史、地理、地質、文化を学習し、研究ノートを作成していった[242]。エンゲルスは、アイルランド農村について「飢饉がこれほど生々しく現実に感じられるとは思いもしなかった」と旅行中に綴り、続けて「村はまるごと放棄されていた。そうした村々のあいだに、まだそこで暮らしているほぼ唯一の人々である小規模な地主の素晴らしい庭園がある。大半は法律家だ。飢饉、海外への移住、そしてその合間の撤去が、こうした事態をもたらしたのだ」と語っている[243]。
アイルランド農村は、1845年から1852年にかけて猛威をふるったジャガイモ飢饉と牧草地転用のために展開された強制的な撤去、小作農立ち退きによって牧畜経済が形成される一方、アイルランドの貧農層はかつてない窮状を余儀なくされた。飢饉による打撃で100万人の死者と100万人超の膨大な人口が離散を強いられてアイルランドの農村プロレタリアートは完全なる壊滅に至っていた[243]。
エンゲルスは、ブリテン支配を先進文明による野蛮の征服とは考えず、アイルランドの窮状に対して一貫して同情的であった。
彼は、ノルマン人のアイルランド征服からクロムウェルの侵略を経て、アイルランドがイングランドによって組織的に略奪されたために惨めな敗者へと転落して「完全に落ちぶれた民族」となってしまったと捉えるようになっていた[243]。マルクスが帝国主義理論を理論化するはるか前に、エンゲルスは「アイルランドはイングランドの最初の植民地と見なせるかもしれない」、「イングランド人の自由は各地の植民地の抑圧に基づいている」と分析し、アイルランド研究を通じて資本主義とブリテン帝国主義の侵略行為とを結び付けて考えた。後にマルクスも「アイルランドはイングランドの土地貴族の砦である」、「イングランドの貴族がイングランドの国内における支配力を維持するための重要手段」であると位置づけるようになった[244]。
こうした状況下でアイルランドでは、革命組織アイルランド共和国同盟による独立闘争が活発化していた。
しかし、ダブリンでの1867年3月5日のフィニアン蜂起は失敗に終わってしまう。この事件は、イングランドを「悪の帝国」と見なし、アイルランドに自由で民主的な共和国を打ち立てるため、立ちあがった義勇兵たちの蜂起であった。蜂起に加わった活動家は逮捕され次々と収監されたが、革命派は脱獄計画を立てクラーケンウェル刑務所の爆破事件を起した[245]。これらの事件はマルクスとエンゲルスが嫌っていた軽挙妄動に他ならなかったが、リディア・バーンズの存在が二人の考え方を変化させた。リジーはマンチェスターで活動家トマス・ケリーとティモシー・ディシー護送中の車両を襲撃して警官を殺害した革命家たちを匿い、逃亡を手助けする謀議に関わっていた。警察もエンゲルスとリジーの動きを察知できず、犯人逮捕に手間取った[246]。五人の実行犯はまもなく逮捕され、そして三名に死刑判決が下り、処刑された。エンゲルス家ではリジー、マルクスの娘ジェニー、トゥシー(エリノア・マルクス)が喪服を着て緑(アイルランドのシンボルカラー)のリボンとポーランド十字架を身に付けたという[246]。
マルクスとエンゲルスは、ドイツの労働者階級の解放がポーランド解放にかかっていたのと同様、アイルランドはイングランドの最大の弱点であり、アイルランド独立によって大英帝国の解体が始まり、イングランドの階級闘争、世界各地で民族解放闘争の狼煙が上がると考えるようになった。
ドイツでの情勢変化
[編集]
フェルディナント・ラッサールは、プロイセン王国の19世紀国家社会主義運動の指導者である。
ラッサールは、1825年にプロイセン東部ブレスラウに裕福なユダヤ人の息子として生まれた。1844年、青年となったラッサールは故郷を離れてベルリン大学へ進学し、ヘーゲル哲学を研究した。交流のあった伯爵夫人の離婚問題からドイツの封建的制度への批判的立場を持ちはじめ、1848年革命に参加していった。ラッサールは哲学者ヘラクレイトスの思想を研究して成功を収め、哲学や革命運動で一時マルクスやエンゲルスとも親交していた。しかし、イタリア統一運動の指導者ガリバルディの影響を受けて政治の世界に参入した後は、ナポレオン3世によるイタリアのサルディニア王国支援に期待するとともに、プロイセン王国が進める小ドイツ主義に基づくドイツ統一に期待をかけて、マルクスとは異なる立場を打ち出し対立していく[247]。
両者は労働者保護に関する志は共有していたが方法論に違いがあった。
マルクスは、労賃に関してラッサールとは異なる見解を示していた。労賃は資本家の恣意で決定されているのだから、価格を上げなくても労賃を上げて生活水準を向上させることは可能であると見ていたのである。こうした賃金闘争のために労働組合は欠かすことのできない組織と位置付けて、その役割を積極的に評価していた。また、マルクスはイギリスやアメリカを例外として、「前衛政党」による暴力革命によって古い政府から国家権力を奪取し「プロレタリアート独裁」によって資本主義を打破する道を探っていた。
これに対して、ラッサールは協同組合の相互扶助を重視し、賃金闘争によって人件費が上がるとコストがかかって物価が上がり結果的に生活水準は向上しないという盲目的な「賃金の鉄則」を支持していたため、労働組合や労働争議を否認していた[248]。かれは国家の支援を得た協同組合の連合が資本主義に取って代わると考えており、革命ではなく「成人男子選挙権」を実現して議会進出を図るべきだと考えていた。1863年には最初の労働者政党全ドイツ労働者同盟を設立し、ビスマルクに積極的に協力しながらプロイセン議会の議席獲得を目指していく。
1864年夏、エンゲルスはプロイセン王国を盟主とする北ドイツ連邦とデンマーク王国間で勃発した第二次シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争(1864年2月1日-7月1日)後まもなく、軍事評論家として同地方への視察旅行をおこなった。この時の視察旅行でエンゲルスはユトランド半島とスカンディナヴィア諸国の文化と歴史、そして人々との交流に大きな喜びを得る一方、プロイセン王国の膨張とその軍国主義に警戒感を高めていった[249]。
帰国後、マンチェスターに戻ったエンゲルスを仰天させるニュースが飛び込んできた。
一つはフェルディナント・ラッサールの死と二つは国際労働者運動の再生であった。ラッサールは1864年8月31日に恋愛問題に絡む決闘で命を落としたのである[250]。訃報はフライリヒラートからの電報ですぐさまマルクスとエンゲルスのもとに届けられた。ラッサールの死は思いがけないものの、弔意を示したマルクスに対して、9月4日の手紙でエンゲルスは冷淡な反応を示してこう述べた。
「ラッサールは、人間的にも、著作の面でも、学問的にもあの通りの人物でしかなかろうとも、政治的には確かにドイツにおける極めて重要な男の一人であった。現在では彼は、われわれにとって、非常に危険な友人であったし、将来はかなりはっきりした敵になったであろう。いずれにせよ、ドイツが急進的な党派の多少とも有為の人物をことごとくだめにしてしまうのを見るのは、ひどい打撃だ。どんな歓声が工場主たちの間や進歩党の豚どもの間で上がることだろう。ラッサールは、なんといっても、彼らに不安を抱かせたドイツ本土における唯一の男だったのだ。それにしてもなんという奇妙な生命の捨て方だろう。バイエルン公使の娘に真剣に惚れ込んで、彼女と結婚しようとし、…ワラキアの詐欺師と衝突して、そいつに射殺されるとは。これはだたラッサールだけに起こりえることだ。まったく彼一人に固有だった、あの浮薄と感傷との、ユダヤ気質と騎士ぶりとの、奇妙な混合物だった彼だけに。」[251]
1864年に決闘でラッサールが世を去った後も「全ドイツ労働者協会」の求心力は強かった。ラッサール派はプロイセン支持に徹した国家擁護の立場だったので、第一インターナショナルには加盟しなかったが、ドイツ、チェコ、オーストリア、そしてドイツ系の移民先であったアメリカに支持者がおり、マルクス主義の主要なライヴァルとなった[252]。
インターナショナルの時代
[編集]第一インターナショナルの発足
[編集]
一方、マルクスがいるロンドンでも一大変化があった。
英仏労働者がポーランド蜂起の支援を目的として結集を誓い、世界初の労働者の国際政治結社「国際労働者協会」(第一インターナショナル,以下IWAと略記)が結成されたのである。ブリテン側の世話人は製靴工のジョージ・オッジャーと大工のランダル・クリーマー、フランス代表は青銅細工職人アンリ・トラン、議長はロンドン大学教授のエドワード・ビーズリだった。また、この集会にはマルクスも同席していた。この集会はヨーロッパ各国の急進派が一堂に会する大規模なものとなった。マルクスはエンゲルスにこの集会とIWAについて以下のように伝えた。
「少し前に、ロンドンの労働者が、パリの労働者に宛ててポーランドのことで呼びかけを送って、彼らにこの問題で共同行動を採るように要求してきた。……。1864年9月28日を期して、公開集会がセント・マーティン・ホールに招集された。……。ル・リュペスという男が僕のところに使いに来た。僕がドイツの労働者を代表して参加するかどうか、とくにドイツの労働者を一人代表してこの集会その他に派遣する気はないかというのだ。僕はエッカリウスを派遣したが、彼は立派にやってのけた。僕も同じく出席してだんまり役として壇上に並んだ。今度はロンドン側からもパリ側からも本当の実力が出ていることを僕は知った。それで、この種の招請はなんでも断るという僕のいつもの決まりを捨てることに決めたのだ。」[253]
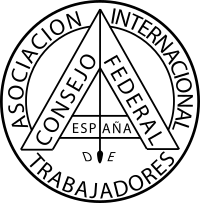
マルクスは国際的な労働者の結集点が登場したことを大いに喜び、エンゲルスも返信で同感であると述べた。
マルクス、エンゲルスは1848年革命とその挫折からプロレタリアートが復活して、やがて資本主義に対する抵抗する政治的行動に結束する歴史的瞬間が再来するのを16年にわたり待ち望んでいた。9月28日の発足集会の決議に基づきロンドンに本部を設置することが定められ、「中央評議会」と年次大会を主軸としたIWAの組織が示された。しかし、エンゲルスは「この新しい協会は、諸問題がいくらか厳密に規定されるや否や、たちまちのうちに理論的にブルジョア的要素と理論的にプロレタリアート的要素に分裂するだろうと僕は思う」と語り、各国のプロレタリアートの国際同盟の性格上、分派が生じる可能性があることを指摘して、マルクスによる包括的な理論的指導が重要になることを助言した[254]。
そこで、マルクスは前もって作成された趣意宣言を「この駄文からなにかを作り出すことなど到底できない」として大幅に書き直すことにした。規約作成委員会での議事妨害と批評を通じて、1845年以来の労働者階級の運動を歴史的に総括する一節を加えることにより各派の思惑が加わった文言を次々と削除して、「権利、義務、真理、道徳、正義」といったブルジョア的な文言も重要個所から国際政治における帝国主義批判の項目等の「何ら害を及ぼせない位置に配置した」り、文言を移し替える等して、その内容を校訂して作り変えてしまった。
こうして、マルクスは『第一インターナショナル創立宣言』と『規約』とを起草して、中央評議会で満場一致で採択されることに首尾よく成功している。マルクスはブルジョア的勢力の一掃のため、労働運動の支援、権力の獲得を目指す政治運動の展開を運動の中心に定めた。そして、IWA内のドイツ担当の一書記に過ぎなかったが、次第にIWAの実質的な指導権を獲得していった[255][256]。
IWAの組織は短期間で整備されたが、最期まで諸派の混在状態にあったため、当初、その意思決定は困難なものであった。近い立場の旧チャーティズムの信奉者、ブランキ主義者やラッサール派の他に、IWAにおいて「権威」となったマルクスへの主な反対者として、ブリテンの労働組合指導者たちやプルードンやバクーニン、マッツィーニらが存在した。マルクスは1871年アメリカ人会員のフリードリヒ・ボルテに宛てた手紙においてこう語っている。
「インターナショナルが作られたのは、社会主義的、半社会主義的な宗派を労働者階級の本当の闘争組織でおきかえるためであった。これは最初の規約や創立宣言をみれば一目でわかる。……。インターナショナルの歴史は、労働者階級の本当の運動に逆らって…自分の地位を保とうとつとめた宗派やアマチュア実験に対する、総評議会のたえまない闘争であった」[257]。
マンチェスターで「エルメン・エンゲルス商会」の経営に打ち込んでいたため、エンゲルスは中央評議会の重職を務めることはできなかったものの、日々の文通を通じてマルクスに状況報告とアドバイス提供に貢献した。マルクスはエンゲルスの助言に従い、IWA内部の雑多な勢力を整理していく算段であった。
マルクスは『資本論』の執筆を前に『賃金、価格、利潤』という講演をおこなうなどますます多忙な生活を余儀なくされていた。しかし、プロレタリアートの国際的連帯の強化の促進とその理論的指導は、将来にわたる国際社会主義運動の方向性を指し示すものとなった。マルクスはブルジョア国家との共存を志向して階級闘争の推進を妨げ続けるプルードン派との論争、労働組合主義者への反駁、ラッサール派の打倒にエネルギーを注ぎ込んでいく。マルクスによって強化されたIWAはフランスでのパリ・コミューン革命で活躍を見せ、ドイツではアウグスト・ベーベルを中心とした社会主義政党の結成へとつながっていく。
ロンドンのセント・マーティン・ホールでの発足集会(1864年)にはじまり、 ジュネーヴ大会(1866年)、ローザンヌ大会(1867年)、ブリュッセル大会(1868年)、バーゼル大会(1869)、ハーグ大会(1872年)が開催された。IWAは国際主義に立って国家的枠組みを超えた社会主義運動に関する決議を採択し各国政府に提言したほか、世界初の社会主義革命というべきパリ・コミューン革命を支援するなど横断的な挑戦を試みた。
引退とロンドン暮らし
[編集]エンゲルスのビジネスライフにはマルクスへの金銭面と知的交友面での自己犠牲の他に、自分自身の健康面への自己犠牲も伴った。
1850年代末から60年代初頭期にかけて、エンゲルスは過労から深刻な体調不良に悩まされていた。1857年には膿瘍を患った他、膿瘍の回復も待たず続いて腺熱で倒れてもいる[258]。この病は妹マリーの看病によって早期に回復を見せ始め、1857年の経済危機の勃発により革命に近づいているという期待感と共に完治した[259]。しかし、病気による不運はエンゲルスではなく、彼の家族に及んだ。1860年にはフリードリヒ・エンゲルス(父)が世を去った。エンゲルスは嫌っていた父の死に対して特別な感情は抱かなかったが、エルメン一族との経営権をめぐる会社内の確執で神経をすり減らすことになった[260]。続いて母がチフスで倒れた際は母を深く愛していたエンゲルスも強い動揺に襲われた。さらに、弟のルドルフ、ヘルマンが長子フルードリヒを愛する母の病気に乗じて、エンゲルスから収益の大きいバルメン工場の重要部門の経営権をはく奪しようと画策した。母も闘病生活の中で息子たちの衝突を仲裁することはできず、やむなくフリードリヒは弟たちに経営権を譲渡することになる。その結果、エンゲルスは自身の体調悪化も相まって病気がちとなっていたためビジネスから引退することを考えるようになっていく[261][262]。
1863年冬、エンゲルスにとって大きな痛手が襲った。サルフォードの工場で下積みをしていた青年エンゲルスが見染めて、その後二十年に渡って連れ添った最愛の女性メアリー・バーンズが41歳の若さで突如急逝したのである。あまりに突然のことだったため、エンゲルスはマルクスに手紙を送った。
「親愛なるムーア。メアリーが死んだ。昨晩、彼女は早く床に就いたのだが、リジーが真夜中少し前に寝ようと思った時には、すでに息絶えていた。なんとも突然のことだ。心不全か脳卒中だろう。僕も今朝はまだ知らされていなかった。月曜の夜は、彼女もまだかなり元気だった。僕がどんな気持ちでいるかとても伝えることはできない。あの可哀そうな娘は僕を心底愛してくれた。」[263]
しかし、マルクスの反応はエンゲルスを落胆させた。メアリーの死に驚きを示しつつ、学費や家賃の支払いといった自分自身の経済状況に関する長文を廻らせ、急の資金援助を求めたのである[263]。さすがのエンゲルスも援助を断ったうえで、「こんなときにこのようなひどい話を君にする私は、恐ろしく利己的だ。しかし、これは同毒療法なんだ。何か悪いことがあれば、別の悪いことからは気が逸らされる。それでは!」と絶縁を想起させるような調子で綴り、マルクスに怒りを示した[263]。
さらに、マルクスは五日も経ってからバツの悪い態度で返信したため、エンゲルスはさらに激高して「君はそれ(メアリーの死)を自分の〈私情をはさまない気質〉の優越性を主張するのにふさわしい場と考えたのだ。よろしい!」と言い放った[264]。ようやく、マルクスはエンゲルスを本当に怒らせたことに気づき、「君にあの手紙を書いたのは、私がひどく間違いだった。手紙を送ってすぐに後悔したよ。しかし、そうなったのは決して薄情さゆえではない」と述べ、傲慢なマルクスに似つかわしくはない素直さで丁重に謝罪した。エンゲルスもマルクスの謝罪の言葉に免じて、「一人の女性と何年間もずっと暮らせば、打撃を受けないはずはない。……。今回の手紙はその埋め合わせとなり、メアリーを失った挙句に、僕の一番古い親友までも失わずに済んだことをうれしく思う」と語り、その非礼を許した。エンゲルスは援助を乞うマルクスのためすぐに100ポンドを送金している[264]。

この出来事の背景には、マルクスがエンゲルスの愛人であるメアリーを良く思っていなかったことが考えられる。マルクスは学のないアイルランド女工のメアリーを内心では軽蔑しており、決して対等には見ていなかったのである[264]。エンゲルスは労働者階級の素朴な女性を好んでいたため、マルクスと女性観・結婚観が大きく異なっていたと考えられる。二人はすれ違いのなかで絶縁寸前のところまで険悪となったが、再び正直な気持ちを打ち明けて和解した。
その後、エンゲルスは妹のリディア・バーンズを家政婦からメアリーの代わりになる伴侶(内縁の妻)の立場に据えている。リジーは気性の激しいメアリーに比べて気さくで社交的だったため、マルクス家と親交が深く、とりわけ、マルクス家の末娘エリノアの回想から、マルクス家とエンゲルス家の絆を強める存在となっていたことがわかる[265]。成長していくマルクス家の三姉妹(長女ジェニー。次女ラウラ、四女エリノア)、リジーとその姪パンプス(メアリー・エレン・バーンズ)、加えてマルクス家の家政婦ヘレーネとの交流がエンゲルスの心の安らぎ、マルクスとの友情の証になっていく[266]。
だが、中年期のエンゲルスが実業と研究の両立ができなくなっていることに変化は生じなかった。
1864年、会社の重役となっていたエンゲルスはエルメン・エンゲルス商会の経営権を完全に弟たちに売却する協定を結んでいる。エンゲルスは退職金をめぐる粘り強い交渉を重ねた後、1869年、1万2500ポンドを一括受取りする約束を受けて、ついに退職を果たした。かくして、エンゲルスは心身の苦痛を伴う工場経営の職から足を洗い、悠々自適な金利生活者になった[267]。立場の変化はエンゲルスの政治運動への復帰を可能にすると同時に、知的活動を大いに刺激して健康状態は劇的に好転した。翌7月1日の母親宛ての手紙でこう語っている。
「お母さん。今日は自由の第一日です。この日の活用法としては、すぐさまあなたにお手紙を差し上げること以外にありえません。私は新しい自由を気に入ってます。私は昨日から全く別人になり、10歳若返っています。私は陰気な街ではなく、すばらしく晴れ渡った空のもと、数時間郊外へ出かけました。そして窓辺には花が置いてあり、家の前には木が数本ある……居心地よくしつらえてある部屋の中で、自分の文机に向かって、……倉庫の全く陰湿な部屋とはまったく違った気持で仕事をしています。」[268]
エンゲルスは退職の日の爽快感についてよほど嬉しかったのであろう。マルクスにも「万歳!今日で愛しの仕事とおさらばだ、僕は自由の身だ!」と告げ、マルクスもエンゲルスの「出エジプト」を祝した。マルクスの娘エリノア・マルクスはこの日のエンゲルスの様子をこう描写した。
「その朝であった。おでかけのため靴をはいていた、そして『ああ、これでおしまいだ』とエンゲルスがいった。それから数時間たって、エンゲルスはステッキをふりふり歌を歌いながら帰ってくるのが向こうのほうに見えた。その顔はほがらかに輝いていた。かれはテーブルの上にご馳走を並べて、いかにも嬉しそうにシャンペンを抜いた。この光景を見たのは私がまだ子供の時であったから、その意味がよく分からなかったが、今となって、あの日のことを思うと、わたくしは涙を止めることはできない。」[267]

1870年、エンゲルスは引退生活の場をマルクスが暮らしていたロンドンに求め、喘息持ちのリジーのために、勾配の少ない地区で落ち着いた住宅地を探していた。マルクスの長女イエニー・マルクスの紹介を受けて物件を見つけ出し、再開発によって北ロンドンの一等地となっていたリージェンツ・パーク近くに立地するプリムローズ・ヒルに居を構えることになった[270]。
エンゲルスの邸宅は地下を含め五階建ての住宅で、地下にキッチンと浴室、一階に広々したリビングダイニングがあり、二階にはエンゲルスが一日の大半を過ごしていた応接室と書斎があり、三階と四階はリジーとエンゲルスの寝室、女中の部屋、リジーの姪のパンプスの部屋、来客用の部屋があった[271]。エンゲルスは社交的な雰囲気を好み、各国の社会主義者やバーンズ家の親族、マルクス家との家族ぐるみの付き合いを楽しんだ。エンゲルスは日々を規則正しく過ごし、午前中は研究時間と書簡の作成に割き、午後からは家から10分ほどのメイトランドパーク・モデナ・ヴィラズ1番地(英: 1 Modena Villas, Maitland Park)、1875年以降は近くのメイトランド・パーク・ロード41番地に住むマルクスを毎日訪ねていた[272]。エリノア・マルクスは二人の様子を次のように述べている。
「エンゲルスは毎日うちの父に会いに来ました。一緒に散歩に出かけることもあったけれど、同じくらいよく父の部屋に籠もったまま、それぞれが部屋の片側をよくゆきつ戻りつして、隅で向きを変えるので、踵で穴が開きました。……。二人が黙ったまま行ったり来たりすることも度々でした。あるいはまた、そのとき自分が最も関心のあることをそれぞれが喋り、しまいに顔を合わせて大声で笑い、それまでの三十分間は正反対の計画について検討していたのだと認めたりするのだ。」[272]
1870年代に入り、大英帝国は産業革命後に世界の工場として君臨していた時代は過ぎ去り、帝国主義的な金融資本主義の国家へと変貌を遂げていった。こうした時代のなかで、引退後のエンゲルスは資産を株式購入に充てて運用し、金利生活を営む富裕な株主となっていた。皮肉にも「強欲で利己的な工場経営者」から「寄生的な金融資本家」へと変貌していたのである[273]。エンゲルスは、自分の立場の矛盾についてこう述べている。
「人は証券取引人であるのと同時に、社会主義者にもなれるのであり、それゆえに証券取引人の階級を嫌い蔑むことにもまったく問題ない。……。自分がかつて工場主であった事実について、謝罪すべきだと思い立った試しがあろうか?その件で僕を攻めようとする人間は誰でも、手厚くもてなされるだろう!」[274]
『資本論』第一巻刊行
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
バクーニンの登場
[編集]
ミハイル・バクーニンはロシア貴族の出であるが、役人になってロシアによるポーランド支配に当たるにつれて次第に政治に疑問を抱き、ついに革命家となっていった。
1848年革命の混乱の中で革命運動に参加したことが角で死刑を宣告されたが、ロシア政府に引き渡されて1855年にはシベリアに流刑となっている。1861年、バクーニンは収容所を脱走して日本とアメリカを経てヨーロッパに帰還している。バクーニンはプルードンの弟子で、反権力の思想や自由な生産者の連帯にもとづく理想の未来社会というヴィジョンを柱とするアナーキズム思想を継承した[252]。
ただ、バクーニンは労働組合の発展期のなかで労働運動の役割を評価する立場をとっており、生産組合を通じて共同体をつくり、その連合に新社会の基礎を見出していた。
バクーニン主義の綱領は、無神論、国家の廃棄、暴力革命、労働組合を単位とする生産共同体、共同体の同盟による緩やかな統合を謳うものであった。また、バクーニンは反権力の立場から、マルクスの理論に反対して権力集中の危険性を説いた。マルクスは、移行段階の国家形態として、プロレタリアートがブルジョアを逆搾取していくための国家形態「社会主義国家」を新社会のモデルに据えており、そのための政府モデルとしてプロレタリアート独裁の概念を提唱していた。しかし、バクーニンは反権力に基づく自由な連合に基づく社会を理想とし、マルクスの中央集権的で革命独裁を含んだ国家理論に反対であった。バクーニンは、社会の末端の下層労働者が革命の担い手だと考えており、暴力革命による権力の転覆を支持する一方で、マルクスが説くような権力主導の理想(社会主義国家を経由した共産主義社会というユートピア)実現にはどうしても賛同できなかったのである。
また、マルクスは、プロレタリアート独裁を提唱する傍ら自身が説く革命独裁には拘っておらず、議会や政府を通じて民主的な方法で社会主義政策を遂行する方向も認めていた。バクーニンはこうした現状肯定的な態度にも反対していた。彼はあくまでも暴力革命を説き、現状との妥協や支配階級に対する説得や交渉といった理性的手段には断固反対で、その思想には柔軟性には欠いた[275]。
バクーニンはイタリアを中心に活動しており、平和自由連盟の中央委メンバーとなっていたが、「連盟」から離脱し1868年新たな活動団体として国際社会民主同盟を組織した。バクーニンは、無神論、階級の平等化、相続権の廃止、国家の廃棄、政治活動の拒否を唱えて支持者を集めていった[276]。その活動は生活力のある労働者には差して支持は広まらなかったが、学生やインテリ、そして貧困労働者など社会的立場の乏しい人々に支持基盤があった。
1868年、ヨハン・フィリップ・ベッカーは国際社会民主同盟とバクーニン一派を代表して、IWAへの加入を申し入れるよう盛んに主張し始めた。だが、マルクスとエンゲルスはバクーニンが主張する秘密結社による陰謀や革命戦術を嫌い、警戒していた。同時に、ベッカーをバクーニンの傀儡に過ぎないと見ており、バクーニンが組織を乗っ取りを図っていて組織をスラブ主義的な陰謀団に変え、社会主義をロシアのテロリズムの道具にしようとしていると疑い始めていた。ロシアからの亡命者による報告の中で、結社を組織して基金を創設しながらその基金を横領したセルゲイ・ネチャーエフというロシアの活動家とバクーニンが関係が深いことを知ると、マルクスはバクーニンへの嫌悪感を強めていった。マルクスは、テロを計画したり非合法な活動に熱中する陰謀団まがいの秘密結社とは連携を取らないように中央評議会に勧告した。これに基づき、12月にはIWAは国際社会民主同盟を解散させない限り認められないとして、1869年のバーゼル大会では加入を断られていた[277]。
だが、バクーニン一派は組織を解散したように見せかけてIWAに密かに潜入して部内に分派を形成し始め、影響力を行使しようと試みるようになる。バクーニンの無政府主義、一揆的な革命主義はスペインや南イタリア、ロシアといった工業化が不十分な地域で支持を集めていた。スペインや南米諸国、南イタリア、ロシアでは労働組合は十分組織されておらず、抵抗運動のスタイルも秘密結社的な組織によるテロリズムが一般的であった。
ただし、マルクス主義と無政府主義にはまだこの頃は類似点も多く、1868年のブリュッセル大会で議論された土地国有化や労働組合に関する問題では、マルクス派とバクーニン派は協調してプルードン派などを抑える役割を果たしていた。しかし、マルクスはプルードン主義の脅威が去った今、新たな危険因子となるのはバクーニン主義であると考えるようになった。こうしてIWA内ではアナルコ・サンディカリズムが台頭し始め、組織内で亀裂が生じていった[278]。バクーニンとマルクスの思想的、運動実践上の相違はIWAを二分する論争へと発展、組織内で最大の衝突をもたらし、ついに組織の解体を招いていく[279]。
1870年、マルクスはバクーニン主義がまだ浸透していないドイツ中部のマインツで大会を開催することを計画した。マルクスは総評議会での討議の流れを通じてバクーニン一派の除名への道すぎを開き、バクーニンを窮地に追い込むことを企図していた。マインツ大会の計画は突発的な普仏戦争開戦によって中止を余儀なくされたが、マルクスは内部闘争での勝利を確実にしようと執念を燃やした。その一つの表れが、エンゲルスがIWAの役職に就いてアナーキズム対策の役割を担ったことに見出される。
1870年9月、総評議会は全権代表としてオーギュスト・セライエをパリに派遣した。セライエはパリでの革命に参加するためにフランスに帰国したのだが、彼が勤めていたスペイン連合評議会の担当書記が空席となってしまう。そこで、エンゲルスが10月4日総評議会の会合での指名を受け、スペイン連合評議会を任されることになった。エンゲルスは就任の挨拶をスペインに発し、その中でプロレタリアが既存の政治勢力に欺かれ吸収されようとしていることを指摘したうえで、既存政党から独立した労働者政党を樹立することが目下急務であることを表明した。
「たしかに、古い諸政党の空虚な大言壮語が…人民の注意をあまりにも引き付けてしまって、そのために我々の宣言の大きい障害となっています。これはプロレタリア運動の初期ではどこでも起こりました。フランス、イギリス、ドイツで、社会主義達は貴族的であろうと、ブルジョワ的であろうと、また君主主義的であろうと、共和主義的であろうと古い諸政党の影響と闘う必要があったし、いまでもその必要があります。いたるところで経験は、古い諸政党のこの支配から労働者を解放する最良の方法が、各国に独自の政策、他の政党のそれと非常にはっきりと区別される政策―プロレタリア政党は労働者階級の解放の条件を表現しなければならぬのですから―をもつプロレタリア党を創立することであったことを証明しました。この政策の細かい点は、それぞれの国の特殊事情によって異なるでしょう。しかし、労働の資本に対する基本的関係はどこでも同一であり、有産階級の被搾取階級に対する政治的支配の事実はどこでも存在しますからプロレタリア政策の諸原則と目標とは、少なくとも西方諸国では同一であるでしょう。」
エンゲルスは、労働者の解放のためには各国が共通の目標を掲げたプロレタリア党を樹立することが必要であり、国際連携によってブルジョワ資本主義に対抗する共通の綱領と戦線を開くよう促している。エンゲルスはバクーニンの影響が強いスペインでアナーキズムと対決していくことなる。
普仏戦争とエンゲルス
[編集]

マルクスとエンゲルスは、ヒューマニストとして戦争を憎んだ。彼らは、戦争を運命の産物や人間の無能力の結果で生じるものとしてではなく、社会矛盾、すなわち階級的搾取から生じる事象として捉えていた[280]。
1870年夏に勃発した普仏戦争は、ビスマルクが狡猾な謀略工作エムス電報事件でナポレオン3世を挑発して、フランスに宣戦布告へと踏み切らせた王朝戦争であった。しかし、ビスマルクは老練な政治力を駆使して、この戦争を北ドイツ連邦と南ドイツ諸国の同盟を強化して、全ドイツ的な同盟軍を動員する国民戦争とした。この開戦を機に、マルクスとエンゲルスはかねてから敵意を抱いていたナポレオン3世に復讐できる歴史的チャンスだと考えた。開戦に際してマルクスはこう語った。
「フランス人たちは棍棒を必要としている。もしプロイセン人が勝てば、国家権力の集中はドイツの労働者階級の集中に有益だ。さらに、ドイツの優越は西ヨーロッパの労働運動の重心をフランスからドイツに移すことになるだろう。そして、これら両国における1866年から現在に至るまでの運動を比較してみただけでも、ドイツの労働者階級が理論的にも組織的にもフランスの労働者階級にも勝っていることを知るには、十分なのだ。世界の舞台におけるフランスの労働者階級に対するドイツの労働者階級の優越は、同時に、プルードンなどの理論に対する我々の理論の優越でもあるだろう。」[281]
エンゲルスに至っては「今度の戦争は明らかにドイツの守護天使がナポレオン的フランスのペテンをこれ限りにしてやろうと決心して起こしたものだ」と嬉々として語っている[282]。
しかし、公的には第一インターナショナルを代表したマルクスに対して、エンゲルスは労働者階級が採るべき戦略を五点の簡潔なテーゼとして提示した。
要約すると、皇帝ナポレオン3世を打倒するまでは戦争を支持するが、打倒後は領土的要求はせずに停戦して和平を結ぶべきだというのがエンゲルスの立場であった。軍国主義のプロイセン王国を嫌悪していたものの、敵はあくまでもナポレオン3世による第二帝政だったのである。独仏の労働者には反戦と連帯、政治的進歩を求める運動に参加して、あくまでも母国の専制政治と侵略政策に反対し、政府に揺さぶりをかけなければならないと言明した。
一方、普仏戦争の展開は諸国民の関心の的となっていた。
ロンドンの『ペル・メル・ガジェット』(英: The Pall Mall Gazette)紙がマルクスに軍事情勢に関する見解を論評してい欲しいと申し入れたのである。これに対して、マルクスは自分は専門外であるため、軍事に明るいエンゲルスを紹介し、彼ならば適任であると推薦した。今回はマルクスの推薦によってエンゲルスは同紙の軍事通信員として能力を活かせる最良の地位を占めることになった[229]。「戦争時評」というタイトルで58回にわたる寄稿がおこなわれた。論文は大変秀逸な戦術分析を含んだものであった。
エンゲルスの友人の縁者がプロイセン軍の前線部隊に所属していたため、分析に有益な情報を収集することができた。プロイセンの大将モルトケの作戦案を分析し、最初の戦闘地域がザールブリュッケン付近となることを予測した。エンゲルスは特別記事をすぐさま執筆し、早馬車を走らせて記事を寄稿するなどいち早く特報した[229]。
また、1870年8月段階でセダンの戦いでのフランスの敗北とナポレオン3世の投降を予測した。エンゲルスの予想は見事に的中し、記事は世間からの評価を受けることとなる。マルクスもエンゲルスに宛て「ロンドンにおける第一級の軍事的権威者として認められる」であろうと語っている。しかし、このときの寄稿はエンゲルスが匿名で執筆したため、筆者が誰なのかについて数多くの憶測を呼んだ。この活躍によって軍事学の権威を示したエンゲルスは、マルクスから「将軍」という渾名を受けている。マルクスの妻イェニー・マルクスは「あなたの論説が当地でどんなにセンセーションを巻き起こしているか、ご想像できますまい!あなたはまったく素晴らしく明確にはっきりとお書きになっていらっしゃり、ですから私、あなたを若きモルトケとお呼びしないわけにはまいりません」と語るなど、エンゲルスに最大の賛辞を送っている[284]。
エンゲルスの軍事理論は普仏戦争の分析を通じて発展された。エンゲルスは後に執筆する『反デューリング論』のなかで、対外戦争から人民革命への転化の可能性を指摘している。そして、大規模なゲリラ戦の抵抗からなる戦争論を提示し、共産主義革命理論を体系化した[285]。エンゲルスの革命論の下敷きとなったのがパリ・コミューンである。
パリ・コミューン革命
[編集]
戦況はプロイセン軍の圧勝に終わったのだが、敗北を喫したフランス側で政変が発生した。
1870年9月4日、フランス立法院ではパリカオ内閣が国防政府の樹立を提案して皇帝の退位要求に蓋をしようと試みていたが、ナポレオン帝政に対する不満は敗戦への怒りとなって爆発し、民衆はブランキ派のエミール・ウードやエルネスト・グランジェに導かれて立法院に殺到してきたのである。人々は「帝政を倒せ!立法院を倒せ!共和政万歳!」と叫び、フランス第二帝政の失権を迫った[286][287]。
レオン・ガンベタは市庁舎のバルコニーに立って共和国宣言を発し、ルイ・ジュール・トロシュを首班とする国防仮政府の閣僚名簿を発表した[288][289][290]。仮政府のもと、すぐにフランスでは国民総動員がかけられ国民衛兵(フェデレ)の緊急招集が実施され、抵抗戦の継続が決定された。フランスは国防政府のもとで戦争を継続していくが、各地で次々と敗北して北フランス一帯を占領され、まもなくパリが包囲され籠城戦に入っていく。厳冬期に厳しい包囲戦を経験したパリ民衆は次第に急進化していったが、国防政府とプロイセンとの講和交渉に人々は憤慨した[291]。
一方、マルクスとエンゲルスはパリに自制を説くとともに、プロイセンによる早期講和の締結と融和策を求めていた。当初、ビスマルクは戦争をドイツ統一を阻止せんとするナポレオン3世による干渉への報復のための防衛として語っていたが、ナポレオン3世の降伏後もフランス侵攻を継続させ、ついにパリに迫ろうとしていた。こうした動きは、普仏戦争をナポレオン3世に対する防衛戦とすべきと主張したマルクスとエンゲルスの立場に反するものであった。
そのため、エンゲルスは戦況分析を戦争の軍事作戦に留まらず、ビスマルクが立案したドイツの安全保障戦略についても射程に置く分析を試みた。エンゲルスは、戦争の第一段階において、ドイツはフランスの排外主義に対して自国を防衛したが、いまや戦争は「しだいに、しかし、確実にドイツの排外主義のための戦争に」転化するであろうと分析した。統一されたドイツはアルデンヌ地方の森林地帯とライン川による地理的防御力によって十分にフランスの侵攻を撃退できるのだから、ストラスブールとメッスの占領を必要としないと主張した。マルクスもエンゲルスの見解に同調した。1870年9月9日、マルクスは第一インターナショナル中央評議会の『第二の呼びかけ』で、エンゲルスの上記の見解を公式見解として提示したうえで、プロイセンが「一九世紀後半期に侵略政策を復活させた」ことを非難した[292]。
マルクスとエンゲルスは、ドイツの領土拡張戦争はフランスの復讐心を煽り、国際的孤立の中でドイツを再び大戦争に巻き込んでいくであろうと予測した。二人は将来のヨーロッパ史で第一次世界大戦が勃発すると予言したのである[293]。
パリ包囲戦中の1871年1月、ビスマルクは、ヴェルサイユ宮殿で南ドイツ諸国の北ドイツ連邦へと加盟させる形式でドイツ統一を取り決めた。ヴィルヘルム1世がドイツ皇帝に戴冠され、これによりドイツ帝国が樹立された。その10日後には、フランスに多額の賠償金の支払いを要求、アルザス=ロレーヌの割譲、パリ占領という懲罰的な条件を盛り込んだ休戦協定を結ばせて普仏戦争を終結させた。これを聞いたエンゲルスは対仏強硬論を主張していた弟ルドルフに宛て、「現実には、人は目先のことしか見えないものだ」、「この先、多年にわたってフランスが間違いなく敵国であり続けるようにしたわけだ」と語った[294]。
エンゲルスの懸念以上に歴史は急展開を見せた。
国民衛兵は依然としてプロイセン軍のパリ入城への抵抗呼びかけていた。国民衛兵は武装解除を拒み、プロイセンに武器が押収されるのを防ぐため大砲を女子供も含んだ多数のパリ民衆と共にモンマルトル、ベルヴィールのなどの労働者地区へと移設していた。1871年3月1日、プロイセン軍は祝勝パレードのためにパリに入城した。弔旗が掲げられて静まり返るパリをプロイセン軍が3日にわたり占領した[295][296]。
3月18日、フランス共和国の行政長官に就任したアドルフ・ティエールは、武装解除のためパリ防衛の重要な堡塁モンマルトル陣地から国民衛兵が守備する大砲の撤去を命じた。 ルコント将軍とパチュレル将軍の指揮で大砲400門余の撤去を実施するが、これを偶然目撃した国民衛兵の女性兵士の一群が撤去に抵抗した。将軍は配下の兵に発砲を命じたが命令は空しく無視され、 ルコント将軍は離反した軍と国民衛兵により捕虜となった。捕えられた将軍のなかに1848年のフランス革命の六月蜂起で労働者の弾圧を行ったクレマン・トマ将軍がいたため、クロウド・ルコント将軍ともども猛る群集によって両将が殺害された[297][298][299]。

この事件を機にパリでは「コミューン万歳!」の声が高まっていた。国民衛兵とコミューンに合流してパリの実権を奪取、ついにパリ・コミューン革命が成就した。休戦協定に反発したパリ市民が武装蜂起した。一報を受けたアドルフ・ティエールは、1848年のフランス革命で果たせなかった計略を実行に移し、軍と政府関係者をひきつれてパリを放棄してヴェルサイユに逃走した[300][301]。3月28日にはコミューン選挙が実施されて、コミューン92名が普通選挙で選出されたが、そのうち17人は第一インターナショナルフランス連合評議会のメンバーだった[302][303]。こうして世界初のプロレタリア政府パリ・コミューンが樹立された。
マルクスはパリは無謀な蜂起するべきではないという立場をとっていたが、いざパリ・コミューン誕生の報に接すると、「なんという回復力、なんという歴史的前衛性、なんという犠牲の許容性をパリジャンは持っていることか!」「歴史上これに類する偉大な実例はかつて存在したことはない!」とルートヴィヒ・クーゲルマンへの手紙で支持を表明した[303][304]。
3月28日、パリ市庁舎前でコミューン政府の樹立が宣言され、以後5月20日まで二か月ほどの期間パリを統治することとなる。
老シャルル・ベレーを議長に、コミューン執行委員会を頂点として執行部、財務、軍事、司法、保安、食糧供給、労働・工業・交換、外務、公共事業、教育の10の各部実務機関が組織された[305][306]。フランスという国家機構から放棄されたパリ市民は、国民衛兵の補佐を受けつつ各執行部を通じて自発的に行政組織を再稼動させ、このときからコミューンは「代議體ではなく、執行権であって同時に立法権を兼ねた行動體」として活動をはじめた革命政府となった[307]。その間、教育改革、行政の民主化、集会の自由、労働組合をはじめとする結社の自由、婦人参政権、言論の自由、信教の自由、政教分離、常備軍の廃止、失業や破産などによる生活困難者を対象とした生活保護、各種の社会保障など民主的な政策が打ち出され、暦も共和暦が用いられた。
しかし、結局このパリ・コミューンは2カ月強しか持たなかった。ヴェルサイユに移ったティエール政府による「血の週間」という激しい攻撃を受けて5月終わり頃には滅亡したのである[303][308][309]。エンゲルスは「敗者は榴弾によって数百人単位で撃ち殺された」、「最後の大虐殺が実行されたペール・ラシェーズ墓地の〈フェデレの塀〉は、今日でも立っている。労働者階級が己の権利のために敢えて立ちあがった途端に支配階級が陥る狂気を、沈黙のなかで最も雄弁に語る証拠である」と描写した。
コミューンの総括
[編集]パリ・コミューンはマルクスとエンゲルスの革命理論に大きな影響を与えた。
マルクスは5月30日にもインターナショナルからパリ・コミューンに関する声明を出した。この声明を後に公刊したのが『フランスの内乱』(独: Der Bürgerkrieg in Frankreich)である。その中でマルクスは「パリ・コミューンこそが真のプロレタリア政府である。収奪者に対する創造階級の闘争の成果であり、ついに発見された政治形態である」と絶賛した[310][311]。
一方、その崩壊原因の分析も重要となった。二十年後の1891年、エンゲルスは『フランスの内乱』第三版の序文を執筆し、歴史的総括を試みている。エンゲルスはパリ・コミューンを「労働者と労働者代表からなる政府」として位置づけ、断固たるプロレタリアート的性質を持っていた」と断言し、コミューンが布告された諸政策の先進性を評価した。
しかし、「コミューン議員は、多数派―国民衛兵中央委でもまた牛耳っていたあのブランキストと、少数派―プルードン社会主義学派の門弟からなる、国際労働者協会の会員とに分裂して」おり、マルクスの科学的社会主義に基づいて政策決定できるものは少なかった。とりわけ、顕著に表れているのが、フランス銀行に蓄えられた金融資産の差し押さえを実行しなかったことである。エンゲルスは、ヴェルサイユ政府に対して軍事的経済的手段の両面で断固たる措置を取らなかったブランキ派とプルードン派の過失を批判した。
また、エンゲルスは工業を再編して労働者の生産組合を組織して、工業生産全体に連携させていくべきであったと語り、組織化された労働ではなく自由な労働を謳うプルードン流の経済運営は死んだことが明らかになったと主張した。同様に、ブランキ派は各地のコミューンの自由な連合を説いていたが、パリ・コミューンに全国的な権力を集中させるべきであった。軍隊、国家警察、官僚政治を打倒して古い国家権力を一掃し、公職の地位を一般投票で任命する任免権を人民に返還して、国家権力が支配者ではなく奉仕者となるよう、公職者の賃金を労働者の賃金と同水準に抑える措置をとることが肝要だと語った。まさにこうした試みが実践されたのが、パリ・コミューンである。
エンゲルスは「パリ・コミューンを見よ。それこそは、 プロレタリアートの独裁だったのだ」と言葉を発して結論とした。プロレタリアは国家の運営に参加し、通常の社会的事務と管理業務と同様に行政活動に加わり、国家の廃止という偉業を果たす歴史の局面に準備しなければならないと訴えた。マルクスとエンゲルスは、富裕層だけが利益を享受する旧来のブルジョア民主主義(ブルジョア独裁)を乗り超え、生産者・労働者が恩恵を受けられる大衆民主主義(プロレタリアート独裁)が導入されなければならず、プロレタリアートの独裁によって大衆の政治参加を拡大しながら人民を訓練していくことが来るべき社会主義革命の役割だと説いた。二人はその後も積極的にコミューンを擁護する見解を発信し続け、革命へと至る歴史的潮流に人民を指導する前衛党の樹立が急務であると説き続けた。こうしたコミューン擁護活動を通じ、ティエール政府に弾圧された活動家たちは革命運動のネットワークを拠点にマルクスと緊密に連携するようになった。マルクスとエンゲルスが一時亡命を余儀なくされた活動家たちに資金援助を働きかけた結果、娘婿ポール・ラファルグやジュール・ゲードをはじめ二人の支援を受けた革命家は後に大成して、フランス労働党の一翼を形成することになった[312]。
しかし、このときマルクスとエンゲルス、そして新しい労働者政党が目指す革命と社会主義国家の樹立を妨害しようとする偽りの兄弟がいた。革命の理想に対する最大の障害物はアナーキズムである。
アナーキズムとの対決
[編集]| アナキズム |
|---|
 |
1871年9月17日から23日、ロンドンにおいて、17名の中央評議会の委員とマルクス、エンゲルスらをはじめとする23人の主席者で臨時会議が開かれた。ロンドン協議会での主たる討議内容は、IWA内部のバクーニン派勢力とアナーキズムの思想―とりわけ、「政治不参加主義」の駆逐であった。労働者政党の組織化を前提とした政治運動の必要性が再度唱えられた[313]。
エンゲルスはロンドン協議会で、政治不参加主義がインターナショナル内部に浸透して運動を分裂させ、組織を内部崩壊させようとしていると指摘した。
エンゲルスは、全ドイツ労働者協会の党首ヨハン・シュヴァイツァーがビスマルクと提携して労働者を政府の政策に同調させようと試みて労働者運動を分断させてしまっていると告発した。また、「政治不参加主義の結果、9月4日にはジュール・ファーヴル(国防仮政府の外相)、エルンスト・ピカール(国防仮政府の財務相、パリ・コミューンの弾圧者)その他が政権を横領した。3月18日には、この政治不参加のため、……、革命の強化のために充てなければならない革命後最初の数日を、わざとなにもしないで空費してしまった」ように、革命が勝利を収める機会を無駄にしたことを指摘した。一方、「イギリスでは労働者が国会に出ることはそう簡単ではない。国会議員には歳費が全然出ないし、労働者は自分で働いて生活を立てるほかないからである。だから国会は労働者の手には届かない。ブルジョアジーは、国会議員に手当を出すことを頑なに拒んでいるが、こうすれば労働者階級の代表は出られなくなることを知りぬいている」ため、運動には困難が伴っていた。
しかし、エンゲルスは「労働者を国家に送ることをどうでもよいこと思ってはならない」と語って労働者を励ましている。「アメリカでは、最近開かれた労働者の大会が、政治問題に携わること、自分たちの代表として、職業的な政治家ではなく、自分たちと同じ労働者を送り、自分たちの階級の利益の擁護にあたらせることを決議し」、ドイツでは国会議員となった「ベーベルやリープクネヒトのようにこの演壇から発言できるなら、彼らの発言を全世界の人が聞く」のだと述べた。また、「普仏戦争に反対して…闘争を始めたとき、全ドイツが揺さぶられ、ビールの値段のためにしか革命をやらないようなミュンヘンでさえ、戦争の終結を求める大示威運動が起こった」ことに触れ、政治運動への参加の意義を説いた[314]。加えて、エンゲルスはスペイン連合評議会に対して、こうも語っている。
「政治問題への絶対的な不参加というのは不可能である。不参加主義の新聞もみな政治に関わっている。問題はただ、どういう仕方で政治に携わるか、どういう政治に携わるか、ということである。それに、我々の場合には、政治不参加というのは不可能である。たいていの国では、労働者党がすでに政党として存在している。政治不参加を説いてこの党をつぶすようなことは、我々のなすべきことではない。実生活の経験や、現存の政府があるいは政治的な、あるいは社会的な目的から労働者に加える政治的抑圧によって、労働者はいやおうなしに政治に携わざるをえなくなっている。労働者に政治不参加を説くことは、労働者をブルジョア政治の抱擁のなかへ押しやることになるだろう。とりわけ今は、プロレタリアートの政治活動を日程にのせたパリ・コミューンの直後であるだけに、政治不参加はまったく不可能である。
われわれは階級を廃止したいと思っている。その手段はなにか?プロレタリアートの政治的支配である。この点では誰も異存はないのに、なおかつ、政治に口を出すなという人がいる!不参加主義者はみな革命家を自称している。……。しかし、革命とは政治の最高の行為である。革命を欲するものは、その手段をも欲しなければならない。すなわち、革命を準備し、革命のために労働者を教育する政治活動をも欲しなければならない。それがないかぎり、労働者の闘いの翌日には……たぶらかされてしまうだろう。……。労働者党は、なんらかのブルジョワ政党のしっぽとしてではなく、独自の目標と政策をもつ独立の政党として建設せねばならない。
もろもろの政治的自由、集会、結社の権利、出版の自由、こうしたものはわれわれの武器である。……あらゆる政治的行為は現状を承認することを意味する、と言う。しかし、この現状がそれに抗議する手段をわれわれに与えている場合に、その手段を利用としたからといって、現状を承認することにはならないのである。」[315]
バクーニン主義者はエンゲルスの演説に反抗し、政治運動の推進を擁護するという案件で評決を下さないように抵抗した。マルクスとコミューン戦士たちによる反駁によって、インターナショナルが革命的な政治運動を主導すること、そのために「労働者階級を政党に組織することが不可欠である」ことが確認された。しかし、パリ・コミューンの反乱は全ヨーロッパの保守的なマスコミや世論を震え上がらせており、各メディアから、マルクスたちが黒幕とするインターナショナル陰謀論、マルクス陰謀論、ユダヤ陰謀論が出回るようになった。
こうした中、ジョージ・オッジャーらイギリス人メンバーはインターナショナルとの関係をブルジョワ新聞からも自分たちの穏健な同志たちからも糾弾された。ついにオッジャーは1871年6月をもってインターナショナルから脱退してしまう[316]。これによりマルクスのイギリス人メンバーに対する求心力は大きく低下した。マルクスの独裁にうんざりしたイギリス人メンバーは自分たちの事柄を処理できるブリテン連合評議会の設置を要求するようになった。自分の指導下から離脱しようという意図だと察知したマルクスは、当初これに反対したものの、もはや阻止できるだけの影響力はなく、最終的には彼らの主張を認めざるを得なかった。マルクスは少しでも自らの敗北を隠すべく、自分が提起者となってブリテン連合評議会を創設させた[317]。
マルクスの権威が低下していく中、追い打ちをかけるようにバクーニンとの闘争が熾烈を極め、いよいよインターナショナルは崩壊へと向かっていく[318]。
パリ・コミューン崩壊後、IWAに対する逆風は強まっていった。IWAは各国政府からテロ組織として見なされ、会員となった個人・団体は監視の対象となっていく。1871年、フランス政府はIWA加入を犯罪とする法令を発布した。加えて、この法律はコミューンの亡命戦士たちの引き渡しを要求していた。ドイツではベーベルとリープクネヒトが逮捕され、二年の禁固刑を宣告された。このようにマルクス派指導者が逮捕されて指導部を失ったため、IWA内部での対立も高まっていく。各国でも状況は悪化を辿り、アメリカでは全国労働総同盟が勢力を失い、イギリスでは分派が著しい状況に陥っていた[319]。
バクーニン一派はパリ・コミューン革命に関する独自の見解を提示し、マルクス主義に対抗しようとしていた。すなわち、革命とは自然発生するもので、下層の民衆による蜂起による権力の転覆と廃止が本来の姿であると見なしたのである。パリ・コミューンはマルクスに社会主義国家像の形成を促す一方で、その闘争はアナーキズムの宣伝に活用されたのである。フランスのプルードン主義やブランキ主義が勢力を失うのにしたがってバクーニン主義は勢いを強めていった[320]。バクーニンとその支持者であるスイスのジュラ連合に関する報告がなされたほか、選挙でのドイツ社会民主労働者党の勝利が祝された。バクーニン一派の追放が会議の眼目になっていた。これに対して、1871年12月、バクーニンもマルクス派に応酬すべく大会の即時招集を要求し、マルクスが牛耳る中央評議会の専制を非難する『ソンヴィリエ通達』という文書をあらゆる国の支部会に送った[321]。バクーニンは自由な政治組織による緩い連合を提案し、マルクスはその意図を疑い権威と規律を主張したが、この両雄の組織論はIWA大会ハーグ大会で討議されることとなった。
1872年9月2日、「IWAにとって生死の問題と化した」ハーグ大会が開催された。さっそく大会では中央評議会に対する信任をめぐって対立し、40名のマルクス派代議員とその他24名の反対派に分裂した。イギリス代表はバクーニンの思想に反対していたが、マルクスの理論や中央統制とも相容れなかったため、中央評議会に対する信任に反対票を投じた[322]。

続いて、政治権力の問題についてはマルクス派29票対バクーニン派5票、棄権9票で、政治権力の破壊を主張するバクーニン派に対して政治権力の奪取を提唱するマルクス派の勝利に終わった[323]。かくして、第7条付則として『規約』に「政党結成」と「政治権力奪取」が明記され、平和的な手段もありうるとして議会進出に意欲を示す文言が盛り込まれた[324]。さらに、これに終わらずマルクスは『インターナショナルのいわゆる分裂』という報告書において中央評議会に反対して無政府主義を掲げたバクーニンとその一派を除名するよう大会に対して勧告した。マルクスの動議を受けて、バクーニン、ジェーム・ギヨーム、シュウィッツギューベル、ブーケ、マロン、マルシャンらがIWAから追放された[325]。9月6日に中央評議会をロンドンからニューヨークに移転するという決議を採択した。同決議はIWAの運命を未来に切り開くことが期待されたが、皮肉にもIWAを衰弱させるものとなった[326]。
ハーグ大会終了後、アムステルダムで公開集会が開催された。マルクスは人々を前に演説をおこない、「労働者階級は、政治の分野でも社会の分野でも、滅びつつある旧社会を攻撃する必要がある、と宣言した」と表明している[327]。また、続けてこうも語った。
「労働者は、新しい労働の組織を打ち立てるために、やがては政治権力を握らなければならない。労働者は、古い制度を支える古い政治を覆さなければならない。(ただし)それぞれの国の制度や習慣や伝統に特別な考慮をはらわなければならない。また、われわれはアメリカやイギリスのように、労働者が平和的手段でその目的を達成できると思われる国があることを、否定しない。……。が、たとえそうだとしても、たいていのヨーロッパ大陸諸国では、実力が革命の梃子とならねばならなぬだろうということを、認識すべきである。()内筆者補足。」[327]
この演説は階級闘争の戦術面での相違や社会主義運動の多様性を示唆するものであった。各国市民の政治的自由度によって「改革」と「革命」の適宜性が左右され、労働者の階級闘争の方向性も、労働者党の戦術や政治的な役割も定まっていくということを指摘した。
第一インターナショナルの崩壊
[編集]
その後、最初の国際的政治団体にして労働者組織であるIWAはアナーキストによる執拗な解散運動に直面する。
バクーニン派は、中央評議会の「政治活動への積極参加」条項に猛反発して独自見解を提唱し、分裂運動を画策したため、ハーグ大会で除名処分を受けたが、彼らは当然処分を承服したりはしなかった。そこで、彼らはIWA本部のニューヨーク移転を機に、中央決定による組織運営を否認し、連絡と統計に基づく自由な連合体を作ろうと試み、独自のインターナショナル組織を作り始める。1872年9月15日バクーニン派は15名ほどの代表者がIWAの名を流用してスイスのサン・ティミエで大会を開催した。そして「社会民主同盟」から継承した「連合」の原理と政治活動の拒絶が新組織の綱領として掲げて新組織を樹立する。ここではこのとき発足したバクーニン派の新組織をアナーキスト・インターナショナルと呼称する。この新組織は加盟団体を募ったが、参加を表明した連合はベルギーとオランダとイギリスの一部支部に留まった。大半の地方支部は元のIWAに残留を表明した[328]。
無政府主義は社会主義の双子の兄弟と言える。アナーキズムは、革命の自然発生性を強調し、組織の中央統制に反対し、集団よりも個人の自由を価値として、暴力革命による急激な社会変革を求め、緩やかな「連合」による社会の統合を目指していた。その理想像はマルクスが目指した共産主義社会と何一つ変わるところはない。
しかし、理想を共有していたものの無政府主義と社会主義には方法論において決定的な違いがあった。マルクスの社会主義は階級闘争が長引くこと、革命の機会は容易には訪れないという現実感覚、大衆の支持を背景に権力を革命あるいは選挙で政権を掌握して「プロレタリアート独裁」を確立すること、議席を得て社会立法を進め階級格差を是正し、工業および農業、そして商業の均衡発展の道を模索するという国家ヴィジョンがあった。こうした段階を追って共産主義の理念を実現させるという現実的な立場をとっていた。
バクーニンらの無政府主義は反権力思想と自己完結型の共同体思想がもつ魅力によって、南欧の下層労働者やロシア、南米の貧農層を取り込んでいった[329]。
19世紀当時は重税、貧困、疫病、言論統制、官憲の取り締まり、医療・福祉・教育の欠如といった苦痛と圧政が是とされた反動的な専制国家の時代であった。とりわけ、工業化は遅れた諸地域では無政府主義とその暴力的方法論が受け入れられていった。例外的に農業国でもあり個人を重んじ自由を尊重するアメリカやフランスでも支持を集めた。一方、先発工業国のドイツ、これに遅れてフランスが、そして、大不況期を経験したイギリスなど労働運動の歴史的中核国ではマルクス主義の影響力が次第に強まっていった。「アナーキスト・インターナショナル」は数度の年次大会を開催し、スペインの革命やイタリアで多くの暴動を画策したが失敗に終わる[330]。また、バクーニンが世を去ってその後の発展の糸口と反乱工作の機会を失ってしまう。19世紀末にイギリス、フランス、ドイツ、アメリカをはじめ各国が社会立法に力を注いで圧政を捨てていくにつれて、無政府主義はしだいに個人革命家のテロリズムの世界へと追いやられて衰退していく[331]。現実路線に即して、内部統制が強い組織を持った社会主義党を作り上げ、国家権力の掌握に力を注ぐ道を選んだことにより、マルクス主義は時代の選別に耐えて生き残ったのである。

一方、アメリカに目を転じるとここでも新しい局面があった。要となる人物はIWAのアメリカ支部書記長フリードリヒ・ゾルゲである[332]。
IWAのマルクス派指導者は社会主義の分派勢力とのせめぎあいの中で巻き返しを図ろうとフィラデルフィアで大会を開催した。そこではアメリカ支部を中央評議会の直轄とする方針を定めて、中央評議会の権威で部内の刷新を図ることが決まった。しかし、無政府主義者の排斥とイギリス支部の脱落によって生じたIWAの空洞化によって、この決定はIWAを欧州の労働者協会からアメリカ合衆国の労働者協会へと変質させるものにつながった。また、無政府主義やラッサール主義政党の影響力を払拭するのは容易ではなく、アメリカにおける各支部の内部分裂がさらに激しくなっていった。1864年から65年の内紛の結果、ニューヨークの二つの支部が排斥されボルテなど主要メンバーが追放された。こうした情勢の中、内紛に疲れたゾルゲが書記長を辞任、すでに中核を失いって混乱をきたしたIWAは組織の命脈を保つことができなくなっていた。世界的にもIWAはもはや求心力を急速に失いつつあったのである。各国で社会主義政党の樹立と独自の政治運動が活発化し、国際的連帯を協議する局面ではなくなっていた[333]。
1876年、中央評議会は時勢の困難さを鑑みて解散を内定したうえで、フィラデルフィアで最期の年次大会を開く決定をする。ドイツ社会主義労働者党の代表とアメリカ支部評議会の10名の委員会が解散手続きをすすめた。7月15日、「国際労働者協会中央評議会は解散する」との決議のもと、IWAは正式に解散する[334]。
晩年の活動
[編集]ドイツ社会主義運動の再建
[編集]この節の加筆が望まれています。 |

第一インターナショナルの誕生と崩壊の後、社会主義は新たな発展期に入っていった。
ドイツでは1867年ヴィルヘルム・リープクネヒト、アウグスト・ベーベルがザクセン人民党を組織し、1869年8月にはドイツ統一の加速と歩調を合わせるかたちでリッティングハウゼン、ベルンヘルト・ベッカー、ヘスといった人物らとともにアイゼナハ綱領を採択、社会民主労働者党(独: Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP) 。通称「アイゼナハ派」と呼ばれる。後のドイツ社会民主党の母体となる)を組織した。ラッサール主義に対峙する本格的なマルクス派の社会主義政党が発足したのである[335]。
この時期の各国政府は労働者が選挙権を獲得していた。北ドイツ連邦では連邦議会が設置され、25歳以上で公的支援を受けていない男性有権者からなる成人男子選挙権が導入され、1867年8月の連邦議会総選挙が実施された。そのため、北ドイツ連邦では新たな有権者の票数確保の必要が生じ、政府が熱心に社会政策に取り組んだ。その一つが労働者の住宅問題の解決である。
エンゲルスは、ミュールベルガーが住宅問題を論じたことを受けて反論記事「住宅問題」を、ドイツ社会民主労働党の機関紙『フォルクスシュタット』(独: Der Volksstaat)に掲載した。労働者の住宅問題を政府が解決策を提示して、社会主義者もこれに協力して、共に住宅問題を解決させよよいう見解であったが、エンゲルスは政府の社会改良政策への迎合に反対の立場を採った。労働者階級の住宅事情が良くないのは住宅がないからではなく、快適な住宅に居住できないような階級的地位の低さに起因することであり、住宅を安価に低金利で販売したとしても抜本的な解決策には至らない。対症療法として効果が出れば一時的に労働者の懐柔につながるが、増加し続ける労働者の旺盛な住宅需要を満たす必要が依然として残され、一時しのぎの政策を採用しても住宅問題がつねに課題となっていくことに変化はないと語った。住宅問題解決に政府が積極的な姿勢を見せても、労働者の階級的抑圧状態が解消されることはなく、社会改良主義的な政策は労働者の目暗ましにしかなっていないと指摘した。

一方、ドイツ社会主義運動の大きな転機が生じた。その転機はドイツの二つの労働者党(アイゼナハ派とラッサール派)の1875年の合同に求められる。
両派の合同は1871年の普仏戦争の勝利を受けてドイツ統一が実現したということが契機となっている。ラッサール派はプロイセン王国を基軸に労働運動を展開するのが有利であるとする政治戦術を採用していた。一方、アイゼナハ派はマルクスの指導によって反戦と国際主義の立場をとり、反プロイセン王国の立場に立ってオーストリアを含む全ドイツ語圏の労働者の結集によって革命を起こして共和制の統一民族国家(大ドイツ民主共和国)を実現させるという構想を持っていた。ドイツの統一によって党派的分立の根拠が一つ解消されたため、ようやく両派は合同したのである。
かくして、アウグスト・ベーベル、ウィルヘルム・リープクネヒトが率いるドイツ社会民主労働党とフェルディナント・ラッサールが設立してドイツ内の労働者党の最大会派となっていた全ドイツ労働者協会が合同を果たす。1875年、ザクセン=コーブルク=ゴータ公国のゴータにて統一綱領「ゴータ綱領」を採択してドイツ社会主義労働者党(Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, SAPD)が結成された[336]。
だが、マルクスとエンゲルスは、ヴィルヘルム・リープクネヒトとアウグスト・ベーベルの政治的妥協を痛切に批判していく。帝国主義、軍国主義のドイツ帝国をいかに近代化させるかという問題が依然として残されていたのである。成人男子選挙制度はあったが、復古的な三級選挙による議会制度を革新して、民主国家の道筋を開いていくことが課題であった。マルクスは『ゴータ綱領批判(ドイツ語: Kritik des Gothaer Programms)』を執筆して、賃金が上昇すると経済停滞を招いて労働者の生活水準が低下するという「賃金鉄則」なるラッサール派の誤謬と共存することはできないと主張した。また、政治的・社会的不平等の是正といった目標はブルジョワ政党の理念であって、革命的プロレタリアートによる社会主義運動の路線ではないと指摘した。マルクスは、革命によって資本主義を打倒して国家を廃止するという理念を提示できないラッサール主義との合流をプロレタリアートに対する背信行為だと厳しく糾弾した[337]。
- 『ゴータ綱領批判』
マルクスは党幹部に対してドイツ帝国下でのブルジョア国家権力との消極的共存に甘んじるのではなく、暴力革命によって全権力を帝国政府から奪取してプロレタリアート独裁を確立し、社会主義国家の建設を目指すように言明した。
エンゲルスもベーベルに次のように警告した。
「マルクスと私はそのような根拠による新党の結成は認めることはできないし、それに対してどんな態度を―公的にも私的にも―とるべきか、きわめて真剣に検討しなければならないであろう。国外ではわれわれが、ドイツ社会民主労働党のありとあらゆる声明と活動に責任をもたされていることを忘れないでくれ。」[338]
マルクスとエンゲルスの怒りの矛先は、党の運営や指導に関して理論創始者に事前に相談しなかったリープクネヒトに集中していった。だが、内輪の争いに長く拘ってはいられない状況となっていく。
社会主義者鎮圧法という逆風
[編集]
1866年に社会民主労働党が結成されていたちょうどその頃、ドイツでは資本主義の成長とプロレタリアート階級の形成が本格化しはじめ、党は得票数を順調に伸ばしていた。1871年のドイツ帝国議会選挙で得票数12万4千票から1877年のドイツ帝国議会選挙では49万3千票を獲得、票数を5倍近く伸ばすことに成功した。
ドイツ帝国宰相ビスマルクは統一した労働者党に強い警戒感を抱くようになる。
二人のテロリスト、1878年5月11日にマックス・ヘーデル、6月2日にカール・ノービリングによって、二度にわたり引き起こされたドイツ皇帝ヴィルヘルム1世の暗殺未遂事件は社会主義運動の鎮圧を図る絶好の口実となった。10月19日、ビスマルクの主導で悪名高い社会主義者鎮圧法が制定された。1890年の撤廃に至るまで同法により、「社会民主主義、社会主義、あるいは共産主義の活動によって既存の政治・社会秩序を覆そうとする」あらゆる組織が非合法とされた。社会主義者は無所属ならば自由に立候補できたが、社会主義を謳うあらゆる集会や出版が禁止され、SAPDに限らず労働組合が非合法とされ、党員の職場からの追放が義務付けられるなど、SAPDは激しい弾圧の対象となった。ベルリン、ハンブルク、ライプチヒ、フランクフルトといった主要都市では戒厳令が敷かれ、警察によってSAPD党員や支持者が次々と検挙された[339][340]。
こうした厳しい弾圧を前に脱落者も生じた。ハンブルクではSAPD幹部が取締り前に党の解散を宣言し、指導部と印刷所を残そうと考えるものが現れた。労働者の政治的権利を犠牲にして国家権力に恭順を示し、取締りを回避しようとする右翼的な日和見主義の風潮が広まり、革命を断念して闘争を放棄する動きが広がった。多くの都市で党組織が解党を決議したため、SAPDは存亡の危機に瀕した[340]。

こうした動きは理論面での逸脱につながっていき、ドイツ修正主義の土壌となっていく。
スイスのチューリッヒに亡命したSAPDの後援者カール・ヘーヒベルクとその秘書エドゥアルト・ベルンシュタイン、シュラムの三名は、三星の署名を用いて『社会科学・社会政策年報』に「ドイツにおける社会主義運動の回顧」という論文を掲載し、マルクス主義の革命理論を公然と批判し始めたのである。修正主義者は階級闘争を否定して中産階級の重視、プロレタリア独裁と暴力革命に反対して議会制民主主義の枠内で福祉政策の推進を説いた点が挙げられる[341]。
エンゲルスは修正主義が党の結束を分断し、闘争の継続を困難にする理論的逸脱と見なして生涯をかけて糾弾を続ける。一方、迫害を受けた社会主義者にエンゲルスは資金援助をおこない、投獄された活動家に同情を示した。その一方で、合同後に妥協的となっていたSAPDが次第に左傾化していくことを歓迎し、「ビスマルク氏は七年の間、まるでこちらから礼金を支払っているかのように、われわれのために働いてくれ、いまや社会主義の到来を早めるための申し出を控えることができないようだ」と語っている[342]。
社会主義者に対して強まっていく弾圧の中で実施されたドイツ帝国議会の1881年のドイツ帝国議会選挙の結果、SAPDは三議席増やして12議席を獲得したという報は、エンゲルスにして「プロレタリアートがこれほど見事な振る舞いを見せたことはない」と言わしめ、彼を大いに喜ばせた。さらに、三年後の1884年のドイツ帝国議会選挙では議席を倍増させて24議席を獲得する快挙を成し遂げ、ついに、ドイツの労働者階級がイギリスやフランスからプロレタリアート運動の政治的理論的な主導権を取り戻す段階に到達したのである[342]。しかし、エンゲルスは、次第に勢力を増して拡大していく党内部に日和見主義が入り込まないかを危惧し、党幹部の声明を入念に調べるなど監視の目を強めていった。こうした中で浮上した危険人物がオイゲン・デューリングである。
『反デューリング論』の執筆
[編集]エンゲルスは順調なロンドン生活の一方で、ドイツの社会主義運動の今後については憂慮を抱いていた。

ドイツの二つの労働者党(アイゼナハ派とラッサール派)の1875年の合同が実現して社会主義運動の発展が続く一方で、党派的な対立が深刻化していたのである。とりわけ、党派的な影響を広げつつあったのが、ベルリン大学の視覚不自由者の私講師であったオイゲン・デューリングの学説だった。デューリングはカール・マルクスの理論を一つの仮想敵として位置づけ、暴力革命や中央集権制と計画経済の導入を否定して、プルードンやラッサールに似た独自の社会主義思想を作り出そうとしていた[343]。
ベルンシュタインもデューリングの学説に影響を受け、ベーベルらにデューリングの著作を送り、ベーベルもこれに呼応してデューリングを支持することを『フォルクスシュタット』(独: Der Volksstaat)誌上で表明した。マルクス主義に忠実なリープクネヒトは危機感を強めてデューリング批判の必要性をエンゲルスに説き、論文を執筆するように要請した。エンゲルスも「彼のまわりに一つの派閥、すなわち将来別個の党になる中核を公然とつくりはじめた」ことに懸念を感じたため、デューリングを批判する論文を機関紙『フォルウェルツ』(独: Vorwärts)で連載した。デューリングは多方面にわたって精力的に論説を展開させていたため、エンゲルスはデューリング批判を全方面に拡大させていく必要に迫られていった[344]。
その結果、ウラジーミル・レーニンが語るところの「哲学、自然科学および社会科学の諸領域に属する最大の諸問題が究明され」、「驚くべき内容豊富なまた教えるところの多い書物」が完成した[345]。これが1878年に出版されて『反デューリング論』(正式名は『オイゲン・デューリング氏の科学の変革』、ドイツ語: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft)となった[346]。
『反デューリング論』の中心軸は弁証法的唯物論であり、自然科学から社会科学・人文科学に至る広範な科学領域における弁証法の適用の試みとなっている[346]。
ウラジーミル・レーニンは、本書の位置づけを「最後まで一貫した唯物論か、それとも哲学的観念論のうそと混乱か、どちらかである。―これが『反デューリング論』の各パラグラフに与えられた問題提起である」と語っている。唯物弁証法が自然科学から社会科学に至る全領域にまたがる包括的な理論であることを立証することがその目的とされた。本書の内容は概ね次のとおりである。
序論においてヘーゲルの弁証法が総論として整理され、観念論の克服と唯物論への転換の重要性が指摘されている[347]。序論の後半部分はデューリングの野心と活動への敵意が表明され、彼の学説に対する宣戦布告となっている。
次いで、エンゲルスは、第一編では自然科学分野への関心に留まらず、法や道徳、真理、平等や自由といった精神哲学の分野に踏み込んだ見解を提示していった。第五、第六章において弁証法が宇宙の秩序とどう関係するかが、第七、第八章で有機体、生体の働きに弁証法がどのように現れているか、デューリングの科学についての理解が如何に不十分なものであるかが論じられている。
後半は道徳ならびに法哲学が論じられた。エンゲルスはデューリングの未熟な世界観を紹介しながら、道徳や真理は時代とともに歴史的に形成されるもので、固定的な万世不易の代物ではないと論じた。
最後に弁証法理論が紹介されている。ヘーゲルの弁証法が総論として整理され、弁証法の核心部分が提示されている。物質や生物の世界で弁証法がどのように展開しているかを例示しながら、弁証法が1)「量から質への転化、ないしその逆の転化」、2)「対立物の相互浸透(統一)」、3)「否定の否定」の三つの構成要素から成り立っていることを明らかにしたのである[348]。弁証法と自然科学の関係性は『自然の弁証法』でさらに深く論じられていく予定であったが、エンゲルスがマルクス死後『資本論』の続編刊行の任に集中していたため、結局遺稿に終わった。エンゲルスは、自然科学分野への関心に留まらず、社会科学分野についての理論的考察を提示していった。
第二編では社会科学の領域に踏み込み経済学を中心に、デューリングが重視した「暴力」や「経済」という切り口から人類社会における政治、階級、国家、奴隷制、軍国主義が次々と論じられていく。私有制の発達から奴隷制や資本主義的階級制度の起源が論じられ、暴力による原初的秩序の形成というデューリングの見解が批判されていく。エンゲルスは、人類史における抑圧は経済システムの中核部分に存在する所有形態に起因するものであり、経済要因によって政治的支配の形態が変動していくという唯物史観の理論を紹介した。また、後半部分ではマルクス主義の骨格部分に当たる剰余価値論の紹介に充てられている[349]。
最後に、第三編では社会主義思想の登場と発展を歴史的理論的な側面から概説がなされている。サン・シモン、シャルル・フーリエ、ロバート・オウエンを取り上げ、思想の革新性と問題点を整理し、これらを空想社会主義として位置づけた。一方、産業革命の本格化に伴う資本主義の発達が進行すると、時代状況を反映する新しい社会主義の登場が現実になっていく。マルクスはヘーゲル主義から弁証法を批判的に取り入れ、唯物論と結合させることにより、唯物弁証法に基づく歴史理論―史的唯物論を確立した。エンゲルスは、マルクスの理論的業績により経済学的アプローチから資本主義の盛衰と社会主義の到来の必然性を論じた科学的社会主義が確立を見たことを明示した。
『空想から科学へ』
[編集]エンゲルスは、上述の歴史観を整理して「社会主義とはなにか?」という大衆の問題関心に応える章を追加した。『反デューリング論』はドイツ語だけであったのと、マルクスの娘婿で「フランス下院議員であるポール・ラファルグの要請によって、私はこの本の3つの章をパンフレットにまとめ、それをラファルグが翻訳して、1880年に『空想的社会主義と科学的社会主義』という表題で出版した」。これが『空想から科学へ』というタイトルで知られている著作である[350]。
『自然の弁証法』
[編集]エンゲルスは、1870年代から80年代にかけて、マルクスの手で完成を見た史的唯物論の普遍性を社会から自然の領域に拡張することを試みた。政治経済と並んで自然科学についても学び、哲学的な唯物論の立場から自然の弁証法の解明と論理的把握を試みた。1883年にエンゲルスの書き残した『自然の弁証法』に関する論考は、最新の自然科学が常に今日でも直面する哲学的危機に対して、多くの重要な示唆を与えている。同書で一章を構成した「猿が人間になるについての労働の役割」 (1876年)も注目に値する。
ロシア革命の可能性
[編集]マルクスの死後
[編集]エンゲルスの最晩年の到達は、『家族・私有財産・国家の起源』(ドイツ語: Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats)、『フォイエルバッハ論(ルートヴィヒ・フォイエルバッハとドイツ古典哲学の終結)』(ドイツ語: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie)、『フランスにおける階級闘争 1895年版序文』「エルフルト綱領草案批判」ほか多くの著述と、マルクスの死後、多くの人物に対して語られたエンゲルスの書簡の中の言葉に表現されている。
それらの中でエンゲルスは、自分たちの大局的な展望と行動・運動の正しさを正当にも主張すると共に、自分たちの置かれた情勢の諸事情から不可避的に生じたそれぞれの局面での誤りや限定的な正当性について率直に述べている。そのような振り返りも、自分たちが作り上げてきた世界史的運動の後世の継承者たちへの思いやりをもって語られている。
マルクスの死
[編集]
エンゲルスの幸せはリジーの病状の悪化に伴って影が差すようになっていった。
1870年代末、リジーは慢性的な喘息に加えて、膀胱の悪性腫瘍に冒されていた。エンゲルスはリジーを手厚く看病したほか、懸命に家事をこなしてリジーが安らかに最期を迎えられるように勤めた。1878年9月11日の晩、リジーは死に瀕する状態となっていた。この日エンゲルスは意を決してリジーへの愛を果たそうと大胆な事をしている。近所のセントマークス教会まで駆け出してギャロウェイ牧師を呼んできたのである。エンゲルスはベッドに横たわるリジーと英国国教会の儀式に則り、正式な夫婦として結婚の証を得ることになった。元来、エンゲルスは無神論者であり、結婚をブルジョワの偽善的慣行と見なしてきた。しかし、最期の瞬間にリジーが幸せであることを願い、結婚の儀式によって夫婦であることの承認を受け、二人で互いの愛を確認したのである[351]。
まもなく、エンゲルスが心から愛する妻リディア・エンゲルスは息を引き取った。彼女はロンドン北西部のローマ・カトリック教会のセント・メアリー墓地に埋葬された。エンゲルスはリジー死去の知らせをマルクスのみならず友人たちに発信した。マルクスも今度は丁重に返事を送り、弔意を示している[352]。
リジーの死以降、エンゲルスは身近な人を次々と失う悲しみの時期と持ち前の一層の力強さを発揮していく時代に踏み出していく。

1880年代、60歳代に入ったマルクスとエンゲルスたちは最晩年に入りつつあった。とりわけ、マルクス夫妻の健康状態は厳しい状況になっていった。
1881年の夏、マルクスの妻イェニー・マルクスは肝臓癌を患い、臨終の床にあった。だが、マルクスも腎臓肝臓の障害に苦しみ、肋膜炎を抱えて病床にあったのである。12月2日、イエニーがこの世を去った時マルクスの容態も悪く、妻の葬儀に出席することもできなかった[353]。
これ以降、マルクスは『資本論』の続編の刊行を継続できないことを悟り、研究から離れて身体の回復のために保養地での静養生活に入ることとなる。肝臓病の治療のためにチェコのカルロヴィ・ヴァリといった温泉地を訪ねたほか、1882年2月から気管支炎治療のために温暖で乾燥した気候の土地を求めて、北アフリカのフランス植民地アルジェリア旅行に出かけ、中心地アルジェを訪ねている。帰国したマルクスはイギリス南部のワイト島の保養地ヴェントナーで過ごした[354]。エンゲルスは意欲低下に直面したマルクスを苦々しく感じていたのだが、マルクスも「エンゲルスの興奮ぶりがじつは私を苛立たせた」と語っている。落胆したエンゲルスは「イェニーが死んだ時、モール(マルクス)も死んだのだ」と述べた[354][355]。マルクスは居心地の良い土地を求めて各国を放浪を続けたが、行く先々で悪天候に悩まされて気管支炎を拗らせていった。1883年1月、マルクスにさらなる悲報が襲う。マルクスの長女ジェニー・ロンゲが38歳の若さで急逝したのである[354]。末娘エリノアが語るには、これが「最後の恐ろしい打撃」となった[356]。
2月に入るころには、マルクスは喉頭炎、肺炎を悪化させて急激に体力が衰弱、食事も喉を通らず、声も出せず、薬も効かない状態となっていた[357]。エンゲルスは盟友の最期を覚悟し、マルクス邸に毎日見舞いに通った。しかし、1883年、カール・マルクスは周囲の手厚い看病の甲斐なく死去してしまう。3月14日、エンゲルスがいよいよ最期が近いということで、ヘレーネ・デムートに促されてマルクスの部屋に入った時、マルクスは既に脈もなく、この世を去っていたのである[358]。エンゲルスはマルクスの最後の瞬間を振り返りつつ、ニューヨークのフリードリヒ・ゾルゲにこう語った。
「とにかく、人類は頭一つだけ低くなった。しかも、人類が持っている最も大事な頭一つだけ。プロレタリアートの運動はさらに前進を続けるが、その中心がなくなった。フランス人、ロシア人、アメリカ人、ドイツ人が決定的な瞬間にはおのずからそこに向かい、天才と完璧な専門知識をだけを与えられることのできる明瞭で、抗弁の余地のない助言をいつでも受けることができた、その中心がなくなった。……。最後の勝利は確実だ。だが、回り道、一時的な地方的踏み迷いは…いまやはるかに多く生じるであろう。さあ、我々はそれを始末しなければならん。このためにこそ、我々がいるのではないか?だから我々は決して勇気を失わないであろう。」[359]
マルクスの葬儀は家族のエリノア・マルクスと同志であるエンゲルス、シャルル・ロンゲ、ポール・ラファルグ、ヴィルヘルム・リープクネヒト、カール・ショルレンマー、フリードリヒ・レスナーら古くからの友人達、計11人で行なわれた。このときのエンゲルスの弔辞は「カール・マルクスの葬儀」として残されている[360]。エンゲルスはマルクスの業績を次のように締め括った。

「ダーウィンが生物界の発展法則を発見したように、マルクスは人間の歴史の発展法則を発見しました。……。それだけではありません。マルクスは今日の資本主義的生産様式とそれが生み出したブルジョワ社会との特殊な運動法則をも発見しました。剰余価値の発見とともに、この分野に突然光が灯されました。しかるにこれまでの一切の研究はブルジョワ経済学者のそれも、社会主義的批判家のそれも、暗闇のなかを踏み迷っていたのでした。……。学識の徒としては上にあるとおりでした。でもこれは、まだこの人の半分をも示すものではありませんでした。マルクスにとって科学は歴史の動力、革命的な力でした。……。というのは、マルクスは、何よりも革命家だったからです。資本主義社会とそれによってつくりだされた国家制度との打倒に…協力すること、近代プロレタリアート…の地位と欲求とを意識させ、みずからを解放する条件を意識した近代プロレタリアートの解放に協力すること―これが彼の一生の使命でした。闘争は彼の本領でした。そして彼は、類いまれな情熱と粘り強さと成功をもって闘いました。……。
そして、彼は、シベリアの鉱山から全ヨーロッパとアメリカを超えてカリフォルニアまでにわたって住む何百万という革命的同志から尊敬され、愛され、信頼されながら没しました。……。彼の名は幾世期にもわたってとどめられましょうし、その事業もまた然りでありましょう。」[361][362][363]
エンゲルスに続き、リープクネヒトはこう語った。
「我々の受けた打撃は大きい。だが、我々は悲しみはしない。故人は死んでいない。彼はプロレタリアートの心の中に生きており、その頭脳の中に生きています。……。死んでもなお生ける友よ!我々はあなたが示した道を、目的を達するまで歩むであろう。我々はあなたの墓の前にこのことを誓います。」[364]
マルクスが世を去り、エンゲルスは孤軍奮闘することを余儀なくされていく。エンゲルスは盟友の死を受け止めた後、マルクスの理論の確立を図るとともに社会主義運動の発展のために、残りの生涯のすべてを捧げようと決意を固めていった。1884年10月15日の友人宛ての書簡で心情を率直に吐露している。
「僕は一生の間いつも第二ヴァイオリンばかりを弾いていた。これならば相当上手といったところまでやれたように思う。が、何といっても、マルクスという第一ヴァイオリンが上手であったのですっかり有頂天になっていた。これからはこの学説を代表して僕が第一ヴァイオリンを弾かねばならぬのだ。よほど用心をしなければ世間の物笑いになるかもしれない。」[365]
周囲はエンゲルスに親類縁者の多い大陸に戻り、スイスのような地で暮らすように勧めたが、マルクスの遺志を継ごうとするエンゲルスの決意は固かった。エンゲルスはロンドンを離れることを拒み、1883年4月末にはアウグスト・ベーベルに書簡を送り、マルクスの学問的偉業を継承することに全身全霊を注ぎこむ覚悟を示した。
「ここ(ロンドン)だけに理論的な仕事を続けていくための平穏さがあるのだ。……。63歳になるいま、自分の山ほどある仕事、それに一年目の仕事として『資本論』第二巻、二年目の仕事としてマルクスの伝記のほかに、1843年から63年までのドイツの社会主義運動と64年から72年までのインターナショナルとの歴史を書く予定になっているいま、……1848年と49年のような事態にふたたびなるようなことがあれば、またもや馬にまたがるであろう。しかし、いまは……マルクスの書斎に自発的に集まってきた万国からの多くの連絡の糸を、私の力の及ぶ限り、どうしても断ち切らずおこうと思う。」[366]

エンゲルスはマルクス主義の新しい中心となり、全世界の社会主義運動の発展のために残りの人生のすべてを賭けることになる。このとき、エンゲルスの力となったのはマルクス家の家政婦ヘレーネ・デムートである。ヘレーネはエンゲルス家に移ってマルクス遺稿の整理を助けると同時に、エンゲルス家の家政を担当して、エンゲルス家に参集した社会主義者へのもてなしをおこなうことで、エンゲルスを支えることになった。そして、二人でマルクスの手紙などの整理をする時間が、残された者の傷心を癒す貴重な時間となっていった[367][368]。
マルクス遺稿の整理
[編集]
かつてない重責がエンゲルスの双肩にかかっていったが、差し当たり直面した難題はマルクスの遺産相続の問題であった。
マルクスは、膨大な書籍数を誇る書庫、膨大な量の未整理の草稿や書簡を保管していた[369]。これらの遺産は第一に末娘のエリノアが相続人となり、第二にエンゲルスがエリノアの後見人として遺産管理人となって『資本論』の完成を目指すということが遺言により確認されていた。しかし、1883年6月、次女のラウラ・ラファルグがこれに反発して異議を申し立てたのである。父から書類や文書を継承して遺稿を整理し、『資本論』や『インターナショナルの歴史』執筆の一端に加わるように言われていたことに言及して、自分にも遺産相続権があるのだとエンゲルスに執拗に要求した。これに対して、エンゲルスは『資本論』執筆の役目は自分にしか成し得ず、末娘のエリノアが指名されたのは彼女がイギリスに在住していたためで、ラウラを排除する意図はないと説明した。かくして、1883年8月、エリノアがマルクスの評価額250ポンドの遺産相続人となる正規の書面が交付された。エンゲルスはラウラに「マルクスの遺稿を出版するという共通の目的を達成するために協力しましょう」と語り、マルクスの書庫にあったフランス語文献は全てラウラに送るなどして姉妹間の紛争をなんとか調停し、ようやく万全の環境のもとでマルクスの業績の整理に着手することとなった[370]。
マルクス死後のエンゲルスの仕事は二つの課題に絞られていた。
すなわち、マルクス主義の体系化と理論を完成させること、そして、国際共産主義の運動を組織して社会主義革命の政治的準備を整えることである。エンゲルスは当面の仕事をマルクスの遺産の整理に費やした。エンゲルスは、『資本論』に関するマルクスの遺稿の編集、それまでのマルクスとエンゲルス自身の著作の諸言語への翻訳に尽力した。当時の諸情勢と全世界の労働運動における自らの位置とを考慮し、エンゲルスは的確にもマルクスの主著『資本論』の完成をマルクス亡き後の自らの最重要課題と位置付け、編集に取り組むことになった。
実際、マルクスの主著『資本論』の第二巻および第三巻の刊行は、エンゲルスの豊富な知力と実務的能力なしには為しえなかった。
マルクスの遺稿は第二部「資本の流通過程」、第三部「総過程の諸容姿」を合わせて二つ折り判で1000ページという膨大な量にのぼり(一説では数m3にのぼったともいわれる)、その筆跡は解読が難しいもので、しかもその内容は著作としての完全な筋道をなしていない部分が多かった。内容の難しさのみならず、原稿が未完成であったことも編集を困難にした。象形文字風の独特な略字によって綴られている文章を読み取りつつ、未整備のまま各所に散乱する典拠情報をまとめていく作業は至難を極めるものだったのである[371]。エンゲルスは、これらマルクスの遺稿の編集を晩年の視力の衰えと闘い、全世界の労働運動の助言者としての激務の合間を縫いながら進めた。
1883年8月、エンゲルスはベーベルに宛てて作業が思うように進展しない苛立ちを打ち明け、「二つぐらいの章を別にすれば、すべてが下書きだ。典拠の引用は未整備で乱雑に山積みされており、あとで取捨選択しようとして集めるだけ集めたものだ。おまけに、絶対に僕しか読めない―それも苦労してやっと読める―あの悪筆だよ」と伝えている[372]。
マルクスの遺稿整理に追われ途方に暮れるエンゲルスに重要な発見があった。遺稿のなかからルイス・ヘンリー・モーガンの文化人類学研究に関する研究ノートを発見したのである。
『家族・私有財産・国家の起源』
[編集]
エンゲルスは、カール・マルクスの史的唯物論の立証と世界史論の構築に情熱を傾けた。とりわけ重要な関心事となったのが、原始共産制に基づく先史時代の共同体の研究である。このような古代史への関心から執筆されたのが、『家族・私有財産・国家の起源』(ドイツ語: Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats,1884)である。本書は、エンゲルスの老年期における最高傑作のひとつである。
本書執筆の経緯はマルクスの遺稿整理にその契機があった[373]。マルクスは生前、古代社会や古い形態の共同体の研究に没頭していた。
1870年代、最晩年に達したマルクスはロシア農村共同体の研究に着手し、やがて共同体一般への関心を高めていった。やがてマルクスは原始共同体への研究の手がかりをルイス・ヘンリー・モーガンの文化人類学研究に求めた。モーガンはイロコイ・インディアンを調査研究した成果を『古代社会』にまとめていたが、マルクスはモーガンの著作とその周辺の関連文献を読み漁り、詳細なノートを作成していた。しかし、1883年にマルクスは研究の半ばで死去する。
本書の序文に「以下の諸章は、ある程度まで遺言を執行したものである」とあるように、エンゲルスがマルクスの研究ノートを使って独自に仕上げたものである。エンゲルスはマルクスの中途に終わった人類学研究を継承し、ヘーゲル弁証法の方法論を加えて唯物史観に構築し直すプロジェクトに携わっていく。この頃、エンゲルスは青年期から関心を深めていた古代ゲルマン人の部族制社会の研究に邁進しており、『原始ゲルマン人の歴史』や『フランク時代』の二編の論文を執筆するなど古代史の研究で成果を出そうとしていた[374]。
エンゲルスは、『空想から科学へ』の中で原始共産制社会の存在を指摘し、平等な共同体が有史以前に存在していたと考えていた[375]。一方、ドイツではカール・カウツキーによる『家族と婚姻の歴史』の出版があり[374]、1879年にはアウグスト・ベーベルによる『婦人論』が刊行され、社会主義による女性と家族に関する理論的考察が試みられていた。しかし、これらの文献は女性の抑圧を人類史の宿命として位置付けるもので、社会主義による女性の解放を主張していたものの、エンゲルスにとっては不十分な研究でより完成度の高い研究が必要だと感じられた[376]。
1884年2月、こうした研究活動の中でエンゲルスはマルクスによるモーガン研究のノートを発見した。
エンゲルスは男性による女性への支配の構造が確立される有史時代以前の原始共産制社会を論じ、原始から古代の単婚制の奴隷制社会への移行過程を整理したのである。エンゲルスの研究は論文としてドイツ社会民主党の理論雑誌『ノイエ・ツァイト』(独: Die Neue Zeit)に掲載する予定であったが、1884年4月から5月にかけての二か月に及ぶ執筆過程で原稿が膨らみ続けて膨大なものとなってしまう。そこで単著で刊行することとなり、「いわば(マルクスの)遺言を執行したもの」として1884年に『家族・私有財産・国家の起源』が刊行されることになった[377][378]。
本書の概要は三部分に整理することができる。一章から三章までの冒頭はモーガン説と古代の人類史の発展過程の紹介に充てられている。まず、原始の人類社会には新時代が到来し始めていた。
第一章では文明期への移行の契機が整理されている。人間が「野蛮」から、「未開」をへて、「文明」にいたる、人類社会の発展図を略述した章である。採集・漁業・狩猟からなる野蛮段階から技術の取得によって新段階へと移行する発展のなかにあった[379]。人々は土器の製作をおこない、牧畜農耕への未開段階へと移行を果たす。さらに人類はムラからクニへと社会編成を変えて、金属器の製作技術を高めて灌漑農業や騎乗遊牧生活を拡大させて、各地で有史時代へと移行を果たした[380]。第二章は、原始的な家族形態を復原して今日の資本主義社会における一夫一婦制の起源を明らかにする部分、階級社会における一夫一婦制の批判する部分、いかに婦人は解放されるのかという共産主義社会での家族と結婚という三つの部分が書かれている[381]。
第三章では、原始的な家族形態をなすイロコイ族の具体的事例が紹介されている。
家族は社会の根幹であったが、野蛮段階では部族を構成する複数男女の集団婚であり、誰が子どもの父親であるか不確定だったため、母系制の共同体を形成していた。しかし、農牧業の発達による富の形成は土地の分割と私的所有をもたらしていく。未開段階の人類は、財産となる土地や家畜の所有を戦闘力に優れる男性の権限に移し替えていった。私有財産制度は、実子への財産の継承、即ち世襲原理を可能とするために、母系制の集団婚から父系制の対偶婚へと婚姻制度の変更を余儀なくさせた。これが画期となって、人類は古典古代へと移行していく。エンゲルスはここで「乱婚(無規律性交)→血族婚→プナルア婚→集団婚→対偶婚」という発展図式を考え、私有財産制度の成立とともに、母系制氏族社会が転覆され、「女性の世界史的敗北」が起きたとした[382]。
私有財産は婚姻制度を家父長制から一夫一婦制へ移行させたが、それとともに一夫一婦婚そのものの内部に第二の対立が発展してくると語った。婚姻が法的制度として確立される一方で、不義密通が生じたのである。エンゲルスは、単婚制は姦通と娼婦制度によって補完されるとした。不貞は厳禁され厳罰に処されはするが、姦通が結婚制度の不可避な社会的制度になった。エンゲルスは、こうした矛盾は社会主義革命によって資本主義が倒壊すると私有財産制が廃止され、単婚制家族の崩壊が始まると歴史は一変革を経験すると予測した。エンゲルスは、私有財産の主要部分、すなわち、生産手段の私的所有の廃止されることで、財産の相続を目的にした一夫一婦制の基礎も消滅するのだと主張した[383]。
第四章から第八章は古代ギリシア、古代ローマ、古代ゲルマンの氏族共同体が紹介されている。いずれも氏族は国家に先行する社会組織であり、史書や現行制度の痕跡からそれを証明しようとしている。ただし、一様なものではなく、民族ごとに豊かな形態があることをエンゲルスは叙述している。
第九章は全体を理論的に結論づけてまとめた章である。国家の発生についての理論的総括がおこなわれ、この部分はマルクス主義階級国家論の基礎の一つとなった。
最後に、エンゲルスは「文明批判」をおこない、文明が金属貨幣と利子、商人、私的土地所有と抵当、奴隷制度を発明して、最終的に人類は奴隷の反乱を防止して階級闘争が内乱へと発展する革命的契機を回避する調停機関として国家を創造したと指摘した[384]。だが、社会主義革命によって生産手段が共同所有に移管されることによって、資本主義経済のもとで奴隷化されていた労働者階級の自立が進み、階級闘争が終わりを告げると役目を終えた国家は廃止されるとされた。そして、母系制氏族社会がつくりだした民主的な社会が共産主義になって高次の形で復元されると主張した[385]。エンゲルスは、国家や一夫一婦制、私有財産を自明のものとするヘーゲル的な歴史観に対して、それらが歴史的なもの、すなわちある条件のなかで生成し、またその条件の解消にともなって消滅(変化)するにすぎないとする歴史観を提示した[386]。
『資本論』編纂
[編集]1884年6月、エンゲルスは『起源』の執筆を終わらせ、ようやく『資本論』第二巻の編纂に取りかかることになった。
『資本論』は前述に指摘した通り、断片的な草稿の集合体で、執筆箇所を加えて編纂を進めなければならなかった。だが、エンゲルスは既に高齢となっており、一日8時間から10時間の長時間デスクに向かい続けたために腰痛を悪化させて、医者からデスクワークを禁じられてしまう。そこでエンゲルスは植字工オスカー・アイゼンガルデンを秘書として雇い、口述筆記をさせることで仕事を継続させた。1884年6月から85年11月にかけての一年半をかけて執筆をすすめては毎晩読み返しをおこなうという日々であった[387]。エンゲルスは次女ラウラに宛ててこう語った。
「土曜日(3月14日)には、ニムとタッシーがパンプスもろともハイゲートへ行くでしょう。僕は駄目です。身体を動かす力が依然として安定せず、じっとしているようにという簡単な注意書をたったいま受け取ったところです。どうせのこと、『資本論』の仕事を続けることにしましょう。これは彼自身の手でつくられた、彼のための記念碑になるでしょうし、また、他人がモールのために建てることのできるどんな記念碑よりもずっと素晴らしいものになるでしょう。この土曜日で二年が経ちますね!それでも、この本の仕事をしている間は、彼と心を通わせているのだ、と僕は本当にそういうことができます。」[388]
『資本論』第二巻は1885年に刊行される。
第三巻は長く困難な数年にわたる編集作業の末、1894年に刊行、マルクスの「遺産」を世に送り出した。エンゲルスは単なる『資本論』の編集者、マルクスの遺稿の整理執行人ではなかった。編集の最中に現れるマルクスの理論、殊に『資本論』に対する剽窃、中傷、誤解に対しては論陣を張った。
『資本論』第二巻、第三巻のエンゲルスによる序文に、資本主義論の最前線でマルクスの理論の擁護に奮闘するエンゲルスの姿を垣間見ることができる。また、エンゲルスは、資本主義の最新の発展段階の諸現象を分析するとともに、資本主義社会と労働者階級の最新の発展を観察し、それまでの自分とマルクスの活動を振り返り、未来社会への道筋の新しい見地を提示した。かつての潤色な革命への展望は、『資本論』の登場とともにより一層確固たる世界観となった唯物史観と、まもなく独占資本主義、帝国主義の段階を迎えんとしていた資本主義の急速な発達の現実の政治経済情勢分析の蓄積とによって、現実的な、したがってより具体的かつ政治的な歴史変革の必然性と民主主義の発展とに関する展望に置き換えられた。
世紀転換期と社会主義の復活
[編集]ドイツとフランスのマルクス主義者たちが互いに呼びかけをおこない、フランス革命の起点となったバスティーユ襲撃の百周年にあたる1889年7月14日、パリのペトレル通りでパリ創立大会を開催した。正統派のマルクス主義者からなるこの集会では20カ国から400名に上る代表者が出席して、エドワール・ヴァイヤンとリープクネヒトが議長を務めて討議を進め、第二インターナショナルの発足が宣言された。

この集会ではイギリス側からケア・ハーディ、ドイツ側からはアウグスト・ベーベル、ヴィルヘルム・リープクネヒト、エドゥアルト・ベルンシュタインといった人物が、フランス側からはジュール・ゲード、ポール・ラファルグ、シャルル・ロンゲ、ヴァイヤンが、オーストリア側からはヴィクトル・アドラー、アメリカからはサミュエル・ゴンパーズ、ロシア側からゲオルギー・プレハーノフが参加した。労働運動の国際的発展の段階に入り、各国で社会主義政党の時代が到来したという現状認識が確認され、ドイツ・フランス・イギリスで社会主義者の立候補と当選が次々と実現して、議会での勢力拡大が見られた。そして、一)、フランスにおける社会主義者たちを統一する。二)、8時間労働制を要求する。三)、常備軍を廃止して民兵制を導入する。四)、普通選挙の実現を要求し、社会主義者の議会への進出を図る。五)、メーデーを国際労働運動のための休日とする、といった以上の五点が決議された。
パリでは、修正主義路線を説くイギリスの社会民主連盟の指導者ヘンリー・ハインドマン、フランスのブノア・マロンといった可能派(ポッシビリスト)の集会も同時に開催されたが、二年後に両派の統合が確認され、国際労働運動の結集が果たされた。労働立法の推進と政治運動への参入が支持されるとともに、無政府主義の排除が確認され、ゼネスト戦略の採用を主張していたフランスのアナルコ・サンディカリズムが拒絶された。一方で、アメリカ労働総同盟が1890年5月1日に8時間労働制の実現のためにゼネストが呼びかけられ、大規模なデモが実行されたことが集会で支持された。
パリ創立大会はマルクス主義的方向を明確に定めた大会であったが、このとき発足した第二インターナショナルは中央評議会を備えた中央集権的機構にはなりえなかった。各国でマルクス主義路線の社会主義政党が発足しており、国際的な連絡と議論の場を設けて各国での議会戦略を練り上げていくことが主たる関心事であった。第二インターナショナルは、組織が樹立されて12年間にわたって、国際的な運動の指導に当たる中央委員会がなく、国際的な合同機関誌も持たず、正規の共同規約も統一綱領も、強制的拘束力のある決議もなく、正式の名称もない状態で活動していた。この点では、第二インターナショナルは第一インターナショナルには組織力として及ぶものではなかった。この組織力の欠如は、戦争の機運が生じてナショナリズムが高まると、国際主義を擁護して反戦を貫き、各国労働者の連帯を守るということができなかった主たる原因で組織崩壊を招く致命傷となった。
1891年8月のブリュッセル大会では、一)、労働条件のための立法を要求すること、二)、国際的な労働組合運動の組織化を推進することが議題にあがった。
この間、エンゲルスは喫緊の政治情勢に対し諸国の労働者階級の組織に助力を与えた。勢力が増大したドイツにおいても、スペイン、ルーマニア、ロシアで新たな一歩を踏み出そうとする社会主義者からも、老エンゲルスの助言が求められた[389]。ロシアの若い革命家レーニンは、エンゲルスを、マルクス亡き後の「全文明世界における現代プロレタリアートのもっともひいでた学者であり教師」と目していた[390]。
1893年8月のチューリヒ大会では、アナルコ・サンディカリズムに対して、主流派のマルクス主義の方針が勝利し、直接行動ではなく議会進出による条件改善に重きが置かれる。また、エンゲルスが第二インターナショナルの名誉会長に選ばれた[391]。
エンゲルスの最期
[編集]
1894年11月28日、フリードリヒ・エンゲルスは74回目の誕生日を迎えた。しかし、エンゲルスは74歳にしても「老人」ではなかった。鋭気に満ち、ステーキを食べワインを飲んで活発に活動する、失意も衰えも知らない「若き革命家」のままであった。12月17日、ラウラ・ラファルグに宛てた手紙でこう述べた。
「僕はヨーロッパの五大国と多くの小国ならびにアメリカ合衆国の運動を追ってゆかねばなりません。この目的のために、僕は日刊紙を、ドイツ語のものを三つ、英語のものを二つ、イタリア語のものを一つ、それに1月1日からはウィーンの日刊紙、合計七紙をとっています。週刊紙では、ドイツからは二つ、オーストリアからは七つ、フランスから一つ、アメリカから三つ、イタリア語のもの二つ、それにポーランド語、ブルガリア語、スペイン語、チェコ語のものをそれぞれ一つずつとっており、このうち三つは、僕がまだその国語を習得しつつあるものです。それにくわえて、ありとあらゆる種類の人たちの来訪とたえず増えてゆく文通者の群れ―これがインタナショナル当時よりも多いのです!。もし僕が僕自身を40歳のF.E(フリードリヒ・エンゲルス)と34歳のF.Eとに分けることができたら、……すぐにでもオーライでしょうに。」
エンゲルスは冗談をいつものように語った。しかし、エンゲルスは現状に満足せず、「すくなくともモールの政治生活の主要な諸章。つまり、1842-1852年とインタナショナルを書きたい。後者は最も重要で急を要する。まず、それをやるつもりだ」と語り、マルクス伝とインターナショナルの歴史を著述することに意欲を見せた。
エンゲルスは人生を楽しみながらも死や老衰に悲観しなかった。エンゲルスは体力と知力に自信を持ち続け、エンゲルス家に同居しながら介助者となっていたルイーゼ・カウツキー・フライベルガーが健康状態を心配して過保護に扱うことに苛立ちながら、友人のパウル・シュトゥンプに宛ててこう語った。エンゲルスは、「なんとかして新しい世紀をのぞいてみたいと強く望んでいる。だがそうなると、1901年1月1日ごろには私もまったく役立たずになっており、そのときにはおさらばできる」と述べたように、後々の歴史の展開を見ていきたいと願っていた。しかし、この望みは果たされることはなかった。1895年の春エンゲルスを病が襲った。以後、最晩年のエンゲルスは、減退する視力、そして困難な病と闘った。「ほとんど仕事ができなくさせる、多くの苦痛と習慣的不眠を伴う不快な頸部リンパ腺腫瘍」の正体は喉頭癌であった。
6月前半、エンゲルスは海風で苦痛を癒したいと考えて、ドーバー海峡に面した保養地イーストボーンに赴いた。海辺の保養地での療養生活にエンゲルスは喜んだが、癌の進行から苦痛は日々増して激痛となっていった。しかし、エンゲルスは、病床にあってもユーモアを絶やさず、明晰な頭脳を保ち続けた。
エンゲルスは、1895年の闘病生活中で実に75通の手紙を書き、政治事件の分析を行い、友人や戦友たちの個人的相談にも乗り、党の革命戦略を練り、助言を与えていった。さらに、残りの力を振り絞って、死後の遺産分割に関する取り決めを定めていった。エンゲルスは相続人をマルクスの娘ラウラとエレノア、故人となった長女ジェニーの子供たち、そして、家政婦のヘレーネ・デムートを遺産相続人に指名した。また、家財の一部をルイーゼ・カウツキーに贈与するとともに、メアリーとリディアの姪パンプス(メアリー・エリン・ロッシャー)に対しても遺産金を提供した。さらに、エンゲルスは莫大な遺産の一部1000ポンドをドイツ社会民主党の選挙資金のために提供することを定めた。エンゲルスはベーベルに「諸君が遺産を受け取ったら、それをプロイセン人につかみとられないように、とくに気をつけたまえ。そして、諸君がこの問題について決議したら、上等のワイン一瓶でもそのために飲んで、こうして私を思い出してくれたまえ」と語った。エンゲルスは、マルクスの通信文と書簡のすべての所有権をエレノア・マルクス・エイヴリングに委ねた。自分の文献と命令書の遺言執行人をアウグスト・ベーベル、エドュアルト・ベルンシュタインを指名、エンゲルスが所有していた膨大な蔵書や文献をドイツ社会民主党に寄贈すると表明した。
7月23日、エンゲルスは自身の最期を悟ったのか、手術による回復を確信したのか、ラウラ・ラファルグに宛てた最後の手紙でこう語った。
「とうとう私の首のジャガイモ畑に峠がきつつあるらしいので、腫瘍を切開して楽になれるだろう。とうとう!こうしてこの長い小道の曲がり角にでる望みができている。それに食欲がないなどのために私はかなり衰弱しているので、もうそうすべき時でもある。……。長い手紙を書く気力がない。では、さようなら。」
ちょうどこの手紙を書いていた時、オーストリアの社会主義者ヴィクトル・アドラーがエンゲルスを訪ねていた。8月を過ぎるころには、声を出しての会話が困難になり、石板を使って対話をせざるを得なくなった最中にも、エンゲルスはなお、ユーモアと労働者階級に対する楽観的な展望を石板上に言葉として書き記すことによって、むしろ来客を勇気づけた。エンゲルスは病床にあったが、まだ面会する体力を保っており、アドラーに伴われてロンドンの自宅に戻っている。アドラーはエンゲルスの病状をドイツのベーベルに報告した。1895年8月5日、ベーベルはヴィルヘルム・リープクネヒトにこう伝えている。
「アドラーがそこへ[ロンドンへ]行った時、エンゲルスはまだ話せたし、半時間話したが、それができなくなった。彼は、石盤で気持ちを分からせるだけだが、それでも上機嫌で、希望をもち、彼の歳の人には、癌など思いもよらぬことなので、どこが悪いのか気づいていないとのことだ。また、彼は石盤に駄じゃれを書いた。こんな具合なのは本当に幸運だ。彼は食餌は、流動食しかとれないし、肉体的には甚だ衰えている。アドラーが立ち去る直前までは、彼はまだ自分自身のことはなんでもしたが、それもやはりできなくなった。彼は脱衣と着衣に人の手を借りなければならない。だから、彼の状態にはまだ一週間は続きうるが、毎日、同じように破局がやってきうるというような事態にある。われわれは、その覚悟をしなければならない。」
しかし、まさにこの1895年8月5日にはエンゲルスは意識不明の危篤状態となっていた。22時30分ごろ、エンゲルスの脈は途切れてロンドンで死去。国際労働運動はその偉大な理論家であり闘士を失った。『資本論』第3巻をようやく仕上げて約1年後のことであった。
エンゲルスの葬儀は、1895年8月10日、ウォータールーにあったロンドン・ネクロポリス鉄道駅内の合室で、ごく近い者でのみ執り行われた。エリノア・マルクス、エドワード・エイヴリング、ヴィルヘルム・リープクネヒト、アウグスト・ベーベル、エドゥアルト・ベルンシュタイン、カール・カウツキー、ポール・ラファルグ、フリードリヒ・レスナー、サミュエル・ムーアといった各国の社会主義指導者たちと近親者、およそ20名程度で営まれた。花輪と生花に飾り付けられた特別列車が、エンゲルスの棺を乗せてウェストミンスター駅を発車。棺をワーキングの火葬場へと運び、火葬に付された。その遺灰は、エンゲルスの遺言により、イギリス南部のドーバー海峡に面する風光明媚な彼のお気に入りの地イーストボーンの沖合いに散骨された。8月27日、荒天のドーバーであった。
主な著作
[編集]生前刊の著書
[編集]- 『ヴッパータールだより』(ドイツ語: Briefe aus dem Wuppertal,1839)
- 「シェリングと啓示」(ドイツ語: Schelling und die Offenbarung- Kritik des neuesten Reaktionsversuchs gegen die freie Philosophie,1842)
- 「キリストの内なる哲学者シェリング」(ドイツ語: Schelling der Philosoph in Christo, oder die Verklärung der Weltweisheit zur Gottesweisheit,1842)
- 「国民経済学批判大綱」『独仏年誌』(ドイツ語: ''Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie,1844)
- 『イングランドにおける労働者階級の状態』(ドイツ語: Die Lage der arbeitenden Klasse in England,1845)
- 『聖家族 批判的批判の批判―ブルーノ・バウアーとその伴侶を駁す』(マルクスとの共著)(ドイツ語: Die heilige Familie, oder Kritik der Kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer & Consorten, (mit Marx) 1845)
- 『ドイツ・イデオロギー』(マルクスとの共著)(ドイツ語: Die deutsche Ideologie, (mit Marx) 1845)
- 『共産主義の原理』(ドイツ語: Grundsätze des Kommunismus,1847)
- 『共産党宣言』(マルクスとの共著)(ドイツ語: Manifest der Kommunistischen Partei, 1848)
- 『ドイツ農民戦争』(ドイツ語: Der deutsche Bauernkrieg, 1850)
- 『ドイツにおける革命と反革命』(ドイツ語: Revolution und Konterrevolution in Deutschland, 1851-1852)
- 『自然の弁証法』(ドイツ語: Dialektik der Natur,1873-1886)
- 『反デューリング論(オイゲン・デューリング氏の科学の変革)』(ドイツ語: Anti-Dühring, Herrn Eugen Dühringś Umwälzung der Wissenschaft. Philosophie, politische Oekonomie, Sozialismus, 1878)
- 『空想より科学へ』(ドイツ語: Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, 1880)
- 『家族・私有財産・国家の起源』(ドイツ語: Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats, 1884)
- 『資本論第二巻』(エンゲルス編集)(ドイツ語: Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie, Band 2, 1885)
- 『フォイエルバッハ論(ルートヴィッヒ・フォイエルバッハとドイツ古典哲学の終結)』(ドイツ語: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, 1886)
- 『資本論第三巻』(エンゲルス編集)(ドイツ語: Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie Band 3, 1894)
日本語訳
[編集]脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ このスケッチに描かれているのは青年ヘーゲル派フライエンの代表人物である。左からアーノルド・ルーゲと彼に拳を挙げて向かうブルーノ・バウアー、机を叩くエトガー・バウアー、煙草を吹かすマックス・シュティルナーと席について様子を眺めるカール・ケッペンがいる。そして争う人々の上にはプロイセンの文部大臣アイヒホルンをもじったリス(独語でアイヒヒョーヒェン)とギロチンが描かれている。
- ^ ブリテンでは19世紀に入り産業革命の本格的進展によって各地の産業構造に変化が生じ、南部の農村地帯から北部の工業地帯へと人口移動がおこっていた。その結果、北部の工業都市に移住した多数の労働者が政治的権利のない二級市民の立場に置かれていた。それまで合理性があった旧来の選挙制度は急速に時代にそぐわないものとなっていた。イギリスでは議会制度の腐敗が進み、改革は避けがたいものとなっていたこうして大規模な社会変動、政治変動が始まる。1832年、第一次選挙法改正が実現した。このときの改革では、都市選挙区に居住する10ポンド以上の家屋・店舗を占有する戸主、州選挙区に居住する10ポンド以上の長期(60年)自由土地保有者、50ポンド以上の短期(20年)自由土地保有者に選挙権が与えられ、議席再配分によって腐敗選挙区の廃止と工業都市への選挙区の割り振りが実施された。だが、労働者には選挙権は与えられず、改革は未解決のままに残され、議会改革問題はチャーティスト運動へと引き継がれる[67]。南部のロンドンからエンゲルスがいたイングランド北部マンチャスターに連なる工業都市がチャーティスト運動の一大拠点となっていた[68]。
- ^ 「黒・赤・金」三色旗は現在、ドイツ国旗に採用されている。その起源は古く、1832年のハンバッハ祭が例に挙げられる。ハンバッハ祭は、重税や政治的抑圧に対する社会不安の高まりを反映して挙行された祭典だが、共和主義者がドイツ統一運動とドイツ人の連帯の象徴として黒・赤・金(ドイツ語版)の三色を採用したことが注目に値する。「黒・赤・金」三色旗は民主的、共和主義的、国民主義的なドイツ共和国の表象となっていった。
- ^ 当時の価格で総額およそ2000~3000ポンド、現在の換算でも大金である。
出典
[編集]- ^ 水村光男編 『世界史のための人名辞典』 山川出版社 1991年。 p.43
- ^ 大内 (1964) p.103
- ^ a b 土屋保男 (1995) p.8
- ^ ハント (2016) pp.19-20
- ^ 土屋保男 (1995) pp.8-9
- ^ ハント (2016) pp.29-31
- ^ ハント (2016) pp.22-23
- ^ ハント (2016) p.21
- ^ ハント (2016) pp.20-21
- ^ a b ハント (2016) p.22
- ^ 土屋保男 (1995) p.9
- ^ ハント (2016) p.31
- ^ a b c 大内 (1964) p.104
- ^ a b c d e 土屋保男 (1995) p.10
- ^ ハント (2016) pp.31-38
- ^ ハント (2016) pp.23-28
- ^ 大内 (1964) p.105
- ^ a b ハント (2016) p.38
- ^ ハント (2016) pp.39-40
- ^ ハント (2016) p.39
- ^ ハント (2016) pp.39-41
- ^ ハント (2016) p.41
- ^ a b ハント (2016) p.42
- ^ a b c d ハント (2016) p.45
- ^ ハント (2016) p.48
- ^ ハント (2016) pp.44-45
- ^ ハント (2016) p.44
- ^ ハント (2016) pp.46-47
- ^ ハント (2016) pp.50-51
- ^ ハント (2016) p.50
- ^ ハント (2016) p.51
- ^ ハント (2016) p.45,48
- ^ a b ハント (2016) p.52
- ^ a b ハント (2016) p.53
- ^ ハント (2016) pp.53-55
- ^ a b c d 土屋保男 (1995) p.11
- ^ ハント (2016) pp.58-59
- ^ ハント (2016) pp.59-60
- ^ ハント (2016) p.61
- ^ ハント (2016) p.43
- ^ a b ハント (2016) pp.62-63
- ^ ハント (2016) p.65
- ^ ハント (2016) p.78
- ^ ハント (2016) p.67,69
- ^ a b ハント (2016) p.79
- ^ a b ハント (2016) pp.71-72
- ^ ハント (2016) pp.72-73, pp.68-69
- ^ a b ハント (2016) pp.72-73
- ^ ハント (2016) p.66
- ^ ハント (2016) p.67
- ^ 土屋保男 (1995) pp.11-12
- ^ a b ハント (2016) p.75
- ^ a b 土屋保男 (1995) p.12
- ^ ハント (2016) p.76
- ^ ハント (2016) pp.76-78
- ^ a b ハント (2016) p.80
- ^ 土屋保男 (1995) p.13
- ^ ハント (2016) p.90-91
- ^ ハント (2016) p.90
- ^ ハント (2016) p.91
- ^ 土屋保男 (1995) p.84
- ^ ハント (2016) pp.109-110
- ^ ハント (2016) p.117
- ^ 全集 2巻(1960) p.225
- ^ ハント (2016) p.128
- ^ ハント (2016) p.129
- ^ 古賀秀男 (1980) pp.3-4,54-55
- ^ 古賀秀男 (1980) pp.87-89
- ^ 古賀秀男 (1980) pp.51-53
- ^ ハント (2016) p.123
- ^ ハント (2016) pp.118-123
- ^ ハント (2016) pp.105-107
- ^ ハント (2016) pp.124-126
- ^ ハント (2016) pp.126-128
- ^ 大内 (1964) p.108
- ^ a b ハント (2016) pp.134-135
- ^ 大内 (1964) pp.108-109
- ^ a b ハント (2016) p.155
- ^ 小牧(1966) p.113
- ^ 小牧(1966) p.115
- ^ 小牧(1966) p.116-117
- ^ a b ハント (2016) p.156
- ^ 城塚(1970) p.128
- ^ 大内 (1964) p.114
- ^ ハント (2016) pp.148-152
- ^ 土屋保男 (1995) p.89
- ^ 土屋保男 (1995) p.90
- ^ ハント (2016) pp.155-156
- ^ 小牧(1966) p.122
- ^ 小牧(1966) pp.123-125
- ^ a b 大内 (1964) p.115
- ^ ハント (2016) pp.156-157
- ^ 大内 (1964) pp.111-112,115
- ^ a b 土屋保男 (1995) p.95
- ^ ハント (2016) p.159
- ^ ハント (2016) p.160
- ^ ハント (2016) p.161
- ^ ハント (2016) pp.162-163
- ^ ハント (2016) p.163
- ^ 土屋保男 (1995) pp.96-97
- ^ ハント (2016) p.165
- ^ ハント (2016) p.166
- ^ 土屋保男 (1995) p.98
- ^ ハント (2016) pp.166-167
- ^ 土屋保男 (1995) p.102
- ^ ハント (2016) p.167
- ^ 大内 (1964) p.117
- ^ 大内 (1964) p.116
- ^ 土屋保男 (1995) p.99
- ^ ハント (2016) pp.167-168
- ^ ハント (2016) p.168
- ^ a b ハント (2016) p.171
- ^ a b 全集 3巻(1963) p.22
- ^ 全集 3巻(1963) p.15
- ^ ハント (2016) pp.172-173
- ^ a b 全集 3巻(1963) pp.15-16
- ^ 全集 3巻(1963) pp.21-22
- ^ 全集 3巻(1963) pp.18-21
- ^ 全集 3巻(1963) p.25
- ^ 全集 3巻(1963) p.65, pp.69-70
- ^ 全集 4巻(1960) p.480
- ^ |経済学批判(1956) pp.13-14
- ^ a b ハント (2016) p.175
- ^ 大内 (1964) pp.124-125
- ^ a b ハント (2016) p.176
- ^ ハント (2016) pp.177-182
- ^ ハント (2016) pp.188-190
- ^ ハント (2016) p.180
- ^ ハント (2016) p.193
- ^ ハント (2016) pp.180-181
- ^ ハント (2016) pp.190-191
- ^ ハント (2016) pp.194-195
- ^ ハント (2016) p.199
- ^ |全集 3巻(1960) pp.475-487
- ^ 大内 (1964) p.126
- ^ 河野健二 (1982) pp.16-17
- ^ ハント (2016) p.200
- ^ 河野健二 (1982) p.35
- ^ ハント (2016) p.201
- ^ 河野健二 (1982) pp.52-58
- ^ a b 河野健二 (1982) pp.59-60
- ^ 河野健二 (1982) pp.64-65
- ^ 河野健二 (1982) p.66
- ^ 河野健二 (1982) p.68
- ^ 河野健二 (1982) p.91
- ^ 河野健二 (1982) p.94
- ^ 河野健二 (1982) pp.100-103
- ^ 河野健二 (1982) pp.102-112
- ^ 望月(1998) p.29
- ^ 望月(1998) pp.29-31
- ^ a b c ハント (2016) p.202
- ^ a b c 望月(1998) p.31
- ^ ハント (2016) p.205
- ^ ハント (2016) p.206
- ^ a b 望月(1998) p.32
- ^ 望月(1998) pp.32-33
- ^ 望月(1998) pp.33-34
- ^ a b 望月(1998) p.35
- ^ 望月(1998) pp.36-39
- ^ ハント (2016) p.198
- ^ ハント (2016) p.203
- ^ ウィーン(2002) p.157
- ^ ハント (2016) pp.203-204
- ^ 石浜(1931) p.171
- ^ a b ハント (2016) p.204
- ^ a b ウィーン(2002) p.158
- ^ a b c 石浜(1931) p.173
- ^ メーリング(1974) 1巻 p.268
- ^ a b カー(1956) p.86
- ^ a b ウィーン(2002) p.159
- ^ ハント (2016) p.208
- ^ ハント (2016) p.207
- ^ ハント (2016) p.209
- ^ ハント (2016) p.210
- ^ ウィーン(2002) p.164
- ^ ハント (2016) p.213
- ^ ハント (2016) p.214
- ^ ハント (2016) pp.214-215
- ^ ハント (2016) p.215
- ^ ハント (2016) pp.216-217
- ^ ハント (2016) p.218
- ^ a b c d ハント (2016) p.222
- ^ ハント (2016) pp.218-219
- ^ ハント (2016) pp.219-220
- ^ ハント (2016) pp.221-222
- ^ ハント (2016) p.223
- ^ ハント (2016) p.224
- ^ ハント (2016) pp.223-224
- ^ ハント (2016) p.224-226
- ^ a b ハント (2016) p.227
- ^ ハント (2016) pp.227-228
- ^ a b ハント (2016) p.228
- ^ a b ハント (2016) p.229
- ^ ウィーン(2002) p.164-166
- ^ ハント (2016) pp.230-231
- ^ ハント (2016) p.231
- ^ a b ハント (2016) p.232
- ^ ハント (2016) p.212
- ^ ハント (2016) p.233
- ^ カー(1956) p.123
- ^ 石浜(1931) p.206
- ^ ウィーン(2002) p.199
- ^ ハント (2016) p.240-241
- ^ ハント (2016) pp.281-282
- ^ ハント (2016) pp.238-239
- ^ ハント (2016) p.241
- ^ ハント (2016) pp.242-245
- ^ a b ハント (2016) p.249
- ^ ハント (2016) p.249,p.251
- ^ ハント (2016) pp.268-272
- ^ ハント (2016) p.259,p.283
- ^ ハント (2016) pp.272-275
- ^ ハント (2016) p.259
- ^ ハント (2016) pp.252-253
- ^ ハント (2016) p.264
- ^ ハント (2016) pp.262-264
- ^ ハント (2016) p.263
- ^ 岩波文庫版(1954) p.7
- ^ 平凡社版(2008) p.247
- ^ 岩波文庫版(1954) p.229
- ^ 岩波文庫版(1954) pp.229-230
- ^ ハント (2016) p.283
- ^ ハント (2016) p.285
- ^ カー(1956) p.207
- ^ メーリング(1974)2巻 p.126
- ^ 石浜(1931) p.224-225
- ^ メーリング(1974)2巻 p.126-128
- ^ ハント (2016) pp.285-286
- ^ a b c ハント (2016) p.288
- ^ 石浜(1931) p.241-242
- ^ Burgess, K. The Origins of British Industrial Relations: The Nineteenth Century Experience. (London, 1975) pp.109-113
- ^ 飯田鼎(1996) p.58
- ^ 鹿島(2004) p.178
- ^ 鹿島(2004) p.369-370
- ^ 石浜(1931) p.243
- ^ 江上(1972) p.210
- ^ 『書簡集(上)』(2012) p.196
- ^ 『書簡集(上)』(2012) pp.198-199
- ^ 『書簡集(上)』(2012) pp.200-201
- ^ ハント (2016) p.292
- ^ a b c ハント (2016) p.293
- ^ ハント (2016) p.301
- ^ a b c ハント (2016) p.302
- ^ ハント (2016) p.303
- ^ ハント (2016) pp.303-304
- ^ a b ハント (2016) p.305
- ^ フォスター(1956) p.53
- ^ フォスター(1956) p.54
- ^ グムコー (1972) p.6
- ^ 江上(1972) p.261
- ^ 『書簡集(上)』(2012) pp.228-229
- ^ a b フォスター(1956) p.55
- ^ グムコー (1972) p.7
- ^ グムコー (1972) p.8
- ^ フォスター(1956) pp.41-42
- ^ グムコー (1972) pp.10-11
- ^ フォスター(1956) p.47
- ^ ハント (2016) p.273
- ^ ハント (2016) p.274
- ^ ハント (2016) p.275
- ^ ハント (2016) pp.275-276
- ^ グムコー (1972) p.44
- ^ a b c ハント (2016) p.295
- ^ a b c ハント (2016) p.296
- ^ ハント (2016) pp.296-297
- ^ ハント (2016) p.299
- ^ a b ハント (2016) p.312
- ^ グムコー (1972) pp.46-47
- ^ ハント (2016) p.318
- ^ ハント (2016) pp.316-317
- ^ ハント (2016) p.319
- ^ a b ハント (2016) pp.319-320
- ^ ハント (2016) pp.344-345
- ^ ハント (2016) p.345
- ^ フォスター(1956) pp.56-59
- ^ フォスター(1956) p.82
- ^ フォスター(1956) p.83
- ^ フォスター(1956) p.84
- ^ フォスター(1956) pp.58-59
- ^ グムコー (1972) p.57
- ^ 『書簡集(中)』(2012) pp.77-78
- ^ カー(1956) p.296-297
- ^ グムコー (1972) p.58
- ^ グムコー (1972) p.60
- ^ ハント (2016) pp.289-290
- ^ 桂圭男 (1971) p.47
- ^ 桂圭男 (1981) p.67
- ^ 桂圭男 (1971) p.51
- ^ 柴田三千雄 (1973) p.55
- ^ 桂圭男 (1981) p.68
- ^ ハント (2016) pp.323-324
- ^ グムコー (1972) p.61
- ^ フォスター(1956) p.90
- ^ ハント (2016) p.323
- ^ 桂圭男 (1971) p.102
- ^ 柴田三千雄 (1973) p.90
- ^ 桂圭男 (1971) pp.112-117
- ^ 柴田三千雄 (1973) pp.97-98
- ^ 桂圭男 (1981) pp.138-140
- ^ 桂圭男 (1971) p.115
- ^ 柴田三千雄 (1973) p.99
- ^ カー(1956) p.302-303
- ^ a b c ウィーン(2002) p.391
- ^ メーリング(1974)3巻 p.97
- ^ 桂圭男 (1971) p.141
- ^ 桂圭男 (1981) p.173
- ^ マルクス(1952) p.95
- ^ カー(1956) p.303
- ^ 小牧(1966) p.214
- ^ 石浜(1931) p.269
- ^ メーリング(1974)3巻 p.103
- ^ カー(1956) p.307
- ^ フォスター(1956) p.104
- ^ [[#CITEREFマルクス,不破哲三2010|マルクス,不破哲三 (2010)]] pp.202-205
- ^ [[#CITEREFマルクス,不破哲三2010|マルクス,不破哲三 (2010)]] pp.207-210
- ^ カー(1956) p.310
- ^ カー(1956) p.309
- ^ カー(1956) p.333
- ^ フォスター(1956) pp.102-103
- ^ フォスター(1956) p.103
- ^ フォスター(1956) pp.104-105
- ^ フォスター(1956) p.105
- ^ フォスター(1956) p.107
- ^ 「ハーグ大会についての演説」1872年9月 マルクス・エンゲルス全集(18) 158ページ、不破哲三『科学的社会主義における民主主義の探求』40ページ
- ^ フォスター(1956) p.109
- ^ フォスター(1956) pp.107-108
- ^ a b フォスター(1956) p.110
- ^ フォスター(1956) pp.112-113
- ^ フォスター(1956) pp.117-118
- ^ フォスター(1956) pp.114-115
- ^ フォスター(1956) pp.119-120
- ^ フォスター(1956) p.122
- ^ フォスター(1956) pp.128-129
- ^ フォスター(1956) p.130-131
- ^ フォスター(1956) pp.80-81
- ^ ハント (2016) p.339
- ^ ハント (2016) p.336
- ^ ハント (2016) p.340
- ^ ハント (2016) pp.340-341
- ^ a b 土屋保男 (1995) p.148
- ^ 土屋保男 (1995) p.149
- ^ a b ハント (2016) p.341
- ^ ハント (2016) pp.380-381
- ^ 『反デューリング論〈上〉』(1980) pp.314-316
- ^ 『反デューリング論〈上〉』(1980) p.323
- ^ a b ハント (2016) p.382
- ^ 『反デューリング論〈上〉』(1980) p.323-324
- ^ ハント (2016) p.383
- ^ 『反デューリング論〈上〉』(1980) p.324
- ^ 『反デューリング論〈上〉』(1980) p.19
- ^ ハント (2016) pp.348-349
- ^ ハント (2016) p.349
- ^ ハント (2016) p.356
- ^ a b c ハント (2016) p.357
- ^ グムコー (1972) p.128
- ^ 佐藤(1984) p.27
- ^ 佐藤(1984) p.28
- ^ ハント (2016) p.358
- ^ グムコー (1972) p.129
- ^ グムコー (1972) p.130
- ^ グムコー (1972) pp.130-131
- ^ ハント (2016) p.362
- ^ 佐藤(1984) pp.29-30
- ^ グムコー (1972) p.131
- ^ 大内 (1964) pp.113-114
- ^ グムコー (1972) p.132
- ^ グムコー (1972) p.133
- ^ 佐藤(1984) pp.34-36
- ^ 佐藤(1984) p.33
- ^ 佐藤(1984) pp.37-42
- ^ 佐藤(1984) pp.53-54
- ^ 佐藤(1984) p.54
- ^ 『起源』(1965) p.273
- ^ a b 『起源』(1965) pp.274-275
- ^ 『起源』(1965) p.274
- ^ ハント (2016) p.398, p.401
- ^ 『起源』(1965) pp.275-276
- ^ 佐藤(1984) p.57
- ^ 『起源』(1965) pp.32-33
- ^ 『起源』(1965) pp.37-38
- ^ 『起源』(1965) p.31
- ^ 『起源』(1965) pp.74-76
- ^ 『起源』(1965) pp.88-89
- ^ 『起源』(1965) pp.226-227
- ^ 『起源』(1965) p.230
- ^ 『起源』(1965) p.225
- ^ 佐藤(1984) pp.58-59
- ^ 佐藤(1984) p.61
- ^ レーニン「フリードリヒ・エンゲルス」、『レーニン全集』第2巻上11-12頁。
- ^ レーニン「フリードリヒ・エンゲルス」、『レーニン全集』第2巻上4頁。
- ^ History of the Second International - Marxists Internet Archive
参考文献
[編集]- 飯田鼎『マルクス主義における革命と改良―第一インターナショナルにおける階級,体制および民族の問題』御茶の水書房、1966年。
- 石浜知行『マルクス伝』改造社〈偉人傳全集第6巻〉、1931年(昭和6年)。
- 江上照彦『ある革命家の華麗な生涯 フェルディナント・ラッサール』社会思想社、1972年(昭和47年)。ASIN B000J9G1V4。
- カール・マルクス、フリードリヒ・エンゲルス、マルクス=レーニン主義研究所 著、大内兵衛,細川嘉六 訳『マルクス・エンゲルス全集』大月書店、1959年。
- カール・マルクス 著、不破哲三 編『インタナショナル (科学的社会主義の古典選書)』新日本出版社、2010年。
- カール・マルクス、フリードリヒ・エンゲルス 著、不破哲三 編『マルクス、エンゲルス書簡選集(上)、(中) (科学的社会主義の古典選書)』新日本出版社、2012年。
- カール・マルクス 著、不破哲三 編『インタナショナル (科学的社会主義の古典選書)』新日本出版社、2010年。
- 鹿島茂『怪帝ナポレオンIII世 第二帝政全史』講談社、2004年(平成16年)。ISBN 978-4062125901。
- ジョナサン・スパーバー 著、小原淳 訳『マルクス(上)(下):ある十九世紀人の生涯』白水社、2015年。
- ハリンリヒ・グムコー,マルクス=レーニン主義研究所 著、土屋保男,松本洋子 訳『フリードリヒ・エンゲルス 一伝記(上)、(下)』大月書店、1972年。
- ドイツ社会主義統一党中央委員会付属マルクス=レーニン主義研究所 著、栗原佑 訳『モールと将軍』大月書店、1976年。
- 大内兵衛『マルクス・エンゲルス小伝』岩波書店、1964年。
- トリストラム・ハント 著、東郷えりか 訳『エンゲルス: マルクスに将軍と呼ばれた男』筑摩書房、2016年。
- テレル・カーヴァー 著、内田弘, 杉原四郎 訳『エンゲルス』雄松堂出版、1989年。
- 土屋保男『フリードリヒ・エンゲルス―若き日の思想と行動』新日本出版社、1995年。
- 良知力『マルクスと批判者群像』平凡社、2009年。
- 佐藤金三郎『マルクス遺稿物語』岩波書店、1989年。
- 大井正『マルクスとヘーゲル学派』福村出版、1981年。
- 河野健二『現代史の幕あけ―ヨーロッパ1848年』岩波書店、1982年。
- 望田幸男『ドイツ統一戦争―ビスマルクとモルトケ』教育社、1992年。
- 柴田三千雄『パリ・コミューン』中央公論社、1973年。
- 桂圭男『パリ・コミューン』岩波書店、1971年。
- 桂圭男『パリ・コミューン―パリが燃えた70日』教育社、1981年。
- ロイ・ウィトフィールド 著、坂脇昭吉, 岡田光正 訳『マンチェスター時代のエンゲルス―その知られざる生活と友人たち』ミネルヴァ書房、2003年。
- フランシス・ウィーン 著、田口俊樹 訳『カール・マルクスの生涯』朝日新聞社、2002年(平成14年)。ISBN 978-4022577740。
- 小牧治『マルクス』清水書院〈人と思想20〉、1966年(昭和41年)。ISBN 978-4389410209。
- ジャック・アタリ 著、的場昭弘 訳『世界精神マルクス』藤原書店、2014年。
- E・H・カー 著、石上良平 訳『カール・マルクス その生涯と思想の形成』未来社、1956年(昭和31年)。
- 喜安朗『夢と反乱のフォブール―1848年パリの民衆運動』山川出版社、1994年。
- 古賀秀男『チャーティスト運動―大衆運動の先駆』教育社、1980年。
- ジョージ=リューデ 著、古賀秀男 訳『歴史における群衆―英仏民衆運動史1730-1848』法律文化社、1982年。
- フランツ・メーリング 著、栗原佑 訳『マルクス伝1』大月書店〈国民文庫440a〉、1974年(昭和49年)。ASIN B000J9D4WI。
- フランツ・メーリング 著、栗原佑 訳『マルクス伝2』大月書店〈国民文庫440b〉、1974年(昭和49年)。ASIN B000J9D4W8。
- フランツ・メーリング 著、栗原佑 訳『マルクス伝3』大月書店〈国民文庫440c〉、1974年(昭和49年)。ASIN B000J9D4VY。
- 『エンゲルス伝』(労働大学)
- ウラジーミル・イリイチ・レーニン「フリードリヒ・エンゲルス」、マルクス=エンゲルス=レーニン研究所編、マルクス=レーニン主義研究所訳『レーニン全集』第2巻上、大月書店、1954年。原論文は1895年執筆、論集『ラポートニク』第1~2号に掲載。
関連項目
[編集]- マルクス主義関係の記事一覧
- フリードリヒ・エンゲルス衛兵連隊 - ドイツ民主共和国(東ドイツ)の儀仗兵部隊。
- 『マルクス・エンゲルス』(2017年の映画。若年期のマルクスとエンゲルスを描いた映画)
外部リンク
[編集]- エンゲルス フリードリッヒ:作家別作品リスト - 青空文庫
- フリードリヒ・エンゲルスの作品 (インターフェイスは英語)- プロジェクト・グーテンベルク
- Friedrich Engelsに関連する著作物 - インターネットアーカイブ
- フリードリヒ・エンゲルスの著作およびフリードリヒ・エンゲルスを主題とする文献 - ドイツ国立図書館の蔵書目録(ドイツ語)より。
- フリードリヒ・エンゲルス「カール・マルクス葬送の辞」(1883年3月17日) - ARCHIVE
- フリードリヒ・エンゲルス - ドイツデジタル図書館
- フリードリヒ・エンゲルスの著作 - Zeno.org
- フリードリヒ・エンゲルスの著作 - LibriVox(パブリックドメインオーディオブック)

- フリードリヒ・エンゲルスの著作 - Marx Engels Archive


