「アーサー・バルフォア」の版間の差分
Omaemona1982 (会話 | 投稿記録) 編集の要約なし |
|||
| (3人の利用者による、間の8版が非表示) | |||
| 5行目: | 5行目: | ||
|画像サイズ = 200px |
|画像サイズ = 200px |
||
|画像説明 = {{仮リンク|ジョージ・グランサム・ベイン|en|George Grantham Bain}}撮影の肖像 |
|画像説明 = {{仮リンク|ジョージ・グランサム・ベイン|en|George Grantham Bain}}撮影の肖像 |
||
|国略称 ={{GBR}} |
|||
|生年月日 = [[1848年]][[7月25日]] |
|生年月日 = [[1848年]][[7月25日]] |
||
|出生地 = {{ |
|出生地 = {{仮リンク|ホィッティンガム|en|Whittingehame}} |
||
|没年月日 = |
|没年月日 = {{死亡年月日と没年齢|1848|7|25|1930|3|19}} |
||
|死没地 = {{ |
|死没地 = {{仮リンク|ウォーキング (イングランド)|en|Woking|label=ウォーキング}} |
||
|出身校 = [[ケンブリッジ大学]][[トリニティ・カレッジ (ケンブリッジ大学)|トリニティ・カレッジ]] |
|出身校 = [[ケンブリッジ大学]][[トリニティ・カレッジ (ケンブリッジ大学)|トリニティ・カレッジ]] |
||
|所属政党 = [[保守党 (イギリス)|保守党]] |
|所属政党 = [[保守党 (イギリス)|保守党]] |
||
|称号・勲章 = [[ガーター勲章]]勲 |
|称号・勲章 = バルフォア伯爵<br/>トラップレイン子爵<br/>[[ガーター勲章]]勲章士(KG)<br />[[メリット勲章]]勲章士(OM)<br />[[枢密院 (イギリス)|枢密顧問官]](PC)<br />[[州副知事]](DL) |
||
|親族(政治家) = [[ジェイムズ・ガスコイン=セシル (第2代ソールズベリー侯爵)|第2代ソールズベリー侯爵]] (祖父)<br />[[ロバート・ガスコイン=セシル (第3代ソールズベリー侯爵)|第3代ソールズベリー侯爵]] (叔父)<br /> |
|親族(政治家) = [[ジェイムズ・ガスコイン=セシル (第2代ソールズベリー侯爵)|第2代ソールズベリー侯爵]] (祖父)<br />[[ロバート・ガスコイン=セシル (第3代ソールズベリー侯爵)|第3代ソールズベリー侯爵]] (叔父)<br />{{仮リンク|ジェラルド・バルフォア (第2代バルフォア伯爵)|label=第2代バルフォア伯爵|en|Gerald Balfour, 2nd Earl of Balfour}}(弟)<br />[[ジェイムズ・ガスコイン=セシル (第4代ソールズベリー侯爵)|第4代ソールズベリー侯爵]] (従弟)<br />[[ロバート・セシル (初代セシル・オブ・チェルウッド子爵)|初代チェルウッドのセシル子爵]] (従弟) |
||
|サイン = Arthur Balfour Signature.svg |
|サイン = Arthur Balfour Signature.svg |
||
|国旗 = UK |
|||
|職名 = [[第一大蔵卿]]兼[[庶民院院内総務]] |
|||
|職名 = [[イギリスの首相|首相]] |
|||
|内閣 = [[第3次ソールズベリー内閣]]<br />[[バルフォア内閣]] |
|||
|就任日 = [[ |
|就任日 = [[1902年]][[7月12日]] |
||
|退任日 = [[1905年]][[12月4日]] |
|退任日 = [[1905年]][[12月4日]]<ref name="秦(2001)511">[[#秦(2001)|秦(2001)]] p.511</ref> |
||
|元首職 = 国王 |
|元首職 = [[イギリスの君主|国王]] |
||
|元首 = |
|元首 = [[エドワード7世 (イギリス王)|エドワード7世]] |
||
|国旗2 = UK |
|||
|職名2 = [[イギリスの首相]] |
|||
|職名2 = [[外務・英連邦大臣|外務大臣]] |
|||
|内閣2 = [[バルフォア内閣]] |
|||
|内閣2 = [[デビッド・ロイド・ジョージ|ロイド・ジョージ]]内閣 |
|||
|就任日2 = [[1902年]][[7月11日]] |
|||
| |
|就任日2 = [[1916年]][[12月10日]] |
||
|退任日2 = [[1919年]][[10月24日]]<ref name="秦(2001)511"/> |
|||
|元首職2 = 国王 |
|||
|国旗3 = UK |
|||
|元首2 = [[エドワード7世 (イギリス王)|エドワード7世]] |
|||
|職名3 = |
|職名3 = {{仮リンク|海軍大臣 (イギリス)|label=海軍大臣|en|First Lord of the Admiralty}} |
||
|内閣3 = [[ |
|内閣3 = [[ハーバート・ヘンリー・アスキス|アスキス]]内閣 |
||
|就任日3 = [[1915年]][[5月 |
|就任日3 = [[1915年]][[5月27日]] |
||
|退任日3 = [[1916年]][[12月 |
|退任日3 = [[1916年]][[12月5日]]<ref name="秦(2001)512">[[#秦(2001)|秦(2001)]] p.512</ref> |
||
|国旗4 = UK |
|||
|元首職3 = 国王 |
|||
|職名4 = [[第一大蔵卿]]兼[[庶民院院内総務]] |
|||
|元首3 = [[ジョージ5世 (イギリス王)|ジョージ5世]] |
|||
|内閣4 = 第2次[[ロバート・ガスコイン=セシル (第3代ソールズベリー侯)|ソールズベリー侯]]内閣<br/>第3次ソールズベリー侯内閣<br />バルフォア内閣(兼任) |
|||
|職名4 = [[外務・英連邦大臣|外務大臣]] |
|||
|就任日4 = [[1891年]][[10月6日]] - [[1892年]][[8月15日]]<br/>[[1895年]][[6月29日]] |
|||
|内閣4 = [[ロイド・ジョージ内閣]] |
|||
| |
|退任日4 = [[1905年]][[12月4日]] |
||
|職名5 = [[庶民院|庶民院議員]] |
|||
|退任日4 = [[1919年]][[10月23日]] |
|||
|国旗5 = UK |
|||
|元首職4 = 国王 |
|||
|就任日5 = [[1874年]][[1月31日]] - [[1885年]][[11月24日]]<ref name="HANSARD"/><br/>[[1885年]][[11月24日]] - [[1906年]][[1月12日]]<ref name="HANSARD"/><br/>1906年2月27日 |
|||
|元首4 = [[ジョージ5世 (イギリス王)|ジョージ5世]] |
|||
|退任日5 = [[1922年]][[5月5日]]<ref name="HANSARD"/> |
|||
|職名5 = [[枢密院議長 (イギリス)|枢密院議長]] |
|||
|選挙区5 = {{仮リンク|ハートフォード選挙区|en|Hertford (UK Parliament constituency)}}<ref name="HANSARD">[http://hansard.millbanksystems.com/people/mr-arthur-balfour/ HANSARD 1803–2005]</ref><br/>{{仮リンク|マンチェスター・イースト選挙区|en|Manchester East (UK Parliament constituency)}}<ref name="HANSARD"/><br/>{{仮リンク|シティ・オブ・ロンドン選挙区|en|City of London (UK Parliament constituency)}}<ref name="HANSARD"/> |
|||
|内閣5 = [[第2次ボールドウィン内閣]] |
|||
|国旗6 = GBR |
|||
|就任日5 = [[1925年]][[4月27日]] |
|||
|その他職歴1 = [[貴族院 (イギリス)|貴族院]]議員 |
|||
|退任日5 = [[1929年]][[6月4日]] |
|||
|就任日6 = [[1922年]][[5月5日]] |
|||
|元首職5 = 国王 |
|||
|退任日6 = [[1930年]][[3月19日]] |
|||
|元首5 = [[ジョージ5世 (イギリス王)|ジョージ5世]] |
|||
}} |
}} |
||
初代 |
初代バルフォア伯爵'''アーサー・ジェイムズ・バルフォア'''({{lang-en-short|Arthur James Balfour, 1st Earl of Balfour}}, {{Post-nominals|post-noms=[[ガーター勲章|KG]], [[メリット勲章|OM]], [[枢密院 (イギリス)|PC]], [[:en:Deputy Lieutenant|DL]]}}、[[1848年]][[7月25日]] - [[1930年]][[3月19日]])は、[[イギリス]]の[[政治家]]、[[哲学者]]、[[貴族]]。 |
||
[[ロバート・ガスコイン=セシル (第3代ソールズベリー侯爵)|ソールズベリー侯爵]]引退後の[[保守党 (イギリス)|保守党]]を指導し、[[1902年]]から[[1905年]]まで[[イギリスの首相|首相]]を務めた。政権交代後も[[自由党 (イギリス)|自由党]]の長期政権下で6年ほど野党保守党の党首を務めたが、[[1911年]]には党首の座を[[アンドルー・ボナー・ロー]]に譲る。 |
|||
[[1902年]][[7月11日]]から[[1905年]][[12月5日]]まで[[イギリスの首相]]を務めたほか、[[海軍大臣 (イギリス)|海軍大臣]]や[[外務・英連邦大臣|外務大臣]]、{{仮リンク|枢密院議長 (イギリス)|en|Lord President of the Council|label=枢密院議長}}を歴任した。{{仮リンク|ロイド・ジョージ内閣|en|United Kingdom coalition government (1916–1922)}}の外務大臣であった[[1917年]]に発した、「[[パレスチナ]]における[[ユダヤ人]]国家の設立を支持する」という[[バルフォア宣言]]で知られる。 |
|||
[[第一次世界大戦]]中に成立した自由党・保守党[[大連立]]の[[挙国一致内閣]]では{{仮リンク|海軍大臣 (イギリス)|label=海軍大臣|en|First Lord of the Admiralty}}や[[外務・英連邦大臣|外務大臣]]などを歴任した。 |
|||
== 経歴 == |
|||
=== 出生と初期の経歴 === |
|||
アーサー・バルフォアは[[1848年]][[7月25日]]、[[スコットランド]]の[[イースト・ロージアン]]州{{仮リンク|ウィッティングハム|en|Whittingehame}}に生まれた。父の{{仮リンク|ジェイムズ・メイトランド・バルフォア|en|James Maitland Balfour}}はイースト・ロージアン州の{{仮リンク|ハディントン|en|}}選挙区選出[[庶民院]]議員を務めた人物で、母のブランチ・メアリー・ハリエット・ガスコイン=セシルは第2代[[ソールズベリー侯爵]][[ジェイムズ・ガスコイン=セシル (第2代ソールズベリー侯爵)|ジェイムズ・ガスコイン=セシル]]の娘であった。「アーサー」の名は、[[代父母|代父]]となった初代[[ウェリントン公爵]][[アーサー・ウェルズリー (初代ウェリントン公爵)|アーサー・ウェルズリー]]による。[[1861年]]から[[1866年]]まで[[イートン・カレッジ]]で学び、次いで1866年からは[[ケンブリッジ大学]]の[[トリニティ・カレッジ (ケンブリッジ大学)|トリニティ・カレッジ]]で[[1869年]]まで哲学を学んだ<ref>{{Venn|id=BLFR866AJ|name=Balfour, Arthur}}</ref>。 |
|||
哲学者としても活躍し、宗教に関する哲学書を多数著している。 |
|||
[[1874年]]にバルフォアは[[ハートフォード (ハートフォードシャー)|ハートフォード]]選挙区で[[保守党 (イギリス)|保守党]]から庶民院議員に選出され、[[1885年]]まで務めた。[[1878年]]には叔父第3代ソールズベリー侯爵[[ロバート・ガスコイン=セシル (第3代ソールズベリー侯)|ロバート・ガスコイン=セシル]]の政務秘書官となり、[[露土戦争 (1877年)|露土戦争]]による領土問題を解決するための[[ベルリン会議 (1878年)|ベルリン会議]]に同行した。これが彼の外交官としての最初の経験となった。また同時に哲学にも時間を割き、科学の教条主義に対して個人的思想の自由を論じた『哲学的懐疑の抵抗』 ''{{lang|en|“Defence of Philosophic Doubt”}}''([[1879年]])は彼の哲学者としての評価を定めた。 |
|||
== 概要 == |
|||
=== ソールズベリー内閣 === |
|||
[[1848年]]に大富豪・大地主の息子として[[スコットランド]]・{{仮リンク|ホィッティンガム|en|Whittingehame}}に生まれる。[[ケンブリッジ大学]]の[[トリニティ・カレッジ (ケンブリッジ大学)|トリニティ・カレッジ]]で[[哲学]]を学んだ後、[[1874年]]1月の{{仮リンク|1874年イギリス総選挙|label=総選挙|en|United Kingdom general election, 1874}}で[[保守党 (イギリス)|保守党]]の[[庶民院]]議員に初当選。叔父にあたる[[ロバート・ガスコイン=セシル (第3代ソールズベリー侯爵)|第3代ソールズベリー侯爵]]が外相となるとその{{仮リンク|議会内個人秘書官 (イギリス)|label=議会内個人秘書官|en|Parliamentary Private Secretary}}を務めた。1879年には『哲学的懐疑の擁護』を出版した。 |
|||
[[1885年]]に首相となったソールズベリーはバルフォアを地方行政委員会委員長({{interlang|en|President of the Local Government Board}})に任命し、[[1886年]]には[[スコットランド大臣|スコットランド長官]]({{lang|en|Secretary for Scotland}})として入閣させた。さらに[[1887年]]には病で辞した[[アイルランド長官]]({{interlang|en|Chief Secretary for Ireland}})の後任にバルフォアを指名したが、この身内贔屓人事は政界に衝撃を与えた。「大丈夫だよ」といった意味の英語の成句 {{lang|en|“[[:en:Bob's your uncle|Bob's your uncle]]!”}} はバルフォアが叔父に贔屓されていることの皮肉に由来すると考えられている。しかしながら彼は「血のバルフォア」 {{lang|en|“Bloody Balfour”}} と呼ばれるほどの刑法の厳格な適用を行なって自身に対する軽薄な印象を払拭した。 |
|||
1880年の保守党の下野後は、[[ランドルフ・チャーチル (1849-1895)|ランドルフ・チャーチル卿]]らとともに保守党内の反執行部グループ「{{仮リンク|第四党|en|Fourth Party}}」を形成した。しかし1885年に{{仮リンク|第一次ソールズベリー侯爵内閣|en|First Salisbury ministry}}が成立すると、バルフォアは{{仮リンク|自治大臣 (イギリス)|label=自治大臣|en|President of the Local Government Board}}として入閣した。 |
|||
議会内においてバルフォアは、[[アイルランド議会党]]({{interlang|en|Irish Parliamentary Party}})が行なった[[アイルランド]]自治権拡大要求に反対し、[[ジョゼフ・チェンバレン]]率いる[[自由統一党]]({{interlang|en|Liberal Unionist Party}}; [[リベラル・ユニオニスト]])とともに{{仮リンク|統一主義|en|Unionism in Ireland}}を強く支持した。[[1890年]]には {{lang|en|Congested Districts Board}} を創設し、貧困層への支援の拡大を図った。また彼が演説の才能を発揮し、この時代における最も有力な論客として知られるようになったのもこの頃からであった。 |
|||
1886年の{{仮リンク|第二次ソールズベリー侯爵内閣|en|Second Salisbury ministry}}では[[スコットランド担当大臣]]、ついで{{仮リンク|アイルランド担当大臣|en|Chief Secretary for Ireland}}に就任する。アイルランド強圧法を制定して激しいアイルランド民族運動の弾圧を行い、「血塗られたバルフォア」の異名を取った。一方で融和政策もとり、アイルランド小作人の土地購入を促すバルフォア法を制定した。1891年には[[第一大蔵卿]]および[[庶民院院内総務]]に就任。 |
|||
[[1891年]]、バルフォアは死去した{{仮リンク|ウィリアム・ヘンリー・スミス (政治家)|en|William Henry Smith (politician)|label=ウィリアム・ヘンリー・スミス}}の後任として[[第一大蔵卿]]および[[庶民院院内総務]]となった(これは第一大蔵卿が首相と異なる最後の例であった)。翌[[1892年]]に[[保守党 (イギリス)|保守党]]が下野するとバルフォアは反対党庶民院院内総務になったが、[[1895年]]に保守党は政権を奪回し、彼も議会内での指導権を回復した。 |
|||
1895年には主著『信仰の基礎』を出版した。同年に成立した{{仮リンク|第三次ソールズベリー侯爵内閣|en|Unionist Government 1895–1905}}にも第一大蔵卿・庶民院院内総務として入閣。1898年に叔父ソールズベリー卿が病になると代行を務めることが増えた。中国分割をめぐる諸交渉や中等教育の普及を目的とするバルフォア教育法の制定を主導した。 |
|||
[[1898年]]にバルフォアは、病床にあったソールズベリーの代理として中国東北部の鉄道を巡る[[ロシア]]との交渉に当たった。 |
|||
1902年7月に叔父ソールズベリー卿が引退すると、代わって首相・保守党党首となる。1903年にはアイルランド担当大臣{{仮リンク|ジョージ・ウィンダム|en|George Wyndham}}の主導でウィンダム法を制定し、バルフォア法に引き続いてアイルランド小作人の土地購入を促進した。1905年に{{仮リンク|帝国防衛委員会|en|Committee of Imperial Defence}}を創設して国防強化に尽力したことも特筆される。 |
|||
=== 首相 === |
|||
[[1902年]][[7月11日]]に[[ロバート・ガスコイン=セシル (第3代ソールズベリー侯)|ソールズベリー]]が[[イギリスの首相|首相]]を辞職すると、バルフォアは後任に指名された。バルフォアの首相としての治績は、後に「バルフォア法」と呼ばれる教育法の支援、アイルランドの小作人に対する土地買収を援助するための国庫からの融資の拡充、[[帝国国防委員会]]({{interlang|en|Committee of Imperial Defence}})の創設などが挙げられる。 |
|||
外交面では極東で膨張する[[ロシア帝国]]を牽制するために[[フランス第三共和政|フランス]]に接近し、[[ムハンマド・アリー朝|エジプト]]、[[モロッコ]]、[[ナイジェリア]]、[[シャム]]([[タイ]])、[[マダガスカル島]]、[[ニューヘブリディーズ諸島]]、[[ニューファンドランド島]]などの利権・領有権をめぐる英仏間の諸懸案に折り合いを付けた。また[[日本]]との関係も強化し、[[日露戦争]]中に[[日英同盟]]を更新・強化した。 |
|||
[[1903年]]、[[植民地大臣]][[ジョゼフ・チェンバレン]]は保護貿易政策への復帰を主張し、「関税改革」論争が起きた。チェンバレンはイギリスの産業保護と植民地との連携強化のため[[特恵関税]]制度の導入を求めたが、[[財務大臣 (イギリス)|財務大臣]]の{{仮リンク|チャールズ・リッチー|en|Charles Ritchie, 1st Baron Ritchie of Dundee}}らはこれに反対し、閣内・与党内に深刻な亀裂が生じた。バルフォアはチェンバレンと自由貿易主義の大臣3名を辞職させることによってバランスをとろうとしたものの、連立与党である統一党からの離党者を生んだ。 |
|||
関税問題では植民地大臣[[ジョゼフ・チェンバレン]]の保護貿易主義に共感を寄せていたが、保守党の分裂を避けるため、折衷的立場に終始した。そのため関税問題の過熱で閣内で孤立したチェンバレンが辞職すると自由貿易主義派の[[財務大臣 (イギリス)|蔵相]]{{仮リンク|チャールズ・リッチー (初代リッチー・オブ・ダンディー男爵)|label=チャールズ・リッチー|en|Charles Ritchie, 1st Baron Ritchie of Dundee}}も罷免した。だがこの問題で保守党の内部分裂、自由党の結束強化、保護貿易を嫌う庶民の保守党離れの傾向は進んでいった。また1904年から問題となっていた南アフリカの中国人奴隷問題でもうまく立ち回れず、労働者層の支持を失っていく。関税問題をめぐって政権内の不一致が強まる中の1905年12月に総辞職し、自由党に政権を譲る。 |
|||
[[1905年]]12月にバルフォアは閣内不一致により首相を辞任し、[[自由党 (イギリス)|自由党]]の[[ヘンリー・キャンベル=バナマン]]に政権を譲った。バルフォアはキャンベル=バナマンが強力な内閣を組織することはないだろうと考えたが、その見込みは外れた。[[1906年]]1月に行なわれた「{{仮リンク|1906年イギリス総選挙|en|United Kingdom general election, 1906|label=地すべり総選挙}}」において[[保守党 (イギリス)|保守党]]・統一党は議席数を半数以下にまで減らす大敗を喫し、自身もマンチェスター東選挙区({{lang|en|Manchester East}})における議席を失った。 |
|||
バルフォアは保守党党首職に在職し続けたが、1906年1月の{{仮リンク|1906年イギリス総選挙|label=解散総選挙|en|United Kingdom general election, 1906}}で保守党は惨敗した。庶民院で多数派を失ったので、[[貴族院 (イギリス)|貴族院]]を中心に反政府闘争を行うようになり、1909年11月には蔵相[[デビッド・ロイド・ジョージ|ロイド・ジョージ]]の「人民予算」を貴族院で葬り去ったが、これがきっかけで自由党政権が貴族院の権限縮小を狙うようになった。1910年の二度の解散総選挙の末に自由党政権は新貴族任命を盾に保守党と貴族院を脅迫してくるようになり、弱気になったバルフォアは1911年8月に貴族院の権限縮小を盛り込む[[議会法]]の可決成立を認めることになった。これによって保守党内での求心力を失い、同年11月には党首を辞した。 |
|||
=== 退陣後 === |
|||
[[1906年]]の選挙における大敗の後もバルフォアは[[保守党 (イギリス)|保守党]]党首の職にあった。[[ジョゼフ・チェンバレン]]が病に倒れたせいもあって彼の党内における力は強化されていたが、[[庶民院]]において[[自由党 (イギリス)|自由党]]が圧倒的多数を占めていたためできることは限られていた。このためバルフォアは保守党[[貴族院院内総務]]の第5代[[ランズダウン侯爵]][[ヘンリー・ペティ=フィッツモーリス (第5代ランズダウン侯爵)|ヘンリー・ペティ=フィッツモーリス]]と協力し、[[貴族院 (イギリス)|貴族院]]議員を使って自由党の政策や法案に抵抗した。[[1909年]]までの間に多数の法案が貴族院で変更されたり否決され、[[デビッド・ロイド・ジョージ]]をして「(貴族院が)憲法の番人ではなくバルフォアのプードルだ」 {{lang|en|“not the watchdog of the Constitution, but Mr. Balfour's poodle.”}} と言わしめた。さらに[[1910年]]のいわゆる「[[人民予算]]」({{interlang|en|People's Budget}})が貴族院によって否決されたことは、庶民院の解散・総選挙を経て[[1911年]]の[[議会法]]の制定へと帰結し、貴族院の権限は大幅に縮小されさらに貴族院議員の新規叙任が制限されることになった。ついにバルフォアは党首を辞任し、[[アンドルー・ボナー・ロー]]にその座を譲った。 |
|||
[[第一次世界大戦]]中の1915年の[[ハーバート・ヘンリー・アスキス|アスキス]]挙国一致内閣では海軍大臣として入閣し、続く1916年のロイド・ジョージ挙国一致内閣では外務大臣となった。この外相就任時の1917年に[[パレスチナ]]にユダヤ人国家の樹立を認める[[バルフォア宣言]]を出している。1919年には{{仮リンク|枢密院議長 (イギリス)|en|Lord President of the Council|label=枢密院議長}}に転じるも1922年の大連立解消を機に退任。1922年には初代バルフォア伯爵に叙爵し、貴族に列する。[[スタンリー・ボールドウィン]]保守党政権下の1925年にも枢密院議長に再任するが、1929年には政界引退し、その翌年の1930年に[[イングランド]]・{{仮リンク|ウォーキング (イングランド)|en|Woking|label=ウォーキング}}で死去した。 |
|||
しかしながらバルフォアは党内における重鎮であることには変わりなかった。[[1915年]]に[[ハーバート・ヘンリー・アスキス]]が{{仮リンク|第2次アスキス内閣|en|United Kingdom coalition government (1915–1916)|label=戦時内閣}}を組閣すると[[ウィンストン・チャーチル]]の後任として[[海軍大臣 (イギリス)|海軍大臣]]となり、[[1916年]]に第2次アスキス内閣が倒れた後に成立した[[ロイド・ジョージ内閣]]でも彼は[[エドワード・グレイ]]の後任の[[外務・英連邦大臣|外務大臣]]に任命された。外務大臣としてのバルフォアは[[ウォルター・ロスチャイルド]]に対して[[パレスチナ]]における[[ユダヤ人]]国家建設への援助を約束する書簡を送った([[バルフォア宣言]])ことで最も知られている。 |
|||
[[#toc|【↑目次へ移動する】]] |
|||
[[1919年]]に[[パリ講和会議]]の結果[[ヴェルサイユ条約]]が調印されるとバルフォアは外務大臣を辞任したが、その後の平時内閣においても[[枢密院議長 (イギリス)|枢密院議長]]として閣僚に留まった。また[[1921年]]から[[1922年]]の[[ワシントン会議 (1922年)|ワシントン会議]]には[[イギリス]]代表として出席している。 |
|||
{{-}} |
|||
== 生涯 == |
|||
[[1922年]]にロイド・ジョージ内閣が総辞職すると、バルフォアは保守党内の職も辞した。またこの年[[バルフォア伯爵]]に叙され貴族院に列した。[[1923年]]に[[アンドルー・ボナー・ロー]]の後任として首相に任命された[[スタンリー・ボールドウィン]]はバルフォアに対して入閣の意思を尋ねたが彼は断った。しかし[[1925年]]に彼は前年に死去した初代ケドルストンのカーゾン侯爵[[ジョージ・カーゾン (初代カーゾン・オヴ・ケドルストン侯爵)|ジョージ・カーゾン]]の後任として再び枢密院議長となった。 |
|||
=== 出生から政界入りまで === |
|||
[[File:Lord Balfour's childhood home.JPG|250px|thumb|バルフォアが生まれ育ったホィッティンガムの屋敷。]] |
|||
[[1848年]][[7月25日]]、[[スコットランド]]の[[イースト・ロージアン]]州{{仮リンク|ホィッティンガム|en|Whittingehame}}に生まれた<ref name="世界伝記大事典(1981,8)27">[[#世界伝記大事典(1981,8)|世界伝記大事典(1981)世界編8巻]] p.27</ref>。 |
|||
父{{仮リンク|ジェイムズ・メイトランド・バルフォア|en|James Maitland Balfour}}は大富豪・大地主であり、また[[庶民院]]議員も務めた人物だった。バルフォア家はスコットランドの旧家であり、[[18世紀]]末に祖父ジェイムズの代に[[イギリス東インド会社]]の貿易で莫大な富を築いた。スコットランドに膨大な土地を購入し、ホィッティンガムをその本拠とするようになった家柄である<ref name="タックマン(1990)57">[[#タックマン(1990)|タックマン(1990)]] p.57</ref>。 |
|||
バルフォアは[[1930年]][[3月19日]]に[[サリー (イングランド)|サリー]]州の{{仮リンク|ウォーキング (イングランド)|en|Woking|label=ウォーキング}}で死去し、故郷の[[ウィッティングハム]]に葬られている。生涯独身であったため、爵位は弟ジェラルドに継承された。 |
|||
母ブランチェ・メアリー・ハリエット嬢(Lady Blanche Mary Harriet)は[[ジェイムズ・ガスコイン=セシル (第2代ソールズベリー侯爵)|第2代ソールズベリー侯爵ジェイムズ・ガスコイン=セシル]]の娘だった<ref name="世界伝記大事典(1981,8)27"/><ref name="平賀(2012)172">[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.172</ref>。セシル家は300年にわたって{{仮リンク|ハットフィールド (ハートフォードシャー)|label=ハットフィールド|en|Hatfield, Hertfordshire}}を領してきた名門貴族である<ref name="タックマン(1990)10">[[#タックマン(1990)|タックマン(1990)]] p.10</ref>。 |
|||
== 出典 == |
|||
<div class="references-small">{{Reflist}}</div> |
|||
次弟にセシル・チャールズ(Cecil Charles Balfour)、三弟に生物学者となる{{仮リンク|フランシス・メイトランド・バルフォア|label=フランシス・メイトランド|en|Francis Maitland Balfour}}、四弟に政治家またバルフォア伯位の継承者となる{{仮リンク|ジェラルド・バルフォア (第2代バルフォア伯爵)|label=ジェラルド|en|Gerald Balfour, 2nd Earl of Balfour}}、五弟に国王副官となるユースタス・ジェームズ・アントニー(Eustace James Anthony)がいる<ref name="タックマン(1990)58">[[#タックマン(1990)|タックマン(1990)]] p.58</ref>。また姉が三人おり、長姉エヴェリン・ジョージアナ・メアリー(Evelyn Georgiana Mary)は数学者[[ジョン・ウィリアム・ストラット|第3代レイリー男爵]]に、次姉[[エレノア・ミルドレッド・シジウィック|エレノア・ミルドレッド]]は[[ヘンリー・シジウィック]]にそれぞれ嫁いでいる<ref name="タックマン(1990)58">[[#タックマン(1990)|タックマン(1990)]] p.58</ref>。 |
|||
[[ワーテルローの戦い]]の英雄[[アーサー・ウェルズリー (初代ウェリントン公爵)|ウェリントン公爵アーサー・ウェルズリー]]が[[代父]]となり、彼の名前をとってアーサーと名付けられた<ref name="タックマン(1990)57">[[#タックマン(1990)|タックマン(1990)]] p.57</ref>。 |
|||
7歳の頃に父が死去<ref name="平賀(2012)172">[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.172</ref><ref name="タックマン(1990)57">[[#タックマン(1990)|タックマン(1990)]] p.57</ref>。[[1861年]]から[[1866年]]まで[[イートン・カレッジ]]で学び、次いで1866年から[[1869年]]にかけて[[ケンブリッジ大学]]の[[トリニティ・カレッジ (ケンブリッジ大学)|トリニティ・カレッジ]]で[[哲学]]を学んだ<ref>{{Venn|id=BLFR866AJ|name=Balfour, Arthur}}</ref><ref name="世界伝記大事典(1981,8)27"/><ref name="平賀(2012)172"/>。哲学研究にのめりこみ、家の財産は弟に譲って自らはケンブリッジ大学に残り、哲学研究を続けようかと考えた時期もあったという<ref name="平賀(2012)172"/><ref name="タックマン(1990)57"/>。 |
|||
しかし叔父にあたる保守党[[貴族院 (イギリス)|貴族院]]議員の[[ロバート・ガスコイン=セシル (第3代ソールズベリー侯爵)|第3代ソールズベリー侯爵]]の勧めや<ref name="世界伝記大事典(1981,8)28">[[#世界伝記大事典(1981,8)|世界伝記大事典(1981)世界編8巻]] p.28</ref>、母ブランチェから高貴な家に生まれた者は政治的・社会的責任を負わねばならないという[[ノブレス・オブリージュ]]的な考えの説教をされたことで、最終的には政界の道を選んだ<ref name="平賀(2012)172"/><ref name="タックマン(1990)57"/>。 |
|||
[[#toc|【↑目次へ移動する】]] |
|||
=== 政界入り === |
|||
[[1874年]]1月の{{仮リンク|1874年イギリス総選挙|label=総選挙|en|United Kingdom general election, 1874}}で{{仮リンク|ハートフォード選挙区|en|Hertford (UK Parliament constituency)}}から[[保守党 (イギリス)|保守党]]候補として出馬して当選した<ref name="HANSARD"/><ref name="世界伝記大事典(1981,8)28"/>。 |
|||
この総選挙は全国的にも保守党が勝利し、[[ベンジャミン・ディズレーリ]]を首相とする保守党政権の発足をもたらした。[[露土戦争 (1877年-1878年)|露土戦争]]の最中の[[1878年]]に叔父ソールズベリー侯爵が外務大臣となり<ref name="坂井(1967)46-47">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.46-47</ref>、バルフォアはその{{仮リンク|議会内個人秘書官 (イギリス)|label=議会内個人秘書官|en|Parliamentary Private Secretary}}{{#tag:ref|各省庁の大臣を補佐する庶民院議員の役職。各省庁の{{仮リンク|政務次官 (イギリス)|label=政務次官|en|Undersecretary}}とは違い、政府の役職ではない。若手議員が選ばれることが多い<ref name="マッケンジー(1965)33">[[#マッケンジー(1965)|マッケンジー(1965)]] p.33</ref>。|group=注釈}}となった<ref name="マッケンジー(1965)33"/>。 |
|||
1878年6月から7月にかけて露土戦争の講和会議である[[ベルリン会議 (1878年)|ベルリン会議]]にディズレーリや叔父ソールズベリー侯爵とともに出席した<ref name="マッケンジー(1965)33"/><ref name="世界伝記大事典(1981,8)28"/>。 |
|||
[[#toc|【↑目次へ移動する】]] |
|||
{{-}} |
|||
=== 「第四党」 === |
|||
[[File:The Fourth Party Vanity Fair 1 December 1880.jpg|250px|thumb|1880年の庶民院議場で固まって座る第四党を描いた『{{仮リンク|ヴァニティ・フェアー (イギリス雑誌)|label=ヴァニティ・フェアー|en|Vanity Fair (British magazine)}}』誌の戯画。左から[[ランドルフ・チャーチル (1849-1895)|ランドルフ・チャーチル卿]]、バルフォア{{#tag:ref|この戯画に描かれる通りバルフォアは議場でちゃんと座っていることが少なく、身体を水平に近い状態にして座っていることが多かった<ref name="タックマン(1990)56">[[#タックマン(1990)|タックマン(1990)]] p.56</ref>。|group=注釈}}、{{仮リンク|ヘンリー・ドラモンド・ウォルフ|en|Henry Drummond Wolff}}、{{仮リンク|ジョン・エルドン・ゴースト|en|John Eldon Gorst}}。]] |
|||
[[1880年]]の総選挙で保守党は敗北し、[[ウィリアム・グラッドストン]]を首相とする自由党政権が発足した。保守党は野党となったが、{{仮リンク|保守党庶民院院内総務|en|Leaders of the Conservative Party#Leaders in the House of Commons 1834–1922}}を務める元蔵相{{仮リンク|スタッフォード・ノースコート (初代イデスリー伯爵)|label=サー・スタッフォード・ノースコート准男爵|en|Stafford Northcote, 1st Earl of Iddesleigh}}は温和な人柄で政権批判に向いているとはいえなかった。しかも彼はかつてグラッドストンの秘書であったため、今でもグラッドストンに敬意を払い続けていた<ref name="小関(2006)32">[[#小関(2006)|小関(2006)]] p.32</ref><ref name="ブレイク(1979)163">[[#ブレイク(1979)|ブレイク(1979)]] p.163</ref>。 |
|||
これに不満を感じていた保守党若手庶民院議員[[ランドルフ・チャーチル (1849-1895)|ランドルフ・チャーチル卿]](後の首相[[ウィンストン・チャーチル]]の父)は、バルフォアや{{仮リンク|ヘンリー・ドラモンド・ウォルフ|label=サー・ヘンリー・ドラモンド・ウォルフ|en|Henry Drummond Wolff}}、{{仮リンク|ジョン・エルドン・ゴースト|en|John Eldon Gorst}}を糾合して「{{仮リンク|第四党|en|Fourth Party}}」と呼ばれるノースコートに造反する独自グループを結成した<ref name="ブレイク(1979)164">[[#ブレイク(1979)|ブレイク(1979)]] p.164</ref>。 |
|||
「第四党」のリーダー的存在はランドルフ卿であるが、バルフォアは常にランドルフ卿に従っているわけではなく、たとえばランドルフ卿が{{仮リンク|保守党貴族院院内総務|en|Leaders of the Conservative Party#Leaders in the House of Lords 1834–present}}を務める叔父ソールズベリー侯爵まで批判した場合には、叔父の擁護にまわるのが常だった<ref name="マッケンジー(1965)33"/>。またランドルフ卿が「民主化」と称して議会外保守党組織である{{仮リンク|保守党協会全国同盟|en|National Union of Conservative and Constitutional Associations}}が党の政策や財政を監督できるようにしようとした際にも、バルフォアは「議会軽視」としてこれに反対している<ref name="マッケンジー(1965)227-228">[[#マッケンジー(1965)|マッケンジー(1965)]] p.227-228</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
[[#toc|【↑目次へ移動する】]] |
|||
=== 第一次ソールズベリー内閣自治大臣 === |
|||
1885年7月にグラッドストン自由党政権が議会で敗北したことにより、{{仮リンク|第一次ソールズベリー侯爵内閣|en|First Salisbury ministry}}が成立。バルフォアは{{仮リンク|自治大臣 (イギリス)|label=自治大臣|en|President of the Local Government Board}}として入閣した<ref name="マッケンジー(1965)33"/>。「第四党」の同志のランドルフ・チャーチル卿も{{仮リンク|インド担当大臣|en|Secretary of State for India}}として入閣している<ref name="小関(2006)64">[[#小関(2006)|小関(2006)]] p.64</ref>。 |
|||
しかし同内閣は短期間で終焉したため、バルフォアもこれといった功績を残すことはなかった<ref name="マッケンジー(1965)33"/>。 |
|||
[[#toc|【↑目次へ移動する】]] |
|||
=== 第二次ソールズベリー内閣アイルランド担当大臣 === |
|||
1886年7月に{{仮リンク|第二次ソールズベリー侯爵内閣|en|Second Salisbury ministry}}が成立すると、叔父の引き立てで初め[[スコットランド担当大臣]]として入閣したが<ref name="平賀(2012)174-175">[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.174-175</ref><ref name="マッケンジー(1965)33"/>、1887年3月に{{仮リンク|マイケル・ヒックス・ビーチ (初代セント・アルドウィン伯爵)|label=ヒックス・ビーチ|en|Michael Hicks Beach, 1st Earl St Aldwyn}}が{{仮リンク|アイルランド担当大臣|en|Chief Secretary for Ireland}}を辞職したため、バルフォアがその後任となった<ref name="神川(2011)412">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.412</ref>。 |
|||
この人事は「身贔屓」として政界に衝撃を与えた。「大丈夫だよ」といった意味の英語の成句 {{lang|en|“[[:en:Bob's your uncle|Bob's your uncle]]!”}} はバルフォアが叔父に贔屓されていることの皮肉に由来すると考えられている<ref name=Trahair>[http://books.google.com/books?id=K0zrsHO27-wC&pg=PA72&lpg=PA72 ''From Aristotelian to Reaganomics: A Dictionary of Eponyms With Biographies in the Social Science''], by R. C. S. Trahair, [[:en:Greenwood Publishing Group|Greenwood Publishing Group]], 1994, page 72. Retrieved online from [[Google Books]], Jul 30, 2012.</ref>。バルフォアは一般にインテリの優男と見られており、マスコミからは「プリンス・チャーミング」「ミス・バルフォア」などと渾名されて侮られた<ref name="タックマン(1990)63">[[#タックマン(1990)|タックマン(1990)]] p.63</ref>。アイルランド人からも「'''[[クララ (曖昧さ回避)|クララ]]'''」という女性名で呼ばれ、馬鹿にされたという<ref name="神川(2011)412">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.412</ref>。 |
|||
==== アイルランド民族運動の弾圧 ==== |
|||
[[File:Arthur James Balfour, Vanity Fair, 1887-09-24.jpg|180px|thumb|1887年9月24日の『{{仮リンク|ヴァニティ・フェアー (イギリス雑誌)|label=ヴァニティ・フェアー|en|Vanity Fair (British magazine)}}』誌のバルフォアの戯画]] |
|||
バルフォアがアイルランド担当相に就任した時、アイルランド問題は深刻化していた。1886年9月に{{仮リンク|アイルランド国民党|en|Irish Parliamentary Party}}党首[[チャールズ・スチュワート・パーネル]]が議会に提出したアイルランドの地代を半減させる法案が否決されて以降、アイルランドでは小作人同士が協定を結んで勝手に地代を減額し、地主がそれを承諾して受け取ればよし、受け取らねば、その地主が小作人を強制立ち退きさせた時の抵抗運動に備えて[[供託]]するという闘争が行われていたのである。これにより強制立ち退きと暴動の危険が高まっていた<ref name="神川(2011)411-412">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.411-412</ref>。 |
|||
これに対してバルフォアはアイルランド民族運動の弾圧を可能とする強圧法の制定を急いだ<ref name="神川(2011)412">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.412</ref>。その法案の第二読会での審議の最中の1887年4月8日に『[[タイムズ]]』紙がパーネルが元アイルランド担当大臣[[フレデリック・キャヴェンディッシュ (1836-1882)|フレデリック・キャヴェンディッシュ卿]]の暗殺を支持していることを示唆する記事を掲載した。パーネルはその事実関係を否認したが、この記事は大きな反響を呼び、バルフォアの強圧法案の良き追い風となった。強圧法は8月にも可決成立した<ref name="神川(2011)413-414">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.413-414</ref>。 |
|||
この後、バルフォアは強圧法を駆使してアイルランドで激しい弾圧を行い、アイルランド国民党の議員たちを含むアイルランド民族運動指導者たちを軒並み逮捕していった。アイルランドの刑務所はあっという間に満杯になったという<ref name="神川(2011)414">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.414</ref>。その弾圧の容赦の無さからバルフォアはアイルランド人から「クララ」改め「'''血塗られたバルフォア'''({{lang|en|“Bloody Balfour”}})」と呼ばれ恐れられるようになった<ref name="神川(2011)414"/><ref name="小関(2006)324">[[#小関(2006)|小関(2006)]] p.324</ref><ref name="タックマン(1990)63">[[#タックマン(1990)|タックマン(1990)]] p.63</ref>。 |
|||
1887年9月9日、アイルランド・[[コーク州]]{{仮リンク|ミッチェルスタウン|en|Mitchelstown}}で警官と農民が衝突し、農民3人が警察官に銃殺される事件が発生した<ref name="小関(2006)324">[[#小関(2006)|小関(2006)]] p.324</ref><ref name="神川(2011)414">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.414</ref>。検死の陪審官は警察官による故意の殺人と断定したが、バルフォアは警官の行動を称賛した。これに対してアイルランド自治を決意していた野党自由党のグラッドストンは「ミッチェルスタウンを記憶せよ(Remember Mitchelstown)」を自由党のスローガンに定めてアイルランド問題を中心に与党保守党と対決する姿勢を強めた<ref name="神川(2011)415">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.415</ref>。 |
|||
==== バルフォア法 ==== |
|||
しかしバルフォアは強圧一辺倒の大臣ではなく、1890年3月と11月にはアイルランド小作人が地主から土地を購入できるよう支援する「土地購入および稠密地方(アイルランド)法案」(通称「バルフォア法」)を提出した。3月提出の法案は否決されたが、11月に再提出されたものが可決された<ref name="高橋(1997)79">[[#高橋(1997)|高橋(1997)]] p.79</ref>{{#tag:ref|この法案の説明の中でバルフォアはアイルランドの現況を次のように分析している。「イングランドとスコットランドでは地主階級は、土地の耕作に従事している二つの階級の福祉に貢献しているといえる。地主階級がいなければ、農業労働者階級は良い住居や良い賃金、適切な割り当て地(allotments)を受けることは不可能であろうし、また借地農階級は地主階級がいなかったら、土地を経営するための流動資本(The working capital)だけでなく、固定資本(The fixed capital)まで提供せねばならなくなるからだ。ところがアイルランドではこうした地主の機能がイングランドほど有効に発揮されていない。もともとアイルランドには地主が恒久的改良(permanent improvements)や農業労働者用の住居を提供するという慣行がない上、政治状況のせいで地主が有益な影響力を行使する可能性を奪われているからだ。そのためアイルランドにおいては自作農を増やすことが望ましい」<ref name="高橋(1997)80">[[#高橋(1997)|高橋(1997)]] p.80</ref>。|group=注釈}}。 |
|||
この「バルフォア法」は、第一次ソールズベリー侯爵内閣期に制定された{{仮リンク|アシュバーン法|en|Purchase of Land (Ireland) Act 1885}}を拡張させたものであり、土地購入を希望するアイルランド小作農に土地購入費の貸し付けを行う「土地委員会」の貸付限度額をそれまでの500万ポンドから3300万ポンドに大幅増額させ<ref>[[#高橋(1997)|高橋(1997)]] p.77/83</ref>、さらに現に小作人である者だけでなく、かつて小作人だった者も保護対象としており、後の追放小作人法の先駆となる法律であったといえる<ref name="高橋(1997)85">[[#高橋(1997)|高橋(1997)]] p.85</ref>。 |
|||
しかし国庫の負担を軽くするために複雑な体系にもなった。まず地主への支払いは現金ではなく、[[アイルランド銀行]]が発行する2.75%の利子付きの土地債権に変更されたが、この土地債権は地主に直接渡されたため、土地債権の価格変動が地主の土地売却の意欲に直接的に影響を及ぼすようになった([[コンソル公債]]と交換可能にすることによって土地債権がコンソル公債以下の価格にならないよう配慮はされているが)<ref name="高橋(1997)84">[[#高橋(1997)|高橋(1997)]] p.84</ref>。また土地購入者は保険金を積み立てることになり、そのために最初の5年間は旧地代の80%を支払わねばならなかった<ref name="高橋(1997)84"/>。さらに土地購入者が49年間に渡って支払うことになっている4%の年賦金の一部が「州のパーセンテージ(County percentage)」として地方税会計に流用されることになった(利子2.75%、償却費1%、州のパーセンテージ0.25%)<ref name="高橋(1997)84"/>。 |
|||
このような制度の複雑化のために結果としてはアシュバーン法の時よりも土地購入申請者数が減少した。1896年のバルフォア法改正の際にアイルランド担当大臣を務めていた弟{{仮リンク|ジェラルド・バルフォア (第2代バルフォア伯爵)|label=ジェラルド・バルフォア|en|Gerald Balfour, 2nd Earl of Balfour}}が議会に行った報告によればアシュバーン法下での申請数は6年間で4645件なのに対して、バルフォア法下での申請数は4年間に2600件に留まるという<ref name="高橋(1997)85">[[#高橋(1997)|高橋(1997)]] p.85</ref>。しかしこの時に弟ジェラルドによってバルフォア法は改正され、「州のパーセンテージ」や保険金制度が廃止されて制度は簡略になり、また年賦金算定の基礎となる前貸金を10年ごとに算出して減少させていく修正案も導入された。この修正のおかげでバルフォア法下での土地購入申請も増えていき、1902年3月までに約3万7000人のアイルランド小作人が土地を購入することができたのであった<ref name="高橋(1997)86">[[#高橋(1997)|高橋(1997)]] p.86</ref>。 |
|||
[[#toc|【↑目次へ移動する】]]{{-}} |
|||
=== 第三次ソールズベリー内閣第一大蔵卿・庶民院院内総務 === |
|||
[[File:Arthur James Balfour00.jpg|180px|thumb|1892年のバルフォアを描いた{{仮リンク|エリス・ウィリアム・ロバーツ|en|Ellis William Roberts}}の絵画]] |
|||
[[1891年]]、死去した{{仮リンク|ウィリアム・ヘンリー・スミス (政治家)|en|William Henry Smith (1825–1891)|label=ウィリアム・ヘンリー・スミス}}の後任として[[第一大蔵卿]]および[[庶民院院内総務]]に抜擢された(これは第一大蔵卿が首相と異なる最後の例であった)。バルフォアはアイルランド民族運動を激しく弾圧したことで保守党庶民院議員たちから人気を集めており、その声にソールズベリー侯爵が応えた人事だった<ref name="マッケンジー(1965)33-34">[[#マッケンジー(1965)|マッケンジー(1965)]] p.33-34</ref><ref name="タックマン(1990)63">[[#タックマン(1990)|タックマン(1990)]] p.63</ref>。 |
|||
翌[[1892年]]に[[保守党 (イギリス)|保守党]]が下野したが、この後の3年間の野党時代にもバルフォアは{{仮リンク|保守党庶民院院内総務|en|Leaders of the Conservative Party#Leaders in the House of Commons 1834–1922#Lord Salisbury's Cabinet, June 1895 – July 1902}}に在職し続けた。[[1895年]]に保守党が{{仮リンク|自由統一党 (イギリス)|label=自由統一党|en|Liberal Unionist Party}}と連立して政権を奪回し、{{仮リンク|第三次ソールズベリー侯爵内閣|en|Unionist Government 1895–1905}}を発足させると再び第一大蔵卿・庶民院院内総務に就任した。首相ソールズベリー侯は自邸暮らしをするようになり、[[ダウニング街10番地]]にはバルフォアが入った<ref name="タックマン(1990)60">[[#タックマン(1990)|タックマン(1990)]] p.60</ref>。 |
|||
さらに[[1898年]]にソールズベリー侯が病となると、甥であるバルフォアがその代理を務めることが増えていった<ref name="平賀(2012)175">[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.175</ref>。 |
|||
==== 中国分割をめぐって ==== |
|||
1895年の[[日清戦争]]で[[清]]が[[日本]]に敗れ、日本に対して負った巨額の賠償金を支払うために清政府が[[ロシア帝国]]と[[フランス第三共和政|フランス]]から借款し、その見返りとして露仏両国が清国内に様々な権益を獲得した。これがきっかけとなり、急速にイギリス、ロシア、フランス、ドイツ、日本など列強諸国による中国分割が進み、[[阿片戦争]]以来のイギリス一国の中国半植民地([[非公式帝国]])状態は崩壊した<ref name="坂井(1967)233-234">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.233-234</ref>。 |
|||
とりわけ急速に北中国を勢力圏としていくロシアとの対立が深まった。バルフォアは1898年8月10日の庶民院での演説で中国分割において「勢力圏」という概念は否定されるべきであり、代わりに「利益範囲」という概念を導入すべきと主張した。これは範囲内において範囲設定国は他国企業を排除できる権利を有するが、[[門戸開放政策|通商の門戸は常に開放]]しなければならないというものでイギリス資本主義の利益に沿った主張だった<ref name="坂井(1967)267">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.267</ref>。一方ロシアはあくまで北中国を排他的な自国の独占市場、つまり勢力圏とする腹積もりだったから北中国を門戸開放する意志などなかった<ref name="坂井(1967)269">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.269</ref>。 |
|||
バルフォアの演説の直後の1898年8月12日には[[ベルギー]]企業が清政府から[[京漢鉄道]]を借款する契約を結んだが、これに危機感を抱いたバルフォアは外相(首相ソールズベリー侯が兼務していた)代理として清政府と交渉を行い、9月6日にもイギリスに5本の鉄道敷設権{{#tag:ref|[[天津]]―[[鎮江]]線、[[山西]][[河南]]―揚子江線、[[九竜]]―[[広東]]線、[[浦口]]―[[信陽]]線、[[蘇州]]―[[杭州]]―[[寧波]]線の5本の鉄道<ref name="坂井(1967)274">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.274</ref>。|group=注釈}}を与えることを認めさせた<ref name="坂井(1967)274">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.274</ref>。 |
|||
一方1898年6月から起こっていた中国東北部の鉄道敷設権をめぐる英露両国の論争ではロシアから妥協を引き出せず、1899年4月に締結された英露両国の協定は、「イギリスは[[長城]]以北に鉄道敷設権を求めない。ロシアも揚子江流域に鉄道敷設権を求めない」ことを確認したのみとなり、その範囲内における自国企業独占や通商自由化を保障し合うことはできなかった<ref>[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.269-270</ref>。 |
|||
1900年5月から8月にかけて中国半植民地化に反発した[[義和団]]が北中国で蜂起した([[義和団の乱]])。乱自体は列強諸国によってただちに叩き潰されたが、ロシアはこれを理由に満洲を軍事占領した。これに対抗すべくバルフォアは植民地大臣[[ジョゼフ・チェンバレン]]や{{仮リンク|イギリス枢密院議長|label=枢密院議長|en|Lord President of the Council}}{{仮リンク|スペンサー・キャヴェンディッシュ (第8代デヴォンシャー公爵)|label=デヴォンシャー公爵|en|Spencer Cavendish, 8th Duke of Devonshire}}ら自由統一党の面々とともに[[ドイツ帝国]]や日本との連携を強化してロシアを抑え込むべきことを主張した<ref name="坂井(1967)283">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.283</ref>。 |
|||
結局ドイツはロシアとの対立を回避したのでイギリスは日本と接近することになり、1902年[[1月30日]]にも5年期限の[[日英同盟]]が締結された<ref name="坂井(1967)283">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.283</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
==== バルフォア教育法 ==== |
|||
[[File:Arthur Balfour 1902.jpg|180px|thumb|1902年のバルフォア]] |
|||
1902年3月には第一大蔵卿として「バルフォア教育法」と呼ばれる{{仮リンク|1902年教育法 (イギリス)|label=教育法|en|Education Act 1902}}の法案を議会に提出した<ref name="坂井(1967)323">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.323</ref>。これは1870年にグラッドストン自由党政権下で制定された初等教育普及のための{{仮リンク|1870年初等教育法|label=初等教育法案|en|Elementary Education Act 1870}}を拡張させ、中等教育普及のための州議会がすべき支援を定めた法律であるが、同時に1870年の初等教育法で定められていた非国教徒(自由党支持基盤)が強い影響力を持つ学務委員会(School Attendance Committee)を廃止して、新たな小学校監督機関として{{仮リンク|地方教育庁 (イギリス)|label=地方教育庁|en|Local education authority}}を設置させるものでもあった。加えて国教会とカトリックの学校には地方教育庁の管理下に置く代わりに地方税の一部を導入するという条文もあり、非国教徒が強く反発する内容だった<ref name="村岡(1991)229">[[#村岡(1991)|村岡、木畑(1991)]] p.229</ref><ref name="トレヴェリアン(1975)185">[[#トレヴェリアン(1975)|トレヴェリアン(1975)]] p.185</ref>。 |
|||
非国教徒の反対運動は激しく、とりわけ[[ウェールズ]]での闘争が激化した。庶民院ではウェールズ出身の自由党議員[[デビッド・ロイド・ジョージ|ロイド・ジョージ]]が中心となって同法への反対運動が展開された<ref>[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.323-325</ref><ref name="村岡(1991)230">[[#村岡(1991)|村岡、木畑(1991)]] p.230</ref>。9カ月にも及ぶ激闘の末、バルフォアが首相に就任した後の1902年12月にバルフォア教育法は可決された<ref name="村岡(1991)230"/>。この法律は1944年のバットラー法成立までイギリス中等教育に関する基本法として君臨することになる<ref name="ブレイク(1979)203">[[#ブレイク(1979)|ブレイク(1979)]] p.203</ref>。 |
|||
しかし[[ボーア戦争]]以来、小英国主義者と[[自由帝国主義|自由帝国主義者]]に分裂していた自由党がこの法律への反対を共通項に一つにまとまってしまうという保守党にとっては逆作用も生んだのだった<ref name="村岡(1991)230"/>。 |
|||
[[#toc|【↑目次へ移動する】]]{{-}} |
|||
=== バルフォア内閣 === |
|||
[[1902年]][[7月11日]]に首相[[ロバート・ガスコイン=セシル (第3代ソールズベリー侯)|ソールズベリー侯]]が[[イギリスの首相|首相]]を辞した。[[ランドルフ・チャーチル (1849-1895)|ランドルフ・チャーチル卿]]はすでに亡く、連立相手の自由統一党の有力者[[ジョゼフ・チェンバレン]]と{{仮リンク|スペンサー・キャヴェンディッシュ (第8代デヴォンシャー公爵)|label=デヴォンシャー公爵|en|Spencer Cavendish, 8th Duke of Devonshire}}も首相になる意思はなく、バルフォアが後任の首相となることに異を唱える者はなかった<ref name="マッケンジー(1965)34">[[#マッケンジー(1965)|マッケンジー(1965)]] p.34</ref>。 |
|||
1907年7月12日に国王[[エドワード7世 (イギリス王)|エドワード7世]]より大命を拝受し、{{仮リンク|バルフォア内閣|en|Unionist Government 1895–1905#Arthur Balfour's Cabinet, July 1902 – December 1905}}を組閣した。さらにその二日後には外務省内で開かれた保守党両院総会で保守党党首に選出された。デヴォンシャー公爵やチェンバレンら自由統一党幹部も引き続き連立を維持していくことを表明した<ref>[[#マッケンジー(1965)|マッケンジー(1965)]] p.34-35</ref>。 |
|||
==== 内政 ==== |
|||
===== ウィンダム法 ===== |
|||
[[File:Portrait of George Wyndham.jpg|180px|thumb|バルフォア内閣アイルランド担当大臣{{仮リンク|ジョージ・ウィンダム|en|George Wyndham}}]] |
|||
バルフォア内閣アイルランド担当大臣{{仮リンク|ジョージ・ウィンダム|en|George Wyndham}}の主導で1903年には新たなアイルランド土地購入法のウィンダム法が制定された<ref name="高橋(1997)93">[[#高橋(1997)|高橋(1997)]] p.93</ref>。 |
|||
この法律は強制的土地購入路線を否定し、あくまで自由契約の範囲内で農地の占有者への所有権移転を推進しようという法律の集大成であった<ref name="高橋(1997)99">[[#高橋(1997)|高橋(1997)]] p.99</ref>。これまでのアシュバーン法とバルフォア法が基本的に土地購入代の前貸しのみを定めているのに対して、ウィンダム法は地主と小作人の間で土地売却契約が結ばれやすくなるよう誘導する規定が盛り込まれている<ref name="高橋(1997)106">[[#高橋(1997)|高橋(1997)]] p.106</ref>。 |
|||
この法律によって自作農創出のための機関「土地財産委員会」が設置されることになり、自作農創設の方式も保有地ごとから所領ごとに変更された。さらに地主への支払いを土地債権から現金に戻し、土地債権の価格変動で地主の売却意思が上下するのを鎮めた。2.75%利子付き土地債権は当時額面割れしていたので、これは地主に有利な規定であったといえる<ref>[[#高橋(1997)|高橋(1997)]] p.100-101</ref>。土地財産委員会は2.75%利子付き土地債権を自ら金融市場に流して資金調達して地主への現金支払いを行う<ref name="高橋(1997)103">[[#高橋(1997)|高橋(1997)]] p.103</ref>。 |
|||
さらに法律施行から1908年11月1日までの5年間の特別規定として、地主が土地売却代金を有価証券に再投資した場合は、その地主に12%の「奨励金」を支払うことが規定された。これも地主の売却意欲を高めるための規定であった<ref>[[#高橋(1997)|高橋(1997)]] p.103-104</ref>。小作人一人あたりへの貸付限度は7000ポンドに増額され、小作人は68年6カ月の期間、利子2.75%と償却費0.5%の合わせて3.75%の年賦金を毎年支払うことになるが、この額は当該小作地の小作料の裁定期に応じて減額される。この要件が満たされている場合には土地財産委員は視察を行わないとされており、この視察免除規定も土地売却契約の締結を大いに促した<ref name="高橋(1997)101">[[#高橋(1997)|高橋(1997)]] p.101</ref>。 |
|||
この法律はアイルランド自治を防ぐための融和政策の頂点であったが、結局アイルランド自治運動を沈静化させることはできなかった<ref name="トレヴェリアン(1975)186">[[#トレヴェリアン(1975)|トレヴェリアン(1975)]] p.186</ref><ref name="ブレイク(1979)208">[[#ブレイク(1979)|ブレイク(1979)]] p.208</ref>。それについて{{仮リンク|ロバート・ブレイク (ブレイク男爵)|label=ブレイク男爵|en|Robert Blake, Baron Blake}}は「自由のために戦う民族を経済的な融和政策で抑圧することはできないことの実例である」と評している<ref name="ブレイク(1979)208"/>。 |
|||
{{-}} |
|||
===== 関税改革論争 ===== |
|||
[[File:Joseph Chamberlain in colour.jpg|180px|thumb|バルフォア内閣植民地大臣[[ジョゼフ・チェンバレン]]]] |
|||
第二次ボーア戦争は1902年5月に講和条約が結ばれて正式に終結していたが、予想外の長期戦は予想外の膨大な戦費をもたらし、1900年以降イギリス財政は赤字となっていた。それを補うために各種増税が行われ、その一環で1902年3月に[[財務大臣 (イギリス)|蔵相]]{{仮リンク|マイケル・ヒックス・ビーチ (初代アルドウィン伯爵)|label=マイケル・ヒックス・ビーチ|en|Michael Hicks Beach, 1st Earl St Aldwyn}}は穀物関税再導入を暫定的かつわずかな額でという条件で実施していた<ref name="坂井(1967)205">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.205</ref>。 |
|||
1902年7月に首相ソールズベリー侯爵と蔵相ヒックス・ビーチがそろって辞職し、代わってバルフォア内閣が成立したが、11月の閣議において植民地大臣[[ジョゼフ・チェンバレン]]はビーチの導入した穀物関税を永続化させつつ、{{仮リンク|帝国特恵関税制度|en|Imperial Preference}}を導入して[[大英帝国]]内の関税は安くする事を主張するようになった<ref name="坂井(1967)208">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.208</ref><ref name="池田(1962)153-154">[[#池田(1962)|池田(1962)]] p.153-154</ref><ref name="ブレイク(1979)210">[[#ブレイク(1979)|ブレイク(1979)]] p.210</ref>。つまり大英帝国の結び付きを強化して自給自足経済圏の建設を目指すとともに、帝国外からの関税収入をもって[[均衡財政]]と社会保障費の確保を図ろうという保護貿易主義であり、自由貿易主義や小英国主義とは真っ向から対立する発想だった<ref name="池田(1962)153-154"/><ref name="坂井(1967)208">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.208</ref>。そのため自由貿易主義者の蔵相{{仮リンク|チャールズ・リッチー (初代リッチー・オブ・ダンディー男爵)|label=チャールズ・リッチー|en|Charles Ritchie, 1st Baron Ritchie of Dundee}}はチェンバレンの主張に強く反発した<ref name="坂井(1967)208">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.208</ref>。 |
|||
バルフォアはリッチーよりはチェンバレンに好感を持っていたが<ref name="ブレイク(1979)212">[[#ブレイク(1979)|ブレイク(1979)]] p.212</ref>、それによって政権が分裂する事態だけは回避したいと考えていた<ref name="村岡(1991)231">[[#村岡(1991)|村岡、木畑(1991)]] p.231</ref>。リッチーは穀物関税を廃止しないつもりなら辞職すると脅迫するようになり、それに対してチェンバレンが譲歩したため、バルフォアは1903年3月末にも穀物関税廃止を閣議決定した<ref name="坂井(1967)209">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.209</ref>。 |
|||
しかしチェンバレンは持論を諦めておらず、1903年5月15日にも本拠地の[[バーミンガム]]市で関税改革(帝国外への関税導入と帝国特恵関税制度の導入)を訴えた<ref name="坂井(1967)209">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.209</ref><ref name="ブレイク(1979)212">[[#ブレイク(1979)|ブレイク(1979)]] p.212</ref><ref name="池田(1962)152-153">[[#池田(1962)|池田(1962)]] p.152-153</ref>。この演説以降、関税問題は政界と世論を二分する大論争となった。貧しい庶民はパンの値段が上がることに反対し、保護貿易には反対だった<ref name="坂井(1967)212">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.212</ref>。金融資本家も資本の流動性が悪くなるとして保護貿易には反対し<ref name="池田(1962)156">[[#池田(1962)|池田(1962)]] p.156</ref>、綿工業資本家も自由貿易によって利益をあげていたので保護貿易には反対だった<ref name="坂井(1967)212"/><ref name="河合(1998)79">[[#河合(1998)|河合(1998)]] p.79</ref>。一方、工業資本家(廉価なドイツ工業製品を恐れていた)や地主(伝統的に保護貿易主義)は保護貿易を歓迎し、チェンバレンを支持した<ref name="池田(1962)157">[[#池田(1962)|池田(1962)]] p.157</ref><ref name="坂井(1967)211-212">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.211-212</ref>。 |
|||
閣内ではリッチーの他、枢密院議長{{仮リンク|スペンサー・キャヴェンディッシュ (第8代デヴォンシャー公爵)|label=デヴォンシャー公爵|en|Spencer Cavendish, 8th Duke of Devonshire}}やインド担当相{{仮リンク|ロード・ジョージ・ハミルトン|label=ジョージ・ハミルトン卿|en|Lord George Hamilton}}などがチェンバレンに反対した。若き新米保守党議員[[ウィンストン・チャーチル]]も自由貿易を奉じてチェンバレンに反対している(彼は1904年に自由党へ移籍する)<ref name="坂井(1967)211">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.211</ref>。自由帝国主義派と小英国主義派に分裂していた自由党も自由貿易支持・反チェンバレンの旗のもとに一致団結した<ref name="坂井(1967)211">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.211</ref>。 |
|||
しかし関税は食品価格の上昇をもたらさない報復関税に使用することも可能であり、バルフォアとしてはそれを支持してチェンバレンの主張に一理を認めていた(チェンバレンも食料関税は当面見送るべきと主張していた)<ref name="ブレイク(1979)214">[[#ブレイク(1979)|ブレイク(1979)]] p.214</ref>。バルフォアは両者の妥協点を探って何とか鎮静化させようと努力したが<ref name="村岡(1991)231">[[#村岡(1991)|村岡、木畑(1991)]] p.231</ref>、結局閣内で孤立したチェンバレンは1903年9月21日に植民地大臣を辞した。以降チェンバレンはバルフォアの側面支援を受けながら主要工業都市で関税改革の世論を盛り上げる遊説を開始する<ref name="坂井(1967)214">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.214</ref><ref name="池田(1962)157">[[#池田(1962)|池田(1962)]] p.157</ref><ref name="ブレイク(1979)213">[[#ブレイク(1979)|ブレイク(1979)]] p.213</ref>。 |
|||
バルフォアはバランスを取るために強硬自由貿易主義者の蔵相リッチーも内閣から追放する意思を固めた。1903年10月9日にも「首相に対する陰謀を図った」としてリッチーら自由貿易主義閣僚を解任した。デヴォンシャー公爵については閣内にとどめようとしたが、結局公爵も自由貿易主義者の圧力を受けて辞職することになった。これによってバルフォア内閣の基盤はだいぶ弱くなった<ref>[[#ブレイク(1979)|ブレイク(1979)]] p.213-214</ref>。 |
|||
===== 中国人奴隷問題 ===== |
|||
[[File:Chinese Mine Workers- South Africa.jpg|250px|thumb|南アフリカで働く中国人鉱山労働者たち]] |
|||
英領南アフリカではボーア戦争後の労働力不足を補うため、1904年2月から1906年11月までの間に6万3000人もの中国人が年季契約で[[清|中国本国]]から南アフリカに鉱山労働者として輸送されてきていた。彼らが低賃金で働くせいで現地人の給料も切り下げられていった<ref name="市川(1982)156">[[#市川(1982)|市川(1982)]] p.156</ref>。 |
|||
イギリス本国の労働者層は植民地においてこうした外国人低賃金労働者の輸入を許していれば、いずれイギリス本国でも外国人労働者が輸入されるようになり、自分たちの労働権や給料が脅かされると恐れていた<ref name="ブレイク(1979)206">[[#ブレイク(1979)|ブレイク(1979)]] p.206</ref>。道徳心と信仰心が強い中産階級の非国教徒も「このように大量の人間を船に詰め込み、鉱山で重労働をさせる行為は、イギリスが禁止している[[奴隷貿易]]に該当する」として強く反発した。また送られてくる中国人たちは力仕事向きのマッチョな男性ばかりだから道中の船の中や到着後の居住先である中国人収容所の中で[[同性愛]]をしている可能性が高く、キリスト教の信仰心と照らし合わせても認めるわけにはいかないことだった<ref name="ブレイク(1979)206">[[#ブレイク(1979)|ブレイク(1979)]] p.206</ref>。 |
|||
だがこれを奴隷貿易と同視するのは誇張だった可能性が高い。なにせ中国人にとって南アフリカは中国本国で働くより15倍も高い給料をもらえる場所なのだから、強制したり騙したりするまでもなく、中国人はわらわらと南アフリカに集まってくるのであった<ref name="ブレイク(1979)207">[[#ブレイク(1979)|ブレイク(1979)]] p.207</ref>。バルフォアも[[オーストラリア総督]]ノースコート卿に宛てた手紙の中で「我々の大きな悩みは中国人労働者について正しい説明を行うことができなかったことだ。(自由党は)中国人労働者が奴隷などという馬鹿げた理由で反対しているが、本当は白人労働者が黄色人労働者に置き換えられるという誤った推測が反対の理由だろう」と語っている。確かにそうした面もあったものの、それを主張したところで保守党批判ムードが鎮静化することはなかった<ref>[[#ブレイク(1979)|ブレイク(1979)]] p.207-208</ref>。 |
|||
この件で労働者層の保守党離れは進み、1906年の総選挙での保守党の惨敗を招くことになる<ref name="ブレイク(1979)206">[[#ブレイク(1979)|ブレイク(1979)]] p.206</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
===== 帝国防衛委員会の創設 ===== |
|||
1905年には、大英帝国全体の帝国防衛体制の確立を求めるチェンバレンの主張を取り入れる形で{{仮リンク|帝国防衛委員会|en|Committee of Imperial Defence}}を設置した。これは自治領と帝国防衛体制を検討するための委員会であった(実際に自治領首相に参加を求めるようになったのは[[ハーバート・ヘンリー・アスキス|アスキス]]自由党政権下の1911年になってのことだった)<ref name="坂井(1967)224">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.224</ref>。これと並行して陸海軍の再編成も進めていった<ref name="ブレイク(1979)203">[[#ブレイク(1979)|ブレイク(1979)]] p.203</ref>。 |
|||
ちなみにこの帝国防衛員会は後にアスキス内閣によって「将来起こる戦争に備えて陸海空三軍と国内戦時体制の調整を行い、また自治領とともに帝国全体の防衛計画を立てる機関」に再編されていくことになる<ref name="トレヴェリアン(1975)191">[[#トレヴェリアン(1975)|トレヴェリアン(1975)]] p.191</ref>。 |
|||
[[#toc|【↑目次へ移動する】]] |
|||
==== 外交 ==== |
|||
===== チベット侵攻 ===== |
|||
[[File:Younghusband-team-1904.jpg|250px|thumb|1904年、[[ラサ]]を占領した[[フランシス・ヤングハズバンド]]大佐らイギリス軍将校たち]] |
|||
[[File:Col Younghusband and Amban.JPG|250px|thumb|1904年、清の{{仮リンク|アンバン|zh|駐劄大臣}}(駐ラサ総督)と会見するヤングハズバンド大佐]] |
|||
悲惨な戦争となった第二次ボーア戦争以降、イギリス国民の戦争意欲は弱まり、ヴィクトリア朝時代のような露骨な侵略は減った。最後に行われたヴィクトリア朝的侵略が1903年のチベット侵攻だった<ref name="モリス(2010)上182">[[#モリス(2010)上|モリス(2010)上巻]] p.182</ref>。 |
|||
イギリスは[[19世紀]]からロシアのインド侵略を警戒してきたが、[[20世紀]]に入るとインド北部諸国と外部勢力を国内に入れないという条約を結んで[[ヒマラヤ山脈]]沿いに[[緩衝地帯]]を完成させていた。ところが[[ダライ・ラマ13世]]を国主に戴く[[ガンデンポタン|チベット]]のみがそれに入っておらず、ロシアがチベットに大きな影響力を及ぼしているという噂が流れていた<ref>[[#モリス(2010)上|モリス(2010)上巻]] p.184-185</ref>。 |
|||
中国分割の中で清領[[トルキスタン]]にロシアの鉄道が次々と敷かれていく中、[[インドの総督|インド総督]][[ジョージ・カーゾン (初代カーゾン・オヴ・ケドルストン侯爵)|カーゾン卿]]は、ロシアがチベットを経由してインドに侵攻してくるのを恐れるようになった<ref name="モリス(2010)上184">[[#モリス(2010)上|モリス(2010)上巻]] p.184</ref>。そんな中の1903年春、チベットの[[ラマ僧]]と英領インド北方の国境守備隊将校の間の[[ヤク]]放牧地をめぐる国境争いがこじれて、チベットはイギリスとの通商条約を破棄した。ここに至ってカーゾン卿は、近衛竜騎兵隊の[[フランシス・ヤングハズバンド]]大佐とともに{{仮リンク|イギリスのチベット侵攻|label=チベット侵攻|en|British expedition to Tibet}}を計画するようになった<ref>[[#モリス(2010)上|モリス(2010)上巻]] p.187-190</ref>。 |
|||
本国のバルフォア首相はチベットとの交易に重要性を感じておらず、チベット侵攻には消極的だったが、最終的にはこの動きを承認した<ref name="モリス(2010)上191">[[#モリス(2010)上|モリス(2010)上巻]] p.191</ref>。 |
|||
こうして1903年12月より「使節団」と称するヤングハズバンド大佐率いるイギリス軍部隊がチベット侵攻を開始した。1904年1月には[[トゥナ]]へ入り、そこでラマ僧と交渉したものの、チベット側は「使節団」の即時撤退を要求した。ヤングハズバンドはこれを無視し、3月末には[[ギャンツェ]]へ向けて進軍を再開した。抵抗するチベット人を殺害しながら夏までにはギャンツェを占領。そこで本国の指示を待ってから首都[[ラサ]]へ進軍し、8月にラサに入城した<ref>[[#モリス(2010)上|モリス(2010)上巻]] p.196-203</ref>。 |
|||
バルフォアは「チベットを占領したり、保護領にしてはならない。首都に英国代表を置くことを強要してもいけない。ただし通商条約の締結と賠償金の支払いを求めること、イギリスの了承なしに他の大国と取引しないことを約束させることは差し支えない」という指示を出していたが<ref>[[#モリス(2010)上|モリス(2010)上巻]] p.201-202</ref>、ヤングハズバンドはこの命令に従わず、9月7日には清のアンバン{{#tag:ref|この時代には形骸化していたとはいえ、いまだチベットは形式的には清の宗主権下にあり、清からアンバンと呼ばれる総督が派遣されていた<ref name="モリス(2010)上185">[[#モリス(2010)上|モリス(2010)上巻]] p.185</ref>。|group=注釈}}も同席させた上でチベット側と[[ラサ条約]]を締結し、5万ポンド賠償金支払い(75年払い)とそれが完了するまではイギリスがチュンビ谷全域を占領すること、またギュンツェにイギリス代表を置くことを認めさせた<ref name="モリス(2010)上207">[[#モリス(2010)上|モリス(2010)上巻]] p.207</ref>。 |
|||
バルフォアはこの独断の「外交的勝利」を全く歓迎しなかった。この時代にはイギリス以外の欧米列強も次々と植民地支配に乗り出しており、もはやイギリス一国だけで世界を自由にできる時代ではなかった。他の列強の許可も得ておかねば、強引な条約はたちまちイギリスを孤立に追いやってしまうのである。バルフォアの予想通り、この条約が発表されるやすぐにもロシア、ドイツ、フランス、[[アメリカ]]、[[イタリア王国|イタリア]]の5大国がイギリス外務省に正式な抗議を送ってきた。バルフォアはイギリス包囲網を避けるため、ラサ条約に定められた賠償金額を3分の1に激減させ、さらにチュンビ谷からも1908年までに撤退することを決定した<ref name="モリス(2010)上208">[[#モリス(2010)上|モリス(2010)上巻]] p.208</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
===== フランスとの接近 ===== |
|||
[[File:Marquess of Lansdowne.jpg|180px|thumb|バルフォア内閣外相[[ヘンリー・ペティ=フィッツモーリス (第5代ランズダウン侯爵)|ランズダウン侯爵]]]] |
|||
先に結ばれた日英同盟は「日英どちらかが二か国以上と戦争になった場合はもう片方は同盟国のために参戦、一か国との戦争の場合はもう片方は中立を保つ」という約定になっていたため、バルフォアとしては早急にフランスを取りこんでフランスがロシアとともに日本に宣戦布告するのを阻止する必要があった<ref>[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.307-309</ref>。 |
|||
フランスを取りこむことについてはそれほど難しくなかった。イギリスは植民地問題で長らくフランスと争ってきたが、1898年の[[ファショダ事件]]でフランスが譲歩して以来、両国関係は好転していたからである。またドイツ海軍が[[ヴィルヘルム2世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム2世]]の「世界政策」のもと海軍力の大幅増強を行い、世界各地でイギリスの植民地支配を脅かすようになったことも英仏を結び付ける背景となった<ref>[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.307-308</ref>。外相[[ヘンリー・ペティ=フィッツモーリス (第5代ランズダウン侯爵)|ランズダウン侯爵]]は駐英フランス大使{{仮リンク|ポール・カンボン|fr|Paul Cambon}}を通じて[[テオフィル・デルカッセ]]仏外相と交渉を進め、[[エジプト]]、[[モロッコ]]、[[ナイジェリア]]、[[シャム]]([[タイ]])、[[マダガスカル島]]、[[ニューヘブリディーズ諸島]]、[[ニューファンドランド島]]などの利権・領有権をめぐる英仏の懸案事項を互譲的に解決した。それは最終的に1904年4月8日の[[英仏協商]]の締結で結実した<ref>[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.308-309</ref> |
|||
===== 日露戦争をめぐって ===== |
|||
[[File:Waganghou.jpg|250px|thumb|日本軍騎兵とロシア軍騎兵の戦い]] |
|||
[[File:MIKASAPAINTING.jpg|250px|thumb|[[日本海海戦]]の際の[[三笠 (戦艦)|戦艦「三笠」]]上の[[東郷平八郎]]]] |
|||
前任のソールズベリー侯爵と同様、バルフォアは当初日本の海軍力を高く見積もっており、日本との同盟によって日英の中国における海軍力を露仏のそれより上回らせ、もってロシア帝国主義の拡張を抑止し、中国情勢の現状維持を図ろうと考えていた。そのためには日露の和解も開戦も阻止する必要があった<ref>[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.306-307</ref> |
|||
日英同盟締結後も日本国内にはロシアと協商を結ぼうという動きがあった。これを警戒したバルフォアは1903年7月30日に日本政府に向けて声明を出し、「日本単独でロシアと協商関係を結ぶよりも日英両国でアメリカに働きかけ、日英米三国でロシアに圧力を加え、日本の主張をロシアに認めさせる方が得策である」と忠告した<ref name="坂井(1967)309">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.309</ref>。また外相[[ヘンリー・ペティ=フィッツモーリス (第5代ランズダウン侯爵)|ランズダウン侯爵]]も駐英日本公使[[林董]]に対して「ロシアの満洲撤兵に関する協定が日露間だけで締結されるなら、日英同盟によって具現した日英の協調関係は弱まらざるを得ない。ロシアとの交渉は日英同盟の範囲内で慎重に行ってほしい」と要請した<ref name="坂井(1967)309">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.309</ref>。 |
|||
しかしロシアは満洲から撤兵する姿勢を全く示さなかったため、結局日露関係は1903年後半から一触即発状態となっていった。バルフォアもここに至って日露開戦は必至と判断するようになった<ref name="坂井(1967)309">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.309</ref>。この頃イギリスの軍事専門家の多くは日本の敗戦を予想しており、その影響でバルフォアも日本への期待感を以前より薄め、1903年12月23日の覚書の中では「日本の海軍力はロシアより劣っている。そのため日本は安全に[[大韓帝国|韓国]]へ派兵できないし、また派兵できたとしても海上補給線を切断されるであろう」と書いている<ref name="坂井(1967)310">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.310</ref>。 |
|||
バルフォアは日本がロシア帝国主義の防波堤になりえない(極東の現状維持ができない)なら、日露開戦を阻止する必要はないと考えるようになった。なぜならば、日露戦争が起こればロシアは戦争で国力を消耗させるだろうし、ロシアが勝利したとしても新たに手に入れるのは領土的に無価値な韓国だけであり、また日本も滅亡することはないだろうから、今後ロシアは無価値な領土を日本から守るために大軍隊を常に極東に貼り付かせる必要に迫られ、これがロシアの行動を阻害し、イギリスの行動を有利にすると考えられるからである<ref name="坂井(1967)311">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.311</ref><ref name="君塚(2012)152">[[#君塚(2012)|君塚(2012)]] p.152</ref>{{#tag:ref|一方外相ランズダウン侯爵はこのバルフォアの考えに反対した。彼は日露開戦の場合、ロシアは[[地中海]]の艦隊を投入するだろうから日本の海軍力は完全に粉砕されてしまい、以降日本はロシアにとって何の害もない存在に落ちぶれるであろうと予測していた<ref name="君塚(2012)152">[[#君塚(2012)|君塚(2012)]] p.152</ref>。|group=注釈}}。 |
|||
このバルフォアの戦略転換によって日露開戦を妨げる要素はなくなり、1904年2月には[[日露戦争]]の勃発に至った<ref name="坂井(1967)312">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.312</ref>。しかしバルフォアの予想に反し、[[日本軍]]は善戦し、1905年1月には最大の激戦地の[[旅順]]で[[日本陸軍]]がロシア軍を降伏に追い込んだ。これにはバルフォアも驚いたという<ref>[[#君塚(2012)|君塚(2012)]] p.163-164</ref>。さらに1905年5月から6月にかけての[[日本海海戦]]でも[[日本海軍]]がロシア・[[バルチック艦隊]]を撃破した<ref name="君塚(2012)166">[[#君塚(2012)|君塚(2012)]] p.166</ref>。 |
|||
これを受けてバルフォアも日英同盟延長に前向きとなり、外相ランズダウン侯爵を林公使と折衝に当たらせ、1905年[[8月12日]]にも第二次日英同盟を締結した。その結果、同盟期間は10年に延長され、イギリスは日本が韓国を保護国化することを承認し、日本はイギリスがインドで行う植民地政策を承認することとなった。同盟適用範囲は東南アジアとインドにまで広げられた。さらに先の日英同盟が締結国の片方が二カ国以上と戦争になった場合にもう片方の締結国が参戦する内容だったのに対し、今度の日英同盟は一か国との戦争であってももう片方は参戦しなければならないという強固なものとなった。ここに日英両国は名実ともに同盟国となったのである<ref>[[#君塚(2012)|君塚(2012)]] p.166-167</ref>。 |
|||
戦争終結後の1905年9月29日には日本の君主である[[明治天皇]]にイギリス最高勲章[[ガーター勲章]]を送るべしとする外相ランズダウン侯爵の提言に首相として了解を出し、この提言は10月8日にも国王エドワード7世の裁可を得て、バルフォア退任後の1906年2月に実現することになる<ref>[[#君塚(2012)|君塚(2012)]] p.175-176</ref>。 |
|||
また日本を公使館国から大使館国に昇格させたのも日露戦争中のバルフォアだった。当時のヨーロッパでは大国には大使館、小国には公使館を置くのが伝統だった。特に気位が高いイギリスはこの格付けに拘っていた。20世紀初頭の段階でイギリスが大使館を設置していた国は[[フランス第三共和政|フランス]]、[[ロシア帝国|ロシア]]、[[ドイツ帝国|ドイツ]]、[[オーストリア=ハンガリー帝国|オーストリア]]、[[イタリア王国|イタリア]]、[[オスマン帝国|トルコ]]、[[スペイン]]、[[アメリカ]]の8カ国のみであった。日本はこれに続く形でイギリスから大使館とするに値する国と認められたのであった(これ以降各国も次々とイギリスに倣って日本公使館を大使館に昇格させていった)<ref name="君塚(2012)172">[[#君塚(2012)|君塚(2012)]] p.172</ref>。 |
|||
[[#toc|【↑目次へ移動する】]]{{-}} |
|||
==== 内閣総辞職 ==== |
|||
バルフォアは保守党分裂を阻止するため、関税改革に触れまいとし続けた。だが野党自由党は保守党政権に揺さぶりをかけようと、1905年3月末に関税改革反対決議案を提出してきた。これに対してバルフォアは決議案の内容が不明瞭であることを理由に保守党は棄権するという方針を示した<ref name="坂井(1967)218">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.218</ref>。一方チェンバレンはバルフォアに関税改革を争点にした解散総選挙に打って出るよう要求したが、バルフォアは応じなかった。バルフォアの態度にイライラしたチェンバレンはついに1905年11月からバルフォア批判を開始した<ref name="坂井(1967)218-219">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.218-219</ref>。 |
|||
ここに至ってバルフォアはこれ以上政権に留まれば党分裂は避けがたいと認識するようになった。また自由党内でアイルランド自治問題をめぐって[[アーチボルド・プリムローズ (第5代ローズベリー伯)|ローズベリー伯爵]]ら自由帝国主義派と[[ヘンリー・キャンベル=バナマン|キャンベル=バナマン]]ら小英国主義派の対立が再燃し始めた情勢を見て、今総辞職して自由党に政権を譲れば、世間の注目が関税問題からアイルランド問題に移り、自由党分裂を促すことができると判断した<ref name="坂井(1967)219">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.219</ref>。 |
|||
そうした意図から1905年12月4日付けでバルフォア内閣は総辞職した<ref name="坂井(1967)219">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.219</ref>。 |
|||
[[#toc|【↑目次へ移動する】]] |
|||
=== 野党党首として === |
|||
[[File:Arthur Balfour.jpg|180px|thumb|1909年のバルフォアを描いた[[ジョン・シンガー・サージェント]]の絵画。]] |
|||
==== 1906年総選挙に惨敗 ==== |
|||
首相退任後もバルフォアは5年にわたって保守党党首職に在任した。バルフォアに代わって大命を受けた自由党党首[[ヘンリー・キャンベル=バナマン|キャンベル=バナマン]]は、少数与党の状況を脱するべく、1906年1月にも{{仮リンク|1906年イギリス総選挙|label=解散総選挙|en|United Kingdom general election, 1906}}に打って出た。この選挙の争点はアイルランド問題ではなく、関税問題や中国人奴隷問題となり、保守党と自由統一党は庶民・労働者層の反発を買って苦しい選挙戦を強いられた。結局自由党が377議席に大躍進する一方、改選前に401議席を持っていた保守党・自由統一党は、157議席に激減した<ref>[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.340-342</ref>。党首バルフォア自身もこれまでの{{仮リンク|マンチェスター・イースト選挙区|en|Manchester East (UK Parliament constituency)}}では落選するという屈辱を喫し<ref name="坂井(1967)340">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.340</ref>、{{仮リンク|シティ・オブ・ロンドン選挙区|en|City of London (UK Parliament constituency)}}に転じて再選を果たしている<ref name="HANSARD"/>。 |
|||
この惨敗っぷりは保守党の歴史にかつてないものだった(これまでの保守党の最低記録は1832年総選挙の際の185議席)<ref name="ブレイク(1979)218">[[#ブレイク(1979)|ブレイク(1979)]] p.218</ref>。しかも当選した157人のうち、109人の議員は関税改革論者だったため、保守党は惨敗に懲りずに保護貿易主義に傾いていくことになった。バルフォアもそれまでの折衷主義を弱めて関税改革路線に傾いていった<ref name="ブレイク(1979)215">[[#ブレイク(1979)|ブレイク(1979)]] p.215</ref>。 |
|||
==== 貴族院を使って反政府闘争 ==== |
|||
[[ジョゼフ・チェンバレン]]が病に倒れたせいもあって彼の党内における力は強化されていたが、[[庶民院]]において[[自由党 (イギリス)|自由党]]が圧倒的多数を占めていたためできることは限られていた。このためバルフォアは{{仮リンク|保守党貴族院院内総務|en|Leaders of the Conservative Party#Leaders in the House of Lords 1834–present}}の[[ヘンリー・ペティ=フィッツモーリス (第5代ランズダウン侯爵)|ランズダウン侯爵]]と協力し、[[貴族院 (イギリス)|貴族院]]議員を使って自由党の政策や法案に抵抗するようになった<ref name="坂井(1967)416-417">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.416-417</ref>。 |
|||
早くも1906年4月には初等教育から宗教教育を排除することを目的とした「教育法案」を貴族院で葬った。これに反発した首相キャンベル=バナマンや急進派閣僚の{{仮リンク|ビジネス・イノベーション・職業技能大臣|label=通商大臣|en|President of the Board of Trade}}[[デビッド・ロイド・ジョージ|ロイド・ジョージ]]は貴族院改革の意を強めた<ref name="坂井(1967)416">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.416</ref>。キャンベル=バナマンは1907年6月にも庶民院の優越を定める法律を制定すべきとする決議案を議会に提出し、その決議案説明の中でロイド・ジョージは「貴族院は長きにわたり、憲法の番犬だったが、今やバルフォアの[[プードル]]である。彼のために吠え、使い走りをし、彼がけしかけたどのような物にも噛みつく」と怒りを露わにした<ref name="坂井(1967)416-417"/>。 |
|||
だがバルフォアは態度を翻すことはなく、首相が[[ハーバート・ヘンリー・アスキス|アスキス]]に変わった後の1908年7月にも醸造業者の独占制限を目的とする「酒類販売免許法案」を貴族院で否決させた<ref name="坂井(1967)417">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.417</ref>。この際に急進派閣僚の通商大臣[[ウィンストン・チャーチル]]は「我々は貴族院を震え上がらせるような予算案を提出するであろう。貴族院は階級闘争を開始したのだから」と語ったという<ref name="坂井(1967)417">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.417</ref>。 |
|||
==== 「人民予算」をめぐって ==== |
|||
[[File:Arthur Balfour Vanity Fair 27 January 1910.jpg|180px|thumb|1910年1月27日の『{{仮リンク|ヴァニティ・フェアー (イギリス雑誌)|label=ヴァニティ・フェアー|en|Vanity Fair (British magazine)}}』誌のバルフォアの戯画。]] |
|||
大蔵大臣ロイド・ジョージは保守党の支持基盤である地主・土地貴族に打撃を与えるべく、「[[人民予算]]」({{interlang|en|People's Budget}})と呼ばれることになる予算案の作成を開始した<ref>[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.417-418</ref>。 |
|||
この「人民予算」に含まれる土地課税は「土地の国有化を企むものである」と地主・土地貴族が強く反発した。彼らの声を代弁するバルフォアら保守党政治家も当然この予算案に強く反対し、、「赤旗の予算(The Red Flag Budget)」と批判した<ref name="坂井(1967)420">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.420</ref>。自由党内のホイッグ派(土地貴族が多い)も保守党と声を合わせるようになったため、結局土地課税についてはロイド・ジョージ自身が骨抜き修正している<ref>[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.420-421</ref>。それにも関わらず、「人民予算」は1909年11月に庶民院の[[読会制|第三読会]]を通過した後、貴族院から激しい反発にあった。彼らはなおも土地の国有化につながる法案と信じていた。バルフォアも11月28日に「貴族院は法案を否決すべきである」と演説した<ref>[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.427-428</ref>{{#tag:ref|これについて[[ジョージ・カーゾン (初代カーゾン・オヴ・ケドルストン侯爵)|カーゾン卿]]は「バルフォアが人民予算を葬ろうとした理由は二つある。一つは貴族院がその予算案を可決すれば、この国の憲法を実施・運営する場合の大きな変化を初めてもたらすことになること、もう一つは本予算案を否決することは関税改革の擁護に結び付くからである。つまり本法案が否決されれば本予算で見積もられた財源を他から求めざるを得なくなり、その新しい財源として関税が浮上してくるからである」と分析している<ref name="坂井(1967)428">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.428</ref>。|group=注釈}}。 |
|||
11月30日に貴族院は賛成75、反対350という圧倒的大差で「人民予算」を否決した<ref name="坂井(1967)428">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.428</ref>。貴族院が金銭法案を否決するのは[[17世紀]]以来のことだった<ref name="河合(1998)118">[[#河合(1998)|河合(1998)]] p.118</ref>。これを受けてアスキス首相は庶民院を解散し、総選挙に打って出た<ref name="坂井(1967)428">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.428</ref>。1910年1月の{{仮リンク|1910年1月イギリス総選挙|label=解散総選挙|en|United Kingdom general election, January 1910}}でバルフォアは「貴族院の権限縮小反対」「関税改革」「海軍拡張」の3つを保守党の公約に掲げた<ref name="坂井(1967)429">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.429</ref>。このうち関税改革は「関税改革が失業を減少させる」というスローガンとセットにして行った。これは労働者層の支持を取り戻すのにかなり役立ったと見られている<ref name="坂井(1967)431">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.431</ref>。選挙の結果は自由党275議席、保守党273議席、{{仮リンク|アイルランド国民党|en|Irish Parliamentary Party}}82議席、[[労働党 (イギリス)|労働党]]40議席となった。前回比で自由党は104議席も減らし、保守党はかなり失地回復を果たした<ref name="坂井(1967)434">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.434</ref>。 |
|||
だが[[キャスティング・ボート]]を握ったアイルランド国民党が「人民予算」を支持したため、自由党政権は引き続き「人民予算」の可決成立を目指した。バルフォアの「人民予算」に対する態度が依然として強硬と見たアスキス首相は1910年2月に貴族院の権限を縮小する貴族院改革法案([[議会法]])を一緒に提出した。これを警戒したバルフォアは1910年4月に「人民予算」を採決なしで貴族院を通過させる妥協姿勢をとった<ref>[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.447-448</ref>。 |
|||
==== 貴族院改革をめぐって ==== |
|||
1910年5月6日のエドワード7世の崩御、新王ジョージ5世の即位に伴う自由党と保守党の融和ムードの中で両党の会合が持たれた<ref>[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.448-449</ref>。この際にロイド・ジョージはバルフォアに連立内閣を提唱してきた。バルフォアはこれに前向きだったが、自由党政権はアイルランド国民党との連携のためにアイルランド自治法案を出してくる可能性が高かったので、もし大連立など組んだら保守党は分裂するという意見が党内には多かった。1910年11月までには両党の交渉は決裂に終わった<ref name="坂井(1967)452">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.452</ref>。 |
|||
この決裂で貴族院改革法案を目指すことにしたアスキス首相は、ジョージ5世から「総選挙を行って勝利した場合には貴族院改革法案に賛成する新貴族議員を大量に任命する」という確約を得て、11月26日にもこの年二度目の庶民院解散に打って出た。こうして行われた12月の{{仮リンク|1910年12月イギリス総選挙|label=総選挙|en|United Kingdom general election, December 1910}}の結果は自由党272議席、統一党272議席、アイルランド国民党84議席、労働党42議席と前回総選挙とほとんど変わらないものだった<ref name="坂井(1967)455">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.455</ref>。得票率で見ると保守党は自由党に優っていた<ref name="村岡(1991)241">[[#村岡(1991)|村岡、木畑(1991)]] p.241</ref>。 |
|||
しかしアスキス首相は[[1911年]][[2月21日]]の新議会で自党と友党アイルランド国民党があわせて過半数を制したので貴族院改革の国民のコンセンサスは得たと力説し、[[議会法]]を再度議会に提出してきた<ref name="坂井(1967)455">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.455</ref>。法案は5月15日に庶民院を通過したが、貴族院は断固反対の姿勢を示した。これを見たアスキス首相は、もし貴族院がこの法案を通過させないなら国王大権によって貴族院改革に賛成する新貴族院議員を大量に任命する方針とそれについて国王の承諾を得ている旨を7月20日にバルフォアら保守党執行部に付きつけた<ref name="坂井(1967)456">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.456</ref>。 |
|||
これを受けてバルフォアは7月21日にもシャドー・キャビネット([[影の内閣]])に所属する保守党幹部を召集して対策を話し合った。バルフォアやランズダウン侯爵、カーゾン卿は「貴族の大量任命など行われたら世界中の文明国の笑い物になる」として譲歩するしかないと主張したが、{{仮リンク|ハーディング・ギフォード (初代ハルズベリー伯爵)|label=ハルズベリー卿|en|Hardinge Giffard, 1st Earl of Halsbury}}や{{仮リンク|ウィリアム・パルマー (第2代セルボーン伯爵)|label=セルボーン卿|en|William Palmer, 2nd Earl of Selborne}}、[[オースティン・チェンバレン]]らは徹底抗戦すべしと主張して意見は分かれた<ref name="坂井(1967)457">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.457</ref>。だがやがて主戦派の意見が強まり、妥協派のバルフォアは焦った<ref name="坂井(1967)458">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.458</ref>。 |
|||
しかもアスキス内閣は新貴族院任命の方針を覆す意思を見せず、8月10日には議会法案の貴族院提出を強行し、その法案説明で「議会法を否決する投票は、すなわち多数の新貴族任命への賛成票ということになる」と明言してきた。バルフォアの息のかかった妥協派貴族院議員たちは当初棄権を考えていたが、棄権すると議会法案否決の公算が高いため、ついにこの法案賛成に回る決意を固めた。これにより議会法案は賛成131、反対114の僅差でなんとか貴族院を通過した<ref>[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.459-460</ref>。 |
|||
これにより貴族院の権限は大幅に縮小され、さらに貴族院議員の新規叙任が制限されることになった。この結果に党内から不満が噴出し、党の分裂は深刻化した。バルフォアの指導力に疑問が呈されるようになり、それを収拾するため、1911年11月8日にバルフォアは健康上の理由として保守党党首職を辞した<ref name="ブレイク(1979)229">[[#ブレイク(1979)|ブレイク(1979)]] p.229</ref><ref name="坂井(1967)497">[[#坂井(1967)|坂井(1967)]] p.497</ref>。後任の保守党党首は決まっていなかったが、最終的には関税改革派・親[[アルスター]]派の論客として名を馳せていた[[アンドルー・ボナー・ロー]]が選出された<ref>[[#ブレイク(1979)|ブレイク(1979)]] p.230-231</ref><ref name="坂井(1967)497"/>。 |
|||
{{-}} |
|||
[[#toc|【↑目次へ移動する】]] |
|||
=== 党首退任後 === |
|||
[[File:Gws balfour 01.jpg|180px|thumb|年老いたバルフォアの写真]] |
|||
しかしながらバルフォアが党内における重鎮であることには変わりなかった。[[1915年]]5月に[[ハーバート・ヘンリー・アスキス]]首相が保守党・自由党の大連立による[[挙国一致内閣]]の{{仮リンク|第2次アスキス内閣|en|United Kingdom coalition government (1915–1916)}}を組閣すると、[[ガリポリの戦い]]で失態を犯した[[ウィンストン・チャーチル]]の後任として[[海軍大臣 (イギリス)|海軍大臣]]となった<ref name="河合(1998)159">[[#河合(1998)|河合(1998)]] p.159</ref>。 |
|||
[[1916年]]に第2次アスキス内閣が倒れた後に成立した[[ロイド・ジョージ内閣]]でも彼は[[エドワード・グレイ]]の後任の[[外務・英連邦大臣|外務大臣]]に任命された。外務大臣としてのバルフォアは[[ウォルター・ロスチャイルド]]に対して[[パレスチナ]]における[[ユダヤ人]]国家建設への援助を約束する書簡を送った([[バルフォア宣言]])ことで最も知られている<ref name="平賀(2012)178-179">[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.178-179</ref>。 |
|||
[[1919年]]の[[パリ講和会議]]にも出席し、10人会議のメンバーの一人となった<ref name="世界伝記大事典(1981,8)28"/>。この会議の結果[[ヴェルサイユ条約]]が調印されるとバルフォアは外務大臣を辞任したが、その後の平時内閣においても[[枢密院議長 (イギリス)|枢密院議長]]として閣僚に留まった。また[[1921年]]から[[1922年]]の[[ワシントン会議 (1922年)|ワシントン会議]]には[[イギリス]]代表として出席している<ref name="世界伝記大事典(1981,8)28"/>。 |
|||
[[1922年]]にロイド・ジョージ内閣が総辞職すると、バルフォアは保守党内の職も辞した。またこの年の5月5日に{{仮リンク|バルフォア伯爵|en|Earl of Balfour}}、トラップレイン子爵(Viscount Traprain)に叙され貴族院に列した<ref name="HANSARD"/>。[[1923年]]に[[アンドルー・ボナー・ロー]]の後任として首相に任命された[[スタンリー・ボールドウィン]]はバルフォアに対して入閣の意思を尋ねたが彼は断った。しかし[[1925年]]に彼は前年に死去した初代ケドルストンのカーゾン侯爵[[ジョージ・カーゾン (初代カーゾン・オヴ・ケドルストン侯爵)|ジョージ・カーゾン]]の後任として再び枢密院議長となった。 |
|||
バルフォアは1929年に政界引退したが<ref name="世界伝記大事典(1981,8)28"/>、その翌年の[[1930年]][[3月19日]]に[[サリー (イングランド)|サリー]]州{{仮リンク|ウォーキング (イングランド)|en|Woking|label=ウォーキング}}にある弟の住居で死去した<ref name="平賀(2012)185">[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.185</ref>。故郷の[[ウィッティングハム]]に葬られた。生涯独身であったため、爵位は弟ジェラルドに継承された。 |
|||
{{-}} |
|||
[[#toc|【↑目次へ移動する】]] |
|||
== 人物・評価 == |
|||
[[File:Anthony wilding and arthur balfour, nice, 1914.jpg|180px|thumb|1914年、テニス選手[[アンソニー・ワイルディング]]とテニスをするバルフォア(右)]] |
|||
身長6フィート(1.82cm)以上の長身であり、髪の色は褐色、眼の色はブルーだった<ref name="タックマン(1990)56">[[#タックマン(1990)|タックマン(1990)]] p.56</ref>。 |
|||
大変なインテリで読書家だった<ref name="平賀(2012)179">[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.179</ref>。哲学書と神学書を中心に、探偵小説や科学書、フランスの小説もよく読んだ。しかし新聞は読もうとしなかったという<ref>[[#タックマン(1990)|タックマン(1990)]] p.65-66</ref>。 |
|||
スポーツマンでもあり、[[テニス]]、[[サイクリング]]、[[ゴルフ]]などに熱中していた<ref name="平賀(2012)174">[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.174</ref><ref name="タックマン(1990)65">[[#タックマン(1990)|タックマン(1990)]] p.65</ref>。とりわけゴルフの腕前は高く、1894年には[[ロイヤル・アンド・エンシェント・ゴルフ・クラブ・オブ・セント・アンドリュース]]のキャプテンとなった<ref name="夏坂(1997)24">[[#夏坂(1997)|夏坂(1997)]] p.24</ref>。[[ハンデキャップ|ハンディ]]は5の腕前であったという<ref name="夏坂(1997)23">[[#夏坂(1997)|夏坂(1997)]] p.23</ref><ref name="平賀(2012)174"/>。バルフォアはゴルフについて次のように語っている。「筋肉と頭脳がかくも融合されたゲームは他にない。私にとって重要なものは食事、睡眠、ゴルフである」<ref name="夏坂(1997)23">[[#夏坂(1997)|夏坂(1997)]] p.23</ref>、「紳士はゴルフをする。例えはじめた時には貴方が紳士でないとしても、この厳しいゲームをやっていれば必ずや紳士となるであろう」<ref name="平賀(2012)174">[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.174</ref>、「ゴルフは三回楽しめるスポーツである。すなわちコースへ行く前、プレイ中、プレイ後である。その内容は期待、絶望、後悔と変化するが」<ref name="平賀(2012)174"/>。首相たる彼があまりにゴルフに熱中するので社交界もつられてゴルフに熱中するようになり、「スコットランド式[[クローケー]]」などとバカにされていたゴルフの名声が高まっていったという<ref name="タックマン(1990)65">[[#タックマン(1990)|タックマン(1990)]] p.65</ref>。 |
|||
紳士的な礼儀正しい人だったという<ref name="ブレイク(1979)203">[[#ブレイク(1979)|ブレイク(1979)]] p.203</ref>。容姿端麗で家柄や財産も申し分ないから、当然女性にもてたし、結婚のチャンスも数多くあったが、ついに結婚しなかった。バルフォアは学生時代にグラッドストンの姪にあたる女性と婚約していたが、その女性は若くして死去しており、これを引きずって結婚を避けているのではと噂されていた<ref name="平賀(2012)173">[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.173</ref><ref name="タックマン(1990)58">[[#タックマン(1990)|タックマン(1990)]] p.58</ref>。保守党の政治家ながら1900年代以降に盛り上がってきた婦人参政権獲得運動には割と好意的な立場をとっていた。これに対してバルフォアの後任の保守党党首[[アンドルー・ボナー・ロー]]は慎重派だった<ref name="村岡(1991)247">[[#村岡(1991)|村岡、木畑(1991)]] p.247</ref>。 |
|||
政敵の自由党党首[[ウィリアム・グラッドストン]]によればバルフォアは叔父の[[ロバート・ガスコイン=セシル (第3代ソールズベリー侯)|ソールズベリー侯爵]]と気質がよく似ており、違いは「大胆さの面で甥が若干勝る。知能と辛辣さは叔父が若干勝る」ことだという<ref name="神川(2011)412">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.412</ref>。 |
|||
同じく政敵の自由党議員[[ウィンストン・チャーチル]]は、バルフォアについて危機を前にしても動じない性格に注目し、「バルフォアは現在もっとも勇気のある男だ。たとえ鼻先にピストルを付きつけられてもうろたえまい」と称賛しつつ、「バルフォアがびくつかないのは冷酷さのせいだ」とも述べている<ref name="タックマン(1990)63-64">[[#タックマン(1990)|タックマン(1990)]] p.63-64</ref>。自由党の首相[[ハーバート・ヘンリー・アスキス|アスキス]]夫人{{仮リンク|マーゴット・アスキス (オックスフォード及びアスキス伯爵夫人)|label=マーゴット|en|Margot Asquith, Countess of Oxford and Asquith}}はバルフォアが決して動じない理由について「問題を真剣には気にかけていないか、事がどっちへ進もうが、それに人類の幸福がかかっているとは信じていないかのどちらかであろう」と主張している<ref name="タックマン(1990)62">[[#タックマン(1990)|タックマン(1990)]] p.62</ref>。 |
|||
エドワード7世はバルフォアに好意を持たなかったが、[[ヴィクトリア (イギリス女王)|ヴィクトリア女王]]からは高く評価されていた。女王は「彼は問題のあらゆる側面を見ることができ、他の人々に対する感情において素晴らしく寛大である」と述べている<ref name="タックマン(1990)66">[[#タックマン(1990)|タックマン(1990)]] p.66</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
[[#toc|【↑目次へ移動する】]] |
|||
== 哲学者としてのバルフォア == |
|||
バルフォアは[[1879年]]に初めての著書『哲学的懐疑の擁護(Defence of Philosophic Doubt)』を出版した<ref name="世界伝記大事典(1981,8)27"/>。この著作のタイトルのためにバルフォアは[[不可知論]]の擁護者であるという評判が広まったが、実際にはこの著作は物質的実在への疑念を主張することで宗教を擁護したものだった<ref name="タックマン(1990)58">[[#タックマン(1990)|タックマン(1990)]] p.58</ref>。バルフォアの哲学への主たる関心は信仰の基盤を現代社会の中に発見することにあり、そのため[[自然主義]]に反発し、人は科学に対してそうであるように宗教に対しても疑念を持ってはならないと考えた<ref name="世界伝記大事典(1981,8)27"/>。この立場は1895年の主著『信仰の基礎』でも踏襲されている<ref name="タックマン(1990)58"/>。この著作はアマチュアのレベルを超えて学術レベルに達していると高く評価されている<ref name="平賀(2012)172">[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.172</ref>。 |
|||
こうした哲学や宗教への深い関心から『[[旧約聖書]]』の[[ヘブライズム]]に惹かれ、「キリスト教は計り知れないほど数多くの物をユダヤ教に負っているのに、恥ずかしいことにほとんどお返しができていない」と考えていた。それが[[シオニズム]]への共感とバルフォア宣言の背景になったといわれる<ref name="平賀(2012)178">[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.178</ref><ref name="タックマン(1990)59">[[#タックマン(1990)|タックマン(1990)]] p.59</ref>。 |
|||
バルフォアの哲学に関する著作には以下のような物がある。 |
|||
* [http://archive.org/details/adefenceofphilos00balfuoft 哲学的懐疑の擁護(Defence of Philosophic Doubt)] ([[1879年]]) |
|||
* [http://archive.org/details/essaysandaddress00balfuoft 評論と演説(Essays and Addresses)] ([[1893年]]) |
|||
* [http://archive.org/details/foundationsofbib028110mbp 信仰の基盤(The Foundations of Belief)] ([[1895年]]) |
|||
* [http://archive.org/details/criticismandbeau00balfuoft 美しさと批判の探究心(Questionings on Criticism and Beauty)] ([[1909年]]) |
|||
* [http://archive.org/details/aspectsofhomerul00balf 内政の側面(Aspects of Home Rule)] ([[1913年]]) |
|||
* [http://archive.org/details/theismandhumanis00balfuoft 有神論とヒューマニズム(Theism and Humanism)] ([[1915年]]) |
|||
* [http://archive.org/details/essaysspeculativ00balfiala 思索的及び政治的評論(Essays Speculative and Political)] ([[1921年]]) |
|||
* [http://www.giffordlectures.org/Author.asp?AuthorID=12 有神論と思想(Theism and Thought)] ([[1923年]]) |
|||
{{-}} |
|||
[[#toc|【↑目次へ移動する】]] |
|||
== シャーロック・ホームズとバルフォア == |
|||
小説家[[コナン・ドイル]]が生み出した名探偵[[シャーロック・ホームズ]]が活躍した時代は、主にソールズベリー侯爵内閣期だが、続くバルフォア内閣期の1903年にも多くの事件を手がけたという設定になっている(同時にこの年にホームズは引退する)<ref name="平賀(2012)152">[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.152</ref>。 |
|||
『[[マザリンの宝石]]』(『[[シャーロック・ホームズの事件簿]]』収録)の依頼人は英国首相であるが、これは1903年の事件と言われており、それが正しければ依頼人の首相というのはバルフォアということになる。作中でビリー少年は首相のことを「付き合いやすそうな人」と評している<ref>[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.152/175</ref>。 |
|||
同じく『[[海軍条約文書事件]]』(『[[シャーロック・ホームズの思い出]]』収録)に登場する外務大臣ホールドハースト卿はソールズベリー侯の変名と言われており(ホームズ小説は[[ジョン・H・ワトスン|ワトスン]]の著作という形式をとっているため、ワトスンが当人に配慮して変名にしていると考える余地がある)、そうだとすれば、その甥という設定で登場する依頼人パーシー・フェルプスはバルフォアの変名である可能性が高い<ref>[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.182-183</ref>。作中でフェルプスの住居はウォーキングに設定されていたが、ここはバルフォアの弟の住居がある場所であり、バルフォアの最期の地でもある<ref name="平賀(2012)185">[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.185</ref>。 |
|||
{{-}} |
|||
[[#toc|【↑目次へ移動する】]] |
|||
== 脚注 == |
|||
{{脚注ヘルプ}} |
|||
=== 注釈 === |
|||
{{reflist|group=注釈|1}} |
|||
=== 出典 === |
|||
<div class="references-small"><!-- references/ -->{{reflist|2}}</div> |
|||
== 参考文献 == |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[池田清 (政治学者)|池田清]]|date=1962年(昭和37年)|title=政治家の未来像 ジョセフ・チェムバレンとケア・ハーディー|publisher=[[有斐閣]]|asin=B000JAKFJW|ref=池田(1962)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[市川承八郎]]|date=1982年(昭和57年)|title=イギリス帝国主義と南アフリカ|publisher=[[晃洋書房]]|asin=B000J7OZW8|ref=市川(1982)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[神川信彦]]|editor=[[君塚直隆]]監修|date=2011年(平成13年)|title=グラッドストン 政治における使命感|publisher=[[吉田書店]]|isbn=978-4905497028|ref=神川(2011)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[河合秀和]]|date=1998年(平成10年)|title=チャーチル イギリス現代史を転換させた一人の政治家 増補版|series= [[中公新書]]530|publisher=[[中央公論社]]|isbn=978-4121905307|ref=河合(1998)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[君塚直隆]]|date=2012年(平成24年)|title=ベル・エポックの国際政治 エドワード七世と古典外交の時代|publisher=[[中央公論新社]]|isbn=978-4120044298|ref=君塚(2012)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[小関隆]]|date=2006年(平成18年)|title=プリムローズ・リーグの時代 世紀転換期イギリスの保守主義|publisher=[[岩波書店]]|isbn=978-4000246330|ref=小関(2006)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[坂井秀夫]]|date=1967年(昭和42年)|title=政治指導の歴史的研究 近代イギリスを中心として|publisher=[[創文社]]|asin=B000JA626W|ref=坂井(1967)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[高橋純一]]|date=1997年(平成9年)|title=アイルランド土地政策史|publisher=[[社会評論社]]|isbn=978-4784508587|ref=高橋(1997)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[バーバラ・タックマン]]|translator=[[大島かおり]]|date=1990年(平成2年)|title=世紀末のヨーロッパ 誇り高き塔・第一次大戦前夜|publisher=[[筑摩書房]]|isbn=978-4480855541|ref=タックマン(1990)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author={{仮リンク|ジョージ・マコーリー・トレヴェリアン|label=G.M.トレヴェリアン|en|G. M. Trevelyan}}|translator=[[大野真弓]]|date=1975年(昭和50年)|title=イギリス史 3|publisher=[[みすず書房]]|isbn=978-4622020370|ref=トレヴェリアン(1975)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[夏坂健]]|date=1997年(平成9年)|title=騎士たちの一番ホール 不滅のゴルフ名言集|publisher=[[日本ヴォーグ&スポーツマガジン社]]|isbn=978-4529028110|ref=夏坂(1997)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author=[[平賀三郎]]|date=2012年(平成24年)|title=ホームズの不思議な世界|publisher=[[青弓社]]|isbn=978-4787292094|ref=平賀(2012)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author={{仮リンク|ロバート・ブレイク (ブレイク男爵)|label=ブレイク男爵|en|Robert Blake, Baron Blake}}|translator=[[早川崇]]|date=1979年(昭和54年)|title=英国保守党史 ピールからチャーチルまで|publisher=[[労働法令協会]]|asin=B000J73JSE|ref=ブレイク(1979)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author={{仮リンク|ロバート・マッケンジー|en|Robert McKenzie (psephologist)}}|translator=[[早川崇]]、[[三沢潤生]]|date=1965年(昭和40年)|title=英国の政党〈上巻〉 保守党・労働党内の権力配置|publisher=有斐閣|asin=B000JAD4LI|ref=マッケンジー(1965)}} |
|||
*{{Cite book|和書|author={{仮リンク|ジャン・モリス|en|Jan Morris}}|translator=[[椋田直子]]|date=2010年(平成22年)|title=帝国の落日 上巻|publisher=[[講談社]]|isbn=978-4062152471|ref=モリス(2010)上}} |
|||
*{{Cite book|和書|date=1981年(昭和56年)|title=世界伝記大事典〈世界編 8〉ハルーフユ|publisher=[[ほるぷ出版]]|asin=B000J7VF5S|ref=世界伝記大事典(1981,8)}} |
|||
*{{Cite book|和書|date=2001年(平成13年)|title=世界諸国の組織・制度・人事 1840―2000|editor=[[秦郁彦]]編|publisher=[[東京大学出版会]]|isbn=978-4130301220|ref=秦(2001)}} |
|||
== 外部リンク == |
== 外部リンク == |
||
{{ |
{{Commonscat|Arthur Balfour, 1st Earl of Balfour}} |
||
* {{Hansard-contribs | mr-arthur-balfour | Arthur Balfour }} {{en icon}} |
* {{Hansard-contribs | mr-arthur-balfour | Mr Arthur Balfour }} {{en icon}} |
||
* {{NRA|P1330}} {{en icon}} |
* {{NRA|P1330}} {{en icon}} |
||
* [http://www.npg.org.uk/collections/search/person/mp00227/ Arthur James Balfour, 1st Earl of Balfour] - ''[[ナショナル・ポートレート・ギャラリー]]'' {{en icon}} |
* [http://www.npg.org.uk/collections/search/person/mp00227/ Arthur James Balfour, 1st Earl of Balfour] - ''[[ナショナル・ポートレート・ギャラリー]]'' {{en icon}} |
||
* {{Find A Grave|11435|name=Arthur James Balfour}} |
|||
{{S-start}} |
|||
{{s-off}} |
|||
{{Succession box| title = {{flagicon|UK}} {{仮リンク|枢密院議長 (イギリス)|label=枢密院議長|en|Lord President of the Council}}| years = [[1925年]]-[[1929年]]| before=[[ジョージ・カーゾン (初代カーゾン・オヴ・ケドルストン侯爵)|カーゾン・オヴ・ケドルストン侯爵]]| after={{仮リンク|チャールズ・クリップス (初代パーモア男爵)|label=パーモア卿|en|Charles Cripps, 1st Baron Parmoor}}}} |
|||
{{Succession box| title = {{flagicon|UK}} {{仮リンク|枢密院議長 (イギリス)|label=枢密院議長|en|Lord President of the Council}}| years = [[1919年]]-[[1922年]]| before=[[ジョージ・カーゾン (初代カーゾン・オヴ・ケドルストン侯爵)|カーゾン・オヴ・ケドルストン伯爵]]| after=[[ジェイムズ・ガスコイン=セシル (第4代ソールズベリー侯爵)|第4代ソールズベリー侯爵]]}} |
|||
{{Succession box| title = {{flagicon|UK}} [[外務・英連邦大臣|外務大臣]]| years = [[1916年]]-[[1919年]]|before=[[エドワード・グレイ|グレイ・オブ・ファラドン子爵]]| after=[[ジョージ・カーゾン (初代カーゾン・オヴ・ケドルストン侯爵)|カーゾン・オヴ・ケドルストン伯爵]]}} |
|||
{{Succession box| title = {{flagicon|UK}} {{仮リンク|海軍大臣 (イギリス)|label=海軍大臣|en|First Lord of the Admiralty}}| years = [[1915年]]-[[1916年]]| before=[[ウィンストン・チャーチル]]| after={{仮リンク|エドワード・カーゾン (カーゾン男爵)|label=サー・エドワード・カーゾン|en|Edward Carson, Baron Carson}}}} |
|||
{{s-bef|rows=2|before=[[ロバート・ガスコイン=セシル (第3代ソールズベリー侯爵)|第3代ソールズベリー侯爵]]}} |
|||
{{s-ttl|title={{flagicon|UK}} [[イギリスの首相|首相]]|years=[[1902年]]–[[1905年]]}} |
|||
{{s-aft|after=[[ヘンリー・キャンベル=バナマン|サー・ヘンリー・キャンベル=バナマン]]}} |
|||
{{s-ttl|title={{flagicon|UK}} [[王璽尚書]]|years=[[1902年]]–[[1903年]]}} |
|||
{{s-aft|after=[[ジェイムズ・ガスコイン=セシル (第4代ソールズベリー侯爵)|第4代ソールズベリー侯爵]]}} |
|||
{{s-bef|before=[[アーチボルド・プリムローズ (第5代ローズベリー伯)|第5代ローズベリー伯爵]]}} |
|||
{{s-ttl|title={{flagicon|UK}} [[第一大蔵卿]]|years=[[1895年]]–[[1905年]]}} |
|||
{{s-aft|rows=2|after=[[ヘンリー・キャンベル=バナマン|サー・ヘンリー・キャンベル=バナマン]]}} |
|||
{{s-bef|before={{仮リンク|ウィリアム・ヴァーノン・ハーコート|label=サー・ウィリアム・ヴァーノン・ハーコート|en|William Vernon Harcourt (politician)}}}} |
|||
{{s-ttl|title={{flagicon|UK}} [[庶民院院内総務]]|years=[[1895年]]–[[1905年]]}} |
|||
{{s-bef|rows=2|before={{仮リンク|ウィリアム・ヘンリー・スミス (政治家)|en|William Henry Smith (1825–1891)|label=ウィリアム・ヘンリー・スミス}}}} |
|||
{{s-ttl|title={{flagicon|UK}} [[第一大蔵卿]]|years=[[1891年]]–[[1892年]]}} |
|||
{{s-aft|rows=2|after=[[ウィリアム・グラッドストン]]}} |
|||
{{s-ttl|title={{flagicon|UK}} [[庶民院院内総務]]|years=[[1891年]]–[[1892年]]}} |
|||
{{Succession box| title = {{flagicon|UK}} {{仮リンク|アイルランド担当大臣|en|Chief Secretary for Ireland}}| years = [[1887年]]-[[1891年]]|before={{仮リンク|マイケル・ヒックス・ビーチ (初代セント・アルドウィン伯爵)|label=サー・マイケル・ヒックス・ビーチ|en|Michael Hicks Beach, 1st Earl St Aldwyn}}| after={{仮リンク|ウィリアム・ジャクソン (初代アラートン男爵)|label=ウィリアム・ジャクソン|en|William Jackson, 1st Baron Allerton}}}} |
|||
{{Succession box| title = {{flagicon|UK}} [[スコットランド担当大臣]]| years = [[1886年]]-[[1887年]]|before={{仮リンク|ジョン・ラムゼイ (第13代ダルフージー伯爵)|label=第13代ダルフージー伯爵|en|John Ramsay, 13th Earl of Dalhousie}}| after={{仮リンク|ションバーグ・カー (第9代ロジアン侯爵)|label=第9代ロジアン侯爵|en|Schomberg Kerr, 9th Marquess of Lothian}}}} |
|||
{{Succession box| title = {{flagicon|UK}} {{仮リンク|自治大臣 (イギリス)|label=自治大臣|en|President of the Local Government Board}}| years = [[1885年]]-[[1886年]]|before={{仮リンク|サー・チャールズ・ディルク (第2代准男爵)|label=サー・チャールズ・ディルク准男爵|en|Sir Charles Dilke, 2nd Baronet}}| after=[[ジョゼフ・チェンバレン]]}} |
|||
{{s-ppo}} |
|||
{{s-bef|before=[[ロバート・ガスコイン=セシル (第3代ソールズベリー侯爵)|ソールズベリー侯爵]]}} |
|||
{{s-ttl|title=[[保守党 (イギリス)|保守党]]党首|years=[[1902年]]-[[1911年]]}} |
|||
{{s-aft|rows=2|after=[[アンドルー・ボナー・ロー]]}} |
|||
{{s-bef|before={{仮リンク|ウィリアム・ヘンリー・スミス (1825-1891)|label=ウィリアム・スミス|en|William Henry Smith (1825–1891)}}}} |
|||
{{s-ttl|title={{仮リンク|保守党庶民院院内総務|en|Leaders of the Conservative Party#Leaders in the House of Commons 1834–1922}}|years=[[1891年]]-[[1911年]]}} |
|||
{{s-aca}} |
|||
{{Succession box| title = {{仮リンク|ケンブリッジ大学学長|en|List of Chancellors of the University of Cambridge}}| years = [[1919年]]-[[1930年]]| before = [[ジョン・ウィリアム・ストラット|レイリー卿]]| after = [[スタンリー・ボールドウィン]]}} |
|||
{{Succession box| title = {{仮リンク|エジンバラ大学学長|en|Chancellor of the University of Edinburgh}}| years = [[1891年]]-[[1930年]]| before ={{仮リンク|ジョン・イングリス (グレンコース卿)|label=グレンコース卿|en|John Inglis, Lord Glencorse}}| after = [[ジェームス・マシュー・バリー]]}} |
|||
{{Succession box| title = {{仮リンク|グラスゴー大学学長|en|Rector of the University of Glasgow}}| years = [[1890年]]-[[1893年]]| before ={{仮リンク|ロバート・ブルワー=リットン (初代リットン伯爵)|label=リットン伯爵|en|Robert Bulwer-Lytton, 1st Earl of Lytton}}| after = {{仮リンク|ジョン・エルドン・ゴースト|en|John Eldon Gorst}}}} |
|||
{{Succession box| title = {{仮リンク|聖アンドルーズ大学学長|en|Rector of the University of St Andrews}}| years = [[1886年]]-[[1889年]]| before ={{仮リンク|ドナルド・マッカイ (第11代リーイー卿)|label=リーイー卿|en|Donald Mackay, 11th Lord Reay}}| after = {{仮リンク|フレデリック・ハミルトン=ブラックウッド (初代ダファリン・アンド・エヴァ侯爵)|label=ダファリン・アンド・エヴァ侯爵|en|Frederick Hamilton-Temple-Blackwood, 1st Marquess of Dufferin and Ava}}}} |
|||
{{s-reg|uk}} |
|||
{{succession box | title={{仮リンク|バルフォア伯爵|en|Earl of Balfour}}| before=新設 | after={{仮リンク|ジェラルド・バルフォア (第2代バルフォア伯爵)|label=ジェラルド|en|Gerald Balfour, 2nd Earl of Balfour}} | years=[[1922年]]-[[1930年]]}} |
|||
{{End box}} |
|||
{{先代次代|[[イギリスの首相]]|1902-1905|[[ロバート・ガスコイン=セシル (第3代ソールズベリー侯)|第3代ソールズベリー侯爵]]|[[ヘンリー・キャンベル=バナマン]]}} |
|||
{{先代次代|[[バルフォア伯爵]]|初代: 1922-1930|-|[[ジェラルド・バルフォア]]}} |
|||
{{イギリスの首相}} |
{{イギリスの首相}} |
||
{{Normdaten| |
{{ Normdaten | NDL = 00766005 | CINII = DA04288454 | VIAF = 29574721 | LCCN = n/50/017666 | PND = 119456605 | SELIBR = 176970 }} |
||
{{DEFAULTSORT:はるふおあ ああさあ}} |
{{DEFAULTSORT:はるふおあ ああさあ}} |
||
[[Category:イギリスの首相]] |
[[Category:イギリスの首相]] |
||
[[Category:イギリス保守党の政治家]] |
[[Category:イギリス保守党の政治家]] |
||
[[Category:イギリスの哲学者]] |
|||
[[Category:ガーター勲章]] |
[[Category:ガーター勲章]] |
||
[[Category:メリット勲章]] |
[[Category:メリット勲章]] |
||
[[Category:イギリスの枢密顧問官]] |
[[Category:イギリスの枢密顧問官]] |
||
[[Category:イギリスの伯爵]] |
|||
[[Category:日英関係]] |
|||
[[Category:英愛関係]] |
|||
[[Category:日露戦争の人物]] |
|||
[[Category:第一次世界大戦期の政治家]] |
|||
[[Category:1848年生]] |
[[Category:1848年生]] |
||
[[Category:1930年没]] |
[[Category:1930年没]] |
||
[[Category:イートン・カレッジ出身の人物]] |
[[Category:イートン・カレッジ出身の人物]] |
||
[[Category:スコットランドの人物]] |
[[Category:スコットランドの人物]] |
||
[[Category:セント・アンドルーズ大学 (スコットランド)の教員]] |
|||
[[Category:グラスゴー大学の教員]] |
|||
[[Category:エディンバラ大学の教員]] |
|||
[[Category:ケンブリッジ大学の教員]] |
|||
2013年7月11日 (木) 20:30時点における版
| 初代バルフォア伯爵 アーサー・バルフォア Arthur Balfour, 1st Earl of Balfour | |
|---|---|
 ジョージ・グランサム・ベイン撮影の肖像 | |
| 生年月日 | 1848年7月25日 |
| 出生地 | ホィッティンガム |
| 没年月日 | 1930年3月19日(81歳没) |
| 死没地 | ウォーキング |
| 出身校 | ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジ |
| 所属政党 | 保守党 |
| 称号 |
バルフォア伯爵 トラップレイン子爵 ガーター勲章勲章士(KG) メリット勲章勲章士(OM) 枢密顧問官(PC) 州副知事(DL) |
| 親族 |
第2代ソールズベリー侯爵 (祖父) 第3代ソールズベリー侯爵 (叔父) 第2代バルフォア伯爵(弟) 第4代ソールズベリー侯爵 (従弟) 初代チェルウッドのセシル子爵 (従弟) |
| サイン |
|
| 在任期間 | 1902年7月12日 - 1905年12月4日[1] |
| 国王 | エドワード7世 |
| 内閣 | ロイド・ジョージ内閣 |
| 在任期間 | 1916年12月10日 - 1919年10月24日[1] |
| 内閣 | アスキス内閣 |
| 在任期間 | 1915年5月27日 - 1916年12月5日[2] |
| 内閣 |
第2次ソールズベリー侯内閣 第3次ソールズベリー侯内閣 バルフォア内閣(兼任) |
| 在任期間 |
1891年10月6日 - 1892年8月15日 1895年6月29日 - 1905年12月4日 |
| 選挙区 |
ハートフォード選挙区[3] マンチェスター・イースト選挙区[3] シティ・オブ・ロンドン選挙区[3] |
| 在任期間 |
1874年1月31日 - 1885年11月24日[3] 1885年11月24日 - 1906年1月12日[3] 1906年2月27日 - 1922年5月5日[3] |
その他の職歴 | |
|
(1922年5月5日 - 1930年3月19日) | |
初代バルフォア伯爵アーサー・ジェイムズ・バルフォア(英: Arthur James Balfour, 1st Earl of Balfour, KG, OM, PC, DL、1848年7月25日 - 1930年3月19日)は、イギリスの政治家、哲学者、貴族。
ソールズベリー侯爵引退後の保守党を指導し、1902年から1905年まで首相を務めた。政権交代後も自由党の長期政権下で6年ほど野党保守党の党首を務めたが、1911年には党首の座をアンドルー・ボナー・ローに譲る。
第一次世界大戦中に成立した自由党・保守党大連立の挙国一致内閣では海軍大臣や外務大臣などを歴任した。
哲学者としても活躍し、宗教に関する哲学書を多数著している。
概要
1848年に大富豪・大地主の息子としてスコットランド・ホィッティンガムに生まれる。ケンブリッジ大学のトリニティ・カレッジで哲学を学んだ後、1874年1月の総選挙で保守党の庶民院議員に初当選。叔父にあたる第3代ソールズベリー侯爵が外相となるとその議会内個人秘書官を務めた。1879年には『哲学的懐疑の擁護』を出版した。
1880年の保守党の下野後は、ランドルフ・チャーチル卿らとともに保守党内の反執行部グループ「第四党」を形成した。しかし1885年に第一次ソールズベリー侯爵内閣が成立すると、バルフォアは自治大臣として入閣した。
1886年の第二次ソールズベリー侯爵内閣ではスコットランド担当大臣、ついでアイルランド担当大臣に就任する。アイルランド強圧法を制定して激しいアイルランド民族運動の弾圧を行い、「血塗られたバルフォア」の異名を取った。一方で融和政策もとり、アイルランド小作人の土地購入を促すバルフォア法を制定した。1891年には第一大蔵卿および庶民院院内総務に就任。
1895年には主著『信仰の基礎』を出版した。同年に成立した第三次ソールズベリー侯爵内閣にも第一大蔵卿・庶民院院内総務として入閣。1898年に叔父ソールズベリー卿が病になると代行を務めることが増えた。中国分割をめぐる諸交渉や中等教育の普及を目的とするバルフォア教育法の制定を主導した。
1902年7月に叔父ソールズベリー卿が引退すると、代わって首相・保守党党首となる。1903年にはアイルランド担当大臣ジョージ・ウィンダムの主導でウィンダム法を制定し、バルフォア法に引き続いてアイルランド小作人の土地購入を促進した。1905年に帝国防衛委員会を創設して国防強化に尽力したことも特筆される。
外交面では極東で膨張するロシア帝国を牽制するためにフランスに接近し、エジプト、モロッコ、ナイジェリア、シャム(タイ)、マダガスカル島、ニューヘブリディーズ諸島、ニューファンドランド島などの利権・領有権をめぐる英仏間の諸懸案に折り合いを付けた。また日本との関係も強化し、日露戦争中に日英同盟を更新・強化した。
関税問題では植民地大臣ジョゼフ・チェンバレンの保護貿易主義に共感を寄せていたが、保守党の分裂を避けるため、折衷的立場に終始した。そのため関税問題の過熱で閣内で孤立したチェンバレンが辞職すると自由貿易主義派の蔵相チャールズ・リッチーも罷免した。だがこの問題で保守党の内部分裂、自由党の結束強化、保護貿易を嫌う庶民の保守党離れの傾向は進んでいった。また1904年から問題となっていた南アフリカの中国人奴隷問題でもうまく立ち回れず、労働者層の支持を失っていく。関税問題をめぐって政権内の不一致が強まる中の1905年12月に総辞職し、自由党に政権を譲る。
バルフォアは保守党党首職に在職し続けたが、1906年1月の解散総選挙で保守党は惨敗した。庶民院で多数派を失ったので、貴族院を中心に反政府闘争を行うようになり、1909年11月には蔵相ロイド・ジョージの「人民予算」を貴族院で葬り去ったが、これがきっかけで自由党政権が貴族院の権限縮小を狙うようになった。1910年の二度の解散総選挙の末に自由党政権は新貴族任命を盾に保守党と貴族院を脅迫してくるようになり、弱気になったバルフォアは1911年8月に貴族院の権限縮小を盛り込む議会法の可決成立を認めることになった。これによって保守党内での求心力を失い、同年11月には党首を辞した。
第一次世界大戦中の1915年のアスキス挙国一致内閣では海軍大臣として入閣し、続く1916年のロイド・ジョージ挙国一致内閣では外務大臣となった。この外相就任時の1917年にパレスチナにユダヤ人国家の樹立を認めるバルフォア宣言を出している。1919年には枢密院議長に転じるも1922年の大連立解消を機に退任。1922年には初代バルフォア伯爵に叙爵し、貴族に列する。スタンリー・ボールドウィン保守党政権下の1925年にも枢密院議長に再任するが、1929年には政界引退し、その翌年の1930年にイングランド・ウォーキングで死去した。
生涯
出生から政界入りまで

1848年7月25日、スコットランドのイースト・ロージアン州ホィッティンガムに生まれた[4]。
父ジェイムズ・メイトランド・バルフォアは大富豪・大地主であり、また庶民院議員も務めた人物だった。バルフォア家はスコットランドの旧家であり、18世紀末に祖父ジェイムズの代にイギリス東インド会社の貿易で莫大な富を築いた。スコットランドに膨大な土地を購入し、ホィッティンガムをその本拠とするようになった家柄である[5]。
母ブランチェ・メアリー・ハリエット嬢(Lady Blanche Mary Harriet)は第2代ソールズベリー侯爵ジェイムズ・ガスコイン=セシルの娘だった[4][6]。セシル家は300年にわたってハットフィールドを領してきた名門貴族である[7]。
次弟にセシル・チャールズ(Cecil Charles Balfour)、三弟に生物学者となるフランシス・メイトランド、四弟に政治家またバルフォア伯位の継承者となるジェラルド、五弟に国王副官となるユースタス・ジェームズ・アントニー(Eustace James Anthony)がいる[8]。また姉が三人おり、長姉エヴェリン・ジョージアナ・メアリー(Evelyn Georgiana Mary)は数学者第3代レイリー男爵に、次姉エレノア・ミルドレッドはヘンリー・シジウィックにそれぞれ嫁いでいる[8]。
ワーテルローの戦いの英雄ウェリントン公爵アーサー・ウェルズリーが代父となり、彼の名前をとってアーサーと名付けられた[5]。
7歳の頃に父が死去[6][5]。1861年から1866年までイートン・カレッジで学び、次いで1866年から1869年にかけてケンブリッジ大学のトリニティ・カレッジで哲学を学んだ[9][4][6]。哲学研究にのめりこみ、家の財産は弟に譲って自らはケンブリッジ大学に残り、哲学研究を続けようかと考えた時期もあったという[6][5]。
しかし叔父にあたる保守党貴族院議員の第3代ソールズベリー侯爵の勧めや[10]、母ブランチェから高貴な家に生まれた者は政治的・社会的責任を負わねばならないというノブレス・オブリージュ的な考えの説教をされたことで、最終的には政界の道を選んだ[6][5]。
政界入り
1874年1月の総選挙でハートフォード選挙区から保守党候補として出馬して当選した[3][10]。
この総選挙は全国的にも保守党が勝利し、ベンジャミン・ディズレーリを首相とする保守党政権の発足をもたらした。露土戦争の最中の1878年に叔父ソールズベリー侯爵が外務大臣となり[11]、バルフォアはその議会内個人秘書官[注釈 1]となった[12]。
1878年6月から7月にかけて露土戦争の講和会議であるベルリン会議にディズレーリや叔父ソールズベリー侯爵とともに出席した[12][10]。
「第四党」

1880年の総選挙で保守党は敗北し、ウィリアム・グラッドストンを首相とする自由党政権が発足した。保守党は野党となったが、保守党庶民院院内総務を務める元蔵相サー・スタッフォード・ノースコート准男爵は温和な人柄で政権批判に向いているとはいえなかった。しかも彼はかつてグラッドストンの秘書であったため、今でもグラッドストンに敬意を払い続けていた[14][15]。
これに不満を感じていた保守党若手庶民院議員ランドルフ・チャーチル卿(後の首相ウィンストン・チャーチルの父)は、バルフォアやサー・ヘンリー・ドラモンド・ウォルフ、ジョン・エルドン・ゴーストを糾合して「第四党」と呼ばれるノースコートに造反する独自グループを結成した[16]。
「第四党」のリーダー的存在はランドルフ卿であるが、バルフォアは常にランドルフ卿に従っているわけではなく、たとえばランドルフ卿が保守党貴族院院内総務を務める叔父ソールズベリー侯爵まで批判した場合には、叔父の擁護にまわるのが常だった[12]。またランドルフ卿が「民主化」と称して議会外保守党組織である保守党協会全国同盟が党の政策や財政を監督できるようにしようとした際にも、バルフォアは「議会軽視」としてこれに反対している[17]。
第一次ソールズベリー内閣自治大臣
1885年7月にグラッドストン自由党政権が議会で敗北したことにより、第一次ソールズベリー侯爵内閣が成立。バルフォアは自治大臣として入閣した[12]。「第四党」の同志のランドルフ・チャーチル卿もインド担当大臣として入閣している[18]。
しかし同内閣は短期間で終焉したため、バルフォアもこれといった功績を残すことはなかった[12]。
第二次ソールズベリー内閣アイルランド担当大臣
1886年7月に第二次ソールズベリー侯爵内閣が成立すると、叔父の引き立てで初めスコットランド担当大臣として入閣したが[19][12]、1887年3月にヒックス・ビーチがアイルランド担当大臣を辞職したため、バルフォアがその後任となった[20]。
この人事は「身贔屓」として政界に衝撃を与えた。「大丈夫だよ」といった意味の英語の成句 “Bob's your uncle!” はバルフォアが叔父に贔屓されていることの皮肉に由来すると考えられている[21]。バルフォアは一般にインテリの優男と見られており、マスコミからは「プリンス・チャーミング」「ミス・バルフォア」などと渾名されて侮られた[22]。アイルランド人からも「クララ」という女性名で呼ばれ、馬鹿にされたという[20]。
アイルランド民族運動の弾圧

バルフォアがアイルランド担当相に就任した時、アイルランド問題は深刻化していた。1886年9月にアイルランド国民党党首チャールズ・スチュワート・パーネルが議会に提出したアイルランドの地代を半減させる法案が否決されて以降、アイルランドでは小作人同士が協定を結んで勝手に地代を減額し、地主がそれを承諾して受け取ればよし、受け取らねば、その地主が小作人を強制立ち退きさせた時の抵抗運動に備えて供託するという闘争が行われていたのである。これにより強制立ち退きと暴動の危険が高まっていた[23]。
これに対してバルフォアはアイルランド民族運動の弾圧を可能とする強圧法の制定を急いだ[20]。その法案の第二読会での審議の最中の1887年4月8日に『タイムズ』紙がパーネルが元アイルランド担当大臣フレデリック・キャヴェンディッシュ卿の暗殺を支持していることを示唆する記事を掲載した。パーネルはその事実関係を否認したが、この記事は大きな反響を呼び、バルフォアの強圧法案の良き追い風となった。強圧法は8月にも可決成立した[24]。
この後、バルフォアは強圧法を駆使してアイルランドで激しい弾圧を行い、アイルランド国民党の議員たちを含むアイルランド民族運動指導者たちを軒並み逮捕していった。アイルランドの刑務所はあっという間に満杯になったという[25]。その弾圧の容赦の無さからバルフォアはアイルランド人から「クララ」改め「血塗られたバルフォア(“Bloody Balfour”)」と呼ばれ恐れられるようになった[25][26][22]。
1887年9月9日、アイルランド・コーク州ミッチェルスタウンで警官と農民が衝突し、農民3人が警察官に銃殺される事件が発生した[26][25]。検死の陪審官は警察官による故意の殺人と断定したが、バルフォアは警官の行動を称賛した。これに対してアイルランド自治を決意していた野党自由党のグラッドストンは「ミッチェルスタウンを記憶せよ(Remember Mitchelstown)」を自由党のスローガンに定めてアイルランド問題を中心に与党保守党と対決する姿勢を強めた[27]。
バルフォア法
しかしバルフォアは強圧一辺倒の大臣ではなく、1890年3月と11月にはアイルランド小作人が地主から土地を購入できるよう支援する「土地購入および稠密地方(アイルランド)法案」(通称「バルフォア法」)を提出した。3月提出の法案は否決されたが、11月に再提出されたものが可決された[28][注釈 3]。
この「バルフォア法」は、第一次ソールズベリー侯爵内閣期に制定されたアシュバーン法を拡張させたものであり、土地購入を希望するアイルランド小作農に土地購入費の貸し付けを行う「土地委員会」の貸付限度額をそれまでの500万ポンドから3300万ポンドに大幅増額させ[30]、さらに現に小作人である者だけでなく、かつて小作人だった者も保護対象としており、後の追放小作人法の先駆となる法律であったといえる[31]。
しかし国庫の負担を軽くするために複雑な体系にもなった。まず地主への支払いは現金ではなく、アイルランド銀行が発行する2.75%の利子付きの土地債権に変更されたが、この土地債権は地主に直接渡されたため、土地債権の価格変動が地主の土地売却の意欲に直接的に影響を及ぼすようになった(コンソル公債と交換可能にすることによって土地債権がコンソル公債以下の価格にならないよう配慮はされているが)[32]。また土地購入者は保険金を積み立てることになり、そのために最初の5年間は旧地代の80%を支払わねばならなかった[32]。さらに土地購入者が49年間に渡って支払うことになっている4%の年賦金の一部が「州のパーセンテージ(County percentage)」として地方税会計に流用されることになった(利子2.75%、償却費1%、州のパーセンテージ0.25%)[32]。
このような制度の複雑化のために結果としてはアシュバーン法の時よりも土地購入申請者数が減少した。1896年のバルフォア法改正の際にアイルランド担当大臣を務めていた弟ジェラルド・バルフォアが議会に行った報告によればアシュバーン法下での申請数は6年間で4645件なのに対して、バルフォア法下での申請数は4年間に2600件に留まるという[31]。しかしこの時に弟ジェラルドによってバルフォア法は改正され、「州のパーセンテージ」や保険金制度が廃止されて制度は簡略になり、また年賦金算定の基礎となる前貸金を10年ごとに算出して減少させていく修正案も導入された。この修正のおかげでバルフォア法下での土地購入申請も増えていき、1902年3月までに約3万7000人のアイルランド小作人が土地を購入することができたのであった[33]。
第三次ソールズベリー内閣第一大蔵卿・庶民院院内総務
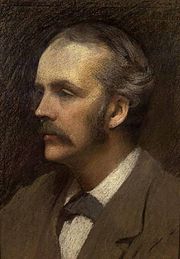
1891年、死去したウィリアム・ヘンリー・スミスの後任として第一大蔵卿および庶民院院内総務に抜擢された(これは第一大蔵卿が首相と異なる最後の例であった)。バルフォアはアイルランド民族運動を激しく弾圧したことで保守党庶民院議員たちから人気を集めており、その声にソールズベリー侯爵が応えた人事だった[34][22]。
翌1892年に保守党が下野したが、この後の3年間の野党時代にもバルフォアは保守党庶民院院内総務に在職し続けた。1895年に保守党が自由統一党と連立して政権を奪回し、第三次ソールズベリー侯爵内閣を発足させると再び第一大蔵卿・庶民院院内総務に就任した。首相ソールズベリー侯は自邸暮らしをするようになり、ダウニング街10番地にはバルフォアが入った[35]。
さらに1898年にソールズベリー侯が病となると、甥であるバルフォアがその代理を務めることが増えていった[36]。
中国分割をめぐって
1895年の日清戦争で清が日本に敗れ、日本に対して負った巨額の賠償金を支払うために清政府がロシア帝国とフランスから借款し、その見返りとして露仏両国が清国内に様々な権益を獲得した。これがきっかけとなり、急速にイギリス、ロシア、フランス、ドイツ、日本など列強諸国による中国分割が進み、阿片戦争以来のイギリス一国の中国半植民地(非公式帝国)状態は崩壊した[37]。
とりわけ急速に北中国を勢力圏としていくロシアとの対立が深まった。バルフォアは1898年8月10日の庶民院での演説で中国分割において「勢力圏」という概念は否定されるべきであり、代わりに「利益範囲」という概念を導入すべきと主張した。これは範囲内において範囲設定国は他国企業を排除できる権利を有するが、通商の門戸は常に開放しなければならないというものでイギリス資本主義の利益に沿った主張だった[38]。一方ロシアはあくまで北中国を排他的な自国の独占市場、つまり勢力圏とする腹積もりだったから北中国を門戸開放する意志などなかった[39]。
バルフォアの演説の直後の1898年8月12日にはベルギー企業が清政府から京漢鉄道を借款する契約を結んだが、これに危機感を抱いたバルフォアは外相(首相ソールズベリー侯が兼務していた)代理として清政府と交渉を行い、9月6日にもイギリスに5本の鉄道敷設権[注釈 4]を与えることを認めさせた[40]。
一方1898年6月から起こっていた中国東北部の鉄道敷設権をめぐる英露両国の論争ではロシアから妥協を引き出せず、1899年4月に締結された英露両国の協定は、「イギリスは長城以北に鉄道敷設権を求めない。ロシアも揚子江流域に鉄道敷設権を求めない」ことを確認したのみとなり、その範囲内における自国企業独占や通商自由化を保障し合うことはできなかった[41]。
1900年5月から8月にかけて中国半植民地化に反発した義和団が北中国で蜂起した(義和団の乱)。乱自体は列強諸国によってただちに叩き潰されたが、ロシアはこれを理由に満洲を軍事占領した。これに対抗すべくバルフォアは植民地大臣ジョゼフ・チェンバレンや枢密院議長デヴォンシャー公爵ら自由統一党の面々とともにドイツ帝国や日本との連携を強化してロシアを抑え込むべきことを主張した[42]。
結局ドイツはロシアとの対立を回避したのでイギリスは日本と接近することになり、1902年1月30日にも5年期限の日英同盟が締結された[42]。
バルフォア教育法

1902年3月には第一大蔵卿として「バルフォア教育法」と呼ばれる教育法の法案を議会に提出した[43]。これは1870年にグラッドストン自由党政権下で制定された初等教育普及のための初等教育法案を拡張させ、中等教育普及のための州議会がすべき支援を定めた法律であるが、同時に1870年の初等教育法で定められていた非国教徒(自由党支持基盤)が強い影響力を持つ学務委員会(School Attendance Committee)を廃止して、新たな小学校監督機関として地方教育庁を設置させるものでもあった。加えて国教会とカトリックの学校には地方教育庁の管理下に置く代わりに地方税の一部を導入するという条文もあり、非国教徒が強く反発する内容だった[44][45]。
非国教徒の反対運動は激しく、とりわけウェールズでの闘争が激化した。庶民院ではウェールズ出身の自由党議員ロイド・ジョージが中心となって同法への反対運動が展開された[46][47]。9カ月にも及ぶ激闘の末、バルフォアが首相に就任した後の1902年12月にバルフォア教育法は可決された[47]。この法律は1944年のバットラー法成立までイギリス中等教育に関する基本法として君臨することになる[48]。
しかしボーア戦争以来、小英国主義者と自由帝国主義者に分裂していた自由党がこの法律への反対を共通項に一つにまとまってしまうという保守党にとっては逆作用も生んだのだった[47]。
バルフォア内閣
1902年7月11日に首相ソールズベリー侯が首相を辞した。ランドルフ・チャーチル卿はすでに亡く、連立相手の自由統一党の有力者ジョゼフ・チェンバレンとデヴォンシャー公爵も首相になる意思はなく、バルフォアが後任の首相となることに異を唱える者はなかった[49]。
1907年7月12日に国王エドワード7世より大命を拝受し、バルフォア内閣を組閣した。さらにその二日後には外務省内で開かれた保守党両院総会で保守党党首に選出された。デヴォンシャー公爵やチェンバレンら自由統一党幹部も引き続き連立を維持していくことを表明した[50]。
内政
ウィンダム法

バルフォア内閣アイルランド担当大臣ジョージ・ウィンダムの主導で1903年には新たなアイルランド土地購入法のウィンダム法が制定された[51]。
この法律は強制的土地購入路線を否定し、あくまで自由契約の範囲内で農地の占有者への所有権移転を推進しようという法律の集大成であった[52]。これまでのアシュバーン法とバルフォア法が基本的に土地購入代の前貸しのみを定めているのに対して、ウィンダム法は地主と小作人の間で土地売却契約が結ばれやすくなるよう誘導する規定が盛り込まれている[53]。
この法律によって自作農創出のための機関「土地財産委員会」が設置されることになり、自作農創設の方式も保有地ごとから所領ごとに変更された。さらに地主への支払いを土地債権から現金に戻し、土地債権の価格変動で地主の売却意思が上下するのを鎮めた。2.75%利子付き土地債権は当時額面割れしていたので、これは地主に有利な規定であったといえる[54]。土地財産委員会は2.75%利子付き土地債権を自ら金融市場に流して資金調達して地主への現金支払いを行う[55]。
さらに法律施行から1908年11月1日までの5年間の特別規定として、地主が土地売却代金を有価証券に再投資した場合は、その地主に12%の「奨励金」を支払うことが規定された。これも地主の売却意欲を高めるための規定であった[56]。小作人一人あたりへの貸付限度は7000ポンドに増額され、小作人は68年6カ月の期間、利子2.75%と償却費0.5%の合わせて3.75%の年賦金を毎年支払うことになるが、この額は当該小作地の小作料の裁定期に応じて減額される。この要件が満たされている場合には土地財産委員は視察を行わないとされており、この視察免除規定も土地売却契約の締結を大いに促した[57]。
この法律はアイルランド自治を防ぐための融和政策の頂点であったが、結局アイルランド自治運動を沈静化させることはできなかった[58][59]。それについてブレイク男爵は「自由のために戦う民族を経済的な融和政策で抑圧することはできないことの実例である」と評している[59]。
関税改革論争

第二次ボーア戦争は1902年5月に講和条約が結ばれて正式に終結していたが、予想外の長期戦は予想外の膨大な戦費をもたらし、1900年以降イギリス財政は赤字となっていた。それを補うために各種増税が行われ、その一環で1902年3月に蔵相マイケル・ヒックス・ビーチは穀物関税再導入を暫定的かつわずかな額でという条件で実施していた[60]。
1902年7月に首相ソールズベリー侯爵と蔵相ヒックス・ビーチがそろって辞職し、代わってバルフォア内閣が成立したが、11月の閣議において植民地大臣ジョゼフ・チェンバレンはビーチの導入した穀物関税を永続化させつつ、帝国特恵関税制度を導入して大英帝国内の関税は安くする事を主張するようになった[61][62][63]。つまり大英帝国の結び付きを強化して自給自足経済圏の建設を目指すとともに、帝国外からの関税収入をもって均衡財政と社会保障費の確保を図ろうという保護貿易主義であり、自由貿易主義や小英国主義とは真っ向から対立する発想だった[62][61]。そのため自由貿易主義者の蔵相チャールズ・リッチーはチェンバレンの主張に強く反発した[61]。
バルフォアはリッチーよりはチェンバレンに好感を持っていたが[64]、それによって政権が分裂する事態だけは回避したいと考えていた[65]。リッチーは穀物関税を廃止しないつもりなら辞職すると脅迫するようになり、それに対してチェンバレンが譲歩したため、バルフォアは1903年3月末にも穀物関税廃止を閣議決定した[66]。
しかしチェンバレンは持論を諦めておらず、1903年5月15日にも本拠地のバーミンガム市で関税改革(帝国外への関税導入と帝国特恵関税制度の導入)を訴えた[66][64][67]。この演説以降、関税問題は政界と世論を二分する大論争となった。貧しい庶民はパンの値段が上がることに反対し、保護貿易には反対だった[68]。金融資本家も資本の流動性が悪くなるとして保護貿易には反対し[69]、綿工業資本家も自由貿易によって利益をあげていたので保護貿易には反対だった[68][70]。一方、工業資本家(廉価なドイツ工業製品を恐れていた)や地主(伝統的に保護貿易主義)は保護貿易を歓迎し、チェンバレンを支持した[71][72]。
閣内ではリッチーの他、枢密院議長デヴォンシャー公爵やインド担当相ジョージ・ハミルトン卿などがチェンバレンに反対した。若き新米保守党議員ウィンストン・チャーチルも自由貿易を奉じてチェンバレンに反対している(彼は1904年に自由党へ移籍する)[73]。自由帝国主義派と小英国主義派に分裂していた自由党も自由貿易支持・反チェンバレンの旗のもとに一致団結した[73]。
しかし関税は食品価格の上昇をもたらさない報復関税に使用することも可能であり、バルフォアとしてはそれを支持してチェンバレンの主張に一理を認めていた(チェンバレンも食料関税は当面見送るべきと主張していた)[74]。バルフォアは両者の妥協点を探って何とか鎮静化させようと努力したが[65]、結局閣内で孤立したチェンバレンは1903年9月21日に植民地大臣を辞した。以降チェンバレンはバルフォアの側面支援を受けながら主要工業都市で関税改革の世論を盛り上げる遊説を開始する[75][71][76]。
バルフォアはバランスを取るために強硬自由貿易主義者の蔵相リッチーも内閣から追放する意思を固めた。1903年10月9日にも「首相に対する陰謀を図った」としてリッチーら自由貿易主義閣僚を解任した。デヴォンシャー公爵については閣内にとどめようとしたが、結局公爵も自由貿易主義者の圧力を受けて辞職することになった。これによってバルフォア内閣の基盤はだいぶ弱くなった[77]。
中国人奴隷問題

英領南アフリカではボーア戦争後の労働力不足を補うため、1904年2月から1906年11月までの間に6万3000人もの中国人が年季契約で中国本国から南アフリカに鉱山労働者として輸送されてきていた。彼らが低賃金で働くせいで現地人の給料も切り下げられていった[78]。
イギリス本国の労働者層は植民地においてこうした外国人低賃金労働者の輸入を許していれば、いずれイギリス本国でも外国人労働者が輸入されるようになり、自分たちの労働権や給料が脅かされると恐れていた[79]。道徳心と信仰心が強い中産階級の非国教徒も「このように大量の人間を船に詰め込み、鉱山で重労働をさせる行為は、イギリスが禁止している奴隷貿易に該当する」として強く反発した。また送られてくる中国人たちは力仕事向きのマッチョな男性ばかりだから道中の船の中や到着後の居住先である中国人収容所の中で同性愛をしている可能性が高く、キリスト教の信仰心と照らし合わせても認めるわけにはいかないことだった[79]。
だがこれを奴隷貿易と同視するのは誇張だった可能性が高い。なにせ中国人にとって南アフリカは中国本国で働くより15倍も高い給料をもらえる場所なのだから、強制したり騙したりするまでもなく、中国人はわらわらと南アフリカに集まってくるのであった[80]。バルフォアもオーストラリア総督ノースコート卿に宛てた手紙の中で「我々の大きな悩みは中国人労働者について正しい説明を行うことができなかったことだ。(自由党は)中国人労働者が奴隷などという馬鹿げた理由で反対しているが、本当は白人労働者が黄色人労働者に置き換えられるという誤った推測が反対の理由だろう」と語っている。確かにそうした面もあったものの、それを主張したところで保守党批判ムードが鎮静化することはなかった[81]。
この件で労働者層の保守党離れは進み、1906年の総選挙での保守党の惨敗を招くことになる[79]。
帝国防衛委員会の創設
1905年には、大英帝国全体の帝国防衛体制の確立を求めるチェンバレンの主張を取り入れる形で帝国防衛委員会を設置した。これは自治領と帝国防衛体制を検討するための委員会であった(実際に自治領首相に参加を求めるようになったのはアスキス自由党政権下の1911年になってのことだった)[82]。これと並行して陸海軍の再編成も進めていった[48]。
ちなみにこの帝国防衛員会は後にアスキス内閣によって「将来起こる戦争に備えて陸海空三軍と国内戦時体制の調整を行い、また自治領とともに帝国全体の防衛計画を立てる機関」に再編されていくことになる[83]。
外交
チベット侵攻


悲惨な戦争となった第二次ボーア戦争以降、イギリス国民の戦争意欲は弱まり、ヴィクトリア朝時代のような露骨な侵略は減った。最後に行われたヴィクトリア朝的侵略が1903年のチベット侵攻だった[84]。
イギリスは19世紀からロシアのインド侵略を警戒してきたが、20世紀に入るとインド北部諸国と外部勢力を国内に入れないという条約を結んでヒマラヤ山脈沿いに緩衝地帯を完成させていた。ところがダライ・ラマ13世を国主に戴くチベットのみがそれに入っておらず、ロシアがチベットに大きな影響力を及ぼしているという噂が流れていた[85]。
中国分割の中で清領トルキスタンにロシアの鉄道が次々と敷かれていく中、インド総督カーゾン卿は、ロシアがチベットを経由してインドに侵攻してくるのを恐れるようになった[86]。そんな中の1903年春、チベットのラマ僧と英領インド北方の国境守備隊将校の間のヤク放牧地をめぐる国境争いがこじれて、チベットはイギリスとの通商条約を破棄した。ここに至ってカーゾン卿は、近衛竜騎兵隊のフランシス・ヤングハズバンド大佐とともにチベット侵攻を計画するようになった[87]。
本国のバルフォア首相はチベットとの交易に重要性を感じておらず、チベット侵攻には消極的だったが、最終的にはこの動きを承認した[88]。
こうして1903年12月より「使節団」と称するヤングハズバンド大佐率いるイギリス軍部隊がチベット侵攻を開始した。1904年1月にはトゥナへ入り、そこでラマ僧と交渉したものの、チベット側は「使節団」の即時撤退を要求した。ヤングハズバンドはこれを無視し、3月末にはギャンツェへ向けて進軍を再開した。抵抗するチベット人を殺害しながら夏までにはギャンツェを占領。そこで本国の指示を待ってから首都ラサへ進軍し、8月にラサに入城した[89]。
バルフォアは「チベットを占領したり、保護領にしてはならない。首都に英国代表を置くことを強要してもいけない。ただし通商条約の締結と賠償金の支払いを求めること、イギリスの了承なしに他の大国と取引しないことを約束させることは差し支えない」という指示を出していたが[90]、ヤングハズバンドはこの命令に従わず、9月7日には清のアンバン[注釈 5]も同席させた上でチベット側とラサ条約を締結し、5万ポンド賠償金支払い(75年払い)とそれが完了するまではイギリスがチュンビ谷全域を占領すること、またギュンツェにイギリス代表を置くことを認めさせた[92]。
バルフォアはこの独断の「外交的勝利」を全く歓迎しなかった。この時代にはイギリス以外の欧米列強も次々と植民地支配に乗り出しており、もはやイギリス一国だけで世界を自由にできる時代ではなかった。他の列強の許可も得ておかねば、強引な条約はたちまちイギリスを孤立に追いやってしまうのである。バルフォアの予想通り、この条約が発表されるやすぐにもロシア、ドイツ、フランス、アメリカ、イタリアの5大国がイギリス外務省に正式な抗議を送ってきた。バルフォアはイギリス包囲網を避けるため、ラサ条約に定められた賠償金額を3分の1に激減させ、さらにチュンビ谷からも1908年までに撤退することを決定した[93]。
フランスとの接近

先に結ばれた日英同盟は「日英どちらかが二か国以上と戦争になった場合はもう片方は同盟国のために参戦、一か国との戦争の場合はもう片方は中立を保つ」という約定になっていたため、バルフォアとしては早急にフランスを取りこんでフランスがロシアとともに日本に宣戦布告するのを阻止する必要があった[94]。
フランスを取りこむことについてはそれほど難しくなかった。イギリスは植民地問題で長らくフランスと争ってきたが、1898年のファショダ事件でフランスが譲歩して以来、両国関係は好転していたからである。またドイツ海軍がヴィルヘルム2世の「世界政策」のもと海軍力の大幅増強を行い、世界各地でイギリスの植民地支配を脅かすようになったことも英仏を結び付ける背景となった[95]。外相ランズダウン侯爵は駐英フランス大使ポール・カンボンを通じてテオフィル・デルカッセ仏外相と交渉を進め、エジプト、モロッコ、ナイジェリア、シャム(タイ)、マダガスカル島、ニューヘブリディーズ諸島、ニューファンドランド島などの利権・領有権をめぐる英仏の懸案事項を互譲的に解決した。それは最終的に1904年4月8日の英仏協商の締結で結実した[96]
日露戦争をめぐって


前任のソールズベリー侯爵と同様、バルフォアは当初日本の海軍力を高く見積もっており、日本との同盟によって日英の中国における海軍力を露仏のそれより上回らせ、もってロシア帝国主義の拡張を抑止し、中国情勢の現状維持を図ろうと考えていた。そのためには日露の和解も開戦も阻止する必要があった[97]
日英同盟締結後も日本国内にはロシアと協商を結ぼうという動きがあった。これを警戒したバルフォアは1903年7月30日に日本政府に向けて声明を出し、「日本単独でロシアと協商関係を結ぶよりも日英両国でアメリカに働きかけ、日英米三国でロシアに圧力を加え、日本の主張をロシアに認めさせる方が得策である」と忠告した[98]。また外相ランズダウン侯爵も駐英日本公使林董に対して「ロシアの満洲撤兵に関する協定が日露間だけで締結されるなら、日英同盟によって具現した日英の協調関係は弱まらざるを得ない。ロシアとの交渉は日英同盟の範囲内で慎重に行ってほしい」と要請した[98]。
しかしロシアは満洲から撤兵する姿勢を全く示さなかったため、結局日露関係は1903年後半から一触即発状態となっていった。バルフォアもここに至って日露開戦は必至と判断するようになった[98]。この頃イギリスの軍事専門家の多くは日本の敗戦を予想しており、その影響でバルフォアも日本への期待感を以前より薄め、1903年12月23日の覚書の中では「日本の海軍力はロシアより劣っている。そのため日本は安全に韓国へ派兵できないし、また派兵できたとしても海上補給線を切断されるであろう」と書いている[99]。
バルフォアは日本がロシア帝国主義の防波堤になりえない(極東の現状維持ができない)なら、日露開戦を阻止する必要はないと考えるようになった。なぜならば、日露戦争が起こればロシアは戦争で国力を消耗させるだろうし、ロシアが勝利したとしても新たに手に入れるのは領土的に無価値な韓国だけであり、また日本も滅亡することはないだろうから、今後ロシアは無価値な領土を日本から守るために大軍隊を常に極東に貼り付かせる必要に迫られ、これがロシアの行動を阻害し、イギリスの行動を有利にすると考えられるからである[100][101][注釈 6]。
このバルフォアの戦略転換によって日露開戦を妨げる要素はなくなり、1904年2月には日露戦争の勃発に至った[102]。しかしバルフォアの予想に反し、日本軍は善戦し、1905年1月には最大の激戦地の旅順で日本陸軍がロシア軍を降伏に追い込んだ。これにはバルフォアも驚いたという[103]。さらに1905年5月から6月にかけての日本海海戦でも日本海軍がロシア・バルチック艦隊を撃破した[104]。
これを受けてバルフォアも日英同盟延長に前向きとなり、外相ランズダウン侯爵を林公使と折衝に当たらせ、1905年8月12日にも第二次日英同盟を締結した。その結果、同盟期間は10年に延長され、イギリスは日本が韓国を保護国化することを承認し、日本はイギリスがインドで行う植民地政策を承認することとなった。同盟適用範囲は東南アジアとインドにまで広げられた。さらに先の日英同盟が締結国の片方が二カ国以上と戦争になった場合にもう片方の締結国が参戦する内容だったのに対し、今度の日英同盟は一か国との戦争であってももう片方は参戦しなければならないという強固なものとなった。ここに日英両国は名実ともに同盟国となったのである[105]。
戦争終結後の1905年9月29日には日本の君主である明治天皇にイギリス最高勲章ガーター勲章を送るべしとする外相ランズダウン侯爵の提言に首相として了解を出し、この提言は10月8日にも国王エドワード7世の裁可を得て、バルフォア退任後の1906年2月に実現することになる[106]。
また日本を公使館国から大使館国に昇格させたのも日露戦争中のバルフォアだった。当時のヨーロッパでは大国には大使館、小国には公使館を置くのが伝統だった。特に気位が高いイギリスはこの格付けに拘っていた。20世紀初頭の段階でイギリスが大使館を設置していた国はフランス、ロシア、ドイツ、オーストリア、イタリア、トルコ、スペイン、アメリカの8カ国のみであった。日本はこれに続く形でイギリスから大使館とするに値する国と認められたのであった(これ以降各国も次々とイギリスに倣って日本公使館を大使館に昇格させていった)[107]。
内閣総辞職
バルフォアは保守党分裂を阻止するため、関税改革に触れまいとし続けた。だが野党自由党は保守党政権に揺さぶりをかけようと、1905年3月末に関税改革反対決議案を提出してきた。これに対してバルフォアは決議案の内容が不明瞭であることを理由に保守党は棄権するという方針を示した[108]。一方チェンバレンはバルフォアに関税改革を争点にした解散総選挙に打って出るよう要求したが、バルフォアは応じなかった。バルフォアの態度にイライラしたチェンバレンはついに1905年11月からバルフォア批判を開始した[109]。
ここに至ってバルフォアはこれ以上政権に留まれば党分裂は避けがたいと認識するようになった。また自由党内でアイルランド自治問題をめぐってローズベリー伯爵ら自由帝国主義派とキャンベル=バナマンら小英国主義派の対立が再燃し始めた情勢を見て、今総辞職して自由党に政権を譲れば、世間の注目が関税問題からアイルランド問題に移り、自由党分裂を促すことができると判断した[110]。
そうした意図から1905年12月4日付けでバルフォア内閣は総辞職した[110]。
野党党首として

1906年総選挙に惨敗
首相退任後もバルフォアは5年にわたって保守党党首職に在任した。バルフォアに代わって大命を受けた自由党党首キャンベル=バナマンは、少数与党の状況を脱するべく、1906年1月にも解散総選挙に打って出た。この選挙の争点はアイルランド問題ではなく、関税問題や中国人奴隷問題となり、保守党と自由統一党は庶民・労働者層の反発を買って苦しい選挙戦を強いられた。結局自由党が377議席に大躍進する一方、改選前に401議席を持っていた保守党・自由統一党は、157議席に激減した[111]。党首バルフォア自身もこれまでのマンチェスター・イースト選挙区では落選するという屈辱を喫し[112]、シティ・オブ・ロンドン選挙区に転じて再選を果たしている[3]。
この惨敗っぷりは保守党の歴史にかつてないものだった(これまでの保守党の最低記録は1832年総選挙の際の185議席)[113]。しかも当選した157人のうち、109人の議員は関税改革論者だったため、保守党は惨敗に懲りずに保護貿易主義に傾いていくことになった。バルフォアもそれまでの折衷主義を弱めて関税改革路線に傾いていった[114]。
貴族院を使って反政府闘争
ジョゼフ・チェンバレンが病に倒れたせいもあって彼の党内における力は強化されていたが、庶民院において自由党が圧倒的多数を占めていたためできることは限られていた。このためバルフォアは保守党貴族院院内総務のランズダウン侯爵と協力し、貴族院議員を使って自由党の政策や法案に抵抗するようになった[115]。
早くも1906年4月には初等教育から宗教教育を排除することを目的とした「教育法案」を貴族院で葬った。これに反発した首相キャンベル=バナマンや急進派閣僚の通商大臣ロイド・ジョージは貴族院改革の意を強めた[116]。キャンベル=バナマンは1907年6月にも庶民院の優越を定める法律を制定すべきとする決議案を議会に提出し、その決議案説明の中でロイド・ジョージは「貴族院は長きにわたり、憲法の番犬だったが、今やバルフォアのプードルである。彼のために吠え、使い走りをし、彼がけしかけたどのような物にも噛みつく」と怒りを露わにした[115]。
だがバルフォアは態度を翻すことはなく、首相がアスキスに変わった後の1908年7月にも醸造業者の独占制限を目的とする「酒類販売免許法案」を貴族院で否決させた[117]。この際に急進派閣僚の通商大臣ウィンストン・チャーチルは「我々は貴族院を震え上がらせるような予算案を提出するであろう。貴族院は階級闘争を開始したのだから」と語ったという[117]。
「人民予算」をめぐって

大蔵大臣ロイド・ジョージは保守党の支持基盤である地主・土地貴族に打撃を与えるべく、「人民予算」(People's Budget)と呼ばれることになる予算案の作成を開始した[118]。
この「人民予算」に含まれる土地課税は「土地の国有化を企むものである」と地主・土地貴族が強く反発した。彼らの声を代弁するバルフォアら保守党政治家も当然この予算案に強く反対し、、「赤旗の予算(The Red Flag Budget)」と批判した[119]。自由党内のホイッグ派(土地貴族が多い)も保守党と声を合わせるようになったため、結局土地課税についてはロイド・ジョージ自身が骨抜き修正している[120]。それにも関わらず、「人民予算」は1909年11月に庶民院の第三読会を通過した後、貴族院から激しい反発にあった。彼らはなおも土地の国有化につながる法案と信じていた。バルフォアも11月28日に「貴族院は法案を否決すべきである」と演説した[121][注釈 7]。
11月30日に貴族院は賛成75、反対350という圧倒的大差で「人民予算」を否決した[122]。貴族院が金銭法案を否決するのは17世紀以来のことだった[123]。これを受けてアスキス首相は庶民院を解散し、総選挙に打って出た[122]。1910年1月の解散総選挙でバルフォアは「貴族院の権限縮小反対」「関税改革」「海軍拡張」の3つを保守党の公約に掲げた[124]。このうち関税改革は「関税改革が失業を減少させる」というスローガンとセットにして行った。これは労働者層の支持を取り戻すのにかなり役立ったと見られている[125]。選挙の結果は自由党275議席、保守党273議席、アイルランド国民党82議席、労働党40議席となった。前回比で自由党は104議席も減らし、保守党はかなり失地回復を果たした[126]。
だがキャスティング・ボートを握ったアイルランド国民党が「人民予算」を支持したため、自由党政権は引き続き「人民予算」の可決成立を目指した。バルフォアの「人民予算」に対する態度が依然として強硬と見たアスキス首相は1910年2月に貴族院の権限を縮小する貴族院改革法案(議会法)を一緒に提出した。これを警戒したバルフォアは1910年4月に「人民予算」を採決なしで貴族院を通過させる妥協姿勢をとった[127]。
貴族院改革をめぐって
1910年5月6日のエドワード7世の崩御、新王ジョージ5世の即位に伴う自由党と保守党の融和ムードの中で両党の会合が持たれた[128]。この際にロイド・ジョージはバルフォアに連立内閣を提唱してきた。バルフォアはこれに前向きだったが、自由党政権はアイルランド国民党との連携のためにアイルランド自治法案を出してくる可能性が高かったので、もし大連立など組んだら保守党は分裂するという意見が党内には多かった。1910年11月までには両党の交渉は決裂に終わった[129]。
この決裂で貴族院改革法案を目指すことにしたアスキス首相は、ジョージ5世から「総選挙を行って勝利した場合には貴族院改革法案に賛成する新貴族議員を大量に任命する」という確約を得て、11月26日にもこの年二度目の庶民院解散に打って出た。こうして行われた12月の総選挙の結果は自由党272議席、統一党272議席、アイルランド国民党84議席、労働党42議席と前回総選挙とほとんど変わらないものだった[130]。得票率で見ると保守党は自由党に優っていた[131]。
しかしアスキス首相は1911年2月21日の新議会で自党と友党アイルランド国民党があわせて過半数を制したので貴族院改革の国民のコンセンサスは得たと力説し、議会法を再度議会に提出してきた[130]。法案は5月15日に庶民院を通過したが、貴族院は断固反対の姿勢を示した。これを見たアスキス首相は、もし貴族院がこの法案を通過させないなら国王大権によって貴族院改革に賛成する新貴族院議員を大量に任命する方針とそれについて国王の承諾を得ている旨を7月20日にバルフォアら保守党執行部に付きつけた[132]。
これを受けてバルフォアは7月21日にもシャドー・キャビネット(影の内閣)に所属する保守党幹部を召集して対策を話し合った。バルフォアやランズダウン侯爵、カーゾン卿は「貴族の大量任命など行われたら世界中の文明国の笑い物になる」として譲歩するしかないと主張したが、ハルズベリー卿やセルボーン卿、オースティン・チェンバレンらは徹底抗戦すべしと主張して意見は分かれた[133]。だがやがて主戦派の意見が強まり、妥協派のバルフォアは焦った[134]。
しかもアスキス内閣は新貴族院任命の方針を覆す意思を見せず、8月10日には議会法案の貴族院提出を強行し、その法案説明で「議会法を否決する投票は、すなわち多数の新貴族任命への賛成票ということになる」と明言してきた。バルフォアの息のかかった妥協派貴族院議員たちは当初棄権を考えていたが、棄権すると議会法案否決の公算が高いため、ついにこの法案賛成に回る決意を固めた。これにより議会法案は賛成131、反対114の僅差でなんとか貴族院を通過した[135]。
これにより貴族院の権限は大幅に縮小され、さらに貴族院議員の新規叙任が制限されることになった。この結果に党内から不満が噴出し、党の分裂は深刻化した。バルフォアの指導力に疑問が呈されるようになり、それを収拾するため、1911年11月8日にバルフォアは健康上の理由として保守党党首職を辞した[136][137]。後任の保守党党首は決まっていなかったが、最終的には関税改革派・親アルスター派の論客として名を馳せていたアンドルー・ボナー・ローが選出された[138][137]。
党首退任後

しかしながらバルフォアが党内における重鎮であることには変わりなかった。1915年5月にハーバート・ヘンリー・アスキス首相が保守党・自由党の大連立による挙国一致内閣の第2次アスキス内閣を組閣すると、ガリポリの戦いで失態を犯したウィンストン・チャーチルの後任として海軍大臣となった[139]。
1916年に第2次アスキス内閣が倒れた後に成立したロイド・ジョージ内閣でも彼はエドワード・グレイの後任の外務大臣に任命された。外務大臣としてのバルフォアはウォルター・ロスチャイルドに対してパレスチナにおけるユダヤ人国家建設への援助を約束する書簡を送った(バルフォア宣言)ことで最も知られている[140]。
1919年のパリ講和会議にも出席し、10人会議のメンバーの一人となった[10]。この会議の結果ヴェルサイユ条約が調印されるとバルフォアは外務大臣を辞任したが、その後の平時内閣においても枢密院議長として閣僚に留まった。また1921年から1922年のワシントン会議にはイギリス代表として出席している[10]。
1922年にロイド・ジョージ内閣が総辞職すると、バルフォアは保守党内の職も辞した。またこの年の5月5日にバルフォア伯爵、トラップレイン子爵(Viscount Traprain)に叙され貴族院に列した[3]。1923年にアンドルー・ボナー・ローの後任として首相に任命されたスタンリー・ボールドウィンはバルフォアに対して入閣の意思を尋ねたが彼は断った。しかし1925年に彼は前年に死去した初代ケドルストンのカーゾン侯爵ジョージ・カーゾンの後任として再び枢密院議長となった。 バルフォアは1929年に政界引退したが[10]、その翌年の1930年3月19日にサリー州ウォーキングにある弟の住居で死去した[141]。故郷のウィッティングハムに葬られた。生涯独身であったため、爵位は弟ジェラルドに継承された。
人物・評価

身長6フィート(1.82cm)以上の長身であり、髪の色は褐色、眼の色はブルーだった[13]。
大変なインテリで読書家だった[142]。哲学書と神学書を中心に、探偵小説や科学書、フランスの小説もよく読んだ。しかし新聞は読もうとしなかったという[143]。
スポーツマンでもあり、テニス、サイクリング、ゴルフなどに熱中していた[144][145]。とりわけゴルフの腕前は高く、1894年にはロイヤル・アンド・エンシェント・ゴルフ・クラブ・オブ・セント・アンドリュースのキャプテンとなった[146]。ハンディは5の腕前であったという[147][144]。バルフォアはゴルフについて次のように語っている。「筋肉と頭脳がかくも融合されたゲームは他にない。私にとって重要なものは食事、睡眠、ゴルフである」[147]、「紳士はゴルフをする。例えはじめた時には貴方が紳士でないとしても、この厳しいゲームをやっていれば必ずや紳士となるであろう」[144]、「ゴルフは三回楽しめるスポーツである。すなわちコースへ行く前、プレイ中、プレイ後である。その内容は期待、絶望、後悔と変化するが」[144]。首相たる彼があまりにゴルフに熱中するので社交界もつられてゴルフに熱中するようになり、「スコットランド式クローケー」などとバカにされていたゴルフの名声が高まっていったという[145]。
紳士的な礼儀正しい人だったという[48]。容姿端麗で家柄や財産も申し分ないから、当然女性にもてたし、結婚のチャンスも数多くあったが、ついに結婚しなかった。バルフォアは学生時代にグラッドストンの姪にあたる女性と婚約していたが、その女性は若くして死去しており、これを引きずって結婚を避けているのではと噂されていた[148][8]。保守党の政治家ながら1900年代以降に盛り上がってきた婦人参政権獲得運動には割と好意的な立場をとっていた。これに対してバルフォアの後任の保守党党首アンドルー・ボナー・ローは慎重派だった[149]。
政敵の自由党党首ウィリアム・グラッドストンによればバルフォアは叔父のソールズベリー侯爵と気質がよく似ており、違いは「大胆さの面で甥が若干勝る。知能と辛辣さは叔父が若干勝る」ことだという[20]。
同じく政敵の自由党議員ウィンストン・チャーチルは、バルフォアについて危機を前にしても動じない性格に注目し、「バルフォアは現在もっとも勇気のある男だ。たとえ鼻先にピストルを付きつけられてもうろたえまい」と称賛しつつ、「バルフォアがびくつかないのは冷酷さのせいだ」とも述べている[150]。自由党の首相アスキス夫人マーゴットはバルフォアが決して動じない理由について「問題を真剣には気にかけていないか、事がどっちへ進もうが、それに人類の幸福がかかっているとは信じていないかのどちらかであろう」と主張している[151]。
エドワード7世はバルフォアに好意を持たなかったが、ヴィクトリア女王からは高く評価されていた。女王は「彼は問題のあらゆる側面を見ることができ、他の人々に対する感情において素晴らしく寛大である」と述べている[152]。
哲学者としてのバルフォア
バルフォアは1879年に初めての著書『哲学的懐疑の擁護(Defence of Philosophic Doubt)』を出版した[4]。この著作のタイトルのためにバルフォアは不可知論の擁護者であるという評判が広まったが、実際にはこの著作は物質的実在への疑念を主張することで宗教を擁護したものだった[8]。バルフォアの哲学への主たる関心は信仰の基盤を現代社会の中に発見することにあり、そのため自然主義に反発し、人は科学に対してそうであるように宗教に対しても疑念を持ってはならないと考えた[4]。この立場は1895年の主著『信仰の基礎』でも踏襲されている[8]。この著作はアマチュアのレベルを超えて学術レベルに達していると高く評価されている[6]。
こうした哲学や宗教への深い関心から『旧約聖書』のヘブライズムに惹かれ、「キリスト教は計り知れないほど数多くの物をユダヤ教に負っているのに、恥ずかしいことにほとんどお返しができていない」と考えていた。それがシオニズムへの共感とバルフォア宣言の背景になったといわれる[153][154]。
バルフォアの哲学に関する著作には以下のような物がある。
- 哲学的懐疑の擁護(Defence of Philosophic Doubt) (1879年)
- 評論と演説(Essays and Addresses) (1893年)
- 信仰の基盤(The Foundations of Belief) (1895年)
- 美しさと批判の探究心(Questionings on Criticism and Beauty) (1909年)
- 内政の側面(Aspects of Home Rule) (1913年)
- 有神論とヒューマニズム(Theism and Humanism) (1915年)
- 思索的及び政治的評論(Essays Speculative and Political) (1921年)
- 有神論と思想(Theism and Thought) (1923年)
シャーロック・ホームズとバルフォア
小説家コナン・ドイルが生み出した名探偵シャーロック・ホームズが活躍した時代は、主にソールズベリー侯爵内閣期だが、続くバルフォア内閣期の1903年にも多くの事件を手がけたという設定になっている(同時にこの年にホームズは引退する)[155]。
『マザリンの宝石』(『シャーロック・ホームズの事件簿』収録)の依頼人は英国首相であるが、これは1903年の事件と言われており、それが正しければ依頼人の首相というのはバルフォアということになる。作中でビリー少年は首相のことを「付き合いやすそうな人」と評している[156]。
同じく『海軍条約文書事件』(『シャーロック・ホームズの思い出』収録)に登場する外務大臣ホールドハースト卿はソールズベリー侯の変名と言われており(ホームズ小説はワトスンの著作という形式をとっているため、ワトスンが当人に配慮して変名にしていると考える余地がある)、そうだとすれば、その甥という設定で登場する依頼人パーシー・フェルプスはバルフォアの変名である可能性が高い[157]。作中でフェルプスの住居はウォーキングに設定されていたが、ここはバルフォアの弟の住居がある場所であり、バルフォアの最期の地でもある[141]。
脚注
注釈
- ^ 各省庁の大臣を補佐する庶民院議員の役職。各省庁の政務次官とは違い、政府の役職ではない。若手議員が選ばれることが多い[12]。
- ^ この戯画に描かれる通りバルフォアは議場でちゃんと座っていることが少なく、身体を水平に近い状態にして座っていることが多かった[13]。
- ^ この法案の説明の中でバルフォアはアイルランドの現況を次のように分析している。「イングランドとスコットランドでは地主階級は、土地の耕作に従事している二つの階級の福祉に貢献しているといえる。地主階級がいなければ、農業労働者階級は良い住居や良い賃金、適切な割り当て地(allotments)を受けることは不可能であろうし、また借地農階級は地主階級がいなかったら、土地を経営するための流動資本(The working capital)だけでなく、固定資本(The fixed capital)まで提供せねばならなくなるからだ。ところがアイルランドではこうした地主の機能がイングランドほど有効に発揮されていない。もともとアイルランドには地主が恒久的改良(permanent improvements)や農業労働者用の住居を提供するという慣行がない上、政治状況のせいで地主が有益な影響力を行使する可能性を奪われているからだ。そのためアイルランドにおいては自作農を増やすことが望ましい」[29]。
- ^ 天津―鎮江線、山西河南―揚子江線、九竜―広東線、浦口―信陽線、蘇州―杭州―寧波線の5本の鉄道[40]。
- ^ この時代には形骸化していたとはいえ、いまだチベットは形式的には清の宗主権下にあり、清からアンバンと呼ばれる総督が派遣されていた[91]。
- ^ 一方外相ランズダウン侯爵はこのバルフォアの考えに反対した。彼は日露開戦の場合、ロシアは地中海の艦隊を投入するだろうから日本の海軍力は完全に粉砕されてしまい、以降日本はロシアにとって何の害もない存在に落ちぶれるであろうと予測していた[101]。
- ^ これについてカーゾン卿は「バルフォアが人民予算を葬ろうとした理由は二つある。一つは貴族院がその予算案を可決すれば、この国の憲法を実施・運営する場合の大きな変化を初めてもたらすことになること、もう一つは本予算案を否決することは関税改革の擁護に結び付くからである。つまり本法案が否決されれば本予算で見積もられた財源を他から求めざるを得なくなり、その新しい財源として関税が浮上してくるからである」と分析している[122]。
出典
- ^ a b 秦(2001) p.511
- ^ 秦(2001) p.512
- ^ a b c d e f g h i HANSARD 1803–2005
- ^ a b c d e 世界伝記大事典(1981)世界編8巻 p.27
- ^ a b c d e タックマン(1990) p.57
- ^ a b c d e f 平賀(2012) p.172
- ^ タックマン(1990) p.10
- ^ a b c d e タックマン(1990) p.58
- ^ "Balfour, Arthur (BLFR866AJ)". A Cambridge Alumni Database (英語). University of Cambridge.
- ^ a b c d e f 世界伝記大事典(1981)世界編8巻 p.28
- ^ 坂井(1967) p.46-47
- ^ a b c d e f g マッケンジー(1965) p.33
- ^ a b タックマン(1990) p.56
- ^ 小関(2006) p.32
- ^ ブレイク(1979) p.163
- ^ ブレイク(1979) p.164
- ^ マッケンジー(1965) p.227-228
- ^ 小関(2006) p.64
- ^ 平賀(2012) p.174-175
- ^ a b c d 神川(2011) p.412
- ^ From Aristotelian to Reaganomics: A Dictionary of Eponyms With Biographies in the Social Science, by R. C. S. Trahair, Greenwood Publishing Group, 1994, page 72. Retrieved online from Google Books, Jul 30, 2012.
- ^ a b c タックマン(1990) p.63
- ^ 神川(2011) p.411-412
- ^ 神川(2011) p.413-414
- ^ a b c 神川(2011) p.414
- ^ a b 小関(2006) p.324
- ^ 神川(2011) p.415
- ^ 高橋(1997) p.79
- ^ 高橋(1997) p.80
- ^ 高橋(1997) p.77/83
- ^ a b 高橋(1997) p.85
- ^ a b c 高橋(1997) p.84
- ^ 高橋(1997) p.86
- ^ マッケンジー(1965) p.33-34
- ^ タックマン(1990) p.60
- ^ 平賀(2012) p.175
- ^ 坂井(1967) p.233-234
- ^ 坂井(1967) p.267
- ^ 坂井(1967) p.269
- ^ a b 坂井(1967) p.274
- ^ 坂井(1967) p.269-270
- ^ a b 坂井(1967) p.283
- ^ 坂井(1967) p.323
- ^ 村岡、木畑(1991) p.229
- ^ トレヴェリアン(1975) p.185
- ^ 坂井(1967) p.323-325
- ^ a b c 村岡、木畑(1991) p.230
- ^ a b c ブレイク(1979) p.203
- ^ マッケンジー(1965) p.34
- ^ マッケンジー(1965) p.34-35
- ^ 高橋(1997) p.93
- ^ 高橋(1997) p.99
- ^ 高橋(1997) p.106
- ^ 高橋(1997) p.100-101
- ^ 高橋(1997) p.103
- ^ 高橋(1997) p.103-104
- ^ 高橋(1997) p.101
- ^ トレヴェリアン(1975) p.186
- ^ a b ブレイク(1979) p.208
- ^ 坂井(1967) p.205
- ^ a b c 坂井(1967) p.208
- ^ a b 池田(1962) p.153-154
- ^ ブレイク(1979) p.210
- ^ a b ブレイク(1979) p.212
- ^ a b 村岡、木畑(1991) p.231
- ^ a b 坂井(1967) p.209
- ^ 池田(1962) p.152-153
- ^ a b 坂井(1967) p.212
- ^ 池田(1962) p.156
- ^ 河合(1998) p.79
- ^ a b 池田(1962) p.157
- ^ 坂井(1967) p.211-212
- ^ a b 坂井(1967) p.211
- ^ ブレイク(1979) p.214
- ^ 坂井(1967) p.214
- ^ ブレイク(1979) p.213
- ^ ブレイク(1979) p.213-214
- ^ 市川(1982) p.156
- ^ a b c ブレイク(1979) p.206
- ^ ブレイク(1979) p.207
- ^ ブレイク(1979) p.207-208
- ^ 坂井(1967) p.224
- ^ トレヴェリアン(1975) p.191
- ^ モリス(2010)上巻 p.182
- ^ モリス(2010)上巻 p.184-185
- ^ モリス(2010)上巻 p.184
- ^ モリス(2010)上巻 p.187-190
- ^ モリス(2010)上巻 p.191
- ^ モリス(2010)上巻 p.196-203
- ^ モリス(2010)上巻 p.201-202
- ^ モリス(2010)上巻 p.185
- ^ モリス(2010)上巻 p.207
- ^ モリス(2010)上巻 p.208
- ^ 坂井(1967) p.307-309
- ^ 坂井(1967) p.307-308
- ^ 坂井(1967) p.308-309
- ^ 坂井(1967) p.306-307
- ^ a b c 坂井(1967) p.309
- ^ 坂井(1967) p.310
- ^ 坂井(1967) p.311
- ^ a b 君塚(2012) p.152
- ^ 坂井(1967) p.312
- ^ 君塚(2012) p.163-164
- ^ 君塚(2012) p.166
- ^ 君塚(2012) p.166-167
- ^ 君塚(2012) p.175-176
- ^ 君塚(2012) p.172
- ^ 坂井(1967) p.218
- ^ 坂井(1967) p.218-219
- ^ a b 坂井(1967) p.219
- ^ 坂井(1967) p.340-342
- ^ 坂井(1967) p.340
- ^ ブレイク(1979) p.218
- ^ ブレイク(1979) p.215
- ^ a b 坂井(1967) p.416-417
- ^ 坂井(1967) p.416
- ^ a b 坂井(1967) p.417
- ^ 坂井(1967) p.417-418
- ^ 坂井(1967) p.420
- ^ 坂井(1967) p.420-421
- ^ 坂井(1967) p.427-428
- ^ a b c 坂井(1967) p.428
- ^ 河合(1998) p.118
- ^ 坂井(1967) p.429
- ^ 坂井(1967) p.431
- ^ 坂井(1967) p.434
- ^ 坂井(1967) p.447-448
- ^ 坂井(1967) p.448-449
- ^ 坂井(1967) p.452
- ^ a b 坂井(1967) p.455
- ^ 村岡、木畑(1991) p.241
- ^ 坂井(1967) p.456
- ^ 坂井(1967) p.457
- ^ 坂井(1967) p.458
- ^ 坂井(1967) p.459-460
- ^ ブレイク(1979) p.229
- ^ a b 坂井(1967) p.497
- ^ ブレイク(1979) p.230-231
- ^ 河合(1998) p.159
- ^ 平賀(2012) p.178-179
- ^ a b 平賀(2012) p.185
- ^ 平賀(2012) p.179
- ^ タックマン(1990) p.65-66
- ^ a b c d 平賀(2012) p.174
- ^ a b タックマン(1990) p.65
- ^ 夏坂(1997) p.24
- ^ a b 夏坂(1997) p.23
- ^ 平賀(2012) p.173
- ^ 村岡、木畑(1991) p.247
- ^ タックマン(1990) p.63-64
- ^ タックマン(1990) p.62
- ^ タックマン(1990) p.66
- ^ 平賀(2012) p.178
- ^ タックマン(1990) p.59
- ^ 平賀(2012) p.152
- ^ 平賀(2012) p.152/175
- ^ 平賀(2012) p.182-183
参考文献
- 池田清『政治家の未来像 ジョセフ・チェムバレンとケア・ハーディー』有斐閣、1962年(昭和37年)。ASIN B000JAKFJW。
- 市川承八郎『イギリス帝国主義と南アフリカ』晃洋書房、1982年(昭和57年)。ASIN B000J7OZW8。
- 神川信彦 著、君塚直隆監修 編『グラッドストン 政治における使命感』吉田書店、2011年(平成13年)。ISBN 978-4905497028。
- 河合秀和『チャーチル イギリス現代史を転換させた一人の政治家 増補版』中央公論社〈中公新書530〉、1998年(平成10年)。ISBN 978-4121905307。
- 君塚直隆『ベル・エポックの国際政治 エドワード七世と古典外交の時代』中央公論新社、2012年(平成24年)。ISBN 978-4120044298。
- 小関隆『プリムローズ・リーグの時代 世紀転換期イギリスの保守主義』岩波書店、2006年(平成18年)。ISBN 978-4000246330。
- 坂井秀夫『政治指導の歴史的研究 近代イギリスを中心として』創文社、1967年(昭和42年)。ASIN B000JA626W。
- 高橋純一『アイルランド土地政策史』社会評論社、1997年(平成9年)。ISBN 978-4784508587。
- バーバラ・タックマン 著、大島かおり 訳『世紀末のヨーロッパ 誇り高き塔・第一次大戦前夜』筑摩書房、1990年(平成2年)。ISBN 978-4480855541。
- G.M.トレヴェリアン 著、大野真弓 訳『イギリス史 3』みすず書房、1975年(昭和50年)。ISBN 978-4622020370。
- 夏坂健『騎士たちの一番ホール 不滅のゴルフ名言集』日本ヴォーグ&スポーツマガジン社、1997年(平成9年)。ISBN 978-4529028110。
- 平賀三郎『ホームズの不思議な世界』青弓社、2012年(平成24年)。ISBN 978-4787292094。
- ブレイク男爵 著、早川崇 訳『英国保守党史 ピールからチャーチルまで』労働法令協会、1979年(昭和54年)。ASIN B000J73JSE。
- ロバート・マッケンジー 著、早川崇、三沢潤生 訳『英国の政党〈上巻〉 保守党・労働党内の権力配置』有斐閣、1965年(昭和40年)。ASIN B000JAD4LI。
- ジャン・モリス 著、椋田直子 訳『帝国の落日 上巻』講談社、2010年(平成22年)。ISBN 978-4062152471。
- 『世界伝記大事典〈世界編 8〉ハルーフユ』ほるぷ出版、1981年(昭和56年)。ASIN B000J7VF5S。
- 秦郁彦編 編『世界諸国の組織・制度・人事 1840―2000』東京大学出版会、2001年(平成13年)。ISBN 978-4130301220。
外部リンク
- Hansard 1803–2005: contributions in Parliament by Mr Arthur Balfour
- "アーサー・バルフォアの関連資料一覧" (英語). イギリス国立公文書館.
- Arthur James Balfour, 1st Earl of Balfour - ナショナル・ポートレート・ギャラリー
- Arthur James Balfour - Find a Grave

