利用者:チョコレート10/sandbox014
 |
ここはチョコレート10さんの利用者サンドボックスです。編集を試したり下書きを置いておいたりするための場所であり、百科事典の記事ではありません。ただし、公開の場ですので、許諾されていない文章の転載はご遠慮ください。
登録利用者は自分用の利用者サンドボックスを作成できます(サンドボックスを作成する、解説)。 その他のサンドボックス: 共用サンドボックス | モジュールサンドボックス 記事がある程度できあがったら、編集方針を確認して、新規ページを作成しましょう。 |
利用者:チョコレート10/sandbox
[編集]利用者:チョコレート10/sandbox en:History of liberalism
リベラリズムの歴史
[編集]| 自由主義 |
|---|
リベラリズムは、自由、平等、民主主義、そして人権を信じる思想であり、歴史的にはジョン・ロックやモンテスキューのような思想家と結びついている。また、立憲君主制によって君主の権力を制限し、議会の優位性を確立し、権利章典を可決し、「被治者の同意」の原則を確立することとも関連している。1776年のアメリカ独立宣言は、世襲貴族制の重荷なしに、リベラルな原則に基づいて新生共和国を設立した。宣言は「すべての人間は平等に創造され、創造主によって一定の譲渡不可能な権利を与えられており、その中には生命、自由、幸福の追求が含まれる」と述べている。[1] その数年後、フランス革命は世襲貴族制を打倒し、「自由・平等・友愛」のスローガンを掲げ、歴史上初めて普通男子選挙権を付与した国家となった。1789年にフランスで最初に成文化された人間と市民の権利の宣言は、リベラリズムと人権の両方の基本的文書であり、1776年に書かれたアメリカ独立宣言に基づいている。啓蒙主義時代の知的進歩は、社会や政府に関する古い伝統に疑問を投げかけ、最終的に強力な革命運動へと結集し、フランス人がアンシャン・レジームと呼んだ絶対王政と国教の信念を打倒した。これは特にヨーロッパ、ラテンアメリカ、北アメリカで顕著であった。
オレンジ公ウィリアムは名誉革命で、トマス・ジェファーソンはアメリカ革命で、ラファイエットはフランス革命で、リベラルな哲学を用いて、彼らが専制的と見なした支配の武力による打倒を正当化した。19世紀には、ヨーロッパ、南アメリカ、北アメリカの国々でリベラルな政府が樹立された。[2] この時期、古典的リベラリズムの主要なイデオロギー的対抗勢力は保守主義であったが、リベラリズムはその後、ファシズムや共産主義といった新たな対抗勢力からの重大な思想的挑戦を乗り越えた。リベラルな政府は、アダム・スミス、ジョン・スチュアート・ミルらが提唱した経済理論を採用することが多く、これらの理論は広く自由市場と自由放任主義の統治の重要性を強調し、貿易への干渉を最小限に抑えることを主張した。
19世紀から20世紀初頭にかけて、オスマン帝国と中東では、リベラリズムがタンズィマートやナフダなどの改革期や、世俗主義、立憲主義、ナショナリズムの台頭に影響を与えた。これらの変化は、他の要因とともに、現在まで続くイスラム教内部の危機感を生み出すことに寄与した。これはイスラム復興主義につながった。20世紀には、リベラル・デモクラシーが両世界大戦で勝利した側に立ったことで、リベラルな思想がさらに広まった。ヨーロッパと北アメリカでは、社会的リベラリズム(アメリカではしばしば単に「リベラリズム」と呼ばれる)の確立が、福祉国家の拡大における重要な要素となった。[3] 今日、リベラル政党は世界中で権力を握り、支配力と影響力を持ち続けているが、ラテンアメリカ、アフリカ、アジアではまだ克服すべき課題が残されている。現代リベラル思想と運動の後の波は、市民権を拡大する必要性に強く影響された。[4] リベラリストたちはジェンダー平等、婚姻の平等、人種平等を提唱し、20世紀の市民権のための世界的な社会運動は、これらの目標に向けていくつかの目的を達成した。
初期の歴史
[編集]

自由主義的思想の孤立した要素は、中国の春秋時代以来の東洋哲学[5]や古代ギリシア以来の西洋哲学に存在していたが、自由主義政治の主要な兆候は近代になって初めて現れた。経済学者マレー・ロスバードは、中国の道教哲学者老子を最初のリバタリアンであると主張し[5]、老子の政府に関する考えをフリードリヒ・ハイエクの自生的秩序理論に類似していると評した[6]。ロックの自由主義的概念の多くは、当時自由に議論されていた急進的な思想の中に予見されていた[7]。パンフレット作家のリチャード・オーバートンは次のように書いている:「自然によって各個人に与えられた個人的財産は、誰にも侵害されたり奪われたりしてはならない...。誰も私の権利と自由に対する権力を持たず、私も他人の権利と自由に対する権力を持たない」[7]。これらの思想は、近代自由主義の父と一般的に見なされるイギリスの哲学者ジョン・ロックによって、初めて明確なイデオロギーとして統合された[8][9]。ロックは、政府は統治される者の同意を得なければならず、その同意は政府が正当性を保つために常に存在しなければならないという急進的な概念を発展させた[10]。彼の影響力のある『統治二論』(1690年)は、自由主義イデオロギーの基礎となる文献であり、彼の主要な思想を概説している[11]。合法的な政府が超自然的な基盤を持たないという彼の主張は、それまでの統治理論からの大きな転換であった[12][13]。ロックはまた、教会と国家の分離の概念を定義した[14]。社会契約の原則に基づき、ロックは良心の自由への自然権が存在し、それゆえにいかなる政府の権威からも保護されるべきだと主張した[15]。また、彼の『寛容についての書簡』において、宗教的寛容の一般的な擁護論を formulated した[16]。ロックは、あらゆる形態の自由の熱心な擁護者であったジョン・ミルトンの自由主義的思想の影響を受けていた[17]。
ミルトンは、広範な寛容を達成する唯一の効果的な方法として国教会制度の廃止を主張した[18]。彼の『アレオパジティカ』において、ミルトンは言論の自由の重要性について最初の議論の一つを提供した—「すべての自由の上に、良心に従って知り、発言し、自由に議論する自由」。アルジャノン・シドニーは、18世紀のイギリスとアメリカ植民地における自由主義的政治思想への影響力においてジョン・ロックに次ぐ存在であり、名誉革命時のホイッグ党の反対派によって広く読まれ、引用された[19]。シドニーの「自由な人々は常に専制的な政府に抵抗する権利を持つ」という主張は、アメリカ革命戦争時の愛国者たちによって広く引用され[20]、トマス・ジェファーソンは、シドニーを建国の父たちの自由観の二大源泉の一つと考えていた[21]。シドニーは絶対君主制を大きな政治的悪とみなし、彼の主要著作『政府論』は、排除危機の間にロバート・フィルマーの『父権論』(王権神授説の擁護論)への反論として書かれた。シドニーはフィルマーの反動的原則を断固として拒否し、君主の臣民は助言と counsel を通じて政府に参加する権利を持つと主張した。
名誉革命
[編集]
西洋哲学において古代ギリシア以来存在していた自由主義思想の孤立した要素は、イングランド内戦の時期に結集し始めた。議会とチャールズ1世の間の政治的優位性をめぐる争いは、1640年代に大規模な内戦を引き起こし、チャールズの処刑と共和制の樹立に至った。特に、当時の急進的政治運動である平等派は、彼らの宣言『人民協約』を発表し、人民主権、拡大された選挙権、宗教的寛容、法の下の平等を提唱した。自由主義思想の影響は17世紀のイングランドで着実に増大し、1688年の名誉革命で頂点に達した。この革命は議会主権と革命の権利を確立し、多くの人が最初の近代的、自由主義的国家と考えるものの設立につながった[22]。この時期の重要な立法上のマイルストーンには、十分な理由や証拠なしの拘留を禁じる慣行を強化した人身保護法(1679年)が含まれる。権利章典は正式に法と議会の君主に対する優位性を確立し、すべてのイングランド人のための基本的な権利を規定した。この法案は、君主による法や議会選挙への干渉を違法とし、新たな税の実施には議会の同意を必要とし、平時における議会の同意なしでの常備軍の維持を違法とした。君主に請願する権利がすべての人に与えられ、あらゆる状況下で「残虐で異常な刑罰」が違法とされた[23][24]。これに続いて1年後に寛容法が制定され、その思想的内容はジョン・ロックの宗教的寛容を提唱する4通の書簡から引き出されたものであった[25]。この法律は、国教会への忠誠と至上権の宣誓を行う非国教徒に礼拝の自由を認めた。1695年には、下院が出版許可法の更新を拒否し[26]、これによって前例のない出版の自由の継続的な期間が始まった。
啓蒙時代
[編集]18世紀の啓蒙時代は、自由主義思想のさらなる発展と普及をもたらした。この時代の思想家たちは、理性と個人の権利を重視し、専制政治や宗教的不寛容に反対する立場を取った。
ジョン・ロックの思想は、フランスの哲学者ヴォルテールによってヨーロッパ大陸に広められた。ヴォルテールは宗教的寛容と言論の自由を強く主張し、教会と国家の分離を支持した。
モンテスキューは『法の精神』(1748年)において、権力分立の理論を発展させた。この理論は後に多くの自由主義的な憲法の基礎となった。
アダム・スミスは『国富論』(1776年)で、自由市場経済の利点を論じ、政府の経済介入を最小限に抑えるべきだと主張した。これは後の経済的自由主義の基礎となった。
アメリカでは、トマス・ジェファーソン、ジェームズ・マディソン、トマス・ペインらが自由主義思想を発展させ、アメリカ革命の思想的基盤を形成した。アメリカ独立宣言(1776年)は、「生命、自由、幸福追求」の権利を不可侵のものとして宣言し、自由主義思想を明確に表現した。
フランスでは、ジャン=ジャック・ルソーの社会契約論がフランス革命に大きな影響を与えた。1789年の人間と市民の権利の宣言は、自由、平等、所有権、安全、圧政への抵抗を基本的人権として定めた。
これらの思想と出来事を通じて、自由主義は18世紀末までに西洋世界で主要な政治的イデオロギーとしての地位を確立した。19世紀に入ると、自由主義は政治制度の改革や社会進歩の原動力となり、多くの国で立憲政府や市民的自由の拡大をもたらすことになる。
フランス啓蒙主義
[編集]
18世紀のフランスの経験は、イングランドとは対照的に、封建制と絶対王政の存続によって特徴づけられた。現状に挑戦する思想は、しばしば厳しく抑圧された。フランス啓蒙主義の哲学者の大半は、自由主義的な意味で進歩的であり、フランスの政治体制をより立憲的で自由主義的な方向へ改革することを提唱した。
モンテスキューは18世紀初頭に一連の非常に影響力のある著作を執筆した。その中には『ペルシア人の手紙』(1717年)や『法の精神』(1748年)が含まれる。後者はフランス国内外で tremendous な影響力を及ぼした。モンテスキューは立憲政治体制の擁護、市民的自由と法の維持、そして政治制度は各コミュニティーの社会的・地理的側面を反映すべきだという考えを主張した。特に、政治的自由には[[:en:separation of powers|権力の分立]が必要であると論じた。ジョン・ロックの『統治二論』を基に、政府の行政、立法、司法の機能を異なる機関に割り当てるべきだと主張した。これにより、政府の一部門が政治的自由を侵害しようとする試みを他の部門が抑制できるようになるとした。彼が深く敬愛していたイギリスの政治体制について長々と論じる中で、君主制においてもこれがいかにして達成され、自由が確保されうるかを示そうとした。また、権力の分立がない場合、共和制であっても自由は確保できないと指摘した。さらに、公正な裁判を受ける権利、無罪推定、刑罰の厳しさにおける比例性を含む、法における堅固な適正手続きの重要性を強調した。
フランス啓蒙主義のもう一人の重要人物はヴォルテールである。当初は、啓蒙された君主が人々の福祉を改善する上で建設的な役割を果たせると信じていたが、やがて新たな結論に達した。「我々自身の庭を耕すべきだ」というものである。実際、不寛容と宗教的迫害に対する彼の最も論争的で激烈な攻撃は、数年後に現れ始めた。[27] 多くの迫害にもかかわらず、ヴォルテールは市民的権利—公正な裁判を受ける権利と信教の自由—のために疲れを知らず闘い、アンシャン・レジームの偽善と不正を告発し続けた勇敢な論客であり続けた。
革命の時代
[編集]アメリカ革命
[編集]
イングランドと13植民地の間の政治的緊張は、1765年以降、七年戦争の後、代表なくして課税なしの問題をめぐって高まり、1776年の新共和国の独立宣言と、合衆国を守るための成功したアメリカ独立戦争に至った。
独立のための知的基盤は、パンフレット作家のトマス・ペインによって提供された。彼の独立支持のパンフレット『コモン・センス』は1776年1月10日に匿名で出版され、即座に成功を収めた。[28] それは軍隊を含め、至る所で朗読された。[29][30] ペインは、複雑な思想を容易に理解できるようにする政治的著述のスタイルを先駆けた。[31]
主にトマス・ジェファーソンによって委員会で起草された独立宣言は、ロックの考えを反映していた。[32] 戦後、指導者たちは今後の進め方について議論した。1776年に書かれた連合規約は、安全保障や機能的な政府さえも提供するには不十分であることが明らかになった。連合会議は1787年に憲法制定会議を招集し、その結果、連邦政府を設立する新しい合衆国憲法が起草された。当時の文脈において、この憲法は共和主義的で自由主義的な文書であった。[33][34] 現在も世界で最も古い有効な自由主義的統治文書である。
アメリカの理論家や政治家たちは、国王の主権ではなく、人民の主権を強く信じていた。ある歴史家の言葉を借りれば、「すべての政府はその正当な権力を被統治者の同意から得るという民主主義理論をアメリカが採用したことは、独立宣言の時点ですでに示されていたが、これは画期的なことであった」。[33][35]
アメリカ革命は、フランス革命とその後のヨーロッパの運動に影響を与えた。[36] 1848年、ドイツの主要な歴史家レオポルト・フォン・ランケは、アメリカの共和主義がヨーロッパの自由主義の発展に重要な役割を果たしたと主張した:
- イギリスの立憲主義を捨て、個人の権利に基づく新しい共和国を創設することで、北アメリカ人は世界に新しい力を導入した。思想は、適切な具体的表現を見出したときに最も急速に広がる。こうして共和主義は我々のロマンス/ゲルマン世界に入ってきた...。この時点まで、君主制が国家の利益に最もよく資するという確信がヨーロッパでは支配的だった。今や国家は自らを統治すべきだという考えが広まった。しかし、代議制の理論に基づいて実際に国家が形成された後にのみ、この考えの完全な意義が明らかになった。その後のすべての革命運動は、この同じ目標を持っている...。これは原理の完全な逆転だった。それまでは、神の恩寵によって統治する王が、すべてが回転する中心だった。今や権力は下から来るべきだという考えが現れた...。これら二つの原理は、二つの対極のようなものであり、それらの間の対立が近代世界の進路を決定する。ヨーロッパでは、この対立はまだ具体的な形を取っていなかった。フランス革命によってそれは具体化した。[37]
フランス革命
[編集]
歴史家たちは、フランス革命を歴史上最も重要な出来事の一つとして広く認識している。[38] 革命はしばしば「近代の幕開け」を示すものとして見られ、[39] その激動は広く「自由主義の勝利」と結びつけられている。[40]
フランス革命から4年後、ドイツの作家ヨハン・フォン・ゲーテはヴァルミーの戦いで敗北したプロイセン兵士たちに「この場所から、そしてこの時から、世界史の新しい時代が始まる。そしてあなたがたはみな、その誕生に立ち会ったと言えるのだ」と語ったと伝えられている。[41] フランス革命の参加型政治を描写して、ある歴史家は「何千人もの男性、そして多くの女性までもが、政治の舞台で直接的な経験を得た。彼らは新しい方法で話し、読み、聞いた。彼らは投票し、新しい組織に加わり、政治的目標のために行進した。革命は伝統となり、共和主義は持続的な選択肢となった」とコメントした。[42] 自由主義者にとって、革命は彼らの決定的な瞬間であり、後の自由主義者たちはフランス革命をほぼ完全に承認した—「その結果だけでなく、行為そのものも」と二人の歴史家が指摘している。[43]
フランス革命は1789年5月の全国三部会の招集から始まった。革命の最初の年には、6月に第三身分のメンバーがテニスコートの誓いを宣言し、7月にはバスティーユ襲撃が起こった。自由主義の勝利を示す二つの重要な出来事は、1789年8月4日の夜に行われたフランスにおける封建制の廃止(これは封建的で古い伝統的な権利や特権、制限の崩壊を示した)と、8月の人間と市民の権利宣言の採択であった。フランス駐在のアメリカ公使ジェファーソンは、その起草に際して意見を求められ、アメリカの『独立宣言』との顕著な類似点が見られる。[44]
その後数年間は、様々な自由主義的な議会と主要な改革を阻止しようとする保守的な君主制との間の緊張によって支配された。1792年9月に共和国が宣言され、翌年にはルイ16世が処刑された。しかし、対立する政治派閥であるジロンド派とジャコバン派の対立は恐怖政治に帰結し、「革命の敵」の大量処刑が行われ、死者数は数万人に達した。[45] 最終的にナポレオンが1799年に政権を掌握し、独裁によってあらゆる形の民主主義を終わらせ、内戦を終結させ、カトリック教会と和解し、ヨーロッパの大部分を征服したが、行き過ぎて1815年に最終的に敗北した。1799年のナポレオンの独裁者としての台頭は、多くの共和主義的・民主主義的成果の逆転を告げるものだった。しかし、ナポレオンはアンシャン・レジームを復活させず、むしろ多くの自由主義的改革を維持し、自由主義的な法典であるナポレオン法典を課した。

ナポレオン戦争の間、フランスは西ヨーロッパに封建制の清算、財産法の自由化、領主制の終焉、ギルドの廃止、離婚の合法化、ユダヤ人ゲットーの解体、異端審問の崩壊、神聖ローマ帝国の最終的な終焉、教会裁判所と宗教権威の廃止、メートル法の確立、そしてすべての男性に対する法の下の平等をもたらした。[46] ナポレオンは「ドイツの人々は、フランス、イタリア、スペインの人々と同様に、平等と自由主義的な思想を望んでいる」と書いた。[47] 一部の歴史家は、彼が政治的な意味で「自由主義的」という言葉を使用した最初の人物かもしれないと示唆している。[47] また、彼はある歴史家が「文民独裁」と呼ぶ方法で統治した。これは「国民投票の形で人々との直接的な協議から正当性を引き出した」ものだった。[48] しかし、ナポレオンは必ずしも自身が掲げた自由主義的な理想を実践しなかった。
フランス国外では、革命は大きな影響を与え、その思想は広く普及した。さらに、1790年代と1800年代のフランス軍は、西ヨーロッパの多くの地域で封建制の残滓を直接的に打倒した。彼らは財産法を自由化し、領主制を終わらせ、起業を促進するために商人と職人のギルドを廃止し、離婚を合法化し、ユダヤ人ゲットーを閉鎖した。異端審問は終わり、神聖ローマ帝国も同様だった。教会裁判所と宗教権威の力は大幅に弱められ、すべての男性に対する法の下の平等が宣言された。[49]
アルツはイタリア人がフランス革命から得た利益を強調している:
- ほぼ20年間、イタリア人は優れた法典、公正な課税制度、より良い経済状況、そして何世紀にもわたって知らなかったほどの宗教的・知的寛容を享受した...。至る所で、古い物理的、経済的、知的障壁が取り払われ、イタリア人は共通の国民性を意識し始めていた。[50]
同様にスイスにおいても、フランス革命の長期的影響はマーティンによって評価されている:
- それは法の下での市民の平等、言語の平等、思想と信仰の自由を宣言した。それは現代の国民性の基礎となるスイス市民権と、旧体制が概念を持っていなかった権力分立を創出した。それは内部関税やその他の経済的制約を廃止した。それは度量衡を統一し、民法と刑法を改革し、(カトリックとプロテスタントの間の)混合婚を許可し、拷問を廃止し、司法を改善した。それは教育と公共事業を発展させた。[51]
彼の最も長続きした功績である民法典は、「全世界で模倣の対象となった」[52]が、同時に「自然の秩序」の旗印の下で女性に対するさらなる差別を永続化させた。[53] この前例のない混沌と革命の時期は、やがて世界中を駆け巡ることになる新しい運動とイデオロギーを不可逆的に世界に紹介した。しかし、フランスにとっては、ナポレオンの敗北がブルボン王政の復古をもたらし、超保守的な秩序が国に再び課せられることとなった。
古典的自由主義
[編集]古典的自由主義の成熟への発展は、フランス革命の前後にイギリスで起こり、古典派経済学、自由貿易、最小限の介入と課税を伴うレッセフェール政府、均衡予算という核心的概念に基づいていた。古典的自由主義者は個人主義、自由、平等な権利に尽力した。ジョン・ブライトやリチャード・コブデンのような著述家は、貴族の特権と財産の両方に反対し、それらを独立自営農民階級の発展を妨げるものとみなした。[54]Template:Incomplete short citation
1800年頃、古典的自由主義者は「自由市場の理論と経済分野における国家の役割縮小」を支持していた。[55]
急進主義
[編集]
急進的自由主義運動は1790年代にイングランドで始まり、自然権と人民主権を強調しながら、議会改革と選挙改革に集中した。リチャード・プライスやジョセフ・プリーストリーのような急進主義者は、議会改革をプロテスタント非国教徒の扱い、奴隷貿易、高物価、高税率など、多くの不満に対処するための第一歩とみなした。[56][要文献特定詳細情報]
トマス・ペインの『人間の権利』(1791年)は、エドマンド・バークの保守主義的エッセイ『フランス革命の省察』からの反応を引き起こした。その後の革命論争には、メアリ・ウルストンクラフトが参加し、初期のフェミニズム論『女性の権利の擁護』を著した。急進主義者は、君主制、貴族制、およびあらゆる形態の特権の拒絶とともに、民主的改革への大衆の支持を奨励した。運動の異なる傾向が発展し、中産階級の改革者たちは、商工業の利益と議会代表のない都市を代表するために選挙権を拡大することを目指す一方で、中産階級と職人から引き出された大衆急進主義者たちは、困窮の救済を含むより広範な権利を主張するために煽動した。選挙改革の理論的基礎は、ジェレミ・ベンサムの功利主義哲学に従う哲学的急進主義者によって提供され、議会改革を強く支持したが、一般的に大衆急進主義者の主張と戦術に敵対的であった。
1821年以降の経済状況の改善、経済法と刑法の改善、抑圧政策の放棄は、二極化の減少とより合意的な改革政治の形態につながり、これが今後2世紀にわたりイギリスを支配することになった。1823年、ジェレミ・ベンサムはジェームズ・ミルと共に『ウェストミンスター・レビュー』を共同創刊し、哲学的急進主義者のための雑誌として功利主義哲学を展開した。
1832年改革法は、公衆の抗議、政治同盟の大規模集会、一部の都市での暴動の支持を得て成立した。これにより中産階級に選挙権が与えられたが、急進派の要求を満たすことはできなかった。改革法の後、下院の主に貴族出身のホイッグ党議員に、少数の議会急進派と増加した中産階級のホイッグ党議員が加わった。1839年までに、彼らは非公式に自由党と呼ばれるようになっていた。自由党は、イギリス最高の首相の一人であるウィリアム・ユーアート・グラッドストーンを輩出した。彼は19世紀の自由主義における巨大な政治的人物としても知られる「グランド・オールド・マン」であった。[57]Template:Incomplete short citation グラッドストーンの下で、自由党は教育改革を行い、アイルランド教会を国教会から切り離し、地方選挙と議会選挙に秘密投票を導入した。
レッセフェール
[編集]
レッセフェールへの尽力は一様ではなかった。一部の経済学者は公共事業や教育に対する国家支援を提唱した。古典的自由主義者は自由貿易についても意見が分かれていた。デイヴィッド・リカードは穀物関税の撤廃が一般的な利益をもたらすかどうか疑問を呈した。ほとんどの古典的自由主義者は、子どもの労働時間を規制する法律を支持し、通常は工場改革法に反対しなかった。[58]Template:Incomplete short citation 古典派経済学者の実用主義にもかかわらず、彼らの見解はジェーン・マーセットやハリエット・マーティノーのような人気のある著述家によって教条的な言葉で表現された。[58]Template:Incomplete short citation レッセフェールの最強の擁護者は、1843年にジェームズ・ウィルソンによって創刊された『エコノミスト』誌であった。『エコノミスト』誌はリカードの自由貿易支持の欠如を批判し、下層階級が自らの経済状況に責任があるという信念から、福祉に対して敵対的な態度を示した。『エコノミスト』誌は、工場労働時間の規制は労働者にとって有害であるという立場をとり、また教育、健康、水の供給に対する国家支援、特許や著作権の付与にも強く反対した。
自由主義経済理論
[編集]
19世紀の自由主義的傾向に対する主要な知的影響は、アダム・スミスと古典派経済学者、そしてジェレミ・ベンサムとジョン・スチュアート・ミルのものであった。スミスの『国富論』は1776年に出版され、1848年のミルの『原理』の出版まで、経済学のほとんどの考えを提供することになった。[59]:63, 68 スミスは経済活動の動機、価格の原因、富の分配、そして国家が富を最大化するために従うべき政策について論じた。[59]:64 スミスの経済学は19世紀に実践され、1820年代の関税引き下げ、1834年の労働の移動を制限していた救貧法の廃止、1858年のインドに対する東インド会社の支配の終結につながった。[59]:69
アダム・スミスの遺産に加えて、セーの法則、マルサスの人口理論、リカードの賃金鉄則が古典派経済学の中心的教義となった。[59]:76 ジャン・バティスト・セーはスミスの労働価値説に挑戦し、価格は効用によって決定されると信じ、また経済における起業家の重要な役割を強調した。しかし、これらの観察はいずれも当時のイギリスの経済学者には受け入れられなかった。トマス・マルサスは1798年に『人口論』を著し、[59]:71–72 古典的自由主義に大きな影響を与えた。[59]:72
功利主義は、1830年代から経済政策を支配することになるイギリス政府による経済的自由主義の実施に対する政治的正当化を提供した。功利主義は立法と行政の改革を促し、ミルの後期の著作はこの主題に関して福祉国家を予見したが、それは主にレッセフェールの正当化として使用された。[60]Template:Incomplete short citation ジェレミ・ベンサムによって発展させられた功利主義の中心概念は、公共政策は「最大多数の最大幸福」を追求すべきというものであった。これは貧困を減少させるための国家の行動を正当化するものとして解釈されうるが、古典的自由主義者によって、全個人に対する純便益がより高くなるという議論で不作為を正当化するために使用された。[59]:76 彼の哲学は政府の政策に非常に影響力があることが証明され、ロバート・ピールのロンドン警視庁、刑務所改革、救貧院、精神病患者のための精神病院など、ベンサム主義的な政府の社会統制の試みが増加した。

19世紀末までに、古典的自由主義の原則は、経済成長の低下、現代の工業都市に存在する貧困、失業、相対的剥奪の弊害に対する認識の高まり、そして組織労働の扇動によって、ますます挑戦を受けるようになった。努力と才能によって世界で自らの地位を築くことができる自力で成功した個人という理想は、次第に実現不可能に思われるようになった。産業化とレッセフェール資本主義によってもたらされた変化に対する主要な政治的反動は、社会的均衡を懸念する保守主義者から起こったが、後に社会主義がより重要な変革と改革の力となった。チャールズ・ディケンズ、トマス・カーライル、マシュー・アーノルドを含む一部のヴィクトリア朝の作家たちは、社会的不正に対する初期の影響力ある批評家となった。[61]Template:Incomplete short citation 新自由主義または社会的自由主義運動は1900年頃にイギリスで出現した。[62]
ジョン・スチュアート・ミルと自由主義政治理論
[編集]ジョン・スチュアート・ミルは、古典的自由主義の要素と後に新自由主義として知られるようになったものを結合することで、自由主義思想に多大な貢献をした。ミルの1859年の著作『自由論』は、社会が個人に対して正当に行使できる権力の性質と限界について論じた。[63] 彼は自由な言論を熱烈に擁護し、自由な言論が知的および社会的進歩の必要条件であると論じた。ミルは社会的自由を「政治的支配者の専制」からの保護と定義した。彼は専制が取りうる様々な形態の概念を導入し、それぞれ社会的専制と多数者の専制と呼んだ。社会的自由は、政治的自由または権利の承認を得ることと、憲法的チェックのシステムを確立することによって、支配者の権力に制限を加えることを意味した。[64]

グリーンの自由の定義は、ジョセフ・プリーストリーとジョサイア・ウォレンの影響を受け、個人は他者に危害を加えない限り望むようにすべきであるというものだった。[65] ミルはまたフェミニズムの初期の提唱者でもあった。彼の論文『女性の隷属』(1861年執筆、1869年出版)において、ミルは女性の法的隷属が間違っており、完全な平等に道を譲るべきであることを証明しようとした。[66][67]
ミルの初期の経済哲学は自由市場を支持し、累進課税はより懸命に働く者を罰するものだと主張したが、[68] 後に彼の見解はより社会主義的な傾向に変化し、『経済学原理』に社会主義的展望を擁護する章を追加し、一部の社会主義的主張を擁護した。[69] これには、賃金制度全体を協同組合的賃金制度に置き換えるという急進的な提案も含まれていた。
ウィリアム・ユーアート・グラッドストーンが議会で率いた自由党は、知的および社会的スペクトルの広範囲から支持を集めた。一方では、科学の方法と自由主義的政治経済学を融合させようとした進歩的エリートたちがいた。例えば、人類学者で国会議員のサー・ジョン・ラボックは、認知科学を用いて公共政策に挑戦し、形成するという戦略を採用した。ラボックはこのアプローチを、普遍的教育、記念物の保存、バンクホリデーの導入に関する議会討論に有名に適用した。[70] 他方で、自由党は福音主義と非国教徒の宗教的要素にも強い基盤を持っていた。オックスフォード大学のベイリオル・カレッジで、トマス・ヒル・グリーンは、国家は個人が最も良心に従って行動する機会を持つ社会的、政治的、経済的環境を育成し保護すべきだと主張した。国家は、自由が個人を奴隷化する明確で証明された強い傾向がある場合にのみ介入すべきであるとグリーンは考えた。グリーンは、国民国家を個人の自己実現を最も促進する可能性の高い権利と義務のシステムを支持する限りにおいてのみ正当であると見なした。[71] グラッドストーン派の自由主義者たちは1891年に「ニューカッスル・プログラム」を採用した。これにはアイルランドの自治、ウェールズとスコットランドにおけるイングランド国教会の国教会としての地位の廃止、酒類販売のより厳格な管理、工場規制の大幅な拡大、様々な民主的政治改革が含まれていた。このプログラムは、自由党の貴族的指導者たちの離脱によって解放されたと感じた非国教徒の中産階級自由主義者層に強い訴求力を持っていた。[72]
世界的な広がり
[編集]ドイツの知識人ウィルヘルム・フォン・フンボルト(1767-1835)は、教育を既に確立された職業や社会的役割に若者を適合させるための手段としてではなく、個人の可能性を実現する手段として構想することで、リベラリズムの発展に大きな貢献をした。スイスのバンジャマン・コンスタン(1767-1830)は自由の概念を洗練させ、それを個人が国家や社会からの干渉を退けることを可能にする存在の条件として定義した。[73]
奴隷制廃止運動と参政権運動が広がり、代議制や民主主義的理想も普及した。フランスは1870年代に長続きする共和制を確立した。一方、ナショナリズムも1815年以降急速に広まった。イタリアとドイツでは、リベラルとナショナリストの感情が混ざり合い、19世紀後半に両国の統一をもたらした。イタリアではリベラルな政権が誕生し、教皇の世俗的権力を終わらせた。しかし、バチカンはリベラリズムに対する反撃を開始した。教皇ピウス9世は1864年に誤謬表を発表し、あらゆる形態のリベラリズムを非難した。多くの国でリベラル勢力はこれに対抗してイエズス会を追放することで応じた。
19世紀後半から、社会民主主義的な考えがリベラリズムに影響を与え始めた。この新しい形態のリベラリズムは、世界中でさまざまな名称で知られるようになった。ドイツでは社会的自由主義、イギリスでは新自由主義、フランスでは連帯主義、スペインでは再生主義、イタリアではジョリッティ時代、アメリカでは進歩主義運動などと呼ばれた。[74]
リベラリズムは20世紀初頭に勢いを増した。専制政治の砦であったロシア皇帝は、1917年のロシア革命の第一段階で打倒されたが、リベラリズムはボリシェビキが勝利するまでのわずか数か月しか続かなかった。第一次世界大戦における連合国の勝利と4つの帝国の崩壊は、ドイツや新しく創設された東欧諸国を含むヨーロッパ大陸全体でのリベラリズムの勝利を示すように思われた。ドイツに代表される軍国主義は敗北し、信用を失った。マーティン・ブリンクホーンが主張するように、「文化的多元主義、宗教的・民族的寛容、民族自決、自由市場経済、代議制と責任ある政府、自由貿易、労働組合主義、そして新しい機関である国際連盟を通じた国際紛争の平和的解決」といったリベラルなテーマが優勢となった。[75]

1929年に始まった世界的な大恐慌は、リベラルな経済学の信用失墜を早め、経済問題に対する国家管理の要求を強めた。経済的苦境はヨーロッパの政治世界に広範な不安を引き起こし、ファシズムと共産主義の台頭をもたらした。1939年のその台頭は第二次世界大戦へと至った。連合国は、共産主義ロシアと共に主要なリベラル国家のほとんどを含んでおり、ナチス・ドイツ、ファシスト・イタリア、軍国主義日本を破った。戦後、ロシアと西側諸国の間に亀裂が生じ、1947年には共産主義東側ブロックとリベラルな西側同盟の間で冷戦が始まった。

一方、大恐慌に対する決定的なリベラルな対応は、イギリスの経済学者ジョン・メイナード・ケインズによって与えられた。ケインズは1920年代に失業、貨幣、物価の関係を検討する理論的研究を始めていた。[77]ケインズは大恐慌時のイギリス政府の緊縮政策を深く批判した。彼は予算赤字は良いものであり、不況の産物であると信じていた。彼は次のように書いている。「政府の借り入れは、ある種の自然の治療法であり、いわば、深刻な不況において生産を完全に停止させてしまうほど大きな事業損失を防ぐためのものである。」[78]
大恐慌の最盛期である1933年、ケインズは『繁栄への道』を出版した。この著作には、世界的な不況下での失業問題に取り組むための具体的な政策提言、主に景気循環に逆行する公共支出が含まれていた。『繁栄への道』には乗数効果についての初期の言及の一つが含まれている。[79]ケインズの主著である『雇用、利子および貨幣の一般理論』は1936年に出版され、[80]不況に対処するためにケインズが好んだ介入主義的政策の理論的正当化として機能した。
冷戦は広範なイデオロギー競争と複数の代理戦争を特徴としたが、広く恐れられていたソビエト連邦とアメリカの間の第三次世界大戦は起こらなかった。共産主義国家とリベラルな民主主義国家が互いに競争する中、1970年代の経済危機はケインズ経済学からの離脱を促した。特にイギリスのマーガレット・サッチャーとアメリカのロナルド・レーガンの下でこの傾向が顕著だった。この古典的リベラリズムの復活は、支持者と批判者によって「新自由主義」と呼ばれ、1980年代と1990年代を通じて続いた。一方、20世紀末に近づくにつれ、東欧の共産主義国家は急速に崩壊し、西側ではリベラルな民主主義が唯一の主要な政府形態として残った。
第二次世界大戦の始まり時点で、世界の民主主義国家の数は40年前とほぼ同じだった。[81]1945年以降、リベラルな民主主義は非常に急速に広がったが、その後後退した。ラリー・ダイアモンドは『民主主義の精神』の中で、1974年までに「独裁制、民主主義ではなく、世界の趨勢となっていた」と論じている。また、「独立国家のわずか4分の1しか、競争的で自由かつ公正な選挙によって政府を選んでいなかった」とも述べている。ダイアモンドはさらに、民主主義は反発し、1995年までに世界は「主に民主的」になったと言っている。[82][83]
リベラリズムの成果は大きかった。1975年には世界で約40カ国がリベラルな民主主義国家と特徴付けられていたが、2008年にはその数は80カ国以上に増加した。[84]世界で最も豊かな国々や最も強力な国々の多くは、広範な社会福祉プログラムを持つリベラルな民主主義国家である。[85]しかし、リベラリズムは依然として課題に直面している。特に、権威主義的政府と経済的リベラリズムを組み合わせたモデルとしての中国の驚異的な成長がある。[86]2007年頃に始まった大不況は、ケインズ経済思想の復活を促した。
リベラリズムの主要な成果には、リベラル国際主義の台頭がある。これは国際連盟や、第二次世界大戦後の国際連合などのグローバル組織の設立に貢献したとされている。[87]リベラリズムを世界中に輸出し、調和のとれたリベラルな国際秩序を構築するという考えは、18世紀以来リベラル派の思考を支配してきた。[88]「リベラリズムが国内で繁栄したところではどこでも、リベラルな国際主義のビジョンが伴っていた」と、ある歴史家は書いている。[88]しかし、リベラルな国際主義への抵抗は深く激しいものだった。批評家たちは、グローバルな相互依存の高まりが国家主権の喪失につながると主張し、また民主主義は国内統治にも世界統治にも適さない腐敗した秩序を代表するものだと論じた。[89]
リベラリズムは現代の支配的なイデオロギーとしてしばしば引用される。[90][91][要文献特定詳細情報] 政治的には、リベラリズムは世界中で広範に組織化されている。リベラル党、リベラルシンクタンク、その他の機関は多くの国に存在するが、それらはイデオロギー的志向に基づいて異なる目的のために活動している。リベラル政党は、その所在地によって中道左派、中道、または中道右派になり得る。
これらの政党はさらに、社会的リベラリズムまたは古典的リベラリズムへの支持に基づいて区別することができる。しかし、すべてのリベラル政党や個人は、市民権と民主主義制度への支持を含む基本的な類似点を共有している。グローバルなレベルでは、リベラリストはLiberal Internationalに結集しており、これにはイデオロギー的スペクトル全体から100を超える影響力のあるリベラル政党や組織が含まれている。
LIに所属する政党の中には、カナダ自由党のように世界で最も有名な政党もあれば、ジブラルタル自由党のように最小規模の政党もある。地域的には、リベラリストは優勢な地政学的状況に応じてさまざまな機関を通じて組織化されている。例えば、ヨーロッパ自由民主改革党はヨーロッパにおけるリベラリストの利益を代表し、ヨーロッパ自由民主同盟は欧州議会における主要なリベラル系会派となっている。
フリーメイソン
[編集]長期的な歴史的観点から見ると、ノーマン・デイヴィスはフリーメイソンが1700年頃から20世紀にかけてヨーロッパとその植民地におけるリベラリズムの強力な推進力であったと主張している。フリーメイソンは啓蒙時代に急速に拡大し、ヨーロッパのほぼすべての国々、さらにはイギリスとスペインの海外植民地にまで及んだ。それは特に王族、有力な貴族、政治家、知識人、芸術家、政治活動家にとって魅力的だった。フリーメイソンの大敵はローマ・カトリック教会であり、フランス、イタリア、オーストリア、ポルトガル、スペイン、メキシコなどカトリック教徒が多数を占める国々では、教会を中心とする保守派とフリーメイソンであることが多いリベラル派との対立が政治闘争の激しさの多くを占めていた。[93][94]
1820年代までに、イギリス軍のすべての連隊に少なくとも一つのフリーメイソンの支部があり、彼らは大英帝国内の駐屯地すべてで民間人の間に支部を形成しようとした。[95] フランス、スペイン、ポルトガルの帝国でも、軍の支部がフリーメイソンの普及に積極的だった。[96] 19世紀から20世紀初頭のメキシコでは、リベラリズムの重要な指導者たちのほとんどが活発なフリーメイソンであり、彼らはロッジを政治組織の装置として利用した。[97][98] 20世紀の全体主義運動、特にファシストと共産主義者は、権力を握ると、自国のフリーメイソン組織を体系的に粉砕しようとした。[99]
アフリカとアジア
[編集]
中東とオスマン帝国におけるリベラリズムの影響は大きかった。19世紀中、アラブ、オスマン、ペルシャの知識人たちはヨーロッパを訪れ、西洋の文学、科学、リベラルな思想について学んだ。これにより彼らは自国の後進性について考えるようになり、社会を近代化するために立憲主義、発展、リベラルな価値観を推進する必要があるという結論に達した。[100] 同時に、中東におけるヨーロッパの存在感の増大と地域の停滞は、マフムート2世とその息子アブデュルメジト1世、ムハンマド・アリー・パシャ、アミール・カビールなどの中東の指導者たちに、社会政治的変革を行い近代化プロジェクトを開始するよう促した。[100] 1826年、知識人で学者のリファーア・アッ=タフターウィーは、ムハンマド・アリーの学者派遣団の一員としてパリに送られた。タフターウィーは倫理学、社会哲学、政治哲学、数学を学んだ。フランス滞在中、彼はコンディヤック、ヴォルテール、ルソー、モンテスキュー、ベズーらの著作を読んだ。[101]
1831年、タフターウィーは帰国し、エジプトのインフラと教育を近代化する全国的な取り組みに参加した。これは後に19世紀後半から20世紀初頭にかけて栄えたエジプトのルネサンス(ナフダ)となり、その後オスマン帝国支配下のアラビア語圏のレバノン、シリアなどにも広がった。彼は1835年に言語学校(翻訳者学校としても知られる)を設立し、これは1973年にアインシャムス大学の一部となった。[102][103] 帰国後、アッ=タフターウィーは議会制、市民の政治参加権、女性の教育を受ける権利の擁護者となった。[104] 言語学校は、最初の近代エジプトの知識人を輩出し、彼らはエジプトにおけるイギリス植民地主義に対する草の根の動員の基盤を形成した。彼の出版された3巻は政治哲学と道徳哲学の作品だった。これらは、エジプトの読者に啓蒙思想のリベラルな考え、例えば世俗的権威や政治的権利と自由、現代の文明社会がどうあるべきか、そして拡張して「良きエジプト人」とは何かについての彼の考え、公共の利益と公共の善についての彼の考えを紹介した。[105][103]
オスマン帝国では、内部の民族主義運動と外部の侵略的勢力に対して領土保全を確保するため、一連の改革が着手された。この時期はタンズィマート(再編成)と呼ばれている。自由主義的大臣や知識人たちが改革に影響を与えようと試みたが、タンズィマートの実施動機は官僚的なものであった。[100][106] これらの変革は市民的自由を改善するために行われた。しかし、ナフダとタンズィマートの改革的思想や傾向は一般大衆に十分に届かなかった。書籍、定期刊行物、新聞は主に知識人や新興中産階級の一部にしかアクセスできず、多くのムスリムはそれらをイスラーム世界への外国の影響とみなしたからである。この認識が中東諸国の改革努力を複雑にした。[103][107] オスマン主義と呼ばれる政策は、オスマン領内に住むすべての異なる民族、「ムスリムと非ムスリム、トルコ人とギリシャ人、アルメニア人とユダヤ人、クルド人とアラブ人」を統合することを目的としていた。この政策は公式には1839年のギュルハネ勅令で始まり、ムスリムと非ムスリムのオスマン人の法の下の平等を宣言した。[108]
1865年、オスマン帝国のタンズィマート改革に不満を持つオスマン・トルコ人の知識人グループが、青年オスマン党と呼ばれる秘密結社を設立した。彼らは改革が十分に進んでいないと考え、帝国の専制政治を終わらせようとした。[109][110] 彼らは帝国を維持しながら、ヨーロッパの線に沿って近代化し、立憲政府を採用することでオスマン社会を変革しようとした。[111] 青年オスマン党はイデオロギー的に頻繁に意見の相違があったが、新しい立憲政府は「オスマンの政治文化の基礎としてのイスラームの継続的かつ本質的な妥当性」を強調するために、ある程度イスラームに根ざすべきであるという点で全員が同意した。[112] しかし、彼らはイスラームの理想主義と近代的自由主義および議会制民主主義を融合させた。彼らにとって、ヨーロッパの議会制自由主義はイスラームの教義に従って追随すべきモデルであった。彼らは「イスラームの統治概念をモンテスキュー、ダントン、ルソー、および同時代のヨーロッパの学者や政治家の考えと調和させようとした」。[113][114][115]
青年オスマン党の形成に影響を与えたナームク・ケマルは、フランス第三共和政の憲法を賞賛した。彼は青年オスマン党の政治的理想を「国民の主権、権力の分立、官僚の責任、個人の自由、平等、思想の自由、出版の自由、結社の自由、財産の享受、家庭の神聖」と要約した。[113][114][115] 青年オスマン党は、帝国衰退の主な理由の一つがヨーロッパの近代性を模倣するためにイスラームの原則を放棄し、両者に対して不適切な妥協をしたことであると信じており、国家とその国民の利益に最もよく貢献すると彼らが信じる方法で両者を統合しようとした。[116] 彼らは、帝国が創設された時のイスラームの基盤を維持しながら、特定のヨーロッパの政府モデルを取り入れることで帝国を活性化しようとした。[117] この社会の著名なメンバーには、イブラヒム・シナーシー、ナームク・ケマル、アリ・スアーヴィー、ズィヤー・パシャ、アガー・エフェンディなどの作家や評論家がいた。

1875年から1876年にかけて生じた内部の財政的・外交的危機により、青年オスマン党は決定的な瞬間を迎えた。アブデュルハミト2世が自由主義的な考えを持つミドハト・パシャを大宰相に任命し、渋々ながら1876年のオスマン憲法を公布した。これはオスマン帝国初の憲法制定の試みであり、第一次立憲政期の幕開けとなり、タンズィマートを終結させた。[118][119] 発展、進歩、自由主義的価値観を促進することで社会を近代化しようとした自由主義的知識人たちのおかげで、オスマン帝国に立憲主義が導入された。[120] ミドハト・パシャはオスマン帝国議会の創設者の一人とみなされることが多い。[121][118][122][123] この期間は短命であり、アブデュルハミトは最終的に1878年に憲法と議会を停止し、自身が権力を握る絶対君主制への回帰を選んだが、[124] 青年オスマン党の遺産と影響力は帝国崩壊まで続いた。数十年後、改革志向のオスマン人の別のグループである青年トルコ党が青年
〈中断〉
青年オスマン党の努力を繰り返し、1908年の青年トルコ革命と第二次立憲政期の始まりにつながった。
ナフダ期はイスラームと社会の近代化を目指した。思想家や宗教改革者たちは伝統的な見解を否定し、タクリード(模倣、法的先例への従順)を放棄し、イジュティハード(知的努力、推論、解釈学)を強調することで近代化を奨励した。彼らはこれをイスラームの起源への回帰とみなした。[125][126] イスラーム近代主義運動は、近代主義サラフィズムとも呼ばれ、「西洋の文化的挑戦に対する最初のムスリムのイデオロギー的反応」と表現されてきた。[注釈 1] イスラーム近代主義は、19世紀半ばに出現したいくつかの運動—世俗主義、イスラーム主義、サラフィズム—の中で最初のものであった。これらの運動は、当時の急速な変化、特にムスリム世界に対する西洋文明と植民地主義の知覚された攻撃に対する反応として生まれた。[128] イスラーム近代主義の創始者には、1905年に死去する直前に短期間アル=アズハル大学のシェイクを務めたムハンマド・アブドゥフ、ジャマールッディーン・アル=アフガーニー、ムハンマド・ラシード・リダー(1935年没)が含まれる。この運動はリファーア・アッ=タフターウィーから始まったが、アル=アフガーニーがイスラームが直面していた社会政治的および神学的課題について議論するムスリム学者のグループを組織したときに人気を得た。[129] この運動は、イスラームの信仰とナショナリズム、民主主義、市民権、合理性、平等主義、社会進歩などの近代的西洋の価値観を調和させようとした。[128] それは「法学の古典的概念と方法の批判的再検討」と、イスラーム神学とクルアーン解釈(タフスィール)への新しいアプローチを特徴としていた。[127] イスラーム近代主義と自由主義的ナショナリズムは相互に関連しており、両者ともイスラームの正統派の退却と絶対主義国家の衰退の要因であった。中東の自由主義的ナショナリズムは西洋の自由主義を手本としたが、文化的・教育的改革を通じた国民統合、固有の国語の推進、宗教と政治の分離を支持し、ナショナリズムの概念と民主的制度の原則を取り入れた。それは植民地主義と介入主義への反応であり、西洋の地域利益と衝突した。[127] エジプトでは、イスラーム近代主義により自由主義的ナショナリストはより広い聴衆に到達できた。これは1920年代と1930年代に終わりを告げ、自由主義的ナショナリズムが強い世俗主義的方向性を取り、イスラーム近代主義を弱体化させた。[127] ムスリム世界におけるこれらの変化はすべて、イスラーム復興主義を促進するイスラーム内の危機感を生み出した。[128][130]
1909年、カージャール朝が支配するペルシア(現在のイラン)では、立憲革命期間中に民主党(民主党としても訳される)が、ライバルの穏健社会主義党と並んで、当時の2大議会政党の1つであった。[131] 当初はトランスコーカサスを拠点とする社会民主党の支部であり、主に自由主義的な中産階級の知識人で構成され、代議制政治システムと政教分離を支持し、君主制と聖職者の権威を制限しようとした。[132][133] 同党は1906年の1906年ペルシア憲法に影響を与え、この憲法はマジュリス(議会)と元老院を創設した。しかし、内部および外部の要因により、同党は大きく成長することができず、1925年にパフラヴィー朝が確立されると弾圧され、様々な小規模な団体に分裂した。[133]
日本では、1920年代には一般的に自由主義的であったが、1930年代には軍部からの圧力の下で自由主義が衰退した。
エジプトでは、ワフド党(「代表団党」)が国民主義的自由主義政党であった。1920年代から30年代にかけて、エジプトで最も人気があり影響力のある政党であったと言われている。自由主義的ナショナリストの努力は1923年エジプト憲法による立憲君主制の形成で頂点に達したが、[134] 自由主義的ナショナリズムは1930年代後半に2つの運動、ムスリム同胞団と汎アラブ主義的アラブ・ナショナリズムの成長と対立により衰退した。[134] しかし、自由主義的価値観や思想を提唱した知識人の例は様々にあった。この時期の著名な自由主義者には、ターハー・フセイン、アフマド・ルトフィー・エル=サイイド、タウフィーク・アル=ハキーム、アブド・エル=ラッザーク・エル=サンフーリー、ムハンマド・マンドゥールなどがいた。[135]
ターハー・フセインとアフマド・ルトフィー・エル=サイイドは20世紀のエジプト人知識人の中で最も影響力のある人物の一人であった。[136][137] フセインはイスラーム主義に反対しており、自由主義運動への彼の主な貢献の一つは、エジプトの自由主義とイスラームがいかに調和できるかを検討したことであった。彼は自由と平等を信じ、エジプトはフランス革命と産業時代の理念に沿って、近代的で啓蒙された社会として発展すべきだと考えた。[138]
エル=サイイドは現代エジプト・ナショナリズム、エジプトの世俗主義、自由主義の設計者の一人であった。「世代の教授」として親しまれ、エジプトの国民主義運動で影響力のある人物であり、反植民地活動家でもあった。[139] エル=サイイドはすべての人々の平等と権利を信じていた。彼は1925年から1941年までカイロ大学の初代学長を務めた。[140] 彼はミルの著作をアラブの一般大衆に紹介した最初のエジプト人官僚の一人とされ、人々が自由主義の概念について学べるようにした。彼は、人々は自分たちの政府と国で何が起こっているかについて発言権を持つべきであり、すべての人々には奪うことのできない特定の市民権があると信じていた。[141]

1949年、イラン国民戦線がモハンマド・モサッデク、ホセイン・ファーテミー、アフマド・ジーラクザーデ、アリー・シャーエガーン、カリーム・サンジャービーらによって設立された。[142] これはイラン国内で活動する最も古い親民主主義グループである。[143] 戦線は幅広い志を同じくする団体の連合として構想され、様々な国民主義的、自由主義的、社会民主主義的政党を含み、民主主義、報道の自由、立憲政府の強化を目的としていた。[144][145] 戦線の中で最も重要なグループは、イラン党、勤労者党、国民党、テヘラン・バザール商工組合協会であった。[146][147] イラン党は1946年にイランの自由主義者のプラットフォームとして設立され、カリーム・サンジャービー、ゴラーム・ホセイン・サーデギー、アフマド・ジーラクザーデ、アッラー・ヤール・サーレなどの人物が含まれていた。[148]
1951年4月、国民戦線は民主的に選出されたモハンマド・モサッデクがイランの首相に就任し、与党連合となった。モサッデクは法の支配と外国の介入からの自由を提唱する自由主義的ナショナリストで著名な議員であった。[149][150] 彼の政権は社会保障や土地改革など、一連の進歩的な社会的・政治的改革を導入した。これには地代への課税も含まれていた。しかし、彼の政府の最も注目すべき政策は、1913年以来アングロ・ペルシャ石油会社(APOC/AIOC)(後のブリティッシュ・ペトロリアムとBP)を通じてイギリスの支配下にあったイラン石油産業の国有化であり、中東で最初に石油産業を国有化した国となった。[151]
モサッデクの自由主義的で独立した統治方法は彼に大衆の支持をもたらしたが、同時に様々なグループを疎外した。それは地域における西洋の利益と直接的に対立し、シャーの権威に挑戦し、モサッデクの左派グループに対する寛容さは伝統主義者とウラマーを怒らせた。[152] モハンマド・レザー・パフラヴィーの君主制支配を強化するため、ウィンストン・チャーチルとアイゼンハワー政権はイランの政府を転覆させることを決定した。前任のトルーマン政権はクーデターに反対していた。[153] モサッデクは1953年8月19日にクーデターによって権力の座から追放された。このクーデターはMI6の要請によりCIAによって組織・実行され、イランのファズロッラー・ザーヘディー将軍がモサッデクの後継者として選ばれた。[154][155][156][157][158]
1953年のクーデターにより、国の政府における自由主義の優位性は終わりを告げた。1953年以前および1960年代を通じて、国民戦線は世俗派と宗教派の間の争いに引き裂かれ、時間とともに様々な内紛を繰り返す派閥に分裂していった。[159][143][160] そして徐々に世俗的自由主義者の主要組織として台頭し、自由民主主義と社会民主主義を支持する民族主義的メンバーを擁するようになった。[161][159]
20世紀半ばには、自由党と進歩党が、政府のアパルトヘイト政策に反対するために結成された。自由党は多人種政党を形成し、当初は都市部の黒人と高学歴の白人から相当の支持を得ていた。[162] また、「西洋化された農民層」からも支持者を獲得し、その公開集会には多くの黒人が参加していた。[163] 党員数は最盛期に7,000人に達したが、白人全体に対する訴求力は小さすぎて、意味のある政治的変化をもたらすことはできなかった。[162] 自由党は1968年に、政府が多人種の党員を持つことを禁止する法律を可決したことを受けて解散した。
インドでは、19世紀後半に自由主義的民族主義者によってインド国民会議派(INC)が設立され、より自由で自治的なインドの創設を要求した。[164] 自由主義は20世紀初頭までの間、同グループの主要なイデオロギー的潮流であり続けたが、次の数十年の間に社会主義が党の思想を徐々に覆い隠すようになった。
INCが率いた有名な闘争は、最終的にイギリスからのインド独立を勝ち取った。近年、同党はより自由主義的な傾向を採用し、社会正義を追求しつつ開かれた市場を支持している。2009年の『マニフェスト』において、INCは右派が唱道していると主張する原住民主義的、共同体的、保守的なイデオロギー的傾向に対抗して、「世俗的で自由主義的な」インド民族主義を称賛した。[165] 一般的に、過去数十年のアジアの自由主義の主要テーマは、大陸の急速な経済近代化を促進する方法としての民主化の台頭であった。[166] しかし、ミャンマーのような国々では、自由民主主義が軍事独裁に取って代わられている。[167]
アフリカ諸国の中で、南アフリカは大陸の他の国々には欠けている顕著な自由主義の伝統を持つことで際立っている。今日、南アフリカの自由主義は、与党アフリカ民族会議に対する公式野党である民主同盟によって代表されている。民主同盟は国民議会で第二党であり、現在西ケープ州政府を率いている。
最近、自由主義政党や機関が政治権力を獲得するための大きな動きを見せている。大陸レベルでは、自由主義者はアフリカ自由主義ネットワークに組織されており、モロッコの人民運動、セネガルの民主党、コートジボワールの共和派連合など影響力のある政党が含まれている。アジアでは、いくつかのアジア諸国が重要な自由主義の原則を明確に拒否している。大陸レベルでは、自由主義者はアジア自由民主評議会を通じて組織されており、フィリピンの自由党、台湾の民主進歩党、タイの民主党など強力な政党が含まれている。自由主義の影響力の顕著な例はインドに見ることができる。世界最大の民主主義国家であるインドでは、インド国民会議派が長年にわたり政治を支配してきた。
アメリカ大陸
[編集]ラテンアメリカにおける自由主義的な不穏は18世紀にまで遡る。当時、ラテンアメリカでの自由主義的な動きがスペインとポルトガルの帝国支配からの独立につながった。新しい政権は一般的に政治的見解において自由主義的であり、近代科学の真理を強調する実証主義の哲学を用いて自らの立場を支持した。[168]

スペインにおける自由主義者と保守主義者の闘争は、ラテンアメリカでも再現された。かつての支配者と同様に、この地域は19世紀を通じて戦争、紛争、革命活動の温床であった。メキシコでは、1850年代に「リベラレス」(自由主義者)が「ラ・レフォルマ」(改革)プログラムを実施し、軍とカトリック教会の力を削減した。[169] これらの措置に「コンセルバドーレス」(保守主義者)は激怒し、反乱を起こし、それが致命的な対立を引き起こした。1857年から1861年にかけて、メキシコは自由主義者と保守主義者の間の大規模な内部的・イデオロギー的対立である改革戦争に巻き込まれた。[169] 最終的に自由主義者が勝利し、献身的な自由主義者で現在はメキシコの国民的英雄であるベニト・フアレスが共和国の大統領となった。フアレスの後、メキシコは20世紀初頭のメキシコ革命まで続く長期の独裁的抑圧に苦しむこととなった。
自由主義の影響を示す地域的な別の例はエクアドルに見られる。当時の地域の他の国々と同様に、エクアドルもスペインからの独立後、紛争と不確実性に悩まされていた。19世紀半ばまでに、国は混沌と狂気に陥り、国民は対立する自由主義陣営と保守主義陣営に分裂していた。これらの紛争から、ガルシア・モレノが保守的な政府を樹立し、数年間国を統治した。しかし、自由主義者はこの保守的体制に激怒し、1895年の自由主義革命で完全に打倒した。保守派を倒した急進的自由主義者はエロイ・アルファロに率いられ、彼は教会と国家の分離、離婚の合法化、公立学校の設立など、様々な社会政治的改革を実施した過激派であった。[170]
メキシコやエクアドルなどの国々における自由主義革命は、ラテンアメリカの多くの地域に近代世界をもたらした。ラテンアメリカの自由主義者は一般的に自由貿易、私有財産、反教権主義を強調した。[171]
アメリカ合衆国では、激しい戦争が国家の統合と南部における奴隷制の廃止を確実なものとした。歴史家ドン・ドイルは、南北戦争(1861-65年)における北軍の勝利が自由主義の進展に大きな後押しを与えたと主張している。[172] 北軍の勝利は民主的な力を活性化させた。一方、南軍の勝利は、自由ではなく奴隷制の新たな誕生を意味していただろう。歴史家ファーガス・ボーデウィッチはドイルに従って次のように論じている:
- 北軍の勝利は民主的政府の耐久性を決定的に証明した。一方、南部連合の独立は、反動的な政治と人種に基づく抑圧のためのアメリカモデルを確立し、それは20世紀、おそらくはそれ以降にまで及ぶ国際的な影を落としていただろう。[173]
カナダでは、1867年に創設され、時折「グリット」として知られる長期政権党の自由党が、20世紀に約70年間国を統治した。同党はピエール・トルドー、レスター・B・ピアソン、ジャン・クレティエンなど、カナダの歴史上最も影響力のある首相を輩出し、カナダの福祉国家の発展に主に責任を負ってきた。自由党の驚異的な成功は、他のどの自由民主主義国家でもほとんど類を見ないものであり、多くの政治評論家に彼らを国の「自然な統治政党」として長年にわたり認識させることとなった。[174]

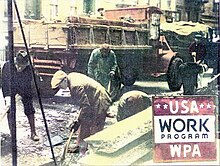
アメリカ合衆国では、現代自由主義はその歴史を、大恐慌に対応してニューディールを開始し、前例のない4期連続で当選した人気のフランクリン・デラノ・ルーズベルト大統領の時代にまで遡る。フランクリン・ルーズベルトが確立したニューディール連合は決定的な遺産を残し、ジョン・F・ケネディを含む多くの後続のアメリカ大統領に影響を与えた。ケネディは自身を自由主義者と称し、自由主義者を「後ろを振り返らず前を見る人、硬直した反応なしに新しいアイデアを歓迎する人...人々の福祉を気にかける人」と定義した。[175] ルーズベルト大統領がアメリカで開始した社会自由主義的プログラムであるニューディールは、アメリカ国民に非常に人気があることが証明された。1933年にFDRが就任した時、失業率はおよそ25パーセントであった。[176] 国民総生産で測定された経済規模は、1929年初頭の半分の価値にまで落ち込んでいた。[177] FDRと民主党の選挙での勝利は、赤字支出と公共事業プログラムの洪水を引き起こした。1940年までに、失業率は10ポイント低下して約15パーセントになった。[178] 追加的な政府支出と第二次世界大戦によって引き起こされた巨大な公共事業プログラムが、最終的にアメリカを大恐慌から脱出させた。社会自由主義的プログラムは、失業率をおよそ25パーセントから1940年までに約15パーセントに減少させた。[176] 追加的な政府支出と第二次世界大戦によって引き起こされた非常に大規模な公共事業プログラムが、最終的にアメリカを大恐慌から脱出させた。1940年から1941年にかけて、政府支出は59パーセント増加し、国内総生産は17パーセント増加し、失業率は1929年以来初めて10パーセントを下回った。[179]
様々な地域的・国家的運動の中で、1960年代のアメリカにおける公民権運動は、平等な権利のための自由主義的努力を強く浮き彫りにした。[180] 大統領リンドン・B・ジョンソンが開始した偉大な社会計画は、メディケアとメディケイドの創設、貧困との戦いの一環としてのヘッドスタートとジョブ・コアの設立、そして画期的な1964年公民権法の制定を監督した。これらの出来事の急速な連続を、一部の歴史家は「自由主義の時間」と呼んでいる。[181]
1960年代と1970年代には、アメリカにおける第二波フェミニズムの大義は、全米女性機構のような自由主義フェミニスト組織によって大きく前進した。[4]

20世紀後半には、ルーズベルトやケネディが擁護したような自由主義に対する保守主義的な反動が共和党内で発展した。[182] この種の保守主義は主に1960年代の文化的・政治的激動に反応したものであった。[182] これはロナルド・レーガン、ジョージ・H・W・ブッシュ、ジョージ・W・ブッシュ、ドナルド・トランプといった大統領を権力の座に押し上げる一助となった。[183] 21世紀初頭の経済的苦境は、2008年大統領選挙におけるバラク・オバマの当選とともに社会自由主義の復活をもたらした。[184] 一方で、それに対抗し部分的に反動的な保守主義的ポピュリズムとネイティビズムがティーパーティー運動とドナルド・トランプの当選に体現されることとなった。
今日、ラテンアメリカの市場自由主義者はラテンアメリカ自由主義ネットワーク(RELIAL)に組織されており、これは数十の自由主義政党と組織を結集させる中道右派のネットワークである。RELIALには、メキシコの新同盟党からキューバでの政権獲得を目指すキューバ自由連合まで、地理的に多様な政党が参加している。しかし、この地域の一部の主要な自由主義政党は、社会自由主義的な理念と政策に自らを結びつけ続けている。その顕著な例が社会主義インターナショナルのメンバーであるコロンビア自由党である。もう一つの有名な例は、パラグアイの真正急進自由党であり、これは国内で最も強力な政党の一つで、中道左派に分類されている。[185]
オセアニア
[編集]オーストラリアでは、リベラリズムは主に中道右派の自由党によって擁護されている。[186] 自由党は古典的自由主義と保守主義の勢力の融合であり、中道右派の国際民主同盟と提携している。[186][187][188][189][190]
歴史学
[編集]ミシェル・フーコー
[編集]フランスの知識人ミシェル・フーコーは、政治哲学および統治の様式としてのリベラリズムの出現を16世紀に位置づけている。[191] 彼は特にアダム・スミス、デイヴィッド・ヒューム、アダム・ファーガソンに焦点を当てている。フーコーによれば、一方での国家の中央集権化と、他方での分散と宗教的異論という二重の動きを通じて、この統治の問題が初めて明確に提示された。[192]
リベラリズムの誕生に関連する中心的な問いまたは統治の問題は、家族の統治形態である「経済」を国家全体にどのように適用するかということであった。家庭内や家族単位における父親の細心の注意を、国家の運営にどのように導入するか?[193] リベラリズムの誕生は、この統治の問いまたは問題への応答に位置づけることができる。その応答は、主権的権力の支配から国家の装置への移行を目撃し、3つの重要な発展によって特徴づけられる:[194]Template:Incomplete short citation
フーコーの考えでは、統治の「合理性」としてのリベラリズムは、人間の行動が統治されるべきであるという前提を基礎とし、社会が国家から分離した領域として理解されるべきであるという考えを育むことを追求したという点で、それ以前の統治技術とは異なるものであった。社会は単に国家を強化するために搾取され侵害されるものではないとされた。[195] フーコー的な意味で、リベラリズムは単に人々をどのように統治するかという教義としてではなく、過剰な統治への永続的な批判から生じた統治の技術として出現した。つまり、「当局が過剰に統治しているという繰り返される不満に対処できる統治の技術の探求」であった。[196]
注釈と参考文献
[編集]- ^ "The Constitution of the United States" Archived 2019-12-29 at the Wayback Machine. (PDF).
- ^ Kalkman, Matthew (2011). New Liberalism. Granville Island. ISBN 978-1-926991-04-7
- ^ Arthur M. Schlesinger Jr. "Liberalism in America: A Note for Europeans" Archived 2018-02-12 at the Wayback Machine. (1956). The Politics of Hope (Boston: Riverside Press, 1962). "Liberalism in the U.S. usage has little in common with the word as used in the politics of any other country, save possibly Britain".
- ^ a b Worell, p. 470.
- ^ a b Rothbard, Murray (2005). Excerpt from "Concepts of the Role of Intellectuals in Social Change Toward Laissez Faire", The Journal of Libertarian Studies, Vol. IX, No. 2 (Fall 1990) at mises.org
- ^ Rothbard, Murray (2005). "The Ancient Chinese Libertarian Tradition", Mises Daily, (5 December 2005) (original source unknown) at mises.org
- ^ a b “The Rise, Decline, and Reemergence of Classical Liberalism”. 17 December 2012閲覧。
- ^ Delaney, p. 18.
- ^ Godwin et al., p. 12.
- ^ Copleston, pp. 39–41.
- ^ Locke, p. 170.
- ^ Forster, p. 219.
- ^ Zvesper, p. 93.
- ^ Feldman, Noah (2005). Divided by God. Farrar, Straus and Giroux, p. 29. "It took John Locke to translate the demand for liberty of conscience into a systematic argument for distinguishing the realm of government from the realm of religion".
- ^ Feldman, Noah (2005). Divided by God. Farrar, Straus and Giroux, p. 29.
- ^ McGrath, Alister. 1998. Historical Theology, An Introduction to the History of Christian Thought. Oxford: Blackwell Publishers. pp. 214–215.
- ^ Bornkamm, Heinrich (1962). “Toleranz. In der Geschichte des Christentums [Tolerance. In the history of Christianity]” (ドイツ語). Die Religion in Geschichte und Gegenwart [Religion past and present]. VI (3rd ed.). col. 942
- ^ Hunter, William Bridges. A Milton Encyclopedia, Volume 8 (East Brunswick, N.J.: Associated University Presses, 1980). pp. 71–72. ISBN 0-8387-1841-8.
- ^ Scott 2008.
- ^ Doherty 2007, p. 26.
- ^ West 1996, p. xv.
- ^ Steven Pincus (2009). 1688: The First Modern Revolution. Yale University Press. ISBN 978-0-300-15605-8 7 February 2013閲覧。
- ^ “England's revolution”. The Economist. (17 October 2009) 17 December 2012閲覧。
- ^ Windeyer, W. J. Victor (1938). “Essays”. In Windeyer, William John Victor. Lectures on Legal History. Law Book Co. of Australasia
- ^ John J. Patrick; Gerald P. Long (1999). Constitutional Debates on Freedom of Religion: A Documentary History. Westport, CT: Greenwood Press
- ^ Professor Lyman Ray Patterson, "Copyright and 'The Exclusive Right' Of Authors" Archived 2014-01-10 at the Wayback Machine. Journal of Intellectual Property, Vol. 1, No. 1 Fall 1993.
- ^ “Letter on the subject of Candide, to the Journal encyclopédique July 15, 1759”. University of Chicago. 13 October 2006時点のオリジナルよりアーカイブ。7 January 2008閲覧。
- ^ "Introduction to Rights of Man" Archived 2013-02-25 at the Wayback Machine., Howard Fast, 1961
- ^ Hitchens, Christopher (2006). Thomas Paine's Rights of Man. Grove Press. p. 37. ISBN 978-0-8021-4383-9
- ^ Oliphant, John. “Paine,Thomas”. Encyclopedia of the American Revolution: Library of Military History. Charles Scribner's Sons April 10, 2007閲覧。
- ^ Merrill Jensen, The Founding of a Nation: A History of the American Revolution, 1763–1776 (New York: Oxford University Press, 1968), p. 668.
- ^ Bernstein, p. 48.
- ^ a b Roberts, p. 701.
- ^ Milan Zafirovski (2007). Liberal Modernity and Its Adversaries: Freedom, Liberalism and Anti-Liberalism in the 21st Century. Brill. pp. 237–238. ISBN 978-90-04-16052-1
- ^ Milan Zafirovski (2007). Liberal Modernity and Its Adversaries: Freedom, Liberalism and Anti-Liberalism in the 21st Century. Brill. pp. 237–238. ISBN 978-9004160521
- ^ Spielvogel, Jackson (2011). Western Civilization: Since 1300. Cengage Learning. p. 578. ISBN 978-1111342197
- ^ Adams, Willi Paul (2001). The First American Constitutions: Republican Ideology and the Making of the State Constitutions in the Revolutionary Era. Rowman & Littlefield. pp. 128–129. ISBN 978-0742520691
- ^ Frey, Foreword.
- ^ Frey, Preface.
- ^ Ros, p. 11.
- ^ Coker, p. 3.
- ^ Hanson, p. 189.
- ^ Manent and Seigel, p. 80.
- ^ Jon Meacham (2014). Thomas Jefferson: President and Philosopher. Random House. p. 131. ISBN 978-0385387514
- ^ David Andress, The terror: Civil war in the French revolution (2005).
- ^ Colton and Palmer, pp. 428–429.
- ^ a b Colton and Palmer, p. 428.
- ^ Lyons, p. 111.
- ^ Palmer and Colton, (1995) pp. 428–429.
- ^ Frederick B. Artz, Reaction and Revolution: 1814–1832 (1934) pp. 142–143
- ^ William Martin, Histoire de la Suisse (Paris, 1926), pp. 187–188, quoted in Crane Brinson, A Decade of Revolution: 1789–1799 (1934) p. 235
- ^ Lyons, p. 94.
- ^ Lyons, pp. 98–102.
- ^ Vincent, pp. 29–30
- ^ Wright, Edmund, ed (2006). デスク百科事典 世界史. New York: Oxford University Press. pp. 374. ISBN 978-0-7394-7809-7
- ^ Turner, p. 86
- ^ Cook, p. 31.
- ^ a b Richardson, p. 33.
- ^ a b c d e f g Mills, John (2002). 経済学の批判的歴史. Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN 0-333-97130-2
- ^ Richardson, p. 32
- ^ Richardson, pp. 36–37
- ^ Michael Freeden, 新自由主義:社会改革のイデオロギー (Oxford UP, 1978).
- ^ Mill, John Stuart "自由論" Penguin Classics, 2006 ISBN 978-0-14-144147-4 pp. 90–91.
- ^ Mill, John Stuart "自由論" Penguin Classics, 2006 ISBN 978-0-14-144147-4 pp. 10–11.
- ^ Mill, John Stuart (April 1862). “アメリカにおける闘争”. Harper's New Monthly Magazine (New York: Harper & Bros.) 24 (143): 683–684.
- ^ John Stuart Mill: 批判的評価、第4巻、ジョン・カニンガム・ウッド著
- ^ Mill, J.S. (1869) 女性の隷属 Archived 2015-04-29 at the Wayback Machine.、第1章。
- ^ "経済的自由と税制競争のために" (PDF). Archived March 27, 2009, at the Wayback Machine.
- ^ Mill, John Stuart; Bentham, Jeremy (2004). Ryan, Alan. ed. 功利主義とその他のエッセイ. London: Penguin Books. p. 11. ISBN 978-0-14-043272-5
- ^ Eddy, Matthew Daniel (2017). “認知の政治学:自由主義とヴィクトリア朝教育の進化論的起源”. British Journal for the History of Science 50 (4): 677–699. doi:10.1017/S0007087417000863. PMID 29019300.
- ^ Nicholson, P. P., "T. H. グリーンと国家行動:酒類法制", History of Political Thought, 6 (1985), 517–550.
- ^ Chris Cook (2010). 自由党の簡潔な歴史:権力への道. Palgrave Macmillan UK. pp. 24–26. ISBN 978-1137056078
- ^ Edmund Fawcett, Liberalism: The Life of an Idea (2nd ed. 2018) pp. 33-48
- ^ Eric Storm, "A New Dawn in Nationalism Studies? Some Fresh Incentives to Overcome Historiographical Nationalism", European History Quarterly, 2018, Vol. 48(1), p 127.
- ^ Martin Blinkhorn , "The Fascist Challenge" in A Companion to Europe, 1900 - 1945 (2006) edited by Gordon Martel, pp: 309-325.
- ^ Mononen, Juha (24 March 2009). War or Peace for Finland? Neoclassical Realist Case Study of Finnish Foreign Policy in the Context of the Anti-Bolshevik Intervention in Russia 1918–1920 (Thesis). trepo.tuni.fiより。
- ^ Pressman, Steven (1999). Fifty Great Economists. London: London: routledge. pp. 96–100. ISBN 978-0-415-13481-1
- ^ Cassidy, John (10 October 2011). “The Demand Doctor”. The New Yorker
- ^ Skidelsky, Robert (2003). John Maynard Keynes: 1883–1946: Economist, Philosopher, Statesman. Pan MacMillan Ltd. pp. 494–500, 504, 509–510. ISBN 978-0-330-488679
- ^ Keith Tribe, Economic careers: economics and economists in Britain, 1930–1970 (1997), p. 61
- ^ Colomer, p. 62.
- ^ Larry Diamond (2008). The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World. Henry Holt. p. 7. ISBN 978-0-8050-7869-5
- ^ “Freedom in the World 2016”. Freedom House. Template:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。
- ^ Farr, p. 81.
- ^ Pierson, p. 110.
- ^ Peerenboom, pp. 7–8.
- ^ Sinclair, p. 145.
- ^ a b Schell, p. 266.
- ^ Schell, pp. 273–280.
- ^ Wolfe, p. 23.
- ^ Adams, p. 11.
- ^ “The International”. June 10, 2006時点のオリジナルよりアーカイブ。 Template:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。
- ^ Richard Weisberger et al., eds., Freemasonry on both sides of the Atlantic: essays concerning the craft in the British Isles, Europe, the United States, and Mexico (East European Monographs, 2002)
- ^ Margaret C. Jacob, Living the Enlightenment: Freemasonry and politics in eighteenth-century Europe (Oxford University Press, 1991).
- ^ Jessica Harland-Jacobs (2007). Builders of Empire: Freemasonry and British Imperialism, 1717–1927. U North Carolina Press. pp. 15–16. ISBN 978-1469606651
- ^ J.P. Daughton (2006). An Empire Divided:Religion, Republicanism, and the Making of French Colonialism, 1880–1914. Oxford University Press. p. 89. ISBN 978-0195345698
- ^ Michael S. Werner (2001). Concise Encyclopedia of Mexico. Taylor & Francis. pp. 88, 610. ISBN 978-1579583378
- ^ Jürgen Buchenau; William H. Beezley (2009). State Governors in the Mexican Revolution, 1910–1952: Portraits in Conflict, Courage, and Corruption. Rowman & Littlefield. p. 21. ISBN 978-0742557710
- ^ Norman Davies, Europe: A History (1996) pp. 634–635
- ^ a b c Lindgren, Allana; Ross, Stephen (2015). モダニズムの世界. Routledge. ISBN 978-1317696162 6 May 2017閲覧。
- ^ Vatikiotis, P. J. (1976). The Modern History of Egypt (Repr. ed.). Weidenfeld and Nicolson. p. 113. ISBN 978-0297772620
- ^ Vatikiotis, P. J. (1976). The Modern History of Egypt (Repr. ed.). Weidenfeld and Nicolson. p. 116. ISBN 978-0297772620
- ^ a b c Abdelmoula, Ezzeddine (2015). Al Jazeera and Democratization: The Rise of the Arab Public Sphere. Routledge. pp. 50–52. ISBN 978-1317518471 7 May 2017閲覧。
- ^ “Faculty of Alsun – Historical background”. alsun.asu.edu.eg. 5 July 2017時点のオリジナルよりアーカイブ。12 April 2018閲覧。
- ^ Vatikiotis, P. J. (1976). The Modern History of Egypt (Repr. ed.). Weidenfeld and Nicolson. pp. 115–116. ISBN 978-0297772620
- ^ Yapp, Malcolm (2014). 近代中東の形成 1792–1923. Routledge. p. 119. ISBN 978-1317871071 6 May 2017閲覧。
- ^ Roderic. H. Davison, オスマン帝国とトルコの歴史に関するエッセイ, 1774–1923 – 西洋の影響, Texas 1990, pp. 115–116.
- ^ オスマン帝国後期における公的イメージとしての伝統の発明, 1808年から1908年, Selim Deringil, Comparative Studies in Society and History, Vol. 35, No. 1 (Jan. 1993), pp. 3–29
- ^ Akgunduz, Ahmet; Ozturk, Said (2011). オスマン史:誤解と真実. IUR Press. p. 318. ISBN 978-9090261089
- ^ Ahmad, Feroz (2014). トルコ:アイデンティティの探求. Oneworld Publications. ISBN 978-1780743028 6 May 2017閲覧。
- ^ Lapidus, Ira Marvin (2002). イスラーム社会の歴史. Cambridge University Press. p. 496. ISBN 978-0521779333
- ^ Finkel, Caroline (2006). オスマンの夢:オスマン帝国の物語, Basic Books. ISBN 0-465-02396-7. p. 475.
- ^ a b Berger, Stefan; Miller, Alexei (2015). 帝国の国民化. Central European University Press. p. 447. ISBN 978-9633860168 6 May 2017閲覧。
- ^ a b Black, Antony (2011). イスラーム政治思想の歴史:預言者から現代まで. Edinburgh University Press. ISBN 978-0748688784 6 May 2017閲覧。
- ^ a b Hanioğlu, M. Şükrü (2008). 後期オスマン帝国の簡潔な歴史, Princeton University Press. ISBN 0-691-14617-9. p. 104.
- ^ Zürcher 2004, p. 78.
- ^ 近代中東の歴史. Cleveland and Buntin p.78
- ^ a b シリアの土地:統合と分裂のプロセス : 18世紀から20世紀のビラード・アッシャーム. Franz Steiner Verlag. (1998). p. 260. ISBN 978-3515073097 6 May 2017閲覧。
- ^ Selçuk Akşin Somel (2010). オスマン帝国のAからZ. Rowman & Littlefield. p. 188. ISBN 978-0-8108-7579-1 9 June 2013閲覧。
- ^ Lindgren, Allana; Ross, Stephen (2015). モダニズムの世界. Routledge. pp. 440. ISBN 978-1317696162 6 May 2017閲覧。
- ^ Hanioglu, M. Sukru (1995). 反対派の青年トルコ党. Oxford University Press. ISBN 978-0195358025 6 May 2017閲覧。
- ^ Zvi Yehuda Hershlag (1980). 中東の近代経済史入門. Brill Archive. pp. 36–37. ISBN 978-90-04-06061-6 9 June 2013閲覧。
- ^ Caroline Finkel (19 July 2012). オスマンの夢:オスマン帝国の物語 1300–1923. John Murray. pp. 6–7. ISBN 978-1-84854-785-8 11 June 2013閲覧。
- ^ Finkel, Caroline (2006). オスマンの夢:オスマン帝国の物語, Basic Books. ISBN 0-465-02396-7. pp. 489–490.
- ^ Rabb, Intisar A. (2009). "イジュティハード". In John L. Esposito (ed.). The Oxford Encyclopedia of the Islamic World. Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acref/9780195305135.001.0001. ISBN 978-0195305135。
- ^ Ennaji, Moha (2005). モロッコにおける多言語主義、文化的アイデンティティ、教育. Springer Science & Business Media. pp. 11–12. ISBN 978-0387239798 7 May 2017閲覧。
- ^ a b c d Mansoor Moaddel (2005-05-16). イスラーム近代主義、ナショナリズム、原理主義:出来事と言説. University of Chicago Press. p. 2. ISBN 9780226533339
- ^ a b c イスラームとムスリム世界の百科事典, Thomson Gale (2004)
- ^ Moaddel, Mansoor (2005). イスラーム近代主義、ナショナリズム、原理主義:出来事と言説. University of Chicago Press. pp. 2–4, 125–126. ISBN 978-0226533339 7 May 2017閲覧。
- ^ Kurzman, Charles (1998). リベラル・イスラーム:ソースブック. Oxford University Press. p. 11. ISBN 978-0195116229 7 May 2017閲覧。
- ^ Ettehadieh, Mansoureh (28 October 2011) [December 15, 1992]. "立憲革命 v. 立憲期の政党". In Yarshater, Ehsan (ed.). Encyclopædia Iranica. Fasc. 2. Vol. VI. New York City: Bibliotheca Persica Press. pp. 199–202. 2016年9月12日閲覧。
- ^ Abrahamian, Ervand (1982). 二つの革命の間のイラン. Princeton University Press. pp. 103–105. ISBN 978-0-691-10134-7
- ^ a b Lorentz, John H. (2010). イランのAからZ. Scarecrow Press. p. 224. ISBN 978-1461731917 9 May 2017閲覧。
- ^ a b Moaddel, Mansoor (2005). イスラーム近代主義、ナショナリズム、原理主義:出来事と言説. University of Chicago Press. p. 4. ISBN 978-0226533339
- ^ Hanssen, Jens; Weiss, Max (2016). 自由主義時代を超えたアラビア思想:ナフダの知的歴史に向けて. Cambridge University Press. p. 299. ISBN 978-1107136335 10 May 2017閲覧。
- ^ Wendell, C; P. Bearman; Th. Bianquis; C. E. Bosworth; E. van Donzel; W. P. Heinrichs (2011). "Luṭfīal-Sayyid, Aḥmad". イスラーム百科事典 第2版. 2017年5月10日閲覧。
- ^ Ghanayim, M. (1994). “マフムード・アミーン・アル=アーリム:政治と文学批評の間で”. Poetics Today 15 (2): 321–338. doi:10.2307/1773168. JSTOR 1773168.
- ^ Osman, Tarek (2013). 崖っぷちのエジプト:ナーセルからムスリム同胞団まで、改訂・更新版. Yale University Press. p. 42. ISBN 978-0300203707 9 May 2017閲覧。
- ^ Hourani, Albert. 1962. 自由主義時代のアラビア思想. p. 177.
- ^ “カイロ大学歴代学長”. Cairo University. 2 January 2013閲覧。
- ^ “none”. Nations & Nationalism 13 (2): 285–300. (2007).
- ^ Kinzer, シャーのすべての男たち (2003) p. 135
- ^ a b John H. Lorentz (2010). “National Front”. イランのA to Z. The A to Z Guide Series. 209. Scarecrow Press. p. 224. ISBN 978-1461731917
- ^ Ritter, Daniel P. (2015). 自由主義の鉄の檻:中東と北アフリカにおける国際政治と非武装革命. Oxford University Press. p. 64. ISBN 978-0199658329
- ^ Abrahamian, Ervand (2013). クーデター:1953年、CIAと現代米国・イラン関係の根源. New York: New Press, The. pp. 52–54. ISBN 978-1-59558-826-5
- ^ Âbrâhâmiân, Ervand, 現代イランの歴史, Cambridge University Press, 2008, p. 115
- ^ Gasiorowski, Mark J. (August 1987). “1953年のイランにおけるクーデター”. International Journal of Middle East Studies 19 (3): 261–286. doi:10.1017/s0020743800056737. オリジナルの29 May 2014時点におけるアーカイブ。 2 August 2013閲覧。.
- ^ Hiro, Dilip (12 April 2018). 必須の中東:包括的ガイド. Carroll & Graf. ISBN 978-0786712694 12 April 2018閲覧。
- ^ Archie Brown (2014). 強いリーダーの神話:現代の政治的リーダーシップ. Random House. p. 241. ISBN 978-1448156986 9 May 2017閲覧。
- ^ Secor, Laura (2016). 楽園の子供たち:イランの魂をめぐる闘争. Penguin. p. 11. ISBN 978-0698172487 9 May 2017閲覧。
- ^ Daniel Yergin, 賞:石油、金、権力をめぐる叙事詩的探求 (ISBN 978-1439110126).
- ^ Davidson, Lawrence (2013). イスラーム原理主義入門 第3版:入門、第3版. ABC-CLIO. p. 33. ISBN 978-1440829444 9 May 2017閲覧。
- ^ Kinzer, Stephen. シャーのすべての男たち. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2008, p. 3
- ^ James Risen (16 April 2000). “歴史の秘密:イランにおけるCIA”. The New York Times 3 November 2006閲覧。
- ^ 秘密工作サービスの歴史:イランのモサデク首相の転覆, Mar. 1954: p, iii.
- ^ イギリス帝国主義の終焉:帝国争奪戦、スエズ、脱植民地化. I.B.Tauris. (2007). pp. 775 of 1082. ISBN 9781845113476
- ^ Bryne, Malcolm (18 August 2013). “CIAがイランのクーデターの背後にいたことを認める”. Foreign Policy.
- ^ 1953年のイランにおけるクーデターに関するCIAの歴史は、以下の文書で構成されている:歴史家の注釈、要約序文、ドナルド・N・ウィルバー博士による長文の叙述的記述、そして付録として彼が添付した5つの計画文書。2000年6月18日にThe New York Timesによって公開された。 https://www.nytimes.com/library/world/mideast/041600iran-cia-index.html Archived 2013-01-25 at the Wayback Machine.
- ^ a b Kazemzadeh, Masoud (2008). イランの今日:イスラム共和国における生活の百科事典. 1. Greenwood Press. pp. 363–364. ISBN 978-0313341632
- ^ Houchang E. Chehabi (1990). イランの政治と宗教的近代主義:シャーとホメイニ下のイラン解放運動. I.B.Tauris. p. 128. ISBN 978-1850431985
- ^ Abrahamian, Ervand (1989). Radical Islam: the Iranian Mojahedin. I.B. Tauris. p. 47. ISBN 978-1-85043-077-3
- ^ a b Van den Berghe, p. 56.
- ^ Van den Berghe, p. 57.
- ^ Hodge, p. 346.
- ^ 2009年 "マニフェスト" Archived 2010-08-01 at the Wayback Machine. インド国民会議派. 2010年2月21日閲覧。
- ^ Routledge et al., p. 111.
- ^ Steinberg, pp. 1–2.
- ^ Arturo Ardao, "Assimilation and transformation of positivism in Latin America." Journal of the History of Ideas (1963): 515–522. Online. Archived 12 February 2015 at the Wayback Machine.; also in JSTOR Archived 2017-02-15 at the Wayback Machine..
- ^ a b Stacy, p. 698.
- ^ Handelsman, p. 10.
- ^ Dore and Molyneux, p. 9.
- ^ Don H. Doyle, The Cause of All Nations: An International History of the American Civil War (2014)
- ^ Fergus M. Bordewich, "The World Was Watching: America's Civil War slowly came to be seen as part of a global struggle against oppressive privilege," Wall Street Journal (Feb. 7–8, 2015) Archived 2017-02-21 at the Wayback Machine.
- ^ Chodos et al., p. 9.
- ^ Alterman, p. 32.
- ^ a b Auerbach and Kotlikoff, p. 299.
- ^ Dobson, p. 264.
- ^ Steindl, p. 111.
- ^ Knoop, p. 151.
- ^ Mackenzie and Weisbrot, p. 178.
- ^ Mackenzie and Weisbrot, p. 5.
- ^ a b Flamm and Steigerwald, pp. 156–158.
- ^ Patrick Allitt, The Conservatives, p. 253, Yale University Press, 2009, ISBN 978-0-300-16418-3
- ^ Wolfe, p. xiv.
- ^ Ameringer, p. 489.
- ^ a b Monsma and Soper, p. 95.
- ^ “国際民主同盟 " 加盟政党”. International Democrat Union. 2017年2月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年12月6日閲覧。
- ^ “自由主義思想の新たな戦線”. The Australian. (26 October 2009)
- ^ “小さな自由主義を救うためにベイユーに投票を”. The Age (Melbourne)
- ^ Karatnycky, p. 59.
- ^ Foucault, M., Burchell, G., Gordon, C. and Miller, P. (1991). The Foucault Effect: Studies in Governmentality: With two lectures by and an interview with Michel Foucault Chicago: University of Chicago Press (p. 92).
- ^ (Foucault 1991: 88).
- ^ (Foucault 1991: 92)
- ^ (Nadesan 2008: 16).
- ^ Rose, Nikolas; O'Malley, Pat; Valverde, Mariana (2006). “Governmentality”. Annual Review of Law and Social Science 2: 83–104. doi:10.1146/annurev.lawsocsci.2.081805.105900.
- ^ (Rose et al. 2006: 84).
出典とさらなる読書
[編集]- Alnes, Jan Harald, and Manuel Toscano. リベラリズムの諸類型:現代の課題 (2014).
- Alterman, Eric. なぜ我々はリベラルなのか. New York: Viking Adult, 2008. ISBN 0-670-01860-0.
- Ameringer, Charles. 1980年代から1990年代のアメリカ大陸の政党. Westport: Greenwood Publishing Group, 1992. ISBN 0-313-27418-5.
- Auerbach, Alan and Kotlikoff, Laurence. マクロ経済学 Cambridge: MIT Press, 1998. ISBN 0-262-01170-0.
- Bernstein, Richard. トーマス・ジェファーソン:思想の革命. New York: Oxford University Press US, 2004. ISBN 0-19-514368-X.
- Chabal, Emile. "リベラリズムの苦悩." Contemporary European History 26.1 (2017): 161–173. online Archived 2020-08-01 at the Wayback Machine.
- Coker, Christopher. 西洋の黄昏. Boulder: Westview Press, 1998. ISBN 0-8133-3368-7.
- Colomer, Josep Maria. 大帝国、小国家. New York: Routledge, 2007. ISBN 0-415-43775-X.
- Colton, Joel and Palmer, R.R. 現代世界の歴史. New York: McGraw Hill, Inc., 1995. ISBN 0-07-040826-2.
- Copleston, Frederick. 哲学の歴史:第5巻. New York: Doubleday, 1959. ISBN 0-385-47042-8.
- Delaney, Tim. 非理性の行進:科学、民主主義、新しい原理主義. New York: Oxford University Press, 2005. ISBN 0-19-280485-5.
- Diamond, Larry. 民主主義の精神. New York: Macmillan, 2008. ISBN 0-8050-7869-X.
- Dobson, John. 強気、弱気、好況、不況. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2006. ISBN 1-85109-553-5.
- Doherty, Brian (2007). 資本主義のための急進派:現代アメリカのリバタリアン運動の自由奔放な歴史[要文献特定詳細情報]
- Dorrien, Gary. アメリカのリベラル神学の形成. Louisville: Westminster John Knox Press, 2001. ISBN 0-664-22354-0.
- Fawcett, Edmund. リベラリズム:ある思想の生涯 (2014).
- Flamm, Michael and Steigerwald, David. 1960年代を論じる:リベラル、保守、急進的な視点. Lanham: Rowman & Littlefield, 2008. ISBN 0-7425-2212-1.
- Gallagher, Michael et al. 現代ヨーロッパの代議制政府. New York: McGraw Hill, 2001. ISBN 0-07-232267-5.
- Godwin, Kenneth et al. 学校選択のトレードオフ:自由、平等、多様性. Austin: University of Texas Press, 2002. ISBN 0-292-72842-5.
- Gould, Andrew. リベラルな支配の起源. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999. ISBN 0-472-11015-2.
- Gray, John. リベラリズム. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1995. ISBN 0-8166-2801-7.
- Grigsby, Ellen. 政治分析:政治学入門. Florence: Cengage Learning, 2008. ISBN 0-495-50112-3.
- Hartz, Louis. アメリカのリベラルな伝統. New York: Houghton Mifflin Harcourt, 1955. ISBN 0-15-651269-6. online
- Hafner, Danica and Ramet, Sabrina. スロベニアの民主的移行:価値の変容、教育、メディア. College Station: Texas A&M University Press, 2006. ISBN 1-58544-525-8.
- Handelsman, Michael. エクアドルの文化と習慣. Westport: Greenwood Press, 2000. ISBN 0-313-30244-8.
- Heywood, Andrew. 政治イデオロギー入門. New York: Palgrave Macmillan, 2003. ISBN 0-333-96177-3.
- Hodge, Carl. 帝国主義時代の百科事典、1800–1944. Westport: Greenwood Publishing Group, 2008. ISBN 0-313-33406-4.
- Jensen, Pamela Grande. 新しいフェミニズムを見出す:自由民主主義のための女性問題の再考. Lanham: Rowman & Littlefield, 1996. ISBN 0-8476-8189-0.
- Karatnycky, Adrian et al. 移行期の国々、2001. Piscataway: Transaction Publishers, 2001. ISBN 0-7658-0897-8.
- Karatnycky, Adrian. 世界の自由. Piscataway: Transaction Publishers, 2000. ISBN 0-7658-0760-2.
- Kerber, Linda. 共和国の母. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976.
- Kirchner, Emil. 西ヨーロッパのリベラル政党. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. ISBN 0-521-32394-0.
- Knoop, Todd. 不況と恐慌 Westport: Greenwood Press, 2004. ISBN 0-313-38163-1.
- Lightfoot, Simon. 社会民主主義のヨーロッパ化?:ヨーロッパ社会党の台頭. New York: Routledge, 2005. ISBN 0-415-34803-X.
- Mackenzie, G. Calvin and Weisbrot, Robert. リベラルの時代:ワシントンと1960年代の変革の政治. New York: Penguin Group, 2008. ISBN 1-59420-170-6.
- Manent, Pierre and Seigel, Jerrold. リベラリズムの知的歴史. Princeton: Princeton University Press, 1996. ISBN 0-691-02911-3.
- Mazower, Mark. 暗黒大陸. New York: Vintage Books, 1998. ISBN 0-679-75704-X.
- Monsma, Stephen and Soper, J. Christopher. 多元主義の挑戦:5つの民主主義国家における教会と国家. Lanham: Rowman & Littlefield, 2008. ISBN 0-7425-5417-1.
- Peerenboom, Randall. 中国の近代化. New York: Oxford University Press, 2007. ISBN 0-19-920834-4.
- Perry, Marvin et al. 西洋文明:思想、政治、社会. Florence, KY: Cengage Learning, 2008. ISBN 0-547-14742-2.
- Pierson, Paul. 福祉国家の新しい政治. New York: Oxford University Press, 2001. ISBN 0-19-829756-4.
- Riff, Michael. 現代政治イデオロギー辞典. Manchester: Manchester University Press, 1990. ISBN 0-7190-3289-X.
- Roberts, J.M. ペンギン世界史. New York: Penguin Group, 1992. ISBN 0-19-521043-3.
- Ros, Agustin. 全員のための利益?:従業員所有制の費用と便益. New York: Nova Publishers, 2001. ISBN 1-59033-061-7.
- Ryan, Alan. 現代リベラリズムの形成 (Princeton UP, 2012).
- Scott, Jonathan (January 2008) [2004]. "シドニー [シドニー]、アルジャーノン (1623–1683)". Oxford Dictionary of National Biography (英語) (online ed.). Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/25519。 (要購読、またはイギリス公立図書館への会員加入。)
- Shaw, G. K. ケインズ経済学:永続的革命. Aldershot, England: Edward Elgar Publishing Company, 1988. ISBN 1-85278-099-1.
- Sinclair, Timothy. グローバル・ガバナンス:政治学における重要概念. Oxford: Taylor & Francis, 2004. ISBN 0-415-27662-4.
- Song, Robert. キリスト教とリベラル社会. Oxford: Oxford University Press, 2006. ISBN 0-19-826933-1.
- Stacy, Lee. メキシコとアメリカ合衆国. New York: Marshall Cavendish Corporation, 2002. ISBN 0-7614-7402-1.
- Steindl, Frank. 1930年代の経済回復の理解. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2004. ISBN 0-472-11348-8.
- Susser, Bernard. 現代世界の政治イデオロギー. Upper Saddle River: Allyn and Bacon, 1995. ISBN 0-02-418442-X.
- Van Schie, P. G. C. and Voermann, Gerrit. 成功と失敗を分ける線:19世紀と20世紀のオランダとドイツにおけるリベラリズムの比較. Berlin: LIT Verlag Berlin-Hamburg-Münster, 2006. ISBN 3-8258-7668-3.
- Various authors. 世界各国とその指導者年鑑 08、第2巻. Detroit: Thomson Gale, 2007. ISBN 0-7876-8108-3.
- West, Thomas G. (1996). “序文”. 政府に関する論説. Indianapolis: Liberty Fund. ISBN 0865971412
- Wolfe, Alan. リベラリズムの未来. New York: Random House, Inc., 2009. ISBN 0-307-38625-2.
- Worell, Judith. 女性とジェンダーの百科事典、第1巻. Amsterdam: Elsevier, 2001. ISBN 0-12-227246-3.
- Young, Shaun. ロールズを超えて:政治的リベラリズムの概念の分析. Lanham: University Press of America, 2002. ISBN 0-7618-2240-2.
- Zvesper, John. 自然と自由. New York: Routledge, 1993. ISBN 0-415-08923-9.
イギリス
[編集]- Adams, Ian. 今日のイギリスにおけるイデオロギーと政治. Manchester: Manchester University Press, 1998. ISBN 0-7190-5056-1.
- Cook, Richard. 偉大なる老人. Whitefish: Kessinger Publishing, 2004. ISBN 1-4191-6449-X グラッドストーンについて。
- Falco, Maria. メアリー・ウルストンクラフトのフェミニスト的解釈. State College: Penn State Press, 1996. ISBN 0-271-01493-8.
- Forster, Greg. ジョン・ロックの道徳的合意の政治. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. ISBN 0-521-84218-2.
- Gross, Jonathan. バイロン:エロティックなリベラル. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2001. ISBN 0-7425-1162-6.
- Locke, John. 寛容についての書簡:謹んで提出する. CreateSpace, 2009. ISBN 978-1-4495-2376-3.
- Locke, John. 統治二論. reprint, New York: Hafner Publishing Company, Inc., 1947. ISBN 0-02-848500-9.
- Roach, John. "リベラリズムとヴィクトリア朝の知識人." Cambridge Historical Journal 13#1 (1957): 58–81. online Archived 2020-09-02 at the Wayback Machine..
- Wempe, Ben. T. H. グリーンの積極的自由の理論:形而上学から政治理論へ. Exeter: Imprint Academic, 2004. ISBN 0-907845-58-4.
フランス
[編集]- Frey, Linda and Frey, Marsha. フランス革命. Westport: Greenwood Press, 2004. ISBN 0-313-32193-0.
- Hanson, Paul. フランス革命を論じる. Hoboken: Blackwell Publishing, 2009. ISBN 1-4051-6083-7.
- Leroux, Robert, フランスにおける政治経済学とリベラリズム:フレデリック・バスティアの貢献, London and New York, Routledge, 2011.
- Leroux, Robert, and David Hart (eds), 19世紀フランスのリベラリズム。アンソロジー, London and New York, Routledge, 2012.
- Lyons, Martyn. ナポレオン・ボナパルトとフランス革命の遺産. New York: St. Martin's Press, Inc., 1994. ISBN 0-312-12123-7.
- Shlapentokh, Dmitry. フランス革命とロシアの反民主主義的伝統. Edison, NJ: Transaction Publishers, 1997. ISBN 1-56000-244-1.
カテゴリ
[編集]- Category:リベラリズム
- Category:イデオロギーの歴史
- Category:リベラリズムの歴史




