サレカット・イスラム
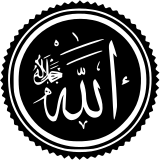 |
|
秀逸な記事 |
|
ポータル・イスラーム |
サレカット・イスラム(Sarekat Islam)[1]は、20世紀初頭、オランダ領東インド(現インドネシア)で結成されたイスラーム系大衆団体である。日本語では「イスラム同盟」と訳される例も多い[2]。略称はSI。
当初は華人系商人に対抗するムスリムの商人組織として結成されたが、組織の拡大とともに植民地支配に抵抗する急進的な民族主義団体としての性格を強め、1910年代から1920年代初頭にかけて、当時としては空前の規模の動員力を誇った。1923年にはサレカット・イスラム党、さらに1929年にインドネシア・サレカット・イスラム党 (PSII) と改名した。
1973年、スハルト体制下において、他のイスラーム系諸政党とともに開発統一党 (PPP) に統合された。
沿革
[編集]結成
[編集]サレカット・イスラム (SI) の前身は、バタヴィア(現ジャカルタ)と西ジャワのバイテンゾルフ(現ボゴール)で、それぞれ1909年と1910年に結成されたサレカット・ダガン・イスラム (イスラム商業同盟、Sarekat Dagang Islam, 以下SDI)である[3]。この団体を結成したのは、ジャワ貴族出身のジャーナリスト、ティルトアディスルヨ[略歴 1]であり、彼の目的は同じムスリムであるアラブ人商人と「原住民」商人が手を結び[4]、当時の東インドで活発な経済活動をおこなっていた華人系商人に対抗することだった[5]。
こうした動きにソロ(スラカルタ)の大手バティック業者、ハジ・サマンフディ[略歴 2]も刺激を受けた。1911年、ティルトアディスルヨの協力を得て、サマンフディはソロで同様の組織を結成した。サレカット・イスラム(以下、SI)の名称は、そのときの組織要綱で初めて使用され、以後、各地で結成される同様の組織にも定着していったようである[6]。
拡大
[編集]1912年9月10日、サマンフディはソロSIの議長の座を退き、SIスラバヤ支部のチョクロアミノト[略歴 3]がその座に就いた。雄弁をもって知られたチョクロアミノトの指導のもとで、SIはジャワ島各地で支部を設立、急速に組織を拡大していった。スラバヤ、スマラン、バンドン、バタヴィアで機関誌を発行し、1913年1月、スラバヤで初めて大規模に開催されたプロパガンダ集会には数万人の参加者を集めた[7]。1912年4月には4500人だった会員数が、1913年4月には15万人に、さらに1914年頃にはジャワ島外にも組織は拡大し、1914年4月の会員数は37万人に達した[8]。その一方で、発足期から華人に対する共同戦線を張ってきたアラブ人との関係では、同月ソロで開催された大会で「非原住民」を排除すると決議されたことで、アラブ人はSIから排除されることになった[9]。
1910年代前半にSIが急速に組織を拡大させた最大の要因は、組織の紐帯としてイスラームを前面に押し出したことであった。東インドにおけるムスリム人口は全体の9割前後であり、その潜在的な動員力は既存の各種団体のそれを上回るものだった。そして組織の拡大とともに、その主導権は、SDIにおける商人たちから、貴族階級出身でオランダ語教育を受けた知識人層へと移っていった[10]。
設立当初のSIは、植民地政府と良好な関係を保とうとしており、オランダ支配下での現地住民の福祉向上をはかり、現地住民の声を代弁する議会の開設を政治的要求の一つに掲げていた。また、植民地政府の側も、当初はSIの活動を容認していた。1912年11月、SIが植民地政府に合法団体としての承認を要請すると、1913年6月30日、植民地政府はSIの地方支部を個別に承認するという方針を打ち出した[11]。そして最終的には、1916年、植民地政府は中央SIを正式に承認したのである[12]。
急進化
[編集]勢力を拡大しつつあったSIだが、その実態は「地方SI支部の寄り合い所帯」にすぎなかった[13]。中央SIから地方支部への統制はかならずしも及んでおらず、地方では中央SIの規約からの逸脱がみられた。

愛称「ヘンク」。東インドに共産主義運動を持ち込み、スマウン、ダルソノら「原住民」活動家らを育てた。
その中でも、労働組合運動で頭角を現した青年活動家スマウン[略歴 4]によって牽引されるSIスマラン支部は急進的だった。当時のスマランは新興工業都市であり、各種組織による労働組合運動が盛んだった。このスマランでは、1914年5月、東インド在住のオランダ人、欧亜混血児らによって、東インド社会民主主義同盟(ISDV) という共産主義政党が結成された。後のインドネシア共産党 (PKI) の前身である[14]。SIスラマン支部に属する17歳のスマウンが、このISDVのオランダ人活動家ヘンドリクス・ヨセフ・フランシス・スネーフリートを慕い、彼の勧めによってISDVに加入したのは1915年のことである[15]。SI会員がISDVにも加入する「二重党籍」となったわけだが、当時、複数の政治組織に加入する例は珍しくはなかった。スネーフリートの戦略は、既存の他組織に党員を参加させ、その組織内で共産主義者の影響力を高め、組織全体をISDVの影響下に置くことであったが、ムスリムでないスネーフリートはSIに加入できないため、スマウンを通して、SIスマラン支部を「赤化」することに成功したのである[16]。
こうした地方支部における急進派の影響を受けて、1917年10月に開かれたSIの第2回大会では、反植民地主義を掲げて、自治権の獲得を謳う綱領が採択された。また、この綱領では植民地支配の根拠となっている資本主義を敢えて「罪深い資本主義」と呼び、これを非難しつつも、民族ブルジョワジーをその非難の対象から外し、彼らの支持を失わないよう努めた。綱領の文言は激しい調子で彩られていたが、闘争の基本路線としては合法的活動であるべきという姿勢を放棄したわけではなかった[17]。

1918年5月には東インドに植民地議会 (Volksraad) が開設され[18]、SIからは総督任命議員としてチョクロアミノトが選ばれ、またSI副議長アブドゥル・ムイスも選出議員として議席を得た。チョクロアミノトらは、この植民地議会での活動を足がかりに、植民地政府に対して「原住民」の地位向上と住民自治の拡大をもとめていこうとしたが、SI内の急進派は、そうした中央SI首脳の活動を微温的であるとして満足しなかった。
1918年9月、10月に開かれた第3回大会では、ISDVにも在籍するSIスマラン支部のスマウンがSI中央運営委員会委員、ダルソノ[略歴 5]が宣伝局員、そしてアリミン[略歴 6]も中央SI指導部入りし、従来のSIの微温的な活動方針を転換し、より過激な方針を取るよう、指導部を突き上げた。これを受けてチョクロアミノトは同年11月、植民地議会に対して、遅くとも1921年末までに、住民の選挙によって公正に選出された立法院、その議会に責任を持つ政府を作れとの動議を提出、植民地政府に対する要求をさらに先鋭化させていくことになった[19]。
急進化するSIに対して植民地政府は警戒感を強めた。1919年6月、7月に相次いでセレベスのトリトリ、西ジャワのガルットで暴動が発生すると、それらの暴動とSIを関連づけ、従来の穏健な対応を改め、SIの弾圧に乗り出した。その結果、SIからは会員の脱退がすすみ、その会員数を激減させた[20]。
分裂
[編集]
SI指導部は地方暴動への関与を否定したものの、幹部の多数が逮捕され、チョクロアミノトも11ヶ月拘留された。植民地政府による取り締まりが厳しくなるとともに、一般会員のSI離れが進んだ[21]。
この地方暴動後に弱体化したSI再興の方向性を探る中で、チョクロアミノトの信頼を得ていたのは中央SI理事のアグス・サリムだった。西洋式教育を学び、冷徹な合理主義者でありながら、イスラームの教義、特にその近代化を志向するイスラーム改革主義に精通したサリムは、初期SIの熱狂、チョクロアミノトのカリスマ性、衝動的・散発的な暴動から組織を脱皮させ、反植民地、反資本主義という点では共産主義者と共闘しつつも、運動を正しく導くためにはイスラームをその指導原理としなければならないと考えていた[22]。
また、第一次世界大戦後の経済的混乱期にあって、SIは労働組合運動に新たな活路を見出した。1919年12月、SI傘下に、22労組、7万2000人の組合員を抱える、労働者運動連合(Persatuan Pergerakan Kaum Buruh)が結成され、その議長には製糖工場従業員組合 (PFB、組合員3万1000人) 議長で「ストライキ王」の異名を持つスルヨプラノト[略歴 7]が選出されるものと期待されたが、スマウンの策略で阻止され、獄中にある国鉄従業員組合 (VSTP、組合員1万1000人) 議長ソスロカルドノ(中央SI書記)が選出された。スマウンはその議長代理、サリムは書記に就任した[23]。
この組織をめぐって、SIスマラン支部とVSTPを主導するスマウンらの「スマラン派」と、SIジョグジャカルタ支部とPFBを主導するスルヨプラノト、アグス・サリムらの「ジョグジャカルタ派」は互いにストライキの成果を競い、連合傘下の組合の奪い合いを演じた。こうした両派の主導権争いの中でチョクロアミノトの指導力は低下した[24]。
さらに、この両派の間には労働組合における主導権争いよりも根本的な、妥協不可能な対立点があった。両派は、反植民地、反帝国主義という点では共闘し得たが、民族の解放と階級の解放のどちらを優先課題とすべきか、国家権力の主体はどの階級であるべきか、という点で妥協の余地はなかった。サリムらジョグジャカルタ派がスマラン派の背後にあるコミンテルンの影を嫌悪すれば、スマウンらスマラン派はサリムの氾イスラーム主義を批判した[25]。
労働組合運動を通して、賃金上昇などの成果を得ることに成功し、勢いを増しつつあったスラマン派に対して、危機感を抱いたサリムらジョグジャカルタ派は、会員に二重党籍を認めてきたことが敗因であるとして、1921年3月のSI第5回大会でこの問題を取り上げた。この時は統一を重んじるチョクロアミノトの反対があって、二重党籍問題は棚上げとなった。しかし、同年6月、スマウンが労働者運動連合から14労組を引き抜いて脱退させ、ISDVの直接指導下に置いたことから、スマラン派とジョグジャカルタ派の対立は最高潮に達した。同年10月、チョクロアミノトが検挙されている間に開かれた第6回大会では両者の激しい論戦が繰り広げられ、サリムが主張する「多重党籍禁止」案が採択された。これによりSIとISDVの二重在籍は否定され、スマウンらISDV在籍者はSIから大量に脱退した[26]。

1923年2月、SIはISDVによる支部の侵食に対抗するため、組織をサレカット・イスラム党 Partai Sarekat Islam (略称SI党) に改編し、党としての体裁を整えることになった[27]。また、急進的な路線を取ることで大衆の支持を獲得しようと試み、1924年8月の党大会では植民地政府、植民地議会への非協力路線を採択したが、政府との対決は避け、氾イスラーム主義に訴えて、党勢の維持、拡大を図ろうとした[28]。
SI党は既存のイスラーム系社会団体と共闘する方針を打ち出したが、イスラーム保守派との共闘には失敗[29]、改革派のムハマディヤとアハマディヤに接近した。しかし、この2団体はライバル関係にあり、チョクロアミノトが後者に接近しすぎたことで、1928年、ムハマディヤはSI党と袂を分かった。その結果、同党は、東インドにおけるムスリムを代表する勢力としての役割も果たせなくなった[30]。1927年1月にはコミンテルンと関係のあった植民地抑圧反対連盟という組織に接近し、反植民地政府に向かう兆しも見せたが、植民地政府による弾圧を受けると、同年9月・10月の党大会では穏健なままの非協力路線に戻ることを余儀なくされた。1929年、インドネシア・サレカット・イスラム党 Partai Sarekat Islam Indonesia(PSII)へと改名し、党勢の回復を図ろうとしたが、1930年には党員数1万9000人の小政党へと転落した[31]。

そのころ、民族主義運動を主導していたのは、1927年にスカルノらによって結成されたインドネシア国民党 (PNI) であった。インドネシアの独立を掲げて植民地政府との対決姿勢をアピールしたPNIは、主にジャワの都市部を中心に支持を広げたが、1929年末にスカルノら党幹部が逮捕されると、PNIは1931年に解散した。植民地政府が民族主義運動に対して強硬路線を敷き、民族主義運動をめぐる環境がきびしさを増していくなかで、1934年12月にチョクロアミノトが死去し、PSII自身も運動のありかたについて、植民地政府への非協力路線を継続するか、それとも協調路線に転じるか、という深刻な内部対立をかかえていた。
当時のPSIIで主流派を形成していたのは非協力路線継続を主張する勢力であった。これに対して、アグス・サリムは、政府の弾圧が厳しさを増していく中で、非協力路線に固執することが党活動の制約となり、党が大衆から遊離する結果を招くことになるとして、1935年3月、党指導部に対して非協力路線の撤回を求めた。これにモハマド・ルム[略歴 8]も同調したが、1937年、主流派はサリム、ルムら29人を追放し、PSIIは非協調路線を継続していくことになった[32]。
しかし、最終的には、1939年5月、東インドをとりまく国際環境が風雲急を告げるなかでPSIIも協力路線を取ることを余儀なくされ、協力路線を取る諸組織による統一戦線「ガピ GAPI」 (Gabungan Politiek Indonesia - インドネシア政治連合) に合流した[33]。ガピは反ファシズムという点でオランダと連携し、自治権と完全な議会を要求したが、植民地政府はこれらの要求を拒んだ。戦前の民族主義運動は、ここに至って、オランダとの協調によっては展望が開かれないことを思い知らされた[34]。また、1940年5月、PSIIは活動禁止処分となった。
その後
[編集]1942年、オランダ領東インドが日本の占領下に置かれると、PSIIは再結成されたが、同年5月、軍政当局によって解散させられた。軍政当局は既存のイスラーム系団体のうち、ナフダトゥル・ウラマーやムハマディヤといった非政治的団体のみを重用し、東インドのムスリムを軍政に利用するため、これらの非政治的ムスリムを糾合して、マシュミを結成した[35]。

日本の敗戦によって東インドにおける日本軍政が終了し、1945年8月17日、インドネシアが独立を宣言すると、オランダとのあいだで独立戦争がはじまった。その戦争期間中の1947年にPSIIは再結成され、インドネシア社会党首班のアミル・シャリフディン内閣を支持した。また、独立宣言後に再組織されたマシュミにも参加した。このときのPSII指導者は、アンワル・チョクロアミノトとハルソノ・チョクロアミノト(上記のチョクロアミノトの二人の息子)、そしてアルジ・カルタウィナタらであった[36]。
インドネシアがオランダからの独立を達成した後、インドネシアでは1950年憲法下での議会制民主主義が導入された。1955年の第1回総選挙で、PSIIは8議席(得票率2.9%)を獲得、その後、スカルノの指導される民主主義体制期、9月30日事件を経て、スハルト政権下での1971年選挙では、10議席(同2.4%)を獲得した。この選挙自体は政権与党ゴルカルの圧勝で終わり、その後、1973年1月に政党ゴルカル法が定められ、既存の政党はイスラーム系の開発統一党(インドネシア語:Partai Persatuan Pembangunan、略称:PPP)か非イスラーム系のインドネシア民主党 (PDI) のいずれかに統合されることになり、PSIIは前者に統合された[37]。
備考
[編集]- スハルト政権崩壊後の総選挙には、SIの後継政党を名乗る2政党が参加した。1998年5月29日に結成されたインドネシア・サレカット・イスラム党と、1998年5月21日に結成された1905年インドネシア・サレカット・イスラム党である。このうち前者は1議席(得票率0.36%)を獲得している。
脚注
[編集]出典
[編集]- ^ インドネシア語では「イスラム」を「イスラーム」と長音で発音しないので、現地語の発音からカタカナで表記すると「サレカット・イスラム」となる。
- ^ 日本語での「イスラム同盟」は、ほぼ定訳といってよい。例えば、専門家の間では、永積(1980年)、白石(1997年)ら多くが「イスラム同盟」と表記している。一方、SI指導者の一人、ハジ・アグス・サリムの生涯と思想をテーマにした間苧谷(1970年)は「サレカット・イスラム」を使用し、また、成立期から初期にかけてのSIについての研究を複数発表した深見は、初期の論文では「イスラム同盟ことサレカット・イスラム」と断った後で「イスラム同盟」を用いたが、深見(1978年)では「サレカット・イスラム」のみを用いている。他にも「サリカット・イスラーム」「イスラーム同盟」と訳された例があるが、定着しているとは言い難い。SIの日本語訳をめぐる問題については、桃木至朗「東南アジア史 誤解と正解」(第4回全国高等学校歴史教育研究会、2006年8月2日、大阪大学)(PDF文書)を参照。本項目の項目名は、この団体名が固有名詞であることに鑑みて、現地語発音から「サレカット・イスラム」とした。
- ^ サレカット・ダガン・イスラム (SDI) の成立事情については、深見、1975年、116-118頁、を参照。
- ^ 当時のオランダ領東インドでは、ヨーロッパ人 Europeanen 、東洋外国人 Vreemde Oosterlingen 、原住民 Inlanders の3つの人種的区分があり、それぞれ法的地位が異なっていた。華人とアラブ人は東洋外国人に属していた。深見、1975年、125頁、脚注20。
- ^ アラブ人商人がイスラームを媒介にして原住民商人と手を結んだのは、19世紀末以来、華人がヨーロッパ人と同等の商法、刑法上の地位を獲得しつつあったことにアラブ人商人が脅威を感じていたからでもあった。深見、1975年、116頁。
- ^ 永積、1980年、148頁。また、1912年9月にチョクロアミノトが作成したSI規約で、名称をSDIではなくSIとした理由についての分析は、深見、1975年、122頁、を参照。
- ^ Shiraishi, 1990、p.49. チョクロアミノトは、大衆動員の三大技術、(1) ジャーナリズム(機関誌の発行)、(2) 団体の組織と運営、(3) 集会と演説、を初めて結びつけて、数十万の原住民の動員に成功した、インドネシア人最初の職業政治家だった。白石、1997年、10頁。
- ^ 間苧谷、1970年、161頁。もっとも、こうした会員数の増加について、白石は、その会員数の集計は各地で開催されたSIの集会に参加料を納めた参加者たちの数であった、と指摘している。白石、1986年、191-192頁、を参照。
- ^ アラブ人の排除の理由として、東インド在住のアラブ人が華人と和解する動きを見せたこと、アラブ人自身が「原住民」を搾取していると批判があったことなどが挙げられる。深見、1975年、117-118頁。
- ^ Van Niel, 1960, p.113、間苧谷、1970年、161頁。
- ^ 植民地政府が承認したSI地方支部は、1919年までにジャワで105支部、外島(ジャワ以外)で100支部に達した。深見、1978年、74頁、永積、1980年、155頁。
- ^ 深見、1977年、160-161頁。
- ^ 中央SIが地方支部の寄せ集めにすぎなかったことについては、深見、1977年、158頁、を参照。また、地方におけるSI指導者の出自や背景については、深見、1978年、76-81頁、に地方SI指導者の称号と職業をまとめた表が掲載されている。
- ^ 東インド社会民主主義同盟(ISDV) の党名はオランダ語表記(Indische Sociaal-Democratische Vereniging) である。東インドに共産主義運動を持ち込んだヘンドリクス・ヨセフ・フランシス・スネーフリートであったが、1917年から1920年にかけて、植民地政府はスネーフリートをはじめとするオランダ人共産主義者を次々と国外退去処分にしたため、以後の東インドにおける共産主義運動は、スネーフリートの下に学んだ「原住民」党員(スマウン、ダルソノ、アリミンなど)によって担われていくことになる。1920年5月の第7回党大会で名称を東インド共産主義同盟(Perserikatan Kommunist di India, インドネシア語表記)に改めると、この党大会での議決により、議長にスマウン、副議長にダルソノが就任した。さらに党名がインドネシア共産党 (Partai Komunis Indonesia, 略称PKI) に変更されるのはその4年後である。
- ^ 永積、1980年、199-200頁。
- ^ SI内部に共産党員を送り込み、組織全体を共産党の影響下に置こうというスネーフリートの戦略は、のちに中国においても国共合作として結実した。McVey, 1965, pp.364-369, 永積、1980年、200頁。
- ^ 間苧谷、1970年、162-163頁。
- ^ 当初の植民地議会は総督の諮問機関に過ぎなかった。20世紀初頭、植民地に「倫理政策」を導入したオランダは、植民地住民に自治を教え、その自治に耐えうるように成熟せしめるための自治政策の一環として、このような植民地議会を設置した。早瀬・深見、1999年、286-287頁。
- ^ 間苧谷、1970年、163-164頁。
- ^ 間苧谷、1970年、164頁。地方暴動については、永積、1980年、209-214頁を参照。
- ^ 地方における暴動と、その後のSI幹部の逮捕を目の当たりにした一般会員は、SIの会員証はトラブルのもとであると恐れて運動から離れていった。この頃からSIの大衆的支持基盤は急速に萎んでいくことになった。Ricklefs, 1993, p.174.
- ^ 間苧谷、1970年、166頁、永積、1980年、159頁。
- ^ 間苧谷、1970年、164頁、Shiraishi, 1990, pp.219,220.
- ^ Van Niel, 1984, p.154.
- ^ スマラン派とジョグジャカルタ派の対立については、間苧谷、1970年、168頁、永積、1980年、229-230頁、を参照。
- ^ 間苧谷、1970年、168-169頁、永積、1980年、229-230頁。
- ^ 間苧谷、1970年、171頁。一方、1924年にインドネシア共産党 (PKI) と名称を変えたISDVは、政府との対決、革命を訴え、植民地政府によってスマウンら党幹部が海外に追放された。その後、組織の求心力を失い、地方支部の急進化・独走を許すことになった。1927年から1928年にかけてPKI地方支部が武装蜂起を起こし、PKIは非合法化された。
- ^ 間苧谷、1970年、176頁、白石、1997年、15-16頁。
- ^ のちにイスラーム保守派は、1926年にナフダトゥル・ウラマーを結成、政治活動とは一線を画すことになる。Ricklefs, 1993, p.177 を参照。
- ^ SI党のイスラーム諸団体との共闘の試みについては、間苧谷、1970年、171-175頁、を参照。
- ^ 間苧谷、1970年、172-176頁。
- ^ Ricklefs, 1993, p.191. その後、除名されたアグス・サリムとモハマド・ルムは新党プニュダールを設立した。間苧谷、1970年、180頁。
- ^ この決定に反対し、非協力路線に固執して組織を脱退したのが、のちにダルル・イスラム運動(独立後から1960年代にかけて起こったイスラーム国家樹立運動)の指導者となるセカルマジ・マリジャン・カルトスウィルヨだった。間苧谷、1970年、181-182頁。
- ^ 早瀬・深見、1999年、307-308頁。
- ^ 日本軍政当局のイスラーム政策については、倉沢、1992年、第9章「イスラム宣撫工作」を参照。
- ^ 首藤、1993年、70頁、脚注9。
- ^ イスラーム諸政党の開発統一党への統合については、大形、1995年、149-150頁、を参照。
人物略歴
[編集]- ^ ティルトアディスルヨ (Raden Mas Tirtoadisoerjo, 1880 - 1918) は、オランダ領東インドにおけるジャーナリズム、民族主義運動の先駆者の一人。原住民官吏養成学校 (OSVIA) を卒業後、原住民官吏とはならずに雑誌編集者になった。1903年、21歳にして花形編集者として名声を確立していた彼は『スンダ・ブリタ』という新聞を自らの手で発刊。これは原住民によって出資、運営、編集、刊行された初めての新聞となった。1907年、週刊誌『メダン・プリアイ』を発刊(1909年からは日刊紙となる)、1911年のその購読者数は2000人に達した。Van Niel, 1984, pp.89-90, Shiraishi, 1990, p.33,34.
- ^ ハジ・サマンフディ (Haji Samanhudi, 1868 - 1956) は、ソロ(スラカルタ)の商人。父を継いでバティック業者となり、ジャワ島各地に支店網を拡げた。Van Niel, 1984, pp.88-89
- ^ チョクロアミノト (Haji Umar Said Tjokroaminoto, 1882 - 1934) は、中部ジャワ・マディウン生まれ。父親が植民地政府で働く原住民地方行政官(郡長)であったことから、オランダ語で授業を受ける原住民官吏養成学校に入学、1902年に卒業。数年間官吏として過ごし、その後職を転々とする。1912年5月にSIスラバヤ支部に加入。サマンフディに代わりSI議長に就任。Van Niel, 1984, pp.92 後に初代大統領となるスカルノは、父親がチョクロアミノトの友人だった関係から、スラバヤでの学生時代、SI議長を務めていたチョクロアミノト宅に下宿した。永積、1980年、249頁、早瀬・深見、1999年、303頁、を参照。スカルノがチョクロアミノトから受けた影響については、白石、1997年、10-12頁、を参照。
- ^ スマウン (Semaun, 1899 - 1971) は東ジャワ・パスルアン生まれ。父親は鉄道員で、スマウン自身も10代の頃から国営鉄道で働いた。その労働組合運動で頭角を現し、SI、ISDV (1924年にPKIと改称) に参加する。1923年に植民地政府によって東インドを追放される。1956年に帰国し、その後のPKIの活動には関与しなかった。
- ^ ダルソノ (Raden Darsono, 1897 - ? ) は、下級貴族の家系に生まれ、学校ではプランテーションの農場長となるべく教育を受けた。卒業後は農業省所属の土壌専門家となったが、2年も経たないうちに職を辞した。その後、読書、特にマルクス主義の著作を読みふけった。そんな中、オランダ人ながら東インド原住民の権利拡大のために戦っていたスネーフリートと出会った。Van Niel, 1984, p.141,142.
- ^ アリミン (Alimin, 1889 - 1964) は、スラカルタ生まれ。チョクロアミノト宅に起居してその薫陶を受け、SIに参加。その後ISDVにも加入し、草創期のインドネシア共産主義運動の礎を築いた。1927年、1928年のPKI蜂起によって組織が壊滅的打撃を受けると海外に脱出。独立戦争期に帰国し、マディウン事件後のPKI再建に関わった。その後、アイディットとの党内主導権争いに敗れ失脚。
- ^ スルヨプラノト (Raden Mas Surjopranoto, 1871 - ? ) は、ジョグジャカルタのパク・アラム王家の出身(弟はキ・ハジャール・デワントロことスワルディ・スルヤニングラット)。原住民官吏養成学校 (OSVIA) を卒業。中央SI理事、SIジョグジャカルタ支部長だった1918年、製糖工場従業員組合 (PFB) を結成。Van Niel, 1984, p.154. スルヨプラノトの経歴については、Shiraishi, 1990, pp.109-111 を参照。
- ^ モハマド・ルム (Mohammad Roem, 1908-1983) は、中部ジャワ出身。高等法学校で学んで弁護士となった。インドネシア独立後はマシュミ党の指導者の一人として、内務大臣、外務大臣、副首相を歴任した。
参考文献
[編集]- McVey, Ruth T. (1966). The Rise of Indonesian Communism (reprint edition). Cornell University Press. ISBN 9780801402876
- Ricklefs, M. C. (1993). A History of Modern Indonesia since c.1300 (2nd edition). Stanford University Press. ISBN 9780333576908
- Shiraishi, Takashi (1990). An Age in Motion : Popular Radicalism in Java, 1912-1926. Cornell University Press. ISBN 9780801421884
- Van Niel, Robert (1984). The Emergence of the Indonesian Elite. Foris Publications. ISBN 9780801421884 -- original edition published by W.van Hoeve in 1960.
- 大形利之 著「第3章 ゴルカル - スハルトと国軍のはざまで -」、安中章夫 編『現代インドネシアの政治と経済 - スハルト政権の30年 -』三平則夫共編、アジア経済研究所、1995年、143-192頁。ISBN 9784258044542。
- 倉沢愛子『日本占領下のジャワ農村の変容』草思社、1992年。ISBN 9784794204608。
- 首藤もと子『インドネシア - ナショナリズム変容の政治過程』勁草書房、1993年。ISBN 9784326300785。
- 白石隆 著「オランダ東インド国家とインドネシア・ナショナリズム - pergerakan(運動)の歴史叙述をめぐって」、日蘭学会 編『オランダとインドネシア 歴史と社会』山川出版社、1986年、273-298頁。ISBN 9784634650701。
- 白石隆『スカルノとスハルト 偉大なるインドネシアをめざして』岩波書店〈現代アジアの肖像11〉、1997年。ISBN 9784000048668。
- 白石隆『インドネシアから考える 政治の分析』弘文堂〈シリーズ「現代の地殻変動」を読む - 4〉、2001年。ISBN 9784335501593。
- 永積昭『インドネシア民族意識の形成』東京大学出版会、1980年。ISBN 9784130250023。
- 早瀬晋三、深見純生 著「第5章 近代植民地の展開と日本の占領」、池端雪浦 編『東南アジアⅡ 島嶼部』山川出版社〈新版世界各国史6〉、1999年、268-365頁。ISBN 9784634413603。
- 深見純生「成立期イスラム同盟に関する研究 - イスラム商業同盟からイスラム同盟へ」『南方文化』第2輯、天理大学、1975年9月、111-127頁。
- 深見純生「初期イスラム同盟 (1911-16) に関する研究(1)」『南方文化』第3輯、天理大学、1976年10月、117-145頁。
- 深見純生「初期イスラム同盟 (1911-16) に関する研究(2)」『南方文化』第4輯、天理大学、1977年7月、151-182頁。
- 深見純生「サレカット・イスラムの地方指導者」『南方文化』第5輯、天理大学、1978年11月、73-94頁。
- 間苧谷栄 著「第3章 インドネシアのイスラム改革主義者とナショナリズム - ハジ・アグス・サリームの生涯と思想 -」、永積昭 編『東南アジアの価値体系2 インドネシア』間苧谷栄共著、1970年、153-232頁。
関連項目
[編集]
